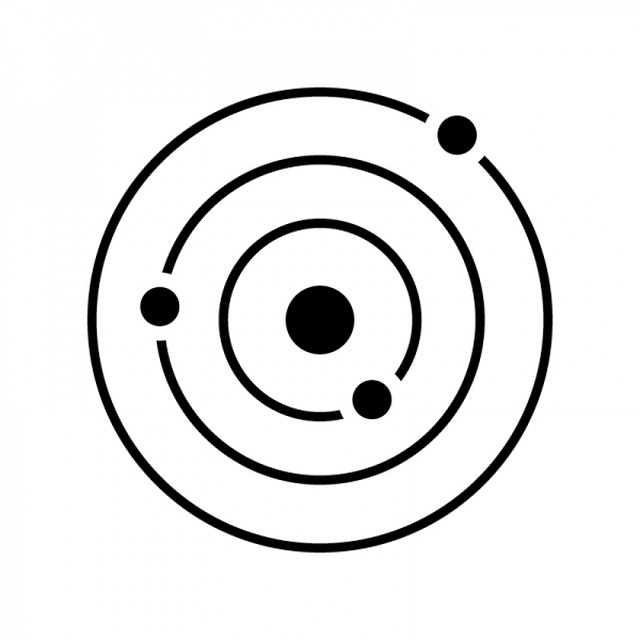重なる声④
文字数 3,618文字
一緒に歌うことを決意して、侑子がユウキの手を取ったあの日から、二人は時間を見つけては声を重ねた。
初めこそ緊張したものの、侑子がユウキの前で歌うことに抵抗を感じなくなるのはすぐだった。
夢の中でよく歌っていたからかもしれないし、すっかりユウキに心を許していたからかもしれない。
そしてユウキは侑子が歌うたびに、恥ずかしくなるくらい称賛してくれたのだった。
どこまでも甘くて優しいその言葉の一音一音は、侑子には錆落としのように思えた。
重く動かしづらかった心の扉の蝶番が、少しずつ本来の動きを取り戻していくのだ。
『ユーコちゃんは耳が良いのかもしれない』
ある日新しい曲の旋律を歌った侑子に、ユウキが言った。
『一度聴いただけで、正確に歌っちゃうんだもんな』
嬉しそうなユウキだったが、侑子は自覚がなかったのでピンとこない。
ただ聴いたとおりに歌うことしかしていないのだから、当然だ。
『もっと自信を持つこと。それがユーコちゃんの一番の課題だね。謙虚は良いことばかりじゃないよ』
日に一度は言われる文言だった。
しかしその日、ユウキは更に一歩踏み込んだところまで言及してきた。
『どうしてそんなに自信がないの?』
侑子と歌うようになってから、日に日に疑問が大きくなっていた。
歌に集中している時の彼女は、普段の大人しい性格が鳴りを潜めていて、別の人格が宿っているようにすら見えた。
指摘しないといけないだろうという予想は、大きく外れた。歌唱中の視線は真っ直ぐ前を向いていたし、本来なら地声だって大きいのではなかろうか。そうとしか思えない位に声量があった。よく通る歌声だった。
それなのに一旦歌が終わってしまうと、すぐに普段の彼女に戻ってしまう。
ユウキは別に普段の侑子のことを好ましく思わないわけではなかったが、歌っている自分に対してちっとも好感を持っている様子のない彼女が、もどかしくて仕方がない。
あんなに魅力的なのに、なぜ拒絶にも見える反応をするのだろう。
『……ちっぽけな理由だって、自分でも分かってはいるんだけど』
ユウキの問に対する侑子の一言目は、苦笑いと共に吐き出された。
『歌は好き。大好きなの。小さい頃からずっと。耳に入ってきた歌で気に入ったフレーズがあると、すぐに真似して歌ってた』
しばらくぶりに思い起こす、何年か前の記憶。
記憶を頭の中でなぞりながら、ユウキに語る。
『私が小学校……七歳から十歳くらいまで、母がお年寄りが共同生活する施設で働いてたの。家のすぐ近所にあって、学校が終わると、母が働く側で仕事が終わるのを待ってたんだ。おじいちゃんやおばあちゃんとお話したり、ちょっとしたお手伝いとかしながら。そこでね、よく昔の歌を皆が歌ってたの。おじいちゃんおばあちゃん達が若い頃に流行った歌とか、子供の頃に皆で歌ってた歌を』
最近では家を離れている時間が長くなっている母も、あの頃は毎日家にいた。
仕事の間も気軽に会いに行くことができたのだ。
叔父一家と兄との生活にも不満はなかったが、思い出すとやはりあの頃は、絶対的な安心感があった。
『そこで覚えた歌を、よく歌ってた。私が歌っていると皆褒めてくれたし、喜んでくれたの。それが嬉しかったのもある。もちろん、歌そのものが素敵だって感じたのが大きいけど。だけどね、ある日学校の友達の中で、好きな歌を歌う機会があって、そこでいつもみたいに歌ったんだけど……』
あの時自分が歌っていた旋律は、簡単に思い出すことができる。
あれから人前で声に出したことはなかったが、頭の中ではしょっちゅう歌っていた。それくらい好きだったのだから。
侑子の脳裏に、あの日のカラオケボックスの、小さな個室の風景が鮮明に蘇った。
地域の子供会イベントの打ち上げだったはずだ。
侑子は母と二人で出席していて、近所の同級生達も親子で参加していた。
そこで侑子は、何の気になしにその時一番大好きだった曲を歌ったのだった。
『他の子が皆その時流行ってた曲を歌ってる中で、私だけ何十年も前の歌を歌ったのね。そしたら一斉にバカにされちゃって……こうやって話していると、些細なことだよなぁって思うんだけど。それから人の前で歌うのが、どんどん嫌になった』
語彙力も、誰かを慮る能力も乏しい小学生の言葉は、素直な分だけ残酷だった。
侑子が美しいと思っていた歌詞表現はダサいと指摘され、心を揺さぶられるほど好ましく感じていた旋律は、古臭いと一蹴された。
終いには自分の歌い方にまで心無い言葉が浴びせられ、泣いていると気づいた時には、既にその場に気まずい空気が立ち込めていたのだった。
貶した子供の親たちは我が子を叱って侑子の歌を褒めてはくれたが、それが本心からの言葉ではなく、とりあえずその場をおさめるために取り繕ったものであることも分かっていた。
それで余計に惨めな気持ちになった。
リモコンのストップボタンを押したのは、誰だったのか覚えていない。
侑子が歌うことをやめた曲の旋律だけが、カラオケ独特の安っぽい音に乗せて、しばらくの間その場に流れていた。
『気にすることないって分かってる。好きな歌は好きでいていいってことも、分かってるの。歌うことが好きな気持ちも、ずっと変わってない。だけど人前で歌おうとすると、あの時のことを思い出して、歌いたくないって思ってしまう。あんな嫌な気持ちにまたなるくらいなら、歌わないでいいやって。歌うだけなら、一人の時でも歌えるんだからって』
そこまで話して、ユウキがずっとこちらを真剣な眼差しで見ていることに、気がついた。
言葉を挟むことなく、ただ侑子の話に集中している。
途端に恥ずかしくなって、俯いた。
『ユウキちゃんが苦しんだことに比べれば、本当にちっぽけな理由でしょう? こんなことも乗り越えられないなんて、やっぱり情けないって思うんだよ。だからますます歌えなくなる』
これ以上説明することもない。
何か理由を付け加えようとすると、言い訳にしかならない気がして、侑子は口をつぐんだ。
今はただ、決めたことをやるしかない。それがユウキと一緒ならば、きっと大丈夫だ。
一人で歌ったあの時とは、違うのだから。
さあ、練習しようと侑子が再び唇を動かそうとした時だった。それよりも早く、ユウキが口を開いた。
『大きいも小さいもない。ユーコちゃんがそれ程辛かったなら、それ程大きな傷だったってことだよ。他の誰かの苦しみと、自分の苦しみを比較するなんて無意味だ』
ユウキの手が侑子の手を包み込んだ。
『話してくれてありがとう』
微笑んだその顔がひどく優しくて、侑子はあの半魚人が目の前にいると強く意識した。
これが夢の中だったら、迷わず胸に飛び込んで抱きしめていただろう。
『俺はユーコちゃんの歌が好きだ。一緒に歌っていると、あの夢の中にいるみたいに感じるんだ。こんなに幸せな気持ちで歌えるのだから、俺は救われている。どんなに大勢の前で歌って、仮に否定的な感想を持つ人がいたとしても忘れないで。一番近くで一緒に歌っている俺だけは、間違いなく君の歌が大好きなんだって』
あの半魚人は喋らなかったし、歌ったことはなかったはずだ。
けれど侑子は不思議なほどすんなりと、あの夢の中で歌った時、半魚人も一緒に歌っていたのだという確信を受け入れていたのだった。
歌おう、というユウキの声に、侑子は今までで一番の前向きな気持ちと共に、頷くことが出来た。
***
そんな出来事の翌日だった。
ユウキが卒業祝いに、謝恩会で一緒に歌ってほしいと言い出したのだ。
まだ一週間ほど猶予があるはずだった噴水広場での披露の日よりも、日数がなかった。しかしそれ以上に侑子を慄かせたのは、予想外の舞台と客層の前で歌うという事態だった。
最初は渋い表情を浮かべていた侑子だが、自分からの卒業祝いにとユウキが希望したことと、気心知れた友人達を前にしたほうが、心のハードルが低いのだというユウキの説明に、遂に承諾してしまったのだった。
確かにいつもユウキの“才”を期待している観客達の前でそれを封印した自分を見せるより、やりやすいのは確かであろう。
そして舞台は変身館なのだ。
いつも素の声で彼が戦っている場所だ。
『……もしかして昨日の一連の流れは、私を今納得させるための作戦だった?』
少々意地悪な気持ちになって、侑子は訊いてみた。
しかしユウキは涼しい顔で口角を上げただけで、否定も肯定もしなかった。
『どうだろう。ただ言えるのは、俺だって怖いってことだよ』
曖昧に濁しつつ、目を細めた。
『歌を、歌声を否定されることは怖いよ。母に性別を否定される以上に、多分今の俺にとって一番怖いことだ』
次の瞬間、ユウキはくしゃりと表情を崩して笑顔になる。
侑子はそんな顔のユウキから繰り出された言葉に、頷くしかなかった。
『だからユーコちゃんに甘えたの。お願いだから、一緒に歌ってほしい。怖いんだ。だから横で、君の歌を聞きながら歌いたい』
初めこそ緊張したものの、侑子がユウキの前で歌うことに抵抗を感じなくなるのはすぐだった。
夢の中でよく歌っていたからかもしれないし、すっかりユウキに心を許していたからかもしれない。
そしてユウキは侑子が歌うたびに、恥ずかしくなるくらい称賛してくれたのだった。
どこまでも甘くて優しいその言葉の一音一音は、侑子には錆落としのように思えた。
重く動かしづらかった心の扉の蝶番が、少しずつ本来の動きを取り戻していくのだ。
『ユーコちゃんは耳が良いのかもしれない』
ある日新しい曲の旋律を歌った侑子に、ユウキが言った。
『一度聴いただけで、正確に歌っちゃうんだもんな』
嬉しそうなユウキだったが、侑子は自覚がなかったのでピンとこない。
ただ聴いたとおりに歌うことしかしていないのだから、当然だ。
『もっと自信を持つこと。それがユーコちゃんの一番の課題だね。謙虚は良いことばかりじゃないよ』
日に一度は言われる文言だった。
しかしその日、ユウキは更に一歩踏み込んだところまで言及してきた。
『どうしてそんなに自信がないの?』
侑子と歌うようになってから、日に日に疑問が大きくなっていた。
歌に集中している時の彼女は、普段の大人しい性格が鳴りを潜めていて、別の人格が宿っているようにすら見えた。
指摘しないといけないだろうという予想は、大きく外れた。歌唱中の視線は真っ直ぐ前を向いていたし、本来なら地声だって大きいのではなかろうか。そうとしか思えない位に声量があった。よく通る歌声だった。
それなのに一旦歌が終わってしまうと、すぐに普段の彼女に戻ってしまう。
ユウキは別に普段の侑子のことを好ましく思わないわけではなかったが、歌っている自分に対してちっとも好感を持っている様子のない彼女が、もどかしくて仕方がない。
あんなに魅力的なのに、なぜ拒絶にも見える反応をするのだろう。
『……ちっぽけな理由だって、自分でも分かってはいるんだけど』
ユウキの問に対する侑子の一言目は、苦笑いと共に吐き出された。
『歌は好き。大好きなの。小さい頃からずっと。耳に入ってきた歌で気に入ったフレーズがあると、すぐに真似して歌ってた』
しばらくぶりに思い起こす、何年か前の記憶。
記憶を頭の中でなぞりながら、ユウキに語る。
『私が小学校……七歳から十歳くらいまで、母がお年寄りが共同生活する施設で働いてたの。家のすぐ近所にあって、学校が終わると、母が働く側で仕事が終わるのを待ってたんだ。おじいちゃんやおばあちゃんとお話したり、ちょっとしたお手伝いとかしながら。そこでね、よく昔の歌を皆が歌ってたの。おじいちゃんおばあちゃん達が若い頃に流行った歌とか、子供の頃に皆で歌ってた歌を』
最近では家を離れている時間が長くなっている母も、あの頃は毎日家にいた。
仕事の間も気軽に会いに行くことができたのだ。
叔父一家と兄との生活にも不満はなかったが、思い出すとやはりあの頃は、絶対的な安心感があった。
『そこで覚えた歌を、よく歌ってた。私が歌っていると皆褒めてくれたし、喜んでくれたの。それが嬉しかったのもある。もちろん、歌そのものが素敵だって感じたのが大きいけど。だけどね、ある日学校の友達の中で、好きな歌を歌う機会があって、そこでいつもみたいに歌ったんだけど……』
あの時自分が歌っていた旋律は、簡単に思い出すことができる。
あれから人前で声に出したことはなかったが、頭の中ではしょっちゅう歌っていた。それくらい好きだったのだから。
侑子の脳裏に、あの日のカラオケボックスの、小さな個室の風景が鮮明に蘇った。
地域の子供会イベントの打ち上げだったはずだ。
侑子は母と二人で出席していて、近所の同級生達も親子で参加していた。
そこで侑子は、何の気になしにその時一番大好きだった曲を歌ったのだった。
『他の子が皆その時流行ってた曲を歌ってる中で、私だけ何十年も前の歌を歌ったのね。そしたら一斉にバカにされちゃって……こうやって話していると、些細なことだよなぁって思うんだけど。それから人の前で歌うのが、どんどん嫌になった』
語彙力も、誰かを慮る能力も乏しい小学生の言葉は、素直な分だけ残酷だった。
侑子が美しいと思っていた歌詞表現はダサいと指摘され、心を揺さぶられるほど好ましく感じていた旋律は、古臭いと一蹴された。
終いには自分の歌い方にまで心無い言葉が浴びせられ、泣いていると気づいた時には、既にその場に気まずい空気が立ち込めていたのだった。
貶した子供の親たちは我が子を叱って侑子の歌を褒めてはくれたが、それが本心からの言葉ではなく、とりあえずその場をおさめるために取り繕ったものであることも分かっていた。
それで余計に惨めな気持ちになった。
リモコンのストップボタンを押したのは、誰だったのか覚えていない。
侑子が歌うことをやめた曲の旋律だけが、カラオケ独特の安っぽい音に乗せて、しばらくの間その場に流れていた。
『気にすることないって分かってる。好きな歌は好きでいていいってことも、分かってるの。歌うことが好きな気持ちも、ずっと変わってない。だけど人前で歌おうとすると、あの時のことを思い出して、歌いたくないって思ってしまう。あんな嫌な気持ちにまたなるくらいなら、歌わないでいいやって。歌うだけなら、一人の時でも歌えるんだからって』
そこまで話して、ユウキがずっとこちらを真剣な眼差しで見ていることに、気がついた。
言葉を挟むことなく、ただ侑子の話に集中している。
途端に恥ずかしくなって、俯いた。
『ユウキちゃんが苦しんだことに比べれば、本当にちっぽけな理由でしょう? こんなことも乗り越えられないなんて、やっぱり情けないって思うんだよ。だからますます歌えなくなる』
これ以上説明することもない。
何か理由を付け加えようとすると、言い訳にしかならない気がして、侑子は口をつぐんだ。
今はただ、決めたことをやるしかない。それがユウキと一緒ならば、きっと大丈夫だ。
一人で歌ったあの時とは、違うのだから。
さあ、練習しようと侑子が再び唇を動かそうとした時だった。それよりも早く、ユウキが口を開いた。
『大きいも小さいもない。ユーコちゃんがそれ程辛かったなら、それ程大きな傷だったってことだよ。他の誰かの苦しみと、自分の苦しみを比較するなんて無意味だ』
ユウキの手が侑子の手を包み込んだ。
『話してくれてありがとう』
微笑んだその顔がひどく優しくて、侑子はあの半魚人が目の前にいると強く意識した。
これが夢の中だったら、迷わず胸に飛び込んで抱きしめていただろう。
『俺はユーコちゃんの歌が好きだ。一緒に歌っていると、あの夢の中にいるみたいに感じるんだ。こんなに幸せな気持ちで歌えるのだから、俺は救われている。どんなに大勢の前で歌って、仮に否定的な感想を持つ人がいたとしても忘れないで。一番近くで一緒に歌っている俺だけは、間違いなく君の歌が大好きなんだって』
あの半魚人は喋らなかったし、歌ったことはなかったはずだ。
けれど侑子は不思議なほどすんなりと、あの夢の中で歌った時、半魚人も一緒に歌っていたのだという確信を受け入れていたのだった。
歌おう、というユウキの声に、侑子は今までで一番の前向きな気持ちと共に、頷くことが出来た。
***
そんな出来事の翌日だった。
ユウキが卒業祝いに、謝恩会で一緒に歌ってほしいと言い出したのだ。
まだ一週間ほど猶予があるはずだった噴水広場での披露の日よりも、日数がなかった。しかしそれ以上に侑子を慄かせたのは、予想外の舞台と客層の前で歌うという事態だった。
最初は渋い表情を浮かべていた侑子だが、自分からの卒業祝いにとユウキが希望したことと、気心知れた友人達を前にしたほうが、心のハードルが低いのだというユウキの説明に、遂に承諾してしまったのだった。
確かにいつもユウキの“才”を期待している観客達の前でそれを封印した自分を見せるより、やりやすいのは確かであろう。
そして舞台は変身館なのだ。
いつも素の声で彼が戦っている場所だ。
『……もしかして昨日の一連の流れは、私を今納得させるための作戦だった?』
少々意地悪な気持ちになって、侑子は訊いてみた。
しかしユウキは涼しい顔で口角を上げただけで、否定も肯定もしなかった。
『どうだろう。ただ言えるのは、俺だって怖いってことだよ』
曖昧に濁しつつ、目を細めた。
『歌を、歌声を否定されることは怖いよ。母に性別を否定される以上に、多分今の俺にとって一番怖いことだ』
次の瞬間、ユウキはくしゃりと表情を崩して笑顔になる。
侑子はそんな顔のユウキから繰り出された言葉に、頷くしかなかった。
『だからユーコちゃんに甘えたの。お願いだから、一緒に歌ってほしい。怖いんだ。だから横で、君の歌を聞きながら歌いたい』