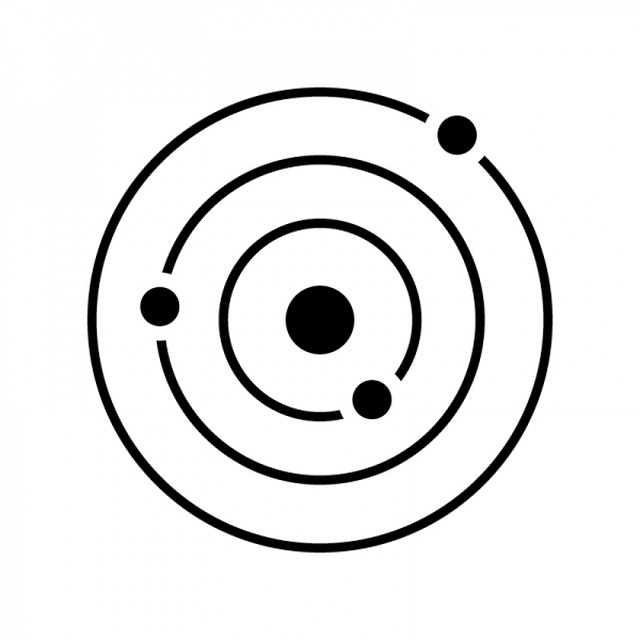60.ラストラリー
文字数 2,110文字
沈黙が流れた。
閉ざされた空間に、穏やかな波の音だけが繰り返される。
ミネコにとっては、懐かしい故郷の音だった。
何かを決意したかのように、ミネコは首にかけていた細い組紐をおもむろに手繰り寄せた。
服の中に隠すようにしまわれていた、紐の先――――そこには、白く光る勾玉があった。
「ミネコさん!」
この場にいる者で目にして良いのは、守り役だけだ。神器に関する掟として伝え聞いていたオリトは、ミネコの突然の行動に、思わず咎める視線を送っていた。
「見たって、目が潰れたりしないでしょう?」
ミネコの口調は落ち着いており、むしろどこか諦めの色さえ浮かんでいる。
「私は既に掟を何度か破っています。王やオリトくんたちに何も連絡しないまま、神器を持って失踪した。勝手に力を解放して、扉を開いた……それも二度も」
首から紐を取り外し、掌の上に勾玉を包み込むように置いたミネコの目は、親しい家族に向けるような優しいものだった。
「鍵は人間を罰することも、褒めたりもしないの。ただ力を解放すべき場所で、守り役に共鳴を求めるだけ。……こんなに掟をやぶり続けている私を、鍵は今だに守り役として認めているでしょう?」
ミネコの言葉を肯定するかのように、勾玉と彼女の身体が、より一層強く輝いた。
同じ白い光の中で、オリトは反論の言葉を失う。
――なんという神々しさだろう
小さな漁村の中で、ミネコは少し年の離れた姉のような存在だった。幼い頃から遊んでもらった、沢山の楽しい思い出がある。よく知っている顔のはずなのに、白い光を纏った彼女は、人間ではない別の次元の生き物のように見えた。
「なぜここへ戻られた?」
直視するのが苦しくなった。
オリトは床を見つめながら、短く問うた。
「代替わりのため? 神器を返すため? 私にはそうは考えられない……あなた以外に、この村には守り役の適任者はいません」
鍵はミネコを今でも守り主に定めている――その直感は外れていないはずだ。曲がりなりにも、この神社を父から受け継いで宮司を務めているのだから。
「……ミネコ」
会話の先を促しているのだろうか。ヘイルがミネコを呼んだ。
「オリトくん。守り役を継いでくれる適任者に、本当に心当たりはいませんか」
これまでで最も声を落とした、ミネコの言葉だった。強い発光はそのまま、表情から力が抜けていく。
「鍵はそれを望んでいないではないですか」
「分かっています。……けれど、試す必要があるの」
「試す?」
怪訝な表情の宮司に、ミネコは僅かに怯んだように言葉を飲み込んだ。
「ミネコさん?」
「中治り現象って、知ってる?」
「え?」
唐突な話題の切り替えかと思ったオリトは、すっとんきょんな声を出した。
「なかなおり現象……?」
腑に落ちていない表情の宮司に、解説を加えたのはシュマだった。高い声がやけに機械的にオリトの耳に響いた。
「死にそうに見えていた人が、死の直前に一時的に元気になる現象のこと――――ですよ、宮司様」
その説明に、オリトは父の最期の数日間の様子を思い出した。
流動食はもちろん、水も飲めなくなった父を、もうこのまま静かに見送るしかないだろうと、心を決めていた日のことだった。リヒトは突然寝床から自力で起き上がり、『アイスが食べたい』と言い出したのだ。大慌てで彼が指定した商品を、買いに走ったものだ。
希望通りの甘味を口にしたリヒトは、その後一週間は自力で動くほどに回復していたが、ある朝目が冷めることなく事切れていた。
「この強い共鳴」
ミネコは目を閉じ、身体に流れ込んでくる、自分のものとは別のエネルギーを感じていた。
雪のように冷たく、冷たいと脳が処理した瞬間、湯に触れたように暖かさを感じる。相反する二つの感覚が捻り合わされている。
「この共鳴を感じる少し前まで、鍵の神力は弱くなっていました。今まで感じたことがないほど……私が意識して感じ取ろうとしないと、分からないくらいに」
「何を」
「神器にも、死は存在するのですか?」
オリトの言葉を遮って、ミネコは訊いた。
「……死?」
「神力が宿って神器として機能している間、その状態を『生きている』と表現できるとしたら。だとしたら、これから鍵に訪れようとしているのは、『死』……私にはそう伝わってくる」
「死? 神器が死ぬというのですか。それは鍵の中の神力が、空っぽになるということですか……私たちの魔力と同じように、枯渇するとでも」
「だから試したいと思ったの。もし守り役が交代したら、鍵は神器として再び蘇るのか」
瞼を上げたミネコの瞳は、遊色を踊らせながら、青い顔の宮司を映していた。
「この強い共鳴が、中治り現象 のように思えてならない。神器が死んだらどうなるの? ねえ、オリトくん。鍵が失われたら――扉が開かれず、来訪者を呼ぶことが出来なくなってしまったら、この国はどうなってしまう?」
神々しい白いヴェールの向こう側に、涙を浮かべた女の顔が見えた。
不安に歪んだその表情に、オリトは人間らしさを見出して少しだけほっとしたものの、口惜しさも感じた。
できれば不安を摘み取った顔で、人らしさを感じたかったのだ。
しかしその方法は、彼には分からなかった。
閉ざされた空間に、穏やかな波の音だけが繰り返される。
ミネコにとっては、懐かしい故郷の音だった。
何かを決意したかのように、ミネコは首にかけていた細い組紐をおもむろに手繰り寄せた。
服の中に隠すようにしまわれていた、紐の先――――そこには、白く光る勾玉があった。
「ミネコさん!」
この場にいる者で目にして良いのは、守り役だけだ。神器に関する掟として伝え聞いていたオリトは、ミネコの突然の行動に、思わず咎める視線を送っていた。
「見たって、目が潰れたりしないでしょう?」
ミネコの口調は落ち着いており、むしろどこか諦めの色さえ浮かんでいる。
「私は既に掟を何度か破っています。王やオリトくんたちに何も連絡しないまま、神器を持って失踪した。勝手に力を解放して、扉を開いた……それも二度も」
首から紐を取り外し、掌の上に勾玉を包み込むように置いたミネコの目は、親しい家族に向けるような優しいものだった。
「鍵は人間を罰することも、褒めたりもしないの。ただ力を解放すべき場所で、守り役に共鳴を求めるだけ。……こんなに掟をやぶり続けている私を、鍵は今だに守り役として認めているでしょう?」
ミネコの言葉を肯定するかのように、勾玉と彼女の身体が、より一層強く輝いた。
同じ白い光の中で、オリトは反論の言葉を失う。
――なんという神々しさだろう
小さな漁村の中で、ミネコは少し年の離れた姉のような存在だった。幼い頃から遊んでもらった、沢山の楽しい思い出がある。よく知っている顔のはずなのに、白い光を纏った彼女は、人間ではない別の次元の生き物のように見えた。
「なぜここへ戻られた?」
直視するのが苦しくなった。
オリトは床を見つめながら、短く問うた。
「代替わりのため? 神器を返すため? 私にはそうは考えられない……あなた以外に、この村には守り役の適任者はいません」
鍵はミネコを今でも守り主に定めている――その直感は外れていないはずだ。曲がりなりにも、この神社を父から受け継いで宮司を務めているのだから。
「……ミネコ」
会話の先を促しているのだろうか。ヘイルがミネコを呼んだ。
「オリトくん。守り役を継いでくれる適任者に、本当に心当たりはいませんか」
これまでで最も声を落とした、ミネコの言葉だった。強い発光はそのまま、表情から力が抜けていく。
「鍵はそれを望んでいないではないですか」
「分かっています。……けれど、試す必要があるの」
「試す?」
怪訝な表情の宮司に、ミネコは僅かに怯んだように言葉を飲み込んだ。
「ミネコさん?」
「中治り現象って、知ってる?」
「え?」
唐突な話題の切り替えかと思ったオリトは、すっとんきょんな声を出した。
「なかなおり現象……?」
腑に落ちていない表情の宮司に、解説を加えたのはシュマだった。高い声がやけに機械的にオリトの耳に響いた。
「死にそうに見えていた人が、死の直前に一時的に元気になる現象のこと――――ですよ、宮司様」
その説明に、オリトは父の最期の数日間の様子を思い出した。
流動食はもちろん、水も飲めなくなった父を、もうこのまま静かに見送るしかないだろうと、心を決めていた日のことだった。リヒトは突然寝床から自力で起き上がり、『アイスが食べたい』と言い出したのだ。大慌てで彼が指定した商品を、買いに走ったものだ。
希望通りの甘味を口にしたリヒトは、その後一週間は自力で動くほどに回復していたが、ある朝目が冷めることなく事切れていた。
「この強い共鳴」
ミネコは目を閉じ、身体に流れ込んでくる、自分のものとは別のエネルギーを感じていた。
雪のように冷たく、冷たいと脳が処理した瞬間、湯に触れたように暖かさを感じる。相反する二つの感覚が捻り合わされている。
「この共鳴を感じる少し前まで、鍵の神力は弱くなっていました。今まで感じたことがないほど……私が意識して感じ取ろうとしないと、分からないくらいに」
「何を」
「神器にも、死は存在するのですか?」
オリトの言葉を遮って、ミネコは訊いた。
「……死?」
「神力が宿って神器として機能している間、その状態を『生きている』と表現できるとしたら。だとしたら、これから鍵に訪れようとしているのは、『死』……私にはそう伝わってくる」
「死? 神器が死ぬというのですか。それは鍵の中の神力が、空っぽになるということですか……私たちの魔力と同じように、枯渇するとでも」
「だから試したいと思ったの。もし守り役が交代したら、鍵は神器として再び蘇るのか」
瞼を上げたミネコの瞳は、遊色を踊らせながら、青い顔の宮司を映していた。
「この強い共鳴が、
神々しい白いヴェールの向こう側に、涙を浮かべた女の顔が見えた。
不安に歪んだその表情に、オリトは人間らしさを見出して少しだけほっとしたものの、口惜しさも感じた。
できれば不安を摘み取った顔で、人らしさを感じたかったのだ。
しかしその方法は、彼には分からなかった。