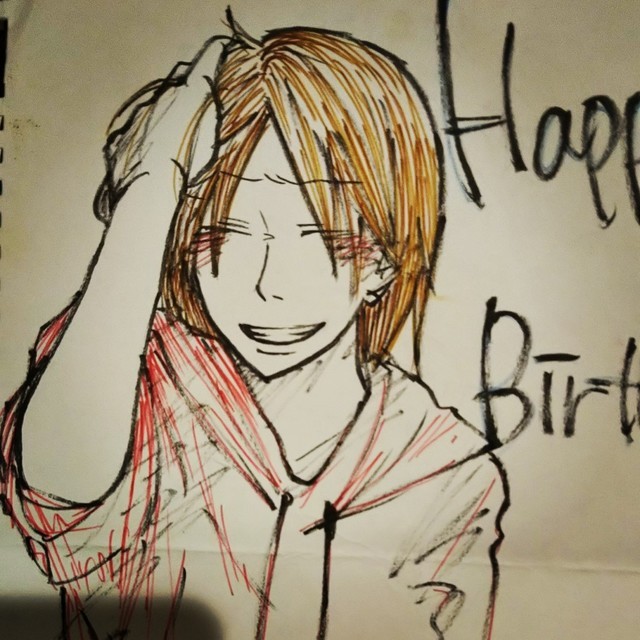聖7〈8月16日(月)〉
文字数 5,459文字
一
「なぁ、女を口説くときに必要なもんっつったら何だと思う?」
まだ日の高い時間の事だった。高崎先輩はシャチの浮き輪に寝転んだまま肘をついた。逆光。歯だけがまぶしい。
「・・・・・・度胸?」
至って真面目に答えたつもりだったが、先輩は吹き出すと、思いっきり笑った。
「確かにその通りだな! お前の場合特に」
ひとしきり笑い終えると、目の端をぬぐう。僕は馬鹿にされる理由が分からない。
「違う。馬鹿になんてしてない。ただ、いい事教えてやろうと思ってな」
再び肘をつく。よく焼けた太い腕には血管が浮き出ている。小さな目が絶えず上下する波を映して、逆光の中揺らめいた。
「言い訳だよ。向こうのな」
海の中心に向かって日が沈んでいくのを見て驚いた。方位磁針が狂う。僕は防波堤沿いを歩きながらぐるりと辺りを見渡した。無意識、というのはまさにこういう事を言うのだろう。疑う余地のなかった前提が突如ひっくり返る。僕は「海のある方角は南」だと思い込んでいた。西日、とは称するものの、日本海側、東北地方だってイレギュラー。テストに出れば当たり前に答えられても、わざわざ問われない限り、立ち止まらず進んでいくのだ。
つまり昨日、僕がバスを降りて辿った道は「とにかく南へ」だった訳だから、本来一本道の、距離にして五分程度の所を、わざわざ十五分かけて迂回した事になる。確かにこの菓子処の看板、行きのバスで見た気がしないでもない。
歩道のすぐ傍を大型のトラックが通った。ガタガタと地面が揺れる。振り向くとその頬に再び橙の光が差すところだった。目が合う。鈴汝さんは気まずそうに顔を伏せた。
遡ること三十分。鮫島先輩が戻ってくると同時にお開きになった。車を運転してきたのは高崎先輩で、火州先輩と鮫島先輩は同乗してきたのだという。六人乗りのエルグランド。乗ってくか? と誘われたが気が乗らず、丁重に断りを入れた。想定外だったのはその時「あたしも水島と帰るんでいいです」という声が上がった事だった。再び浮かび上がる不審。素直に喜ぶことが出来ない。その一方で、所在なさげにしていた草進さんは「おう弟子、お前も乗れ」の一言で車に詰められた。
「悪かったわね、無理やりついて来て」
「・・・・・・いえ」
車が肩先をかすめるような狭い歩道はもう少しで抜ける。僕は少しだけ足を速めた。
二
あの後鈴汝さんは「遅くなってごめんなさい。ちょっと辺りを探索していたら時間を忘れてしまったの」と小走りに戻ってきた。そこに一緒にいたはずの鮫島先輩の姿はなく、高崎先輩が尋ねると「寄るとこあるから先行っててだって」と言った。言いながら探すタオル。その唇が青ざめている。よく見れば震えていた。返された上着。右腕をのぞく全身から水がしたたり落ちている。今更海に入ったのかと思うと、得体の知れない違和感が僕を覆った。
大層な迂回に気づかないはずがなかった。けれども鈴汝さんはその事について何も言わなかった。十六時二十八分発のバスに乗り、座席に着くと「楽しかった?」と目を合わさずに聞いてきた。
「はい」
コンビニの前を通る。瓦屋根の住宅。民家に紛れた工場の煙突。昨日見た光景をそのままなぞって進む。手すりの低い橋。遮ることのない夕日を全身に浴びる。くっと胸の奥が引き攣れた。本物の美しさに触れると、多少なりとも傷を負う。それは本当に美しいと感じるもの自体が、特定の相手の存在によって生み出される事に他ならない。光とともに伸びる影。それは幼子が自宅に帰るときの安心感でもあり、同時に母親がいなくなったらどうしようという底抜けの不安感でもあった。
「・・・・・・そう。良かったわね」
僕の返事に反応して返ってきのは、思ったよりもずっと小さな声だった。橋を越えて建物の間に入れば、ウソのように辺りは暗くなった。空こそ水面が反射した光を見せてくれるが、それが影を濃くもしていた。ただ熱を持った上着はそう簡単には元に戻らない。例え建物の隙間から光が差すことがあったとしても、黒は何物にも影響されない色なのだ。
「水島」
「はい」
「あんた・・・・・・その、亡くなった彼女さんを忘れるためにどうした?」
「忘れようだなんて思った事はありません」
とある状況下での対応、ケース一。そんなフォーマット化を強いられるのは不本意だった。下手な共有は控えめに言って不愉快だ。
「そう・・・・・・ごめんなさい」
鈴汝さんはつぶやくように口にするとうつむいた。流れる街並。まるで走馬灯だ。昨日、今日の出来事を、目に見える形で思い出にかえていく。音もなくうつろう。
「何か・・・・・・あったんですか?」
「・・・・・・ううん、別に」
そう言って鈴汝さんは、再び黙り込んだ。
三
「なぁ」
昨晩の風呂上がり、敷かれた布団に寝転がると、鮫島先輩が上目遣いに聞いてきた。細い体躯。その胸元がはだけている。赤みを帯びた肌は純粋に日焼けによるものだ。
「お前何か食うとき、好きなもんあったら先に食べる派? 後にとっとく派?」
僕は二つの水鉄砲をバッグにしまい、振り返る。これらは元はと言えばいたずら好きのこの人から身を守るために購入したものだったが、他に温泉の利用客がいなかったため、露天のドアや岩、鏡の設置された洗い場のコンクリートを使って、割と本気で遊んでしまった。洗面器片手に何やってんだこいつらと言われても弁解のしようがない。
「・・・・・・とっとく派です」
「だろうね。ちなみに俺は先食べちゃう派」
鮫島先輩は聞いてもいないのに答えて足を揺らした。頬杖。女子ではないため、かわいくはない。その目がキラキラしている。
「だってその後なんかあったとしても、そこまでの楽しみって残る訳じゃん?」
僕も寝転がる。仰向けだと蛍光灯がまぶしい。「そう思わない?」にんまりと笑った顔。右に偏った表情筋。つられて僕も笑った。久しぶりに正面から真逆の価値観に触れる。それがひどく小気味よかった。まっすぐ見上げる。
「さぁ、どうでしょう」
焼津駅に着くと切符を買う。時刻は十六時四十七分。丁度五分後に下りの電車が来る。構内が混み始める頃だった。基本静岡か三島か興津から来る電車は、とにかく激しい乗車争いを静岡で繰り広げてやって来る。横に長いにもかかわらず、鈍行しかないという希有な存在の東海道線は、だからどの列車を選んでも同じ条件だ。降車する乗客と肩を入れ違うようにして乗車すると、シートは隙間なく埋まっていた。仕方ないので反対側のドアの近くの手すりをとった。振り返ると鈴汝さんはスーツを着た男性に押されるようにしてつんのめっていた。つり革が頼りなく音を立てる。思わずため息が出た。黙って身体の位置を入れ替える。
「ここ」
つり革を離そうとしない彼女に、座席の手すりを示すと、ようやく不安定極まりない姿勢から解放された。鈴汝さんは一度だけ会釈すると、窓の方を見た。
ガタタン。
長いまつ毛。西日は当たっても平気なのか、まっすぐ前を向いてる。額、鼻先、唇、顎。なめらかな輪郭に、密度の高い焼けた肌。向こうを向いた所で窓に反射する。まばたき。愛想のない頬。その喉が少しだけ動いた。ああ、どうして。
ガタタン。
目をつむる。つむってゆっくりと開ける。今度はちゃんと窓の外を見た。
「鈴汝さんは・・・・・・楽しかったですか?」
大きな山は緑。大自然の腹を通過して田んぼが整備された土地に出ると、なぜかホッとした。確実に自分たちの居住空間に近づいているのだという安心感からかもしれない。
「ええ」
次の駅に着くと一気に乗客が減った。掛川は新幹線の停車駅でもある。この時期は特に利用する人が多いのだろう。二人並んでシートに腰かける。腰掛けた所で、残り一駅か二駅。時間換算したら残り十分もないのだが。
ガタタン。
非日常が終わる。今、当然のように隣にいる彼女は、十分後にはいなくなってしまう。そうなってしまえばスズナと大差ない。触れられない一点に限っては完全に合致してしまう。まばたきが目の端に映った。息を吸い直す音。膝が電車に合わせて揺れた。
〈さしずめ、都合のいいように美化されてな〉
大袈裟だろうか。でも仕方ないのだ。僕はある種、病にかかってしまったのだから。
ガタタン。
「あたし、次で降りるから」
だから、仕方ない。次の駅に止まって彼女が立ち上がった瞬間、その腕をつかんで放さなかったことは。本当に仕方ないことだった。
四
駅の北口から出ると、ターミナルに沿って歩き始めた。駐輪場の手前では、電車の到着に合わせた送迎車が列をなしている。その間を自転車で器用にくぐり抜けていったのは、丁度僕らと同じ位の年の子だった。大きな鞄から見えた冊子。夏期講習の帰りかもしれない。すぐ後ろにある気配から少しだけ距離を置く。
郵便局の前を通って北に抜けると、十字路を右折。丁度一年前この場所にあった進学塾は、いつの間にか駅から北に伸びた主要道沿いに立て直されていた。緩やかな下り坂の脇に走る線路。
「どうして」
道幅の割に車通りが多い。やむなく一本中の道に入るが、コの字型に元の道路に戻され、なかなか思うように進めない。それでも何とか愛野公園まで辿り着いた所だった。袖を引かれて足を止める。時刻は十八時二十分。その輪郭が焼け始めていた。
逆光。うつむいた顔。震える指先。
「どうしてあの時引き止めたの?」
この人は今、弱っている。本来持ち合わせているはずのまっすぐな芯を持たない。スズナに見立てた立ち振る舞いは鳴りを潜め、会長としての立場さえ考慮しない関係性は、赤の他人そのものだった。
前を向く。道は二手に分かれていた。橋に隣接する主要道と、公園に続く脇道。僕は再び歩き始めた。
愛野公園とは言ったものの、正確に言うとここは原野谷川親水公園の前の通りだ。大橋の南に東西に走る道路で分けられた四つの区画の内一つで、地元の人間はまとめて愛野公園と称する。駐車場と公園を仕切る生け垣。僕はため息をつくと公園の敷地に入った。
「もう少し一緒にいたかった。それだけですが何か」
年季の入ったベンチ。けれどもささくれていないし、鳥のフンも落ちていない。鉄骨に木の板を乗せたそれはきちんと手入れされている。腰を下ろすと、うつむいたままの鈴汝さんの表情がよく見えるようになった。口元。奥歯を噛みしめているようだった。
「あたし、男の人大嫌いよ」
「知ってます」
「飛鳥様が好きよ」
「それも、知ってます」
「今日・・・・・・」
ぐ、と言葉に詰まる。豊かな水分。逆光の中でまばたきせずとも瞳が揺らめいた。
「以前お伝えしたはずです」
瞳の表面が揺れる。握り込んだ指先。まるで幼子だ。
「例えあなたが悪魔だろうと、他の誰かを好きになろうと、僕があなたを護ると言ったんです」
おそるおそるその顔が上がる。やっと目が合う。
「覚えておいて下さい。僕はあなたのことが好きなんです」
五
残っていた一台の車が出て行った。今宵は満月。いくら長い日に惑わされても、いい加減よい子は帰路につく時間だ。バーベキューでにぎわうカラフルな三角屋根。小川をまたいだ小橋や飛び石。なだらかな斜面はきちんと芝生が生えそろっていた。
「僕からも聞きたいことがあります」
座っている位置を少しずらすと隣を勧める。鈴汝さんは素直に従った。やっと話ができる。
「以前見かけた『前期会計報告書における用途不明金について』の書類、あれは何なんですか?」
一瞬その呼吸が止まった。大きく見開かれた目。息を呑んだまま凍りつく。
「何っ、のこと」
「あと、前期の書類の提出期限はいつですか?」
もはや隠しおおせない動揺。意味をなさない端の言葉だけを強い口調でぶつけて来る。だからもちろん、その事自体も全く意味はなさない。
「聞いているんです。金銭に関わる大事な事でしょう。一生徒会員として見過ごせないと言っているんです」
眉間に寄ったしわ。体裁を整える事も追いつかない。会長は「それは・・・・・・」と言ったっきり押し黙った。
ぽっかりと浮かんだ月。暮れなずむ空は水色。紫の尾ひれをつけてやさしいグラデーション。それと同時に、静かに下がっていく明度。三角屋根のシルエットが浮かび上がる。
「何があったんですか?」
「・・・・・・」
「言えないなら僕が会計を引き受けます」
はじかれたように顔を上げる。
「それは・・・・・・」
「だってそうでしょう。金銭の管理も出来ない生徒会に行事の運営を任せますか? 別にあなたを責めている訳ではありません。役割を分担した方がいいと提案しているんです」
「・・・・・・」
「とにかく、会計に関する書類一式を僕に下さい。分からないことは必ず確認しますから」
その目の表面が先程とは比べものにならない揺れ方をしている。否、音を立てて震えていた。何かを言おうとしてつぐむ。それを何度か繰り返した後、やっと、本体が顔を出す。
「渡せない・・・・・・」
「だから事情を聞いて、納得できれば手を出しませんよ」
「違うの」
その喉が引き攣れた。夏の微風にさえかき消されてしまいそうなか細い声。
「ないの。そろってないの」
「・・・・・・どういう事ですか」
ずるり、と引きずり出される。それは、悲鳴だった。
「ないの。領収書が。だから会計を引き継ぐことも出来ないの」
三角屋根のシルエットは全部で四つ。見方によっては、遠くからじっとこちらを観察しているようでもあった。