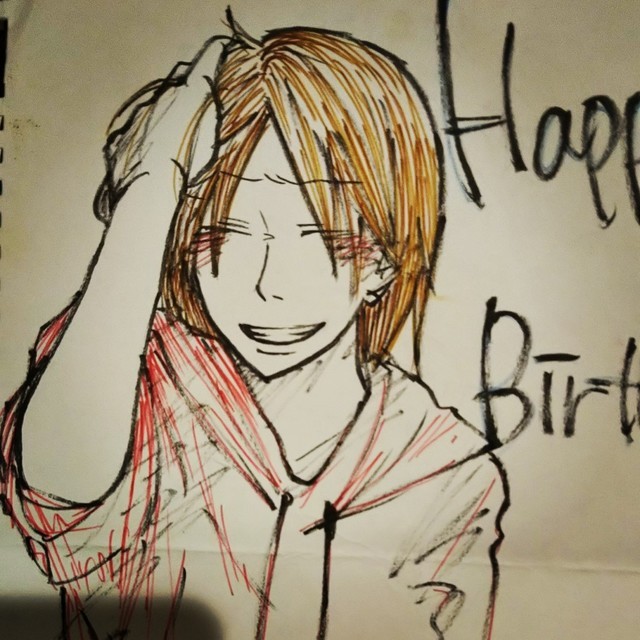真琴14〈1月6日(木)、7日(金)〉
文字数 5,362文字
一
既視感。この空と同じものを知っている。霧がかった、霞がかった、やわらかな質感。
あ、と思い当たる。フェルトだ。やわらかな生地を絵の具に沈めてすぐ上げ、色のしみこみきらない状態でやすりをかけた、そんなグラデーション。藍色をした山脈は別のフェルト。くぐもって塞ぐ。低い透明度。宇宙の存在など、どこにも見渡せない。
あったかいってのは気温どうこうだけじゃない。
「・・・・・・だなんて言うと思うなよ。テメェは黙って膝貸しときゃいいんだよ」
屋上。冷たい風はあっても、それを遮るものさえあれば日の光に包まれて心地よい昼間。師匠は不機嫌そうにそう宣言すると、私の太ももに顎をのせて腰にしがみついた姿勢のまま、鼻先をお腹にすりつけた。
冬休み明けの一月六日。時刻は十二時五十分。今日は半日のため、部活の始まる十三時半までは昼休憩だ。元は部室に直行するはずだった。
大きく息をついて空を見上げる。薄いアルミ製のドアを隔てて、階下から足音がした。冷気。キュッと縮まったサンダルの裏が固い音を立てる。
「浚(さら)いの風・・・・・・」
頭上を走り向ける風。フェルト。前夜が全てをさらったために何も残らない空を思い出す。
〈いました! こっちです〉
音のない世界。雪に閉じ込められていたのは時間にして六時間強。あの後警察に保護されて宿に戻った。そうして宿の別室に案内されると、毛布にくるまれたまま二三質問を受けた。内容は覚えていない。そのまま私だけ残して場所を変えようとする集団についていこうとすると、師匠に止められた。
〈いいから〉
移動した先は隣の部屋だった。この部屋の電気を消すと同時につけられた明かりがカーテン越しに漏れている。微かに聞こえる話し声。聞き取ろうと耳をそばだてている傍から、いつの間にか眠ってしまった。
二
「・・・・・・甘ぇ」
ふと目を落とすと、うつ伏せの体勢のまま、人のスカートをテーブルクロス代わりにしてカップケーキを食べていた。
「ちょっと師匠、行儀悪いですよ! あと食べカス落ちてるんですけど!」
「やるよ」
大きな歯形のついたそれは、現在進行形でボロボロカスを落とし続けている。それは
「・・・・・・これ、どうしたんですか?」
「ん? 雅ちゃんにもらった」
息を呑む。これは以前、私のクラスの調理実習でつくったものだ。
「前にお前にもらったのでチャラにしたから、これでチャラにしてくれって」
ざわめく。何かがつながる。私は、この会話を知っている。
〈・・・・・・これでチャラって言っといて。言えば分かるから〉
〈水島君にですか?〉
「『決して鮫島先輩を想ってつくった訳じゃありません。これはあくまで対価であって、あの時と条件は同じはずです』だって。もう途中から水島君と話してるのかと思っちゃった」
ざわめく。居合わせなくてもやりとりをする鈴汝さんの姿が浮かぶ。まっすぐに伸びた背筋。はじき返す。水島君が、何かから鈴汝さんを守る。
「これで計画がパァだよ。キモチよくつながっちまった。もう勝てねぇ」
「・・・・・・水島君にですか?」
「いんや」
人のスカートで口をぬぐう。最低を極めている。
「雅ちゃんにだよ」
〈おかえりなさい。無事でよかった。心配したのよ〉
そう言った鈴汝さんは、寝られなかったのだろう、目の下にクマをつくっていた。にも関わらず、顔を洗いなさい、ご飯を食べなさい、少し眠りなさいと矢継ぎ早に切り出すと、自分は部屋のドアを開ける。
「ここ鍵、閉めて頂戴」
せわしない。気遣いからか鈴汝さんは自室で食事をすることを選んだ。そのために階下のコンビニに赴く。
せわしない。表現はそれで合ってるはずだ。断じてよそよそしいではない。目が合わないのは偶然。未開封の歯ブラシやコップも偶然に違いない。
その後、髪を整えて時計を見ると、六時半を回るところだった。鈴汝さんは買って来たおにぎりやサンドウィッチを広げると、自分はミルクティーを開けた。
「・・・・・・甘」
「いいでしょ。人の好みよ」
ご飯にジュースとはなかなか刺激的だ。私は近くのおにぎりをとると、一口頬張った。
三
「・・・・・・こっちは特に問題ありませんでしたか?」
「ええ、」という返事はサンドイッチに向けてされた。
「停電こそあったけど特に不便はなかったし、そんなことよりあんた達が帰ってこないことの方が問題だったわ」
私達が旅館を出たのは十九時半。停電で不便が出ないというにはまだ早い時間帯に思える。
「水島君は何か言っていませんでしたか?」
「随分心配してたわ。結局フロントとのやりとりは全部あの子に任せてたの」
水島君。
安心したからこそ会いたくなる。水島君は今も一人で部屋にいるのだろうか。
「わ、私、水島君に一言」
「やめておきなさい。あの子眠れないって一晩中起きてたのよ。いい加減休んでる頃だわ」
エアコンがブゥン、とうなった。レースのカーテンの向こう、青空。昨日の事がウソのような晴天。うっすらと透けて見えるのは箱形の・・・・・・あれは浴槽だ。
コポポ。コポポポポ。
「あ、違うわ。そう聞いただけで、実際どうか知らないけど」
「・・・・・・いつ聞いたんですか?」
「明け方よ。あんたが帰ってくる直前。フロントから何か連絡入ってないかと思って」
「連絡入ってないかと思って、部屋まで行った」
ということですか、と尋ねると鈴汝さんはサンドウィッチを置いてミルクティーをとった。
「ええ、そうよ」
時計を見る。さっきから十五分しか進んでいない。
「六時とかにですか?」
「外が明るくなる頃よ。分かったことがあるかもしれないじゃない」
ペットボトルに口をつける。そのなめらかなのどが大きく動いた。わずかに陰った色味。横を向いたときに浮き出る首筋の内側、それは何かの跡にも見えた。
偶然。それも偶然。明るい光の差し込む部屋。影ができない方が不自然だ。
「・・・・・・火州さんは朝弱そうですね」
「・・・・・・。そうね。海行った時、翌朝動けてなかったものね」
減り続けるミルクティー。私はそののど元を見つめ続ける。何度見ても、同じ所に同じ形の影ができる。
「今回、火州さん来れなくて残念でしたね」
「そうね。でも大事な時期っていうんだから仕方ないじゃない」
本人ではなく高崎先輩に聞いたという。火州さん自身、自分の事は話したがらないらしい。
「努力を見せびらかす人と、隠したがる人がいるのって何でかしらね」
そう言うと鈴汝さんは笑った。自分は少しでも何かしたらすぐに言いたくなってしまうのに、と。でもそれはそんな『言葉で収まってしまうだけのことしかしてない』っていうことの裏返しなんでしょうね、と。
何故だろう。水島君に渡した黒いヘアゴムが頭をかすめた。
「鈴汝さん」
「あと、言いそびれてしまったけど、あたしちゃんとフラれたから。飛鳥様に」
ミルクティーを置く。初めてまっすぐ目が合う。偶然の中に紛れた、これこそが真実。
四
「お前の、何か細工してあったの?」
スカートの上の食べカスを払うと、再び元の体勢に戻る。のどが乾いたとだだをこねる師匠は再びお腹に鼻先を押しつけてくる。
「くすぐったいですやめて下さい。・・・・・・水島君とは同じ授業で同じものを作っていたので、別に渡す分にはインスタントコーヒーを大さじ一杯分足しました」
「だからか。王道はこっちで、お前がアレンジを加えてたワケね」
押しつけられたカップケーキ。一口かじると教科書通りの味がした。同じ授業、同じ教室で作ったもの。その場にいなかったはずの鈴汝さんが、これを。
「・・・・・・悪かったな。俺二つとも水島君の分だと思ってたけど、そうじゃなかったのな。雅ちゃんに聞いた」
コク、と乾いたものがのどを通る。詰まったのは想い。
二つ。一つは水島君。一つは鈴汝さんにあげようと思っていた。ミルクティー。甘い物が好きなあの人には元々合わなかったのかもしれない。
ふいに手をつかまれる。その反動で半身を起こした師匠は、カップケーキにかぶりついた。不安定。狙いを定めきれなかったために私の手までかじっていく。仰向け。再び横になって咀嚼する細いあご。長いまつげが落とす影。その頬は相変わらず不健康なほど白い。口元を拭う指先は女性以上に白魚のようだ。
「・・・・・・ばっちぃ」
だからといって人の唾液を好む人はいないだろう。私は残った水分のせいでひんやりとした部分をこすると、その眉間にシワが寄った。
「・・・・・・。回収。もういいだろ。胃がもたれる。まったく、俺の胃袋を間にはさんでやりとりするなっつの」
間に飛び込んできたのは師匠だ。
「うるさい。・・・・・・にしてもお前も災難だよな。こんな返し方されちゃ俺でも傷つくよ」
詰まったのは想い。鼻の奥がツンと痛んだ。
「アイツ、お前がそんな工夫してんのにも気づけねぇのな」
〈ごめん。付き合うって言ったの、なかったことにして欲しい〉
そう言ったとき、水島君は完全に閉じていた。何を言った所で入れやしない。それほどまでに圧倒的な距離感だった。どう思われようと構わない。自己防衛を放棄したその姿から感じたのは、身の凍るような冷たさだった。
一切の言い訳をしない。好きにしてくれと差し出す首。甘んじて罰を受けるというよりはむしろ罰を受けたがっているようにも見えるのは、その先に赦されたい何かがあるから。
『あなたにどう思われようと、そんなことよりも優先すべきことがある』という意思表示。それがどれだけ残酷なことか分かっているのだろうか。
ののしれれば良かった。手をあげられれば良かった。でもそんなことをしたところで、きっとこの人に決定的ダメージを与えることはない。自分が根付くことはない。絶望的な温度差にゆくゆく後悔するのは自分でしかない。だから黙って手を放す。最も影響力の大きいであろう、罰を受けないことで生じる後ろめたさ。それさえもいずれ過去の一瞬に与することを予感しながら、それしかできないのがどこまでも悲しかった。
降り積もった雪をまき散らす風。ものを吹きさらう風のことを「浚(さら)いの風」というらしい。教えてくれたのは鈴汝さんだ。じゃあその日、降り積もった雪を吹き散らしたのは、何かを吹きさらったのは、本当に風の仕業だろうか。じゃあその言葉自体、本当に鈴汝さんが知っていたのだろうか。決定的に変わってしまったあの日の何かを、恨まずにはいられない。
「・・・・・・寒くないか?」
「はい」
私のお腹と腰を守るようにしてホールドした状態で、師匠は大きく息を吸って吐くと「水島君にはもったいないよ」と言った。アイツバカだなぁ、と。
笑った。
「水島君をバカにしないで下さい」
「・・・・・・お前もバカだなぁ」
その頬が緩む。そうして「俺も大概か」と言った。
五
思いも寄らぬ事件が起こったのはその翌日だった。朝イチのざわついた教室。先生が来る前の数分に凝縮されているのは、同じテーマに対する考察だった。ミヤが駆け寄ってくる。
「慶子のこと、何か聞いてない?」
友人を心配して、というよりかは単純な好奇心による情報収集ととれた。私は「知らない」と答えるとその席を見た。その姿はまだ見えない。
慶子が谷浦先生と噂になったのは、昨日書庫に二人でいる所を生徒が目撃したからだ。それも先生が下になった状態で抱き合っている所を。元々書庫は図書室とは別に大学の入試関係、赤本だけを集めた部屋で、丁度職員室の真下にある。位置としての利便性と使用頻度は必ずしも一致しないが、全く使用されていない訳ではない。ごく一部の真面目な生徒にはちゃんと活用されている。しかしその真面目な生徒が目撃してしまった事が事を大きくする要因でもあった。自分が教えを乞う相手であるはずの教師による、それは立派な裏切りだった。
その日最後の授業が終わってもその席は空いたままだった。
慶子。
球技大会の時、同じチームだからと一緒に体育館に向かったのを思い出す。
〈水島君、この後試合するんだってね〉
楽しみだね、と振り返る。それは友人の幸せを心から願う顔。慶子自身、試合が終わるとミヤや早苗と合流するため卓球場に行ってしまったが、一緒にいなくても同じものを見ているような気がした。隣にいればきっと面白がって脇腹を小突いたのだろう。そうして夢と現実を行ったり来たり、私は足元を失うことなく安心して没入できたのだろう。
〈真琴〉
師匠が教室に現れた時首をもたげた繊細で獰猛な魔物。慶子だって気づいたはずだ。
〈ちょっと、ねぇ〉
それでもその向かいに立つ。今なら分かる。あの時の気持ちが。
鞄を持って顔を上げる。一方じゃあ私は慶子の何を知っているというのか。
「草進さん、」
振り返る。
水島君。
愛し、愛しいその声は、このときばかりは味方。
「・・・・・・床に散らばってたっていう本は、全部最上段のものだと思う。そこだけ天面にホコリが溜まってなかったから。事故の可能性が高い」
私はうなずくと足早に教室を出た。先生がいなくなり、再び自由を得て好き勝手に動き出した魔物。近くにいたはずのミヤや早苗の笑い声が嫌に耳に残った。
既視感。この空と同じものを知っている。霧がかった、霞がかった、やわらかな質感。
あ、と思い当たる。フェルトだ。やわらかな生地を絵の具に沈めてすぐ上げ、色のしみこみきらない状態でやすりをかけた、そんなグラデーション。藍色をした山脈は別のフェルト。くぐもって塞ぐ。低い透明度。宇宙の存在など、どこにも見渡せない。
あったかいってのは気温どうこうだけじゃない。
「・・・・・・だなんて言うと思うなよ。テメェは黙って膝貸しときゃいいんだよ」
屋上。冷たい風はあっても、それを遮るものさえあれば日の光に包まれて心地よい昼間。師匠は不機嫌そうにそう宣言すると、私の太ももに顎をのせて腰にしがみついた姿勢のまま、鼻先をお腹にすりつけた。
冬休み明けの一月六日。時刻は十二時五十分。今日は半日のため、部活の始まる十三時半までは昼休憩だ。元は部室に直行するはずだった。
大きく息をついて空を見上げる。薄いアルミ製のドアを隔てて、階下から足音がした。冷気。キュッと縮まったサンダルの裏が固い音を立てる。
「浚(さら)いの風・・・・・・」
頭上を走り向ける風。フェルト。前夜が全てをさらったために何も残らない空を思い出す。
〈いました! こっちです〉
音のない世界。雪に閉じ込められていたのは時間にして六時間強。あの後警察に保護されて宿に戻った。そうして宿の別室に案内されると、毛布にくるまれたまま二三質問を受けた。内容は覚えていない。そのまま私だけ残して場所を変えようとする集団についていこうとすると、師匠に止められた。
〈いいから〉
移動した先は隣の部屋だった。この部屋の電気を消すと同時につけられた明かりがカーテン越しに漏れている。微かに聞こえる話し声。聞き取ろうと耳をそばだてている傍から、いつの間にか眠ってしまった。
二
「・・・・・・甘ぇ」
ふと目を落とすと、うつ伏せの体勢のまま、人のスカートをテーブルクロス代わりにしてカップケーキを食べていた。
「ちょっと師匠、行儀悪いですよ! あと食べカス落ちてるんですけど!」
「やるよ」
大きな歯形のついたそれは、現在進行形でボロボロカスを落とし続けている。それは
「・・・・・・これ、どうしたんですか?」
「ん? 雅ちゃんにもらった」
息を呑む。これは以前、私のクラスの調理実習でつくったものだ。
「前にお前にもらったのでチャラにしたから、これでチャラにしてくれって」
ざわめく。何かがつながる。私は、この会話を知っている。
〈・・・・・・これでチャラって言っといて。言えば分かるから〉
〈水島君にですか?〉
「『決して鮫島先輩を想ってつくった訳じゃありません。これはあくまで対価であって、あの時と条件は同じはずです』だって。もう途中から水島君と話してるのかと思っちゃった」
ざわめく。居合わせなくてもやりとりをする鈴汝さんの姿が浮かぶ。まっすぐに伸びた背筋。はじき返す。水島君が、何かから鈴汝さんを守る。
「これで計画がパァだよ。キモチよくつながっちまった。もう勝てねぇ」
「・・・・・・水島君にですか?」
「いんや」
人のスカートで口をぬぐう。最低を極めている。
「雅ちゃんにだよ」
〈おかえりなさい。無事でよかった。心配したのよ〉
そう言った鈴汝さんは、寝られなかったのだろう、目の下にクマをつくっていた。にも関わらず、顔を洗いなさい、ご飯を食べなさい、少し眠りなさいと矢継ぎ早に切り出すと、自分は部屋のドアを開ける。
「ここ鍵、閉めて頂戴」
せわしない。気遣いからか鈴汝さんは自室で食事をすることを選んだ。そのために階下のコンビニに赴く。
せわしない。表現はそれで合ってるはずだ。断じてよそよそしいではない。目が合わないのは偶然。未開封の歯ブラシやコップも偶然に違いない。
その後、髪を整えて時計を見ると、六時半を回るところだった。鈴汝さんは買って来たおにぎりやサンドウィッチを広げると、自分はミルクティーを開けた。
「・・・・・・甘」
「いいでしょ。人の好みよ」
ご飯にジュースとはなかなか刺激的だ。私は近くのおにぎりをとると、一口頬張った。
三
「・・・・・・こっちは特に問題ありませんでしたか?」
「ええ、」という返事はサンドイッチに向けてされた。
「停電こそあったけど特に不便はなかったし、そんなことよりあんた達が帰ってこないことの方が問題だったわ」
私達が旅館を出たのは十九時半。停電で不便が出ないというにはまだ早い時間帯に思える。
「水島君は何か言っていませんでしたか?」
「随分心配してたわ。結局フロントとのやりとりは全部あの子に任せてたの」
水島君。
安心したからこそ会いたくなる。水島君は今も一人で部屋にいるのだろうか。
「わ、私、水島君に一言」
「やめておきなさい。あの子眠れないって一晩中起きてたのよ。いい加減休んでる頃だわ」
エアコンがブゥン、とうなった。レースのカーテンの向こう、青空。昨日の事がウソのような晴天。うっすらと透けて見えるのは箱形の・・・・・・あれは浴槽だ。
コポポ。コポポポポ。
「あ、違うわ。そう聞いただけで、実際どうか知らないけど」
「・・・・・・いつ聞いたんですか?」
「明け方よ。あんたが帰ってくる直前。フロントから何か連絡入ってないかと思って」
「連絡入ってないかと思って、部屋まで行った」
ということですか、と尋ねると鈴汝さんはサンドウィッチを置いてミルクティーをとった。
「ええ、そうよ」
時計を見る。さっきから十五分しか進んでいない。
「六時とかにですか?」
「外が明るくなる頃よ。分かったことがあるかもしれないじゃない」
ペットボトルに口をつける。そのなめらかなのどが大きく動いた。わずかに陰った色味。横を向いたときに浮き出る首筋の内側、それは何かの跡にも見えた。
偶然。それも偶然。明るい光の差し込む部屋。影ができない方が不自然だ。
「・・・・・・火州さんは朝弱そうですね」
「・・・・・・。そうね。海行った時、翌朝動けてなかったものね」
減り続けるミルクティー。私はそののど元を見つめ続ける。何度見ても、同じ所に同じ形の影ができる。
「今回、火州さん来れなくて残念でしたね」
「そうね。でも大事な時期っていうんだから仕方ないじゃない」
本人ではなく高崎先輩に聞いたという。火州さん自身、自分の事は話したがらないらしい。
「努力を見せびらかす人と、隠したがる人がいるのって何でかしらね」
そう言うと鈴汝さんは笑った。自分は少しでも何かしたらすぐに言いたくなってしまうのに、と。でもそれはそんな『言葉で収まってしまうだけのことしかしてない』っていうことの裏返しなんでしょうね、と。
何故だろう。水島君に渡した黒いヘアゴムが頭をかすめた。
「鈴汝さん」
「あと、言いそびれてしまったけど、あたしちゃんとフラれたから。飛鳥様に」
ミルクティーを置く。初めてまっすぐ目が合う。偶然の中に紛れた、これこそが真実。
四
「お前の、何か細工してあったの?」
スカートの上の食べカスを払うと、再び元の体勢に戻る。のどが乾いたとだだをこねる師匠は再びお腹に鼻先を押しつけてくる。
「くすぐったいですやめて下さい。・・・・・・水島君とは同じ授業で同じものを作っていたので、別に渡す分にはインスタントコーヒーを大さじ一杯分足しました」
「だからか。王道はこっちで、お前がアレンジを加えてたワケね」
押しつけられたカップケーキ。一口かじると教科書通りの味がした。同じ授業、同じ教室で作ったもの。その場にいなかったはずの鈴汝さんが、これを。
「・・・・・・悪かったな。俺二つとも水島君の分だと思ってたけど、そうじゃなかったのな。雅ちゃんに聞いた」
コク、と乾いたものがのどを通る。詰まったのは想い。
二つ。一つは水島君。一つは鈴汝さんにあげようと思っていた。ミルクティー。甘い物が好きなあの人には元々合わなかったのかもしれない。
ふいに手をつかまれる。その反動で半身を起こした師匠は、カップケーキにかぶりついた。不安定。狙いを定めきれなかったために私の手までかじっていく。仰向け。再び横になって咀嚼する細いあご。長いまつげが落とす影。その頬は相変わらず不健康なほど白い。口元を拭う指先は女性以上に白魚のようだ。
「・・・・・・ばっちぃ」
だからといって人の唾液を好む人はいないだろう。私は残った水分のせいでひんやりとした部分をこすると、その眉間にシワが寄った。
「・・・・・・。回収。もういいだろ。胃がもたれる。まったく、俺の胃袋を間にはさんでやりとりするなっつの」
間に飛び込んできたのは師匠だ。
「うるさい。・・・・・・にしてもお前も災難だよな。こんな返し方されちゃ俺でも傷つくよ」
詰まったのは想い。鼻の奥がツンと痛んだ。
「アイツ、お前がそんな工夫してんのにも気づけねぇのな」
〈ごめん。付き合うって言ったの、なかったことにして欲しい〉
そう言ったとき、水島君は完全に閉じていた。何を言った所で入れやしない。それほどまでに圧倒的な距離感だった。どう思われようと構わない。自己防衛を放棄したその姿から感じたのは、身の凍るような冷たさだった。
一切の言い訳をしない。好きにしてくれと差し出す首。甘んじて罰を受けるというよりはむしろ罰を受けたがっているようにも見えるのは、その先に赦されたい何かがあるから。
『あなたにどう思われようと、そんなことよりも優先すべきことがある』という意思表示。それがどれだけ残酷なことか分かっているのだろうか。
ののしれれば良かった。手をあげられれば良かった。でもそんなことをしたところで、きっとこの人に決定的ダメージを与えることはない。自分が根付くことはない。絶望的な温度差にゆくゆく後悔するのは自分でしかない。だから黙って手を放す。最も影響力の大きいであろう、罰を受けないことで生じる後ろめたさ。それさえもいずれ過去の一瞬に与することを予感しながら、それしかできないのがどこまでも悲しかった。
降り積もった雪をまき散らす風。ものを吹きさらう風のことを「浚(さら)いの風」というらしい。教えてくれたのは鈴汝さんだ。じゃあその日、降り積もった雪を吹き散らしたのは、何かを吹きさらったのは、本当に風の仕業だろうか。じゃあその言葉自体、本当に鈴汝さんが知っていたのだろうか。決定的に変わってしまったあの日の何かを、恨まずにはいられない。
「・・・・・・寒くないか?」
「はい」
私のお腹と腰を守るようにしてホールドした状態で、師匠は大きく息を吸って吐くと「水島君にはもったいないよ」と言った。アイツバカだなぁ、と。
笑った。
「水島君をバカにしないで下さい」
「・・・・・・お前もバカだなぁ」
その頬が緩む。そうして「俺も大概か」と言った。
五
思いも寄らぬ事件が起こったのはその翌日だった。朝イチのざわついた教室。先生が来る前の数分に凝縮されているのは、同じテーマに対する考察だった。ミヤが駆け寄ってくる。
「慶子のこと、何か聞いてない?」
友人を心配して、というよりかは単純な好奇心による情報収集ととれた。私は「知らない」と答えるとその席を見た。その姿はまだ見えない。
慶子が谷浦先生と噂になったのは、昨日書庫に二人でいる所を生徒が目撃したからだ。それも先生が下になった状態で抱き合っている所を。元々書庫は図書室とは別に大学の入試関係、赤本だけを集めた部屋で、丁度職員室の真下にある。位置としての利便性と使用頻度は必ずしも一致しないが、全く使用されていない訳ではない。ごく一部の真面目な生徒にはちゃんと活用されている。しかしその真面目な生徒が目撃してしまった事が事を大きくする要因でもあった。自分が教えを乞う相手であるはずの教師による、それは立派な裏切りだった。
その日最後の授業が終わってもその席は空いたままだった。
慶子。
球技大会の時、同じチームだからと一緒に体育館に向かったのを思い出す。
〈水島君、この後試合するんだってね〉
楽しみだね、と振り返る。それは友人の幸せを心から願う顔。慶子自身、試合が終わるとミヤや早苗と合流するため卓球場に行ってしまったが、一緒にいなくても同じものを見ているような気がした。隣にいればきっと面白がって脇腹を小突いたのだろう。そうして夢と現実を行ったり来たり、私は足元を失うことなく安心して没入できたのだろう。
〈真琴〉
師匠が教室に現れた時首をもたげた繊細で獰猛な魔物。慶子だって気づいたはずだ。
〈ちょっと、ねぇ〉
それでもその向かいに立つ。今なら分かる。あの時の気持ちが。
鞄を持って顔を上げる。一方じゃあ私は慶子の何を知っているというのか。
「草進さん、」
振り返る。
水島君。
愛し、愛しいその声は、このときばかりは味方。
「・・・・・・床に散らばってたっていう本は、全部最上段のものだと思う。そこだけ天面にホコリが溜まってなかったから。事故の可能性が高い」
私はうなずくと足早に教室を出た。先生がいなくなり、再び自由を得て好き勝手に動き出した魔物。近くにいたはずのミヤや早苗の笑い声が嫌に耳に残った。