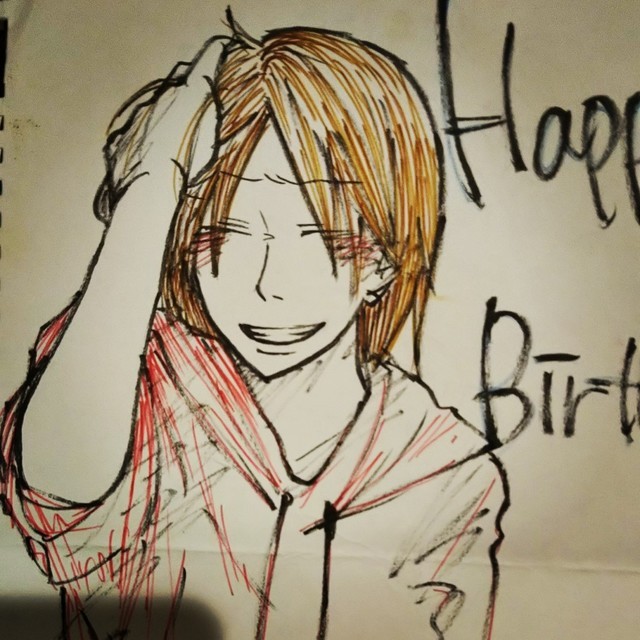聖16〈2月3日(木)〉
文字数 5,147文字
一
底冷え。外は外で風があるが、中は中で地味に冷えている。
気温三度。ただのハコである体育館は、外の気温に素直になじむ。足先の神経がしびれてなくなる。息をする度に白い息が舞った。
「ようやく決めたか」
遅いんだよ、と言うのは高野さん。僕は一つ頭を下げる。
「お待たせしました」
「本当にいいのか」
「はい」
そうか、と首を回す。肩を回す。足首を回す。
「新しい世界が見えるようになると思ったんだけどな」
そう言った表情はまだ残念そうだ。僕はもう一度頭を下げる。
もう決めたことだった。
キャプテンかエース。どちらを目指すか問われてやっと出した答え。部長と会長は兼任できない。会長を志す以上、自ずとそれは決まっていた。
手首につけた蛍光色のヘアゴム。野上さんと目が合う。その大きな口。
あくび一つ、寒さに身体を震わすとその背中をまるめたままランニングを始めた。
〈そういうの嫌いじゃない〉
順々に列をなす。二列で走るのに野上さんのいる方の列は人一人分後ろにずれる。丁度真後ろになった僕はその背中に声をかけた。
「後ろ行きましょうか?」
すると野上さんは目だけよこして、列から外れた。僕もそれに続く。
「・・・・・・別にお前呼んでないけど」
最後尾。あっという間に団体と差ができる。僕もそのペースに合わせて併走する。
「エースはマイペース。野上さんを見ているとそんな気がしまして」
「・・・・・・何。何か言いたいことでもあるの?」
「いえ」
なびく長髪。なかなか温まらない身体。
「合わせない、というのも一つの技術かと思ったので。追い込まれたときでも、野上さんは変わらず淡々と自分の役割をこなしますよね。そこに感情によるブレが見られない。次第にチームの重心が落ち着いてくる」
「・・・・・・技術って程大げさなモノじゃないと思うけど。実際そんなヤツばっかだったらチームプレイとか破綻するしね」
「でも五人全てが同じである必要はないですよね。流されない碇があるからこそ安定を取り戻す」
ギリギリ地面を擦らない程度に上げる足。進む一歩は薄く、けれども大きい。この人は極限まで体力を温存する。大事なとき、皆が苦しいとき必ず踏ん張れるように。
「目的は」
ペースが上がる。迷惑そうな顔。誰かがいると自分本位になりきれないのだろう。波打つ髪。その額に前髪が張り付いた。
「勝つこと。そのためになら何だってする。それだけじゃない?」
左斜め四十五度から放たれるシュート。野上さんは外さない。不安に、一時の感情に流されたりしない。自分の心拍数すらコントロールしているように思える。
常に一定。土台を築ければ、積み上げられた基礎を前に相手が勝手にペースを乱す。
「キャプテンはキャプテンでやるべきことがある。でもエースはエースで絶対的な支柱でいる必要がある。皆と同じじゃいけない」
団体の最後尾に追いつくと同時にランニングが終了した。両の脇腹に手をついて歩くその頬が、心なしかやわらかく見えた。
「・・・・・・もしマネしたいんだったら俺がいなくなってからにしてね。マイペースは五人に一人で充分」
その後「邪魔だな」と言って蛍光色のヘアゴムをとると、髪をくくる。現れた耳にはピアスのようなホクロがあった。今まで本番でしかしない髪型だったため、気づく余裕などなかった。
何を言う訳でもない。でもその背中から「ついて来い」と声をかけられた気がした。
二
部活を終えると、着替えを済ませて足早に部室を出る。ついさっきまで全力疾走していた身体は、まだ沸騰した熱を蓄えている。保温。しばらくは熱い。小走りで向かう先は生徒会室だった。
階段を一段飛ばしで駆け上がる。だるさはまだ感じない。満腹中枢の時差のごとく、まだ脳に身体の正確な情報が行き渡っていない。生徒会室の電気はついていた。
「お待たせしました」
バッグからデスクの鍵を取り出すと、ソファに腰掛けていた鈴汝さんに向かって差し出す。その目は二週間前に比べていくらか鋭さを和らげているようだった。
「どうも」
開いて見せた右のてのひら。その薬指と小指の付け根に楕円形の跡があった。そこだけ黄みがかっている。
「タコ・・・・・・ですか?」
見慣れない場所にできた肥厚。筆記具では決してつかない跡。鈴汝さんは鍵を受け取ると同時に「そうね」と言うと、何故だか目元を緩めた。
「グリップの関係で丁度当たるの。でもこれは前から。最近サーブを重点的に強化してるから、こっちにもできちゃって」
その口調はただの惚気。愛おしそうになでさする親指の側面は、外から見ても分からない。それでもそこだけ皮膚の質が異なるのだろう。
「そうですか」
静かなのは室内だけじゃない。廊下の突き当たりの図書室はとっくに施錠されているし、職員室以外明かりのついていない棟はもう半分寝ているようなものだ。薄い黄色のカーテン。そんな遮光なんて皆無のか弱いベールは、けれども二人で会う事ができる位には役立つ。例え同じ時間に終わろうと、関係者以外ここにたどり着くことはない。
自分の指を見続けていた鈴汝さんは、ゆっくり胸を上下させるとようやく顔を上げた。
「座って頂戴。聞きたいことがあるわ」
別に彼女で一杯になることを悪いことだとは思っていない。けれどもそれによって見失ってしまう問題があるとしたら話が違った。それに時間が経てばきっと冷静に話ができるようになるとも思っていた。しかし
「・・・・・・」
ソファから三メートル。不自然な距離をとることで半眼のまなざしに晒される僕は、決して間違ったことをしているとは思わない。唯一間違っているとしたら、それは「時間が経てばきっと冷静に話ができるようになる」という見立てそのものだった。
想像をはるかに凌駕する影響力。こんなにも他力を前にすくんだことはない。
息が詰まる。
〈俺が好きなのは雅ちゃんじゃないってば〉
相手の思いどうこう以前に「まっすぐ想いを伝えていい」その事自体が起爆剤になる。今僕は全力で彼女を抱きしめたくてたまらなかった。危うくて、ともすれば簡単に外れるたが。適切な距離を保つのは必然だった。
横長の白い机をはさんで手前に置いたパイプ椅子。鈴汝さんはその後、結局そのまま本題に入った。
「真琴と別れたって本当?」
三
暖房の効かない教室はしんしんと冷え続ける。防寒の観点だけで話をしたら、きっとここの壁は体育館と同じ材質に違いない。窓から床から冷気を漂わす。
僕は今さらコートの襟を立てると、肩をすくめた。
「はい」
「そう」
鈴汝さんは小さな声で返事をすると、再び手元に目を落とした。僕も目線を下げる。危惧していたことがあった。
沈黙。それはどんな事情があれ、草進さんと付き合っていた以上、別れたからとすぐ他の女性に手を出すなど褒められたことではない。機を誤れば本当に大切な人に不信感を抱かせてしまう可能性があった。
あれから一ヶ月。自分ではよく我慢した方だと思うが、相手がどうとるかは分からない。事実、のぞき見た表情からは何も読み取れない。
「あたしのせいかしら」
その目はうつろ。すぐさま口を開く。
「違います。僕が至らなかっただけで」
「旅行に行ったとき、抱き合ってしまったわ」
ヒリつく空気。覆うのは罪悪感。思わず声を荒げる。
「抱きしめただけです。ほっぺにチューぐらいなら海外では挨拶代わりです」
その目がまっすぐ僕を射る。
「あれで挨拶代わり? 大したものね」
嘲笑。その様子は純粋に傷ついたようだった。
「不義は認めます。でもそれは相手があなただったからだ。いつだってそうだと思って欲しくありません」
重ねるほどに言い訳がましくなる。物理的な距離三メートルがはるか遠い。
「信じて下さい。僕はただ・・・・・・」
冷えた教室。その身体を縮こめる。反射で思わず浮きそうになった腰をすんでで止める。
まだだ。まだ手を出してはいけない。
〈どうぞお好きに〉
その冷ややかな目。
〈お前の考えだけを押しつけるなと言っているんだ。一人一人見ているものが違う〉
放置してきた数々の問い。僕にはまだ答えていないことがある。
〈何も焦ることはない。まずきちんと向かい合うことから始めればいいと思うぜ。じきに心も開いて来るだろう〉
「・・・・・・『どうして鮫島先輩がからんでいると言わなかったのか』でしたね」
「え?」
「領収書の件です。あの日のことをお話しします」
短い日照時間。暗くなると外の部活は早々筋トレに移る。それでも帰る時間は夏に比べて一時間ほど早い。なんだかんだで学生だ。何かあってはいけないと、煌々とした体育館競技も外の部活に合わせた帰宅時間になる。十九時。だから今丁度夏場の部活終了時刻。まだ大丈夫。職員室はまだ起きている。
一通り話を終えると、鈴汝さんはうつむいた。己のふがいなさに打ちのめされているようだった。
「そうだったの」
「鮫島先輩のことを『殺したって死なない』と言ったのは、もう一度試合をすると約束したからです。前の球技大会の結果にあの人は納得できなかった。だからどんな手を使ってでも勝ちに来る」
「そう」
「あと以前津山に向かって『殺す』と口走ってしまったのは、あなたを傷つけられたと感じたからです。草進さんじゃない」
「そう」
ため息一つ、鈴汝さんは机のただ一点を見つめていた。
「随分苦労をかけていたのね」
「いえ、」
不健康な青白い光がまたたく。鈴汝さんは前髪を押し分けるようにして手のひらで額をつかむと、再びため息をついた。
「あの二人って何かあるの?」
鮫島先輩と草進さんのことを言っているようだ。
「何か、というのは?」
「何か、よ」
言った後その頭をかぶり振る「・・・・・・何でもないわ。下世話ね。聞かなかったことにして頂戴」
相変わらず低い室温。その目は変わらず一点を見つめたままだ。
「・・・・・・この間真琴に会ったの。話があったからあたしが呼び出して」
息を呑む。背筋がざわついた。
「開口一番、あんたのことを好きにならないと誓って欲しいと言われたわ。驚いた。あの子、あんたが関わるとあんなにまっすぐ人と向き合えるのね」
「・・・・・・っ! 何でそんなこと」
〈嫌われるように努力してくんない? 周りが危ない。早めに頼むよ〉
目が合う。その頬が緩んだ。悲しい顔。この表情、どこかで見たことがある。
「さぁ。あたしの想いに気づいたからじゃないかしら」
四
蛍光灯は時間経過に寄らず真下に影を落とし続ける。気温も底をつけば大して変わりない。つまり外的刺激を受けないこの空間の時は止まっているも同然だった。にも関わらず、色味が加わる。予期せずたきつけられた温度に神経がむき出しになる。
「どういうことですか?」
「・・・・・・」
にじむのは背徳感。噛みしめた唇。
「・・・・・・質問を変えます。あの時、どうして僕を拒まなかったんですか?」
その目をつむる。閉じる。その奥に、僕の知るべき思いがある。
もう、いい加減いいだろう。
「・・・・・・先程『あれで挨拶代わりか』とおっしゃいましたね。あなたはどうなんですか?」
立ち上がる。理性を保っていた距離は、歩数にしてたったの五。
見上げた揺れる瞳。寒さ故にかみ合わない歯。その震える頬に触れる。
こじ開ける。
「あなたは不義を認めますか? 同罪なら容赦しません。一緒に堕ちてもらいます」
揺れる瞳。かすかにこぼれた息はまだ音にならない。
揺れる。その頼りない首を青白い光が照らす。
息がかすめる。かすかな音を伴って。
かすかな。
その唇の動きを読む。
深呼吸一つ、その頬に触れていた手を離す。
離して、今度こそしっかり抱きしめる。しなる身体。片膝をつく。背中に回った手が肩先にしがみつく。
読んだ唇。かすれた声に腰から砕けた。
〈一緒にいく〉
息がつまる。狂う。何もかもどうでもよくなる。
たった一言、たった一言で人一人破壊する。この人はやっぱり悪魔だ。
「好きだ」
頬にキスをする。
「好きだ」
まぶたにキスをする。
やっとまっすぐ向き合える。その目が開く。
「水島」
そうつぶやいた彼女の唇は震えていた。思わず目尻が緩む。
懐に飛び込んできた彼女を、恐れるもの全てから守ることができる。こんな喜びが他にあるだろうか。
「何よ」と弱々しく言ったその両耳を塞ぐ。声さえ要らない。触れているところが全て。
「好きだ」
その目が僕の唇の動きを辿る。目の奥、感情の深いところがあらわになる。声にならない声。必死でこらえようとする泣き顔。
もうそんな必要もない。
キスをする。
泣こうがわめこうが構わない。
あなたはもう、僕のものだ。