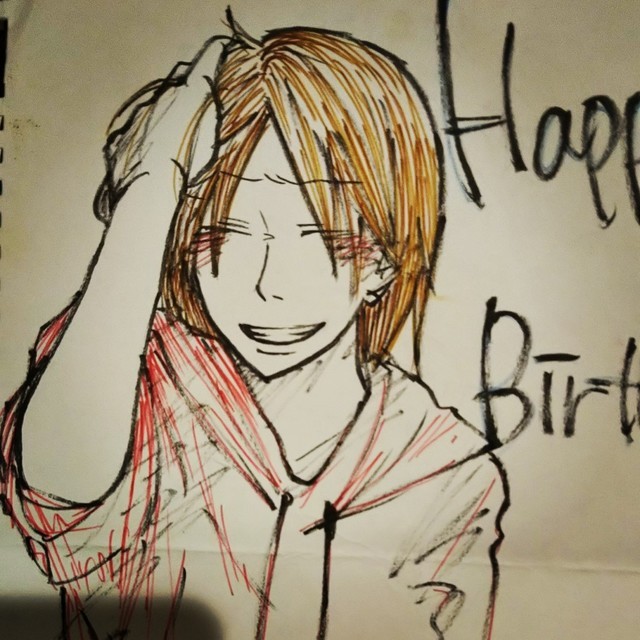寺岡千嘉〈12月初旬某日〉
文字数 5,401文字
一
口にする言葉の最後尾。区分は五つ。いつしかその口元を見つめるのがクセになる。
「ねぇ聡さん。パートナーと友人で友人が上回ることってあると思う?」
冷え込みが深くなる紫の空。気温は十度を下回る。黄色いイボのついた軍手。その指先は灰色。店先の影が濃い。聡さんは身体を起こすと「どうした急に」と行った。
肘から手首にかけての筋肉。その筋が浮き上がっている。二リットルの酒ビンかける五。十キロをやすやすと運ぶ。気温にそぐわない薄着の下、その肩甲骨が波打った。
「いいじゃん。ねぇ、あると思う?」
お酒の陳列された木棚。茶色、白、緑。目線の高さにある小ぶりなモノを見やる。青いビン。あたしはこれが一番好きだ。果物がプリントされたやさしいパッケージ。こういうのを持っていたら、自分もかわいく映る気がする。
「あるんじゃねぇの」
何のことない返事。
「そっか」
ケースを下ろす、その焼けたつむじを見つめる。
「ねぇ、今回こそは一緒に行ってもいい?」
「何?」
「スノボ。行くんでしょ? クリスマスに」
知ってるんだからね、と言うと聡さんは軍手で酒ビンをなでながら苦笑いした。
「・・・・・・俺は行かねぇよ」
「ウソ」
「ウソついてどうする。それに俺だけじゃない。火州もだ」
目を丸くする。じゃあ残るのは
「二、二じゃん。え、どういう組み合わせ・・・・・・」
鮫島さんと、生徒カイチョウと、水島君と、真琴ちゃん。どうとでも組み合わせられるようで、どうにもならない気もする。どうしても真ん中に水島君が来るためだ。
「さぁ」
その目尻が寂しそうに細まる。思わずその背中に身体を寄せた。
この人の感情は、いつだってあたしを経由する。
二
何が面倒くさいって女の子の人間関係に決まってる。それ以外面倒くさいものなんてこの世に存在しない。無意識の格付けは自己防衛。多少進化したところで所詮は動物。本能的に危険を察知する能力は失われることはなかった。ただ、どうあがいた所で順位は覆らない。 ワンランク上の高級アイス『ハーゲン』トップはほんの一握り。残りはみんな九十八円。だからバランスを取るために徒党を組む。居場所を確保。伺う顔色。
バカバカしい。
そんなことに割く脳みそこそがムダ。あたしにはやりたいことがある。目的地に向かうのに、最短を通りたい。その太い腕に鼻を近づける。
「・・・・・・また一緒にいた?」
だからハーゲンを手に入れた。分かりやすい強めの最上級生。初めて聡さんを見たのは部活見学の時だった。その日は丁度手前半面を男子バレー部が使用していた。緊張しながら館内に踏み入れた次の瞬間目にしたのは、とても高校生とは思えない、すでに完成された巨体。一枚岩のような背中だった。
トス。最高到達地点で静止するボール。
息をのむ。
同じように宙に浮いたまま静止したその背中。にわかに信じがたい脚力。これだけ恵まれた肉体を持った人が跳んで良い高さではなかった。はたして純粋に人力だけであの高さの空気に触われる人は、この世界に一体どれだけいるんだろう。
それは一枚の絵。その背中に見えたのは大きな翼。
顔を上げる。そんな、聡さんだけでもインパクトはあるが、何てったってつるむ仲間がSランク。とても九十八円じゃ隣に立てない。
「浮気みたいに言うなよ」
そう言って笑う姿は楽しそうだ。
褐色の肌によく映える青みがかった白シャツ。腹部。その裾が揺れると再びセブンスターのニオイがかすめた。
少しだけうらやましいのは、その名を呼ぶときだけ見せる幸せそうな顔。そういう意味では末尾の音って結構大事なんだなって思う。確率は五分の二。口角が横に引っ張られる母音。聡さんが呼ぶ人で、あたしが知っているのは一人しかいない。
「ねぇ、千嘉平気なの?」
七月。それは聡さんと付き合い始めた頃のことだった。声量よりも多めの吐息。振り返ったのはうなじにそれを感じたからだ。周りを伺う目。ひそめた声。
聡さんは目立つ。それは元々身体が大きいこともあるが、時代に逆行した筋肉のつき方も手伝っている。シワの寄りようのないシャツ。パン、と張った胸板。半袖から突き出た二の腕は、伸びないシャツの生地をそれでも押し広げんばかりだ。
夏のまぶしい白。でも聡さん自身は真っ白じゃない。過去に関係をもった女性皆が皆、口をそろえて言ったという「あの人はムリ」
上級生に姉を持つその子は、その事を気にしているようだった。
「アレ、相当激しいって聞いたけど。それでトラウマになってる人もいるって」
思わず声が出た。
「あはは、ありがとう。でも大丈夫だから」
やさしさ即ち余計なお世話だった。
それは本人直々付き合う前に確認されたことだ。
〈手加減できねぇんだ。気をつけるつもりだが、それでも傷つけるかもしれん〉
それを聞きながらいい目だと思った。
覚悟を問う警告。たまらずのどが鳴る。
上等だ。その背中に見えた大きな翼。傷つこうと何だろうと、どんな手を使ってでも手に入れる価値がある。ハーゲンを手に入れるため。自分が九十八円だという自覚がある以上、始めから代償のない契約なんて考えてない。わざと軽い調子で口にする。
〈知ってますよぉ。それで細い人はムリって公言してるのも。あたし位なら大丈夫ですよね?〉
値踏みするように輪郭をなぞる雄の視線。気を遣うつもりはなさそうだった。おもむろに私の左肩をつかむと「ああ、いいな」とつぶやいた。
身震いする。つかまれた所から血が湧き出るようだった。全身の細胞が目覚める。
恐れからくる、それは歓喜。手に入れたが最後、もう後戻りはできない。
「大人であること」は子供である当事者にとって重要だ。体つき、服装、メイク。それに非処女であること。それだけで
ただ、そこに絶望的な大人と子供の差が生まれるのもまた事実。大人は知っている。「初めて」結局はそれがベースになる。大切にされた子は、別れたその後も不当な扱いをはねのける。相手の願望だけを満たしてきた子は男性をそういう生き物だと認識するようになる。大げさではなく、その後の人生に大きな影響を及ぼす。
あたしの初めては、兄だった。
三
「忘れもん」
剛毛。太い指から桃色のハンドタオルを受け取る。今日は今日で別のものを持っている。この間来たときに置き忘れたようだ。蝉時雨。それは夏休みも後半に差し掛かった頃のことだった。
「別に置きっぱでもいんだけど」
白い歯。気は利かない。見つけた所で洗濯なんて発想に至らないその粗雑さこそが、この男の性質だった。それにしても
めずらしいことを言う。
数日前の感触そのままのそれを受け取ると、バッグにしまう。
「・・・・・・ねぇ、海で一泊してきたってホント?」
裸足。そのずんぐりとした親指が動いた。汗をかいたグラスを取る。それが口元にたどり着くまで約二秒。
「ああ」
大きく上下するのど仏。口の端を伝った水分を黒い手の甲で拭う。
自身ののどが鳴った。未だ慣れない。聡さんがいる空間は、どんな広さがあっても狭い。空気の密度が濃い。息がしづらい。
「真琴ちゃんと水島君もいたとか?」
「ああ」
水分の少ない髪は日に焼けて茶色。地黒の肌といい勝負だ。
「悪い。急に決まったんだ」
悪びれることなくそう言うとグラスを戻す。ひんやりとしたその手が、そのままあたしの腕を取った。強い力で引かれる。それは意思。一個体につき一つの。あたしに生じる痛みは、だから
「なぁ、してぇ」
ただのわがまま。小さい頃はガキ大将はそろいもそろって大きな身体をしていた。囲う取り巻き。それは一個体が持て余す力をこぞって制御しているようにも見えた。起こり得る最悪の事態を防ぐため、互いに監視し合う。そう考えれば「力を持つ」というのは、拮抗する相手がいないというのは、決して楽じゃない。
冷たい舌はアイスコーヒーの味がした。砂糖もミルクも使わないそれはただ苦いだけで、けれどもだから大人の味なのだろう。
背中が絨毯につく。薄いTシャツ。その背中に手を回すと、下でゴツゴツとした肩甲骨が動いた。張り詰めた筋肉。びくともしない肩。その質量だけで窒息しそうだ。
ひんやりとした口が通常の体温を取り戻す頃には、ブラもなければパンツもはいていなかった。室内温度二十七度の八月。時間換算した所で大した時間にもなってないはずだ。
前髪をわしづかみにされる。歯を食いしばると、右の鎖骨に歯が当たった。噛まれた所に血がにじむのが分かる。胸にも同じ痛みが走る。その先端にも
ガリ。
食いしばる。脳天を貫く痛みにたまらずうめく。
ちぎれる。身体の一部を奪い取られるような、とてつもない恐怖。
にじんだ視界に映る目は容赦ない。愛なんてカケラもない。この人は己の欲望に忠実なだけ。そこに一切の不純物は存在しない。それはある種、美しい獣のようでもあった。
「・・・・・・っ!」
濡れる、訳がない。痛みにおびえて縮こまった身体に割って入られる。と、今度こそ悲鳴を上げた。弱い部分がこすれる度に血がにじむようだった。食いしばる。
怖い。
身体の芯を揺さぶられる。今度こそ壊れる。
深い所をえぐられる。行き止まりを突き破ろうとする質量。目を開けても閉じても消えないハレーション。点滅を繰り返す、それは警告。その合間に映したのは、最後に見た兄の顔だった。
〈あやまらねぇ〉
「キツっ・・・・・・!」
その動きが一層激しくなる。自己防衛からか、単純に本来の働きを思い出したからか分からない。下半身が潤い始めて、痛みから摩擦が消える。代わりにひどくなる鈍痛。こんなもの、生理痛だと思えばいい。
呼吸を思い出した口が一瞬開く。そこに丁度身体を沈めた肩が当たった。
〈誰にも言うなよ〉
ガリ!
タイミングが悪かった。食いしばるつもりが、その肩に歯を立ててしまう。うなり声にあわてて顔を背けるが「いい、」という声が聞こえた。
「いい。かんで」
耳元でささやいた声は、次の瞬間にはうめき声に変わる。身体の中で膨らむ体積。終わりが近づく。ハレーションは、もう見えない。身体の重心をずらす勢いで動き続けるその背中に爪を立てる。
「・・・・・・っぇ!」
聞きなじんだ声。口にする言葉の最後尾。区分は五つ。
少しだけうらやましいのは、その名を呼ぶときだけ見せる幸せそうな顔。確率は五分の二。口角が横に引っ張られる母音。聡さんが呼ぶ人で、あたしが知っているのは一人しかいない。
その母音は「エ」
目をつぶる。身体の中で大きく脈打つ気配がした。
〈千嘉〉
四
思えば、ずっと罰されることを望んでいた。それは我慢することで、ちゃんと相応の痛みを受けることで、赦されたいことがあるからに違いない。
隣を見る。用が済んだ男は、大口を開けたまま眠りについていた。うるさいいびき。その固い腕に額を押しつけて目をつむる。
必ずしも間違い探しが得意でなくても、自分と違う存在にはひどく敏感な年頃。身体が大きい兄はその実、高校でいじめられていたという。あたしはそのストレスのはけ口に過ぎない。小学生の頃、兄には小さかったランドセル。その背中は最も身近なヒーローだった。その大きな背中を丸める姿を見ていられなかった。本人どうこうではない。純粋にあたしが嫌だった。傲慢でいられる場所になれるなら、ここだけのヒーローでよかった。
発育の良かった兄は持て余す自我に人一倍苦しんだに違いない。身体と心が一致しない。だからそれは
だから仕方なかった。だから仕方がなかった。
正しくなくていい。あたしだけはあの人を赦す。罰は全てあたしが受ける。だから神サマ。
あの人とイチからやり直させて。
球技大会のタイマー係は特等席だった。隣同士肩を付き合わせないといられない距離でひしめく多数。それを横目にパイプ椅子できちんと一人分の空間を確保する。
「ブザーの音がムリなんて、ピストル使う体育祭どうやって切り抜けてきたっての」
バスケで使用するタイマーは体育館中に響き渡る大音量を放つ。その音量に慣れているはずのバスケ部の子でさえ、人によって耳を塞いだり、気づかず至近距離で聞いてしまって肩を震わせている光景はよく見る。今回は本来じゃんけんで負けた同じクラスの子が担当するはずだったが、間近で聞いたトラウマがどうとかで交代させられた。結果的にラッキーと思えたからいいものの、この程度で引き合いに出されるトラもウマもいい迷惑だ。
目の前を横切る人影。上がった口角。細身のその人は見たことない活き活きとした表情をしていた。無心で壁の端に目を移す。そこからなでるように目をスライドさせる。急ぐ必要はない。丁寧に、見落とす事のないように一人一人。
「リバンッ!」
絶対、どこかで見ている。それでいてきっとその表情は
あ。
見つける。丁寧に、なんて本当は必要なかった。あの大きさ、あの背格好は見間違えようがない。人ゴミに紛れようと、決して紛れることのできない人なのだ。その他大勢になりたくてもなれない。キュッと引き攣れる心臓。
寂しそうに細まる目尻。やっぱりその表情は思った通りのものだった。
あの人はこの後連絡をよこす。素直で、あたしの思った通りの道をまっすぐ歩く。
けたたましいブザーの音。それと同時に膝の上で携帯が震えた。