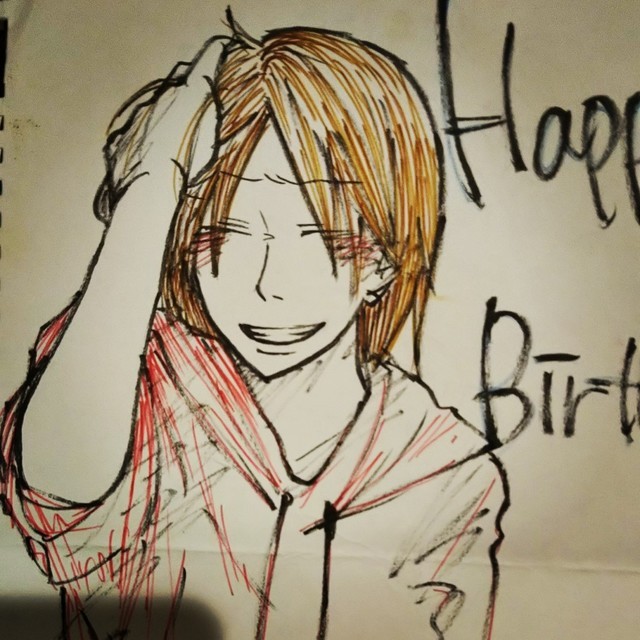真琴13〈11月28日(日)、30日(火)〉
文字数 5,456文字
一
今更寒い、と感じた事に驚いた。明後日から十二月。寒くない方がおかしい。
真っ先に歯磨きを済ませて自室に戻ると、布団にもぐる。階下から「お風呂入ってー」という声がした。電車に乗ってからずっと握りしめている携帯。いい加減汗ばんで、ウィンドウが曇っている。寒いと感じていた背中が徐々に熱を取り戻していく。
消えないのはその横顔。
〈じゃあな〉
何も言わなかったけれど、送ってもらった以上着いたら連絡を入れるのが常識だろう。難しい事じゃない「今日はありがとうございました」と言うだけだ。いや、向こうも片付けとかで忙しいならメールの方がいいか。しまった。それ以前にメアド知らないんだった。
そんなこんなで、布団にくるまったままうんうん言っていると、突然携帯が震えだした。ディスプレイに表示される名前。
向こうから来たー!
激しく取り乱す。あわててつなぐと、耳に押し当てた。
「・・・・・・はい」
「家着いたか?」
「はい。あの、すいません。本来はこちらからお礼を言わなければいけない立場でありながら、今、たった今ですね、ご連絡をばさせていただくつもりで」
「をばって。いつの時代だよ」
笑う気配がした。機械を通して聞く声は、対面で聞く声と同じではない。加えて表情が分からない分、緊張もする。
「着いたならいい。それだけだ」
そのまま切ろうとしたため、あわてて「今日はありがとうございました」と滑り込ませる。「ああ」と返ってきたのは、途方もなくやさしい声だった。
切れた通話。その画面を見つめる。時間経過で一段階暗くなって、その後真っ暗になる。本当は聞きたいことがあった。
おぼろげな、本当におぼろげな記憶を辿る。それは九月。師匠と屋上で話しをした日の事だった。同日の夜、気を失っていた自分を介抱してくれたお礼を言うために、後日その元を訪れる。しかし返ってきたのは「起きてそこにいたの、火州だっただろ?」という問いかけだった。当時は疑いもしなかった。自分に危害を加えようとする人が、まさかそんなことするはずが無いと思っていたからだ。けれども
あの時感じた違和感が、おぼろげながらも焦点を結ぼうとしている。それはニオイによる特定だった。師匠はタバコを吸う。そのニオイは吸わない人ほど敏感に反応する。だから近くにいればすぐ分かるはずだ。でもあの時、そんな不快さを感じた記憶はない。私自身、深く眠っていたためだ。だいぶ深く眠れたためだ。
汗ばんだ携帯を置く。ついたため息。目をつむる。
火州さんのニオイは、知っている。海に行ったときに借りたパーカー、今日間近でかいだ上着。そうして知っている。
深く鳴る、心臓の音。火州さんは背が高いため、あたしの頭が丁度火州さんの胸の辺りに来る。今日聞いた音と、以前聞いたそれは
頭を振る。本人に聞かなければ分からない事をいくら考えたってしょうがない。それにもう三ヶ月も前のことだ。今更という話でもある。
途方もなくやさしい声。例えば介抱していたのが火州さんだったとして、一体何が変わるというのだろう。師匠に火州さん。どちらも近寄りがたいが決して悪い人ではなくて、直接的な関係はないにも関わらず、何故だか切れない人達。
変わりはない。だから気にする必要なんてない。二人ともわざわざこちらから関わる必要のない相手なのだから。
「礼奈ちゃん、かわいかったなぁ」
あえて声に出してつぶやく。少しだけ穏やかな気持ちになる。楓君と三人でギュッと身体を押しつけ合うようにして過ごした時間。小さいからこそ高い体温。
電気を消す。暗くなると目立つ心臓の音。頭を抱える。このまま穏やかな眠りにつきたい。師匠と火州さん。自分にとっての二人がいくら似てても違う生き物なのだから、礼を言う相手が違ったなら立ち返るべきだとか、それが常識だとか。そんなことよりも少し前まで触れていた所がまだ熱い気がしてならない。
電話ごし、澄ませた耳に残る、穏やかな声。
動揺なんてしてない。だからこれ以上考える必要もない。私は普通の高校生。それ以上でもそれ以下でもない。
二
うれしいのは、久しぶりにバスケ部と体育館使用時間がかぶったからだ。十一月末日の火曜日。時刻は十七時半を回る。以前にも増してすさまじい早さで攻撃を仕掛ける水島君。スピードの落差を警戒して下がるディフェンス。生まれる余白。その世界が少しだけ広がったように見えた。長髪の男性が横切る。その手首の蛍光色のヘアゴムが揺れる。
「交代!」
ウチのキャプテンの声がした。返事をして駆け出す。ポジションについて落とす腰。
低く、誰よりも低く。相手サーバーがボールを床に打ち付ける。宙に放る。
一、二。
ヒュッと息を吸う。膝はやわらかく、しなやかに。どこまでも
どこまでも追ってやる。
「水島君」
部室から出てきた所を呼び止める。その目がこっちを向いた。
「私も今終わったとこなの。今日ね、一本しか落とさなかったんだ」
目元が緩む。
「そう」
「よかったね」でも「頑張ったね」でもないけれど、その少ない言葉と表情だけで満たされる。ちゃんとプラスの意味を含んでる。
「手首、真っ赤」
「私がいる意味あったってこと」
胸を張ると、たくましいなぁと言った。歩き出す。その隣に並んで歩き出す。
バスケをする時だけあらわになる額。落ちかかる前髪。また伸びたと思う。
「野上さん」を思い出す。
自転車片手に坂を下る。私はその隣でずっと聞きたかったことを口にした。
「どっちにするか決められた?」
その目は前を向いたまま。でも質問の意図はちゃんと伝わっているようだった。
「エースかキャプテンか」
だから進む足に動揺は見られない。変わらぬ歩調に合わせて流れる景色。
「ん」
私も前を向いた。それは一ヶ月前、同じようにバスケ部と体育館の使用時間がかぶった時だった。練習終了間際、身体の大きなキャプテンが水島君を呼んでそう聞いた。
〈どっちも支柱だ。ただ、純粋に個人の実力を研磨し続けるのと、チーム全体のことを考えてする動きは違う。お前はどうなりたい〉
水島君は選ばなかった。時間をを下さいとだけ言うと、その後も変わらず黙々と練習を続けた。野上さんはエース向きだと言っていた。アイツの突破力はこのチームのエンジンで、ムダなことに時間を割いて錆びつかせる訳にはいかない、と。高野さんはキャプテンをやらせたいと言っていた。視野を広げることで攻撃に幅が出るし、何より両方できるようになって本人が選択した方が良い、と。
「よく頑張ったよね。強化ギプス、ようやく外れたんでしょ」
頭をかく。水島君は「やっとね」と言った。
三
攻撃制限。別名、強化ギプス。水島君はこの二ヶ月「ボールを持って三秒以内、及び五秒以上のドリブル禁止」という制限をかけられていた。
「おかげで自分の所でタメをつくれるようになった。元々怖かったんだよね。自分より大きい相手が来ると思うと、接触を避けてすぐドリブルでかわそうとするクセがついていた」
ドリブルは不可逆行為だ。止めるのは次の動作、パスやシュートに移る時であって、再び戻ることはできない。だから重要なのはドリブルを始める前の時間で、水島君に必要なのはその余裕だった。
「でも、だから武器が活きてくる」
肩の力が抜ける。視野が広がる。ディフェンスが惑う。スペースが空く。一瞬の隙を見逃さない。
「パスが通る」
その横顔。うれしくて頬が緩む。
「変わったね、水島君」
少し前なら自分で行ってた。今はディフェンスを完璧な形で崩すことに重きを置いている。目の前の相手との一対一ではなく五対五。ちゃんとバスケをするようになる。
カラカラカラカラ。
車輪が乾いた音を立てる。そのムダのない輪郭。頬が固い。
「・・・・・・それでもまだ不満?」
わずかに目尻が反応する。痛みを我慢するような緊張した面持ち。
〈今日ね、一本しか落とさなかったんだ〉
聞いてあきれる。きっと水島君は落とした一本と向き合う。一本しか落とさなかったじゃない。一本落としてしまった、だ。
ストイックであることは決して悪いことじゃない。尊敬するし、自分でもそうありたいと思う。けれどもその表情を見ていると、時々不安になることがある。追い込みすぎじゃないかと、もっと気楽に考えて良いんじゃないかと、言ってしまいたい衝動に駆られる。
ただ、一方でそれが自分都合であることも否めない。それはどんどん先に進もうとするその手を引くことで、自分が安心したいだけなのではないか。唇を噛みしめる。
〈み、水島君とどういう関係なの?〉
いつの間にこんなに欲張りになってしまったのだろう。その姿を目にするだけで、その声を聞けるだけで満足していたはずなのに。
あの時、球技大会の時の姿が焼き付いてしまって離れない。ボールを持った瞬間、意識して伸ばす背筋。接触を恐れないドリブル。仲間を見る横顔。闘志をむき出しにした目。挑発的に笑う口。全部全部
見ないで、と思った。努力も、苦労も、その先でつかみかけているものも全部知ってる。水島君を知っているのは自分だけでよかった。一番良い所だけ見て近づく人が現れるのを想像して、気が狂いそうだった。
「負けず嫌いなんだ」
振り返る。
草進さんが思っているより、僕はずっと幼い。そう言うと数歩先に目を落とす。
「勝ちきりたかった。二度とない、大事な試合だったんだ」
その横顔。痛みに耐える表情は今にも壊れそうだ。
水島君が苦しんでる。
本気で好きな人を助けようとする時、その他大半の事は意味をなさなくなる。この場合の「大半」は人間関係に加えて良心、節度、マナーも含まれる。自分を投げ打ってでもその人の力になりたい。それを自己犠牲というのか、はたまた見返りを期待した計算というのかは人それぞれ。いずれにしても
腹さえくくれば今の私は誰より強い。情報を握っているのだからなおさらだった。
「水島君の、勝ちだよ」
四
その目がこっちを向く。それだけで脳がとろける。必要とあらば悪魔にだって心を売るのだろう。一つうなずくと口を開く。月明かりが足元を照らした。
「これ、本当は言うなって言われてるんだけど、球技大会の時・・・・・・あの時最後一対一になったでしょ? 詳しくは分かんないけど、師匠が言うには『球技大会だからって審判甘くなってたけど、足が付いて行かなくて手だけで止めたから、もしちゃんとした試合ならファウルだった』って。だから本当は負けてたって。水島君はドリブラーだからフリースロー絶対外さないって」
目を見開く。動揺。その足が止まる。
「あの人・・・・・・そんな事考えて」
「うん。だから最初すごい悔しがってた。でも師匠はアンフェアを嫌うから、隠しておけなかったんだと思う」
見上げる。半分の月が低い位置から照らしていた。良心。プライド。知ったことではない。私は好きな人の味方でありたい。どこまでもどこまでも。正しくなんかなくていい。
「師匠、頑張ったんだよ。禁煙して、専用ルームでトレーニングして。低酸素トレーニングってその中で三十分走ると二時間走った事になるの。とにかく時間がないからって。後輩に体力ないって言われたの、相当堪えたみたい」
息を吸う。お腹まで冷たい空気が入り込む。不思議と寒いと思わなかった。
「『バスケで言う四分ほど長いもんはない』って。とにかく四分間走りきれるだけの体力をつけるのに必死だった。でもそのために大事な事を見落としたって」
水島君は何も言わない。何も言わずに続く言葉を待つ。自然と頬が緩んだ。
「共有だよ。今の三回生と一緒にプレイしたことあるの、今の主将さんともう一人だけだったんでしょ? だから他のメンバーのプレイスタイルを知らせておく必要があった。シューターの野上さんや動き出しの早い杉下さん。その辺のコミュニケーションがとれてなかった」
元々早くに退部した身。知らせるにしてもどう伝えたらいいか迷ったに違いない。そういうとこ、師匠はあまり器用じゃない。
「自分で言ってた『やっぱ必死になっちゃダメだな。視野が狭くなる。アイツ見てそう思ってたはずだったんだけどな』って。だから水島君の勝ちだよ」
本気で勝ちに来ていた師匠を打ち負かしたのだ。目一杯胸を張っていいことだった。
しかしやっぱりその顔色は浮かない。この後に及んでまだ不満があるのだろうか。手を伸ばすほどに離れていく。
近くにいるほどに遠い気がしてしまうのは何故だろう。それはもしかしたら互いの距離に見合った関係を無意識の内に期待してしまうからかもしれない。前に進むこと。階段を上ること。どんどん離れていこうとする背中に手を伸ばす。水島君は前しか見ない。私はその腕にしがみつきたくて夢中になって手を伸ばす。
豊かな水を独り占めしようとして、必死で必死で手を伸ばす。
「もっと・・・・・・肩の力を抜いてもいいんじゃないかな?」
再び上がる目。苦しみから助け出したい。何より、笑って欲しい。
「充分頑張ってるし・・・・・・すごいよ。先輩達に混じっても何の遜色もないなんて」
うつろな目は光を跳ね返さない、でも大丈夫。怖くなんかない。
「大丈夫。私で良ければいくらでも力になる・・・・・・力になりたいの。だから」
私が、あなたの光になる。お願い
「水島君、私を好きになって」
私を見て。
雲が月を覆う。暗闇の中に溶け込む輪郭。微かに動く。
その表情は、全く見えない。