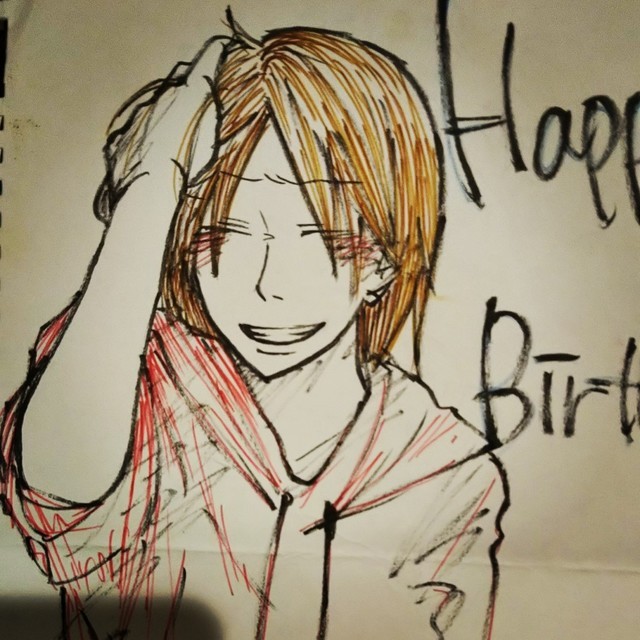聖14〈12月24日(金)〉
文字数 7,045文字
一
気づくとすっかり日が落ちていた。
車で走ること二十分。ゲレンデから先に荷下ろしをした宿に戻ると、熱いフロに浸かって身体をほぐし、着替えを済ませて食事をとる。溶岩プレートで焼いて食べた牛はとろけるように甘く「でしょ?」という満足げな鮫島先輩と目が合った瞬間、今夜この人に抱かれるんじゃないかと思った。
すっかりくつろぎモードでロビーに向かうと、同じような浴衣に身を包んだ二人が、リラックスチェアから足を投げ出すようにしてくつろいでいた。みずみずしい頬に淡い石けんの香り。草進さんは昼間は帽子に収納していた髪を下ろして、片側で結んでいた。
「お待ちかねー。大富豪やるよー」
乱暴に腰掛けた椅子。下を履いているとはいえ、きわどい所まで見えるような足の組み方をすると、鮫島先輩はトランプを切り始めた。ちなみに誰も待ってはいない。前置きなしで戸惑う二人から集まる視線に、僕は手をかざした。
「師匠、ルールって八切りの革命ありでいいですか?」
「え、階段、イレブンバック、クイーンボンバーもありだよ」
何だよクイーンボンバーって。
ローカルルールの多い大富豪は、こうして前もって足並みをそろえておかなければどエラいことになる。さすがに同じ地元でここまでの差は想定していなかったが。
「クイーン出したヤツが好きな数字爆破できるの。その数字持ってたヤツは手札から捨てなきゃいけない」
どんだけ強いんだよクイーン。ある意味最強じゃないか。
説明しながら配り終える手札。一斉にカードをとる。自分のものに目を走らせて口角を上げる男は、既に狩りの目をしていた。
「さぁ、楽しいゲームの始まり始まりー」
時刻は十九時を回る。僕二勝、鈴汝さん一勝、鮫島先輩が五勝あげた所で一旦休憩に入る。
「お前弱すぎだろ。全部顔に出てんだよ」
未だ一勝もできない草進さんはくやしそうに「ぐぅ」とうなると、残った手札ハートの三を開示した。その前のダイヤのエースで仕留められなかった段階で彼女に勝ち目はなかった。
「それはそうと、あんた帽子あったの?」
「まだ見つかってないです。あっちに置いて来ちゃったのかも・・・・・・」
「何、忘れもん? どこ」
「昼間立ち寄ったレストランだと思うんですけど。あの、山の真ん中辺にあった・・・・・・とったのそこだったんで」
「じゃあそこしかねぇじゃねぇか」
ホント、トロくせぇなお前、と言うと、鮫島先輩は立ち上がる。
「え、と、とりに行くんですか?」
「なくなったとか気持ち悪いからな。ボサッとしてねぇでお前も行くんだよ」
パラパラとかすめる粒の大きな雪。わずかな光をたたえる街灯。その向こうは真っ暗だ。何だか胸騒ぎがして声をかける。
「明日でもいいんじゃないですか? 山の天気は変わりやすいって言いますし、危ないですよ」
「大丈夫だって。チャッと行って来るから。・・・・・・お前も早く上着取って来いよ」
後に続く草進さんに声をかけると大股に歩き出す。
その後着替えて二人して出て行く後ろ姿にフロントの人が声をかけた。
「行ってらっしゃいませ」
その頭は、姿が見えなくなるまでずっと下げられていた。間違ってもイチ高校生相手の対応ではなかった。
二
「あの、一旦部屋戻りましょうか?」
おそるおそるかけた声は、何のためらいもなく突っぱねられる。
「戻っていいわよ。あたしはもうしばらくここにいるわ」
「二人が戻ってくるまでですか?」
「・・・・・・あたしにも監督責任はあるわ。あの子と一緒にいたんだから」
それは聞いたことに対するイエスだった。大窓を見つめる横顔は、相も変わらずつくり物めいている。
これは学校行事ではない。この場において生徒会長でもない。それでも責任、と口にするのは、純粋な気質からだろう。よこしまなものを払う鈴の音。清廉なその音は彼女そのものだった。
ふと顔を上げる。僕と同じように彼女を見つめる相手を見つけたからだ。彼女をはさんで丁度向こう、ドレッドと呼ばれる髪型をした男だった。男は進む足を一旦止めて彼女を見ると、やけにしつこく視線を残したまま喫煙所に向かった。
窓をはさんでいる分実際の所は分からないが、先程より闇が深くなりつつあった。センサーが反応して開いた自動ドアから、つま先を冷やすような風が吹き込んでくる。大きく、不気味な音。それは、ムダに不安をあおった。
「ねぇ、ちょっと遅くない? 往復一時間もかからないでしょ?」
片道二十分。確かにゆっくり行ったところでもう帰ってきてもおかしくない。
「念のためフロントに伝えておきましょう」
そう言って立ち上がった瞬間、轟音とともにロビーの電気が落ちた。外灯もやられる。突然奪われた視界。外をうずまく風が低い声で笑った。
「鈴汝さん、大丈夫ですか?」
声を張る。停電前と同じ距離から返事があった。僕は携帯を取り出し、その明かりを頼りにあわただしいフロントに向かうと、
「すいません」
迷惑承知で声をかける。この施設では上の方の人に違いない。薄明かりの中、スーツにバッジをつけたヒゲの男性が振り返った。その眉間にシワが寄る。少なくとも子供の相手をしているヒマはなさそうだった。
「一時間程前、友人が外出しました。まだ帰ってきていません」
そう伝えると、男性は元々チェックインで使用する受付用紙を引き寄せた。
「こちらにそのご友人のお名前をご記入下さい」
ガキが手間増やしてんじゃねぇよ、は副音声。急いでペンを走らせると、一人目の名字、いや正確には一文字目を見た段階で男性の声色が変わった。
「鮫島教授の・・・・・・ご子息ではありませんか」
男性は近くの従業員に耳打ちすると、まっすぐ僕の目を見て言った。
「直ちに捜索を開始しますので、お連れ様はお部屋でお待ち下さい。くれぐれもお風邪など召されませぬよう」
それと同時に電気が復旧した。チン、とタイミング良くエレベーターが到着する。さっき耳打ちされた男性従業員がエレベーターの前でドアを押さえて待っていた。これまで何度か思ったことがあるが、あえてもう一度言わせてもらう。ほんと何者なんだよ。
僕たちはエレベーターに乗り込むと、それぞれの部屋に向かった。
地響きのするようなそれは界雷。元々寒冷前線に沿って発生する雷雨を指すが、強い風にあおられて、ただでさえ地吹雪になっているところに降り注ぐのは当然雪だった。
小動物のように肩をいからせて浅い呼吸を繰り返す鈴汝さんは「何て言ってたの? 真琴と鮫島先輩は?」と震える声でたずねた。僕はフロントで言われたことを伝える。今できることはそれしかなかった。
三
部屋に戻ると一旦ベッドに腰を下ろして、出て行くときの二人の服装を思い返した。決して厳重な防寒対策はしていなかった。河口湖。ここから少し距離はあるとはいえ、強風でそっちにあおられたなんてことはないだろうか。レストランも確か山の中腹と言っていたが、あの辺りは特に雪が深い。雪崩の心配もある。ダメだ。考える程悪い方にしか向かない。
顔を上げると部屋を出た。鈴汝さんも同じような思いをしているのではないかと思ったためだ。しかし向かった先で見るより先に僕を貫いたのは、悲しい程高く自分を呼ぶ声だった。
「水島!」
「反射」とは意識とは無関係に起こる運動であり、大脳を介さないために行動に移すまでのロスがない。そう習ったのはついこの間のことか。
半開きのままのドア。部屋に飛び込むと、彼女にのしかかっている長髪の男に跳び蹴りをかまして部屋を飛び出す。ドレッド。先程ロビーで見かけた男だった。すぐさま「待てコラァ!」という声が追いかけてくる。無我夢中で走ると、エレベーターのボタンを連打する。片っ端から叩くことで全ての階のボタンが点灯した。男の足音がすさまじい早さで近づいていた。
「・・・・・・行ったみたいね」
その声と同時に息を吐き出す。全力疾走後の息を殺すなんて、本当に死ねる案件だった。腕に力をこめると、肩で呼吸をする。未だ暴れ狂う心臓。恐怖で身体がわなないていた。その後少しして
「水島」
ありがとう、と消え入りそうな声でつぶやいたのは
「・・・・・・っ! すいません! いえ、こちらこそ!」
守らなければと無意識に抱きすくめていた鈴汝さんだった。すかさず身体を離す。まだ落ち着かない心臓。それでも経緯を振り返るだけの頭は取り戻す。その目が戸惑いがちに揺れた。
〈こっち〉
廊下をはさんで反対側。非常用の階段の入口に飛び込む。時間経過で閉まって下りていったエレベーター。その前で舌打ちすると、男は戻っていった。全ての階のボタンが点灯していたため、早い段階であきらめたようだった。深呼吸一つ、
「大丈夫ですか」
ようやく彼女を気遣えるだけの余裕を取り戻す。良いタイミングでくしゃみをした彼女は、肩をさすりながら「寒いわ」と言った。
四
「お願い」
「嫌です」
暴風に轟音。そのさなかで何度このやりとりを繰り返しただろう。またイチから始まる。
「危険だからここに連れてきた訳でしょ? あなたが代わりにその部屋を使うなんておかしいじゃない」
「僕も男ですから」
「だから危なくないってこと? アイツ連れがいるって言ってたし、今もこのどこかにいるのよ。こうしてる間にも見つかるかもしれない」
「僕は危ないって言ってるんです」
「言ってないわ。それに聞きたいことがあるって言ってるの。いい加減分かって頂戴」
以上繰り返し。ここに来てどの位時間が経っただろう。部屋のドアを開け放した状態でのやりとりが続く。物理的な力は使っていないにも関わらず肩で息をする。ある意味力を使った方がよっぽど楽だった。暴風に轟音とはいえ、良く響く廊下。
「周りのお客さんに迷惑よ。早くして頂戴」
「分かりました。帰ります」
「何っにも分かってないじゃない! だからここにいてって言ってるの!」
「鈴汝さん、声大きいです。言ってることとやってることが合ってません・・・・・・」
「だからあなたが折れればすぐ済む話じゃない」
繰り返し。何だって頑固なんだ。僕も受け入れるつもりはなかった。結果
「お願い」
「嫌です」
何の工夫もない押し問答に終始する。ひたすら相手が折れるのを待つ、なんとも幼い戦いだった。
「何で?」
「だから何度も言ってるじゃないですか」
「分かんないわよ。あたしの方が同じこと何度も言ってるわ」
その時だ。備え付けの電話が鳴った。その横をすり抜けて部屋に入る。
「はい」
鮫島先輩と草進さんのことだろう。見つかったのだろうか。
大きく音を立てる心臓。吹っ飛んでいたが、本来こんなことをしている場合ではない。
「はい、分かりました。よろしくお願いします」
電話を切る。不安げな鈴汝さんと目が合った。
「・・・・・・警察も動いてるけど、この天候でほとんど視界がきかず捜索が難航しているようです。こっちに連絡が入ることがあればすぐ教えて欲しいとのことでした」
「そう」
「行き、ガソリンのメーター見えましたか? あとどれくらい残ってるか」
「見てないわ。二時間半と二十分を一往復。計三時間半走ったらどの位残るのかしら」
「そもそも満タンでスタートしてるとは限らないので分かりませんが、以前家族で岐阜に行ったとき、片道四時間弱で向こうでも三十分程度は走れました。少なくとも一時間程度は余力があるはずです」
「車種によってもガソリン入る量違うわよね?」
「・・・・・・そうですね」
これ以上話したところでムダだった。結局全て想像でしかないし、いくらこねくり回した所で実際に何もできない。だったらお湯を沸かして待っていた方がずっとマシだった。
五
コポポ。コポポポポ。
暴風に轟音の一瞬の静寂を縫って入ってきた豊かな水音。最上階であるにも関わらず、動力で運ばれたお湯は浴槽を満たしてやまない。その音がここでのやりとりをリセットした。
「帰ります」
「だからいい加減分かって頂戴!」
閉まったドア。迷惑かどうかは別として、廊下に比べて声は響かない。入口に急ぐ腕を、とうとうつかまれる。
「何でっ」
「だから何度も言ってるじゃないですか!」
その身体がすくみ上がった。一瞬強く絡み合う視線。
この人は何も分かっていない。
「・・・・・・僕も男ですから危ない、と」
「・・・・・・何言ってるの?」
「・・・・・・」
これ以上何をつけ足せと言うのだろう。この人の無防備さには心底あきれる。
応える代わりにため息をつくと、噛みつくがごとく吠えられた。
「あんた、真琴と付き合ってるんでしょ?」
「関係ありません。知ってるでしょう。気持ちがなくてもできることはできます」
「あきれた! 結局あんたもあいつらと一緒なのね」
「あいつら、がどなたを指すか分かりませんが、そう思っていただいて結構です。あなたがちゃんと節度を持った行動をできるようになれば」
「・・・・・・何よそれ! バカにしてる。自分はどう思われてもいいってこと? それがあんたの言う『対象と別の目的』? このやりとりもそこにたどり着くための一つなの?」
蝉時雨の残る夏休み明け。部活に対しての考え方「好き」の形の違いについて話した時のことを持ち出しているのだろう。僕はその、必死にまっすぐ立っている姿を見返す。
どう思われてもいい。この人が護られれば。
その相手が必ずしも僕でなくても。
コポポ。コポポポポ。
暴風に轟音。その合間に聞こえる音。復旧した電力によって、律儀に供給され続けるお湯。
一瞬の静寂。彼女は肩で息をしていた。引き結ばれた口元。その喉が引き攣れる。
「どうして」
何も応えない僕に、独り言のようにその声だけが重なっていく。
頼りない首はほんの少しの衝撃で折れてしまいそうだ。
「どうして。そんなの勝手よ。自己満足じゃない」
そうかもしれない。こうあって欲しいという思いは願いであって、ただの理想に過ぎない。
「あなたが分からない。何なの『信じて』って。何を信じればよかったの? どこで何が変わっちゃったの?」
チカ、と瞬く白熱灯。くつろぎの空間。メインの照明は橙。一時復旧した電気関係はまだ不安定なのかもしれない。天候に変化はないのだ。当たり前と言えば当たり前だ。
「ねぇ、どうして? どうしてあの時鮫島先輩がからんでるって教えてくれなかったの?」
六
目を見開く。鮫島先輩がからんでいて秘密にしていることなんて一つしかない。
「今、何と」
「え? ・・・・・・どうして鮫島先輩がからんでるって教えて」
「どうしてその事を知ってるんですか!」
その身体が強張る。一斉に血の気が引いた。両肩をつかんでゆさぶる。その両目が涙の膜を張ったまま揺れた。
「どうしてって・・・・・・本人に聞いたからよ」
何てことだ。
「ふざけるな。あれほど忠告したじゃないですか。どうしてそんなバカなこと」
落ち着け。落ち着くんだ。
〈大丈夫だよ。雅ちゃんは何も知らない。俺も認知しない。だから支払い義務は発生しない〉
背筋を這い上がる怖気。ダメだ。頭をかきむしる手を止められない。
「・・・・・・鮫島先輩に何かされませんでしたか?」
その肩の両端に寄ったシワは、僕がつかんだ時にできたものだ。無意識に身体を縮こめている彼女は、より一層か弱い生き物に見えた。
「・・・・・・。・・・・・・まだ」
コポポ。コポポポポ。
橙の光がぼかす顔色は明らかに悪かった。青白い。少なくとも日焼けを気にするような人の色ではない。かすれた声。
コポポ。コポポポポ。
コポポ。コポポポポ。
暴風に轟音。低くうなる風の合間、野外の水音がやけに大きく聞こえるようになる。ざわざわする。これは本能が選別して差し出したものだ。
〈だって嫌じゃん。何が悲しくて野郎とお湯シェアしなきゃなんない訳?〉
確か昼間、鮫島先輩は言っていた。その本当の意味を知る。
何が悲しくて野郎とお湯シェアしなきゃなんない訳?
ガンッ!
その身体が一瞬浮き上がる。思わず叩きつけたのは唐木の座卓。畳がしなって余韻が残る。部屋に戻ったときには敷き終わっていた布団。旅館側にどう伝わっていたか分からないが、二組のそれはぴったりとくっついていた。
そういうことか。
だからといって別に問題はないはずだった。元々こうなることを望んでいたし、いざという時ブレないために草進さんと付き合った。しかし
僕はその腕をつかむと、布団に押し倒す。
「水島?」
不安のかすめたその身体に覆い被さる。全神経がむき出しになる。思い知らされる。僕が欲しいのは、
抱きすくめる。考えるより先に身体が動く。キツく、キツく抱きしめる。
多分力を込めることに意味はない。ただの執着。手に入るモノは手に入るし、ムリなモノは何をしたってムリだ。けれど僕の不幸は、その手を伸ばしてはいけないはずの人が反応を返したことだった。すなわち
黙って、僕の背中を抱き寄せた。苦しくて、浅い呼吸を繰り返していたその人が、だ。
感情の蓋がぶっ飛ぶ。何も考えられなくなったその時、再びブレーカーが落ちた。一瞬にして奪われる視覚。
「・・・・・・っ!」
でも、必要なかった。相手はこの人で間違いなかった。
全身の毛穴という毛穴が粟立つ。全神経が刮目する。見るのはなにも目だけじゃない。息づかい一つでその表情を確かめることができる。
その腕は、どれだけ抱きしめる力を強めても拒むことはなかった。