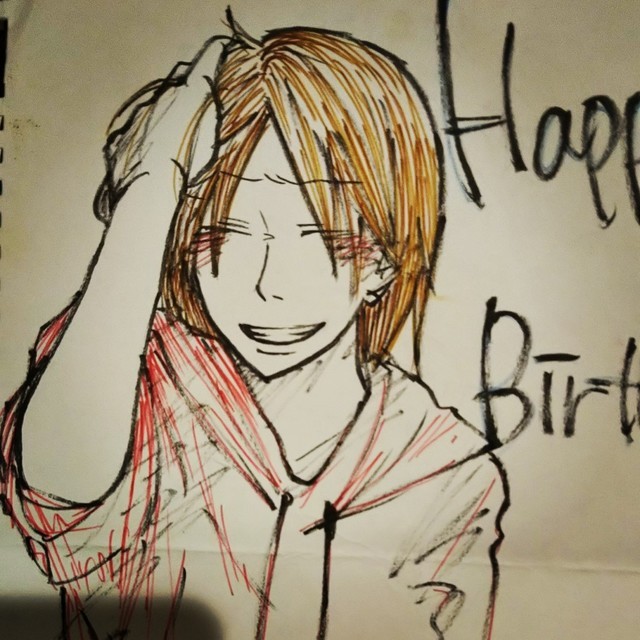雅11〈10月8日(金)〉
文字数 5,007文字
一
そこから見えたのは、身体を縮こまらせた真琴と、誰かに馬乗りになっている水島の背中だった。
〈もういっぺん言ってみろ。殺すぞ〉
それはあたしの知っている水島ではなかった。廊下からでは窓枠から見える景色が全てだ。フレームアウトした所から、微かな笑い声が聞こえた。
〈火のない所に煙は立たねぇよ〉
真琴の事が気にかかっていた。その小さな背中。悪意の立ちこめる密室で過ごす苦行を思う。具体的に何かされるとかの問題ではない。あくまでどんな気持ちで同じ時間を過ごすか。休み時間のたった十分が耐えられない事だってある。
〈実は・・・・・・その、津山君に告白されたんです〉
何しろ悪目立ちする要素が多すぎる。その場に居なくてもその場の空気や視線を感じるようだった。
「丁度俺も話そうかと思っていたんだが、」
屋上。高崎先輩はそう言うと、重心を前に移した。あぐらをかいた膝に肘を置く。
「あのクラスでは火州と真琴ちゃんが付き合ってることになってるんだと。夏休みの前まで火州がよく真琴ちゃんのところに行ってたから、元々火種はあったんだが、それにしたって話が飛びすぎる。近い人間が何か知ってることを広めたのかと思ったんだが」
「真琴の友人に慶子って子がいます。その子が一番近かったはずです」
「いや、その子は知らなかったんだと」
「何をですか?」
口をつぐむ。高崎先輩は口元を覆って尚もためらうと「嫌な気分になったらごめんな」と断りを入れて、再度顔を上げた。
「火州や真琴ちゃんを含む四人がみんな片思いをしてるってことを、だ」
風が前髪をあおった。まばたきを忘れる。
真琴は水島を好きで、水島はあたしを好きで、あたしは飛鳥様を好きで、
「じゃあ・・・・・・」
「そうだ。火州は真琴ちゃんのことが好きなんだ」
薄々気づいていたことだけれど、はっきり言われるとズシンときた。
慈しむようなまなざし。確かに飛鳥様はいつだってあの子を気にかけていた。無意識だろうけど、その姿を見ていたあたしはよく知っていた。
「そのことを千嘉から聞いた慶子って子が別の子に話したのかもしれんし、千嘉が触れ回った可能性もある。どっちにしてもその辺が尾ひれをつけて回っちまったんだと思うが」
言い終わって天を仰ぐ。と同時に「あいつ口軽いからなー。あいつだろうなー」とつぶやく。何かしらの罪悪感を感じているようだった。
「でもまぁ、長く続くようなもんでもないだろうし、大丈夫だろ」
それでもそう思うしかない。何を思った所で、あたし達は立ち入れないのだから。
自分を呼ぶ真琴の姿がかすめる。
祈ることしかできないのが、ひどく歯がゆかった。
二
十月十二日月曜日。体育祭当日は秋の晴天に恵まれた。
行事の準備はもちろん、当日の運営も生徒会が請け負うため、今は各々の配置についている。その内一つがこの放送だった。
「会長、お先にお昼どうぞ」
午後に放送で使用する原稿を準備しながら多須さんが言った。一回生だけれど、言われたことをきちんと実行できる子で、安心して任せられた。仕事を振る上で、言葉の齟齬云々は非常にデリケートだ。余計な気を遣わずに済むのが何よりだった。
「ありがとう。でも大丈夫。もう少し確認することがあるから、先行って」
尻尾のようなポニーテールが顔の向きを変える度に大きく揺れる。
「いいんですか?」
ええ、と返す。多須さんは頭を下げて放送室を出て行った。ため息一つ、目頭をもむ。ヘアゴムの蛍光色がやけに目に残った。
丁度午前中の種目が終わった所だった。ホッと息をつくと、放送室の窓から同じテニス部の子が見えた。ペアを組んでいる二人だ。別の色のクラスTシャツを着てはいるが、同じような笑顔をしていた。
昨日配られた対戦表を思い出す。
ダブルス。当然マリエの名前はなかった。以前ペアを組んでいた子とは別の子と組んでいて、見慣れない組み合わせが現実を突きつけた。
マリエのテニスを思い出す。
打ち方がキレイだったかと言われればそうではなかったし。秀でたショットを持っていたかと聞かれればそうではなかった。もう一度対戦したいかと聞かれればやっぱりそうではなかった。対戦したくはなかった。決して技術のある選手ではなかった。高校から始めた以上、圧倒的に練習量が足りない。それは仕方のないことだった。けれども
その目を思い出す。嫌な目をしていた。どんなに追い込まれても強い光を失わない。今目の前に来たボールだけに集中する。それは余裕のなさ故の視野の狭さだったか、今となっては分からない。けれど
その目が嫌だった。己の気持ちを問われる気がした。
〈そのボール、打てる?〉
〈私なら打つよ。全力で〉
自身の引退をかけた試合で、ベースラインギリギリに打ち込んだバックハンド。その一打が忘れられない。技術じゃない。テニスで試されるのは心の強さ。あたしは打てただろうか。あの場面で。
当然のように刻まれた名前。ここにあるべき名前は、本当は
「お昼、行かないんですか?」
勢いよく振り返ると、入口にもたれかかるようにして水島が立っていた。黒地に白の唐草文様のクラスTシャツ。はいているのはバスケ部の練習用ズボンだ。
「・・・・・・いつからいたの。声くらいかけなさいよ」
「たった今来た所です」
言いながら歩いて来る。放送室は黒い機材に囲まれながら、たった一つの小さい窓からの光しか受けられないため、全体的に薄暗い。ともすればその輪郭は背景に溶け込んでしまいそうだった。そうか。それでヘアゴムの蛍光色一つで目が驚いたのか。
「行くわよ。ここが終わったらね」
その目が不自然に見開かれる。大股で二歩、あたしの片側に手をつくと、
パチン。
「・・・・・・鈴汝さん、マイクの電源入ったままでしたよ」
ホッと肩をなで下ろす。一方あたしは水島の右手を見て固まった。
緑のランプ。確かにたった今切れたに違いなかった。
「別に、僕は一向に構いませんが」
「・・・・・・うるさい」
何とかそう返す。
BGMとして流している曲が変わった。テンション高めのものから、ゆったり聴かせるものへ。昼食が一段落した頃、丁度消化によさそうなテンポ。生徒は日陰で過ごしているため、今は一周四百メートルトラックが欠けることなく見渡せる。
「あとどの位かかりそうですか?」
「五分もかからないわよ」
欠ける事のない白帯。練習前にコートのラインを出す作業。
聖域。理想のテニス。
言っていることとは裏腹に、身体が動かない。この薄暗さは考え事をするのに丁度よかった。放っておいてもずぶずぶと沈んでいく。
鼻息がかかった。目を上げる。水島は近くにあった椅子を引くと腰を下ろした。
「聞きますよ。どうしたんですか」
三
「別に何でもないわ。いいから先行って頂戴」
「何でもないなら、僕がいるとき位何でもないって顔してて下さい。気になるんで」
「あんたが勝手に入って来たんでしょ。何であたしが合わせなきゃいけないの」
「僕はお昼行かないのか聞きに来ただけです。行くと答えたのは鈴汝さんでしょう? そうでなきゃここを離れていたかもしれません」
「ウソ」
「よく分かりましたね。すいません」
「何それ」
不覚にも笑ってしまった。時にこの子の潔さは無敵なんじゃないかと錯覚する。
「で、」
向き直る。
「どうしたんですか」
苦み。喉の奥が鳴った。
嫌な目。どんなに追い込まれても強い光を失わない。
マリエを思い出した。
「仕方のないことだったの」
薄暗い空間。その目だけがきちんと光を反射する。
「学校側だって実績を求めてるし、それ以前にあそこは県内トップの進学校だから、時間を有効に使えるように早めに肩を叩いただけ。出られないのに練習時間を割いて勉強時間削る必要ないでしょ?」
ほどよい暗さと余分に口をはさまない水島のせいで、勝手に口が動いた。
「だから正しい選択をしただけ。あの子にとっては良いことだったの」
自分に言い聞かせるように自らうなずく。喉元があつい。
奥の方から。奥の方から出てきたがってる思いがある。
「でも?」
静かな相づちだった。
ヒュッと空気が鳴る。何かが決壊する。
吐き出す。それは、決して正しくない思いだった。
「でも、それでも続けて欲しかった。一緒に終わりたかった。あの子のテニスが好きだった。ただボールだけを見つめて。あんなに必死で、何かを追う姿見たことなかった。あんなに」
声が詰まる。飲み下す。
「あんなにテニスが好きだったのに」
好き、に理由なんてない。理屈じゃない。あれだけまっすぐに追っていたものを突如奪われる痛み。キレイじゃない。上手くもない彼女のひたむきなまなざしを、あたしは未だに忘れられない。その痛みが、彼女がテニスを続けられなかった理由全てが、敵になる。
「後輩に上手な子がいて、顧問はその子の育成に時間を割いたの」
不自然に動きを止めた影。水島はあたしの頭の近くまで伸ばしていた手で自分の頭をかいた。
「・・・・・・分かるわ。さっきも言ったけど、実力主義。その子ジュニアからやってたみたいで、入部の段階で群を抜いてた。シングルスワン。通常部長が請け負うポジションをすぐに取って代わった。ダブルスもそう」
唇を噛みしめる。正しくないことは分かっていた。
「でもその子にはまだあと丸一年ある。あたし達にはもう、そんな時間残されてないのに」
好きな物を奪い取られるまでのリミット。カウントダウンが始まる。あと何回試合に出られるんだろう。あと何回練習が出来て、あと何回打てるんだろう。有限。うっすらと見えて来る彼岸。
「・・・・・・そうですね」
そう言った水島は寂しげに微笑んでみせた。ざわりとする。同じことを伝えたらマリエもそんな顔をした気がして、急に不安になった。
「あんた・・・・・・」
四
「やっぱりー」
その時だった。入口に細身のシルエットが現れた。猫背。細い目は三日月型をしている。
「・・・・・・何がやっぱりなんですか?」
声に圧を感じた。邪魔立てに、害した気分を隠さない。
「いや、心地いい鈴の音に、若干ノイズが混じったと思ったからさ」
「・・・・・・相当耳いいですね。マイクから充分距離はあったと思いますが」
片側に寄せた笑顔。一歩室内に入ると、ポケットに突っ込んでいた手を出した。藍色のクラスTシャツ。明暗のコントラストで突き出た腕の白さが際立つ。細く、しなやかな指先。
「おいで」
切り裂く。
今あるもの全てを無視するその声は容赦ない。油断して緩んでいた心がキュッと縮み上がった。その目はあたしを見ていた。その手のひらはまっすぐあたしに向けられていた。
身体が動く。選択肢なんて最初からなかった。
〈これは雅ちゃんが望んだことだ〉
「鈴汝さん」
手首に加わった体温。振り向く。
水は、あたしと同じような体温しか持たないにも関わらす、それ以上の熱を伝えようとする。その大きな目に射られて、身体の内側がポコポコと音を立て始める。
この子の良さを分かり始めていた。水島の行動にはちゃんと意思がある。自分の目的だけを見据えて突き進むことができる。でもその強さが、今のあたしにはまぶしすぎる。
「・・・・・・放して頂戴」
視線を外す。尚も離そうとしない手をムリヤリ外すと、鮫島先輩の元へ向かった。その片頬がつり上がる。
「じゃあね、水島君」
その表情は分からない。
〈例え悪魔の心を持っていようと、他の誰かを好きになろうと〉
水島。
きつく、目をつむる。
残像。強いまなざしだけが、消えない。
「・・・・・・調教、しきれてなかったみたいだね」
なぶるように細まる目。
「いい? 水島君には近づいちゃダメだよ。それは、俺が赦さない」
奥歯を噛みしめる。本当の恐怖は、言葉よりも気配からにじむ。全身が小刻みに震えだす。
〈俺も雅ちゃんのこと好きだし〉
それは上下関係。横暴なその意思は、難なくあたしを取り込む。
「俺を、怒らせないほうがいいよ」
そう言い残すと鮫島先輩は階段を下りていった。日中の正しい明るさ。反射する廊下。その窓からさわやかな風が流れ込んでくる。
見ると十三時を回っていた。あと十五分もすれば午後の競技が始まってしまう。まだ震えのおさまらない膝をなだめながら、もう売るものなど残っていないだろう購買に足を向ける。
今のあたしにこの明るさはひどくこたえた。