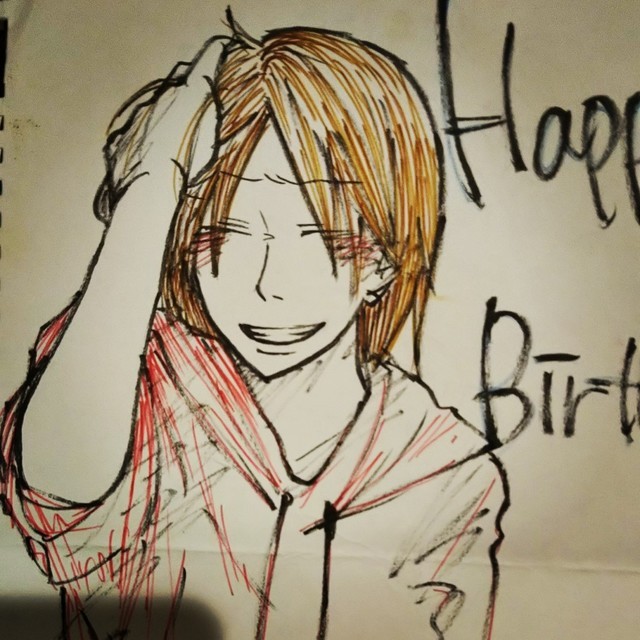雅14〈12月24日(金)〉
文字数 6,402文字
雅十四、十二月二十四日(金)
一
感じた恐怖は、さっき男に襲われた時とは全く別物だった。違いは合意か否か。種類は違えど底抜けの、という点では深度は変わらない気がした。
苦しい。
胸が痛い。それは決して物理的な感覚だけではない。責め具のように締め上げる腕。ふっくらと厚みのある掛け布団、自身と水島の重みの分だけ沈み込んだ身体。
耳元に熱い息がかかった。声にならない声。拍動。頭がガンガンする。
怖い。
「ねぇ」
動かない。静止しているように見えるだけで、実際呼吸をすれば胸は動くし、音もする。腕に限れば肘から先は自由が利くし、だからその背中を叩くこともできる。
「ねぇ」
しかし、できたところで自分の思う方に向かうとは限らない。変わらず有無を言わさず抱きしめ続ける腕。その唇が頬に押しつけられた。
熱い。
「ねぇってば」
恐怖を感じたのは、この状況を心地よいと感じ始めた自分にだった。のしかかる重みを、しっかりと抱きとめる腕を、この子自身を、無意識に受け入れている。いくら他の異性に比べて関わる機会が多かったとはいえ、いろんな手順を飛ばしていた。現にこの子は真琴と付き合っているのだ。
暗闇に少しずつ目が慣れてきた。その輪郭。わずかな光が陰影を映し出す。
「教えて。あの時何があったの?」
再度その背中をたたく。たたく。たたく、と、荒く息を吐く音がした。
上半身ごと、その物憂げな図体が上がる。と同時に下半身に固いモノが当たった。
ゴリ。
わざと押しつけられたようで思わずひるむ。目を上げると真上から見下ろされる形で目が合った。動じない。意にも介さないその圧力に、言葉を飲み込む。
気配。水島は怒っていた。キツく引き結ばれた唇。
「・・・・・・まだ言いますか」
言いながらため息一つ、その目がふいにあたしの頭上に留まった。
「・・・・・・」
おそるおそる視線を辿ると、黒いキャリーケースに行き着いた。鮫島先輩のものだろう。持ち手についた小さな鍵。あれはいつも乗っている原付のものだ。
水島の動きが止まったのをいいことに、あたしは素早く口をはさんだ。
「あ、あたしは鮫島先輩に聞いたこと、間違ったとは思ってない。それは・・・・・・不都合はあったかもしれないけど、結果的に欲しかった答えは手に入れたわ」
その目はキャリーケースを見つめたままだ。それでもちゃんとこの子に伝えなければいけないことがあった。それは、あるいは真琴とのことがあったからようやく気付けたのかもしれない。あたしは自分で思うよりずっとこの子に助けられていた。
分からない、は分かりたいと思うこと。ただ言われるがままに信じることができないのは、その全てを共有したいから。こびりつく罪悪感は、開けてしまったパンドラの代償。その行動自体、必死で護ろうとする水島を信じられなかったと受け取られても仕方がない。それでも
「ごめんなさい。あなたを傷つけたことは謝るわ。でも代わりにまっすぐ向き合っても大丈夫だって分かった。あなたをちゃんと頼っていいと」
その目が戸惑いがちにこっちを向く。いつの間にか楽に呼吸ができるようになっていた。お腹いっぱい空気を吸い込む。
「今後あなたに会計をお願いするわ。後期の明細引き継ぐから、年明けからよろしく」
暴風に轟音。まっすぐ見上げる。一瞬、ほんの一瞬、泣きそうな顔をしたかのように見えたその後、水島は肩から崩れ落ちた。再び人一人分の体重がかかる。続けて聞こえてきたのは心底恨みがましい声だった。
「・・・・・・。・・・・・・それ、今言うことですか」
二
電気が復旧する。何事もなかったかのように照らす橙は、空気を読む気のないあたしに味方した。
水島がトイレに行っている間にお湯を沸かすと、備え付けのココアを二人分入れる。その後しばらくして戻ってくると、黙って口をつけた。
ダックスフンドのような座卓は、端と端に座ると随分遠くに感じた。時刻は二十二時。
「まだ連絡ないわね」
コポポ。コポポポポ。
復旧に合わせて再びくみ上げられるお湯の音。それは変わらぬ悪天候の合間を縫って、やけに目立つ。
「・・・・・・あの人はほんと、一回くらい痛い思いをした方がいい」
もう見るからに不機嫌なその姿は、常に似合わず片肘をついていた。
「そんなことよりも先に考えることがあるでしょう」
どこかを向いた目は、再びその目的だけを映している。
「そんなことって・・・・・・。命がかかってるのよ? 痛い痛くないも無事な前提でしょ?」
「死にませんよあの人は。殺したって死なない。約束したんです。そのために必ず戻ってくる」
「殺したって死なないって・・・・・・一体どんな約束をしたっていうの」
水島は再び湯飲みに口をつけると、一口飲んだあと手元を見た。
「・・・・・・マグカップ的なものはなかったんですか?」
「それが一番手前にあったの。いいじゃない。飲めば一緒よ」
うわぁ、という顔をする。何よ。不満があるなら自分でやって頂戴、と言うと、初めてその頬が緩んだ。
「いえ、いただきます。ありがとうございます」
窓を叩く大粒の雪。いや、雪自体それほどの強度を持ち合わせていない。そう考えると「叩く」というよりも「ぶつかって」の方が正しい気がする。正面衝突。窓にはじけた雪は一瞬で大粒の雨と変わらない姿になる。
「最近部室を使うようになったのね。前に『一年だから部室は使えない』って言ってたけど、レギュラーは別なのね。真琴から聞いたわ」
「あ、いえ、定着したのは割と最近なので」
「本当は会計のことも十一月の段階で話そうと思ってたけど、あなためっきり生徒会室に出入りしなくなったから」
「すいません」
「別に謝ることじゃないわ。ただ」
空調がうなる。不安定な電力の供給に、力のいる機械は未だ本気を出してもいいのか考えあぐねていた。
「・・・・・・。何でもないわ。それより前に他校の友人の話をした時、あなたが試合に出てること知らずに言ったこと謝るわ。ごめんなさい」
一、五メートル先で身じろぎする気配がした。
「いえ、気にしてないですよ。それに本当のことじゃないですか」
言葉が足りないと思ったのか、水島は頭をかくと続けた。
「・・・・・・試合こそ出た所で問題がないとは言えません。視野が狭くて、そのために迷惑をかけることも少なくないのですが、それを一個性として育てようとする先輩がいて初めて成り立っているんです」
大きな目。まっすぐ見つめられると身動きがとれなくなる。年齢どうこうの話ではない。もっと原始的なもの。深く眠る本能がその位置づけを決める。その、今になってはじき出された答えに動揺する。あたしにとってのこの子は
三
「・・・・・・それ、真琴から?」
黒いヘアゴム。あたしから視線を外さずそれごと手首をつかんだ水島は「いえ、その」と口ごもった。言葉が続かない。頬を緩めると「多須さんも同じようなことしてたわね」とつぶやく。
「野上さんは髪が長いんで・・・・・・」
「あのすごいシュート入る人、野上さんっていうの?」
「はい。本番でやっと本気を出すような人ですが」
座卓の木目を見つめる。橙がまたたいた。
「どうしたの?」
「いえ、」
前髪をかき上げる。本来バスケをしているときにだけ見える濃い眉。
「ずっと分かり合えないと思っていました。野上さんと僕は見ている世界が違うと思い込んで。それまで僕は、自分がラストパスを受けるための動き方をしていたことにも気づきませんでした。分からなかったんです。あの人のパスの意味が、ずっと」
分からなかったんです、は、本当は分かりたかった。
「それぞれの形があるはずなのに、己に固執することで本来活きるはずのラインを消していました。返球は『もう一度周りを見ろ』のサイン。僕はボールを手元に置くことでしか見えない世界を遮断していたんです」
その目元がやわらぐ。沙羅が教えてくれました、と水島は言った。
「僕を認めてるって。不足している力を補うために、一時プレイに制限を加えられてたんですが、その時『あれだけ制限されて武器がさび付かない訳がない。プライドなんだろうな。そういうの嫌いじゃない』って言ってたって。上下関係関係なく、ちゃんと互いを活かせるチームメイトになりたかったんだって」
上下関係関係なく、互いを活かせる
「多須さんは野上さんって人のこと信頼してるのね。話す表情が見えるようだわ」
同じような強さで互いを思い合うことのできるような
「・・・・・・あなたも真琴のこと、とても大事にしているものね。前に津山って子に馬乗りになってるのを見たとき驚いたわ。殺す、なんて大事な人を亡くしてるあなたが口にするとは思えなかったから」
一瞬目を上げた水島は何か言いたそうだったが、結局押し黙った。一方あたしも、自分でその名を口にしておいて、その伺うような目を思い出していた。何の温度も伴わない視線。
「まだ何かあるんですか?」
「何かって?」
「例えば弱みを握られているとか。・・・・・・あいつ言ってたんですよ。『火のない所に煙は立たない』って」
湯飲みが滑った。不釣り合いな茶色い液体が鈍く照った木目に落ちる。
「ごめんなさい」
拭き取ったティッシュをゴミ箱に捨てる。のどが引き攣れた。煙による残り香。
「大丈夫よ」
四
気づくと随分静かになっていた。今はただ音もなく雪が降り注いでいる。窓の近くにいるとひんやりしたベールに肩を覆われるようだった。ピ、という音がして顔を上げると、水島が設定温度を変えた所だった。一呼吸おいてうなり出すエアコン。
にじんだ窓を水滴が伝った。露天の水音が悪目立ちを始めた気がして障子を閉める。上着は自室にある。見回したところで羽織れそうなものはなかった。
「もう少し上げますか?」
「いえ、大丈夫よ」
少しすれば部屋全体があったかくなるに違いない。それまで少しの辛抱だった。元の位置に戻るのと入れ替わりに水島が立ち上がる。床の間の手前、大きめのボストンバッグにかかっていた上着を取って差し出す。
「大丈夫だってば」
「二人が帰ってきたとき、あなたが体調を崩してたら僕が笑われます。あるものは使って下さい」
仕方なく羽織った分厚い上着は、重みのせいで肩だけでは引っかけておけず、袖を通すと手のひらまで隠れた。袖を二つ分めくる。
「・・・・・・上着で思い出した。あんた何勝手に球技大会で部員同士の試合組み込んでるのよ。それも鮫島先輩まで巻き込んで。何がどうしてそんなことになったのよ」
「・・・・・・。何で上着で思い出したんですか」
「学年色のジャージよ。半袖で駆け回ってたあんた達には関係ないでしょうけど」
まさかの流れ弾に面食らう。その口がもぞもぞと動いた。
「いえ、巻き込んだというか、最初は聞きたいことがあって鮫島先輩を呼び止めたんですけど、元々バスケやってたって聞いてたから、その流れで一対一をやることになって」
小さかった声が尻すぼみになったのは、必ずしも後ろめたさからではなさそうだ。
光が差す。その目が大きく見開かれる。何かを見つけたようだった。
「それだ」
「何?」
「カップケーキですよ」
勝手に合点すると、水島は窓の方を見やった。障子に遮られているにも関わらず、その向こうが見えているようだった。
「これで安心して二人の無事を祈れる」
その横顔はつきものが落ちたかのように晴れやか。その目が時計を向く。二十三時を回っていた。
「もう休みましょう。明日に差し支えます」
五
歯を磨いていると鏡越しに目が合った。一足先に磨き終えた水島は、今は腕組みをしてドアに寄りかかっている。変なプレッシャーを感じて、口をゆすぐと同時に声をかける。
「・・・・・・そういえばあんたが最初に言ってた『そんなことよりも先に考えるべきこと』って何だったの?」
緩む頬。穏やかな表情ににじむのは、確かな余裕。
「既に解決したことです。気にする必要はありません」
「・・・・・・そう」
ここで問い詰めた所でムダな気がした。必要とあらばいずれ自ら話すだろう。この子にはこの子のペースがある。イチイチ詮索するのは違う気がした。
口元をぬぐうと振り返る。直接目が合うも動こうとしない。代わりに組んでいた腕をほどくと、その右手を上に向けた。
「選択して下さい。この後どうして欲しいか。一つ、僕はあなたが使うはずだった部屋を使う。一つ、僕もこの部屋を使う」
「何を今さら。万が一でも何かあったら困るわ」
「万が一以上の確率で、僕が大人しくしていられるとは思わないと言ってもですか?」
コポポ。コポポポポ。
やわらかな橙に照らされた障子。静かな部屋に豊かな水音だけが響く。
「先程お伝えしたはずです。僕は危険だと」
「だったらどうしろって言うの?」
何だか悔しくなって声を荒げる。こっちは相手の身の安全を考えているのに、どうしてそんな言われ方をしなければいけないというの。にらみつけると、水島は困ったように眉を下げた。
「・・・・・・お部屋、お借りしますね。鍵を下さい」
何が選択して下さい、だ。最初から答えは決まってる。これ以上何も言うことはなかった。あたしは洗面所を出ると、布団を踏み越えて座卓に向かう。そうして鍵をとって戻るとまっすぐ差し出した。
以前隣に並んだ時よりまた少し身長差が広がったようだ。見えない圧力は潜在的なもの。これ以上近づけない。そうして立ち止まったのは一メートル手前。
コポポ。コポポポポ。
部屋の明かりがギリギリ届く廊下は空調の影響も少ない。寒いと感じたその時だった。水島が手を伸ばしてとったのは、鍵ではなくあたしの手首だった。あっという間に抱きすくめられる。
「水島?」
「気が変わりました」
筋張った顎の付け根。動く喉仏はただの男性の象徴。
軽々抱き上げると、そのまま布団のそばにおろした。驚きのあまりその場にへたり込む。掛け布団がめくられた。
「どうぞ」
「え」
「上着は必要ないので脱いで下さい」
「ちょっと待って。何だって急に・・・・・・。あなた戻るんじゃなかったの?」
「そのつもりでした。でもあなたをあたためる方が先です」
言うやいなや腕を引かれる。再び布団をかぶせられる時には全身を絡め取られていた。
「ちょっと、何で」
「何でまだ上着脱いでないんですか。邪魔でしょうが」
言いながら引き剥がす。首元を生ぬるい風がなでた。空調は室内の気温にそぐわない弱々しさで活動を続けていた。
「水島」
「いい加減観念して下さい」
うるさい、と言われた気がした。口をつぐむと頭上から長いため息がふってきた。
「・・・・・・僕がしたくてしていることです」
虚を突かれる。瞬時にこみ上げたのは罪悪感。
〈これは雅ちゃんが望んだことだ〉
〈とんだクソビッチだな〉
「鈴汝さん、」
肩がはねた。気づくと音を立てて震えていた。その手が背中をさする。頭をなでる。
「大丈夫ですから」
何が大丈夫、という問題ではなかった。その一言は、触れている部分を伝って全身に染み渡った。肩の力が抜ける。ついていた手の力を抜くと、代わりに熱いものがこみ上げてきた。
「ふ」
強い日差しを跳ね返す防波堤。赤く焼けた足。澄んだ空と入道雲。
〈やめた方がいいよ。何かのせいにしようとするの〉
どこか錆びついたニオイ。蝉時雨。背中の真ん中に走った鈍い痛み。
いつの間にか涙腺まで一緒に緩んでいた。自制が利かなくなる。ふいごのように波打ち始める背中。その首に腕を回すと、とうとう何かが決壊した。声をあげて泣き出す。
あたしは自分の意思で間違ったことをしたのかもしれない。それはさげすまれても仕方のないことだったのだろう。
泣きやみ方も知らないままわめき続ける。
でも今は、何を言われても構わない。このあたたかい手だけは放したくないと思った。