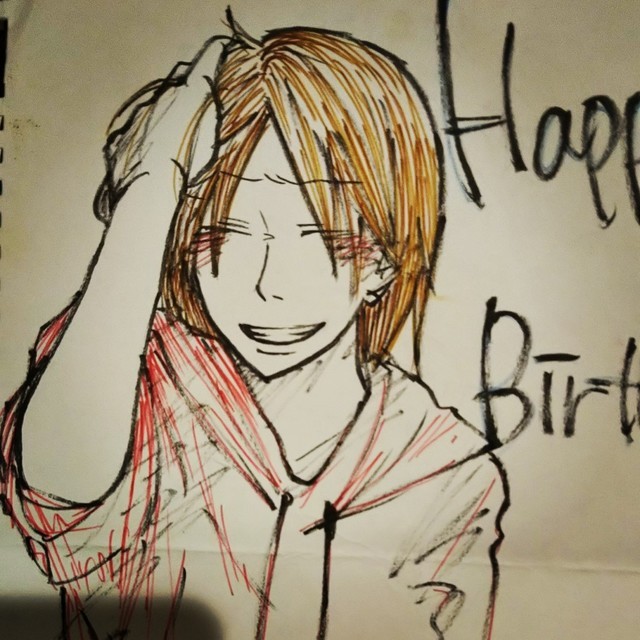勤14〈12月24日(金)〉
文字数 7,009文字
一
〈どうしても手に入らないなんてことないじゃないですか。自ら手放すか、絶対に手の届かない所まで離れる以外〉
凍える息吹。赤みを帯びた小さな鼻。
〈私は水島君を信じてる〉
ウソだ。血反吐のように吐き出される言葉。まっさらな雪の表面。とても踏み入ってはいけないおごそかな空気。
それは覚悟。世間一般とはかけ離れた、本人だけがたどり着ける幸せの頂。
「・・・・・・マジかよ」
わずかに震えた車体が完全に力尽きたのは二十時を回る頃だった。ゲレンデの中腹、ただでさえ雪深い中に取り残される。
「え、エンジンかからないんですか?」
「ああ。ウンともスンとも言わねぇ。これはヤベぇ。超ヤベぇ。俺様のホワイトクリスマスが台無しになっちまう」
暴風。ナビを使って走ってきたはいいものの「実際の道路交通標識に従って」とアナウンスが忠告する通り、全部が全部正しい訳じゃない。どこを間違えたのか、目的地付近で足止めをくう。最後に見た気温は、車内表示で零下二度だった。季節、時間を考えたら奇跡のイージーモードで、さして深く考えなかった。が、
時間経過で冷気が首に手を回してくると嫌な予感がした。暖房の効かなくなった車内は、外からの圧力でみるみる冷やされていく。
「ちきしょう。よりによって何でお前なんだよ。今頃アイツら同じベッドで寝てんだろうなぁ。いいなぁ」
襟元をかき合わせながらわめくと、弟子ににらまれた。
「水島君はそんなことしません。何てこと言うんですか」
「お前の脳みそこそどうなってんだ。そんなことするために生きてんの俺達は。足寒っ。エコノミー症候群とかカンベン。後ろ倒そ」
トランクに積んであった寝袋を引っ張り出すと、後部座席を倒してフラットにする。どうしても手狭だが、何とかラクな姿勢をとれるようになった。
「うぅ寒。寝袋積んどいてよかった。水島君詰めて転がそうと思ってたのが幸い」
「何が幸いですか。師匠にはほんと、一回くらい痛い思いをしてもらいたいです」
吐き捨てるように言い残すと前を向き直る。俺は構わず声をかけた。
二
「お前、ホントに水島君と付き合ってんの?」
「はい。報告が遅くなってすいません」
「え、何で。何がどうしてそうなったの?」
「なるべくしてなったんです」
本来ここぞとばかりにノロケる所だ。間違ってもこんな強い口調で返すことじゃない。
それはただ単に聞いた相手が俺だったからか、それとも他に理由があるからか分からない。ただ、いずれにしても
「水島君に聞いたよ。一ヶ月くらい前からだって?」
「はい」
「それで? 何か変わったの?」
「はい?」
「ビフォーアフター」
「・・・・・・」
「え、お前の言う付き合うって何? 俺今お前に合わせて水島君って呼んでるけど、本人の前ではひじき君って呼ぶよ。呼び方一つとっても俺の方が近くない?」
「関係ありません」
やっぱり強い口調。それは余裕のなさ。苛立ちが狭い車内にこもる。曇った窓ガラス。
「私は水島君が好きで、水島君も私のことを好いてくれてる。それでいいじゃないですか。首を突っ込まないで下さい」
「いや、本来彼女なら首じゃないもん突っ込みたくなるのは水島君だと思うんだけど・・・・・・。そもそもホントにお前のこと好きって言ったの? 何かの間違いじゃなくて?」
一瞬の間があった。雲が月を覆って暗闇。その表情は、見えない。
「・・・・・・うなずいてくれました」
「何?」
「いいじゃないですか」
頑なな横顔。小さな鼻は襟元に埋まっている。
「よかねぇよ。だってアイツ今日だってずっと雅ちゃんのことばっか見て」
「知ってます!」
暴風。灰色の雪。薄い雲を選ぶようにしてギリギリ拾う光。本当の闇夜に呑まれたら少しとして正気を保っていられないとの恩情か、あずかり知らない光源がぼんやりと照らす。
「・・・・・・知ってて黙ってんの?」
「いいじゃないですか」
「だからよかねぇだろ。何ソレ。とても正気の沙汰とは思えないんだけど。何なの? 何の苦行なの?」
その目が静かに振り返る。井戸の底をのぞき込んだかのような昏い穴ぼこ。呪いでもかけられるのかと思った。
「この世界でどうしても手に入らないものなんてないじゃないですか。自ら手放すか、絶対に手の届かない所まで離れる以外」
分かりますよね、と穴ぼこが問う。師匠なら分かりますよね。
「知ってますよ。何かあるたびに少しずつ傷ついて、傷つきたくないから先回りして疑って。夢占いでもろくな結果にならないから寝るのが怖くて、恨んでまた疑って」
「超病んでんじゃん。でも分かってんなら話は早いじゃねぇか」
「それでも、苦しくても私が手放さない限り終わらないんです。幸せなんです。水島君の彼女でいることが。好きな人とつながってられる。そのことがこんなに幸せだなんて知りませんでした」
三
暴風。光の加減でようやく見えた表情。振り返った顔半分、見開かれた目は常軌を逸していた。青い。少なくともまともな精神状態じゃなかった。
「お前、冷え切ってんじゃねぇか。何で言わねぇんだよ」
半身を起こすと肩をつかむ。その丸みに一瞬ひるむ。気づかなかった。着こんでいる量が少ない。すぐ戻ると思っていたからだろう。
「・・・・・・っざけんな。オイ!」
エコノミー症候群以前に、座ったまま凍死しそうな勢いの弟子は、声に肩を震わせると、思い出したように歯を打ち鳴らした。自ら後部座席に移ることさえできそうにない。俺はそのバックシートを倒すと、青白い手首を引いた。
「悪いな、コレ一つしかねぇんだわ。でも良かったな。お前位のサイズなら大丈夫そうだ」
高崎だったら完璧アウトだったけどな、と言うと寝袋の入口を開ける。しかし弟子はその場に腰を下ろしたまま動こうとしない。青白い頬、血色のない唇。人がしのげる限界値。いつ自我を失ってもおかしくない状況で、意思を持ったその目が反射する。
「いえ、」
暴風。どれくらい経ったのか分からない。気づいたら携帯は立ち上がれなくなってたし、揺れるわずかな明かりも心許ない。闇は深くなる一方だ。
「いえ、じゃねぇよ。テメェの顔色分かってんのか」
「大丈夫ですよ。足上げたら少し楽になりました」
「違ぇよ。何言ってんだよお前。マジで死ぬぞ。この俺様が場所空けてやってんの。早くしてくんない?」
「いえ、」
頭にきた。バカかコイツは。
「いい加減にしろよ! これは命令だ。お前に何かあって俺だけ帰れるか。テメェのせいで人生狂わされるのとか超カンベンだかんな」
「だって!」
その歯が鳴った。キバをむき出す。
「だって、私がここで自分が楽になることを選んだら、水島君も同じ事をしてると思っちゃうじゃないですか。私は水島君を信じてる」
それは純粋な願掛けだった。恋人という立場からすればあまりに儚い。信じてると口にはするものの、それは得体の知れないモノに願わなければ信じられないということでもあった。
「知らねぇよ。神サマ仏サマがいくら頑張ったところで、なるようにしかならねぇ。テメェとの因果関係はゼロだ」
弟子は膝を抱え込むと、目を閉じた。互いを説得するために使う労力をムダだと感じたのだろう。勝手に省エネモードに切り替える。
「違います。きっと師匠には分からない」
ピ、と切り裂く。弟子はそれきり動かなくなった。
四
〈さ、鮫島先輩、少々お話がっ・・・・・・〉
ふと思い出したのは海に行った日、初めて話しかけて来たときのことだった。あの時は確か、火州と一緒にいたことをバレたくないと言っていた。雅ちゃんが傷つくからと。
〈師匠!〉
利害関係。水島との関係にプラスに働くと知ったとき、コイツは心からうれしそうにした。一方俺も、ストレスのはけ口として無害なコイツは重宝した。
互いにどう見られるかを一切気にしない、これ以上ない関係だったはずだ。目に見えない所で円滑油になるような。なのに
「分かるかよ!」
すさまじいブレーキがかかる。互いの考えがぶつかって、どちらかが折れることでしかおさまらない。本来向き合うことのない相手なだけに、力任せで済むと思っていた。ところが声を荒げれば荒げる程、膝を抱えて襟元を合わせて頑なな小さな塊になっていく。
何なんだ。
コイツは望んで苦しい方を選んでいる。凍えながらもぶれない意思。ざわざわする。なんとしてでも言うことを聞かせないといけない。
「いいから! 俺が寒いんだよ」
「・・・・・・我慢して下さい」
「水島には言わないから」
「・・・・・・大丈夫ですよ」
「大丈夫じゃねぇから言ってんだよ!」
反応が鈍い。四の五の言ってるヒマはなかった。
「俺が野郎だからか? 男だと思わずに済めばいいのか?」
返事はなかった。再び省エネモードに入る。
いい加減腹くくるしかない。俺はゆっくり息を吸うと、吐いた。
「・・・・・・安心しろ。俺がお前をどうこうすることはない」
「そういう問題じゃ」
「できねぇんだ」
暴風。少しの間の後、その顔が上がった。言ってる意味を理解したというよりは、声色の変化に反応したようだった。寝袋の入口を塞ぐ。冷気の遮断によって安心したからか、身震いが起きた。
閉じる。自己防衛の意思表示。形は違えどそれは弟子と同じ体勢だった。
俺は確かにコイツを傷つけることばかり口にしていた。それが現実だとしても、それを突きつけられることを望んでいた訳じゃないし、それ以前にコイツは分かってて付き合っていた。全部知ってた上で、水島の彼女というポジションを守ろうとしていた。もはや水島の気持ちなど関係ない。それは周りからどう見えようと本人だけはそれを望んでいるのだ。
閉じる。本当は傷つきたくない。でも目的のために傷つかなきゃならない。それは相応の覚悟のいる事だった。
「・・・・・・たたねぇんだ。前話したろ。ガキつくっちまったって。あれから全然ダメで、今日ダメならもう諦めようって。だからお前だからとかじゃなくて、何も起こらねぇから安心しろ」
言いながらホッとしたのはむしろ俺の方だったと思う。弟子は一テンポ遅れて頭をかいた。
五
「師匠・・・・・・」
「何も言うな。分かっただろ。いいから早くこっち来い」
「いえ、たたないって何がですか?」
「は?」
「え?」
「・・・・・・」
「・・・・・・」
「・・・・・・。・・・・・・」
「・・・・・・」
「・・・・・・ち、ちょっと待て。ウソだろ。マジで言ってんの? え、何、お前コウノトリ信者なの?」
「こうのとり?」
「保健体育出てるよな? ガキがどうやってできるか知ってるよな?」
「漠然と・・・・・・。なんかこう、好きな人同士が抱き合ってると自然と」
「授からねぇよ! こわいこわいこわいこわいちょっと待ってよくそんなんで付き合うどうこう言えたな! 下手したらお前、強制わいせつ罪とかで相手を犯罪者にしたてあげてたとこだぞ! 恐ろしすぎる!」
え? え? と戸惑っている被害者ヅラは見るに堪えない。いいから、とその手を引くと、思ったよりずっと軽い力で動いた。理解出来ていないなりに、安全と知ってガードが緩んだのかもしれない。
「し、ししょ」
「早く! マジで凍え死んだらテメェのせいだかんな!」
この距離での命令はよく効く。弟子はしぶしぶ寝袋に入った。
「・・・・・・っ! お前アイスかよ! 人間の足じゃねぇ!」
空気よりずっと凍えた身体を抱きしめる。弟子は身体を縮こめると「かたじけない・・・・・・」と言った。どこの武士だよ。その時ふと火州の顔が頭をかすめた。
「・・・・・・。『をば』の使い方、ね」
気の毒すぎる。相当ハードル高ぇぞコイツ。アイツの苦労が目に浮かぶようだった。
「何ですか?」
「いや、」
言いながら目の端に映ったのは緩んだその頬。くやしくなって当たる。
「ホラ。やっぱり一旦懐に入っちまったらたやすいもんだな。何が『水島君が』だよ」
「違いますよ。師匠がうれしそうにしたから」
身じろぎ。得意げな顔色は決してよくないが、少しずつ体温を取り戻していく。満たされてやっと、人にやさしくなれる。
〈いいから! 俺が寒いんだよ〉
それはあながち間違ってなかったのかもしれない。ため息一つ「うるせぇ」とつぶやく。
六
まさか二人から断られるとは思わなかった。冬のスノボはなんだかんだで恒例行事だ。
火州の目は冷たかった。弟子と水島の事をあの時既に知っていたのかもしれない。高崎も把握してたんだろう「火州行かねぇんだろ? なら俺もパスだ」と言った。アイツが行かねぇから行かないなんて、まるで俺には何の価値もないみたいじゃねぇか。
何だよ。絶対って何だ。何で俺だけ知らねぇんだよ。何で勝手に進んでんだよ。俺だけずっと同じ所で
「火州さんと高崎先輩、来れなくて残念ですね」
肩が跳ねた。考えてることが漏れてんのかと思った。
「別に」
「気を遣わなくていいのに」
弟子は笑って見せると両手をこすり合わせた。
「百パーセントの力でぶつかれる相手がいないのは寂しいですね『フェアじゃない』から」
「気ぃ遣ってなんかねぇよ」
確かに同じ力が返ってこないのは漠然と不安ではあった。どうしても一方的で、俺ばかり居心地がよくなる。少なくともアイツらは大富豪だろうと何だろうと負けっぱなしで終われるような寛容さは持ち合わせていない。同じ生き物が集まればただのガキで、そこには互いの甘えが根付いていた。でも
「・・・・・・俺だけだったのかもな」
静かだった。いつの間にか暴風は鳴りをひそめ、ただただ雪が降り続ける。時間が経過すればこの車ごと埋もれて仲良く窒息死するのかもしれない。
「師匠、トイレ」
「・・・・・・」
そんな憂いを最小限の声量でぶっ飛ばすと、弟子は寝袋を抜け出した。助手席に戻り、靴を履いて車を出る。俺は脱力して思いっきりため息をついた。マイペースか。
今何時だ? 動くのがおっくうであるため、確認する術も持たない。くもった窓越しに薄明かりが差していた。
今頃水島達はしっぽりやることやってんのかな。アイツ未熟だけど腹据わってるからなぁ。コイツとの恋人関係なんて関係ねぇんだろうな。そんで遅かれ早かれ
「師匠! ちょっと来て下さい!」
「何だようるせぇ。寒いんだよ。今外気温何度だと思ってんだよ」
いくら悪態をついた所で、ドアを開けたまま待っていられてはたまらない。イヤイヤ寝袋を抜け出すと、そこは
「・・・・・・っ」
息の止まるような銀世界だった。分厚い雲が立ちこめるその隙間にぽっかり月が顔を出す。まぶしいほど強く清廉な光が舞い続ける雪を一つ残らず照らしていた。まっさらな雪の表面。とても踏み入ってはいけないおごそかな空気。ただただその美しさに圧倒される。
「トイレ、あっちにありました」
・・・・・・もうちょっと待てよ。
本人あくまで気を利かせて言ったつもりなのだろう。ため息一つ、その前を横切るとロッジに向かう。吐く息が白い。それさえ月の光があるからだ。遮るもののない視界。胸の奥が引き攣れるように痛んだのは足りないものを自覚したから。
寂しい、というのは本来あるはずのものがない時に起こる感情らしい。
今、ここに足りないのは
〈つとむくん〉
違う。
〈鮫島〉
違う。
〈鮫〉
違う。舞う息。視界が大きくぼやける。
全部、だ。
七
車に戻ると、既に弟子が寝袋に入っていた。
「寒かったので」
いや、そんな中引っ張り出したのどこのどいつだよ。
俺もその中に入ると、弟子は身体をひねるようにして場所を空けた。
「・・・・・・帽子、水島にもらったとか褒められたとか、そういうんじゃないか?」
「まさか」
「そうか。悪いな。それなら諦めてもらってもいいか?」
ふ、とその身体から力が抜けた気がした。
「いいですよ。本当は『プレゼントしてもらった』とか言ってみたかったんですけど、むなしいだけですしね。ないです。そんな証拠。私たちが付き合ってる事なんて何も残らない。雪が降り積もってしまえばおしまい。少しだけ寂しいと思うことがあるんです」
仕方ないんですけどね、そう言うと一人で笑った。その背中を抱き寄せる。
「・・・・・・寒くないか?」
「はい」
何とか朝まで持ちそうだと安心したからか、疲れがドッと押し寄せる。まぶたが重い。
「師匠」
「・・・・・・何」
「大丈夫ですよ。師匠が思ってる程、深刻なことじゃない」
背中に回った腕。身体が重い。返事がないことをよしとしたのか、弟子は身じろぎすると少しだけ上に移動した。頭を、なでられた気がする。そのまな板同様の胸に顔を埋める。
「抱き合うだけで満たされるんです。それだけで承認欲求も不安も寂しさもストレスも全部解消できます。万能なんです。だから無理しなくていいんです。頑張らなくていいんです。ましてや背伸びなんてしなくていいんです」
眠たい。それは子守歌だった。
「もう一度やり直しましょう。早く走ることが全てじゃない。ちゃんと承認される所から。何もなくてもここにいていいんです。師匠は、ちゃんと大事な存在なんです」
雪の降る音が聞こえるようだった。それ程までに静かで安らかな音色。さっき見た銀世界を思い出す。まっさらな雪の表面。とても踏み入ってはいけないおごそかな空気。ただただ圧倒されたその美しさは
「おやすみなさい」
どうしてだろう。水島を想うその横顔と重なった。