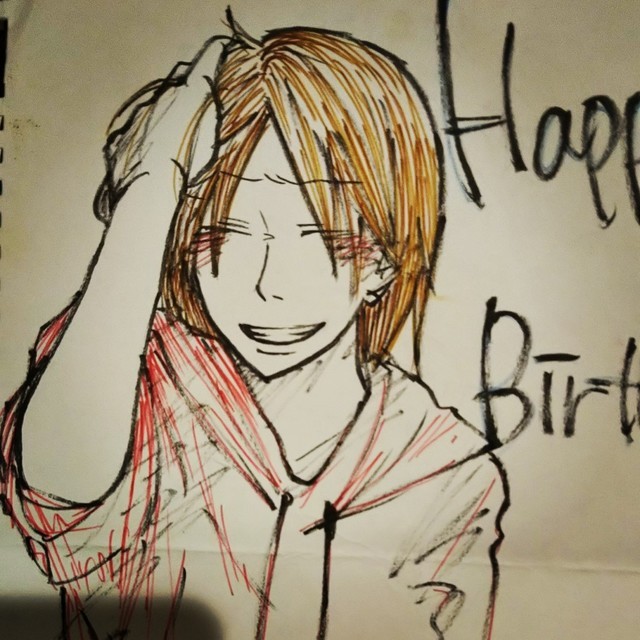真琴8〈9月8日(水)〉
文字数 4,786文字
一
「出来た」
オーブンを開けると同時に、甘いにおいが鼻をなでた。わずか五十センチ四方の機械に閉じ込められた空気が、正しく成熟して四方八方にあふれ出る。母親の笑顔を連想させる、お砂糖のやさしい香り。
水曜五限。授業は一学期の技術と入れ替わりに家庭科になる。その初めての調理実習。テーマはカップケーキだった。
「いっこもーらい。あちっ。でもうめぇ」
素早い動きで盗塁を決めると、津山君はやけどしないようにテーブルにそれを置いた。その目がキラキラしている。目を大きくすると同時に鼻の穴も膨らむ。元々アーモンド型の目に丸い鼻先。野球部の坊主頭をしているが、さらに丸の要素が追加される。このまま行くとよく焼けのアンパンマンになってしまう。その真っ白な歯だけが焼けに目立つ。
「俺もー」
「ちょっと男子! 先に全部下ろしなよ! 草進さんトレイ持ったままでしょ!」
瀬川君と滝口さんが両側から顔を出す。あ、熱いから気をつけて。なんて鍋つかみを使用している立場で思ったが、既に軽いテンポで大皿に移し始めていた。縁がギザギザのアルミホイルが十個そこそこ。卵と小麦粉、ベーキングパウダーにバターという単純な材料から成るカップケーキは、生クリームもフルーツもない素朴な外見であるからこそ出せる、一種の親しみやすさを備えていた。やさしい色。優しいにおい。ふんわりとした
ふと幼い頃に見た絵本に、大きな卵のパウンドケーキを仲間と一緒に食べる場面があって、それに憧れていたのを思い出す。
「何か草進さん、こういうの似合うな」
トレイを戻して振り返る。思ったより近くで目が合った。思わず一歩後ずさる。
その後津山君は「俺それ片付けるわ」と言うと、そのまま水場に行ってしまった。調理実習は一班四人で行われる。瀬川君と滝口さんもケーキを平等に配り終えると、机の上を片付け始めた。その向こう、クリーム色のエプロンが横切る。
水島君。
水島君がエプロンしてる。お玉持ってる。え、何で? もう焼き上がってるのに何でお玉・・・・・・あ、拭き上げてどこにしまうか分からなかったんだかわいい。その口が「アリガト」って動いた代わって平田さん。今すぐそのポジション代わってぇぇぇぇぇぇ!
しまった。落ち着け私。それにしても水島君は水島君で自分の分があるから、追加であげたとしてもカップケーキ三昧で迷惑じゃないかな。でも部活後にはお腹すくだろうし。・・・・・・あれ、今日水曜? 部活なくない? でもそれなら家帰って食べてもらってもいいけどその場合お母さんに見つかって「あら、それどうしたの?」とか。いやん。そんな、私ただのクラスメイトなんで。ちょっと仲良くなりつつはあるんですケド。なんて。
「・・・・・・草進さんどうしたの? 思いだし笑い?」
拭き上げながら滝口さんが言う。あわてて頬をこすると「何でもない」と食器を片付け始めた。
実は海に行ったあの日、師匠所望のかき氷を買いに行く道中、今までで一番たくさん水島君と話しをした。近い内に試合があったらしく、その事について話してくれたのだ。
「負けちゃったんだけどね」
そう言ってはいたが、一年で試合に出ている時点ですごいと思ったし、相手も相当強かったという。
「ううん、残念かもしれないけど、すごいね」
そう言うと、水島君は「そうかな」と言って鼻の頭をかいた。
一方師匠と鈴汝さんはしばらく帰って来なかったけれど、もしあの二人に何かあるとしたら、願ってもないことだ。落ち着かない様子の水島君を横目に吐いた息。浅ましくも本音だった。
二
時刻は十六時を回る。家庭科は五限だったため、教室に戻ると掃除をして、それぞれ帰路につく。私は水島君の姿を目視すると、まだあたたかいカップケーキをつかんだ。深呼吸。一、二、三。頑張れ自分。
「水・・・・・・」
「おい弟子、ちょっと来い」
はっきりとした声だった。振り返った身体を一周させて元に戻す。白い手首。前のドアに片腕をかけるようにして師匠が顔をのぞかせていた。当然だ。私を弟子と呼ぶのは、今の所一人しかいない。一瞬シン、となった教室が再びざわつき始める。元のものを取り戻したざわつきではない。新たに加わった話題への、積極的な交流だった。
うなじが熱い。バッグをつかむと、背中一杯に視線を浴びながら入口に向かう。
「真琴」
その時だった。走り寄ってきた慶子が私の手首をつかんだ。
「どうしたの? 何かあったの?」
心配してくれているのだろう。まるで縁のない相手に、新学期同様からまれていると思ったためかもしれない。つかまれた手首が痛い。
「大丈夫、知り合いだよ」
「ちょっと、ねぇ」
落ち着いて、とその目が言っていた。ミヤが、早苗が、氷川さんが、月下(つきのした)さんが、たくさんの目が集まる。今この場面で師匠についていく事は、このクラスでの立場を考えれば明らかに悪手だ。しかし
「大丈夫だよ」
そう口を挟んだのは千嘉ちゃんだ。
「あの人あたしも知ってるし、彼氏の友人だから」
慶子はぐっ、と口をつぐんだ。突然の申し出に混乱しているようだ。つかまれていた手首が軽くなるのを感じて、さりげなく外す。戸惑いに揺れる目と目が合う。
「ありがとう。本当に大丈夫だから」
「真琴・・・・・・」
それっきり慶子は何も言わなかった。すぐにドアを出てしまったのだ。何か言っていたとしても、今の私に聞こえるはずがなかった。
三
「・・・・・・師匠、ここって立ち入り禁止じゃ」
「俺だからいいの。黙ってついて来いや」
ひぃ、である。先生でもあるまいし、俺だからいいのって一体何者なんだこの人。
北校舎、丁度西日の影になった突き当たりの階段を上る。この先は屋外に続いていて、本来生徒は使用することのないものだ。階下の図書館から微かな声が聞こえて振り返る。
「早く」
私はただの高校生。それ以上でもそれ以下でもない。そんなチキン代表にいきなりこんな高めのハードル、用意された所で跳べる訳
「早く」
「跳びます」
「は?」
先生に怒られる可能性より、今怒られるのを回避する方に頭が回った。後で考えてもこの選択は間違っていないと思う。どうやら人は追い詰められると本当の正しさが分からなくなるらしい。
灰色の踊り場。橙の光が磨りガラスから漏れている。チカチカと目を突くのは塵が反射したものだ。師匠は屋外に続くドアの鍵を開けると、一歩踏み出した。その後に続く。
「わぁ・・・・・・」
本体以外分厚い雲に覆われた落日。わずかに漏れ出た光の束が、懸命に東の空に手を伸ばしている。ぬいぐるみのはらわたをぶちまけたような空。詰まっていたのは白いモコモコの綿なのに、ここからだと影ばかり目立つ。昔は大切にされていたのに、寂しさで一杯になって、お腹の中から悲しい色になってしまったかのようだ。キュッと心臓の一部が引き攣れる。
「気に入ったか?」
手すりに手をかけて眺める私の隣に腰を下ろすと、柵に背をあずけてタバコを取り出す。その目はこれだけ美しいものを見ようともしない。見慣れているのか、それともあえて避けているのか。
「これを、見せるために呼んだんですか?」
「はっ、そういうことは好きな相手にするもんだろ?」
じゃあ何だよ。「ですよねー」と返して目をすがめる。
副流煙。その強いニオイが鼻を刺激する。不規則な白は、何にもとらわれず背景に溶け込む。師匠はタバコがよく似合う。橙がじっくり低温で頬を焼く。
四
「お前、最近どうよ」
「最近、ですか?」
「今一番近いのって誰なの?」
聞いちゃいない。私はまだ一つ目の質問で立ち往生しているというのに。
「一番近いの、ですか?」
だから最初のはなかった事にして次の質問に向き直る。
「近いの・・・・・・」
ふとこの間部活帰りに見かけて声をかけた背中を思い出す。赤いフレームのラケット。赤茶の髪に焼けた肌。
「鈴汝さんで」
「そういうのいいから」
ズバン! といっそすがすがしい太刀で切られる。
俺が聞いてるのそういう事じゃないよね。え、空気読めないの? バカなの? いいから早く
目を合わせるだけでセリフが流れ込んでくるこれは恐怖からくる推察に他ならない。この場をうまく乗り切るためにはどうしたらいいのか、再び頭がフル回転を始める。しかし
「え、っと」
一番近いの・・・・・・水島君とか言ったらおこがましいだろうか。そもそもこの場合主観だけで答えていいのかも危うい。それに水島君だって
水島君。
急いでバッグの中を見る。そこには本来いるはずのないカップケーキが、バツが悪そうにいらっしゃった。
「・・・・・・あれ、俺何かまずいこと聞いちゃった?」
ショックを隠しきれない私を見上げたまま師匠が言う。その口の右端がつり上がっている。ちきしょう。
「いえ、別に・・・・・・」
「うわ、やった。丁度俺腹減った所だったんだよね」
悲しみの余り脱力してしゃがみ込んだ時バッグの中が見えたのか、次の瞬間それがもう自分のものになっている辺り、この人やはりただ者ではない。
「ちょちょちょこれ水島君にあげようと」
「水島君の分? じゃあ問題ないから大丈夫」
どゆことー! 正規の了承を得ないままに、師匠は吸い殻を側溝に押しつけてラップを外した。
「うわ。やるじゃねぇか弟子。うめぇ」
その細い目をかっぴらく。小さな黒目がキラキラと輝いた。
恐れを抱く相手が相手だけに、予想外の反応に驚いて思わず「じゃあ、もうこれもあげます」と残る一つも差し出してしまった。その無邪気な笑顔。
「マジで? 今お前、俺ん中でちょっと評価上がったよ?」
それでも一番下に変わりはないらしいが。
心から楽しそうな顔。丁寧に指先をなめ終えて両手をこすり合わせる。ついでにゲップを一つ。その目がおもむろにどこか一点を捉えた。影が差す。
「・・・・・・これでチャラって言っといて。言えば分かるから」
「水島君にですか?」
「そ」
その後両手をはたくとポケットを探る。
「お返し、一本でいい?」
「え?」
「あ、二つだから二本か」
「え、あ、いや、私吸いませんから!」
私もアナタも高校生。謎の力で通ってるけど師匠も立派な未成年ですから!
全力で拒絶するも、困り顔で「じゃあ何がいいの?」と聞いてくる。
「他やれるもんないしなぁ。何かないの? 何か」
強奪しておきながらもお返しはしたいタチらしい。意外と誠実、というのか。
「じゃあ師匠は誰が好きなんですか?」
五
「・・・・・・聞かれた事に答えるのが礼でいいんだな?」
それならそれで、というカンジで向き直る。こういう場合きちんと向き合ってくれるらしい。
「誘われたのは私ですけど、師匠の目当ては別の人なんでしょう?」
何かを思い出したようだ。その片頬が上がった。
「お前」
「私か、」
師匠とまっすぐ向き合う。師匠は、逃げない。
「鈴汝さんか」
その時だった。ほんの一瞬、その顔が歪んだ。まばたきにかき消されてしまう程の微々たる変化。まばたきの合間に捉えてしまった事が幸か不幸か。
心臓が縮み上がる。これは罪悪感だ。優位に立ってした発言の何かで相手を傷つけた。
「あの、」
「うーん、さんかく一点」
天を仰ぐ。東の空では雲の隙間を星が埋めるようにして輝いている。月に照らされて、はらわたはやっぱり灰色。
「・・・・・・え?」
まさかの部分点。私はその不可解な返答に戸惑う。師匠はその後自嘲気味に笑うと「面白い話をしてやるよ」とまっすぐ目を合わせた。師匠は、逃げない。
太陽が沈んで月が昇る。色彩が、気温が、湿度が、まるで同じ場所とは思えない、たった三十分で起きた変化。浮かび上がるシルエット。私はそのいたずらっぽい目の奥に何か深い闇を見る。
既に後悔し始めている。それは五感ではなく、第六感の域で感じたものだった。