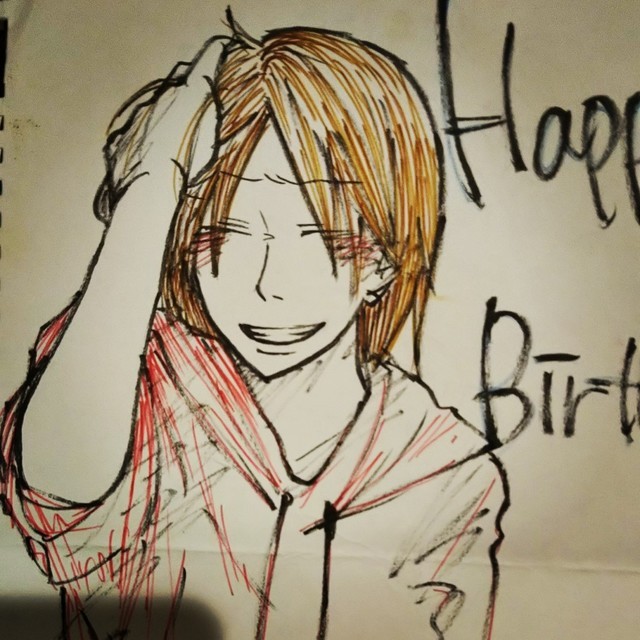雅7〈8月16日(月)〉
文字数 5,093文字
一
波の打ち寄せる音が鼓膜を叩いた。昨日より水際に近い分、足元を這うようなさざ波になったとしても、余韻が潮風になって頬をなでる。強い光が針のように目を刺す。拷問とはこういうものかもしれない。地続きの現実。この足元は、この場にいなくても飛鳥様に続いていて、時間も規則正しく前に進んでいる。だから受け入れがたい現実も全て、その軌道上にある。事実、太陽に向けて目を開けたまま固定されるという拷問は存在するそうだ。
合わない焦点で無色の光の筋を見つめる。その時だった。男性の声がした。
「雅ちゃん、ちょっと行こうか」
そうして腕を引っ張り上げられる。
触覚。感じたのはその時だけだ。しかし現実を伝えるには充分すぎるほどの力を発揮する。その後鮫島先輩はすぐに手を離すと、真琴達の向かった方向に歩き出した。肘に残った痛みを感じながらその後に続く。例え何があろうとあたしの足は勝手に動く。それは中学の時から鍛え上げられた上下関係。先輩、後輩は決して覆ることはない。半ば無意識に、その強い赤みを帯びた背中を追う。
笑い話をしよう。ただ自分が笑うために。
元々男の人が苦手だった。それは、必ずしも一年前の事件だけが、原因な訳ではない。それより前から男性の女性に対する視線が変化したことに気づいていた。あたしはそれが、鳥肌が立つほど嫌だった。
しかしその一方で、自分がそれを堂々と口に出せるほど出来上がった人間ではないことも分かっていた。なんだかんだ言いながら嫌いになりきれないのは、自分に無いものを持っているという、強い関心から起こる感情だった。
だからあたしは「あの人」を選んだ。男らしくて、リードしてくれる頼もしい人。結果的に下衆野郎だったけど、今思えば必ずしも悪い人ではなかったように思う。そうしてその時分かったのは、やっぱりあたしは男の人以前に父親を求めている、という事だった。足りないものを必死で補おうと、物心ついた頃には既にいなかった父親の影を探した。
飛鳥様。
その名を呼ぶだけで涙腺にまでその振動が届いてしまう。
〈その・・・・・・火州さんは、男の人として好きなんでしょうか?〉
〈妹・・・・・・みたいな感じなんだ〉
つま先に目を落とす。桜色のネイル。それはどこまでもかわいらしく、同時に、どこまでも幼い。それでも
鼻の奥がしびれる。のどの奥が熱い。それでもこの一年にウソはなかった。例えばそれが一般的に言う「恋愛感情」と少しばかりずれていたとしても、飛鳥様を想って過ごした時間は、何物にも代えがたい宝物だ。
あたしはちゃんと、恋してた。
二
十分も経っただろうか。昨日食料調達に行った売店の少し手前で東に向かう。いつの間にか足全体が強く赤く染まっていた。もし上着を羽織っていなければ、背中も同じ色に染まっていただろう。
「こっち」
鮫島先輩はそう言って、防波堤を乗り越えて反対側に腰を下ろした。その後に続く。
『海抜八メートル』と黄色の帯で表示された防波堤は、砂浜から階段五段分の高さにあり、南北に際限なく続いていた。本体の高さは一、二メートルそこそこ。座ってしまえば海からは完全に見えなかった。ささやかな駐車スペースなのだろう。ヒラヒラと手招きをする鮫島先輩が座っているのは、そんな防波堤が海に突き出すようにしてコの字型に変形した所だった。分厚いコンクリートは外であるにも関わらず重厚な閉塞感を与える。
「火州と、何かあったの?」
変わらない声の調子。ただ距離が近いだけに、音が直接肌を刺激するようだった。身じろぎをする。鮫島先輩は苦笑いすると、腰から手を戻した。
「・・・・・・また忘れた」
あ、と思う。タバコの事かもしれない。売店までそう距離はない。買って来ることを申し出るが断られた。その立てた膝の上で両手を組み合わせる。
「機嫌、悪くなったらごめんね」
その口の右端がつり上がる。薄い唇。ふいに花火の夜のことを思い出す。
太陽がそうっと角度を変える。
「いや、別に答えたくないならいいんだけど」
鮫島先輩はそう言うと、頭を掻いた。質問に対してあれっきり黙ってしまったあたしに、そんな逃げ道が用意される。あたしは内心ほっとして沈黙を守り続ける。
ここにいると波は元より、そのほとんどの音が遠ざかったように感じる。聞こえる音はと言えば、防波堤のすぐ裏の階段を使用する人達の話し声ぐらいだ。
「前にさ、俺雅ちゃんに『何で火州がいいの?』って聞いたの覚えてる?」
うなずく。
「何で突然あんなこと聞いたかっていうと、あの時もし『前に男達から助けてくれたから』がその答えだったとしたら聞きたいことがあったからなんだよね」
鮫島先輩は組んだ手をそのまま口元まで持っていくと空を見上げた。続く言葉を待つ。ぬるい風が肌の表面をなでる。しばらくその姿勢でいたが、ふと気付いたように笑って「・・・・・・うん・・・・・・でもやっぱいいや」と言った。そう言われると気になるもので「何ですか?」と聞く。その目がスッとこっちを向いた。
「知りたい?」
うなずく。鮫島先輩は心からうれしそうに笑うと「教えてやんない」と言った。
何よそれ。こうなると益々知りたくなるものでもう一度聞き直す。うれしそうにしている鮫島先輩は、その顔を崩さないまま、ふざけてあたしの頭の横に片手を付いた。その表情が一変する。
「あの時、助けに入ったのが俺だったら、俺を好きになっていた?」
三
上着を挟んで背中が擦れた。小石や砂を固めた防波堤はひんやりとしている。太陽が傾く。その光を受けるすべてのものの影が伸びる。
喉が鳴った。あたしは予期せぬ問いかけに戸惑う。
「・・・・・・え?」
やっとのことで声に出す。黙っていれば再び逃げ道を用意してくれるだろうという甘い考えは、その間の長さから消し飛んだ。重苦しい沈黙。互いの距離が近い分空気が薄くなる。数秒が心臓の早さに反比例して数分にも感じられる。
背負った影、赤い肌。強い光をたたえた冷たい目。身体の位置を変えていないため、腕一本で簡易の檻が形成される。
「ねぇ」
その声に反応する。あたしは質問の意図が分からない。
「いえ・・・・・・あの・・・・・・」
逃げられない。視線を落とすが、その視線をすくいとるかのように、鮫島先輩はじっと顔を覗き込んだ。
「・・・・・・」
続く沈黙。この状況を楽しんでいるのかとも思ったが、少しの笑みも見て取れない目元や口元から、すぐにその考えは打ち消した。脳が痺れる。あたしはそれでも何も言えずに黙っていた。
「あの、さ」
肩が強張る。しかしどうやらあたしのほうが沈黙に打ち勝ったようだ。依然緊張状態であることに変わりはないが。
「これは高崎が言ってたんだけど、例え決まった相手がいたとしても、言い訳さえつくってやれば女は案外簡単に手に入るもんなんだと」
甲高い鳥の鳴き声は警鐘。通常、考えられない近さで発される声は低い。その振動が頬の筋肉をしびれさせるようだ。まともに呼吸ができない。防波堤で背中がゴリ、とすれた。目をそらせない。
何の話?
「例えば『お前は嫌がったけど、俺が無理やりさせた』っていう言い訳を先に与えたとしたら、よほど毛嫌いしていない限り、素直に言うことを聞くようになるんだと」
だから何だというのだろう。あたしには関係ない。どこか他人事として受け流そうとする意識そのものを自己防衛と呼ぶのだろうか。だってあたしにとっての決まった相手は・・・・・・。
ズキリと心臓が音を立てる。最後に見たその人は悲しい顔をしていた。かかるにおい。それは半日タバコに接していないためか、微かな苦みと、それ以上に男の人のにおいがした。 その口の右端を吊り上がる。続く言葉におびえる。それでももう、飛鳥様を呼ぶことはかなわない。その心底楽しそうな両の目。
「悪いけど、俺そういうフェアじゃないのって好きじゃないんだよね。女だけが被害者ぶるの訳分かんないし、それなら同じ罪背負ってもらいたいんだよね。だから」
目を逸らせない。身体が動かない。
その口元が奇妙にゆがんだ。
「三秒待ってあげる。嫌だったら逃げて」
四
真っ白になる。音未満の声が漏れた。
「いち」
ちょっと待って、と言おうとするが声が出ない。本当に震えて欲しい喉だけが、頑として動こうとしない。
「に」
ギシ、と肩が鳴った。地面についた手。どちらも信じられない程固まっていた。遅れて膝からも同じ音がする。これじゃとても間に合わな
「さん」
「ちょっ・・・・・・」
やっと出た声はそのまま飲み込まれた。鮫島先輩は身体を起こすと、覆いかぶさるようにして唇を重ねた。痛い。髪が小石と砂の間に引っかかる。布越しに背中が擦れた。固くて痛い。無機質なコンクリートは刺さるようだ。身動きがとれない。それでも何とかその胸元を押しやる。しかしその両手も手首から絡めとられ、
「むっ・・・・・・」
顔をぶっ違いにされる。思わず目を見開くと、状況に似つかわしくない澄んだ空と立ち上った入道雲を見た。今こそ人通りはないものの、いつ横切ったっておかしくない。必死に腕に力をこめるがびくともしない。一体何だってこの細い腕にどれほどの力が秘められているのか。
「んっ!」
身体を震わせる。噛み付くようにして開けられた口に、熱をもった舌が入り込んできた。異物。予測できない動きに、全ての神経を持って行かれる。熱い。息が出来ない。次の瞬間脳裏にはじけたのは、あの昏い廃墟だった。
〈泣き叫んでもいいよ〉
懇願も拒絶も通用しない、意思疎通の叶わない相手、男と名のつく生き物。
〈相手に言い訳さえつくってやれば〉
傷口に割って入られる。足首が断続的に鈍い痛みを伝える。顔をゆがめると、口内から低く笑う音がした。
ゾク、と何かが背筋を這い上がる。必死で脈打つ心臓に、不穏な影が映り込む。
一瞬、また一瞬。純粋な恐怖と嫌悪の間に顔を出す不純物。それは
こわいこわいこわいこわい。
足を引き寄せて身体を縮こめる。それは今あるものを手放してしまわないようにするための行動。それは飛鳥様の笑顔であり、異性への警戒心であり、そうして外から与えられた未知の刺激に流されそうになる意識でもあった。
くちゅ、という音がして、身体を強張らせる。
信じられない。
動揺。意識との乖離。
知らない内に身体の奥が溶け出す。ゆるゆるとあいまいになっていく境界線。その端に映り込む飛鳥様。こういう時に限ってキレイな部分がよみがえる。そうしてそれは片っ端から黒く塗りつぶされていく。不純物。それは生殖本能でもある、ただの快楽。
「はい、べー」
息継ぎ。鮫島先輩は右手を放すと、あたしのあごを掴んで強引に上を向かせた。くぐもった声が漏れる。一瞬、相手の舌の根に触れた気がした。どうやらそれは相手も一緒だったようで、
捕まる。歯で押さえて吸い上げられると、全身の力が抜けた。熱い。こわい。その肩にすがる手。いつしか相手の欲するであろう事に応え始める。深くつながる瞬間が増えていく。荒削りに、噛み付くように繰り返されるそれは、根こそぎ抵抗する力を奪い去った。
「・・・・・・声、漏らすなよ」
一旦身体を離すと、それでも鼻先が触れ合う距離でささやく。カッと顔が熱くなる。
応える前に再び口を塞がれる。だめだ。分かっていても力が入らない。熱い息。微かな苦みが後ろめたさをあおった。
日が傾く。空が燃え始めていた。あごをつかんでいた手が外れ、左肩に触れる。その後指で辿って襟元をつかむと、むしりとるように脱がせにかかった。肩がはだける。
目を見開いた。ようやく目が覚めると、思い切って突き飛ばす。鮫島先輩は口元を拭って、にらみ上げた。
「邪魔なんだよ、それ」
眉間に刻まれたしわ。ドスの利いた声に一瞬動けなくなる。
羽織っていた上着は、ここに来る前水島が着せてくれたものだった。あらわになった左肩は、じんじんとその焼けた痛みを訴える。あたしはとうとう、こらえきれずに涙を落とした。
影が伸びる。前にも同じように泣いた事はあったが、そのときは優しく拭ってくれた。
鮫島先輩は一瞬、その時と同じように激しい動揺を見せたが、そのすぐ後「ほらやっぱり、すぐ女は被害者ぶる」とつぶやいた。でも一方で「泣くんじゃねぇよ」と手のひらであたしの頬を拭った。その姿をぼうっと見つめる。
足首の傷が、鈍く痛みを訴える。それは「今」がうつつであることを伝える唯一の指針。そうしてあたしは、もうどこにも戻れないことを、静かに悟った。