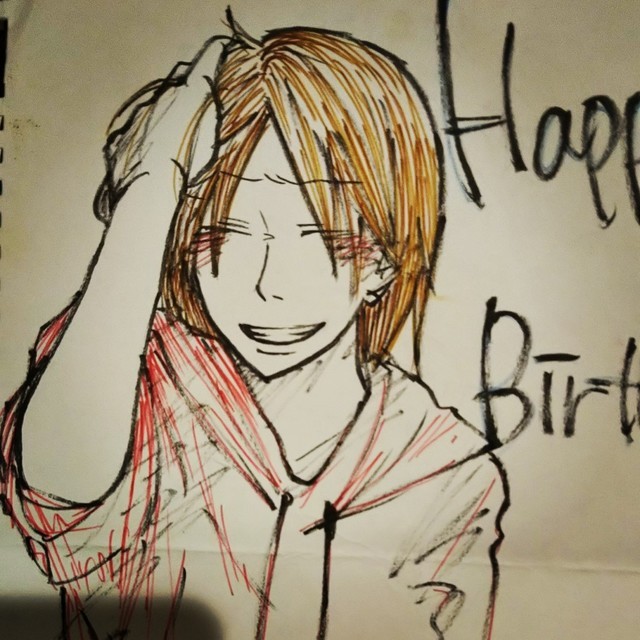真琴15〈1月7日(金)、8日(土)〉
文字数 5,154文字
一
驚いたのは、慶子がちゃんと登校していたことだった。
保健室の一番奥、ベッドに引かれたカーテン。薄い薄いプライバシーは、非力でありながらその繊細な心を守っていた。消去法だったのだろう。様子を見に家に行ってもいいか尋ねたとき、ここにいることが判明した。
血色が悪い。乾いた目の周りにはこすった跡がある。
「不注意だったの」
かすれ声。枕元に置かれた水さえ手をつけていないようだ。慶子は手元を見つめたまま、つぶやくように話し始めた。
先生の手伝いで資料室に行ったこと。知り合いの通っている大学名を見つけて、その本を取ろうとしたこと。届かなくて脚立を持ってこようと振り返った時、代わりにとろうとした先生にぶつかったこと。その時先生がとっさにつかんだのが頭上の本数冊だったこと。慶子をかばおうとして自分が下になり、その頭を抱えたこと。カシャン、というメガネの落ちる音がしたこと。ここまで一連のことに事故以外の何かは全く見られなかった。しかし
「問題はその後」
その場ですぐ起き上がって、互いの無事を確認すればそれで仕舞いだった。事実、真面目な生徒が物音に駆けつけるまで数秒のタイムラグが存在したという。そののどが引き攣れた。
「前から、触ってみたかった」
「何を」
久しぶりに見る笑顔はあまりに弱々しい。ただ目元が緩んだだけの、マイナスがゼロに戻っただけの表情。同時に吐かれた息。それは、あるいは自虐めいた
「メガネの跡。そこだけくぼむじゃない? 日焼けした頃からずっと触ってみたかった。だから」
偶然外れたメガネ。目の前にそれはあった。良いか悪いかなんて判断基準は介さなかった。静かな純粋な衝動。ただ触れてみたい。それ以上でもそれ以下でもないその一瞬が切り取られてしまった。当人が思うよりずっと鮮やかに。
グラウンドから鉄砲の音がした。陸上部だ。早々と傾く日。本来なら私も部活の時間だった。隔離された部屋に漂う、消毒薬のにおい。身動きがとれない。
自分に何ができるだろう。
消毒薬のにおい。転んでできた傷がいつかは癒えるように、他人を巻き込んでできた傷も同じように癒えるときが来るのだろうか。ならばそれまではどうしたらいいんだろう。先生は、どうなるのだろう。
慶子は分かってる。分かった上で後悔してる。
触れてみたいと思ってしまったこと自体、間違いだったと。深い意味はなかったとしても切り取られた瞬間で判断されてしまうことがある、そのことに気づけなかったと。それは
「違う」
運動部のかけ声が聞こえる。沈みゆく太陽。圧倒的に暗い室内。それでも声が大きければそれが正しい訳じゃない「絶対」なんてない。慶子がその瞬間抱いた思いは
「間違ってなんかない」
誰にも否定できない。同じ立場だったらなんて、同じ立ち場になれっこないんだから分かりようがない。規則が、モラルが、常識と呼ばれる何かが、必ずしも正しい訳じゃない。マイノリティ。王道とは外れた何かを排除しようとするのは、むしろ多数に甘んじる人の弱さ。
「ちゃんと順を追って、先生に話をしよう」
大丈夫。慶子は私が本来の居場所を離れようとした時、手を引いた唯一。先生は見てる。ただの王道に戻れる。問題は
「・・・・・・ミヤと早苗ちゃんは?」
その目に張った膜。ゆらゆらと揺れる。うつむく拍子に肩に落ちかかった髪。
「こわい」
たった一言。震える肩。対象は二人に限らない。二人の向こうに見える多数。その肩をつかむ。
「大丈夫」
揺れる。落ちた涙がスカートをぬらした。乾いたのど。上あごに張り付いた舌。正直な身体がわななく。恐れているのは拒絶。
「私だけじゃ不安?」
笑われるだろう。豹変女と先生と噂のあった女。でも私は
「私はちゃんと、もう一度慶子と向き合いたい」
気を遣ったり、言いたいことが言えなかったり、自分のよさも分からなくなってしまうような関係はもう嫌だ。一緒にいて気疲れしない、呼吸するように話のできる相手はそういないことにやっと気づけた。気づけたから
「お願い」
また一つ、涙が落ちた。紺に黒。スカートのそこだけ濃くなる色。続いたのは笑い声。
「何それ」
顔を上げる「何それ」続けて笑う。マイナスをゼロにじゃない。ゼロからプラスを生み出すための表情。
紺に黒。三つ目の涙は私のスカートの上に落ちた。
二
何かあるときは続くものなのかもしれない。それは高校の体育館を使えない時に使用していた市の運動施設が工事のため使用できず、部活がなくなった土曜日のことだった。
「あのー師匠、私暖をとるためのものじゃないですし、今日はちょっと・・・・・・」
「何、反抗期? 甘えるところから始めろっつったのお前じゃん?」
「いや、甘えるというか『やり直しましょう』って」
「同じじゃん。何、嫌なの?」
別に嫌とは言ってないですけど・・・・・・と返すと、やりとりが終了した。相変わらず私の太ももにあごを乗せて、腰にしがみついた姿勢のまま動こうとしない。
「一応ですけど、水島君にフラれて傷心真っ最中なの知ってますよね? なのでしばらくは静かに過ごしたいと言いますか・・・・・・」
「何、俺がうるさいって言ってるワケ? しゃべってないんだけど」
「いや、そういう類いの静かさとはまた違ってですね・・・・・・」
言ったところでダメだ。この人聞いちゃいない。お腹に鼻先を押しつける。本人「甘えたいから甘えてる」ただそれだけなのだ。ここまで素直になれるのはうらやましいし、どこか愛おしいとさえ思えてくる。
「・・・・・・お前、生理中?」
「だから! 今日はちょっとって言ってるんです!」
前言撤回。デリカシーのない素直さはイコール無神経だ。
屋上。故にそのまま突き抜ける声。透明度の高い青空。師匠は肩を揺らすと、思いのほか小さな声でつぶやいた。
「そっか。お前でもガキ産めんだよな」
必死で引き剥がそうとしていた腕の力をゆるめる。師匠は膝に頭を乗せると仰向けになった。やさしいまなざし。その口の端がつり上がる。
ずるい。
「何、同情した?」
「してません」
そんなこと言われたらどうにもできない。
やさしいまなざし。見つめているのは、その手に抱くことのなかった我が子だ。
「頼むよ。あと十分。そうしたらちゃんと立つから」
下ネタじゃないよ、と付け足すとその目を閉じる。
長いまつげ。色素の薄い眉。度々こうして甘える師匠は、何とか大人になろうとしているようだった。インプットしてアウトプットする。単純なようでいて難しいのは、誰もが同じ環境で育つ訳ではないからだ。インプットを補う。足りなかったのは自己肯定感。
顔を上げる。背もたれにしている柵が背中に食い込んで痛い。身体を起こそうとすると下から不満そうな声が聞こえた。
三
「火州さんと高崎先輩、元気ですかね?」
「・・・・・・」
静かな屋上。私自身、師匠に引きずられて来るとき以外ここに縁はないのだが、元はと言えば三人の秘密基地だという。存在感のある二人はいるだけで空気を変えた。
「気になるの?」
「気になると言いますか・・・・・・」
目を閉じたままその口だけ動かして、組んだ指を頭の下に敷く。少しだけ身体を引いた。
「特に火州はお前の天敵じゃん? 何で?」
それは純粋な疑問だった。顔を上げる。
「そうですね。でも本当はそうじゃないって分かったからでしょうか。師匠こそ知ってるんじゃないですか」
「何で分かったの? 言えば納得するもんじゃないでしょ」
「以前一緒に出かけたことがあって、その時の様子で」
「何? なになになに一緒に? 火州と? どゆこと?」
「いえ、二人でという訳ではなくて、弟さんと妹さんと一緒に・・・・・・。水族館に行ったんです。浜名湖の」
いつの間にかまるっと見開かれた目が、言ってる事だけでなく表情思惑全てを見透かす。
「それ、いつの話?」
「・・・・・・十一月の末です」
その目が記憶を辿る。おおよそ一ヶ月前。何かに、たどり着いたようだ。
「をば」
「え?」
「お前、アイツと話したとき『をば』って言い回し使っただろ」
「・・・・・・。あ、確か『ご連絡をばさせていただくつもりで』とか何とか」
大きなため息。先程とは打って変わって、師匠は冷えたまなざしを向けた。
「それでその後すぐ水島君と付き合うってなったの? お前脳みそどうなってんの? 残酷過ぎだろ」
「え?」
「分かんないの? アイツ自分から動くことなんて今までなかった。周りが甘やかすのもあるけど、それでも自らの意思で動いたんだよ」
テメェの宝もんさらすなんて、どんだけ必死なんだよあのシスコン。そう言うと勢いよく起き上がって頭をかく。と、ふと私越しに何かを見つける。
「・・・・・・オイ、お前何か待ち合わせでもしてんの?」
「え?」
あごでしゃくる。柵越し。振り返ると校門の所に小さな人影を見つけた。あれは
「オイ!」
気づいたら駆け出していた。軽いアルミ製の扉を開けると、一段飛ばしで階段を下る。
小さな人影。間違えようがない。あれは、楓君と礼奈ちゃんだ。
四
予期せぬ小さな来訪者二人の様子に、ただならぬ事態を感じ取った師匠は、原付で先に火州さんの元に向かった。二人も師匠と火州さんのつながりは知っているようで「さめくん・・・・・・」とつぶやいた後、私の手をとった。
「よめも来てくれ。さめさんだけで止められるか分かんない」
楓君が空いている方の手をつかんで引く。思ったよりずっと強い力に驚いた。
「どうしたの? 何があったの? それに二人ともどうやってここへ」
「いいから早く!」
火州さんの家は愛野の駅南だ。マラソン大会の練習のために走るコースほぼそのまま使える。ただ、この時期の西風は容赦なく、線路に沿う一本道を西に向かう者の心を折るには充分すぎる力を発揮した。故に帰りは追い風。背中を押されて身体が勝手に進む。
「歩いてきたの?」
「あるいてない、早あるき。走るとコイツがおいつけないから」
礼奈ちゃんが握る手に力をこめる。噛みしめた下唇。ムリを言ってついてきたのかもしれない。
延々続く一本道。早々帰り支度を始めた太陽は、橙の光を供給し始める。色味だけで全然暖かさは感じられない。背中を叩き続ける冷たい風。
「よめ、何かしらない? アイツ、ここんとこおかしいんだ。むかしにもどったみたいに」
「昔に、ですか?」
「うん。むかしはこんなのばっかだったから。よくさめさんやたかさきさんが何とかしてくれてた」
思い出したのは、鈴汝さんに髪を切られた、あの保健室での出来事。
〈オイ、火州やめとけ!〉
〈またキレちゃったのー?〉
確かにあの時、二人はその状況に慣れていた。
伸びる影。コンクリートの貯水池を過ぎると、あともう少しだった。師匠はもうとっくに先についているだろう。私が行く意味なんて
〈分かんないの?〉
しっかりとつかまれた手。楓君はなんの疑いもせず、私を引っ張り続ける。しっかりとつかまれた手。礼奈ちゃんが必死で後をついてきている。
「いつもさめさんやたかさきさんがいるならいいけど、いないとどうしようもないんだ」
それは小さいなりに考え抜いた末の行動だった。偶然見つけられたから良かったものの、元々知った顔を探して、いなければ職員室に向かうつもりだったらしい。センター試験が来週に迫っている。私たちが先に見つけられたのは不幸中の幸いだった。
楓君が振り返る。もう家が見えていた。
「よめ頼む。飛鳥をたすけてくれ」
「大丈夫だよ。もうお友達が先についてるはずだから」
「ちがう」
握られた手に力がこもる。
「アイツがあんなたのしそうにするのはじめて見た。よめなんだろ? アイツがおとなしくなったの」
〈うわ冷たっ! お前らバカじゃねぇの!〉
〈俺は、楽しかった。アイツらも楽しんでた。それでいいにしてくれねぇか〉
〈をばって。いつの時代だよ〉
ニオイによる特定。深く鳴る、心臓の音。
〈もう、いいにしねぇ?〉
〈俺も手ぇ上げて悪かったと思ってるし、だからその・・・・・・もう本当にお前のこと嫌ってないし、怖がるようなことしないから。だから〉
〈今日、お前がいてよかった〉
関係の修復。何もしなければなくなるはずだったつながりが保たれる。確かに、息づく。
〈手、貸せ〉
〈真琴には手を出すな〉
矛盾。師匠の言うとおり、俺はいいけどお前はダメ的な。
その家にたどり着く。目立った物音はしない。楓君がドアに手をかけた。待って、まだ心の整理が
〈真琴ちゃんは水島君が好きなわけでしょ? それで水島君がその先輩のことが好きだとして、その先輩が火州さんのこと好きで、火州さんが真琴ちゃんのこと好きだったらすごくない?〉
〈着いたならいい。それだけだ〉
ドアが開いた。