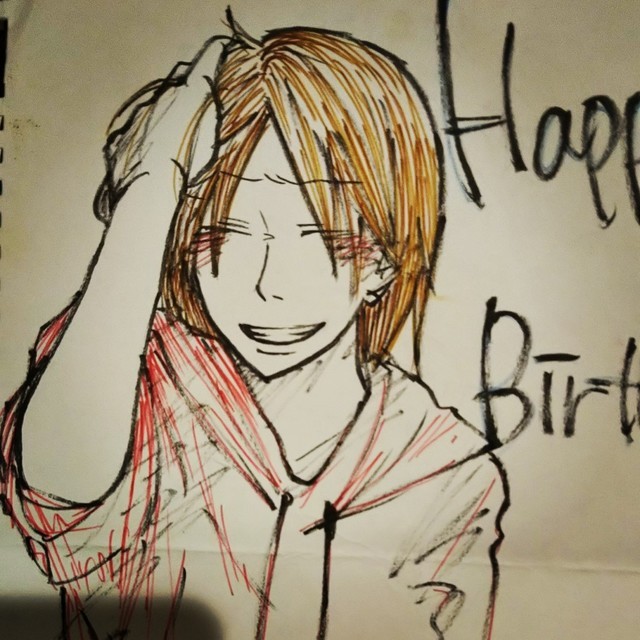聖12〈10月21日(木)〉
文字数 6,820文字
一
「いやいやいやいやめんどくさ。あるでしょロッカーぐらい」
「ありますよ大きいのが五台。スタメン分で、あとは先輩が使う棚だけです」
「一回は?」
「それ以外の歩かないスペースです」
「地べたってコト? マジか。俺達の時はもちっとマシだった気がすんだけど」
「強制意識改革だそうです」
時代に逆行してんねーと言うと、鮫島先輩は生徒会室の前の廊下で立ち止まった。
「早く取ってきてー」
僕の荷物は基本生徒会室にある。三階まで上ることに対してさんざん文句を言うものの、しっかりついてくる所よく分からない。僕は自分のロッカーから荷物を取り出すと、戸締まりをする。その時だった。
「あー待ってー」
高い声がして振り返る。沙羅が小走りに走ってくる所だった。
「忘れ物しちゃってー」
言いながら顔を上げて目を丸くする。その先には同じく目を丸くした鮫島先輩がいた。
「あ・・・・・・」
「先、行ってるわ」
鮫島先輩はそう言い残すと、階段へ向かった。
「知り合い?」
「え? ・・・・・・ううん」
違うならそれ以上話を深めることはない。僕は鍵を渡すと、その後を追った。
すっかり日が落ちて丸い月が出ていた。電灯は等間隔に設置されているが、足元を照らすだけで、ここから見えるのはほとんど人影のみだ。見れば分かるシルエットでも、見当たらなければ探すしかない。見回しながら歩いている内に校舎の西側、駐輪場まで来てしまった。どこかですれ違ってしまったのかもしれない。校舎に戻ろうとすると、背後から声がした。
「遅いんだけどー」
原付のエンジン音。鮫島先輩は既に校門を出た所にいた。
「いやいやいやいや分かりませんから。見つけられませんから」
「あ、連絡手段がないからってコト?」
言いながら携帯を取り出す。その指先が動いた。次の瞬間には僕の携帯が震え出す。
〈ツトム君だよ☆〉
「・・・・・・いやいやいやいや何で僕の連絡先知ってるんですか。その前に誰ですか『ツトムくん』って」
「弟子から盗・・・・・・聞いた。あ、俺ツトムっていうの。よろしくね」
「今盗んだって言いかけましたよね。言いましたよね」
「サジ加減。受け取り方次第。許容ハンイは広めのがイイ男」
言い逃げもいいとこ、その後「乗って」と自分の背後を指し示す。
「『後で教える』って話は・・・・・・」
「うん。だから乗って。後で教えてあげるよ」
「僕自分の自転車があるんですけど」
「いいよそれでも。ついて来れるならドーゾ」
バカ言え。部活終わりの人力なめんなよ。
よい子は真似しないでね。しぶしぶ乗って掴まる。細い骨格。見た目以上に薄い肩だった。
「いっくよー」
しかしそんな声とともに急発進したため、余裕なしにしがみつく。頼りない肩にめりこんだ指先。鮫島先輩の笑い声が響いた。
「ぎゃはは。しっかり掴まってるんだよー」
ゴーイングマイウェイは揺るがない。
カーブ。後ろに寄った重心。最大積載量をオーバーしたまま、フルスロットルで切り裂く闇夜。気が気でないのはまぶしいテールランプ。
「鮫島先輩! 制限速度越えてますよね!」
「いんや。普通六十キロだよ。知らなかった?」
他力。ぶっ飛びそうな心臓に、思い出したのは高い声だった。
〈早い早い早い早い!〉
猛省する。休みが明けたら真っ先に謝ろうと思った。
二
走ること十五分。辿り着いたのは
「・・・・・・何ですかここ」
お屋敷だった。庭園? 邸宅? 城? いや、やっぱりお屋敷が一番しっくりくる。
「俺んち。お前名前何てーの?」
「え? 聖ですけど・・・・・・」
「ひじき?」
「誰がミネラル豊富ですか」
鮫島先輩は笑いながら外門扉備え付けの機械に登録をする。
「漢字は?」
「高野聖の聖です」
「コウヤって・・・・・・一瞬高野(アイツ)の顔が浮かんだ。二度と言わないで」
聞いたのはそっちだと言う前に扉が開いた。自動だった。言い忘れていたがこの門扉、僕や鮫島先輩より大きい。開いたとき確認したが、厚みも二十センチほどある。お屋敷でありながら要塞でもある、被弾を想定したようなつくりだった。
外門扉から玄関まで三十メートル。歩き始めると庭の影から何かが駆けてくるのが見えた。
「ワフッ!」
ドーベルマン! 庭にドーベルマン!
僕はちぎれんばかりに尻尾を振りながら主人の周りを回る犬の姿を食い入るように見つめる。めっちゃなついてる。ってかめっちゃなついてる。
その後ようやく玄関まで辿り着くが、視線を感じて振り返る。微かに聞こえる息づかい。このドーベルマン(名はポン太だそうだ)と同じくらいの高さに瞬く光が、行儀良く二つずつ暗闇に紛れている・・・・・・気がしたが、もう気のせいという事にしておく。
「ココ」
指差したのはドアの脇にあるインターホンだ。
「遊び来たら門の所で名前入力して、ココに向かって『タコタコ焼きタコ三昧』って言ってね。合言葉。それで開くから」
合言葉って子供が秘密基地の入口で言うあれか。要するに大人版のあれなのか。
「あ、でも気をつけてね。間違ったり途中でかんだりすると、コイツら怒るから」
言いながらポン太の頭をなでる。その目が爛々と輝いた。
怖ぇぇぇぇぇぇ! ポン太めっちゃ見てる! めっちゃ見てるぅぅぅぅぅ!
「・・・・・・コイツ『ら』って」
「コイツだけじゃないから。あの辺にいるだろ?」
気のせいじゃなかった。行儀良く二つずつ暗闇に紛れている光を、僕は確かにさっき見ていた。眉間をおさえる。
全く現実味のない足元に、ポン太の息がかかった。
「だいぶ前に火州が合言葉噛んだんだけどさー。あいつ強いじゃん? コイツら目が合った瞬間上下関係が分かっちまって、でかい声で「ワンッ!」って威嚇されたらみんなキャンキャン言って逃げやがんの。それ以来火州は顔パス。マジ番犬の意味なし」
ははっと笑う。「あいつ強いじゃん?」って知らないよ。火州先輩一体何者なんだよ。
「でも高崎はまんまと食われてた。すぐ止めたけどね。だから気をつけたほうがいいよ」
気の毒過ぎる。友人宅に遊びに行って犬に食われたなんて聞いたことがない。二度とここに来る事はないだろう。
「いい? 『タコがたこ焼きタコ三昧』だからね」
僕は二度と来る事はないと思ったため、右から左へ受け流す。しかし
「・・・・・・『が』って欲しいですか?」
「あれ、なぁんだ。つまんなーい」
鮫島先輩はそう言って口の端を吊り上げると、ドアを開けた。僕は真顔でその背中を見つめる。
いつかこの人に想像を絶するバチが当たりますようにと心から願った。
三
結局『後で教える』に辿り着いたのは、その後夕食を済ませて(僕が部活に戻ったタイミングで連絡していたらしく、当然のように出てきた。奥に長い帽子をかぶった人がいた)風呂に入って(ジャグジーだった)部屋に戻った後の事だった。
「・・・・・・ひろっ・・・・・・」
もはや状況に見合った力で驚く気力さえ残っていない。適応した、と言うべきか。脳がきちんと情報を処理するために、正式にこの家をどこぞの貴族の別荘と認識する。
首にかけたタオルの両端を握りしめて立ち尽くしていると、開けられたドアにぶつかった。
「あ、わり。その辺テキトーに座ってて」
言いながら六十センチ四方のローテーブルを運ぶと、上に色違いのコースターを置いた。
その辺、の選択肢の無限たるや。下手すると自宅のワンフロアに相当する一室は、テレビ、ベッド、本棚、机、それに備え付けのクローゼットがあるだけで、肌触りの良い絨毯の敷かれた中央一帯には今来たテーブル以外何もない。
「あ、椅子欲しい? 俺床が落ち着くから置いてないんだけど、欲しけりゃ持ってくるよ」
「いいですいいですお構いなく」
どんな代物が運ばれてくるか分かったもんじゃない。全力で拒否すると、テーブルの傍に腰を下ろした。
「あ、と、僕の服は・・・・・・」
風呂から出ると、脱いだ服及び制服一式がなくなっていて、代わりに未開封のスウェットが用意されていた。
「今、和田さんが回してくれてるよ。大丈夫。アイロンまでかけてくれるから」
わださんってだれだ。
「いやいやいやいやいいですよ何かもうそんな」
「あ、もしかして自分で全部やりたいタイプ?」
そうじゃない。何故だろう。同じ国の住人のはずなのに全く会話がかみ合わない。
僕は脱力すると「何でもないです」と言った。
「何飲みたい?」
「・・・・・・。・・・・・・お茶を」
「紅茶? 緑茶?」
「緑茶で」
「あったかいの? 冷たいの? 玄米? ほうじ? 番茶? あ、わり。抹茶は切らしてんだ。先週の茶会で好評だったみたいで、今取り寄せてる」
どこの誰が茶と言って抹茶を要求する。京都かここは。申し訳なさそうにしなを作るな。
「・・・・・・冷たい玄米茶で」
「おけ。ちょっと待っててね」
これ以上のやりとりは、やぶへびだと感じた。ドアが閉まるのを確認してため息をつく。
それにしてもあのテレビ台の中にあるの、昨日ニュースで見た、真夜中に行列が出来てたゲーム機だよな。あのソフト、パッケージ初回限定のやつだよな。ほんと何者なんだよ。
淡いチャコールグレーのカーテン。
「お待たせー」
その後ドアを蹴破るようにして現れた鮫島先輩は、コースターにグラスを乗せると、小脇に抱えていたボードを下ろした。
「じゃあ始めようか」
四
時刻は二十一時を回る。この時間になってやっと、泊まっていく前提で話が進んでいた事を認識した僕は、自宅に連絡を入れて向き直った。
「別に難しいことじゃない」
空調は季節をなくす。着慣らした甚平。あぐらに片肘をついて、鮫島先輩が口を開いた。
ホワイトボードにマグネット。バスケのラインが全て引かれたボードを僕らは作戦盤と呼んでいる。内一つ、赤いマグネットを動かす。
「聞いたんだ。五番に。ボールが上がる直前『誰が走れ』て、速攻決まった段階で『ゴール下で戦え』るか。冷静だったね。時間が限られてた分、割り切りもよかった」
次々と動かされていくマグネット。三つの赤はセンターラインから手前。残り二つは奥。それでもフリースローラインに位置する。僕たちのチームにとっては自陣に深く食い込まれるような陣形だ。青いマグネットが僕たちの位置取り。手前に二つ、中央に一つ、その向こうに二つ。
「『走れ』るのは一、二、四番。『ゴール下』は厳しい。なら戦い方は決まってる。走れる四番の存在が有難かったね。おまけに肩もあるときた。おかげで俺何もすることなかったよ」
マグネットが数時間前に見た光景を彷彿とさせる。ウチの五番、円さんは
「・・・・・・円さんはここまで来てました」
「そうだね。運べないんだもん。でもここまで出てきちゃマズかった。ディフェンスからしたらロストの心配がなくなるから、かえって守りやすくなった。もっとプレッシャーをかけられた」
センターライン上に置かれた赤いマグネットは三番。王様は特等席で見渡していた。
「でもすぐに押し戻したじゃん。あいつ成長したな。自分で運べるようになったもんな」
〈下がれ!〉
沈黙の前半、その重心を相手の陣地まで押し下げたのは高野さんだった。緩急をつけた視野の広いドリブルは「安易に近づけない」そう警戒させると同時に、守りの重心が高すぎる事を思い出させた。結果、見えない圧力に押されるように赤はじりじりと後退した。ただ、その先はどうしたって五対五だ。
「後は言ってた通り。ゴール下で戦わず済むようにしただけ。丁度一分。見事な奇襲だったでしょ?」
敵陣の中央。円さんのいた所を見つめる。バイオレーションを取られないように、エリアを行き来する、その元にボールが渡ることはなかった。
「・・・・・・鮫島先輩ならどうしていましたか?」
キレイな爪で鼻先をかく。涼しい目元。小さな黒目が一回り小さな黄色のマグネットをとらえた。
「これを」
左手の中指で押す。緩やかな軌道を描くマグネット。
「こう」
僕の位置から放られたボールは作戦盤上では円さんに届いた。四人のディフェンスの中央、ゴール下。勢いよく顔を上げる。しかし口を出す前に鮫島先輩が首を振った。
「・・・・・・ファウルだ。誰もとれない」
目を見開く。『ゴール下は厳しい』川崎さんは確かにそう言った。
「どうしたって中に寄る。場所で区分けして守ってる分、即席チームのボロが出る。俺んトコなんか特にそう。見合いになるかぶつかるか。どっちにしても乱れる。自由にパスが通るようになる」
「でも・・・・・・あれだけ密集した中に」
「とれなくてもいいんだよ放れば。空中戦でも力でもアイツに叶うヤツなんかいないんだろ? 選択肢が増えればディフェンスにも隙が出来る。互いの守備ハンイがあいまいな事に気づけば迷いが出る。崩壊とまでいかなくても、バスケで言う一分は短くない」
シュート、と言って小さいマグネットをゴールに合わせると、鮫島先輩は後ろ手をついた。
「お前は自分だったらあの状態でもらっても困るって思ったんだろ? じゃあ高野みたいに器用じゃなくて、野上みたいにシューターじゃないヤツが何のためにあそこにいるんだよ。テメェの身体張るためだろ? それなら戦えるし、それなら負けねぇ」
小首をかしげる。細く白い首。こんなにも華奢なのに。
「任せりゃいいじゃねぇか。部長なんだろ? あとヨロシクで片付くコトだ。逆にそうまでお膳立てしないと仕事出来ないと思ってるワケ? 何様だよ」
この人は言葉を選ばない。ナイフのようなそれは、的確に急所を突いてくる。
「お前に足りないのって、メンバーをアテにする気持ちなんじゃね? 全部自分でやろうとするからドン詰まるんだよ」
この人は、敵である僕の動きもよく見ている。
時間にして一分。たった一分で丸裸にされる。
「・・・・・・はい」
「なんとなくだけどねっ! あ、そうだ。俺からもイッコ聞いていい?」
その口元、改めてみると長い指をしていた。むき出しのすね。足の小指も僕の一、三倍位ある。「地面をとらえて蹴り出す」「何かを捕まえる」軽量の身体。「捕獲する」という事に長けているように見えた。その目が獲物を見定める。
「なんか隠してるよね。ひじきくん、一応スタメンなんでしょ?」
五
「もう一杯飲むでしょ?」
同じのでいい? と聞くと、鮫島先輩は再びドアの向こうへ消えた。僕は今し方のやりとりを振り返る。作戦盤。ただのマグネットにそれぞれの顔が浮かんだ。
〈バスケで言う一分は短くない〉
それは僕も思った事だった。一旦落ち着けば見えたはずのもの。時間にあおられて冷静さを欠いた事も敗因の一つに違いない。そう思った瞬間、苦笑いが漏れた。この方向の思考が、ドン詰まり。
大きく息を吸うと改めて部屋を見回した。割り当てられた贅沢な空間は整いすぎていて、どこか無機質でぬくもりが感じられない。気持ち肌寒さを覚える。
天井高っ。ベッドでかっ。わださんってお母さんじゃないよな。キッチンにいたあの長い帽子の人もまさかお父さんじゃないよな。一体どうなってるんだ。
その時本棚の下段にある中学の卒業アルバムが目に止まった。青の背表紙「北中」出身だった。入口を確認して引っ張り出す。最初の数ページを飛ばして生徒一覧を指で辿る。思ったよりもすぐに見つかったその人は、始め名前と顔が一致しなかった。坊ちゃん刈り。その前髪は短い。まっすぐこちらを見つめる目。
鮫島勤。そこには背筋を伸ばしたただの模範生が映っていた。
手を動かす。面倒でまとめてめくる。風圧で舞ったのは一枚の写真だった。
〈元生徒会長だぜ? あの人〉
紙面一杯の寄せ書き。踊る「会長」の文字。視線をスライドする。風圧で舞った一枚の写真はツーショット。鮫島先輩と一緒に映っている女性。それは
息を呑む。僕はこの子を知っている。どうしてこの子が
その後再びドアを蹴破るようにして現れた鮫島先輩は、僕の手元を見て一瞬動きを止めた。僕はその、やっぱりこの写真と一致しない人物を呆然と見つめる。
「・・・・・・見たらちゃんと元のとこに戻しとけよ」
「鮫島先輩・・・・・・なんでこの子が・・・・・・」
見開いた目。揺れるポニーテール。蛍光色のヘアゴム。帰り際に鉢合わせした子。
その片頬が歪む。グラスを置くと、ベッドに腰掛けた。
「違ぇよ」
「何が違うんですか。知り合いじゃないですか」
「だから違うって。よく見ろよ」
鮫島先輩は仰向けに倒れ込むと、これ見よがしにため息をついた。
「お前の知ってるその子、笑ったときそんな風に八重歯見えたか? そんなに色黒だったか? そんなに髪短かったか?」
息を呑む。投げられた質問の答えは全て同じだった。
「いえ」
再びため息一つ。少しだけ室内の明かりが暗くなった気がした。
「・・・・・・でしょ? それ、お前の知ってる子の姉ちゃんだもん」