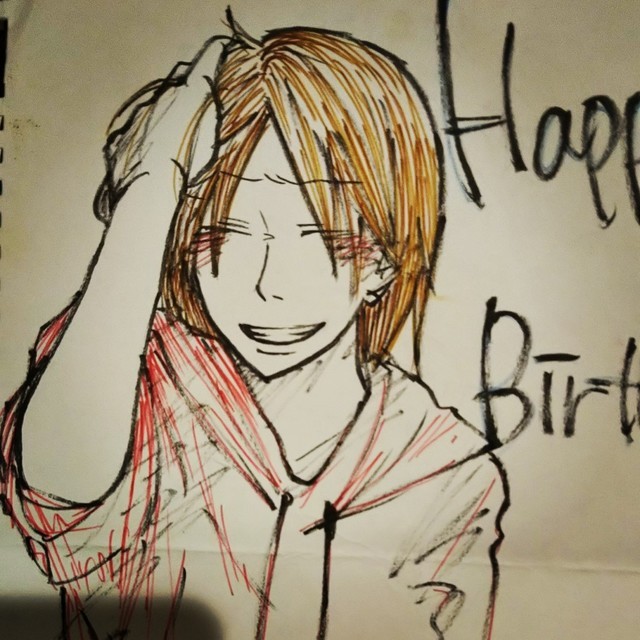雅13〈12月24日(金)〉
文字数 7,081文字
一
ようやく真実にたどり着く。あれは確か夏休み明け、九月頭の出来事だったから時間にして丸三ヶ月の月日を隔てた事になる。
十一月末日。週明けの放課後、やっと鮫島先輩をつかまえると、球技大会の日、兼子君から聞いたことを尋ねる。
「領収書の件です。鮫島先輩が関わっていると聞きましたが、本当ですか?」
残り日。薄暗い橙と紫の雲をバックに、その片頬がつり上がる。タバコをはさんだ長い指。風にあおられて長い前髪が揺れる。
「知りたい?」
「どういうことですか? 教えて下さい。本当のことを」
それは水島の表情に、言葉に、その行動全てにつながっていた。あの子の手を借りるためになくてはならない情報だった。しかしそんな思いとは裏腹に、その口をついで出たのは、あたしの選択が大いなる間違いだという宣告だった。
「惜しかったね、水島君。あと少しだったのに」
冷たい風が吹く。背筋がざわついた。
「言われなかった? この件について深入りするなって」
「言われました。でも」
「じゃあ自業自得だ」
その目は鋭利。ゆるりと細まる三日月は、新月に向かう闇を思わせる。
不穏。本当のことを知りたい、その事がどうして自業自得につながるのだろう。
「確かに一枚かんだ。上級生を動かすために、水島君じゃ力不足だからね」
「どうして鮫島先輩が・・・・・・」
「水島君が動こうとしているのを見かけたからだよ。ホント、これは偶然」
〈僕は何もしてないです〉
〈大丈夫です。この件についても、今後も、あなたに実害が及ぶことはないでしょう〉
〈・・・・・・先輩の協力があったから〉
その輪郭が見えてくる。水島の言っていたことが理解できるようになる。
〈デキてんの? あいつと〉
〈そうでもなきゃあんなかばい方しないだろうし〉
その全ぼうが姿を現す。あたしは本当に何も知らなかった。遡って一つ一つ飲み込んでいく傍ら、鮫島先輩は一歩足を踏み出すと距離をつめた。一メートル弱。ニオイがうつる。
「これを機会に知るといいよ。世の中には知らない方がいいことがある。いわゆるパンドラの箱だね」
頭上から降り注ぐ声のトーンは一定。心を介してないようだ。長い影が視界を覆う。
「この件は決して開けちゃいけない箱だった。今後雅ちゃんと関わる上で、今回のことは悪影響でしかない。年齢とは別に俺に気を遣うことになるからね」
正規のルートで歩めなかった道。意図せず手助けに入ったのはジョーカーだった。それを知ってしまった以上、確かにその通りだ。
「嫌じゃんそういうの。誰だって根っこはフェアでいたいでしょ? だからこの場合、対価が必要になる」
対価?
「そ。これは俺なりの気遣い。何かを与えたら何かをもらう。ギブアンドテイク。これできちんと元通り」
にっこりと笑う口元。その歯が月の光を受けて鈍く光った。一本の線になっていた目がゆっくりと開く。小さな黒目以上に、青みがかった白目に浮世離れした色香を感じる。
「雅ちゃんが差し出せるモノは何? 自分が受けた恩恵に見合うと思ったものをもらうよ」
ゼロメートル。ニオイが、うつる。その細い指が口元のホクロをなでた。
自業自得。その意味にたどり着く。
知ってはいけないもの。気づいてはいけないこと。あの時確かに水島は頑なだった。
〈・・・・・・信じて下さい。僕はあなたの味方です〉
〈あなたのためなんです〉
そしてそれは唐突な誘いだった。
「十二月二十四と二十五でスキー行くんだけど、火州と高崎は来れないみたいで、行くのは水島君と弟子と俺らだから」
誘い? ウソだ。行く前提で進められる話。気遣い、と称するまなざしは容赦ない。弧を描いた両目が昏く光る。
「キレイにして来てね。大切な夜だから」
強張る。これ程までにあからさまな物言いが他にあっただろうか「キレイ」は「着飾って」の意味ではない。デリカシーのかけらもない言い草は、けれども確かな意思を伝えた。
「分かったね」
その後鮫島先輩は強い一瞥を残すと、いつも通り偏った笑みを残して去って行った。全身が脈打つ。あたしはその音を聞きながら、片肘をギュッと握った。握った部分がゆがんだ感覚を伝える。
伝えるにも関わらず、この身体はもはや自分のものでないような気がした。
二
真琴から連絡が来たのは十二月に入ってすぐの事だった。
〈水島君と付き合うことになったんです〉
にわかに、突然、ふいに。短い言葉に詰まった圧倒的な事実に言葉を失う。物理的なダメージさえ感じかねない衝撃による自己防衛からだろう。電話越しの気配を感じるも、なかなか言葉を発せない。
その後望むような言葉を期待できないと察したのだろう。何とか絞り出した「そう」という返事を聞くと、真琴は「鈴汝さんも頑張って下さいね」と言って通話を切った。
ここが自室でよかった。あたしは携帯を下ろすと膝の上に置いた。時間経過で画面の光が消える。焦点は合わない。たった今聞いた声がこだまする。自分の認識と、そのことが違いすぎて、まるで別世界の話を聞いているかのようだ。
どういうこと。
一周回って冴えた頭が、さかのぼって間違い探しを始める。
一体どこから違ってた。何が分岐になったというの。
頭を抱える。身体を横たえる。蛍光灯の明かりが目に刺さった。ジン、と目の奥に感じる痛み。痛み。だからこれは夢じゃない。それでもまだ信じられない。
〈何でもないなら、僕がいるとき位何でもないって顔してて下さい。気になるんで〉
〈でも?〉
信じられない。
〈例え悪魔だろうと、他の誰かを好きになろうと〉
〈信じて下さい。僕はあなたの味方です〉
あれがウソだというのなら、あたしは何も信じられない。
〈・・・・・・そうですね〉
寂しげに微笑んでみせた顔。真摯に思いを伝える水島に、あたしはどうしてきた。
〈・・・・・・放して頂戴〉
電気を消す。両手で顔を覆う。
どこから違ってたなんてとんだ愚問。そもそも最初から違ってないところなんてなかった。何が分岐になったなんて、火を見るより明らかだった。
水島があたしにこだわる理由なんて、昔の彼女以外何ものでもない。時間に癒やされて前を向き始めたとき、その子がきちんと過去におさまったとき、自分を肯定してまっすぐ見つめてくれるパートナーの手を取る。それは自然なことだった。その時点であたしはもう
「用済み・・・・・・」
ごちそうサマ、という声がリフレインした。
三
ガタン。
大きな揺れを感じて意識を取り戻す。
時刻は十時。東名高速道路上り線を走ること一時間、一般道に入って少しした所だった。走るほどに左右からせり出す木々が大きくなっていく。これからジブリ映画の生き物に会いに行くかのようだ。
「・・・・・・鮫島先輩、普通車内はもっと静かだと思うんですけど」
後部座席から水島の声がした。横を見るとその口角が分かりやすく下がる。
「え、俺の運転にケチつけんの? ひじきくんここで降りたい?」
「ひじきじゃないですひじりです。嫌です。もうちょっとやさしく運転してください」
「何言ってんの? ハナから俺の半分はやさしさでできてんだよ。これ以上何を求めるってんだよ」
「先輩こそ何言ってるんですか。本当にやさしい人は三日前に確定の宿泊の連絡はよこしません」
「いいじゃん。どうせヒマなんだから。それにしてもクリスマスに予定ないって・・・・・・むしろ俺感謝されてもいい、いやされるべきだと思うんだけど」
あたしは二人のやりとりを聞きながらバックミラーを見やる。映りこんだ真琴は必死で笑いを押し殺していた。その様子に気づいた鮫島先輩がミラー越しに脅迫する。
「おい弟子、お前もだぞ」
「・・・・・・はぁい」
十二月二十四日、山梨県にあるゲレンデに向かう車内にて。
指先にはさまったタバコ。運転は鮫島先輩。助手席にあたし。そうして鮫島先輩の後ろに真琴、あたしの後ろに水島が座っている。
「今どの辺にいるんですか?」
手元にある地図を広げて尋ねる。鮫島先輩はタバコをくわえてハンドルを持ち替えると、地図上をトントンと叩いた。距離にして残り三分の一。すでに悲鳴を上げている三半規管。あたしは静かにため息をついた。
太陽が高い。ちらほら雲は浮かんでいるが、すっきりと晴れた空はくもりと言うまではほど遠い。まず荷物を下ろそうとたどり着いたのは、河口湖付近にある異様な風格漂う旅館だった。荷下ろしさえすれば、あとは従業員が運んでくれる。
「いいよ」
声に反応して振り返ると、顔の前で全力で手を振っている真琴がいた。全部の荷物を一回では運びきれない。人手が足りない分を水島が運んだ。それが真琴のものだったのだろう。
ズキン。
たまたま残っていたのが真琴の荷物だっただけかもしれない。それに水島の性格上、それが誰のものだろうと同じようにしたに違いない。それでも
分かっていたはずなのに、たったそれだけのことでひどく胸が痛んだ。すぐ目を逸らしたその時ポン、と頭に手を乗せられる。合った目は逆光で光を映さない。最低限の労力。低音、ハスキーな声があたしにだけ届く。
「どこを見ているのかな?」
静かに「いえ」とつぶやくと、鮫島先輩はにっこり笑った。
頭に乗せられた手。用途は決して「なでる」ではない。
四
コポポ。コポポポポ。
豊かな水音。純和室の二人部屋は、表向き真琴と共有するものだ。唐木の座卓を中央にしつらえた八畳間。障子越しに窓から差し込む光。まだ充分明るいにもかかわらず間接照明を蓄えた床の間には、陶器の壺が置かれている。
二○六号室。畳の香りに魅了された真琴は、足元に寝そべったまま動こうとしない。あたしはそのまま水回りを見て回ると、化粧水の類いを置いた。
コポポ。コポポポポ。
何気なく顔をあげる。と、
一瞬誰かと思った。鏡の中で見開かれた目。落ちた頬。絶望的に生気のない顔は、認めたくなくても自分自身だった。目を強くつむって開ける。鏡に向かって笑ってみせる。上手く笑えようと笑えなかろうと、せめて人前に出られる顔でいなければならない。
その後少しして洗面所を出ると、やけに規則正しい呼吸音が耳に入った。まさか。
「ちょっと、何寝てんのよ」
「んあっ! す、すいません、つい」
「つい」じゃないわよ。確かに長旅ではあったけど、向こうで待ってるんだから。
その手の甲で口元をぬぐう。相変わらず抜けてる子。そのあどけなさが、今は少しだけ鼻につく。
青と白のコントラスト。贅沢に蓄えられた雪は、その表面にひっかき傷がついた位ではびくともしない。スノーリゾートと呼ばれるこの場所は、小児の遊べるスペースから、傾斜三十度越え、コブつきの本格コースまで網羅している。スキー板をつけること自体、小学生以来のあたしからしたら、傾斜十度のファミリーコースが望ましいと思いながらいると、
「ひゃっほう!」
スノボを装着したシルエット。ジャッという歯切れのいい音とともに鮫島先輩が現れた。毎年のように来ているのだろう。厚い手袋越しでもすんなり上がるサングラス。その顔の周りに白い息が舞った。
青いジャケット。寒さには弱いのだろう。丸い背中は随分着込んでいるように見えた。
「わざとですか? わざとですね」
言いながらその胸倉に掴みかかっているのは水島だ。グリーンのジャケット、その前面が白い。歯切れの良い音とともに舞い上がった雪を正面からかぶっていた。
「違うよぉ。そんな俺器用じゃないしぃ」
さすがに冬休みだけあって、人があふれていた。はじめこそ初心者の真琴に合わせてファミリーコースで戯れていたものの、ストレスをためた鮫島先輩の「つまらん!」の一声により、あたしが強制的に山に駆り出される。
三カ所あるリフト。内、先程より傾斜のあるロマンスコースを辿るリフトに乗り込む。図面で見ると、さっきの倍以上の長さだ。不安になって見下ろすと、このコース自体カップル向けのもののようで、手助けと称してイチャつく男女がひしめいていた。その姿に水島と真琴を重ねる。
上達のきざしの見えない真琴に対して、水島は雪だるまをつくって遊ぶ広場に行こうと提案した。「ちびっこ」と名のつくその場所は、本来幼子の遊び場だけれど、用途は同じなのだから気にしなくていいと言う。
鼻で笑う鮫島先輩の視線をまっすぐはじき返して、水島は背を向けた。
五
強い風が吹き抜ける。リフトが低い音を立てて揺れた。
「随分余裕だね」
口の端についた髪の毛を直しながら振り返る。ほぼほぼ全面禁煙の施設内、ようやく見つけた穴場で悠々タバコをふかす鮫島先輩は、長い指先で頬杖をついた。その目の色は何色か分からない。
「今日一緒に過ごす相手よりも、隣の芝が青く見える?」
緑の芝は草。グリーンのジャケットは芝の緑。その実、青いのは鮫島先輩。
「そんなこと・・・・・・」
言いかけて口をつぐんだ。対価に思い至ったからだ。ワンフット。その片足だけつけたボードがゆらゆら揺れる。タバコの火が消える音がした。錆びた手すり。煙が強い残り香だけ残して消える。それは以前どこかで見たことのある光景だった。
「大丈夫、怒ってる訳じゃないよ。ただちょっと寂しかっただけ。ホラ、誘ったの俺だし」
左手の携帯灰皿。相変わらず繊細な輪郭を持つ横顔。少しだけ申し訳ない気持ちになる。
「・・・・・・すいません」
「あやまらないでよ。怒ってないって言ってるじゃん」
確かに怒ってはなさそうだった。暖かい日の光に照らされてにこやか。目線をかえる。
「・・・・・・今日、飛鳥様と高崎先輩はどうして来られなかったんですか?」
「まだ気になるの? 飛鳥サマ」
「いえ、そういう訳ではなくて・・・・・・ただいつも一緒にいたので、めずらしいなと・・・・・・」
フーン、と鮫島先輩は鼻で息をついた。手のひらで頬杖をつき直す。
「いつも同じじゃツマンナイから。たまには気分を変えたいじゃん?」
「特別用があった訳ではないんですか?」
「火州はおべんきょ。高崎はお家の手伝い。用って言えば毎日あることだよ」
そう言う鮫島先輩こそ、最もつまらなそうに見えた。いくら仲が良くてもずっと一緒という訳にはいかないようだ。
「もうちょっとで着くよ。足元気をつけてね。シャレんなんないケガすることあるから」
ギョッとする。どう考えても降りる三秒前に言うことではない。シャレにならないケガって何? 隣から聞こえてくる含み笑い。水島の言っていた「本当にやさしい人」の意味を、身をもって知る。
その後無事着地してほっとしたのも束の間、目の前に広がる急斜面に息を呑む。さっきも断ったが、スキー自体小学生ぶりである。にも関わらずこれはそういうレベルではない。
「先がいい? 後がいい?」
心から楽しそうにそう尋ねられるが、そこまで頭がたどり着けていない。そんな恐怖で一杯一杯の所に助け舟が入った。
「もしどっちか決められないようだったら、手つないで一緒に行こうか?」
言いながらその手を差し出す。あたしは思いがけない提案に顔を上げる。
「その場合、一直線に下るけど。あと、途中何回か跳ぶけど」
何のこれしき。あたしくじけない。助けに入った船が泥舟だったってだけのこと。
「・・・・・・先行きます」
そうしておそるおそる滑り始めた。
六
人は人生に何度かのモテ期なるものに遭遇すると、どこかで聞いたことがある。しかし
「彼女一人? もっと上手に滑る方法教えてあげるよ。一緒に滑らない?」
どうやらあたしのモテ期なるものは、肝心なところでは使われないパターンらしい。
目の前にはサングラスをかけたドレッドの兄ちゃん。側頭部のそりこみが効いてる。うん、イカスよ。だからお願い。他当たって頂戴。
「いえ、友人がいるんで」
「そうなの? じゃあその子も呼んで来ればいいよ。こっちもツレいるから」
「いえ、あの、本当にいいんで」
「そんな事言わないでさぁ」
お願いだからあっち行って。お願いだから。他の誰でもない、見ず知らずのあなたのことを思って言っているの。
「いえ、本当に結構ですんで」
「いいから! 来いっつったら来りゃいいんだよ」
いや、本当に来ちゃうから。
シャー。
「いえ、本当に」
「だからっ・・・・・・!」
あー・・・・・・。
次の瞬間、ドレッドがキレイに白い地面にめり込む。スノボの裏面を思いっきりその顔に叩きつけられたのだ。鮫島先輩はその後素早く旋回すると、体勢を整えて男の顔の辺りを指差した。はずむように動く指先。何かを数えているようだ。かけているサングラスから、その表情は読み取れない。
「・・・・・・っだよ何だテメェ! やんのか!」
地面に手をついたドレッドは勢いよく顔を上げた。その様子は頭から雪に突っ込んだにも関わらず、今にも火を噴き出しそうだ。鮫島先輩はようやく指差しを終えると、同時に片頬をつり上げた。
「ははっ。丁度十本。タコの次はイカだね」
「ふざけてんのか! ああ?」
ポケットから手を出してサングラスをよける。その顔つきが次の瞬間ガラリと変わった。
「ふざけてんのはどっちだ? 下等生物の分際で獲物の横取りなんていい度胸してんじゃん」
獲物の横取り。その時脳裏に、餌をたらふく食べて太らされた子豚がおいしそうに食べられる映像が浮かんだ。さしずめ鮫島先輩にとってあたしは太った子豚。獲物なのだ。
「来いよ。相手してやる」
ゴングが鳴り響く。それはカーンだったかチーンだったか分からない。
あたしはぼんやりと能天気な空を見つめた。