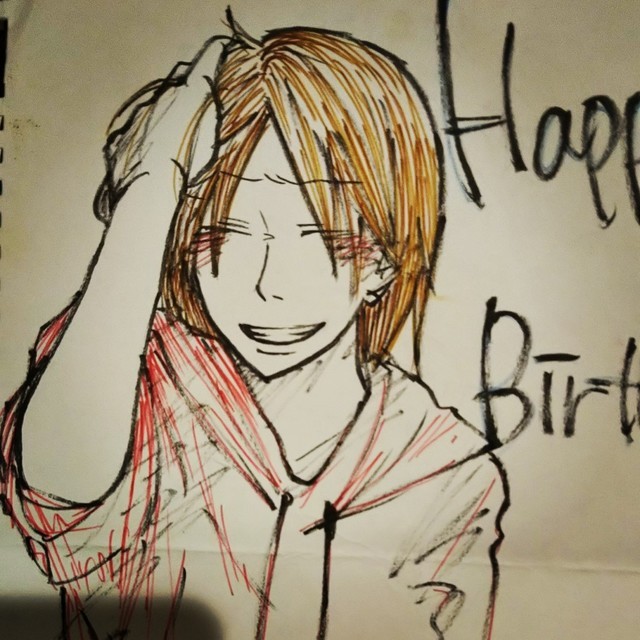雅12〈11月24日(水)〉
文字数 8,013文字
一
十一月最後の水曜日。この曜日設定は、放課後の部活の事を考えず思いっきりやれということなのだろう。冷え込みも深まる晴天の元、球技大会は開催された。
体育祭でも使用されたクラスTシャツが再びここで日の目を浴びる。ただ上着を羽織るため、どちらかというと学年色の方が強調される印象だ。
手のひらをこすり合わせながらグラウンドに向かうと、突如進路に小さな人影が飛び出した。肩の両サイドに入った、学年色赤のジャージ。
「鈴汝さんっ!」
おさげ。誰かと思ったら、長い髪をまとめた真琴だった。ジャージの下に水島と同じ黒い唐草文様のTシャツを着ている。
「びっくりしました。鈴汝さん、ピンク着るんですね」
「何言ってるの。クラスの色よ。好き好んで着てる訳じゃないわ」
「いえ、かわいいですよ」
馬鹿にしないで、と言いかけて口をつぐむ。まるで水島と会話しているかのような気がしたからだ。本当にそう思っているのだろう。真琴はうれしそうに頬をほころばせると、「鈴汝さんは何の競技に出るんですか?」と聞いた。
球技大会は全部で三種目。どの競技に出たいかは希望を募った上で決定する。サッカー、バスケ、卓球。あたしが選んだのはサッカーだ。そう答えると、真琴は顔をしかめた。
「えー。寒いですよー」
そんなの知ったことではない。しかしそう言う以上、真琴は館内競技なのだろう。選択肢一つ削れるだけだけれど。
「はい! 知ってますか? 今回隠れ行事があるみたいですよ。何でも全部の競技が終わった後、その部の人達同士の試合があるっていう。えきしびじょん、って言うんですか?」
「・・・・・・何それ。運営は生徒会よ。あたしが知らない事があるはずないじゃない」
「え、そうなんですか? でも夏に引退した三年生と、一二年生混合チームが戦って、引導を渡すとか何とか・・・・・・」
「あんたそれ、誰に聞いたの?」
一瞬しまった、という顔をしたのを見逃さなかった。真琴は「そういう訳でたぶん十五時位からになると思います。良ければ一緒に見ましょう」と言い残すと、そそくさと人ゴミに突っ込んでいった。すぐさま追いかけるが、謎のスピードを発揮した姿を早々見失う。
〈良ければ一緒に見ましょう〉
あれから真琴はクラスで二重人格というレッテルの元、一瞬時の人となったようだが、「飛鳥様と付き合っているというのはデマ」という新しい情報に助けられて、騒ぎは収束に向かったようだ。ただ単に噂する側が飽きたという可能性もあるが、いずれにしてももう一度あの「慶子」って子とも話が出来るようになったのだから、わざわざあたしを誘わなくてもいいのに。
そんな風に思いながらも自然と緩む頬。約束があるというと、少なくとも自分はそこまで生きていてもいいのだと思える。能動的に存在を主張できる。そんな小さな決め事が、嫌なことを乗り越えるためのブースターになる。
「十五時・・・・・・」
そうだ、場所を聞いていない。でもあの子の事だ。水島を基準に考えれば。
そこでふと思い至る。競技は三種。サッカー、バスケ、卓球。
バスケ。
「・・・・・・あの子・・・・・・!」
運営は生徒会。球技大会の隠れ行事。共通して思い当たる人物は一人しかいなかった。
二
見つけたらすぐ様問いただしてやろうと思っていたのに、競技場所が離れていたのと、思いの他勝ち進んでしまったのが相まって、結局真琴の言う「十五時」を回ってしまった。
足早に体育館に向かうと、中に入れない人が入口から溢れ出ていた。低い気温にも関わらず、通常締め切っているはずのシャッターが全て解放されている。鉄格子。その全箇所にも人がべったり張り付いている。
一体何なの。
あたしは隙間をかいくぐって何とか真琴を発見すると、ものすごい嫌悪の目を向けられながら、押し分けへし分けその元に辿り着いた。そこは丁度リングの真裏だった。ゴール下のラインから二メートル後ろ。一見危険なその場所は、けれども十二分に人がひしめいていて、感覚が麻痺する。
「あっ、鈴汝さん・・・・・・」
「・・・・・・え。何であんた泣いて」
その時だった。目の前を影がよぎる。
それは、水島だった。
ザンッ。
着地。バッシュが小気味よい音を立てる。あらわになった額。濃い眉の下で光る目。直後、視界に入ってきた細身の背中。ゴールネットをくぐったボールを味方に向かって投げたのは、
「走れ!」
鮫島先輩だった。
ワァッと歓声が上がる。館内に立ちこめる熱気。とても全てのシャッターを開放しているとは思えない。突然の光景に息も出来ずにいると、真琴は身をよじって場所を空けた。
「ここ、座って下さい」
「あ、ありがとう。今始まったとこ?」
言いながら得点板を見る。真ん中の数字が残り時間のようで「三」と表示されている。バスケは一クォーター四分だから、まだ始まったばかりなのだろう。今は向こうのゴール下で争いが繰り広げられているため、落ち着いて見られる。
「・・・・・・ねぇ、あんたのクラスってあんな大きい子いたかしら」
「いえ、この試合はバスケ部の三年生対一二年生の混合チームなんで、分かりやすいようにそれぞれTシャツの色だけ揃えています。ちなみに一年生は水島君だけです」
言われてみれば確かに、身体の大きな男性のTシャツは、黒地だけれど別の柄がプリントされている。学年は違っても、クラスTシャツの色は縦割りだ。水島と同じ組か、もしくはその組の人に借りたのだろう。
キュキュキュッ。
熱風。激しくバッシュがこすれる音がする。再び手前半面での試合展開になる。
一人に一人。五対五の分かりやすい戦い方。縦パスの多用される早い試合展開の中、ゴール下でボールを取ったピンクのTシャツの男性に向かって手を出したのは、左サイドにいる鮫島先輩だった。一つにくくった髪。その元にボールが渡る。
「落ち着けよ」
上がる口角。
「まだ始まったばっかだ」
その正面で腰を落としている男性もまた、笑ってみせた。丸い目。柴犬のような顔立ち。
「短いっすよ。後たったの三分しかない。どんだけ待ったと思ってるんすか」
手を出す。その俊敏な動き。よける。鮫島先輩は苦笑いすると、ボールを後ろに回してからドリブルを始めた。
「オラ、下がれ。相手してやるよ」
三
バスケという競技自体に明るくないあたしにとって、その判断基準は美しいかどうかだった。一流と呼ばれるプレイヤーに共通するのは、洗練されているが故の美しい身のこなし。そういう意味ではこの試合自体、非常にレベルの高いものではないかと感じる。中でもひときわ目を引いたのは
「リバンッ!」
ピンクのクラスTシャツ。細い背中のその人と、
「円さん!」
黒地に唐草文様のTシャツ。
「・・・・・・ねぇ、水島って上手いの?」
バスケ。と聞くと、真琴はコートから目を離さずに声を弾ませた。
「もちろんです! 一年生でスタメンですよ!」
「え、スタメンってあの子が?」
「はい! 今コートにいる人達全員レギュラーメンバーです」
三回生は当時の、一二回生は現在の、という事だろう。ふと一ヶ月前の会話を思い出す。
〈・・・・・・そうですね〉
寂しげに微笑んで見せたその理由を知る。まさか水島にそんな実力があるなんて。
再び手前半面での試合展開。と、ディフェンスの形が微妙に変わった。中央に寄るコンパクトな守り。ただ、動き出しであるゴールから最も遠い位置、トップのマークだけは離れなかった。隙あらば手を出そうとする。その動きに、水島はあえて身体を起こした。
「落ち着きましょうよ」
上がる口角。
「久しぶりで楽しみなのは分かりますけど、身体が心配です」
「変わんねぇなお前。手厚くかわいがられてるって聞いて心配した俺が間違いだった」
手を出す。その俊敏な動き。よける。水島は苦笑いすると、ボールを後ろに回してからドリブルを始めた。
「変わりましたよ。どうぞご覧下さい」
人口密度の高い台形の中、突っ込んでいった男性の元にボールが通る。あ、と思った矢先、男性はそれをはじくと、台形の一歩外、最も低い位置に回した。受け取ったのは最初に話に出た大きな男性だ。すぐさまマークが飛び出す。
「チェック」
振り払おうとするが、行き詰まる。止めてしまったドリブル。その間にもう一人が囲いに来た。無理だ。あれじゃ勝負できない。
「円さん!」
水島の声がした。ゴール下のラインギリギリ。サイドでボールを受けると、味方に回す。と同時にディフェンスの間に入ると、再びボールを受ける。驚いたのは相手の前列二人だ。後ろに任すべきか一瞬迷った。そのタイミングでパスが通る。ゴールから斜め四十五度。続けてトップへ。黒いTシャツ。受け取った物憂げな雰囲気の男性は、ポイ、とボールを放ると、とてもスポーツマンとは思えない長い髪をなびかせて敵陣に突っ込んだ。
「スイッチ!」
鈍い音がする。捕まえたのは骨太の男性だ。ぶつかった衝撃でよろめく。突っ込んだ男性はそのまま渦中をすり抜けると、ようやく振り返った。台形の真ん中にいた水島からパスが通る。スリーポイントライン。自分のテリトリーだと分かっている男性は動かない。コンパクトに守っているのだ。今彼がいる所は守備範囲外だと思ったのだろう。
ゼロ度。ゴール背面のボードは、見えない。
「崎田! 外だ!」
鮫島先輩が叫ぶ。でももう間に合わない。
ハチの毛をくくった髪。蛍光色のヘアゴムが揺れる。
「・・・・・・そっか。センパイは知らないんだ」
上しか見てなかったもんな。そうつぶやくと、男性は笑った。
四
ミスマッチ、という言葉を聞いたことがある。高さ、早さ、大きさ。全て揃えば申し分ないのだが、身体をつくろうとして筋肉を増やせば、重たい筋肉が動きを鈍らせる。早さを求めて減量すれば、当たりに弱くなる。それに持って生まれた体格差も加わる。
それは、完全なミスマッチだった。
身体の大きな人を外に出し、小さな水島を中に突っ込み、当たりに強そうな人を前に置き、やる気のなさそうな人が決定打を下す。個々の持ち場の特性に合わせたら、それぞれ勝てる見込みなんてない。
気持ち悪い。
何だかザワザワする。違和感。もっと正しい戦い方があるはず。そう思わずにはいられなかった。それは相手も同じようで、ピンクの集団に動揺が見られた。その時だった。
「大丈夫」
ゴールネットをくぐったボールを持ったまま鮫島先輩が言った。あの場所でボールを持つにもタイムリミットがあるはずだ。バスケは競技時間が短い分、時間の制約が多い。
「大丈夫、走らせなきゃいい」
そう言うと、チームメイトの一人に声をかけた。
既に形を作っていた黒い集団。そのトップ、水島が目の色を変えた。上がる人差し指。
「一本」
ゆっくりドリブルをしながら水島の向かいに立ったのは鮫島先輩。その表情はここからでは分からない。次の瞬間、一つでくくられた髪が根元から揺れる。ドリブル。止めて一歩引くと、台形ライン上、ゴール下に回す。
「・・・・・・っ!」
ダメだ。個の力じゃ叶わない。カバーに入ると、そのタイミングで空いた味方にボールが渡った。そこへ別の人がカバーに入る。後手後手。それでも最後は帳尻が合うはずだった。
「そんな訳ないデショ」
空中でボールを受け取ると、そのまま放る。本当にただ放っただけのボールは、大人しくゴールに収まる。アリウープと呼ばれるものだった。
ワァッと体育館が揺れる。鮫島先輩は仲間とハイタッチすると振り返った。
「足りないなぁ。もっと楽しもうよ」
手にしたボール。てっきり顔をしかめるものだと思っていた。水島は
「あ、ははっ!」
笑った。目の奥がギラギラしている。あんな表情見たことない。目的とは別に、まるで狩りそのものを楽しんでいるかのようだ。相手のゴールだけを見つめるその姿。
「最後までもつといいですね」
〈僕はあなたの事が好きなんです〉
「お前のメンタルがな」
〈俺も雅ちゃんのこと好きだし〉
胸を押さえる。
五
本当にこの人達はあたしの知っている二人なのだろうか。
そのくくられた髪を見る。それは猫じゃらしのようにいたずらに揺れ。知っている。それはまるで針金。安易に触れると手のひらに突き刺さる。
そのまっすぐな瞳を見る。それは揺らがず、決して揺らがず、ただ目的のモノだけを映し。知っている。どこまでも真摯なそれは、同時にこちらのあり方も問う。
鋭いまなざし。むき出しの闘志。ジャージを着ない彼らは学年色を持たない。同じ土俵で、同じ目線で戦っている。
走る。得体も知れず漂う男達の、足が地につく。
それでも終わりは来る。それは黒いTシャツ、大柄の男性の一声が合図だった。
「当たれ!」
ゴールを決めた直後、一人に一人がつく。隣で見ていた男性が「オールコートとか、マジムリ」とつぶやいた。激しい息づかい。落とした腰。相手の一挙一動に反応する身体。
「いいの? リスク高いよー」
残り二十秒。余裕の笑みを浮かべているであろう鮫島先輩は、ボールを小脇に抱えると、片足に体重を乗せた。点差は二点。ピンクが優勢だった。
「・・・・・・っ!」
奥歯を噛みしめる。水島の焦りが伝染するかのようだ。安易には飛び出せない。どうしたって相手の出方次第。じりじりと後退する時間がもどかしい。それを知った上でのボールさばき。しかし「それ」は右サイドにいた男性にボールが渡った後起こる。
シュートを決めるにはゴールに近づかなければならない。スポーツほどアナログなものはない。届かないシュートは入れようがない。物理的に離せば安心だった。勝っているが、僅差であるが故、安パイを求める。なるべく自分たちのゴールから遠ざけたい。それもなるべく早く。だから「それ」は当然の行動だった。ただ想定外だったのは
「待て! ダメだそこは」
決して油断した訳ではない。しかし正しい放物線を描いた軌道は突如遮られた。センターライン上に出現したイレギュラー。
「っ四番!」
体格の良い男性は、取ったボールを前方、誰もいないコートの隅に向かって投げた。
「・・・・・・あり得ない」
あれ、追いつくの? 思わず口を継いで出てしまう。瞬時に現れた人影。水島はそれを受けると、足元についた。目の前には鮫島先輩。
「行かせるかよ!」
完全な一対一。五秒を切っていた。
水島のドリブルに火がつく。
六
館内のざわめきは、人の移動に寄ってスライドしていく。試合時間四分のバスケを見た後、四十五分のサッカーを見るのだろう。いや、卓球が先か。それでも所々残る黄色い声は、いつまでも尾を引くようだった。
「行くわよ。ちょっと」
あたしは未だ夢見心地の真琴の腕を引くが、まるで自立する気がない。骨抜き、とはよく言ったものだ。ため息一つ、もう一度声をかけようとした時、その口が開いた。目線を辿る。
コートサイド。肩に大判のタオルを掛けたまま歩いてきたのは水島だった。目が合う。何だか居心地が悪くて視線を外すと、その後聞こえてきたのは予想した声ではなかった。
「沙羅!」
思わず顔を上げる。
さら?
水島は足早に近くを通り過ぎると「話がある」と言って多須さんを連れ出した。
不穏。真琴に声をかけようとするが、今度は激しい足音がこっちに向かって近づいてきた。
「オイ弟子! ちょっと来い!」
そうして片腕でヘッドロックした状態で、物言えぬ真琴を連れて行ったのは鮫島先輩。突然の事に呆然とする。
その後、館内を出て行こうとする人の中に、見慣れた人影を見つけた。何故だか分からない。分からないけれど、言うなら今だと思った。
「兼子君!」
あたしはその焼けた横顔に近づくと、一旦一呼吸置いて声を張った。
「お願い。あたしをどうこう言うのは構わない。けど」
その目をしっかり見返す。
「水島のことを悪く言わないで」
隣にいるのは部活の後輩か。似たような焼け方をしている。兼子君を見上げる目。
「・・・・・・何のこと?」
まるで身に覚えのない事に戸惑っているようだった。周りを気にしながら、迷惑そうに顔をしかめる。
「前にあいつとデキてんの? って言ってたじゃない。あたしはいいけど、あの子を巻き込まないで」
はぁ。と言うと、兼子君は隣にいる子を見た。
「え、実際のところデキてんの?」
「だからそんな訳ないじゃない」
「そうだよな」
再び隣にいる子を見る。
「何? 何か言いたいことでもあるの?」
「いや、」
兼子君はようやく顔を上げた。
「あいつと・・・・・・って俺、あの人のつもりで言ったんだけど」
ピンクの、細身の、三回。
「・・・・・・。・・・・・・え?」
大半の人が出て行く事によって、館内に正しい気温が戻ってくる。首元を通り抜ける風もちゃんと冷たい。あたしは思わぬ言葉にサッと血の気が引くのを感じる。
「待って、どういうこと? どうして鮫島先輩が出てくるの?」
「こっちが聞きたいよ。生徒会の人間でもないのにずかずか入ってきて、ブツが出たから結果オーライだったけど、あれなかったらほんと、どうするつもりだったんだろ」
「え、待って待って。鮫島先輩が? 最初から教えて」
その眉間にさらに深いシワが寄る。本人に聞けば? と返ってきた。
七
「そんなことより、じゃあやっぱりそっちとデキてた訳ね。それなら納得できる」
「何のこと?」
嫌な感じがする。背筋が粟立つこの感じ。目が合ったのは兼子君の隣にいた彼だった。
「・・・・・・九月末、屋上に続く踊り場にいましたよね?」
ばくんっと心臓が跳ね上がる。九月末。衣替えの前。まだ制服が白の頃。
「タバコのニオイがして階段を上がったら、吸い殻が落ちてました。この学校でタバコを吸う人はたぶん一人しかいません」
「・・・・・・どうしてあたしがそこにいたというの?」
ニオイですよ。とその子は言った。
「ニオイがした、と言ってました。草進さんが水島に。その日草進さんに会ったんですよね? 水島がどう取ったか分かりませんけど、俺は納得しました。ああそういう事かって」
「二人きりでいたとは限らないじゃない」
「それって複数プレイってコトっすか? さすがにそこまでは頭回らなかったです」
目を見開く。激情。全身から噴き出る、焼けるほどの屈辱と憎悪。
生物学上同じ生き物に分類されようと、言葉が通じると思えなかったあの時。
「いい加減にして頂戴!」
出す声が震えた。感情に制御が利かない。下手に動けば何を口走ってしまうか分からなかった。
「やめろ津川」
好奇な目をとがめる。兼子君は手綱を引くようにして言った。
「わきまえろ。仮にもお前にとっては先輩だ。下手なことは言うもんじゃない」
津川。その名に聞き覚えがある。一旦うつむいたかに見えたその目が、再び伺うようにしてこっちを向く。先輩だなんてみじんも思っていない。
「・・・・・・でも俺は吸わないんで分かんねっすけど、あれですよね。タバコ吸いたくなるのって、食事の後とかなんですよね?」
〈ごちそうサマ〉
「・・・・・・どっちにしても気をつけた方がいいですよ。誰が見てるか分かりませんから」
そう言い残すと踵を返した。その足が出口に向かう。その後振り返ったのは兼子君だった。
「水島君は嫌いじゃない。上級生の中であれだけのパフォーマンスができるんだから相当腹据わってるし、コイツにもただ妬むだけじゃなくていいとこ盗めって話してたとこ。元々悪く言うつもりはないし、だから会長がわざわざ声をかける必要は全くなかったっていう」
お互い無駄な時間を過ごしましたね。そう言うと、再び前を向き直った。
〈やめろ津川〉
あれは、あたしをかばったのではない。
かばったのは、反動を受けかねない後輩。その証拠に、
残された視線は何の温度も伴っていなかった。