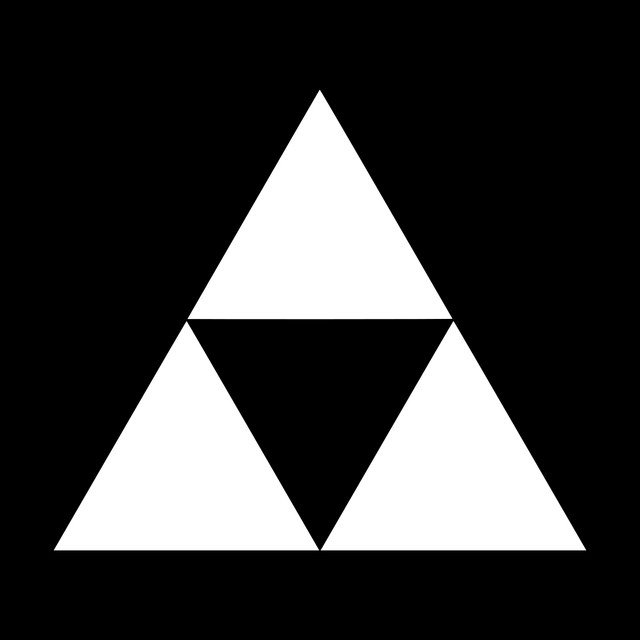第414話 友達5
文字数 3,047文字
神妙な面持ちの星は意を決したように大きく息を吸い込むと、ゆっくりと話し出す。
「……私はゲームの中にいた時に人を……人を殺したんです」
それを聞いたエミルはほっとした様子で胸を撫で下ろすと、俯く星に優しく告げる。
「ゲームで人を殺したからって罪に問われるわけじゃないわ。それに、あんな状況だったんだし。誰もあなたの事を責める人なんていないわよ」
エミルの言葉を聞いた星の脳裏には、1人でテレビを見ていた時のキャスターの言っていた『犯罪者』という言葉と、以前コンビニで自分を襲ってきた男達の言っていた『お前のせいで俺の彼女が眠ったままになった。だから使わせろ』と言っていたのを思い出していた。
当事者じゃないエミルにとっては大したことじゃなくても、星にとってはそういうわけにはいかない。
星はエミルの顔を真っ直ぐに見つめながら。
「……テレビで見ました。私が……私が手を抜いていたから犠牲者が多くなったって――」
責任を感じている星の瞳には涙が溜まっていた。それを隠すように俯く星を見ていたエミルは憤ったように震えた声で呟く。
「そう。そのテレビ局へは苦情を入れて、権力使ってスポンサーを外させなきゃいけないわね……」
星の瞳から流れる涙が水面に浮かぶバラの花びらに当たる。
元々星は人前で泣く性格ではない。それは、人前で泣くことは恥ずかしいことだと思っているからに他ならない。
フリーダムの中では喜怒哀楽を数値化されている為に設定されている数値を超えると自然と表情に現れてしまう。そのせいで普段よりも涙もろくなってしまうは仕方がないのだ――。
無言のまま流れる涙を拭って深呼吸をして気持ちを整え、エミルの顔を見つめながら言った。
「……私は人殺しで、犯罪者で、卑怯者なんです。エミルさんに助けてもらって今があります……でも、私にはそんな価値なんてない。あなたに優しくしてもらえる人間じゃないんです……」
涙で潤んだ星の紫色の瞳は揺らめいていて、そこには覚悟と恐怖、不安なんかが入り混じっているような気がした。
だが、もしもこの場でエミルが星のことを拒絶すれば、星は静かに頷いてどこかに消えてしまうだろう。
それをエミルも理解していた。本当は抱きしめたい気持ちでいっぱいだったが、今の星はそれでは納得しないだろうということも分かっていたし、抱きしめたら壊れてしまうようなほど服を脱いだ星の体は細く小さかった。
「……私は星のそういう真面目なところも好きよ? だけど少し気にしすぎなきがするわ。そんなに気にしなくていいのよ?」
エミルのその言葉を聞いた星は俯いて手をぎゅっと握り締めた。
そんな星を見ていたエミルは湯船から立ち上がって俯いている星の頭を優しく撫でる。すると、星はその手を振り払うように後ろに数歩下がった。
エミルが不思議そうな顔をしていると、星は悲しそうな顔で弱々しく言った。
「――どうして……私に優しくしてくれるんですか? 私がみんなに迷惑をかけて……ゲームをクリアするまでに掛かる時間も掛かっちゃって……なにもうまくできなかったのに……」
「そんな事を気にしなくていいのよ? 私達は星に心から感謝しているの。だって、あなたがいなかったら、私達は皆あのゲームの中から帰ってこれなかったわ。だから感謝してもしきれないわよ」
「……感謝されるなんてありえません」
微笑むエミルに星がそう告げると、俯きながら唇を噛みしめた。
そして、重い口をゆっくりと開いて……。
「――私は今まで人に感謝された事がありません。私が失敗したら周りから責められる……学校でも家でも……だからなんでもできて当たり前なんです。うまくできてれば誰も私を責めないから……でも褒められたいわけじゃない。私は私でいたいだけなんです……最近、ひとりでいるのが怖いんです。私が私じゃなくなるみたいで――私の中のなにかが私を呑み込んでいくような感じで……すごく怖い」
唇を噛みしめる星にエミルがそっと手を伸ばした直後。
「……でも、優しくされるのも怖い。なんだか、自分が別の人になったように感じるんです……私がこんなことされるわけない。私は頑張るから必要とされてるんだって……お母さんがいなくなって、私は頑張る必要がなくなりました。だから……頑張らなくなった私も必要なくなったんです。頑張っても、ゲーム世界を早く終わらせられなかった。エミルさん達ならもっと早く終わらせられたのに! 私は頑張るからって必要とされたいからって剣を手放せなかった! それが大勢の人達を今も苦しめている!」
俯き、手を強く握り締めた星の瞳から涙が溢れ水面に落ちていくつもの波紋を作る。
「私の自分勝手でこんなことになったのに、私はエミルさんから優しくされてる。本当は私が変わってあげないといけないのに……私が眠ったままでいなきゃいけないのに……」
徐々に星の呼吸が早くなり苦しそうに肩で息をし始める。
その直後、体が大きく揺れて前に倒れそれをエミルが受け止めた。
「星!? 大丈夫!! 大丈夫だからゆっくり息をして!!」
「はぁはぁ……私が……私が…………」
星は息が更に激しくなって気を失った。
次に星が目を覚ました時にはバスローブを着てベッドの上に寝かされていた。
目を覚ました星がまず目にしたのは執事の小林の顔だった。整えられた白い髭に優しく微笑む小林は「もう大丈夫です」と言ってエミルの方を見た。
エミルは心配そうな表情で星の側に駆け寄ってくると。
「大丈夫!? 過呼吸になって気を失ったのよ? 脳に後遺症とかあるかもしれないわ! 私が誰だか分かる?」
「……はい。大丈夫です」
星が頷くと、エミルはほっとしたように息を吐いて「良かった」と呟く。
だが、星は複雑そうな顔をして俯いたまま黙ってしまう。
「それでは、私は隣の部屋に戻りますのでまた星お嬢様の体調が悪くなったら呼んでください」
小林は微笑みながらそう言って部屋を出て行った。
部屋に2人だけ残され、しばらくの間は無言でいたが。
「……ごめんなさい。世間の反応を知っていたのに、学校に通わせて星にまた負担をかけてしまっていたわ……これじゃ姉失格ね」
「いえ。私は学校に行けて感謝しています……私には勉強くらいしか取り柄はないですから……」
暗い表情で謝るエミルに、星はそう言葉を返した。
すると、エミルが頭を左右に振ってベッドの上に座っている星の体を抱きしめる。
驚き目を大きくさせている星に、エミルは優しい声音でそっと告げた。
「星のいいところは私がいっぱい知ってるわ。勉強だけじゃない! たまに失敗してかわいいところも優しいところも頑張り屋なところも自分より相手を優先しちゃうところも全部が好き。だけど……頑張りすぎる事と自分を大事にしないのがあなたの悪いところ」
胸に抱きしめた星の頭を撫でてとそう言ったエミル。
「あなたは1人しかいないんだから、大切にしなきゃだめ。人より自分が価値が低いとか考えちゃだめよ? 私は星がいないと、もう生きていけないの……だから、迷惑なんて思った事なんて一度もないわ。安心して」
エミルがそう言って微笑むと、星は信じられないといった感じに眉をひそめた。
星にとっては言葉だけでそれを信じることができなかった。
今までの人生で自分と友好な関係を築いてくれる人間がいなかったのだ。エミルの言葉を信じられないのも無理もない。
俯きながら何も言わない星にエミルは苦笑いを浮かべた。
「……私はゲームの中にいた時に人を……人を殺したんです」
それを聞いたエミルはほっとした様子で胸を撫で下ろすと、俯く星に優しく告げる。
「ゲームで人を殺したからって罪に問われるわけじゃないわ。それに、あんな状況だったんだし。誰もあなたの事を責める人なんていないわよ」
エミルの言葉を聞いた星の脳裏には、1人でテレビを見ていた時のキャスターの言っていた『犯罪者』という言葉と、以前コンビニで自分を襲ってきた男達の言っていた『お前のせいで俺の彼女が眠ったままになった。だから使わせろ』と言っていたのを思い出していた。
当事者じゃないエミルにとっては大したことじゃなくても、星にとってはそういうわけにはいかない。
星はエミルの顔を真っ直ぐに見つめながら。
「……テレビで見ました。私が……私が手を抜いていたから犠牲者が多くなったって――」
責任を感じている星の瞳には涙が溜まっていた。それを隠すように俯く星を見ていたエミルは憤ったように震えた声で呟く。
「そう。そのテレビ局へは苦情を入れて、権力使ってスポンサーを外させなきゃいけないわね……」
星の瞳から流れる涙が水面に浮かぶバラの花びらに当たる。
元々星は人前で泣く性格ではない。それは、人前で泣くことは恥ずかしいことだと思っているからに他ならない。
フリーダムの中では喜怒哀楽を数値化されている為に設定されている数値を超えると自然と表情に現れてしまう。そのせいで普段よりも涙もろくなってしまうは仕方がないのだ――。
無言のまま流れる涙を拭って深呼吸をして気持ちを整え、エミルの顔を見つめながら言った。
「……私は人殺しで、犯罪者で、卑怯者なんです。エミルさんに助けてもらって今があります……でも、私にはそんな価値なんてない。あなたに優しくしてもらえる人間じゃないんです……」
涙で潤んだ星の紫色の瞳は揺らめいていて、そこには覚悟と恐怖、不安なんかが入り混じっているような気がした。
だが、もしもこの場でエミルが星のことを拒絶すれば、星は静かに頷いてどこかに消えてしまうだろう。
それをエミルも理解していた。本当は抱きしめたい気持ちでいっぱいだったが、今の星はそれでは納得しないだろうということも分かっていたし、抱きしめたら壊れてしまうようなほど服を脱いだ星の体は細く小さかった。
「……私は星のそういう真面目なところも好きよ? だけど少し気にしすぎなきがするわ。そんなに気にしなくていいのよ?」
エミルのその言葉を聞いた星は俯いて手をぎゅっと握り締めた。
そんな星を見ていたエミルは湯船から立ち上がって俯いている星の頭を優しく撫でる。すると、星はその手を振り払うように後ろに数歩下がった。
エミルが不思議そうな顔をしていると、星は悲しそうな顔で弱々しく言った。
「――どうして……私に優しくしてくれるんですか? 私がみんなに迷惑をかけて……ゲームをクリアするまでに掛かる時間も掛かっちゃって……なにもうまくできなかったのに……」
「そんな事を気にしなくていいのよ? 私達は星に心から感謝しているの。だって、あなたがいなかったら、私達は皆あのゲームの中から帰ってこれなかったわ。だから感謝してもしきれないわよ」
「……感謝されるなんてありえません」
微笑むエミルに星がそう告げると、俯きながら唇を噛みしめた。
そして、重い口をゆっくりと開いて……。
「――私は今まで人に感謝された事がありません。私が失敗したら周りから責められる……学校でも家でも……だからなんでもできて当たり前なんです。うまくできてれば誰も私を責めないから……でも褒められたいわけじゃない。私は私でいたいだけなんです……最近、ひとりでいるのが怖いんです。私が私じゃなくなるみたいで――私の中のなにかが私を呑み込んでいくような感じで……すごく怖い」
唇を噛みしめる星にエミルがそっと手を伸ばした直後。
「……でも、優しくされるのも怖い。なんだか、自分が別の人になったように感じるんです……私がこんなことされるわけない。私は頑張るから必要とされてるんだって……お母さんがいなくなって、私は頑張る必要がなくなりました。だから……頑張らなくなった私も必要なくなったんです。頑張っても、ゲーム世界を早く終わらせられなかった。エミルさん達ならもっと早く終わらせられたのに! 私は頑張るからって必要とされたいからって剣を手放せなかった! それが大勢の人達を今も苦しめている!」
俯き、手を強く握り締めた星の瞳から涙が溢れ水面に落ちていくつもの波紋を作る。
「私の自分勝手でこんなことになったのに、私はエミルさんから優しくされてる。本当は私が変わってあげないといけないのに……私が眠ったままでいなきゃいけないのに……」
徐々に星の呼吸が早くなり苦しそうに肩で息をし始める。
その直後、体が大きく揺れて前に倒れそれをエミルが受け止めた。
「星!? 大丈夫!! 大丈夫だからゆっくり息をして!!」
「はぁはぁ……私が……私が…………」
星は息が更に激しくなって気を失った。
次に星が目を覚ました時にはバスローブを着てベッドの上に寝かされていた。
目を覚ました星がまず目にしたのは執事の小林の顔だった。整えられた白い髭に優しく微笑む小林は「もう大丈夫です」と言ってエミルの方を見た。
エミルは心配そうな表情で星の側に駆け寄ってくると。
「大丈夫!? 過呼吸になって気を失ったのよ? 脳に後遺症とかあるかもしれないわ! 私が誰だか分かる?」
「……はい。大丈夫です」
星が頷くと、エミルはほっとしたように息を吐いて「良かった」と呟く。
だが、星は複雑そうな顔をして俯いたまま黙ってしまう。
「それでは、私は隣の部屋に戻りますのでまた星お嬢様の体調が悪くなったら呼んでください」
小林は微笑みながらそう言って部屋を出て行った。
部屋に2人だけ残され、しばらくの間は無言でいたが。
「……ごめんなさい。世間の反応を知っていたのに、学校に通わせて星にまた負担をかけてしまっていたわ……これじゃ姉失格ね」
「いえ。私は学校に行けて感謝しています……私には勉強くらいしか取り柄はないですから……」
暗い表情で謝るエミルに、星はそう言葉を返した。
すると、エミルが頭を左右に振ってベッドの上に座っている星の体を抱きしめる。
驚き目を大きくさせている星に、エミルは優しい声音でそっと告げた。
「星のいいところは私がいっぱい知ってるわ。勉強だけじゃない! たまに失敗してかわいいところも優しいところも頑張り屋なところも自分より相手を優先しちゃうところも全部が好き。だけど……頑張りすぎる事と自分を大事にしないのがあなたの悪いところ」
胸に抱きしめた星の頭を撫でてとそう言ったエミル。
「あなたは1人しかいないんだから、大切にしなきゃだめ。人より自分が価値が低いとか考えちゃだめよ? 私は星がいないと、もう生きていけないの……だから、迷惑なんて思った事なんて一度もないわ。安心して」
エミルがそう言って微笑むと、星は信じられないといった感じに眉をひそめた。
星にとっては言葉だけでそれを信じることができなかった。
今までの人生で自分と友好な関係を築いてくれる人間がいなかったのだ。エミルの言葉を信じられないのも無理もない。
俯きながら何も言わない星にエミルは苦笑いを浮かべた。