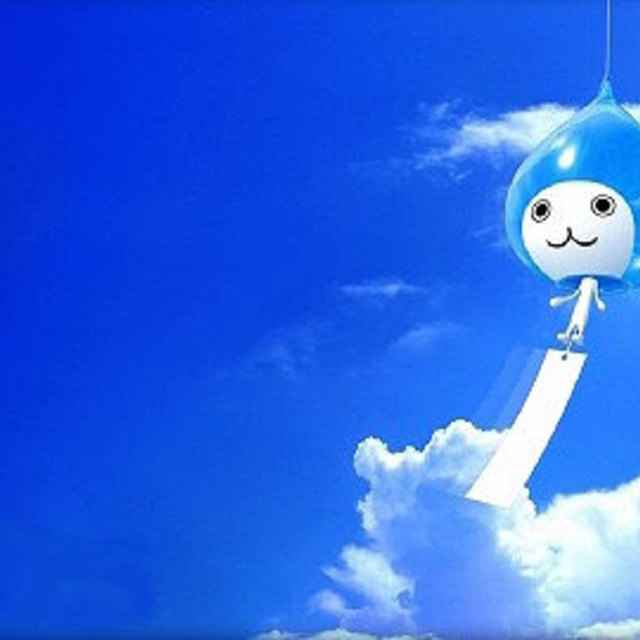5. How to create biz 一念あるのみ。
文字数 2,216文字
仕事は人間を作る。これは確かなことだ。また、環境が人を育てるというのも正しい。商社での絶対評価は「注文を取って来れるかどうか」これがすべてだった。「どれだけ稼げるか」だ。ボクは、Offer をいくら繰り返しても注文は中々取れなかった。決していい加減に仕事をしていた訳ではなかった。「上司が無謀な利益を求めてくるのから」「引合が合見積で、立場が二番手以下だから」「仕入れ先が、いい値段を出してくれないから」...、そんな(真っ当な)理屈に意味はなかった。理屈を越えて注文をとってくるのが環境からの求めだった。「じゃあ、どうやって?」...。
しょぼい注文しか取れないのを見かねて八藤丸さんはボクに「いい加減にL/Cをとってこいや!」と不満をストレートにぶつけてくるようになる。入社して半年ぐらいのころだ。*L/Cは大口の注文の意味。どちらかと言うと悠長に過ごしていたのだが、自分の立場が、かなり危うくなっていることをボクは悟る。他の男性二人は、ボクとは違う形で仕事を進めていた。小西は韓国のオファー商との関係を既に多く担当していた。燕は中国関係のラインをいろいろやっていた。彼らは絶えず優越感を確認するべく、ボクを意識した振る舞いが常態になっていた。ボクには、いろいろと個人的に制約があり、動揺を覚えることが多かった。結果、気分的に滅入ることが多くなる。会社内でのボクの位置は、彼らによって巧みに操作され、貶められていってた。やがては彼らの雑務までやらざるを得ないようになる。*彼らが出張がある時は、[協力]との名目で彼らの担当のOffer までさせられていた。社長も副社長も気付いているだろうが、「我関せず」の姿勢だった。これは職場の色合いによる自然な展開でしかないからだ。誰これが悪い、モラルがどうこう言うことになんの意味もない。こうして、弱き者、無能なる稼ぎのないも者は排除されていく仕組みなだけだ。「嫌だったら、頑張れや」が声なき、メッセージであった。回りの女子達の目線も気にはなった。彼女らは各人の立場の位置関係にはしごく敏感であった。「こいつ、恐れるに足らず」とボクを見切り、冷ややかな応対に変わっていく女の子もいた。
「じゃあ、どうやって」この不快なる状況を打開していけばいいのか?理屈では打開策はありえない...。決まっている。[執念]をもってだ。「狂おしいまでに願う」ことによって。この思いを行為で練っていく。あらゆる仕事のスピードを極端に上げる。無駄な見積/事務の積み重ねでさえ、思いを練り高めていく為の因(よすが)とする。寝ても覚めても大口の受注を願う。すると、結果、思いもしない展開が発生してくる。理屈に沿わない展開が現れてくる。呼んでもいない郵便の集荷係がタイミングよく事務所に顔を出す。他人の思考を一瞬ではあるが共有してしまう。
いろいろ不思議な展開があったのだが、やっぱり会社の色合いが大きな制約になると思った。それは、ボク自身の色合いとのマッチングがどうかということだ。やがては大口の注文もとれたが、何故か障害が、そこには何時も潜んでいた。バングラからの中古の繊維加工ラインでは、大切なパーツが調達不可能との知らせが、L/Cの到着後に届く。中東向けの電子鍵の受注では、メーカーの貿易部が、遅れて物言いをして来た。こちらに渡せと。既に受注は完了していたのに。あまりの障害の多さに、自分の性なのか?、との思いもあったが。直感は、この理晃という会社の傾向が、ボクには合わないからとの理由を告げていた。
『美味い仕事は残ってないで〜』は、社長の林さんのよく言う言葉だった。この会社の強みは、繊維加工において、[日本品質]の実体を機械からケミカルまで熟知した人間が二人いることだった。更には京都にある西陣を基盤とした大口/中小の機械、ケミカルの両メーカーとの関係があったことによる。海外からは、とても魅力的な技術ノウハウの窓口であり、海外へモノ売ることを望む日本のメーカーからすると頼りになる営業代理だった。
商談の要所は現地の夜の接待の場である。日本から連れて行くのは先ず社長クラス。この人達を最後、値段を妥協させるのが役割だ。説得力が必要になる。深夜に、どれだけの時間と手間をかけて行われるのかは筆舌に尽くしがたい。そりゃ、胃の半分も切除になる訳だ。とあるメーカーの二代目の社長に「あんたは吸血鬼だ」と言われたそうだ。
こうして取引が定まって定期で流れだすと、やがては違う問題が起ってくる。少しでも利幅をとりたいという思いからの、中抜き工作だ。買手と売手が相互に確認された時点で、理晃の関与は無用なるものと見なされていく。信義も義理もあったものではない。
理晃の次の会社での話にはなるが、高卒の女の子たちがアクセル全開で仕事を続ける中、やがて臭い立つほどの生気のオーラを放つようになっていく様を見て驚くととになる。彼女らは容姿の関係なく、みるみる魅力的になっていった。営業の補佐的な仕事で、激務ではあったが、頼りとされていること、女子は各部署では自分一人であったこと、また彼女らの潜在能力が実は、かなり高かったことも関係してたのだがろうが、その変化には目を見はるものがあった。みんな私服で、高いヒールを履いて会社を闊歩しまくっていた。世に言うアムラーの群れである。
しょぼい注文しか取れないのを見かねて八藤丸さんはボクに「いい加減にL/Cをとってこいや!」と不満をストレートにぶつけてくるようになる。入社して半年ぐらいのころだ。*L/Cは大口の注文の意味。どちらかと言うと悠長に過ごしていたのだが、自分の立場が、かなり危うくなっていることをボクは悟る。他の男性二人は、ボクとは違う形で仕事を進めていた。小西は韓国のオファー商との関係を既に多く担当していた。燕は中国関係のラインをいろいろやっていた。彼らは絶えず優越感を確認するべく、ボクを意識した振る舞いが常態になっていた。ボクには、いろいろと個人的に制約があり、動揺を覚えることが多かった。結果、気分的に滅入ることが多くなる。会社内でのボクの位置は、彼らによって巧みに操作され、貶められていってた。やがては彼らの雑務までやらざるを得ないようになる。*彼らが出張がある時は、[協力]との名目で彼らの担当のOffer までさせられていた。社長も副社長も気付いているだろうが、「我関せず」の姿勢だった。これは職場の色合いによる自然な展開でしかないからだ。誰これが悪い、モラルがどうこう言うことになんの意味もない。こうして、弱き者、無能なる稼ぎのないも者は排除されていく仕組みなだけだ。「嫌だったら、頑張れや」が声なき、メッセージであった。回りの女子達の目線も気にはなった。彼女らは各人の立場の位置関係にはしごく敏感であった。「こいつ、恐れるに足らず」とボクを見切り、冷ややかな応対に変わっていく女の子もいた。
「じゃあ、どうやって」この不快なる状況を打開していけばいいのか?理屈では打開策はありえない...。決まっている。[執念]をもってだ。「狂おしいまでに願う」ことによって。この思いを行為で練っていく。あらゆる仕事のスピードを極端に上げる。無駄な見積/事務の積み重ねでさえ、思いを練り高めていく為の因(よすが)とする。寝ても覚めても大口の受注を願う。すると、結果、思いもしない展開が発生してくる。理屈に沿わない展開が現れてくる。呼んでもいない郵便の集荷係がタイミングよく事務所に顔を出す。他人の思考を一瞬ではあるが共有してしまう。
いろいろ不思議な展開があったのだが、やっぱり会社の色合いが大きな制約になると思った。それは、ボク自身の色合いとのマッチングがどうかということだ。やがては大口の注文もとれたが、何故か障害が、そこには何時も潜んでいた。バングラからの中古の繊維加工ラインでは、大切なパーツが調達不可能との知らせが、L/Cの到着後に届く。中東向けの電子鍵の受注では、メーカーの貿易部が、遅れて物言いをして来た。こちらに渡せと。既に受注は完了していたのに。あまりの障害の多さに、自分の性なのか?、との思いもあったが。直感は、この理晃という会社の傾向が、ボクには合わないからとの理由を告げていた。
『美味い仕事は残ってないで〜』は、社長の林さんのよく言う言葉だった。この会社の強みは、繊維加工において、[日本品質]の実体を機械からケミカルまで熟知した人間が二人いることだった。更には京都にある西陣を基盤とした大口/中小の機械、ケミカルの両メーカーとの関係があったことによる。海外からは、とても魅力的な技術ノウハウの窓口であり、海外へモノ売ることを望む日本のメーカーからすると頼りになる営業代理だった。
商談の要所は現地の夜の接待の場である。日本から連れて行くのは先ず社長クラス。この人達を最後、値段を妥協させるのが役割だ。説得力が必要になる。深夜に、どれだけの時間と手間をかけて行われるのかは筆舌に尽くしがたい。そりゃ、胃の半分も切除になる訳だ。とあるメーカーの二代目の社長に「あんたは吸血鬼だ」と言われたそうだ。
こうして取引が定まって定期で流れだすと、やがては違う問題が起ってくる。少しでも利幅をとりたいという思いからの、中抜き工作だ。買手と売手が相互に確認された時点で、理晃の関与は無用なるものと見なされていく。信義も義理もあったものではない。
理晃の次の会社での話にはなるが、高卒の女の子たちがアクセル全開で仕事を続ける中、やがて臭い立つほどの生気のオーラを放つようになっていく様を見て驚くととになる。彼女らは容姿の関係なく、みるみる魅力的になっていった。営業の補佐的な仕事で、激務ではあったが、頼りとされていること、女子は各部署では自分一人であったこと、また彼女らの潜在能力が実は、かなり高かったことも関係してたのだがろうが、その変化には目を見はるものがあった。みんな私服で、高いヒールを履いて会社を闊歩しまくっていた。世に言うアムラーの群れである。