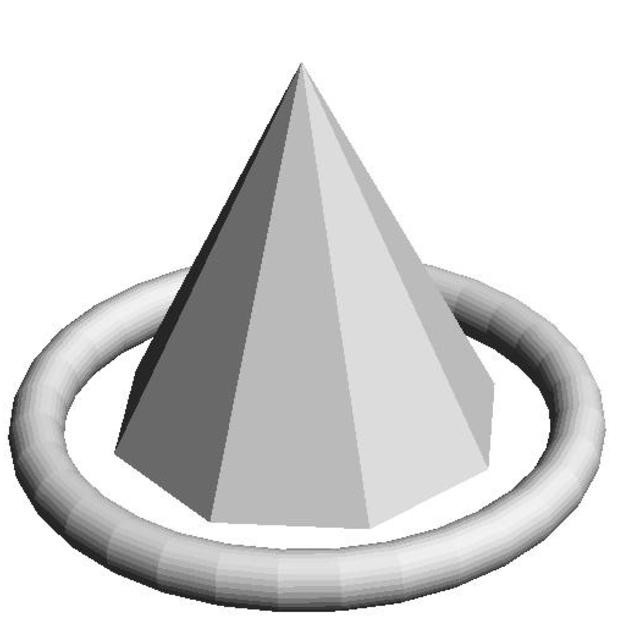優しくない姉上
文字数 3,289文字
摂政府。はじめは誇らしかったこの建物が、今は張りぼてに見える。
出陣を翌朝に迎え、ここでは宴が催される予定だった。
黒繭家の親族を集め、親交のある貴族にも招待状を送ってありったけの人数を揃える。その人たちに、盛大に送り出してもらいたい。
せめて一度くらい、主役になりたかった。次男でも立会人でもない場の中心として、ちやほやされたかったのだ。最後の宴になるかもしれないのだから。
誰も来なかった。
空の大広間でサキは頭を抱える。大ぶりの机に、椅子は三十も余っている。
「これは寂しいですね」
ニコラが言って、メイドに集めさせたぬいぐるみで席を埋めた。
泣きたい。
「こんなの予想外です。僕って、こんなに嫌われていたんですか」
「そんなことはないですよ」
ニコラが弁護してくれる。
「とくに好かれていなかった、というだけです」
消えたい。
いや、事情は理解できる。革命軍が攻め寄せてくるのだから、皆、避難の準備に忙しいのだろう。
だとしても、だ。その革命軍と戦うために命をかけるのはこの自分なのだから、少しは時間を割いてほしかった。
楽団も用意していたのだが、盛り上がる可能性のない宴席のため、彼らの避難も遅らせるのは忍びないため、帰らせた。使用人も最低限の人員だけ残している。
「残念ですが、私たちだけで食事にしましょう」あたため直したミルヒライスをニコラは顎で示す。
「待って。父上は?」
「お父様もいらっしゃいません」
さも当然のような姉の口ぶりだった。
「来ないって」サキは信じられない。
「翌朝死地に向かう息子と夕食をとる以上の重大事ってなんですか」
「劇団の方たちを避難させる手助けです。ほうぼう手を尽くして、通行証を調達したり、道中で強盗から守ってあげるための警備を雇ったり――」
「息子より劇団が大事」
「お父様程度の権力では、あなたを助けることはできない。しかし劇団員にならできることがある、というご判断なのでしょう」
ニコラの口調には父親に対する失望と軽蔑が漂っていたが、サキの憤懣はその比ではない。
「もういやだ」
「がまん」「せきにん」といった文字がぺらぺらに吹き飛んだ。
「摂政なんて、やめる。出陣も断ります」
「それは不可能だという説明を受けてきたのでは?」
料理に手をつけようとしていたニコラは、フォークを傍らのぬいぐるみに突き刺した。
現実から逃げるなという一刺しだ。
「なんとかできないでしょうか。避難する劇団員に紛れて逃げるとか。荷物に隠れるとか」
これまで散々軽蔑してきた父親にすがらざるを得ない状況を、少年は恥じる。だが、なりふり構っていられない。
「無理でしょうね」
姉は首を横に振った。
「宴の招待状を送りましたよね。そのとき、見たのです。招待状を運ぶ馬車が、門の前で武装した兵士に臨検されていました」
「それって」気が遠くなりそうだ。
「確かめたのでしょうね。あなたが隠れていないか。貴方を通さないために厳戒態勢が敷かれている」
姉の言葉は硬い。
「当然の判断でしょう。サキが摂政の地位に登ったことは、すでに新聞等にも書き立てられています。それが逃げ出すようでは、ルイ十六世と同じになってしまいます」
「じゃあこのまま、脱出を強行したら……」サキは自分で自分の喉を掴んだ。
「そうですね。離宮行きですね」
「やめてくださいその表現」
サキは頭を抱える。自分を始末したら、病死とか革命軍に暗殺されたとか、適当にでっちあげるのだろう。そして次の操り人形を立てる。
「姉上」
サキは悲嘆を絞り出す。
「僕、そんなに愚かでしたか。ほぼ死ぬような状況に追い込まれるくらいに、僕の選択は愚劣極まりないものだったでしょうか」
「そこまでとは思いません」姉は瞑目して言う。
「最初に摂政の話が来た時点では、革命軍の宣戦布告さえまだでしたから。あなたを使い捨てにする話が持ち上がったのは、ここ二・三日のことでしょう。私の責任です。私が楽観的過ぎました。あなたを縛ってでも、薬を飲ませてでも、摂政にはさせるべきではありませんでした……」
頭を少し傾ける姉に、サキは何とも返せなかった。
「姉上、僕は嫌です。恐ろしいのも、痛いのも嫌です」
自分でもバカみたいなことを口にしているが、弱音が止まらない。
「そもそも楽をしたい、上に立ちたい、えらくなりたいのが人間の性分というものでしょう。そうしてくれると誘われたら、それは飛びつきます。なのにどうして、こんな、こんな……」
ぬいぐるみをたたく。
「サキ」
声が優しくなった。不穏さを感じて、サキは姉を見る。
「おそろしいのはいやなんですね。いたいのもいやなのですね」
「はい……」
「サキ、わたしは色々な薬物を調合しています」
少年は寒気を感じた。
服毒死を薦める姉に対してではない。
姉に、そこまで決意させたこの状況の切迫に対してだ。
「そこまで塞がっているんですか」
まだ十五年も過ぎていない自分の人生が、たった一つの選択によって閉ざされようとしている。
姉は両手をサキの肩に乗せた。
「私は戦場を知りません。このまま戦場に出ることが、どのくらいの確率で死に繋がるものか、明言はできないのです。サキ、貴方が自分の悪運を信じるのであれば」
サキの両肩に、ニコラの気遣いがずしりと染みた。
「戦場に向かうべきです。生き残ったなら、本物の権力だって手に入るかもしれません」
サキの脳内に、天秤が現れた。枯れ木で組み上げたような、何の信頼性もない天秤だ。
薬を仰いだら、死が訪れるのは確実だ。戦場へ赴いたなら、生き残る目は残っている。しかし苦痛と恐怖の果てに、やっぱり命を落とすかもしれない。
「街を見たいです」
馬車を手配して、サキは姉と一緒に摂政府の門を出た。監視していたらしい騎兵数騎が付いてくる。いずれも眼光が鋭く、出し抜くのは不可能と思われた。
街中は、すでに避難を開始した市民の荷車で混みあっていた。途中で馬車を帰らせ、歩く。監視役の兵士がいるのだから、ある意味安全だ。
意図もなく歩き回る内に、少年は実家の門前にたどり着いていた。闘技場・黒繭劇場・虹色の屋台を含む、趣味の悪いおもちゃ箱みたいな侯爵邸の敷地。
内部は閑散としていた。大半の関係者は避難を済ませたらしい。忘れ物でもあったのか、数台の荷車がすれ違いに門を出て行った。
これほど人気の少ない領内を見るのは初めてだった。
樽風呂の屋台も、劇場の入場券売り場も、客引きの一人も見当たらない。
「静かですね、姉上」
緩い風に吹かれて、かさかさとチラシが転がってきた。明日の公演予定だ。こういう場合、前売り券の払い戻しはどうなるのだろう。
「ザッカーヘルズ」
ふいにサキは、幼児にもらった菓子を思いだした。
「ザッカーヘルズが食べたい。屋台の場所、教えて下さい姉上」
「闘技場から見て仮面売りの屋台が途切れる右側です。ですが、もう閉まっているのでは?」
一抹の期待を胸に、「閉店」の看板が連なる軒先を急ぐ。
心臓にしか見えない菓子を描いたザッカーヘルズの看板。やはり閉店の張り紙が揺れていた。
屋台の前にある小さな机に菓子の名残らしき桃色の欠片が残っていたが、風にぐずぐずと崩れ、地面に零れた。
もう一度、食べてみたかった。
屋台の連なり、黒繭劇場、闘技場――三百六十度全てをサキは凝視する。
嫌いだった。つくりものの世界。けばけばしい出し物。安っぽい娯楽に魅せられはしゃぐ大衆たち。
無くなってしまえ、とさえ願っていた。
その願望は、現実のものとなる。明日か明後日には革命軍が王都に至るだろう。ここにある色々なものは、「決闘の王子」という文化を構成している諸要素だ。間違いなく、壊される。避難した俳優たちも、どれくらい逃げおおせるものか分かったものではない。
嫌いだった。今も大嫌いだ。それなのに。
見捨てることができない。
出陣を翌朝に迎え、ここでは宴が催される予定だった。
黒繭家の親族を集め、親交のある貴族にも招待状を送ってありったけの人数を揃える。その人たちに、盛大に送り出してもらいたい。
せめて一度くらい、主役になりたかった。次男でも立会人でもない場の中心として、ちやほやされたかったのだ。最後の宴になるかもしれないのだから。
誰も来なかった。
空の大広間でサキは頭を抱える。大ぶりの机に、椅子は三十も余っている。
「これは寂しいですね」
ニコラが言って、メイドに集めさせたぬいぐるみで席を埋めた。
泣きたい。
「こんなの予想外です。僕って、こんなに嫌われていたんですか」
「そんなことはないですよ」
ニコラが弁護してくれる。
「とくに好かれていなかった、というだけです」
消えたい。
いや、事情は理解できる。革命軍が攻め寄せてくるのだから、皆、避難の準備に忙しいのだろう。
だとしても、だ。その革命軍と戦うために命をかけるのはこの自分なのだから、少しは時間を割いてほしかった。
楽団も用意していたのだが、盛り上がる可能性のない宴席のため、彼らの避難も遅らせるのは忍びないため、帰らせた。使用人も最低限の人員だけ残している。
「残念ですが、私たちだけで食事にしましょう」あたため直したミルヒライスをニコラは顎で示す。
「待って。父上は?」
「お父様もいらっしゃいません」
さも当然のような姉の口ぶりだった。
「来ないって」サキは信じられない。
「翌朝死地に向かう息子と夕食をとる以上の重大事ってなんですか」
「劇団の方たちを避難させる手助けです。ほうぼう手を尽くして、通行証を調達したり、道中で強盗から守ってあげるための警備を雇ったり――」
「息子より劇団が大事」
「お父様程度の権力では、あなたを助けることはできない。しかし劇団員にならできることがある、というご判断なのでしょう」
ニコラの口調には父親に対する失望と軽蔑が漂っていたが、サキの憤懣はその比ではない。
「もういやだ」
「がまん」「せきにん」といった文字がぺらぺらに吹き飛んだ。
「摂政なんて、やめる。出陣も断ります」
「それは不可能だという説明を受けてきたのでは?」
料理に手をつけようとしていたニコラは、フォークを傍らのぬいぐるみに突き刺した。
現実から逃げるなという一刺しだ。
「なんとかできないでしょうか。避難する劇団員に紛れて逃げるとか。荷物に隠れるとか」
これまで散々軽蔑してきた父親にすがらざるを得ない状況を、少年は恥じる。だが、なりふり構っていられない。
「無理でしょうね」
姉は首を横に振った。
「宴の招待状を送りましたよね。そのとき、見たのです。招待状を運ぶ馬車が、門の前で武装した兵士に臨検されていました」
「それって」気が遠くなりそうだ。
「確かめたのでしょうね。あなたが隠れていないか。貴方を通さないために厳戒態勢が敷かれている」
姉の言葉は硬い。
「当然の判断でしょう。サキが摂政の地位に登ったことは、すでに新聞等にも書き立てられています。それが逃げ出すようでは、ルイ十六世と同じになってしまいます」
「じゃあこのまま、脱出を強行したら……」サキは自分で自分の喉を掴んだ。
「そうですね。離宮行きですね」
「やめてくださいその表現」
サキは頭を抱える。自分を始末したら、病死とか革命軍に暗殺されたとか、適当にでっちあげるのだろう。そして次の操り人形を立てる。
「姉上」
サキは悲嘆を絞り出す。
「僕、そんなに愚かでしたか。ほぼ死ぬような状況に追い込まれるくらいに、僕の選択は愚劣極まりないものだったでしょうか」
「そこまでとは思いません」姉は瞑目して言う。
「最初に摂政の話が来た時点では、革命軍の宣戦布告さえまだでしたから。あなたを使い捨てにする話が持ち上がったのは、ここ二・三日のことでしょう。私の責任です。私が楽観的過ぎました。あなたを縛ってでも、薬を飲ませてでも、摂政にはさせるべきではありませんでした……」
頭を少し傾ける姉に、サキは何とも返せなかった。
「姉上、僕は嫌です。恐ろしいのも、痛いのも嫌です」
自分でもバカみたいなことを口にしているが、弱音が止まらない。
「そもそも楽をしたい、上に立ちたい、えらくなりたいのが人間の性分というものでしょう。そうしてくれると誘われたら、それは飛びつきます。なのにどうして、こんな、こんな……」
ぬいぐるみをたたく。
「サキ」
声が優しくなった。不穏さを感じて、サキは姉を見る。
「おそろしいのはいやなんですね。いたいのもいやなのですね」
「はい……」
「サキ、わたしは色々な薬物を調合しています」
少年は寒気を感じた。
服毒死を薦める姉に対してではない。
姉に、そこまで決意させたこの状況の切迫に対してだ。
「そこまで塞がっているんですか」
まだ十五年も過ぎていない自分の人生が、たった一つの選択によって閉ざされようとしている。
姉は両手をサキの肩に乗せた。
「私は戦場を知りません。このまま戦場に出ることが、どのくらいの確率で死に繋がるものか、明言はできないのです。サキ、貴方が自分の悪運を信じるのであれば」
サキの両肩に、ニコラの気遣いがずしりと染みた。
「戦場に向かうべきです。生き残ったなら、本物の権力だって手に入るかもしれません」
サキの脳内に、天秤が現れた。枯れ木で組み上げたような、何の信頼性もない天秤だ。
薬を仰いだら、死が訪れるのは確実だ。戦場へ赴いたなら、生き残る目は残っている。しかし苦痛と恐怖の果てに、やっぱり命を落とすかもしれない。
「街を見たいです」
馬車を手配して、サキは姉と一緒に摂政府の門を出た。監視していたらしい騎兵数騎が付いてくる。いずれも眼光が鋭く、出し抜くのは不可能と思われた。
街中は、すでに避難を開始した市民の荷車で混みあっていた。途中で馬車を帰らせ、歩く。監視役の兵士がいるのだから、ある意味安全だ。
意図もなく歩き回る内に、少年は実家の門前にたどり着いていた。闘技場・黒繭劇場・虹色の屋台を含む、趣味の悪いおもちゃ箱みたいな侯爵邸の敷地。
内部は閑散としていた。大半の関係者は避難を済ませたらしい。忘れ物でもあったのか、数台の荷車がすれ違いに門を出て行った。
これほど人気の少ない領内を見るのは初めてだった。
樽風呂の屋台も、劇場の入場券売り場も、客引きの一人も見当たらない。
「静かですね、姉上」
緩い風に吹かれて、かさかさとチラシが転がってきた。明日の公演予定だ。こういう場合、前売り券の払い戻しはどうなるのだろう。
「ザッカーヘルズ」
ふいにサキは、幼児にもらった菓子を思いだした。
「ザッカーヘルズが食べたい。屋台の場所、教えて下さい姉上」
「闘技場から見て仮面売りの屋台が途切れる右側です。ですが、もう閉まっているのでは?」
一抹の期待を胸に、「閉店」の看板が連なる軒先を急ぐ。
心臓にしか見えない菓子を描いたザッカーヘルズの看板。やはり閉店の張り紙が揺れていた。
屋台の前にある小さな机に菓子の名残らしき桃色の欠片が残っていたが、風にぐずぐずと崩れ、地面に零れた。
もう一度、食べてみたかった。
屋台の連なり、黒繭劇場、闘技場――三百六十度全てをサキは凝視する。
嫌いだった。つくりものの世界。けばけばしい出し物。安っぽい娯楽に魅せられはしゃぐ大衆たち。
無くなってしまえ、とさえ願っていた。
その願望は、現実のものとなる。明日か明後日には革命軍が王都に至るだろう。ここにある色々なものは、「決闘の王子」という文化を構成している諸要素だ。間違いなく、壊される。避難した俳優たちも、どれくらい逃げおおせるものか分かったものではない。
嫌いだった。今も大嫌いだ。それなのに。
見捨てることができない。