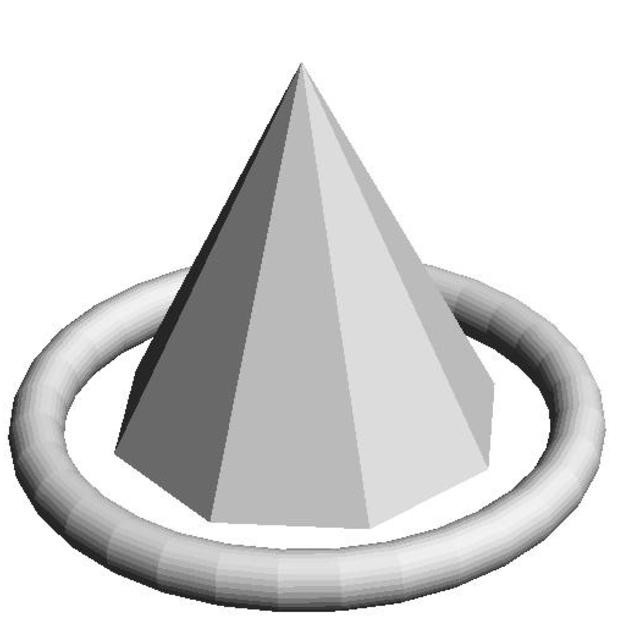戦場の歌
文字数 5,238文字
旅団の手綱を握るのが指揮官の役目。だが何千という兵士を操る長大な手綱など存在しない。
そのため伝令や文書やハリネズミの布陣図が代用品となるわけだが、指揮官の感傷までを伝えることは難しい。何としても前進するのだという気迫、あるいはさっさと退がれという焦慮、それらを染み渡らせるためには、本能に訴える賑やかさが必要だ。けたたましい太鼓。猥雑な遊び笛。音楽は使い勝手のいい伝令だ。無教養な兵士でも関係ない。
そういうわけで軍隊には楽団があてがわれ、兵士の背を蹴りつける役目を担っている。
軍楽隊・鼓笛隊――呼び名は様々だが、奏でる楽曲には、単純かつ人口に膾炙しているものが求められる。楽団が千切れ飛んでも、鼓膜が少々傷ついても聞き分けれる図太さを備えていなければ、砲声にかき消されてしまうからだ。
前線へ向かう途中で、サキは鼓笛隊から予備の遊び笛を借りた。遊び笛(ルーダン)は子供でも数日で吹きこなすことのできる単純なつくりの横笛だ。黒眉家の劇場でも使用される楽器なので、サキも吹き方は心得ていた。
前線の楽団に混ざり、遊び笛を奏でることで兵士の士気を上げようというのが、サキの目論見だった。ただ、前線にやってきて、「頑張れ」と叫ぶだけで効果があると考えるほど、サキは馬鹿ではない。前線とは言え、楽団は歩兵に比べれば安全な位置にいる。自身の勇気と、命惜しさを秤にかけて、サキが見出した妥協点だった。ところが、
「楽団はこちらにございません」
たまたま前線で出会ったフランケンが申し訳なさそうに言った。前線とは言え、敵の攻撃が一時的に止んでいる状況のようで、弾は飛び交っていない。
「砲弾が反れまして、運悪く楽団を直撃したのです。もう、合奏できる人数が残っておりませんので、演奏は、隣の隊の楽団にまかせることになりました」
まずい。
サキはやってくる部隊を間違えたのだ。まさか、楽団が機能していない部隊を選んでしまうとは。「じゃあ、楽団がいるところへ行くから」というわけにはいかない。すでに周囲の兵士が、摂政殿下が前線にいらっしゃったと騒ぎ始めているのだ。ここで何もしないで踵を返しては、「のこのこ前に出てきたと思ったら、臆病風に吹かれてすぐにどこかへ帰った」という印象を与えてしまう。まるで逆効果だ。
他所へ移るにしても、何かしてからでないと恰好がつかない。
「前線の士気を上げに来たんだけど、いいやり方はないかな」フランケンに小声で尋ねる。首を捻りつつ、老兵は右斜め前方を指さした。
「あの一帯ですが、最前列に並ぶ横隊の位置が、敵陣から離れすぎております」
フランケンに言われた場所を見ると、横隊の前方に地面を削った線がある。兵士が並ぶべき位置を示しているらしいが、全員、その手前で踏みとどまっているようだ。その位置までが緩い上り坂になっており、そこに立つことが恐ろしい気持ちは分からないでもなかった。
「本来なら上官がどやしつけて線まで進ませるところですが、現在、前線に穴があいたせいで手が回りません。あちらへ攻撃が再開される前に、誰かが言って聞かせる必要がございます。言って聞かないようであれば」
フランケンは申し訳なさそうな視線をサキに送った。
「誰かが線の場所で立って見せるのが早いでしょうな」
「……それを、僕にやれ、と?」
「やれば、兵士は坊ちゃま殿下に感服するでございましょう」
「けど、あそこに立つってのは」
サキは身震いした。間違いなく目立つ。正真正銘の最前線だ。狙撃されるかもしれない。
しかし、と考え直す。この僕は単なる最高指揮官ではない。国家元首でもある大将は、政治的な意味合いも持っている。狙撃手の判断だけで射殺はされないかもしれないのだ。
やるのなら、今だ。あの場所は現在、砲火にさらされてはいない。さっさと仕事を終えて退がればいい。
「行くしか、ないな」
サキは指揮車から拡声器を取り出した。軍用品ではなく、黒繭家の芝居で稀に使われる高級品だ。装飾をちりばめた大砲のような形状で、牛の頭部くらいのかさばる大きさだが、遠くまで声を響かせることができる。
車を降り、早足で歩く。当然のようについてきたカヤを、最前線の手前で待機させた。兵士たちがサキに敬礼をしながら道を開ける。全員、戸惑いの表情だ。無理もない。サキが横列より前に出ると、どよめきが広がった。
――早まったかもしれない。
サキは早速後悔し始めた。前線の左手から聞こえる砲声が次第に大きくなっている。敵の攻撃が再開されたのだ。
「この小さな丘は、この戦いの要所である!」
勾配の中途当たりでサキは振り返り、拡声器で横列の兵士たちに呼びかけた。適当に言っている。たぶん、そこまでの要所ではない。
「しかるに今、諸君らの意気はくじけ、前へ進めないでいる。減退した兵士の闘志を高めるのも指揮官のつとめ。ゆえに、わたしが手本を示すっ」
言ってしまった。後には退けない。
一歩一歩、サキは勾配を登る。
さあ、だませ。兵隊をだませ。
ここはまだ六十ルーデの外側だ。理屈の上では弾丸も逸れる遠さのはず。だからお前たち、もっと前に出ろ。最低でも僕と並ぶ位置に立たなければ、戦列は意味を成さない。
並べよ。恥ずかしくないのか?僕みたいないたいけな子供を矢面に立たせるつもりか。お前たちは、村々から選ばれた優秀な兵士なんだろう?
まだ数秒。命の空白地で、サキは背後の横列を待った。我慢できずに、振り返る。
兵士たちは元の位置から動いていない。
だめだ、並んでくれない。
出てくるんじゃなかった。僕は死ぬのだな。
涙が出そうになって、目を閉じる。瞼の裏に浮かんだのは、劇場街の風景だった。嫌いだったはずの、浮かれ騒ぐ庶民たちだった。
諦めが、悪あがきに裏返る。
最後に、試してみようと思った。
拡声器を頭の位置まで持ち上げ、敵陣を向いたまま、サキは歌い始めた。
下品な歌を歌って死にたい
下品な歌を歌って死にたい
毎日に振り掛けるような歌
毎日に振り掛けるような歌
背後からどよめきが聞こえる。成功かもしれない、とサキは期待する。
これは、ぺてんだ。兵士との一体感をでっちあげる詐術。お偉い摂政殿下が俺たち庶民の歌を知っていると驚かせて、死なせたくない仲間だと、一緒に六十ルーデの境に立っていい仲間だと勘違いさせたい、まやかしだ。
愛のためじゃなく 夢のためじゃなく
命のためでもなく 希望のためでもなく
寂しい歌だ。しかし案外歌いやすい。
ただ生きているだけで疲れるような
どうしようもない気だるさを慰めるだけの歌
そんな言葉を教えておくれ
そんな音を拾わせておくれ
サキにとって、これは賭けだった。
サキの知っている歌は、音楽の授業で教わる行儀のいい習い歌か、後は「決闘の王子」の劇中歌くらいなもの。
どちらも、末端の兵士を昂ぶらせるにはふさわしくないものだ。
上流階級の歌なんて大抵の兵士は知らないだろうし、黒繭家の息子が「決闘の王子」を歌うなんて当たり前なので、有難くもなんともないだろう。
ここで求められる歌は、サキが知らないだろうと思われているような歌だ。
お偉い摂政殿下が、こんな巷間の歌をご存知だなんて!
俺たちのために歌ってくださるなんて!
そういう心当たりを、少年は一つしか知らなかった。
あの吟遊詩人が奏でてくれた、戦歌。
これなら兵士にも膾炙しているかもしれない。
拡声器を降ろす。ソプラノの残響が収まった直後、泣き声が聞こえた。
「……げひんなうたをうたってしにたい」
違う。歌声だ。銃弾の中で歌など忘れていたに違いない誰かが、しぼりあげるよう応じてくれた、音だ。
「毎日に振り掛けるような歌」
「毎日に振り掛けるような歌」
気配を感じ、左右を見ると、二人の兵士が歌いながら傍らに立っている。六十ルーデに立ってくれた!
二人の合唱は、一瞬の後に波のような大合唱へと変わる。前線が、数歩動いたのだ。後ろを向いたサキは、その光景に圧倒される。見渡す限りの兵士たちによる、不器用な合唱。土誇りに汚れた唇、血泡に染まった唇……戦歌らしくない滑稽な、場違いな歌が、今このときより、全軍の督戦歌に成り上がったのだ。
さらに軍楽隊までもが、同じリズムを奏で始めた。
ぺてん、詐欺の歌。それでもサキの胸中に、熱い灯火が宿る。
前方で枯れ木が弾ぜた。革命軍の突撃が再開されたのだ。
少年は拳を堅く握る。これで目的達成ではない。ここからだ。
「奮い立て諸兵よ。摂政殿下が勇気を示して下さった!」
髭面の士官が、サキの右隣で叫んだ。サーベルを引き抜き、剣舞のように振り回しながら言葉を繰り返す。同時にさりげない掌の動きで、サキを数歩下がらせる。最前線に立ち、士気の高揚に貢献したサキだが、必ずしも先頭に立ち続ける必要はないからだ。その辺りを心得ている士官がいることは、サキを安心させた。
「殿下のお心遣いに我らは全霊でお応えいたします。凶弾飛び交う前線なれど、我ら全力を、全力を注ぎっ!」肥満気味の別の士官が、青筋を立てて叫んだ。
「殿下が毛ほどの傷すら召されることのないよう、お守りすることを誓いまするっ!」
サキは震えた。
おためごかしであることは充分承知している。それでもこんなに心を打たれるのは、生まれて初めてじゃないだろうか。
士官に賛同するように声が上がる。
傍らで、カヤが忙しく木炭を操っていた。
そうか、今の僕は絵になるか。こんなに美しい構図はない。僕は兵士たちに誠意を示し、彼らは衷心で応えてくれた。革命軍がなんだ。散兵突撃がどうした。団結の力で、僕は恐怖を克服したぞ!
サキは拡声器を車に戻して、代わりに天蓋に結い付けられていた国旗を空へ掲げた。これ以上ないほどの万能感が、脳内を満たす。
自分の発案した幻想に取り込まれていることも自覚しているが、抗えない。
「こちらこそ感謝する。そうとも、僕は毛ほども傷つくことはないっ!」
虚勢ではない。サキは気付いていた。すでに敵陣から弾丸が放たれ始めている。最前線より少し引いた位置にいるサキだが、敵がその気になれば、自分を狙い撃ちにすることは可能なはずだ。
それなのに、自分はまだ生きている。
これは奇跡ではない。必然だ。
革命軍は、自分を単純に殺したいというわけではない。「象徴としての」王国君主を討ち取る狙いなのだ。ギロチンの下まで引きずって、革命の勝利を高らかに宣言した後に首を刎ねる。そして「決闘の王子」の首を掲げるのだ。
こんな最前線で、他の兵士と同じように射殺しても劇的ではないのだ。マスケットの弾丸は、当たり所が悪ければ頭部が弾け飛ぶ破壊力だ。この土煙の中で不用意に狙撃でもしたら、誰だか分からない死体が出来上がってしまう。
だから敵兵は、意図的にサキを外している。生け捕りにするという判断が、あるいは判断が難しいので保留にしておくという発想か――とにかく敵の前線指揮官は、サキを殺さないように気を使ってくれている。
味方の兵士に、そこまで事情を推察する余裕はないだろう。だからここにいるサキに感動している。
末端の兵士も王国摂政も、同じ命の線をまたいでいるような勘違いを与え、それが士気高揚に繋がっているのだ。
(なんだ、簡単じゃないか)
気分がよくなった。後ろで怯えていたのが馬鹿みたいだ。危なくないのに危ないふりをして、味方を喜ばせ、前線を硬くする。いい仕事だ、お飾りの君主というものは!
次の瞬間、弾丸が旗の支柱を砕いた。破片がサキの額を削った。
とぷり、血が流れる。毛ほどの傷、どころではない。
「……あっ」
調子に乗っていた。単純な理屈を忘れていた。
射撃はずらしてくれたとしても、破片は避けてくれない。
破片の勢いか、脳みその揺れか、体が傾いた。
兵士たちがサキの周囲に集まる。
「おおー、こんな風に裂けるんだ」
カヤが驚くべき無神経さでスケッチしている。
「ああもう、今のサキ、正面から描きたいのに」革命軍を指さし、カヤが憎々しげに叫んだ。「あいつら邪魔!どっかどけて!」
うん、みんなそう思ってるよ…
「摂政殿下、これを!」髭面の士官が近づいてくる。サキの首を掴み、瓶詰の何かを額に注いだ。注ぎ方が雑すぎる。顔全体が液体に浸される。
「熱っ!」傷口を焼かれているかのようだ。
「ツイカにございます。負傷の直後に傷口に注ぐと、直りが早いとか」
ツイカは李の蒸留酒だ。
それがどうして最前線ですぐさま取り出せる状況にあるのか、サキに追求する余裕はない。酒精か、痛みか。意識が浮沈を繰り返した。
そのため伝令や文書やハリネズミの布陣図が代用品となるわけだが、指揮官の感傷までを伝えることは難しい。何としても前進するのだという気迫、あるいはさっさと退がれという焦慮、それらを染み渡らせるためには、本能に訴える賑やかさが必要だ。けたたましい太鼓。猥雑な遊び笛。音楽は使い勝手のいい伝令だ。無教養な兵士でも関係ない。
そういうわけで軍隊には楽団があてがわれ、兵士の背を蹴りつける役目を担っている。
軍楽隊・鼓笛隊――呼び名は様々だが、奏でる楽曲には、単純かつ人口に膾炙しているものが求められる。楽団が千切れ飛んでも、鼓膜が少々傷ついても聞き分けれる図太さを備えていなければ、砲声にかき消されてしまうからだ。
前線へ向かう途中で、サキは鼓笛隊から予備の遊び笛を借りた。遊び笛(ルーダン)は子供でも数日で吹きこなすことのできる単純なつくりの横笛だ。黒眉家の劇場でも使用される楽器なので、サキも吹き方は心得ていた。
前線の楽団に混ざり、遊び笛を奏でることで兵士の士気を上げようというのが、サキの目論見だった。ただ、前線にやってきて、「頑張れ」と叫ぶだけで効果があると考えるほど、サキは馬鹿ではない。前線とは言え、楽団は歩兵に比べれば安全な位置にいる。自身の勇気と、命惜しさを秤にかけて、サキが見出した妥協点だった。ところが、
「楽団はこちらにございません」
たまたま前線で出会ったフランケンが申し訳なさそうに言った。前線とは言え、敵の攻撃が一時的に止んでいる状況のようで、弾は飛び交っていない。
「砲弾が反れまして、運悪く楽団を直撃したのです。もう、合奏できる人数が残っておりませんので、演奏は、隣の隊の楽団にまかせることになりました」
まずい。
サキはやってくる部隊を間違えたのだ。まさか、楽団が機能していない部隊を選んでしまうとは。「じゃあ、楽団がいるところへ行くから」というわけにはいかない。すでに周囲の兵士が、摂政殿下が前線にいらっしゃったと騒ぎ始めているのだ。ここで何もしないで踵を返しては、「のこのこ前に出てきたと思ったら、臆病風に吹かれてすぐにどこかへ帰った」という印象を与えてしまう。まるで逆効果だ。
他所へ移るにしても、何かしてからでないと恰好がつかない。
「前線の士気を上げに来たんだけど、いいやり方はないかな」フランケンに小声で尋ねる。首を捻りつつ、老兵は右斜め前方を指さした。
「あの一帯ですが、最前列に並ぶ横隊の位置が、敵陣から離れすぎております」
フランケンに言われた場所を見ると、横隊の前方に地面を削った線がある。兵士が並ぶべき位置を示しているらしいが、全員、その手前で踏みとどまっているようだ。その位置までが緩い上り坂になっており、そこに立つことが恐ろしい気持ちは分からないでもなかった。
「本来なら上官がどやしつけて線まで進ませるところですが、現在、前線に穴があいたせいで手が回りません。あちらへ攻撃が再開される前に、誰かが言って聞かせる必要がございます。言って聞かないようであれば」
フランケンは申し訳なさそうな視線をサキに送った。
「誰かが線の場所で立って見せるのが早いでしょうな」
「……それを、僕にやれ、と?」
「やれば、兵士は坊ちゃま殿下に感服するでございましょう」
「けど、あそこに立つってのは」
サキは身震いした。間違いなく目立つ。正真正銘の最前線だ。狙撃されるかもしれない。
しかし、と考え直す。この僕は単なる最高指揮官ではない。国家元首でもある大将は、政治的な意味合いも持っている。狙撃手の判断だけで射殺はされないかもしれないのだ。
やるのなら、今だ。あの場所は現在、砲火にさらされてはいない。さっさと仕事を終えて退がればいい。
「行くしか、ないな」
サキは指揮車から拡声器を取り出した。軍用品ではなく、黒繭家の芝居で稀に使われる高級品だ。装飾をちりばめた大砲のような形状で、牛の頭部くらいのかさばる大きさだが、遠くまで声を響かせることができる。
車を降り、早足で歩く。当然のようについてきたカヤを、最前線の手前で待機させた。兵士たちがサキに敬礼をしながら道を開ける。全員、戸惑いの表情だ。無理もない。サキが横列より前に出ると、どよめきが広がった。
――早まったかもしれない。
サキは早速後悔し始めた。前線の左手から聞こえる砲声が次第に大きくなっている。敵の攻撃が再開されたのだ。
「この小さな丘は、この戦いの要所である!」
勾配の中途当たりでサキは振り返り、拡声器で横列の兵士たちに呼びかけた。適当に言っている。たぶん、そこまでの要所ではない。
「しかるに今、諸君らの意気はくじけ、前へ進めないでいる。減退した兵士の闘志を高めるのも指揮官のつとめ。ゆえに、わたしが手本を示すっ」
言ってしまった。後には退けない。
一歩一歩、サキは勾配を登る。
さあ、だませ。兵隊をだませ。
ここはまだ六十ルーデの外側だ。理屈の上では弾丸も逸れる遠さのはず。だからお前たち、もっと前に出ろ。最低でも僕と並ぶ位置に立たなければ、戦列は意味を成さない。
並べよ。恥ずかしくないのか?僕みたいないたいけな子供を矢面に立たせるつもりか。お前たちは、村々から選ばれた優秀な兵士なんだろう?
まだ数秒。命の空白地で、サキは背後の横列を待った。我慢できずに、振り返る。
兵士たちは元の位置から動いていない。
だめだ、並んでくれない。
出てくるんじゃなかった。僕は死ぬのだな。
涙が出そうになって、目を閉じる。瞼の裏に浮かんだのは、劇場街の風景だった。嫌いだったはずの、浮かれ騒ぐ庶民たちだった。
諦めが、悪あがきに裏返る。
最後に、試してみようと思った。
拡声器を頭の位置まで持ち上げ、敵陣を向いたまま、サキは歌い始めた。
下品な歌を歌って死にたい
下品な歌を歌って死にたい
毎日に振り掛けるような歌
毎日に振り掛けるような歌
背後からどよめきが聞こえる。成功かもしれない、とサキは期待する。
これは、ぺてんだ。兵士との一体感をでっちあげる詐術。お偉い摂政殿下が俺たち庶民の歌を知っていると驚かせて、死なせたくない仲間だと、一緒に六十ルーデの境に立っていい仲間だと勘違いさせたい、まやかしだ。
愛のためじゃなく 夢のためじゃなく
命のためでもなく 希望のためでもなく
寂しい歌だ。しかし案外歌いやすい。
ただ生きているだけで疲れるような
どうしようもない気だるさを慰めるだけの歌
そんな言葉を教えておくれ
そんな音を拾わせておくれ
サキにとって、これは賭けだった。
サキの知っている歌は、音楽の授業で教わる行儀のいい習い歌か、後は「決闘の王子」の劇中歌くらいなもの。
どちらも、末端の兵士を昂ぶらせるにはふさわしくないものだ。
上流階級の歌なんて大抵の兵士は知らないだろうし、黒繭家の息子が「決闘の王子」を歌うなんて当たり前なので、有難くもなんともないだろう。
ここで求められる歌は、サキが知らないだろうと思われているような歌だ。
お偉い摂政殿下が、こんな巷間の歌をご存知だなんて!
俺たちのために歌ってくださるなんて!
そういう心当たりを、少年は一つしか知らなかった。
あの吟遊詩人が奏でてくれた、戦歌。
これなら兵士にも膾炙しているかもしれない。
拡声器を降ろす。ソプラノの残響が収まった直後、泣き声が聞こえた。
「……げひんなうたをうたってしにたい」
違う。歌声だ。銃弾の中で歌など忘れていたに違いない誰かが、しぼりあげるよう応じてくれた、音だ。
「毎日に振り掛けるような歌」
「毎日に振り掛けるような歌」
気配を感じ、左右を見ると、二人の兵士が歌いながら傍らに立っている。六十ルーデに立ってくれた!
二人の合唱は、一瞬の後に波のような大合唱へと変わる。前線が、数歩動いたのだ。後ろを向いたサキは、その光景に圧倒される。見渡す限りの兵士たちによる、不器用な合唱。土誇りに汚れた唇、血泡に染まった唇……戦歌らしくない滑稽な、場違いな歌が、今このときより、全軍の督戦歌に成り上がったのだ。
さらに軍楽隊までもが、同じリズムを奏で始めた。
ぺてん、詐欺の歌。それでもサキの胸中に、熱い灯火が宿る。
前方で枯れ木が弾ぜた。革命軍の突撃が再開されたのだ。
少年は拳を堅く握る。これで目的達成ではない。ここからだ。
「奮い立て諸兵よ。摂政殿下が勇気を示して下さった!」
髭面の士官が、サキの右隣で叫んだ。サーベルを引き抜き、剣舞のように振り回しながら言葉を繰り返す。同時にさりげない掌の動きで、サキを数歩下がらせる。最前線に立ち、士気の高揚に貢献したサキだが、必ずしも先頭に立ち続ける必要はないからだ。その辺りを心得ている士官がいることは、サキを安心させた。
「殿下のお心遣いに我らは全霊でお応えいたします。凶弾飛び交う前線なれど、我ら全力を、全力を注ぎっ!」肥満気味の別の士官が、青筋を立てて叫んだ。
「殿下が毛ほどの傷すら召されることのないよう、お守りすることを誓いまするっ!」
サキは震えた。
おためごかしであることは充分承知している。それでもこんなに心を打たれるのは、生まれて初めてじゃないだろうか。
士官に賛同するように声が上がる。
傍らで、カヤが忙しく木炭を操っていた。
そうか、今の僕は絵になるか。こんなに美しい構図はない。僕は兵士たちに誠意を示し、彼らは衷心で応えてくれた。革命軍がなんだ。散兵突撃がどうした。団結の力で、僕は恐怖を克服したぞ!
サキは拡声器を車に戻して、代わりに天蓋に結い付けられていた国旗を空へ掲げた。これ以上ないほどの万能感が、脳内を満たす。
自分の発案した幻想に取り込まれていることも自覚しているが、抗えない。
「こちらこそ感謝する。そうとも、僕は毛ほども傷つくことはないっ!」
虚勢ではない。サキは気付いていた。すでに敵陣から弾丸が放たれ始めている。最前線より少し引いた位置にいるサキだが、敵がその気になれば、自分を狙い撃ちにすることは可能なはずだ。
それなのに、自分はまだ生きている。
これは奇跡ではない。必然だ。
革命軍は、自分を単純に殺したいというわけではない。「象徴としての」王国君主を討ち取る狙いなのだ。ギロチンの下まで引きずって、革命の勝利を高らかに宣言した後に首を刎ねる。そして「決闘の王子」の首を掲げるのだ。
こんな最前線で、他の兵士と同じように射殺しても劇的ではないのだ。マスケットの弾丸は、当たり所が悪ければ頭部が弾け飛ぶ破壊力だ。この土煙の中で不用意に狙撃でもしたら、誰だか分からない死体が出来上がってしまう。
だから敵兵は、意図的にサキを外している。生け捕りにするという判断が、あるいは判断が難しいので保留にしておくという発想か――とにかく敵の前線指揮官は、サキを殺さないように気を使ってくれている。
味方の兵士に、そこまで事情を推察する余裕はないだろう。だからここにいるサキに感動している。
末端の兵士も王国摂政も、同じ命の線をまたいでいるような勘違いを与え、それが士気高揚に繋がっているのだ。
(なんだ、簡単じゃないか)
気分がよくなった。後ろで怯えていたのが馬鹿みたいだ。危なくないのに危ないふりをして、味方を喜ばせ、前線を硬くする。いい仕事だ、お飾りの君主というものは!
次の瞬間、弾丸が旗の支柱を砕いた。破片がサキの額を削った。
とぷり、血が流れる。毛ほどの傷、どころではない。
「……あっ」
調子に乗っていた。単純な理屈を忘れていた。
射撃はずらしてくれたとしても、破片は避けてくれない。
破片の勢いか、脳みその揺れか、体が傾いた。
兵士たちがサキの周囲に集まる。
「おおー、こんな風に裂けるんだ」
カヤが驚くべき無神経さでスケッチしている。
「ああもう、今のサキ、正面から描きたいのに」革命軍を指さし、カヤが憎々しげに叫んだ。「あいつら邪魔!どっかどけて!」
うん、みんなそう思ってるよ…
「摂政殿下、これを!」髭面の士官が近づいてくる。サキの首を掴み、瓶詰の何かを額に注いだ。注ぎ方が雑すぎる。顔全体が液体に浸される。
「熱っ!」傷口を焼かれているかのようだ。
「ツイカにございます。負傷の直後に傷口に注ぐと、直りが早いとか」
ツイカは李の蒸留酒だ。
それがどうして最前線ですぐさま取り出せる状況にあるのか、サキに追求する余裕はない。酒精か、痛みか。意識が浮沈を繰り返した。