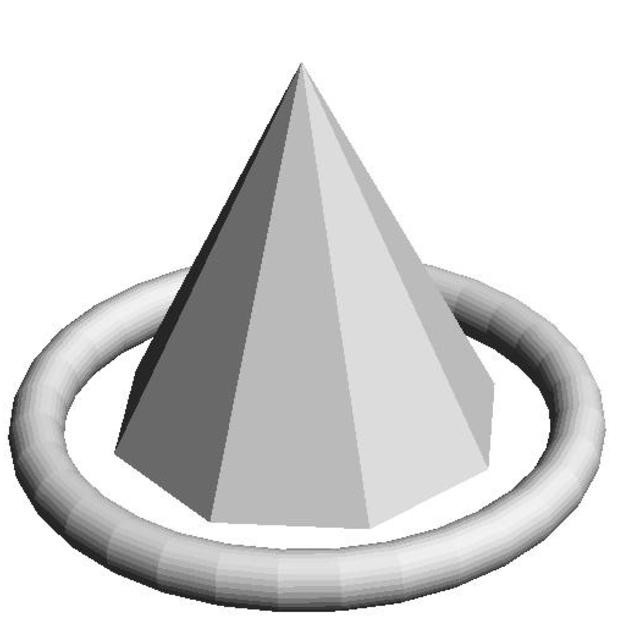老兵の追憶
文字数 3,964文字
ゲオルグ・フォン・ゼマンコヴァが王国軍に入隊したのは、今から八十年前、十五歳の冬だった。
最初から兵士として入隊したわけではない。荷役として遠征に同行したのがきっかけだった。父親が軍用馬の放牧を生業としており、その
あるとき輜重部隊が敵軍の奇襲を受けた。燃え盛る兵糧の中で逃げ惑っていたゲオルグの視界に、猛り狂う三頭の馬が目に入った。乗り主とはぐれたか、馬丁に見捨てられたらしい。
ゲオルグはこの三頭を同時に操り、(一頭の背にまたがり、もう一頭は綱を引き、残り一頭は口で手綱を制御した)危険地帯を脱出することに成功した。子供のころから馬の扱いには慣れており、これくらいの曲芸はお手のものだっった。
幸運にも、その様子を一人の将官が目撃していた。
当時、王国は軍備拡張路線をひた走っており、中でも急務とされたのが竜騎兵隊の拡充だった。竜騎兵とは、単純に言えば槍を銃に持ち替えた騎兵のことを指す。どの国家もある程度の兵数は保持している兵種ではあったが、人員の増強は容易ではない。騎乗しながらマスケットを構え、敵兵に命中させるというのは高度な訓練を要する技術だからだ。そのため、射撃あるいは乗馬技術に長けた人材に、勧誘の声がかかるのは当然の成り行きだった。
「荷物運びだけさせておくにはもったいない乗りこなしだ」
高級軍人を前に恐縮しているゲオルグ少年に、将官は書類を押しつけた。
「明日から君は見習い竜騎兵だ。活躍の機会は山ほどあるだろう。登れるところまで上り詰めるといい」
そうして数十年。軍の最上位まで、ゲオルグは上り詰めていた。
楽な道のりではなかった。竜騎兵部隊の構成員は大抵が貴族階級出身で、平民のゼマンコヴァは様々な場面で冷遇された。しかし、後から振り返って考えると、貴族の世界へ紛れ込んだ平民に対する扱いとしては優しいほうではなかったかと思われなくもない。同僚と比べると亀の歩みではあったが、ゼマンコヴァも着実に出世を重ね、大軍の指揮を任される程の地位を得た。
その直後だった。隣国に「彼」が現れたのは。
公国の若き天才将軍、グロチウス。
その頭脳から生み出される奇策の数々は、敵軍を翻弄し続けた。
当時、王国と公国の間には戦力面で大きな格差があったにも関わらず、グロチウスの軍勢と相対した王国軍は、常に敗北を喫した。彼が公国にいなかったら、公国の領土は半分となり、王国のそれは五割り増しになっていただろうと推定する声もあるほどだ。
将官の大半が自信を喪失するほどの敗戦が続いた。
グロチウスに勝てないという点ではゼマンコヴァも同様だったが、次第に、他の部隊に比べて損耗が少ないと賞賛を得るようになる。貴族階級でもなく、元々兵士になるつもりで軍に入ったわけでもなかったという経歴から来るこだわりのなさが、比較的冷静な判断に繋がったのかもしれない。天才相手に無理な戦いは挑まず、グロチウスのいない戦場ではここぞとばかりに勝利をもぎ取った。ゼマンコヴァがいなければ公国の領土は二割り増しとなり、王国は現在の八割の広さになっていただろうと算定する向きもあるくらいだ。
その堅実さが貴族・平民出身を問わず軍中で評価されるようになり、自身の穏やかな性格も相まって、現在、ゼマンコヴァは重鎮として尊敬を集めている。
夕暮れ、籐の安楽椅子でうたた寝していたゼマンコヴァは、ゆっくりと背を起こし、周囲を見回した。
正面には地平線の果てまで続く麦畑。手前の芝生では幼い曾孫たちが犬と戯れている。
椅子の背後にある漆喰の小屋は、彼の生家の再現だ。小屋の後ろには、小降りで地味だが堅牢な造りの城館が鎮座している。叙爵された折に建てたものだが、「お城に住む」という感覚が何年経っても肌に合わない。そのため年の半分は、小屋で寝起きしている。
右手には水車小屋と、澄み渡った小川。
左手には常葉樹の茂る小山。ちょっとした散策を楽しむための、整備された自然だ。
三百六十度視界に映るすべてが、ゼマンコヴァの人生で手に入れたものだった。
「もう、充分だの」
「なんて仰いました?」
声に振り返ると、小屋から老妻が出てきたところだった。若い頃から苦楽を共にしてきた人生の同志とでも言うべき存在だ。
「……もう充分に生きた、と言ったんじゃよ」
「あらまあ、諦めの早いことで」
妻も安楽椅子を引っ張りだして、ゼマンコヴァの隣に腰掛けた。
「そんな風に言う人ほど、長生きするものですよ。評議会、でしたか?飽きもせず、まだお勤めされてるじゃないですか」
痛いところを突かれた。本日も評議会に出席していたが、赤薔薇家の封鎖が三日目に入ったにも関わらず事態が動きそうにないので頃合いを見て帰宅したのだった。まだ軍服から着替えていなかったことにゼマンコヴァは気付く。
「儂としてはいつ辞めても構わないんじゃがの、皆、今抜けるのはまずいと言うものでなあ」
ゼマンコヴァは静脈の浮き出た掌を凝視する。現時点で、平民出身の元帥は王国軍に彼一人しかいない。革命の嵐が吹き荒れる現状で、ある種の抑止力を期待されているのだろう。政治にはさほど関わってこなかったゼマンコヴァだが、その程度の事情は理解できる。
「今もややこしい事情を抱えておってのう、ゆっくりできるようになるのはいつのことやら……おや、」
視界の角から、ひ孫の一人が顔を覗かせた。七歳くらいだったか、本が好きなせいか、もう眼鏡をかけている女の子だ。手に新聞を抱えている。
「どうしたどうした。読めない文字でもあったかな」
「お、じい、さま」
眼鏡の少女は逡巡している様子だったが、やがて決意したのか、胸元の新聞を押し出した。
「新聞を読んだの。新聞に書いてあったの……おじいさまが、わるいひとだって」
「おやおや?」
手渡された新聞の日付は、三週間近く前、カヤ嬢を有罪とする判断に摂政殿下が挑戦状を突き付けた際のものだった。色あせているので、使用人が掃除かなにかに使ったものを見つけたのかもしれない。文面は摂政殿下に好意的な一方で、口を極めて評議員の面々を罵っていた。
「まあ、こんなの嘘ですよ。新聞の中には、嘘つきが書いているものもあるんですよ」
妻が咎めるような声を出したせいか、少女は身を震わせた。叱られると勘違いしたのかもしれない。
ゼマンコヴァは身を屈めて少女に目線を会わせた。
「この新聞を書いた人は、儂を悪い人と思っている。それは間違いないの。お前はどう思うかね」
「わか、らない」
少女はずれ落ちそうになった眼鏡を手で支えながら答えた。
「では、自分のことは?これまでお前は、自分を悪いやつだと思ったりしなかったかね」
少女にとっては予想外の質問だったろう。首を傾げ、長い間沈黙した後で、
「わたし、一昨日ね、子ヤギのエシルの鼻に、絵の具で落書きしたわ」
「うんうん」
「昨日は、弟のおやつをよこどりしたわ」
「うんうん」
「お隣のマーシャに貸してもらったご本を、まだ返していないわ」
告白しながら、少女の顔は青ざめていく。
「どうしよう」
涙目になり、手で頬を押さえた。
「わたしも、わたしもわるいこだったわ!」
「そうじゃなあ」
ゼマンコヴァは立ち上がり、曾孫の頭を撫でた。
「お前さんも、儂も。悪いことをしない人間なんて一人もおらん。みんな悪い。みんな悪いひと
なんじゃ」
「そうなの?」
少女の表情が凍る。これまで家庭教師や教会では聞かされたことのない話なのだろう。その肩を、ゼマンコヴァは優しく掴む。
「しかしの、お前さんはヤギの鼻を汚したままにしたのかの?弟のおやつを取りっぱなしかの?借りた本を自分のものにしてしまうつもりかな?」
少女は激しく首を横に振った。
「エシルの鼻は拭ったし、次のおやつは弟にあげたし……マーシャのご本も、これから返しに行きますっ!」
「えらい、えらい」
もう一度頭を撫でてやる。
「お前は悪い子だったかもしれん。でもずっと悪い子でいたくはないから、悪いことをなくそうと考えた。大人も同じなんじゃよ。皆、悪い人じゃが、それを自分でもよおく分かっておる。世の中をよくしようと必死でがんばっておる、悪い人じゃが、良くなりたい悪い人の集まりなんじゃよ」
少女の表情は、別人のように晴れやかなものへ変わっていた。
手を振って、芝生で遊んでいた他の曾孫たちのところへ駆けて行く。
溜息をつき、ゼマンコヴァは安楽椅子に戻った。
傍らの妻が、揶揄するように笑う。
「上手く誤魔化しましたわねえ」
「はっはっは」
手厳しい。まあ、子供相手とはいえ、全くの嘘をついたわけではない。
ゼマンコヴァは椅子から立ち上がり、城館へ向かう。年を取ると軍服のぴったりした締め付けが我慢できなくなってくる。さっさと着替えてしまおう。
もう充分に生きた。それは嘘偽りのない感想だった。
ではどのように世を去るのが望ましいだろうか?ゼマンコヴァは想像する。幾多の戦役に身を投じ、九十の齢を過ぎてもなお、己の死は実感できない。童 の頃と、変わらないままだ。
――――一つ、あるな。いい死に方が、ある。
老元帥は苦笑した。それを実行した場合、さっきの曾孫は自分をどう思うことだろう。あの子ばかりではない。家族皆に迷惑をかけてしまうのう。
まあ、許してもらうしかないな。ゼマンコヴァは決意する。これから先、情勢が煮え立つようであれば、誰もそれを選ばないようなら。
想像する。
本物の「悪い人」になって世を終えるのも、おもしろい。
最初から兵士として入隊したわけではない。荷役として遠征に同行したのがきっかけだった。父親が軍用馬の放牧を生業としており、その
つて
で軍務に就いたのだ。あるとき輜重部隊が敵軍の奇襲を受けた。燃え盛る兵糧の中で逃げ惑っていたゲオルグの視界に、猛り狂う三頭の馬が目に入った。乗り主とはぐれたか、馬丁に見捨てられたらしい。
ゲオルグはこの三頭を同時に操り、(一頭の背にまたがり、もう一頭は綱を引き、残り一頭は口で手綱を制御した)危険地帯を脱出することに成功した。子供のころから馬の扱いには慣れており、これくらいの曲芸はお手のものだっった。
幸運にも、その様子を一人の将官が目撃していた。
当時、王国は軍備拡張路線をひた走っており、中でも急務とされたのが竜騎兵隊の拡充だった。竜騎兵とは、単純に言えば槍を銃に持ち替えた騎兵のことを指す。どの国家もある程度の兵数は保持している兵種ではあったが、人員の増強は容易ではない。騎乗しながらマスケットを構え、敵兵に命中させるというのは高度な訓練を要する技術だからだ。そのため、射撃あるいは乗馬技術に長けた人材に、勧誘の声がかかるのは当然の成り行きだった。
「荷物運びだけさせておくにはもったいない乗りこなしだ」
高級軍人を前に恐縮しているゲオルグ少年に、将官は書類を押しつけた。
「明日から君は見習い竜騎兵だ。活躍の機会は山ほどあるだろう。登れるところまで上り詰めるといい」
そうして数十年。軍の最上位まで、ゲオルグは上り詰めていた。
楽な道のりではなかった。竜騎兵部隊の構成員は大抵が貴族階級出身で、平民のゼマンコヴァは様々な場面で冷遇された。しかし、後から振り返って考えると、貴族の世界へ紛れ込んだ平民に対する扱いとしては優しいほうではなかったかと思われなくもない。同僚と比べると亀の歩みではあったが、ゼマンコヴァも着実に出世を重ね、大軍の指揮を任される程の地位を得た。
その直後だった。隣国に「彼」が現れたのは。
公国の若き天才将軍、グロチウス。
その頭脳から生み出される奇策の数々は、敵軍を翻弄し続けた。
当時、王国と公国の間には戦力面で大きな格差があったにも関わらず、グロチウスの軍勢と相対した王国軍は、常に敗北を喫した。彼が公国にいなかったら、公国の領土は半分となり、王国のそれは五割り増しになっていただろうと推定する声もあるほどだ。
将官の大半が自信を喪失するほどの敗戦が続いた。
グロチウスに勝てないという点ではゼマンコヴァも同様だったが、次第に、他の部隊に比べて損耗が少ないと賞賛を得るようになる。貴族階級でもなく、元々兵士になるつもりで軍に入ったわけでもなかったという経歴から来るこだわりのなさが、比較的冷静な判断に繋がったのかもしれない。天才相手に無理な戦いは挑まず、グロチウスのいない戦場ではここぞとばかりに勝利をもぎ取った。ゼマンコヴァがいなければ公国の領土は二割り増しとなり、王国は現在の八割の広さになっていただろうと算定する向きもあるくらいだ。
その堅実さが貴族・平民出身を問わず軍中で評価されるようになり、自身の穏やかな性格も相まって、現在、ゼマンコヴァは重鎮として尊敬を集めている。
夕暮れ、籐の安楽椅子でうたた寝していたゼマンコヴァは、ゆっくりと背を起こし、周囲を見回した。
正面には地平線の果てまで続く麦畑。手前の芝生では幼い曾孫たちが犬と戯れている。
椅子の背後にある漆喰の小屋は、彼の生家の再現だ。小屋の後ろには、小降りで地味だが堅牢な造りの城館が鎮座している。叙爵された折に建てたものだが、「お城に住む」という感覚が何年経っても肌に合わない。そのため年の半分は、小屋で寝起きしている。
右手には水車小屋と、澄み渡った小川。
左手には常葉樹の茂る小山。ちょっとした散策を楽しむための、整備された自然だ。
三百六十度視界に映るすべてが、ゼマンコヴァの人生で手に入れたものだった。
「もう、充分だの」
「なんて仰いました?」
声に振り返ると、小屋から老妻が出てきたところだった。若い頃から苦楽を共にしてきた人生の同志とでも言うべき存在だ。
「……もう充分に生きた、と言ったんじゃよ」
「あらまあ、諦めの早いことで」
妻も安楽椅子を引っ張りだして、ゼマンコヴァの隣に腰掛けた。
「そんな風に言う人ほど、長生きするものですよ。評議会、でしたか?飽きもせず、まだお勤めされてるじゃないですか」
痛いところを突かれた。本日も評議会に出席していたが、赤薔薇家の封鎖が三日目に入ったにも関わらず事態が動きそうにないので頃合いを見て帰宅したのだった。まだ軍服から着替えていなかったことにゼマンコヴァは気付く。
「儂としてはいつ辞めても構わないんじゃがの、皆、今抜けるのはまずいと言うものでなあ」
ゼマンコヴァは静脈の浮き出た掌を凝視する。現時点で、平民出身の元帥は王国軍に彼一人しかいない。革命の嵐が吹き荒れる現状で、ある種の抑止力を期待されているのだろう。政治にはさほど関わってこなかったゼマンコヴァだが、その程度の事情は理解できる。
「今もややこしい事情を抱えておってのう、ゆっくりできるようになるのはいつのことやら……おや、」
視界の角から、ひ孫の一人が顔を覗かせた。七歳くらいだったか、本が好きなせいか、もう眼鏡をかけている女の子だ。手に新聞を抱えている。
「どうしたどうした。読めない文字でもあったかな」
「お、じい、さま」
眼鏡の少女は逡巡している様子だったが、やがて決意したのか、胸元の新聞を押し出した。
「新聞を読んだの。新聞に書いてあったの……おじいさまが、わるいひとだって」
「おやおや?」
手渡された新聞の日付は、三週間近く前、カヤ嬢を有罪とする判断に摂政殿下が挑戦状を突き付けた際のものだった。色あせているので、使用人が掃除かなにかに使ったものを見つけたのかもしれない。文面は摂政殿下に好意的な一方で、口を極めて評議員の面々を罵っていた。
「まあ、こんなの嘘ですよ。新聞の中には、嘘つきが書いているものもあるんですよ」
妻が咎めるような声を出したせいか、少女は身を震わせた。叱られると勘違いしたのかもしれない。
ゼマンコヴァは身を屈めて少女に目線を会わせた。
「この新聞を書いた人は、儂を悪い人と思っている。それは間違いないの。お前はどう思うかね」
「わか、らない」
少女はずれ落ちそうになった眼鏡を手で支えながら答えた。
「では、自分のことは?これまでお前は、自分を悪いやつだと思ったりしなかったかね」
少女にとっては予想外の質問だったろう。首を傾げ、長い間沈黙した後で、
「わたし、一昨日ね、子ヤギのエシルの鼻に、絵の具で落書きしたわ」
「うんうん」
「昨日は、弟のおやつをよこどりしたわ」
「うんうん」
「お隣のマーシャに貸してもらったご本を、まだ返していないわ」
告白しながら、少女の顔は青ざめていく。
「どうしよう」
涙目になり、手で頬を押さえた。
「わたしも、わたしもわるいこだったわ!」
「そうじゃなあ」
ゼマンコヴァは立ち上がり、曾孫の頭を撫でた。
「お前さんも、儂も。悪いことをしない人間なんて一人もおらん。みんな悪い。みんな悪いひと
なんじゃ」
「そうなの?」
少女の表情が凍る。これまで家庭教師や教会では聞かされたことのない話なのだろう。その肩を、ゼマンコヴァは優しく掴む。
「しかしの、お前さんはヤギの鼻を汚したままにしたのかの?弟のおやつを取りっぱなしかの?借りた本を自分のものにしてしまうつもりかな?」
少女は激しく首を横に振った。
「エシルの鼻は拭ったし、次のおやつは弟にあげたし……マーシャのご本も、これから返しに行きますっ!」
「えらい、えらい」
もう一度頭を撫でてやる。
「お前は悪い子だったかもしれん。でもずっと悪い子でいたくはないから、悪いことをなくそうと考えた。大人も同じなんじゃよ。皆、悪い人じゃが、それを自分でもよおく分かっておる。世の中をよくしようと必死でがんばっておる、悪い人じゃが、良くなりたい悪い人の集まりなんじゃよ」
少女の表情は、別人のように晴れやかなものへ変わっていた。
手を振って、芝生で遊んでいた他の曾孫たちのところへ駆けて行く。
溜息をつき、ゼマンコヴァは安楽椅子に戻った。
傍らの妻が、揶揄するように笑う。
「上手く誤魔化しましたわねえ」
「はっはっは」
手厳しい。まあ、子供相手とはいえ、全くの嘘をついたわけではない。
ゼマンコヴァは椅子から立ち上がり、城館へ向かう。年を取ると軍服のぴったりした締め付けが我慢できなくなってくる。さっさと着替えてしまおう。
もう充分に生きた。それは嘘偽りのない感想だった。
ではどのように世を去るのが望ましいだろうか?ゼマンコヴァは想像する。幾多の戦役に身を投じ、九十の齢を過ぎてもなお、己の死は実感できない。
――――一つ、あるな。いい死に方が、ある。
老元帥は苦笑した。それを実行した場合、さっきの曾孫は自分をどう思うことだろう。あの子ばかりではない。家族皆に迷惑をかけてしまうのう。
まあ、許してもらうしかないな。ゼマンコヴァは決意する。これから先、情勢が煮え立つようであれば、誰もそれを選ばないようなら。
想像する。
本物の「悪い人」になって世を終えるのも、おもしろい。