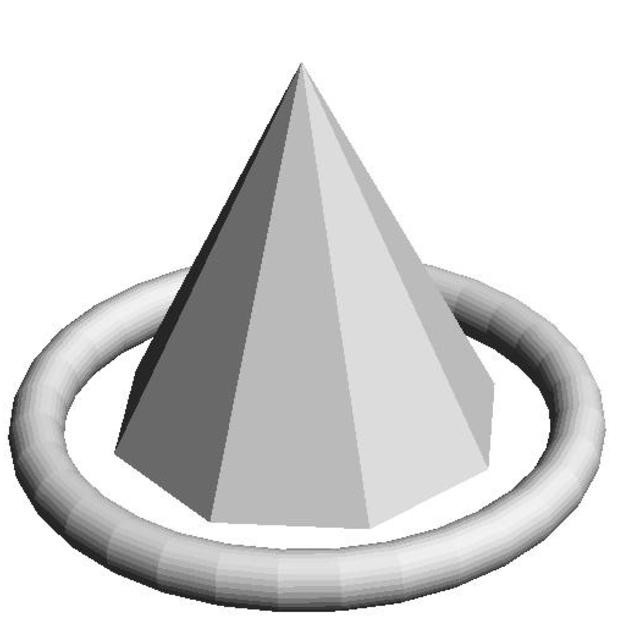少年の鬱屈
文字数 5,830文字
その少年が決闘の立ち会い人を務めるのは、その日が二十回目だった。
決闘に杓子定規なルールは要求されないものの、最低限の骨組みは定まっている。立会人もその一つだ。決闘の公正さを保証、闘いの行く末を見届け、たとえ決闘者たちが共倒れになったとしても、彼らの誇り高さを記憶に留め、ふれ回るという役割だ。
だったら見物客がいるような状況では不要とも思われるがーー不在では何となく場がしまらない、という理由でこの闘技場でも常に配置されていた。ここでは、もったいぶった仕草で場を盛り上げるだけの役割だ。
観客席を見回し、少年は自己紹介を行う。
「黒繭家次男、サキ。非才ながら西側の立会人を務めさせていただきます」
観客から拍手が起こる。サキと名乗った少年に続き、もう一人の立会人も声を張り上げた。今回の決闘では当事者二名に対し、一名ずつの立会人と、二名ずつの「介添人」が配分されていた。介添人は相手方に卑怯な振る舞いがあった際に加勢する役割なので、やはり仕事をすることはまれな飾りの一要素だ。 いずれも双方の関係者を有志で参加させるのが一般的だが、頼れる人間が足りない場合、劇場とコロシアムの所有者である、黒繭家の人間が代役を務めることが多い。この国有数の名門であり、当主が候の爵位を冠する黒繭家は「決闘の王子」の子孫でもあるからだ。
この決闘では、片方の立会人にあてがなかったため、サキが割り当てられたのだった。
こういう場合、「決闘の王子」に近い年代の子供が喜ばれる。
サキは十四歳。劇中の王子と同い年で小柄な体格も似通っているため、添え物として申し分がない。
双方の立会人が決闘者たちの言い分を読み上げる。
元々決闘は神前裁判とも呼ばれ、行いの正しい者に対してのみ神は味方するはずという発想から命のやりとりが許されている、一種の訴訟行為なのだ。そのためたとえ形式上であっても、最初に和解の可能性が模索される。決闘の場に姿を見せたお互いの勇気を評価して、この段階で双方、矛を収めるケースも無くはない。しかしこの闘技場のように人が集まる場所を選んだ場合、土壇場で翻意して見せても、恥をかくだけだ。
形だけの調停が終わり、いよいよ本番だ。主役二人が向かい合う。懐から拳銃を取り出し、交換した。用いられる武器は様々だが、公平を演出するため、武器の入れ替えはしばしば行われる。そうでない場合、決闘のためだけに拳銃を二人分特注する例もある。
静まり返る観客席。
用意していた硬貨を、サキが上空へ放つ。 金色が地面に跳ねたとき、二丁の拳銃が火を噴いた。
決闘者たちが崩れ落ちたのは、ほぼ同時だった。
いずれも、抱えた肩に赤い染みを咲かせている。片膝を立てた体勢で踏みとどまり、しばし睨み合う。
やがて、どちらからともなく破顔した。
そして抱擁を交わした。放浪の果てに巡り会えた親友のように。
憎悪から弾丸でかたを付けようとした二人だったが、命のやりとりの中でお互いの意気に感じ入り、遺恨を捨て去ったのだ。
満場の拍手が沸き起こる。介添人も、立会人も手を叩き、友情の始まりを祝福する。
―――――くだらない。
拍手を繰り返しながら、サキは心の中で毒づいた。
こんなものは、にせものの感動だ。にせものの英雄だ。
なぜって、銃弾は命中などしていないからだ。火薬と鳥の血袋を肩の布地に仕込み、ひじの角度で炸裂させる仕組み。それを使って、相打ちを演出しただけだ。
今回の当事者たちは、宴席の諍いが原因で銃をとる羽目に陥ったのだが、名誉のために命を投げ出すつもりは毛頭なかったらしい。周囲が熱くなりすぎてしまったため、ここまで追い込まれてしまったというだけだ。そういうケースでは、血袋のような手品の出番となる。
悪いことかと言えば、違うかもしれない。お互い傷付くこともなく、仲間への面目も立って、観客も喜ぶ。
でも、サキにとっては拷問だ。この数年、大半はこんなインチキに付き合わされてきたのだから。
黒繭家は王族に連なる名門でありながら、まつりごとの中枢からは離れた場所にいる。数百年、芝居と決闘ごっこで民衆を喜ばせることに没頭しているせいだ。この闘技場も、劇場も黒繭家の所有物で、維持や改修に大金を費やし続けている。
現実にため息をつきながら、少年は先祖の偉業に思いを馳せる。
黒繭家の先祖は初代国王の弟だ。彼は「決闘の王子」の発案者の一人であり、芝居を利用して人心を収攬してみせた傑物だった。サキが残念で仕方がないのは、それから先だ。どこかの代で手段と目的が入れ替わり、政治そっちのけで芝居の運用に熱中するような家風に変わってしまったからだ。
不平を噛み殺しながら少年は闘技場を後にする。
通常、貴族の子弟は従者を連れて外出するものだが、厳密に言うと今のサキは「外出」してはいない。闘技場も、劇場も黒繭家の敷地内にあるからだ。敷地は短辺が400ルーデ(約1.2km)、長辺が800ルーデ(約2.4キロメートル)の長方形を成しており、短編の片側に劇場と闘技場が、もう片側に繭家の邸宅が配置されている。さすがに邸宅へ出入りできるのは黒繭家の関係者のみだが、門扉の手前まで敷地の七割を占める領域が庶民に開放されている。
所定の手続きと地代を納めれば、屋台を組んで商いすることさえ認められているのだ。そのためコロシアムと劇場は虹色の線で繋がれている。両方の観客をあてにした色とりどりの屋台の列だ。飴売り、酒売り、似顔絵書き、孔雀男のお面……大振りの樽や水瓶を利用した風呂屋さえ軒を連ねている。風呂は回教徒が持ち込んだ風習のひとつで、他宗教の民や、貴族階層にも広く受け入れられている。サキも嫌いではないが、往来でも平気で裸をさらす、庶民の入浴風景には憎しみに近い嫌悪を抱いていた。黒繭家の敷地内で下品な体をさらす庶民。それを許容する当主。うんざりだった。
とにかくサキの毎日には、大嫌いな「決闘の王子」が散りばめられている。
無意味とまでは、思わない。劇場や闘技場、屋台から黒繭家が得ている収入は膨大なものだ。
しかし黒繭家当主であるサキの父親は――その父親もさらに前もだが――大金を使って領土を開拓しようとか、政財界へ影響力を得ようとか、そういう外向きの発想を一切持たず、ただただ「決闘の王子」に関連するあれこれを充実させる行為だけに資材を注ぎ込んできたのだ。立派な衣装、座り心地のいい観客席、美味しい飲み物……客は喜ぶだろう。しかし黒繭家には何ら益をもたしていない。王国でも指折りの名門にも関わらず、宮廷での存在感は寂しいものだった。むしろ、年月を経るほどに減退しつつある。
いらいらと歩くサキの前に、一台の馬車が停まった。幌も車体も御者の服装も地味な色合いで衆目を牽くものではないが、幌には蚕の繭を模した紋章が縫い付けられている。
黒繭家の馬車だ。
「サキ、お役目ご苦労様でした」
かきわけた幌から銀髪がそよぐ。三歳年長の姉、ニコラが半身を見せた。
灰の絹服に白のヒマティオンという取り合わせは、中身に華がなければ無様になりかねないが、彼女には無用の心配だ。姉は美しい。名門ともなれば結婚相手に美男美女が集まるから整った容貌の子供が生まれるのも当然の話だが、ニコラの容姿は、殊更に調和がとれている。姿を絵画に例えるなら僕は試し描きで姉上が本番ーーー異性でありながらそんなふうに劣等感を感じるくらいだ。
引け目を覚えるのは容姿だけではない。
姉は膝の上に封筒を何通か乗せていた。サキが馬車に乗り込み、御者が鞭を入れると、揺れる座席に構わず中身を吟味し始める。この時間、馬車で領内を巡るのが彼女の日課で、弟が立会人をする日は、ついでに回収もしてくれる。その際、時間つぶしに自分に届いた便りを車内で読むことが多い。
「また学会への誘いですか」封筒の一つ、先程まで臙脂色の蝋で封がされていたものをサキは見とがめた。封筒に描かれた文様は、王立数学会を示すものだった。
ニコラは幼少の頃から数学の素養に恵まれている。今年の春、腕試しに王立数学会へある方程式に関する論文を提出したところ、高い評価を経て学会誌に掲載された。論文は学界の重鎮にも捨て置けない完成度だったらしく、以来、王立数学会の会員にならないかという誘いが繰り返されているのだった。ただ、学界は女性会員を認めておらず、姉は架空の名義で論文を提出していたため、入会は固辞し続けている。
「何度もお断りしたはずなのに、わかっていただけないようです。封筒の無駄なのですが」
「ばらしてしまえばいいじゃないですか」
自分ならそうするのに、とサキは思う。
「謎の論文執筆者、その正体は黒繭家の令嬢!きっと評判になりますよ。規定を改定して、女性でも入会が認められるかもしれない」
「私は別に、学界に入会するために学問をしているわけではありません」
ニコラは封筒を左右に振った。
「論文を送ったのは、客観的な評価を知りたかったからです。私と同様の評価を得ておられる数学者の中には、経済的に恵まれない方もいらっしゃると聞いています。学会に入れば年金も支給されますから、そういう方々を優先してもらった方がいいでしょう」
「傲慢ですね、才人ならではの」
「相変わらず、機嫌が悪そうですね」
ニコラは指摘するが、気遣ってくれているわけではなく、「天気が悪いですね」と話す場合と変わらない調子だ。
「ずっと悪いですよ。この領内にいる限り」サキは不貞腐れる。
「その割には、まじめに役目をこなしているようですが」
ニコラは二つ目の封を開いた。
「立ち合いの役目、評判は悪くないようですよ」
「適当にやってたら、皆に迷惑がかかるじゃないですか!」
サキは声を荒げた。決闘の王子は嫌いだ。それでもこの演劇が、一つの文化として成り立っていることは否定できないし、それに連なることで生活を成り立たせている人々がいる点も無視できない。だから真面目に取り組むしかないのだ。立ち合いをする決闘の前後に宴席など設けられた場合、サキも参加して愛想よく会話に加わっている。社交の重要性も、人脈を紡ぐ意味も理解しているつもりだ。
ただ、それらが全て、「決闘の王子」に繋がっていることが気に食わない。
「我慢しているんです。飽き飽きなんですよ」
サキは憎しみを込めて馬車の窓から外を眺めた。仮面売りの店先に飾られた色とりどりの孔雀男が、自分をあざ笑っているかのようだ。
「僕がこの黒繭家を好き勝手できるなら」
サキは窓枠をつつく。
「こんな屋台の群れなんて、更地にしてしまうのに」
「サキは次男ですから、我が家を好き勝手はできませんよ」
「知ってますよ!たとえばの話っ、でっ?」
言葉が跳ねる。馬車が急停止したのだ。
「申し訳ない!」
御者が恐縮している。「ばっかやろっ。とびだしてきやがってっ」
サキは馬車を降りた。前方に、汚れた身なりの子供が倒れている。顔を上げてこちらを見た途端、その顔が恐怖にひきつった。
「あっ、ううううあっ、ごめん、ごめんなさいいいっ」
七歳くらいの男の子だ。サキを知っているらしい。闘技場で目にしたのだろうか。怯えているのは、相手が「えらいひと」であると気づいたからだろう。
涙目だ。土誇りで頭が黄色に染まっている。
「……まったく」
サキはハンカチで頭を拭ってやった。
「今度から気をつけるんだぞ。それとこっちのおじさんにも謝るんだ」
御者のほうを向かせて、頭を下げさせる。
「ごめん…なさい」
涙が引っ込んだ。サキの方に向き直って、男の子は晴れやかな笑顔を浮かべる。
「ありがとう!」
ありがとうはおかしいだろ、とサキは思ったが、
「これ、あげる」
男の子は服の中から拳大の包み紙を取り出し、サキに押し付けた。もう一度頭を下げて、屋台の方へぱたぱたと走って行く。
「やさしいのですね」
ニコラが馬車の窓から頭を出した。
「無駄に厳しくないだけです」
ばつの悪い気持ちで、サキはもらった包み紙をまさぐった。
「うえっ、なんだよこれ!」
開いた紙ごと、落としそうになる。包まれていたのは謎の物体だった。つやつや光る薄桃色の塊。表面に赤と紫色の筋が張り巡らされている。小動物の心臓みたいだ。
「ザッカーヘルズですね」ニコラが指先で突く。
「流行りのお菓子です。膨らませたパンに、柔らかい竹串で管を通して、イチゴとブルーベリーのジャムを流すものです。最後に砂糖水で固めると、そういう色合いになるみたいですよ」
姉が菓子類に詳しいとは、意外だ。普通の女の子みたいだ。
「外見は醜悪ですが、味はなかなかのものですよ。この辺りに屋台があって、繁盛していると聞いています」
サキは手の中の菓子を凝視する。これほど食欲をそそられない食べ物を見たことがない。
「どうしろっていうんだよ。こんな気持ち悪いお菓子、押し付けて……」
「要らないのなら、捨てればいいのでは」
「だめでしょう、食べ物を粗末にするなんて!」
迷ったが、自分で処理することにした。男らしく、がぶりと噛り付く。
馬鹿な……美味しい!
一齧りすると、表面の砂糖が砕けるさくりとした感触が心地いい。そのあとでパンの程よい柔らかさ。チーズが薄く混ざっているようで、香ばしい。
続けざまに、イチゴとブルーベリーの酸味が、交互に舌を刺激する。甘さの波状攻撃だ。歯ごたえの竜巻だ。
馬車に乗り込む前に、すべて平らげてしまっていた。
「灼熱亭という屋台で売っています。場所、教えてあげましょうか」
姉に訊かれて、赤面する。
「要りませんよっ。ま、まあ、庶民のおやつにしては、悪くない味ですかねっ」
馬車は家路を急ぐ。相変わらず、窓を流れ去るのは色とりどりの屋台。
「僕がこの黒繭家を好き勝手できるなら、こんな屋台の群れなんて……」
口ごもる。まあ、繁盛もしているようだし、更地にするほどではないか。
「そういえばサキ」
ニコラが封筒の一つをサキに差し出した。
「珍しく、貴方に手紙が届いていましたよ」
珍しく、は余計だ。サキは封蝋を確かめる。黒繭家の紋章と僅かに意匠の異なる白繭。王国の、宮廷の紋章だ。
名門とは言え、十四の子供に、国家から手紙が届いたのだ。何の知らせだろう?
逸る気持ちを抑えつつ、サキは慎重に封を開く。
その瞬間、少年の日常は終わりを告げたのだった。