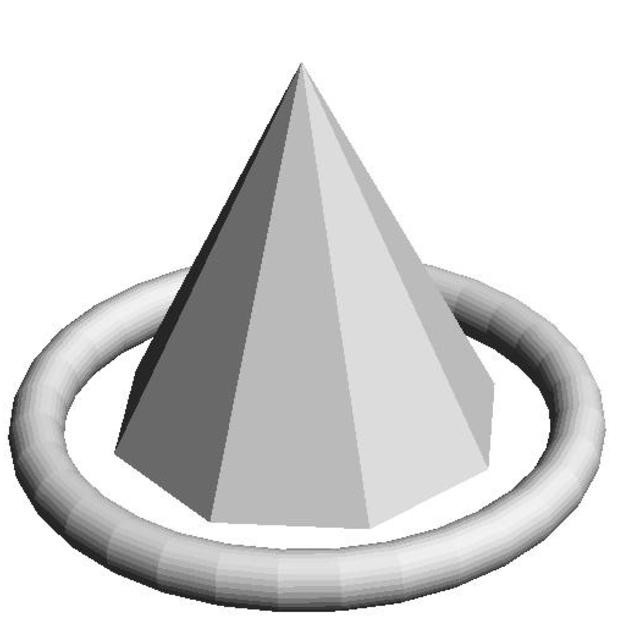ワルツと内緒話
文字数 7,495文字
「まさかお相手していただけるとは、思いもよりませんでした」
カザルスは警戒心を表に出さないよう注意しながら、少女の手を取った。
ワルツの相手を務めてくれるのは、摂政殿下の姉君だ。これまで友好的とは言えない態度を見せられていた上に、好んでこのような場にやってくるような性格ではないだろうと思い込んでいた。
「必要と感じたなら、踊りますよ。ワルツくらい」
ニコラの返事はそっけない。
「必要とは」
カザルスは少女の腕を優しく誘い、立ち位置を変える。
「私の機嫌をとる必要ですか」
「あなたとお話する必要です」
少女は愛想笑い一つ見せない。
「お窺いしたかったのです。議長閣下の死に関して、どのように考えておられますか」
「考えるもなにも、感心させられるばかりでした。まさか、犯人があのグロチスウスだったとは!おのれの不明を恥じるばかりです」
「本当ですか」
少女の瞳は冷たい。しなやかな手つきで身を揺らし、右方向へターンした。
「少将も気付いていらっしゃるのでは?孔雀男の説明には矛盾点が混ざっていたことを」
「穏やかではありませんね」
カザルスは驚く振りをした。
「この期に及んで、真犯人は別にいると?」
「そこまで重大な間違いではありません」
少女の指先に力がこもる。
「グロチウスが議長を殺したという事実は変わりません。しかし、あの場にいた人々を納得させるために、孔雀男があえて言及しなかった要素があるのです」
「どの部分でしょう。私には想像もつかないな」
少女はカザルスの瞳を覗き込んできた。
「例の外套です。隠し倉庫で見つかった外套を折り畳んで決闘台の絨毯に置くと、絨毯の血糊が欠けていた部分と一致した。冷静に考えると、これはおかしな話です」
「どうしてです。一致したからこそ、カヤ嬢の無罪が確定したのではないですか」
「そのこと事体は間違っていません」
カザルスの肩から少女は手を離した。
「問題は、グロチウスが死亡していたという事実です。あの決闘でグロチウスも負傷したに違いない、と孔雀男は推測していましたが、それならグロチウスは負傷した体の上に外套をまとって外へ出て行ったことになってしまいます」
「なるほど」
近くで摂政殿下とカヤ嬢が踊っている。カザルスが会釈すると、殿下は不振そうに眉を寄せた。
カザルスは声を小さくする。
「その場合、議長の血で汚れた外套に、グロチウス自身の血も染み込んだはず。すると折り畳んだ外套の血痕が、絨毯の欠落とぴったり一致するのはおかしい、という理屈ですね?」
公女は頷いた。
「つまり、グロチウスは決闘で負傷したわけではない。議長を殺めた直後は健康そのものだったのに、二日後には死体になっていた。遺体がどういう状況だったのか、私は資料を見てはいませんが、しばらくの間、戦死だったと思われていたのですから、銃弾を浴びた状態だったはずです」
「おっしゃる通り、胴体に数発の銃弾が命中していました」
カザルスは意図的にステップのペースを上げた。動揺も見せず、付いて来る。
「結論から言いますと、グロチウスはいばら荘を出て国境付近へ戻る際に、誰かに射殺されたのです」
少女はすらすらと話した。
「それは……少々粗い筋立てではありませんか」
カザルスは唇を曲げる。
「議長に撃たれた部分が、たまたま出血しない箇所だったのかもしれません。あるいは完璧な手当を施したので、血は滲まなかったのかも。外套と、絨毯の血痕が一致しないというだけでは、根拠としては少し、弱い」
「遺体に銃弾は残っていたのですか」
公女は引き下がらない。
「決闘で負傷したのであれば、議長が特注した弾丸が体内に残っているかもしれません」
「遺体はすでに、共和国へ移送しています」
カザルスは頭を振った。
「銃弾は摘出した後、廃棄してしまいました。まさかそのような確認が必要になるとは思いもよらなかったものでね」
「では確認は不可能ですね」
だしぬけに少女は後退した。
「そう考えたからこそ、孔雀男はこの件に言及しなかったのです。あの場で優先するべきは、犯人の正体を明らかにすること、それを群衆に納得させることでしたから」
「しかし貴女は納得されてはいないのですね」
「していません。論証材料は乏しく、今後も手に入らないでしょう。けれども推測は可能です。グロチウスが北方で射殺されていたとしたら、相手は誰だったのか」
「事情を知らない我が軍の兵士の仕業だったかもしれませんよ。怪しい人影を見たから発砲した結果、致命傷になったとか」
「そうかもしれません。その場合、その兵士は何故グロチウスを発見できたのでしょうか。あらかじめ、周辺を見張るよう上官から指示があったのでは?」
「それはまあ」
カザルスは天井を眺める。
「戦争が終わってからも、敗残兵が農家を襲うおそれもありますから、ある程度の網は張り巡らせていますがね」
「そもそも皆が、『グロチウスは戦場で命を落とした』と思いこんでいた原因は何だったでしょうか」
少女の眼差しが、氷の鋭さでカザルスに迫り来る。
「それは、権威ある将官であり、この戦いの殊勲でもあるカザルス少将が、そうに違いない、と仰ったからでは?」
フルートのト単調が広間を切り裂いた。
「ははは」
カザルスはあえて悪役を意識した笑い方を選んだ。
「不徳の極みですな。見間違いと思いこみが疑いに繋がってしまうとは」
「否定されるならされるで結構です。これは推測に過ぎませんから」
「いや、面白いお話です。続きを聞かせていただけますか?」
「あの戦場で、あなたはグロチウスが本国への退却に加わらず、単騎で王都の方へ戻ったらしいと情報を掴んだ。その情報を、誤報と断じて手元で握りつぶした上で、彼は戦死したにちがいないと宣言した」
「目的は?」
「今回、騒ぎになったように、あなたもグロチウスが軍上層部の誰かと繋がっているのではないかと睨んだのでしょう。グロチウスはわざわざ敵地へ引き返したのですから、そう疑って当然です。証拠を掴んだら、今後の役に立つかもしれない。だから泳がせることに決めたのです。グロチウスが王国のどこに潜伏しているかまでは予想できなかったので、帰還する際の道筋を予想して、網を張った。
果たして数日後、王都から戻ってきたグロチウスを補足することに成功した……場所や詳しい状況は分かりませんが、おそらくあなたは一人でグロチウスと対面した。一人でも同席者がいたならば、彼が生存している事実は隠し通せないだろうと判断して、公表したと思われますから」
おや、とカザルスは嬉しくなった。自分はこの少女に思ったより評価されているようだ。同席者を口封じに殺したと決めつけられない程度には。
「その仰り方ですと、私が意図的にグロチウスを殺害したとはみなしておられないようですね」
「事故に近いものだったでしょうね」
公女殿下はそっけない。
「グロチウスは、王都方面へ戻った理由を知られたくなかったでしょうから、なんとかあなたを振り切ろうとしたのでしょう。成り行きで撃ち合いとなり、彼を射殺してしまった貴方は、『やはりグロチウスは戦死していた」と皆に納得させるため、遺骸を冷水に沈めて、腐敗が進行していない点を偽装したのです」
「その段階で、彼の死んだ日付を誤魔化す理由が私にありますか?」
「ありのままを伝えない方がよいと判断したのでしょう。グロチウスの内通者が国内に存在した場合、彼が殺された事実には驚くでしょうが、死亡日が勘違いされている点は歓迎するだろうと予測したのでは」
今度はイオナ夫妻が近くを通ったので、公女殿下はコレートと会釈を交わした。
「その後数日、あなたは観察に徹した。やがて議長と連絡がとれない状況になっているとの報告を受け、私たちとともにいばら荘へ出向き、そこでグロチウスの目的を把握した。我が国に混乱をばらまくためグロチウスは議長に決闘を挑み、殺害に成功したのだと」
「過大評価にも程がありますよ」
カザルスは肩でおおげさに波をつくる。
「神様ですよ。あの現場を観ただけで、犯人がグロチウスだと看破できる人間なんて」
「そうとも言えません。皆がグロチウスを容疑者の範囲から閉め出していたのは、彼が決闘より前に死亡していたと認識していたからでしょう。そうではないと知っていた人物なら、彼と議長の死を結びつける思考も容易だったはず。それに、グロチウスを出し抜くほどの狂気めいた作戦を立案して、成功させたのも貴方です。彼の考えを理解する素養はお持ちだった」
「仮にそうだった場合、私は犯人を見抜きながら、長い間黙っていたことになるじゃないですか」
ほんの僅かに威圧を込めて、カザルスは少女の顔を覗き込んだ。
「あまりに中途半端なのでは?革命分子に力も貸さず、カヤ嬢の疑惑を晴らそうともせず、中くらいの混乱を長引かせた。なにがしたかったのでしょうね?」
「それを知りたいのは私の方です」
公女殿下は怯みもしない。澄んだ瞳をまっすぐに向けてくるだけだ。
「私は推測を述べているだけです。これ以上は、あなたの内心の問題。私にも分析はできません。あなたから教えてください」
「お伝えしたとして、この私に何の得がありますか?」
「何の恩恵もありません」
一秒だけ、二人は歩みを止めた。
「自慢話を聞いてさしあげる。それだけです」
カザルスは返答に迷う。
この少女、案外、子供っぽい側面を持っている。
「仮定の話でも、よろしいでしょうか」
ずるい大人の逃げ方を思いついた。
「私よりちょっぴり賢い人間が今回のような状況でどう考えるものか、それを推量するだけでも、よろしいですか?」
「かまいません」
「そういう人間が存在するなら、彼は民衆を恐れていたに違いありません」
「それは、我が国の民衆ですか」
「すべての民草です。二つの国で成立した革命と称される出来事は、民衆が国をひっくり返した、というだけの単純な話ではないのです。あらゆる国家の民衆が、公国やフランスの民のように変貌する可能性を秘めている。何百年もの間、まつりごとなど偉い人にまかせておけばいい、と信じ込んでいた連中が、政治を自分たちの問題であると見なすようになりました。国家というものは国民が存在しなければ立ち行かないものなのだと理解したからです。ならば自分たちにも国家の運営に口を出す権利があるのだと悟り、声を上げ始めた。彼らの求めに応じ、支配者たちは参政権だの給付金だのを与えなければならなくなった。
引き替えに国家が手に入れるのは、忠誠を誓ってくれる兵隊です。自らを国家の一部と見なしている市民は、自身を守るように国を守る。さほど関わりのない僻地の戦いさえ、故郷を守るような情熱を持って戦ってくれる。大変魅力的な手札です。一度使ったら、もう手放すことはできないほどの」
「それは」
公女殿下は顎の角度を変えた。
「議会民主制を採る国家に限った話ではないのですね」
「ご推察の通りです」
カザルスは飲み込みの早さを誉めて差し上げたくなった。
「王であれ、大統領であれ、その権力の源泉を民衆に依らねばならない世の中が到来したのです。それは、毒杯かもしれません。じじつフランス政府は強大な国民軍を手に入れましたが、副作用として惨劇にも見舞われた。パリで、リヨンで、ブルターニュで…… 判明しているだけでも二十万人以上の市民が、革命に協力しなかったという理由で虐殺の憂き目に遭いました。手を下したのは、『正しい市民の』軍隊でした」
「本当に外国の事情に通じておられるのですね」
「私の本分は情報収集ですので」
カザルスはかけていないメガネを直す仕草をする。
「報告書を読むだけに留まらず、亡命者から詳細を聴いたりもしています。彼らの口から伝わってくるのは、よくも悪くも、すさまじい熱気です。革命の興奮、虐殺の酸鼻。雪崩のようにすべてを飲み込み、業火のように焼き尽くす民衆の暴力性……私自身、フランスに出向いたわけではありませんが、その恐ろしさは身に染みてわかりました。
しかし、この国に住む大半の人間はそうじゃあない。気付いた頃には、手遅れになっているかもしれない。だから」
声を落とし、カザルスは公女殿下に顔を近付けた。
「教育して差し上げたのですよ。危機感のない方々をね」
「それが目的ですか。犯人の心当たりがありながら、指摘もしなかった理由ですか」
少女からも、挑むように顔を近付けてくる。
「疑心暗鬼を膨らむだけ膨らませ、暴動寸前にまで持ち込んだ。そうして弟や評議員の方々を含めた権力者たちに、民草の恐ろしさを『学習』させたのですか。いよいよ危なくなったら、犯人の正体に気付いたと公表すればいい―――そういう計画だったわけですか」
「これは仮定の話ですから」
カザルスは頭を後ろに引いた。
「私は議長が犯人だったなんて思いもよりませんでしたし、知らなかった以上、黙っていたということもありません。グロチウスだって、殺してなんかいませんよ」
「そうでしたね、仮定のお話でしたね」
公女殿下は眼を細めた。
「それではバンド氏が革命派だったことも、ご存じなかったと」
「もちろんです。彼を操っていたわけでもない」
「ではグロチウスが死亡して以降、この国に陰謀の主は不在だったと?すべてを操る元凶のような存在はあり得なかったと、そうおっしゃいたいのですね」
「それは少し違います」
カザルスは首を振り、崩れかけていた髪を整えた。
「元凶、という意味合いとは少し異なりますが、騒動の核となるものは確かにありましたよ。ある意味でそれは、皆を支配していた神のような存在です」
「それは、誰ですか」
予想外の返答だったらしく、少女の瞳が揺れた。
「『決闘の王子』その人ですよ」
「それは弟のことですか」
眼を大きくした公女殿下に、カザルスは上機嫌になった。
「摂政殿下だけではありません。摂政殿下もその一部を担っておられた、決闘の王子と呼ばれる幻のことです」
カザルスはデジレ荘で見た、孔雀男の幻影を思い出していた。
「全ての始まりは、王都に押し寄せた革命軍を食い止めるために思いついた、選抜民兵の指揮官を摂政殿下に引き受けていただくという奇策でした。『決闘の王子』は他国にも膾炙している物語であるから、主人公と同一視できるような少年を戦場に送り込めば、きっと革命軍は王都よりそちらを優先してくれる、と期待したものです。最初の発案者は議長閣下で、時間稼ぎをしてもらっている間に敵国へ攻め入るというのは私が付け加えた策ですが――まあ、その部分はどうでもよろしい。問題は、この作戦が上手くはまりすぎたという話です。
ただ陣中にいるばかりでなく、前線にまで出て兵士を鼓舞された摂政殿下は、兵士のみならず民衆に広く支持される存在へと成長された。これに議長閣下は危惧を覚え、グロチウスはそうした議長の心理を読みとったからこそ、決闘を持ちかけたのです。
ある意味で、グロチウスも議長閣下も、決闘の王子という幻に踊らされていた」
カザルスは目線を斜めに動かし、踊り続けている摂政殿下とカヤ嬢を見つけて微笑した。
「一連の騒動で、摂政殿下は次から次へと巻き起こった問題に、日々苦闘されているご様子でした。ご自身はこの一ヶ月、騒動の嵐の中を彷徨していたように感じておられるかもしれません。
しかしながら、嵐を巻き起こしていたのは、ある意味で殿下ご自身なのです。殿下もその一部である巨大なうねり――実体があるともないとも判別できない『決闘の王子』こそがこの騒動の支配者であり、創造主でもあったのですからね」
「弟が聞いたら、何というでしょうね」
公女殿下も視線を弟君へと動かした。もう踊り飽きたのか、少年君主はカヤ嬢と共に広間を離れて行く。
「まあ、とにかくそういうわけでして」
ありったけの誠実さを込めて、カザルスは笑う。
「今回の危難は幻が巻き起こしたものであり、私に何の責任もないと信じていただけたなら、じつに幸いですな」
「……心の底から納得できました」
無表情のまま少女は言う。
「貴方があまりに度しがたいお方であるということに」
「それは残念」
十秒程会話が止まる。
少女の冷たい手と視線に居心地の悪さを感じながら、カザルスはワルツに集中していた。
とりとめのない思考が頭をよぎる。
どうして大抵の舞には円運動が混ざっているのだろう。
おそらく、日常生活で弧を描く足運びなど使う機会がないからだ。踊る間、日常を忘れ、演奏が終われば、また日常へ還る。ならば踊りながらこんな話題に興じている俺たちは、とんだ野暮と笑われるべきだろう。
「あなたは神様になりたいのですか」
出し抜けに少女から投げかけられた質問に、カザルスは驚いた。
「いるのでしょうか。なりたくない人間なんて。人は万能を求めます。上昇を求めます」
「そうかもしれませんね。けれどもどれほど優秀で、高みに届いた人間でも、神様にはなれない」
こんなに美しい表情ができるものか、と感嘆するほどの笑顔が、少女の顔に咲いた。
視界の隅で、銀色が光る。
いつの間にかカザルスから離れていた少女の右手が、拳銃を握っていた。
「さようなら」
ごつりと、脇腹に銃口が押し当てられた。
ぱちん、と泡の砕けるような音が周囲に響いたが、誰一人として注意を牽かれなかった様子だ。ワルツの輪は止まらない。
ただ親指の先程度の大きさしかない茶色の球体が床を転がり、楽団員の足に跳ね返って、もう一度カザルスの足下に戻ってきた。玩具の拳銃から発射されたコルク玉だ。
「戯れです。ご容赦を」
コルクを拾い、公女殿下はにこりともせずに言う。
カザルスの額に汗が伝っている。少女がハンカチで拭ってくれた。二人は舞を止め、広間から離れる。
「それでは、失礼します。とても楽しかったです」
もう一度、魅力的な笑顔を見せて、公女殿下は去った。
つられたように笑っていたことに気付き、大したものだ、とカザルスは自分を誉めたくなった。
そして掌を頬に沿わせる。
なぜか連想したのは、遠い昔の出来事。生まれて初めて女性に頬を叩かれた思い出だった。
カザルスは警戒心を表に出さないよう注意しながら、少女の手を取った。
ワルツの相手を務めてくれるのは、摂政殿下の姉君だ。これまで友好的とは言えない態度を見せられていた上に、好んでこのような場にやってくるような性格ではないだろうと思い込んでいた。
「必要と感じたなら、踊りますよ。ワルツくらい」
ニコラの返事はそっけない。
「必要とは」
カザルスは少女の腕を優しく誘い、立ち位置を変える。
「私の機嫌をとる必要ですか」
「あなたとお話する必要です」
少女は愛想笑い一つ見せない。
「お窺いしたかったのです。議長閣下の死に関して、どのように考えておられますか」
「考えるもなにも、感心させられるばかりでした。まさか、犯人があのグロチスウスだったとは!おのれの不明を恥じるばかりです」
「本当ですか」
少女の瞳は冷たい。しなやかな手つきで身を揺らし、右方向へターンした。
「少将も気付いていらっしゃるのでは?孔雀男の説明には矛盾点が混ざっていたことを」
「穏やかではありませんね」
カザルスは驚く振りをした。
「この期に及んで、真犯人は別にいると?」
「そこまで重大な間違いではありません」
少女の指先に力がこもる。
「グロチウスが議長を殺したという事実は変わりません。しかし、あの場にいた人々を納得させるために、孔雀男があえて言及しなかった要素があるのです」
「どの部分でしょう。私には想像もつかないな」
少女はカザルスの瞳を覗き込んできた。
「例の外套です。隠し倉庫で見つかった外套を折り畳んで決闘台の絨毯に置くと、絨毯の血糊が欠けていた部分と一致した。冷静に考えると、これはおかしな話です」
「どうしてです。一致したからこそ、カヤ嬢の無罪が確定したのではないですか」
「そのこと事体は間違っていません」
カザルスの肩から少女は手を離した。
「問題は、グロチウスが死亡していたという事実です。あの決闘でグロチウスも負傷したに違いない、と孔雀男は推測していましたが、それならグロチウスは負傷した体の上に外套をまとって外へ出て行ったことになってしまいます」
「なるほど」
近くで摂政殿下とカヤ嬢が踊っている。カザルスが会釈すると、殿下は不振そうに眉を寄せた。
カザルスは声を小さくする。
「その場合、議長の血で汚れた外套に、グロチウス自身の血も染み込んだはず。すると折り畳んだ外套の血痕が、絨毯の欠落とぴったり一致するのはおかしい、という理屈ですね?」
公女は頷いた。
「つまり、グロチウスは決闘で負傷したわけではない。議長を殺めた直後は健康そのものだったのに、二日後には死体になっていた。遺体がどういう状況だったのか、私は資料を見てはいませんが、しばらくの間、戦死だったと思われていたのですから、銃弾を浴びた状態だったはずです」
「おっしゃる通り、胴体に数発の銃弾が命中していました」
カザルスは意図的にステップのペースを上げた。動揺も見せず、付いて来る。
「結論から言いますと、グロチウスはいばら荘を出て国境付近へ戻る際に、誰かに射殺されたのです」
少女はすらすらと話した。
「それは……少々粗い筋立てではありませんか」
カザルスは唇を曲げる。
「議長に撃たれた部分が、たまたま出血しない箇所だったのかもしれません。あるいは完璧な手当を施したので、血は滲まなかったのかも。外套と、絨毯の血痕が一致しないというだけでは、根拠としては少し、弱い」
「遺体に銃弾は残っていたのですか」
公女は引き下がらない。
「決闘で負傷したのであれば、議長が特注した弾丸が体内に残っているかもしれません」
「遺体はすでに、共和国へ移送しています」
カザルスは頭を振った。
「銃弾は摘出した後、廃棄してしまいました。まさかそのような確認が必要になるとは思いもよらなかったものでね」
「では確認は不可能ですね」
だしぬけに少女は後退した。
「そう考えたからこそ、孔雀男はこの件に言及しなかったのです。あの場で優先するべきは、犯人の正体を明らかにすること、それを群衆に納得させることでしたから」
「しかし貴女は納得されてはいないのですね」
「していません。論証材料は乏しく、今後も手に入らないでしょう。けれども推測は可能です。グロチウスが北方で射殺されていたとしたら、相手は誰だったのか」
「事情を知らない我が軍の兵士の仕業だったかもしれませんよ。怪しい人影を見たから発砲した結果、致命傷になったとか」
「そうかもしれません。その場合、その兵士は何故グロチウスを発見できたのでしょうか。あらかじめ、周辺を見張るよう上官から指示があったのでは?」
「それはまあ」
カザルスは天井を眺める。
「戦争が終わってからも、敗残兵が農家を襲うおそれもありますから、ある程度の網は張り巡らせていますがね」
「そもそも皆が、『グロチウスは戦場で命を落とした』と思いこんでいた原因は何だったでしょうか」
少女の眼差しが、氷の鋭さでカザルスに迫り来る。
「それは、権威ある将官であり、この戦いの殊勲でもあるカザルス少将が、そうに違いない、と仰ったからでは?」
フルートのト単調が広間を切り裂いた。
「ははは」
カザルスはあえて悪役を意識した笑い方を選んだ。
「不徳の極みですな。見間違いと思いこみが疑いに繋がってしまうとは」
「否定されるならされるで結構です。これは推測に過ぎませんから」
「いや、面白いお話です。続きを聞かせていただけますか?」
「あの戦場で、あなたはグロチウスが本国への退却に加わらず、単騎で王都の方へ戻ったらしいと情報を掴んだ。その情報を、誤報と断じて手元で握りつぶした上で、彼は戦死したにちがいないと宣言した」
「目的は?」
「今回、騒ぎになったように、あなたもグロチウスが軍上層部の誰かと繋がっているのではないかと睨んだのでしょう。グロチウスはわざわざ敵地へ引き返したのですから、そう疑って当然です。証拠を掴んだら、今後の役に立つかもしれない。だから泳がせることに決めたのです。グロチウスが王国のどこに潜伏しているかまでは予想できなかったので、帰還する際の道筋を予想して、網を張った。
果たして数日後、王都から戻ってきたグロチウスを補足することに成功した……場所や詳しい状況は分かりませんが、おそらくあなたは一人でグロチウスと対面した。一人でも同席者がいたならば、彼が生存している事実は隠し通せないだろうと判断して、公表したと思われますから」
おや、とカザルスは嬉しくなった。自分はこの少女に思ったより評価されているようだ。同席者を口封じに殺したと決めつけられない程度には。
「その仰り方ですと、私が意図的にグロチウスを殺害したとはみなしておられないようですね」
「事故に近いものだったでしょうね」
公女殿下はそっけない。
「グロチウスは、王都方面へ戻った理由を知られたくなかったでしょうから、なんとかあなたを振り切ろうとしたのでしょう。成り行きで撃ち合いとなり、彼を射殺してしまった貴方は、『やはりグロチウスは戦死していた」と皆に納得させるため、遺骸を冷水に沈めて、腐敗が進行していない点を偽装したのです」
「その段階で、彼の死んだ日付を誤魔化す理由が私にありますか?」
「ありのままを伝えない方がよいと判断したのでしょう。グロチウスの内通者が国内に存在した場合、彼が殺された事実には驚くでしょうが、死亡日が勘違いされている点は歓迎するだろうと予測したのでは」
今度はイオナ夫妻が近くを通ったので、公女殿下はコレートと会釈を交わした。
「その後数日、あなたは観察に徹した。やがて議長と連絡がとれない状況になっているとの報告を受け、私たちとともにいばら荘へ出向き、そこでグロチウスの目的を把握した。我が国に混乱をばらまくためグロチウスは議長に決闘を挑み、殺害に成功したのだと」
「過大評価にも程がありますよ」
カザルスは肩でおおげさに波をつくる。
「神様ですよ。あの現場を観ただけで、犯人がグロチウスだと看破できる人間なんて」
「そうとも言えません。皆がグロチウスを容疑者の範囲から閉め出していたのは、彼が決闘より前に死亡していたと認識していたからでしょう。そうではないと知っていた人物なら、彼と議長の死を結びつける思考も容易だったはず。それに、グロチウスを出し抜くほどの狂気めいた作戦を立案して、成功させたのも貴方です。彼の考えを理解する素養はお持ちだった」
「仮にそうだった場合、私は犯人を見抜きながら、長い間黙っていたことになるじゃないですか」
ほんの僅かに威圧を込めて、カザルスは少女の顔を覗き込んだ。
「あまりに中途半端なのでは?革命分子に力も貸さず、カヤ嬢の疑惑を晴らそうともせず、中くらいの混乱を長引かせた。なにがしたかったのでしょうね?」
「それを知りたいのは私の方です」
公女殿下は怯みもしない。澄んだ瞳をまっすぐに向けてくるだけだ。
「私は推測を述べているだけです。これ以上は、あなたの内心の問題。私にも分析はできません。あなたから教えてください」
「お伝えしたとして、この私に何の得がありますか?」
「何の恩恵もありません」
一秒だけ、二人は歩みを止めた。
「自慢話を聞いてさしあげる。それだけです」
カザルスは返答に迷う。
この少女、案外、子供っぽい側面を持っている。
「仮定の話でも、よろしいでしょうか」
ずるい大人の逃げ方を思いついた。
「私よりちょっぴり賢い人間が今回のような状況でどう考えるものか、それを推量するだけでも、よろしいですか?」
「かまいません」
「そういう人間が存在するなら、彼は民衆を恐れていたに違いありません」
「それは、我が国の民衆ですか」
「すべての民草です。二つの国で成立した革命と称される出来事は、民衆が国をひっくり返した、というだけの単純な話ではないのです。あらゆる国家の民衆が、公国やフランスの民のように変貌する可能性を秘めている。何百年もの間、まつりごとなど偉い人にまかせておけばいい、と信じ込んでいた連中が、政治を自分たちの問題であると見なすようになりました。国家というものは国民が存在しなければ立ち行かないものなのだと理解したからです。ならば自分たちにも国家の運営に口を出す権利があるのだと悟り、声を上げ始めた。彼らの求めに応じ、支配者たちは参政権だの給付金だのを与えなければならなくなった。
引き替えに国家が手に入れるのは、忠誠を誓ってくれる兵隊です。自らを国家の一部と見なしている市民は、自身を守るように国を守る。さほど関わりのない僻地の戦いさえ、故郷を守るような情熱を持って戦ってくれる。大変魅力的な手札です。一度使ったら、もう手放すことはできないほどの」
「それは」
公女殿下は顎の角度を変えた。
「議会民主制を採る国家に限った話ではないのですね」
「ご推察の通りです」
カザルスは飲み込みの早さを誉めて差し上げたくなった。
「王であれ、大統領であれ、その権力の源泉を民衆に依らねばならない世の中が到来したのです。それは、毒杯かもしれません。じじつフランス政府は強大な国民軍を手に入れましたが、副作用として惨劇にも見舞われた。パリで、リヨンで、ブルターニュで…… 判明しているだけでも二十万人以上の市民が、革命に協力しなかったという理由で虐殺の憂き目に遭いました。手を下したのは、『正しい市民の』軍隊でした」
「本当に外国の事情に通じておられるのですね」
「私の本分は情報収集ですので」
カザルスはかけていないメガネを直す仕草をする。
「報告書を読むだけに留まらず、亡命者から詳細を聴いたりもしています。彼らの口から伝わってくるのは、よくも悪くも、すさまじい熱気です。革命の興奮、虐殺の酸鼻。雪崩のようにすべてを飲み込み、業火のように焼き尽くす民衆の暴力性……私自身、フランスに出向いたわけではありませんが、その恐ろしさは身に染みてわかりました。
しかし、この国に住む大半の人間はそうじゃあない。気付いた頃には、手遅れになっているかもしれない。だから」
声を落とし、カザルスは公女殿下に顔を近付けた。
「教育して差し上げたのですよ。危機感のない方々をね」
「それが目的ですか。犯人の心当たりがありながら、指摘もしなかった理由ですか」
少女からも、挑むように顔を近付けてくる。
「疑心暗鬼を膨らむだけ膨らませ、暴動寸前にまで持ち込んだ。そうして弟や評議員の方々を含めた権力者たちに、民草の恐ろしさを『学習』させたのですか。いよいよ危なくなったら、犯人の正体に気付いたと公表すればいい―――そういう計画だったわけですか」
「これは仮定の話ですから」
カザルスは頭を後ろに引いた。
「私は議長が犯人だったなんて思いもよりませんでしたし、知らなかった以上、黙っていたということもありません。グロチウスだって、殺してなんかいませんよ」
「そうでしたね、仮定のお話でしたね」
公女殿下は眼を細めた。
「それではバンド氏が革命派だったことも、ご存じなかったと」
「もちろんです。彼を操っていたわけでもない」
「ではグロチウスが死亡して以降、この国に陰謀の主は不在だったと?すべてを操る元凶のような存在はあり得なかったと、そうおっしゃいたいのですね」
「それは少し違います」
カザルスは首を振り、崩れかけていた髪を整えた。
「元凶、という意味合いとは少し異なりますが、騒動の核となるものは確かにありましたよ。ある意味でそれは、皆を支配していた神のような存在です」
「それは、誰ですか」
予想外の返答だったらしく、少女の瞳が揺れた。
「『決闘の王子』その人ですよ」
「それは弟のことですか」
眼を大きくした公女殿下に、カザルスは上機嫌になった。
「摂政殿下だけではありません。摂政殿下もその一部を担っておられた、決闘の王子と呼ばれる幻のことです」
カザルスはデジレ荘で見た、孔雀男の幻影を思い出していた。
「全ての始まりは、王都に押し寄せた革命軍を食い止めるために思いついた、選抜民兵の指揮官を摂政殿下に引き受けていただくという奇策でした。『決闘の王子』は他国にも膾炙している物語であるから、主人公と同一視できるような少年を戦場に送り込めば、きっと革命軍は王都よりそちらを優先してくれる、と期待したものです。最初の発案者は議長閣下で、時間稼ぎをしてもらっている間に敵国へ攻め入るというのは私が付け加えた策ですが――まあ、その部分はどうでもよろしい。問題は、この作戦が上手くはまりすぎたという話です。
ただ陣中にいるばかりでなく、前線にまで出て兵士を鼓舞された摂政殿下は、兵士のみならず民衆に広く支持される存在へと成長された。これに議長閣下は危惧を覚え、グロチウスはそうした議長の心理を読みとったからこそ、決闘を持ちかけたのです。
ある意味で、グロチウスも議長閣下も、決闘の王子という幻に踊らされていた」
カザルスは目線を斜めに動かし、踊り続けている摂政殿下とカヤ嬢を見つけて微笑した。
「一連の騒動で、摂政殿下は次から次へと巻き起こった問題に、日々苦闘されているご様子でした。ご自身はこの一ヶ月、騒動の嵐の中を彷徨していたように感じておられるかもしれません。
しかしながら、嵐を巻き起こしていたのは、ある意味で殿下ご自身なのです。殿下もその一部である巨大なうねり――実体があるともないとも判別できない『決闘の王子』こそがこの騒動の支配者であり、創造主でもあったのですからね」
「弟が聞いたら、何というでしょうね」
公女殿下も視線を弟君へと動かした。もう踊り飽きたのか、少年君主はカヤ嬢と共に広間を離れて行く。
「まあ、とにかくそういうわけでして」
ありったけの誠実さを込めて、カザルスは笑う。
「今回の危難は幻が巻き起こしたものであり、私に何の責任もないと信じていただけたなら、じつに幸いですな」
「……心の底から納得できました」
無表情のまま少女は言う。
「貴方があまりに度しがたいお方であるということに」
「それは残念」
十秒程会話が止まる。
少女の冷たい手と視線に居心地の悪さを感じながら、カザルスはワルツに集中していた。
とりとめのない思考が頭をよぎる。
どうして大抵の舞には円運動が混ざっているのだろう。
おそらく、日常生活で弧を描く足運びなど使う機会がないからだ。踊る間、日常を忘れ、演奏が終われば、また日常へ還る。ならば踊りながらこんな話題に興じている俺たちは、とんだ野暮と笑われるべきだろう。
「あなたは神様になりたいのですか」
出し抜けに少女から投げかけられた質問に、カザルスは驚いた。
「いるのでしょうか。なりたくない人間なんて。人は万能を求めます。上昇を求めます」
「そうかもしれませんね。けれどもどれほど優秀で、高みに届いた人間でも、神様にはなれない」
こんなに美しい表情ができるものか、と感嘆するほどの笑顔が、少女の顔に咲いた。
視界の隅で、銀色が光る。
いつの間にかカザルスから離れていた少女の右手が、拳銃を握っていた。
「さようなら」
ごつりと、脇腹に銃口が押し当てられた。
ぱちん、と泡の砕けるような音が周囲に響いたが、誰一人として注意を牽かれなかった様子だ。ワルツの輪は止まらない。
ただ親指の先程度の大きさしかない茶色の球体が床を転がり、楽団員の足に跳ね返って、もう一度カザルスの足下に戻ってきた。玩具の拳銃から発射されたコルク玉だ。
「戯れです。ご容赦を」
コルクを拾い、公女殿下はにこりともせずに言う。
カザルスの額に汗が伝っている。少女がハンカチで拭ってくれた。二人は舞を止め、広間から離れる。
「それでは、失礼します。とても楽しかったです」
もう一度、魅力的な笑顔を見せて、公女殿下は去った。
つられたように笑っていたことに気付き、大したものだ、とカザルスは自分を誉めたくなった。
そして掌を頬に沿わせる。
なぜか連想したのは、遠い昔の出来事。生まれて初めて女性に頬を叩かれた思い出だった。