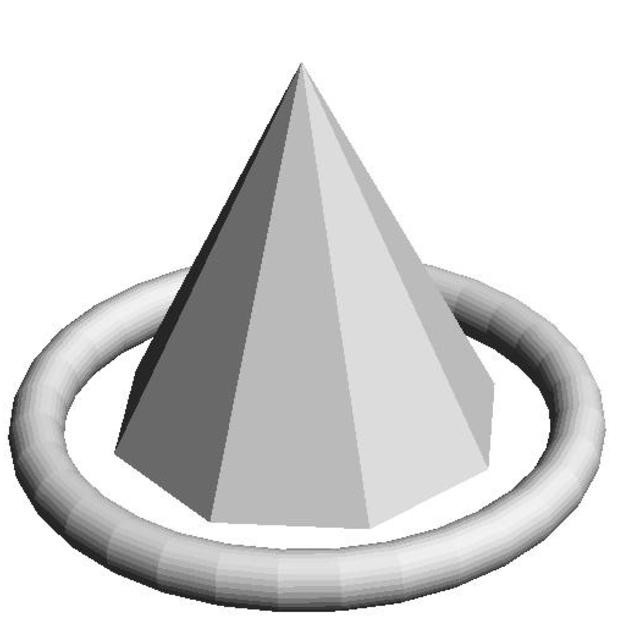議長と老僕
文字数 7,407文字
「見張り台、ですか」
最上階へ戻り、隠し通路の入り口を監視していた見張りが存在した可能性について勢い込んで訊ねたサキだったが、バンドの返答は芳しいものではなかった。
「たしかにあの塔は城周辺を監視する目的のために設けられたものではございますが、常駐の監視要員は割り当てられておりません。この近辺で動乱が発生する事例は、ほとんどございませんでしたので……」
「いいえ、監視役はいたはずなんです。すくなくとも、当日は」
サキは怯まない。
「ついさっきまで考えもしなかった話ですけれど、カヤが犯人でないとしたら、犯行当時、少なくとも二人の人間が隠し通路から出入りしていたことになります」
「それは、そうでございますね」
「あの隠し通路に鍵は必要なかった。そしてニコラは、自分の好きなときにあの部屋を訪れていた。だから決闘の最中にカヤが部屋に入ってくる可能性も考えられたはずです」
「それは確かに」
バンドは両目を大小させた。
「カヤの安全を考慮する意味でも、決闘相手を秘匿する意味でも、カヤが決闘相手とはち合わせる状況は避けたかったはず。そのためには当日、隠し通路の入り口を誰かに監視させる必要があったと思われますし、議長なら手を打っていたでしょう」
「なる、ほど」
バンドは拳と掌をすり合わせた。
「議長が入り口の監視を誰かに任せていたと仮定した場合、それは使用人の誰だと思いますか」
サキの質問に、赤薔薇家家宰は懐から帳面を取り出した。
「当館の使用人が何時、どのような業務に携わるかは私が分刻みで管理しております。旦那様の意向が優先されるのは当然でございますので、その場合のズレも記録しておりまして・・」
帳面を顔に近づける。近眼なのか、字が小さいのか。
「ふむ、この時間、旦那様の意向で持ち場を離れた使用人が一人おりました。掃除夫のゲラクという男にございます」
「掃除夫、ですか。掃除夫を見張り台に立たせるものですか?」
「掃除夫と申しましても、旦那様が戦場に出ておられた時分には、従者を務めていた男にございますので、荒事も理解しております。もう七十近いので年金を与えて城の裏手に住まわせておりますが、体を動かさないと錆び付くと申しますので、掃除の一端をまかせております次第でして」
これだけ広大な別荘地だ。掃除役はいくらいても足りないのだろう。
「話を聞きたい。会わせてもらえますか」
「ご案内差し上げるのはやぶさかではございませんが、その……」
バンドは眉根を寄せた。
「少々変わり者でございまして、ご無礼を申し上げるかもしれませんので、お許しいただけますように」
その小屋は、小屋という呼称が、ぎりぎり許されるような建造物だった。何も知らない者が見たら、建物と認識するかさえ怪しい。
レンガを積み上げた立方体から、人間が生活できる最低限の体積分だけ穴を穿ったような構造物。レンガは城館に使用されているものと同じだが、ひび割れが目立つので、不良品を転用しているのかもしれない。
バンドが呼びかけると、穴から小男がのそりと姿を見せた。
小綺麗な浮浪者、というのがサキの抱いた第一印象だった。王都や黒繭家領内の屋台付近でよく見かける人種だ。髭も髪も伸び放題だが、悪臭は漂わせていない。毎日、川や水路で丁寧に洗っているからだ。下層階級にも風呂や選択という習慣が普及している王国では、不潔でいることが社会からの阻害要因となり得る。
言うならば、かろうじて社会の隅っこに引っかかっているような人間たち。
サキを眼にして、ゲラクが口にした言葉は、
「あんた、王様か?」
なるほど、無礼だ。しかし腹は立たない。言葉遣いは丁寧でも、敬意のかけらも持っていない連中に揉まれてきたせいだろうか。
「うん、まあ、そういうようなものだ」
サキは曖昧に肯定する。
「早速だけど、議長が亡くなった日の話を聞かせて欲しい」
髭の中の両目が猜疑心を漂わせている。当たりだな、とサキは期待する。隠し通路を最初に検分したとき、見張り台から見下ろしていたのは、多分、この顔だ。
「隠し通路の入り口を知っているね?あの日、議長に指示されて入り口を監視していた人間を探している。もし君がそうだったら、教えて欲しい」
「はな、はな」
言葉の発し方に戸惑うように、老人は単語を繰り返した。
「話すことなんか、なんにもねえっ」
吐き出すように叫ぶ。それから深呼吸を一回して、
「話すことなんか、なんにもねえっ」
のしのしと、部屋に戻ってしまった。
「……申し訳ございません」バンドが頭を下げて謝罪するので、大丈夫、とサキは答える。
「どうして証言を拒むのでしょう」
「あのような半・世捨て人ですが、おおまかな風聞は伝わってくるのでしょう」
バンドは哀れむように話す。
「殿下が議長と対立されていた事情を知っていて、警戒したのかもしれません」
べつに、対立ってわけじゃあないけど。サキは巨人の顔を頭に描いた。彼が生きていた間は、一方的に利用されて終わっただけだ。恨み、報復を考えてもよさそうなものだが、現在、思い出しても、悪感情はまるで生まれてこなかった。どちらかというと自分を執念深い性格と見なしていたサキは、少々意外に思った。もしくは死んでしまった人間なんかに対して感情を使うなんてもったいないと感じる酷薄な性格なのかもしれない。
誤解を解くにはどうしたらいいだろう。無理矢理白状させても、真実を口にするとは限らない。
バンドに礼を言って、城内へ戻らせる。しばらくの間、サキはこの場に留まることを決めた。
小屋から少し離れた位置に、いばらを切り開いて耕したらしい小振りな畑があった。季節は初冬、畝が連なっているだけで、農業に明るくないサキには、何を育てる畑なのかもわからない。
畑の前に、数本分の切り株が並んでいた。 その中の一つに、サキは腰掛ける。
小一時間ほどが経過した。途中で画工の一人がやってきて、今のところめぼしい発見はないと伝えてくれた。調査を継続するようにサキは返事する。
正午をすぎたころ、小屋からゲラクが顔を出した。サキを見て不快そうに両目を見開いたが、すぐに切り株が並ぶ場所にやってきた。
「だめだったかな。座ったら」
サキの問いに、ゲラクは髭の周囲をもぐもぐと動かした。
「別に」
ゲラクはサキから左に三つ置いた切り株に腰掛ける。
しばらくの間、二人とも何も話さなかった。
死んでしまったあの少年を、サキは思い出した。
彼に会ったなら、姉の言っていた信念とやらが手に入るかもしれないと期待していたが、そんなに甘い話ではなかった。それでもある種のコツのようなものを掴みはしたらしいと今になって理解し始めている。信念とはほど遠いが、自分のような位置にいる人間にとって有用な心構えだ。
領内に格安の劇場や屋台の存在を許している黒繭家の性質上、サキは幼い頃から同階級の貴族や身の回りを世話させる使用人だけでなく、庶民も視界に入る状況で日々を過ごしてきた。それが貴族として必ずしも標準的な日常ではないと知ったのは最近のことだ。田舎暮らしの貴族など、庶民の姿を眼にすることさえ嫌い、使用人に対してさえ、最低限の接触しか許さないという極端な事例もあるらしい。
サキの場合、彼らと言葉を交わす機会には恵まれていたので、嫌悪しているわけではなかった。(皆、芝居や決闘に酔いしれているところはいただけなかったが)
ただし理解も共感もしていなかった。
何年か前、町中で雇い主に叱咤される日雇い人夫らしき男を見かけたことがある。大事な荷を地面に叩きつけて台無しにしてしまった様子だった。激怒して唾をとばし、罵り続ける雇用主に対して、人夫は地面に頭をこすりつけて謝罪を繰り返していた。
―――よくもまあ、あんなふうに卑屈にふるまえるものだ。
あきれかえったのを憶えている。もし、自分が彼の立場だったとしたら、耐えきれずに一発お見舞いしているだろう。庶民というものには、「誇り」の概念がないのだな、と決め付けた。
ひどい間違いだった。
誇りを持たない者が、身を挺して同僚をかばったりできるものだろうか。誇りを持たないものが、「生きろ」と言われたことを至上の喜びとして死んでいけるものだろうか。
そもそも攻め込んできた革命軍の兵士たちにしたってそうなのだ。彼らは自発的に銃を取り、戦場へ馳せ散じた。散々苦労させられた厄介な敵だったが、その精神性は評価すべきものだった。
現在、サキは考えを改めた。どれだけ惨めな暮らしぶりをしている人間も、一片の誇りは宿している。日々の苦難で疲れ、はがれ落ちて身体のほんの一部まで擦り減ってしまったが、だからこそ硬く、強く、最後の希望として心を支えている。
サキ自身の信念は、まだ見つからない。それでも掴んだこの事実こそが、これから先を切り開くための刃となってくれそうだ。それは庶民階級に限った話でもない。
誰もが抱える誇り。
それを認め、称え、なでさすり、刺激する。そうすれば形ばかりの支配者だった自分も、本当の権力を入手できるかもしれない。
切り株に座り、サキはゲラクを見ている。
「議長とは、一度会っただけなんだ」
頃合いと判断して、切り出した。
「恥ずかしながら、議長がどういう方なのか存じ上げていなかった。だから対面したときは驚いたよ。おとぎ話の大海賊みたいな強面の巨人が目の前に現れたんだから」
苔のような髭が、わずかに動いた。
「でも思い返してみると、僕が圧倒されたのは体格や厳つい顔だけじゃなかった。ライオンなのに、狐みたいな賢さも持っていた」
少なくとも現時点で、サキは議長に対する正直な評価を語っている。嘘も誇張もない。この使用人が主人をどう思っていたかが分からないので、ありのままを語ることに決めたのだ。
「陰謀を組み立てる力、とでも言うべきかな。僕が嫌で嫌で仕方がないような仕事を引き受けざるを得なくなるように、短期間で根回しが終わっていて、もうどうしようもない状況に追い込まれてしまったんだ。今思い出しても、ぞっとする。仮にあの人が小男だったとしても、僕はあの人に太刀打ちできなかっただろう」
「そうだ」
ゲラクの顔がサキの方を向く。ようやく話に乗ってくれた。
「みんな、旦那様を、ばけものみたいにこわがってた。手もでかい。身体もでかい。声もでかい・・・こわいのは当たり前だ。けど、あの人は頭の中もでかい。知恵が回るんだ。取り澄ました学者みたいな小利口じゃねえ、もっと、なんていうか、実際の賢さだ。ただのでかぶつじゃねえ、からだも、あたまも、何もかもすごいひとだった」
「君も、議長を恐れていたのかい」
少し踏み込んだ質問かも、とサキは危惧したが、
「あの人を怖がらない方がおかしい」
ゲラクはぶっきらぼうに応じてくれた。
「さいしょは、旦那様の外側をみてこわいと思う。つきあいが長くなってくると、内側も恐ろしくなってくる」
「その議長が、いなくなってしまった」
サキは座る位置をずらし、ゲラクとの距離を少しだけ詰める。
「君も、安心している?」
眼を見開き、ゲラクはぶるぶると震え始めた。
「だんなさまには世話になった」
身を乗り出し、サキに近づこうとしたようだが、思いとどまったのか元に座りなおした。
「おれみたいな半端者を、放り出しもせず面倒を見てくださった。だから、そんなのろくでなしかもしれねえけど」
重大な秘密を打ち明けるように、掃除夫はサキの顔をまっすぐに見据えて言う。
「ほっとしている。でも、さびしいのも本当だ」
「べつに、おかしなことじゃない」
サキは軽く頷いた。
「尊敬しながら恐れてもいいし、怯えながら好きになってもいいと思うよ」
「大きい人だったんだ」
ゲラクは譫言のように話す。
「悪い心も、優しい心もでかいひとだった。逆らったり、邪魔をした人間は、酷い目にあった。でも馴染みの人間には、思いやりを下さることもあったんだ・・・」
そこでためらうように唇を閉じたが、すぐに溢れ出した。
「昔な。俺みたいなやつでも、所帯を持ってたことがあったんだ」
内心、サキはほくそ笑む。この男の昔話など、本来ならカヤの無実に関わりはない。しかし硬く閉ざされていた口が緩み始めている。人付き合いが苦手な男だからこそ、一度話し出したら止まらないのだろう。
「館の下女とねんごろになって、腹をふくらませちまったから、一緒に暮らそうかって話になった。貯金をはたいて、人に見せても恥ずかしくねえような一軒家を買って、そこで畑を耕しながら、一年くらい住んでた。なんだか毎日が明るかった。それまで目の前には何もなかったのに、急に大きな道が拓けて、そこを歩いていけるような気がしたもんだ。おれと、女房と、ガキの三人でな」
そこまで話して、ゲラクは殴られたように身を縮こまらせた。
「けど、子供が死んじまった。」
自分の言葉に打たれたように、もう一度身を震わせる。
「娘だった。まだ、つかまり立ちもできない齢だったけど、おれにはこの国一番の美人に見えた。手の形もきれいだった。その手が指先から青白くなって、顔も、全部が黒ずんで・・・医者にはみてもらったんだ。旦那様に頭を下げて、指折りの名医にも紹介してもらったけど、駄目だった、免疫がどうとか、難しい話はわからねえけれど、とにかく助けられなかった」
髭の中で、ゲラクの瞳がぐるぐると動く。もてあました感情を動力にする車輪みたいだ。
「それで、女房ともしまいになった。所帯を持ったとき、俺はこの館での勤めを辞めていた。どうしようもなくなって戻ってきたとき、だんなさまは俺を放り出したりはしなかった」
ゲラクは誰も座っていない切り株に視線を落とした。
「俺が話すガキの話を、旦那様は黙って聞いてくれた。俺はこの切り株に座って、旦那様も隣に座ってた。腰を下ろすには小さすぎる切り株の上で、夕日が落ちるまで、俺の話を聞いて下さった―――娘の話なんて大したものじゃねえ。すぐに死んじまったんだからな。『アー』って言葉を出したとか、人差し指が一番よく動いたとか、わっかみたいな巻き毛が生えてたとか、そういう、どうでもいいことを」
赤薔薇家の使用人は、あごを突き上げて祈るように空を見た。
「聞いてくれたんだ。空が真っ黒になるまで、聞いてくれたんだ」
そして今、サキも話を聞いている。
聞き役に徹したのは間違いではなかったようだ。
それきりゲラクは黙り込んでしまった。
多弁を恥じたのだろうか。
「わかったよ」
わかっていないかもしれないが、サキは決めつける。
「君は、議長が『弱かった』と思われることを怖れているんだね」
髭に包まれた口が大きく開かれる。ゲラクは驚愕したようだ。宝の隠し場所を言い当てられた表情だった。
触れた。サキは確信する。この男の大事な部分を、撫でさすってやったのだ。
「そうだ、そうだ、そうなんだよ!」
ゲラクは大声を上げる。様子を観に来た画工の一人が、怯えた顔をするくらいだった。
「だんなさまは強いひとだった!何もかもに強い人だった!ちからで押しつぶすのも、知恵でだまし尽くすのも、かんたんにこなせる人だった!」
腰を浮かし、身を揺らす。
この男にとって、グリムという主人は悪魔に近い存在だったのかも、とサキは想像する。悪魔、あるいは荒ぶる神様の類。あらゆる暴力で周囲を虐げ、怯えさせるが、力があるからこそ尊敬もされるし、希に恩恵も施す。
「まともなやり方で、殺せるようなお人じゃねえ。犯人がどんな野郎かしらねえが、きっと、とてつもなく汚い手をつかったに違いねえんだ……」
あれ、とサキは訝しむ。
「君、新聞は読まないの」
「字なんて読めねえよ」
ゲラクは吐き捨てる。
「使用人の中には読めるやつも多いが、そういう連中は俺をばかにして、教えてなんかくれねえ」
「そうか」
気の毒とも、意地が悪いともサキは言わない。替わりに、すでに公表されているこれまでの経緯をかいつまんで話した。
「議長は決闘で殺された。そうに違いないと僕は信じているんだよ」
「決闘」
しばらく下を向いて考え込んだゲラクは、
「それ、銃を使うやつか?」
「多分ね。少なくとも状況はそう示唆している」
「ああ、それなら、あるかもしれねえ」
使用人は腑に落ちたように頷いた。
「鉛玉はどうしようもねえ。だんな様でも、当たりどころが悪かったら一発だろう。そうか、決闘か……」
うんうんと繰り返し頷いている。戦場に従者として同行した経歴の持ち主だからこその感想かもしれない。
「ただ、評議会の方は別の見方をしている」
少し迷ったが、サキはニコラを犯人とする論証についても伝えることにした。ゲラクがその気になれば、使用人の誰かに教えてもらえば済む内容なので、公平な態度を示そうと思ったからだ。
「あの絵描きが、旦那様の娘・・」
ニコラが議長の実子だった事実については、つき合いの長いゲラクも初耳だったらしい。それほど驚いた風でもないのは、振り返ってみると、議長の行動に得心できるそぶりがあったということだろう。
ただしニコラ犯人説については、納得できない様子だった。
「たとえ実の娘でも、だんなさまは、銃を持った相手に油断するような人じゃねえ。そういうところも、あの人のこわさだった」
サキもゲラクの見解に大賛成だった。大貴族なら血族同士の諍いなど実例は多いはずだ。実子に対しても、全く無警戒でいるとは考えがたい話だ。
「今話した通り、僕は議長が決闘で命を落としたという論証を確実にするための材料を探している」
ようやく本題に入ることができる。押しつけがましく聞こえないよう、サキは慎重に言葉を選ぶ。
「君もこの見解に賛同してくれるのなら、証拠集めに協力してくれないだろうか」
ゲラクは観念したように肩をすくめた。
「俺は知っていることを話すだけだ。嘘の証言とかはできねえ。それでいいんだな?」
最上階へ戻り、隠し通路の入り口を監視していた見張りが存在した可能性について勢い込んで訊ねたサキだったが、バンドの返答は芳しいものではなかった。
「たしかにあの塔は城周辺を監視する目的のために設けられたものではございますが、常駐の監視要員は割り当てられておりません。この近辺で動乱が発生する事例は、ほとんどございませんでしたので……」
「いいえ、監視役はいたはずなんです。すくなくとも、当日は」
サキは怯まない。
「ついさっきまで考えもしなかった話ですけれど、カヤが犯人でないとしたら、犯行当時、少なくとも二人の人間が隠し通路から出入りしていたことになります」
「それは、そうでございますね」
「あの隠し通路に鍵は必要なかった。そしてニコラは、自分の好きなときにあの部屋を訪れていた。だから決闘の最中にカヤが部屋に入ってくる可能性も考えられたはずです」
「それは確かに」
バンドは両目を大小させた。
「カヤの安全を考慮する意味でも、決闘相手を秘匿する意味でも、カヤが決闘相手とはち合わせる状況は避けたかったはず。そのためには当日、隠し通路の入り口を誰かに監視させる必要があったと思われますし、議長なら手を打っていたでしょう」
「なる、ほど」
バンドは拳と掌をすり合わせた。
「議長が入り口の監視を誰かに任せていたと仮定した場合、それは使用人の誰だと思いますか」
サキの質問に、赤薔薇家家宰は懐から帳面を取り出した。
「当館の使用人が何時、どのような業務に携わるかは私が分刻みで管理しております。旦那様の意向が優先されるのは当然でございますので、その場合のズレも記録しておりまして・・」
帳面を顔に近づける。近眼なのか、字が小さいのか。
「ふむ、この時間、旦那様の意向で持ち場を離れた使用人が一人おりました。掃除夫のゲラクという男にございます」
「掃除夫、ですか。掃除夫を見張り台に立たせるものですか?」
「掃除夫と申しましても、旦那様が戦場に出ておられた時分には、従者を務めていた男にございますので、荒事も理解しております。もう七十近いので年金を与えて城の裏手に住まわせておりますが、体を動かさないと錆び付くと申しますので、掃除の一端をまかせております次第でして」
これだけ広大な別荘地だ。掃除役はいくらいても足りないのだろう。
「話を聞きたい。会わせてもらえますか」
「ご案内差し上げるのはやぶさかではございませんが、その……」
バンドは眉根を寄せた。
「少々変わり者でございまして、ご無礼を申し上げるかもしれませんので、お許しいただけますように」
その小屋は、小屋という呼称が、ぎりぎり許されるような建造物だった。何も知らない者が見たら、建物と認識するかさえ怪しい。
レンガを積み上げた立方体から、人間が生活できる最低限の体積分だけ穴を穿ったような構造物。レンガは城館に使用されているものと同じだが、ひび割れが目立つので、不良品を転用しているのかもしれない。
バンドが呼びかけると、穴から小男がのそりと姿を見せた。
小綺麗な浮浪者、というのがサキの抱いた第一印象だった。王都や黒繭家領内の屋台付近でよく見かける人種だ。髭も髪も伸び放題だが、悪臭は漂わせていない。毎日、川や水路で丁寧に洗っているからだ。下層階級にも風呂や選択という習慣が普及している王国では、不潔でいることが社会からの阻害要因となり得る。
言うならば、かろうじて社会の隅っこに引っかかっているような人間たち。
サキを眼にして、ゲラクが口にした言葉は、
「あんた、王様か?」
なるほど、無礼だ。しかし腹は立たない。言葉遣いは丁寧でも、敬意のかけらも持っていない連中に揉まれてきたせいだろうか。
「うん、まあ、そういうようなものだ」
サキは曖昧に肯定する。
「早速だけど、議長が亡くなった日の話を聞かせて欲しい」
髭の中の両目が猜疑心を漂わせている。当たりだな、とサキは期待する。隠し通路を最初に検分したとき、見張り台から見下ろしていたのは、多分、この顔だ。
「隠し通路の入り口を知っているね?あの日、議長に指示されて入り口を監視していた人間を探している。もし君がそうだったら、教えて欲しい」
「はな、はな」
言葉の発し方に戸惑うように、老人は単語を繰り返した。
「話すことなんか、なんにもねえっ」
吐き出すように叫ぶ。それから深呼吸を一回して、
「話すことなんか、なんにもねえっ」
のしのしと、部屋に戻ってしまった。
「……申し訳ございません」バンドが頭を下げて謝罪するので、大丈夫、とサキは答える。
「どうして証言を拒むのでしょう」
「あのような半・世捨て人ですが、おおまかな風聞は伝わってくるのでしょう」
バンドは哀れむように話す。
「殿下が議長と対立されていた事情を知っていて、警戒したのかもしれません」
べつに、対立ってわけじゃあないけど。サキは巨人の顔を頭に描いた。彼が生きていた間は、一方的に利用されて終わっただけだ。恨み、報復を考えてもよさそうなものだが、現在、思い出しても、悪感情はまるで生まれてこなかった。どちらかというと自分を執念深い性格と見なしていたサキは、少々意外に思った。もしくは死んでしまった人間なんかに対して感情を使うなんてもったいないと感じる酷薄な性格なのかもしれない。
誤解を解くにはどうしたらいいだろう。無理矢理白状させても、真実を口にするとは限らない。
バンドに礼を言って、城内へ戻らせる。しばらくの間、サキはこの場に留まることを決めた。
小屋から少し離れた位置に、いばらを切り開いて耕したらしい小振りな畑があった。季節は初冬、畝が連なっているだけで、農業に明るくないサキには、何を育てる畑なのかもわからない。
畑の前に、数本分の切り株が並んでいた。 その中の一つに、サキは腰掛ける。
小一時間ほどが経過した。途中で画工の一人がやってきて、今のところめぼしい発見はないと伝えてくれた。調査を継続するようにサキは返事する。
正午をすぎたころ、小屋からゲラクが顔を出した。サキを見て不快そうに両目を見開いたが、すぐに切り株が並ぶ場所にやってきた。
「だめだったかな。座ったら」
サキの問いに、ゲラクは髭の周囲をもぐもぐと動かした。
「別に」
ゲラクはサキから左に三つ置いた切り株に腰掛ける。
しばらくの間、二人とも何も話さなかった。
死んでしまったあの少年を、サキは思い出した。
彼に会ったなら、姉の言っていた信念とやらが手に入るかもしれないと期待していたが、そんなに甘い話ではなかった。それでもある種のコツのようなものを掴みはしたらしいと今になって理解し始めている。信念とはほど遠いが、自分のような位置にいる人間にとって有用な心構えだ。
領内に格安の劇場や屋台の存在を許している黒繭家の性質上、サキは幼い頃から同階級の貴族や身の回りを世話させる使用人だけでなく、庶民も視界に入る状況で日々を過ごしてきた。それが貴族として必ずしも標準的な日常ではないと知ったのは最近のことだ。田舎暮らしの貴族など、庶民の姿を眼にすることさえ嫌い、使用人に対してさえ、最低限の接触しか許さないという極端な事例もあるらしい。
サキの場合、彼らと言葉を交わす機会には恵まれていたので、嫌悪しているわけではなかった。(皆、芝居や決闘に酔いしれているところはいただけなかったが)
ただし理解も共感もしていなかった。
何年か前、町中で雇い主に叱咤される日雇い人夫らしき男を見かけたことがある。大事な荷を地面に叩きつけて台無しにしてしまった様子だった。激怒して唾をとばし、罵り続ける雇用主に対して、人夫は地面に頭をこすりつけて謝罪を繰り返していた。
―――よくもまあ、あんなふうに卑屈にふるまえるものだ。
あきれかえったのを憶えている。もし、自分が彼の立場だったとしたら、耐えきれずに一発お見舞いしているだろう。庶民というものには、「誇り」の概念がないのだな、と決め付けた。
ひどい間違いだった。
誇りを持たない者が、身を挺して同僚をかばったりできるものだろうか。誇りを持たないものが、「生きろ」と言われたことを至上の喜びとして死んでいけるものだろうか。
そもそも攻め込んできた革命軍の兵士たちにしたってそうなのだ。彼らは自発的に銃を取り、戦場へ馳せ散じた。散々苦労させられた厄介な敵だったが、その精神性は評価すべきものだった。
現在、サキは考えを改めた。どれだけ惨めな暮らしぶりをしている人間も、一片の誇りは宿している。日々の苦難で疲れ、はがれ落ちて身体のほんの一部まで擦り減ってしまったが、だからこそ硬く、強く、最後の希望として心を支えている。
サキ自身の信念は、まだ見つからない。それでも掴んだこの事実こそが、これから先を切り開くための刃となってくれそうだ。それは庶民階級に限った話でもない。
誰もが抱える誇り。
それを認め、称え、なでさすり、刺激する。そうすれば形ばかりの支配者だった自分も、本当の権力を入手できるかもしれない。
切り株に座り、サキはゲラクを見ている。
「議長とは、一度会っただけなんだ」
頃合いと判断して、切り出した。
「恥ずかしながら、議長がどういう方なのか存じ上げていなかった。だから対面したときは驚いたよ。おとぎ話の大海賊みたいな強面の巨人が目の前に現れたんだから」
苔のような髭が、わずかに動いた。
「でも思い返してみると、僕が圧倒されたのは体格や厳つい顔だけじゃなかった。ライオンなのに、狐みたいな賢さも持っていた」
少なくとも現時点で、サキは議長に対する正直な評価を語っている。嘘も誇張もない。この使用人が主人をどう思っていたかが分からないので、ありのままを語ることに決めたのだ。
「陰謀を組み立てる力、とでも言うべきかな。僕が嫌で嫌で仕方がないような仕事を引き受けざるを得なくなるように、短期間で根回しが終わっていて、もうどうしようもない状況に追い込まれてしまったんだ。今思い出しても、ぞっとする。仮にあの人が小男だったとしても、僕はあの人に太刀打ちできなかっただろう」
「そうだ」
ゲラクの顔がサキの方を向く。ようやく話に乗ってくれた。
「みんな、旦那様を、ばけものみたいにこわがってた。手もでかい。身体もでかい。声もでかい・・・こわいのは当たり前だ。けど、あの人は頭の中もでかい。知恵が回るんだ。取り澄ました学者みたいな小利口じゃねえ、もっと、なんていうか、実際の賢さだ。ただのでかぶつじゃねえ、からだも、あたまも、何もかもすごいひとだった」
「君も、議長を恐れていたのかい」
少し踏み込んだ質問かも、とサキは危惧したが、
「あの人を怖がらない方がおかしい」
ゲラクはぶっきらぼうに応じてくれた。
「さいしょは、旦那様の外側をみてこわいと思う。つきあいが長くなってくると、内側も恐ろしくなってくる」
「その議長が、いなくなってしまった」
サキは座る位置をずらし、ゲラクとの距離を少しだけ詰める。
「君も、安心している?」
眼を見開き、ゲラクはぶるぶると震え始めた。
「だんなさまには世話になった」
身を乗り出し、サキに近づこうとしたようだが、思いとどまったのか元に座りなおした。
「おれみたいな半端者を、放り出しもせず面倒を見てくださった。だから、そんなのろくでなしかもしれねえけど」
重大な秘密を打ち明けるように、掃除夫はサキの顔をまっすぐに見据えて言う。
「ほっとしている。でも、さびしいのも本当だ」
「べつに、おかしなことじゃない」
サキは軽く頷いた。
「尊敬しながら恐れてもいいし、怯えながら好きになってもいいと思うよ」
「大きい人だったんだ」
ゲラクは譫言のように話す。
「悪い心も、優しい心もでかいひとだった。逆らったり、邪魔をした人間は、酷い目にあった。でも馴染みの人間には、思いやりを下さることもあったんだ・・・」
そこでためらうように唇を閉じたが、すぐに溢れ出した。
「昔な。俺みたいなやつでも、所帯を持ってたことがあったんだ」
内心、サキはほくそ笑む。この男の昔話など、本来ならカヤの無実に関わりはない。しかし硬く閉ざされていた口が緩み始めている。人付き合いが苦手な男だからこそ、一度話し出したら止まらないのだろう。
「館の下女とねんごろになって、腹をふくらませちまったから、一緒に暮らそうかって話になった。貯金をはたいて、人に見せても恥ずかしくねえような一軒家を買って、そこで畑を耕しながら、一年くらい住んでた。なんだか毎日が明るかった。それまで目の前には何もなかったのに、急に大きな道が拓けて、そこを歩いていけるような気がしたもんだ。おれと、女房と、ガキの三人でな」
そこまで話して、ゲラクは殴られたように身を縮こまらせた。
「けど、子供が死んじまった。」
自分の言葉に打たれたように、もう一度身を震わせる。
「娘だった。まだ、つかまり立ちもできない齢だったけど、おれにはこの国一番の美人に見えた。手の形もきれいだった。その手が指先から青白くなって、顔も、全部が黒ずんで・・・医者にはみてもらったんだ。旦那様に頭を下げて、指折りの名医にも紹介してもらったけど、駄目だった、免疫がどうとか、難しい話はわからねえけれど、とにかく助けられなかった」
髭の中で、ゲラクの瞳がぐるぐると動く。もてあました感情を動力にする車輪みたいだ。
「それで、女房ともしまいになった。所帯を持ったとき、俺はこの館での勤めを辞めていた。どうしようもなくなって戻ってきたとき、だんなさまは俺を放り出したりはしなかった」
ゲラクは誰も座っていない切り株に視線を落とした。
「俺が話すガキの話を、旦那様は黙って聞いてくれた。俺はこの切り株に座って、旦那様も隣に座ってた。腰を下ろすには小さすぎる切り株の上で、夕日が落ちるまで、俺の話を聞いて下さった―――娘の話なんて大したものじゃねえ。すぐに死んじまったんだからな。『アー』って言葉を出したとか、人差し指が一番よく動いたとか、わっかみたいな巻き毛が生えてたとか、そういう、どうでもいいことを」
赤薔薇家の使用人は、あごを突き上げて祈るように空を見た。
「聞いてくれたんだ。空が真っ黒になるまで、聞いてくれたんだ」
そして今、サキも話を聞いている。
聞き役に徹したのは間違いではなかったようだ。
それきりゲラクは黙り込んでしまった。
多弁を恥じたのだろうか。
「わかったよ」
わかっていないかもしれないが、サキは決めつける。
「君は、議長が『弱かった』と思われることを怖れているんだね」
髭に包まれた口が大きく開かれる。ゲラクは驚愕したようだ。宝の隠し場所を言い当てられた表情だった。
触れた。サキは確信する。この男の大事な部分を、撫でさすってやったのだ。
「そうだ、そうだ、そうなんだよ!」
ゲラクは大声を上げる。様子を観に来た画工の一人が、怯えた顔をするくらいだった。
「だんなさまは強いひとだった!何もかもに強い人だった!ちからで押しつぶすのも、知恵でだまし尽くすのも、かんたんにこなせる人だった!」
腰を浮かし、身を揺らす。
この男にとって、グリムという主人は悪魔に近い存在だったのかも、とサキは想像する。悪魔、あるいは荒ぶる神様の類。あらゆる暴力で周囲を虐げ、怯えさせるが、力があるからこそ尊敬もされるし、希に恩恵も施す。
「まともなやり方で、殺せるようなお人じゃねえ。犯人がどんな野郎かしらねえが、きっと、とてつもなく汚い手をつかったに違いねえんだ……」
あれ、とサキは訝しむ。
「君、新聞は読まないの」
「字なんて読めねえよ」
ゲラクは吐き捨てる。
「使用人の中には読めるやつも多いが、そういう連中は俺をばかにして、教えてなんかくれねえ」
「そうか」
気の毒とも、意地が悪いともサキは言わない。替わりに、すでに公表されているこれまでの経緯をかいつまんで話した。
「議長は決闘で殺された。そうに違いないと僕は信じているんだよ」
「決闘」
しばらく下を向いて考え込んだゲラクは、
「それ、銃を使うやつか?」
「多分ね。少なくとも状況はそう示唆している」
「ああ、それなら、あるかもしれねえ」
使用人は腑に落ちたように頷いた。
「鉛玉はどうしようもねえ。だんな様でも、当たりどころが悪かったら一発だろう。そうか、決闘か……」
うんうんと繰り返し頷いている。戦場に従者として同行した経歴の持ち主だからこその感想かもしれない。
「ただ、評議会の方は別の見方をしている」
少し迷ったが、サキはニコラを犯人とする論証についても伝えることにした。ゲラクがその気になれば、使用人の誰かに教えてもらえば済む内容なので、公平な態度を示そうと思ったからだ。
「あの絵描きが、旦那様の娘・・」
ニコラが議長の実子だった事実については、つき合いの長いゲラクも初耳だったらしい。それほど驚いた風でもないのは、振り返ってみると、議長の行動に得心できるそぶりがあったということだろう。
ただしニコラ犯人説については、納得できない様子だった。
「たとえ実の娘でも、だんなさまは、銃を持った相手に油断するような人じゃねえ。そういうところも、あの人のこわさだった」
サキもゲラクの見解に大賛成だった。大貴族なら血族同士の諍いなど実例は多いはずだ。実子に対しても、全く無警戒でいるとは考えがたい話だ。
「今話した通り、僕は議長が決闘で命を落としたという論証を確実にするための材料を探している」
ようやく本題に入ることができる。押しつけがましく聞こえないよう、サキは慎重に言葉を選ぶ。
「君もこの見解に賛同してくれるのなら、証拠集めに協力してくれないだろうか」
ゲラクは観念したように肩をすくめた。
「俺は知っていることを話すだけだ。嘘の証言とかはできねえ。それでいいんだな?」