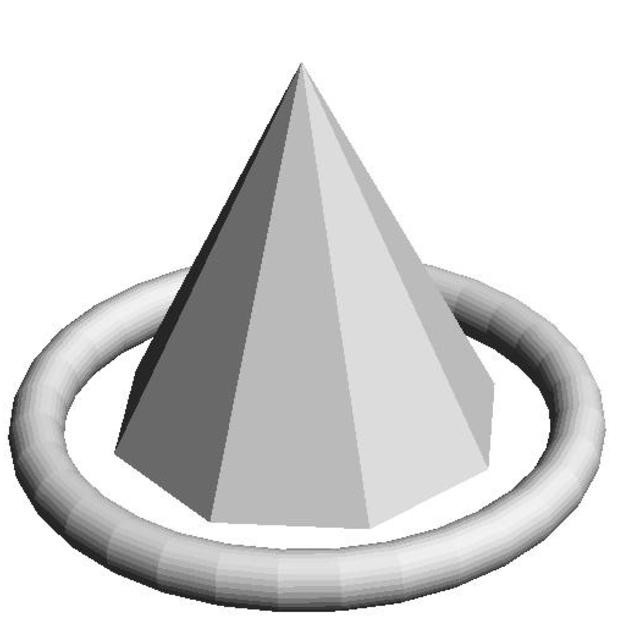戦闘開始
文字数 4,696文字
「はじまりましたよ」
傍らのフェルミが無感動に告げる。あまりに事務的な口振りだったので、サキはあやうく「何が?」と訊き返しそうになった。火蓋が切られたのだ。
指揮車の傍らの荷車に数台の遠眼鏡が積み込まれている。携帯用から、天文台で使用するような大掛かりな機械まで、用途に合わせて指揮官に供するためのものだ。
覗いてみるべきか、サキは躊躇した。居ることだけが自分の役割なので、無理をして凄惨な光景を見る必要などないのだ。ぼーっとしているうちに済んでくれたらとてもありがたい。
しかし状況は最初からこちらの不利、ぼーっとしているうちにあの世行きにもなりかねない。だから戦況を確かめたいとも思うのだけれど、覗き込んだ前線の様子が芳しくなかったら、それだけでくじけてしまいそうだ。
肉眼に映る前線は、現在、白いもやだ。
自軍の軍服軍帽と、斉射の煙がそう見せている。
ぱら、ぱらと間の抜けた響きが銃声であることにしばらく気付かなかった。
毛布にもぐり込んで聴く夕立のような気安さに、楽観に揺れたサキは、ついつい遠眼鏡を寄せた。
(見るんじゃなかった)
拡大された自軍兵士は、教本のような整った対応とはまるで遠いあわてふためき振りだった。
サキが覗いているのは、渓谷の前に陣取る味方大隊に敵の騎兵が突撃を敢行する一角だ。迫る騎兵に、銃を構えた横列が斉射を開始する。しかし各所で引き金を引けない兵士、装填すら終わっていない兵士、構えた銃口があさってを向いている兵士が弾幕に隙間をつくってしまっているため、成すすべもなく、騎兵に切り伏せられている。袈裟懸けにされた兵士が二つに割れた。それが、最初にサキが目にした戦死者だった。
「ああ」
サキの口から間抜けな声が漏れる。死を眼にするのはこれがはじめてではない。これまで決闘の立会人を務めてきたのだ。たまにインチキではなく真面目な決闘が行われるとき、ごく稀に当たり所が悪くて人死にが出る場合もあった。
しかし、そのときの死は緩慢なものだった。決闘に使用するピストルは、殺傷力の強いものではなかったからだ。血を流し、少しずつ顔色が青ざめて動かなくなる。命が失われるとは、そういう光景だとサキは思い込んでいた。
だが戦場の死は――すくなくとも最前線の死は――瞬間で終わるものだった。
マスケットに撃ち抜かれた兵士の頭部が弾け飛ぶ。木枯らしの後、枝の枯れ葉が何枚か消失するように、気づいたらなくなっている。
所どころで敵騎兵がこちらの兵士を殺し、横列に歯抜けが生じた。割合でいえば横列まで到達できた敵騎兵は少数派で、冒険はせず、一旦自陣へ旋回したため、こちらの横列自体は保たれている。ただし騎兵の突撃で時間を稼いだ分、敵の歩兵がこちらとの距離を詰めたようだ。
「なんであんなに、当たらなかったんだっ?」
サキは叫ぶ。前線の兵士は武器を放り捨てて逃げ出すほど錯乱してはいなかった。ただ、押し寄せる敵に撃ち返す弾丸が、ちっとも命中しないのだ。
「あたらない距離だからですよ」
フェルミが乾いた声で応える。
「六十ルーデ(約二百メートル)離れていればまず当たるものじゃありません」
フェルミも遠眼鏡を除きながら、
「訓練をしても、射撃の精度には限界があります。マスケットの性能も関わってきますからね。プロイセンの記録によると、二十ルーデ (約七十メートル)で射撃精度は七割程度だったそうです。 あの訓練狂いのプロイセンですらその数字ですからね。我が国の、正規軍でない奴らなら、精度はもっと落ちる」
「それなら、もっと引き付けてから撃たせればいいだろう」
「おっしゃる通りですが、その距離だと相手の命中精度も上がってしまいます。そうなると、今以上に兵士が恐慌をきたす。精度を犠牲にして離れて撃たせるか、ビビり上がる兵士を承知で近くから撃たせるか――検討した結果、離れた方が良い数字になるって結論が出ているんですよ」
「その計算は、革命軍も同じなのか」
「違います。残念ながら。おそらく革命軍の兵士は、こちらより距離を詰めてもビビることが少ない」
「訓練不足ってことか」
選抜民兵が訓練に参加するのは週に一度。その頻度が問題なのかとサキは考えた。
「それだけじゃないんです。人間の本質ってものが邪魔をするんですよ。いくらしごきあげようが、戦場に出ると兵士の何割かは動きが鈍ります。訓練では百発百中だった兵士が、本番では引き金にさえ触れなくなる場合もあるんですよ。用兵ってものは、そういう鈍りも織り込み済みで考えなくちゃあならない。兵士の働きぶりを戦場で見極め、選り分けるのが肝要なんですが……」
フェルミが軽く呻いたのに気付き、サキは双眼鏡の角度を変えた。優美な横列を維持したまま前進を続ける革命軍の歩兵たち。対して距離を稼ぐために後退をはじめた選抜民兵たちだが、ほとんど逃亡に近いような乱れっぷりだった。
「わが軍とは違うでしょう?これがグロチウスの強さです。恐怖を乗り越えて 二十ルーデ以下に立てる兵士はどいつとどいつか。連戦で擦り減り、前に出れなくなってしまった割合はどの程度か?――そういう数字を、あの老将軍は帳簿みたいにまとめているんです。戦闘の度に名簿を書き換え、適所に兵士を振り分けてる。だから行動全体にそつがない。自由・平等・博愛っていうものは、凶悪な宗教ですな」
右眼で遠眼鏡を、左眼で布陣図に挿したピンをいじりながらもフェルミは話を止めない。
「意欲が違う。献身が違う。下っ端兵士でさえ、自分が軍団を動かしている歯車の一つだと自負していやがるから、兵士の状態を一人一人確認するなんて面倒な試みにも協力的なんです。むろんグロチウスの着眼点も大したものですが」
敵将を堂々と褒める。フェルミが型破りな将官なのかそうでないのかはサキに判断できないが、有能か否かについてはすぐに明らかとなった。
「第七連隊と第二連隊はこっちにずれろ。それからこの名簿の奴らを前線に回せ」
針ねずみの布陣図を、フェルミは伝令たちに示す。伝令も各々ポケットから針と地図を取り出し、瞬く間に複製品を作り上げた。ふざけて見えるが、案外有用な連絡方法だ。ペンに比べて修正する手間がかからず、雨でインクが滲むこともない。
次にフェルミが配ったのは、活版で鮮明に刷り込まれた紙切れだった。サキに見せてくれる配慮は皆無のようで、こちらにはそれが何らかの名簿らしいことしかわからなかったが、視界を通り過ぎる名前に見知った者が含まれていた。
「フランケン?」
確かめようと手を伸ばしたら、フェルミに払いのけられる。
「あー、フランケンね。あれはいい兵士ですよ。たった今から准尉に昇進です」
眼で促された伝令たちは、リストと布陣図を持って四方へ散った。
「今の、古参兵のリストか」
「迷ったんですよ。若さと経験、どっちが役に立つかってね。遺憾ながら逆に張っちまったみたいだが、いつでも変えられるよう、準備はしていたんです」
手元に残していた一枚を、これ見よがしにひるがえす。
「訓練もさせておきました。戦場を知っている年寄り主体で動く訓練です。殿下、よもや『僕の執事を殺さないでよう』なんてお止めにはならないでしょうね」
「聞くつもりなんてない癖に」
毒づきはするが、サキはフランケンを退がらせようとは思わない。それは執事への非礼にあたるだろう。
「これで前線が落ち着いてくれるといいんですが」フェルミは布陣図を睨む。
幸いにして大佐の目論見は、ある程度の成功を収めた。古参兵の投入で、前線が踏みとどまってくれたのだ。
サキの感覚で、それは音に反映された。戦闘開始の直後、前線より流れてきたのは射撃音、軍馬のいななき、兵士の怒号と悲鳴の混合物だった。
現在、その喧騒が和らいでいる。斉射音や命令の怒号は依然、続いてはいるのだが、響く間隔にリズムが備わり、喧しさが軽減されたのだ。悲鳴に関しても、確実に薄れている。
相変わらず、レンズは死を映し続けている。銃撃に斃れる兵士。その前でパニックに陥る若年兵。しかし先程とは異なり、恐怖が咲き乱れることはない。扱い方を心得た老兵が、芽吹いたそれを色々なやり方で摘み取って行くからだ。
泡を吹いて暴れる兵士を、赤子をあやすような手ぶりで前線から引き離す老兵。仲間の死に目もくれず、日常の仕草で弾込めを続ける老兵。彼らに感化されて、経験の浅い兵士たちも、死をただそこにあるものとして受け入れ始めたように見受けられる。
戦闘が、作業に変わり始めたのだ。
「そろそろ一休みできそうですな」
フェルミが予測を口にする。
「歴戦のグロチウスなら、こちらが持ち直してきたことを把握するでしょう。攻めを急くより、一旦、切っ先を整える方が賢明だと判断するはずです」
大佐の言った通り、前線の煙が薄れ始めたので、サキは感心した。
「どのくらい空けてくれるだろう。二十、いや三十分?」
取り出した懐中時計に、サキは願望を注ぐ。戦端より五十分、古参兵の投入からも二十分が経過している。時間稼ぎは、まだまだ足りない。
「あの名将なら、十五分で立て直すでしょうな。時間より、どう攻めてくるかが気がかりだ」フェルミが渋面で眺めるのは針ねずみの布陣図だ。
「これまで通り攻め直してくるか、あるいは当初こちらが目論んだ形で、側面から回り込んでくるのか」
「今でも一緒なんだな?側面から攻めてくれた方が、対処しやすいというのは」
「一緒以上です。敵にとっては、我慢比べに敗北したに等しい。正面から攻めるのを断念するわけですからね。徒労感も相当でしょう。士気も下がるでしょうね」
「勝ち目が出てくるってわけか」
「まさか。そいつで五分の線ってとこですな」
「……それだけか。そんなに低いのか」
「お忘れなく。二倍以上の敵勢に、わざと隙を晒すような綱渡りの最中なんです」
首の動きで、フェルミは敵陣を示す。五分の状況。あまり有難くもないが、せめてその位置に立てなければ、王国の未来は血霧に霞む。
けれどもサキは、いやな予感に包まれていた。こうなったらいいな、こうなって欲しくはないな、と願ったとき。これまでの経験では、大抵、「こうなってほしくない」より酷い事態が訪れるのだ。
「敵軍、攻撃を再開しました」
喘ぐような報告が響く。時計は、まだ十分と経っていない。
「北と南の五千を降ろしますか」
クローゼの問いを、グロチウスは首の動きで否定した。
「斥候から報告があった。遠めにわかりにくいが、南北の山麓に沼沢地が点在しているようだ。呼応して挟み撃ちは難しい」
地図に黒い点々を書き入れて行く。三方からの挟撃といえば華やかな響きだが、致命打を与えるにはタイミングを合わせることが肝心だ。
細長い平野に兵を密集させた場合、互いの勢いを殺すおそれも出て来る。
正面だけでも二倍の優勢。ならば、効果の見えない全軍投入は控えた方がいい。
「敵将は――いや、敵将の代わりに判断を下す将官は――」
グロチウスは少年の肖像を眺めながら、その向こうに顔のない参謀を思い浮かべた。
「われらの方針転換を期待しているだろう。焦りをはらみつつ、側面を伺う我らを縦列で挟み殺す。しかし残念ながら」
余裕を空気に乗せ、老将は敵の挑発的な陣構えを見据えた。
「乗ってやらぬよ。王国の指揮官殿。この場は押し通し、刺し貫くのが正しい」
傍らのフェルミが無感動に告げる。あまりに事務的な口振りだったので、サキはあやうく「何が?」と訊き返しそうになった。火蓋が切られたのだ。
指揮車の傍らの荷車に数台の遠眼鏡が積み込まれている。携帯用から、天文台で使用するような大掛かりな機械まで、用途に合わせて指揮官に供するためのものだ。
覗いてみるべきか、サキは躊躇した。居ることだけが自分の役割なので、無理をして凄惨な光景を見る必要などないのだ。ぼーっとしているうちに済んでくれたらとてもありがたい。
しかし状況は最初からこちらの不利、ぼーっとしているうちにあの世行きにもなりかねない。だから戦況を確かめたいとも思うのだけれど、覗き込んだ前線の様子が芳しくなかったら、それだけでくじけてしまいそうだ。
肉眼に映る前線は、現在、白いもやだ。
自軍の軍服軍帽と、斉射の煙がそう見せている。
ぱら、ぱらと間の抜けた響きが銃声であることにしばらく気付かなかった。
毛布にもぐり込んで聴く夕立のような気安さに、楽観に揺れたサキは、ついつい遠眼鏡を寄せた。
(見るんじゃなかった)
拡大された自軍兵士は、教本のような整った対応とはまるで遠いあわてふためき振りだった。
サキが覗いているのは、渓谷の前に陣取る味方大隊に敵の騎兵が突撃を敢行する一角だ。迫る騎兵に、銃を構えた横列が斉射を開始する。しかし各所で引き金を引けない兵士、装填すら終わっていない兵士、構えた銃口があさってを向いている兵士が弾幕に隙間をつくってしまっているため、成すすべもなく、騎兵に切り伏せられている。袈裟懸けにされた兵士が二つに割れた。それが、最初にサキが目にした戦死者だった。
「ああ」
サキの口から間抜けな声が漏れる。死を眼にするのはこれがはじめてではない。これまで決闘の立会人を務めてきたのだ。たまにインチキではなく真面目な決闘が行われるとき、ごく稀に当たり所が悪くて人死にが出る場合もあった。
しかし、そのときの死は緩慢なものだった。決闘に使用するピストルは、殺傷力の強いものではなかったからだ。血を流し、少しずつ顔色が青ざめて動かなくなる。命が失われるとは、そういう光景だとサキは思い込んでいた。
だが戦場の死は――すくなくとも最前線の死は――瞬間で終わるものだった。
マスケットに撃ち抜かれた兵士の頭部が弾け飛ぶ。木枯らしの後、枝の枯れ葉が何枚か消失するように、気づいたらなくなっている。
所どころで敵騎兵がこちらの兵士を殺し、横列に歯抜けが生じた。割合でいえば横列まで到達できた敵騎兵は少数派で、冒険はせず、一旦自陣へ旋回したため、こちらの横列自体は保たれている。ただし騎兵の突撃で時間を稼いだ分、敵の歩兵がこちらとの距離を詰めたようだ。
「なんであんなに、当たらなかったんだっ?」
サキは叫ぶ。前線の兵士は武器を放り捨てて逃げ出すほど錯乱してはいなかった。ただ、押し寄せる敵に撃ち返す弾丸が、ちっとも命中しないのだ。
「あたらない距離だからですよ」
フェルミが乾いた声で応える。
「六十ルーデ(約二百メートル)離れていればまず当たるものじゃありません」
フェルミも遠眼鏡を除きながら、
「訓練をしても、射撃の精度には限界があります。マスケットの性能も関わってきますからね。プロイセンの記録によると、二十ルーデ (約七十メートル)で射撃精度は七割程度だったそうです。 あの訓練狂いのプロイセンですらその数字ですからね。我が国の、正規軍でない奴らなら、精度はもっと落ちる」
「それなら、もっと引き付けてから撃たせればいいだろう」
「おっしゃる通りですが、その距離だと相手の命中精度も上がってしまいます。そうなると、今以上に兵士が恐慌をきたす。精度を犠牲にして離れて撃たせるか、ビビり上がる兵士を承知で近くから撃たせるか――検討した結果、離れた方が良い数字になるって結論が出ているんですよ」
「その計算は、革命軍も同じなのか」
「違います。残念ながら。おそらく革命軍の兵士は、こちらより距離を詰めてもビビることが少ない」
「訓練不足ってことか」
選抜民兵が訓練に参加するのは週に一度。その頻度が問題なのかとサキは考えた。
「それだけじゃないんです。人間の本質ってものが邪魔をするんですよ。いくらしごきあげようが、戦場に出ると兵士の何割かは動きが鈍ります。訓練では百発百中だった兵士が、本番では引き金にさえ触れなくなる場合もあるんですよ。用兵ってものは、そういう鈍りも織り込み済みで考えなくちゃあならない。兵士の働きぶりを戦場で見極め、選り分けるのが肝要なんですが……」
フェルミが軽く呻いたのに気付き、サキは双眼鏡の角度を変えた。優美な横列を維持したまま前進を続ける革命軍の歩兵たち。対して距離を稼ぐために後退をはじめた選抜民兵たちだが、ほとんど逃亡に近いような乱れっぷりだった。
「わが軍とは違うでしょう?これがグロチウスの強さです。恐怖を乗り越えて 二十ルーデ以下に立てる兵士はどいつとどいつか。連戦で擦り減り、前に出れなくなってしまった割合はどの程度か?――そういう数字を、あの老将軍は帳簿みたいにまとめているんです。戦闘の度に名簿を書き換え、適所に兵士を振り分けてる。だから行動全体にそつがない。自由・平等・博愛っていうものは、凶悪な宗教ですな」
右眼で遠眼鏡を、左眼で布陣図に挿したピンをいじりながらもフェルミは話を止めない。
「意欲が違う。献身が違う。下っ端兵士でさえ、自分が軍団を動かしている歯車の一つだと自負していやがるから、兵士の状態を一人一人確認するなんて面倒な試みにも協力的なんです。むろんグロチウスの着眼点も大したものですが」
敵将を堂々と褒める。フェルミが型破りな将官なのかそうでないのかはサキに判断できないが、有能か否かについてはすぐに明らかとなった。
「第七連隊と第二連隊はこっちにずれろ。それからこの名簿の奴らを前線に回せ」
針ねずみの布陣図を、フェルミは伝令たちに示す。伝令も各々ポケットから針と地図を取り出し、瞬く間に複製品を作り上げた。ふざけて見えるが、案外有用な連絡方法だ。ペンに比べて修正する手間がかからず、雨でインクが滲むこともない。
次にフェルミが配ったのは、活版で鮮明に刷り込まれた紙切れだった。サキに見せてくれる配慮は皆無のようで、こちらにはそれが何らかの名簿らしいことしかわからなかったが、視界を通り過ぎる名前に見知った者が含まれていた。
「フランケン?」
確かめようと手を伸ばしたら、フェルミに払いのけられる。
「あー、フランケンね。あれはいい兵士ですよ。たった今から准尉に昇進です」
眼で促された伝令たちは、リストと布陣図を持って四方へ散った。
「今の、古参兵のリストか」
「迷ったんですよ。若さと経験、どっちが役に立つかってね。遺憾ながら逆に張っちまったみたいだが、いつでも変えられるよう、準備はしていたんです」
手元に残していた一枚を、これ見よがしにひるがえす。
「訓練もさせておきました。戦場を知っている年寄り主体で動く訓練です。殿下、よもや『僕の執事を殺さないでよう』なんてお止めにはならないでしょうね」
「聞くつもりなんてない癖に」
毒づきはするが、サキはフランケンを退がらせようとは思わない。それは執事への非礼にあたるだろう。
「これで前線が落ち着いてくれるといいんですが」フェルミは布陣図を睨む。
幸いにして大佐の目論見は、ある程度の成功を収めた。古参兵の投入で、前線が踏みとどまってくれたのだ。
サキの感覚で、それは音に反映された。戦闘開始の直後、前線より流れてきたのは射撃音、軍馬のいななき、兵士の怒号と悲鳴の混合物だった。
現在、その喧騒が和らいでいる。斉射音や命令の怒号は依然、続いてはいるのだが、響く間隔にリズムが備わり、喧しさが軽減されたのだ。悲鳴に関しても、確実に薄れている。
相変わらず、レンズは死を映し続けている。銃撃に斃れる兵士。その前でパニックに陥る若年兵。しかし先程とは異なり、恐怖が咲き乱れることはない。扱い方を心得た老兵が、芽吹いたそれを色々なやり方で摘み取って行くからだ。
泡を吹いて暴れる兵士を、赤子をあやすような手ぶりで前線から引き離す老兵。仲間の死に目もくれず、日常の仕草で弾込めを続ける老兵。彼らに感化されて、経験の浅い兵士たちも、死をただそこにあるものとして受け入れ始めたように見受けられる。
戦闘が、作業に変わり始めたのだ。
「そろそろ一休みできそうですな」
フェルミが予測を口にする。
「歴戦のグロチウスなら、こちらが持ち直してきたことを把握するでしょう。攻めを急くより、一旦、切っ先を整える方が賢明だと判断するはずです」
大佐の言った通り、前線の煙が薄れ始めたので、サキは感心した。
「どのくらい空けてくれるだろう。二十、いや三十分?」
取り出した懐中時計に、サキは願望を注ぐ。戦端より五十分、古参兵の投入からも二十分が経過している。時間稼ぎは、まだまだ足りない。
「あの名将なら、十五分で立て直すでしょうな。時間より、どう攻めてくるかが気がかりだ」フェルミが渋面で眺めるのは針ねずみの布陣図だ。
「これまで通り攻め直してくるか、あるいは当初こちらが目論んだ形で、側面から回り込んでくるのか」
「今でも一緒なんだな?側面から攻めてくれた方が、対処しやすいというのは」
「一緒以上です。敵にとっては、我慢比べに敗北したに等しい。正面から攻めるのを断念するわけですからね。徒労感も相当でしょう。士気も下がるでしょうね」
「勝ち目が出てくるってわけか」
「まさか。そいつで五分の線ってとこですな」
「……それだけか。そんなに低いのか」
「お忘れなく。二倍以上の敵勢に、わざと隙を晒すような綱渡りの最中なんです」
首の動きで、フェルミは敵陣を示す。五分の状況。あまり有難くもないが、せめてその位置に立てなければ、王国の未来は血霧に霞む。
けれどもサキは、いやな予感に包まれていた。こうなったらいいな、こうなって欲しくはないな、と願ったとき。これまでの経験では、大抵、「こうなってほしくない」より酷い事態が訪れるのだ。
「敵軍、攻撃を再開しました」
喘ぐような報告が響く。時計は、まだ十分と経っていない。
「北と南の五千を降ろしますか」
クローゼの問いを、グロチウスは首の動きで否定した。
「斥候から報告があった。遠めにわかりにくいが、南北の山麓に沼沢地が点在しているようだ。呼応して挟み撃ちは難しい」
地図に黒い点々を書き入れて行く。三方からの挟撃といえば華やかな響きだが、致命打を与えるにはタイミングを合わせることが肝心だ。
細長い平野に兵を密集させた場合、互いの勢いを殺すおそれも出て来る。
正面だけでも二倍の優勢。ならば、効果の見えない全軍投入は控えた方がいい。
「敵将は――いや、敵将の代わりに判断を下す将官は――」
グロチウスは少年の肖像を眺めながら、その向こうに顔のない参謀を思い浮かべた。
「われらの方針転換を期待しているだろう。焦りをはらみつつ、側面を伺う我らを縦列で挟み殺す。しかし残念ながら」
余裕を空気に乗せ、老将は敵の挑発的な陣構えを見据えた。
「乗ってやらぬよ。王国の指揮官殿。この場は押し通し、刺し貫くのが正しい」