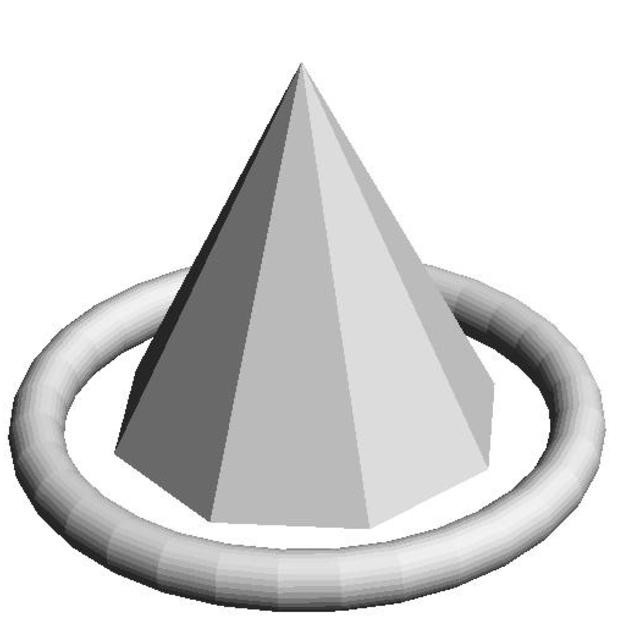お飾りの誇り
文字数 6,632文字
サキは遠眼鏡から離れている。詳しい状況を知るのが嫌になったのだ。肉眼で、煙の線だけ凝視している。
前線の土煙は、前より濃度を増している。
さらに十五分が経過した。
伝令がフェルミの周辺に集まり始めた。針ねずみを受け取るたび、大佐は舌打ちを繰り返す。
暫くその光景を見ていたサキが、再び前を見ると、煙がさらに濃くなっていた。
違う。煙の位置がこちらに接近しているのだ。それはつまり――
「はい、殿下。よくない報告です」
注意を惹くように、フェルミが拍手をする。
「前線が崩壊しました」
「ほうかい……」
「詳しく言うと、三個大隊が突き崩されて、横列の役割を果たせなくなりました。再構成できる部隊だけ、後方の一個大隊に合流させています。この一個大隊が最後の蓋です。破られたらここまで遮る部隊はない。おそらく敵は、歩兵横隊を前進させつつ、左右に騎兵を同行させるでしょう。歩兵同士がぶつかった後に、騎兵が囲みにくる手筈でしょうね。この本陣を」
意外と丁寧に解説してくれるが、感謝する余裕はサキにない。
「だからこちらも、虎の子の騎兵をぶつける他にない。予備兵力を保つ余裕はありません。それほど時間は経過してませんが、最後の局面ですね」
最後。その言葉がずしりと伸し掛かる。蓋が破れたら、もうおしまいなのだ。
「選抜民兵と言ったか。制度としては悪くないかもしれんな」
丘の上で、グロチウスは敵軍の動きをつぶさに吟味している。敵の最前線を叩き割った。しかし崩壊した前線から撤退した部隊の内、半数近くが後方の大隊に吸収され、次の前線を形作っている。遠景からでも窺えるその滑らかさに、老将は舌を巻いた。
「素人に毛が生えたようなものと聞いておりましたが、評価を改めるべきですな」
傍らのクローゼも、布陣図を眺めながら硬い表情だ。過小評価は、選抜民兵が職業軍人ではなかったからだ。革命軍も大半が市民で構成されているが、戦いに臨む意欲が違う。彼らは革命のために立ち上がり、君主を追放して市民国家を成立させた。選抜民兵は所詮、上からの命令によって集められた連中に過ぎない。こまめに訓練を施しても、士気という面でこちらの兵士に比べて見劣りするだろう、という予断があったのだ。やる気のない兵隊は、一度ひびわれたらあっけなく崩れるはずだった。
「郷土愛、か」
グロチウスは呟く。
「君主制であろうと、市民国家であろうと、民衆が生まれ故郷を愛する想いに変わりはない。慣れ親しんだ土地が敵国に蹂躙されるとなれば、懸命に戦うというわけか」
閉じた瞼の裏に、老将は未来図を描く。
「その郷土愛を、硬く束ねることができたなら――行ったこともない他国との国境線を侵されることが、自分たちの住処に攻め込まれるのと同様の屈辱を感じるように教育できるなら――増やせるかもしれぬな。今以上に、命がけで戦ってくれる兵士たちを」
そこまで口にして、グロチウスは敵陣に視線を戻す。今は未来の兵士よりも、目の前の配下を死なせないことが重要だ。
遠眼鏡を弄るうちに、サキは子供を見つけた。自分より年少に見える、小柄でやせた少年。顔は青白く、震えながら前線の近くをさまよっている。
サキは自分より年下の少年が戦場に駆り出される例もあることは知っていた。高級将校の従者や鼓笛隊であれば、成長途上の肉体でも役目を果たせるからだ。しかしレンズに映る少年は楽器を手にしておらず、将校が好んで侍らせるような見栄えの良さもない。一般の歩兵として放り込まれたにしては体格が貧弱すぎる。マスケットもまともに持てそうにない痩せぎすだ。これでは大人の兵隊と連携がとれないだろう。
制度上の不備というやつだろうか、とサキは考える。
選抜民兵は「良民より適性のあるものを選出」した兵士という説明だった。だが詳しい選出方法については聞いていない。例えば町の有力者が、息子を危険な戦場に送り込みたくない場合、ある種の不正を通す余地はありそうだ。選出担当に賄賂を贈ったり、金銭的援助をちらつかせて貧困家庭の子弟を身代わりにしたり、というやり方でだ。
あの少年は、そういう事情で前線に送り込まれたのかもしれない。
サキは少年から眼が離せなくなった。身代わりで連れてこられたのだとしたら、きっと家庭でも愛されていなかったのだろう。金と引き換えに死んでも構わないと見なされ、売られた少年。
下劣と知りながら、サキは嬉しくなってしまう。
十四歳で出陣を余儀なくされ、不幸の極みだと嘆いていた自分より、もっと可哀そうなやつを見つけたからだ。
あの子は、この戦場で生きていられるだろうか。死んでしまうのだったら、僕が見ている内に死んでほしい。今でもいい。今、大砲に吹き飛ばされても……
背後に轟音が響き、サキは慌てて遠眼鏡から目を離す。振り替えると土埃が顔に吹き付けた。せき込みながら、視界が整うのを待つ。
地面が凹んでいた。サキの位置から六ルーデ(約二十メートル)と離れていない。
周囲を見渡すと、カヤがすでにスケッチを開始していた。フェルミは平然と部下に指示を続けている。
(死ぬのは、僕の方かもしれなかった)
脳が震える。死の危険を感じながら、前線を眺めている内に見世物気分になっていた。この観客席は、砲弾も降ってくる距離なのだ。
これまで生きてきた十四年で、自分が死ぬことを意識しなかったわけではない。ただ想像していたそれは、靄のように曖昧なものだった。
こんな堂々と、ノックをして入ってくるような死なんて、思いもよらなかった。
サキは肉眼ではるか前線を眺めた。
脈動する灰と赤。
砲煙と土埃、軍服と鮮血が混ざり合った前線のモザイクだ。
あれが壊れたとき――敵兵はまっしぐらにこちらへ押し寄せ、自分を虜にするだろう。よくてギロチン、最悪ならサキの想像もつかない殺し方が待っている。
今、胴体の上に頼りなく乗っかっているこの頭が、猫の玩具のようになぶられ、転がされるかもしれない。
(いやだ。そんなひどい死に様はいやだ。欲を言えば、死ぬのもいやだ)
平然と指示を飛ばすフェルミ。担架の負傷兵を興味深気にスケッチするカヤ。
いいよなお前たちは。所詮、上級将校と部外者だ。革命軍が虐殺に走りさえしなければ、まだ生き永らえる芽が残っている。兵士たちだって、弾が当たりさえしなかったら、負けたところで皆殺しにされるわけではない。
けれども、この僕には道がない。
捕まったら、死。王国を背負っての死だ。国王の嗣子に名乗り出ただけで、たいしておいしい思いもしていない僕が、責務だけ押し付けられて死んでいく。
――逃げてやろうか。
ふいに、サキは思い立った。
「逃げたら駄目ですよ」
だしぬけに、フェルミが言った。サキを横目に、乾いた口調で浴びせた。
「どうしてわかったって?そんなにがたがた震えて、足を遊ばせていたら、サルでも気取ります」
己の醜態に、サキは初めて気が付いた。立ち方を忘れたように脚部がぐらついている。額に浮かぶ、不快な温さの汗玉。視線は落ち着かず、遠くも近くも焦点が合わない。
「生きててもらうのが、あんたの仕事ですけどね、殿下」
フェルミは早口で伝える。
「あんまりみっともないようなら、生きてるふりをしてもらうだけでもけっこうなんですよ」
怒る気力もない。
筆を止めたカヤが、サキとフェルミを交互に眺めた。
「誤解されてるようだが、おれたちは、あんたを軽く見てるわけではない。ばかにもしていませんよ」
傍らを、担架の列が通り過ぎる。薄汚れた肌の負傷兵から、草笛のようなうめき声が漏れたとき、フェルミは眉根を寄せた。
「ただ、要求しているだけです。必要な仕事をね。おれは布陣図とにらめっこ。嬢ちゃんは、この時間を絵に留める。あんたの場合、余裕ぶって突っ立っていることが大事な任務なんです」
反感を覚えながらも、サキはフェルミが本音を口にしていると理解した。
「わかったら、震えを抑える努力でもしてください。頭の中でお歌を歌うとか、なぞなぞを考えるとか、なんでも結構ですから」
言い捨てて、集まってきた士官に何やら新しい指示を与え始める。
サキは友達に助けを求めようとした。カヤは筆を止めたまま、依然としてこちらを見据えている。
この少女も、ニコラも同じだ。サキの身近にいる女性は、サキに慰めを与えてくれることは決してない。ただ、無言で突き放す。
(ああ、不幸だ。不幸すぎる……)
(……いや)
自分を押しつぶしそうになる寸前で、サキは踏みとどまる。遠眼鏡を動かす。僕より不幸なあいつを見て、恐怖を和らげるしかない。
幸運を、愚行で使い果たしたかもしれない。ものの数秒で、サキはその少年兵を探し当てた。
みじめな少年兵。泥に汚れ、先ほどより老けたようにも見えた。たぶん、混乱と恐怖に洗われた結果だろう。他の兵士より消耗が目立つのは、心の貯えが、元々乏しかったせいかもしれない。サキの見立て通り、ろくでもない境遇で暮らしていたのだろう。
(見苦しいなあ、あまりに見苦しい)
よだれか胃液か、少年の口元から粘液が垂れている。「だめなやつ」を眺めるのは本当に気分がいい。名門貴族であるサキの周辺には、身分を問わず如才ない人材がたむろしている。執事も下男も従僕も、小器用で物覚えのいい連中ばかり。彼らに傅かれながらサキは常々疑っていた。こいつら、胸の奥では、僕をどう思っているんだろう。
生まれがいいというだけで大した取り柄もない自分のことを、見えない角度ではあざ笑っているかもしれない。事実、サキは知っている。遊学中の長兄に較べて、自分が低く評価されているらしいことを、怒る気にはなれない。庶民の身でありながら、才覚で名家の名家の高級使用人にまで這い上がった彼らから見れば、貴族の子供、というだけのからっぽな僕など、蔑みの対象でしかないだろう。
だからこそサキは、身分が卑しく才能もない愚者を見つけると、喜んでしまうのだ。その感情こそ、さもしさの極と知りながら。
少年兵が吐いた。胃液のようだ。
いいぞ、もっと惨めになれ。
名前も知らない他人の不幸を、サキは切実に願う。
少年兵は胸に張り付いた吐瀉物を懸命にぬぐおうとするが、汚物は泥と混ざり、もう取り返しがつかない。その軍装が衛生兵のものであることにサキはようやく気付いた。この汚さでは、けが人に触れもしないだろう。表情が、ふいに笑顔へと変わる。いや、紛らわしいが、泣き顔だ。きっと上官に叱られるのが恐ろしいのだ。
死んでくれないかな。おもいきりむごたらしく、しんでくれないかな。
サキは願う。自分より理不尽で無様な死を見せてくれたなら、僕も、いくらかましな心地で死ぬことができる。
少年が殴られた。同僚らしき大男が顔を赤くして何かわめいている、今の失態のせいか、ただのやつあたりかは分からない。大男がわめき続けている。少年は何か応えようと胸元を探っているが要求に応えられなかったらしく、今度は平手を食らった。
叱責され、委縮し、さらに間違う。ああ、「だめなやつ」の典型だ。いいぞ。いいぞ。もっと「だめ」を見せてくれ。さらけ出した挙句に、あっけなく虫みたいに殺されてほしい。
三度殴られた少年は、救いを求めるように両手を伸ばした。
その手が、同僚を突き飛ばした。
少年の腹部が、赤に染まった。前のめりに倒れる。
しりもちをついた上官は、信じられないといった風で少年を見つめていたが、やがて口を大きく開き、少年兵を助け起こした。
サキが事態を飲み込むまで、さらに時間が必要だった。
あいつ。
かばいやがった。銃撃から、身を挺して仲間をかばいやがった。
しかも仲間とは呼び難いような、自分を虐げていたような相手を。
腹の底から、怒りがこみ上げる。自分でもわかっている、理不尽な怒りだ。
なんだよ?
なんで、そんなことができるんだよ。
僕より弱そうな体で、僕より弱そうな心で、たかが庶民の分際で。
その清らかさ。忌々しい清らかさを、どこから拾ってきた!
今、父親より革命軍より評議会より、この少年が憎かった。お前のせいだ、お前みたいな奴がいるから、僕は苦しいんだ!
視界が滲む。泣いている自分に、サキは驚いた。
くやしい――
掃き溜めにまみれながら、気高さを失わない魂がある。あの少年兵だ。
お菓子の国に育ちながら、ミミズの吐瀉物にも劣る、くずな魂がある。この僕だ。
くやしい。なさけない。
僕には何もない。何も身に付かなかった。何も育たなかった。
性根が空っぽだったから。生まれつきが無能だったから。
あるのは、立派な家柄だけ。お飾りの地位だけ。
こじつけの、「決闘の王子」だけ―――
何もない!何もない!何もない!
涙の視界がぐらぐらと揺れる。合わせて意識もぶれ始める。このまま真っ白に何も考えられなくなってしまいたい、とサキは願った。
何もないこの僕が、無に戻る。ふさわしい話じゃないか。何もない僕が、名前だけの僕が、飾りだけ、名前――
名前。
飾りだけ。
引っかかった。
その言葉だけが、サキの言葉にしがみつき、弱い光を放った。
名前だけしかない。
それは、名前だけは持っているという意味だ。だったら、あがくべきではないのか?獣に襲われる旅人が、持ち物すべてを投げつけて身を守るように、あるならば、それを使って抗うべきじゃあないのか?
(僕が、今、やるべきことは)
意識を立て直す。すぐ前方に、フェルミが立っている。
指示が一段落したのか、落ち着き払って直立しているが、首筋が強張っていた。
「な、なあ」
声をかけると、邪魔だと言いたげな視線を返された。サキはたまらず目を逸らす。それでも多大な努力を払って勇気を組み立て直し、もう一度呼びかけた。
視線を合わせるのも面倒と言いたげなフェルミの表情に、サキの心は再びおじけづいたが、もう止まれない。
「前線に出たい」
「はあ?」
虚を突かれたのか、間が抜けたフェルミの声。
「前線へ出る。大将たるこの僕が、前線に立つ」
「何を言い出すと思ったら……頭煮えましたか?あんたがあそこに入ったところで、何もできやしません」
「わかってる。だから、『何もできない』をやりに行くんだよ」
今度はひるまない。やけと勇気の中間くらいの感情が背中を押している。
「僕は、お飾りにすぎない。それでも、上等な飾りであることは間違いないだろう?だったら、前線に行った方が、ご利益があるんじゃないか?形だけとはいえ、国家の最高位にいる僕が、死の危険を兵士と共有する。いくらか士気が上がらないか?何もしないよりはましじゃあないか?」
フェルミは指先で頬を擦った。
「言っときますが、私はここに残りますからね」
「あたりまえだろ。君は布陣図とにらめっこ。僕は余裕ぶって前線に立つ。それが仕事なんだからさ」
「んじゃ、邪魔にならない程度でお願いします」フェルミは底意地悪そうに笑った。
「前線までに、その震えと汗を黙らせといてくださいね」
難しい。
前線へ急ぐ指揮車の中、サキは身体に鋼鉄の串が刺さったと仮定して震えを鎮めようとしたが、たった今、五本目の串がぐにゃりと曲がったところ。歯も噛み合わないこの有様では、兵士の鼓舞など、笑い話に終わってしまう。
「題名・震える偽摂政」
横合いを見ると、カヤが毛布の隙間から筆を動かしていた。
「なんでいるんだよ……」
「何でって」カヤは心外と言わんばかりに口を尖らせた。
「みんなが、それぞれの仕事をするんでしょーが。サキを描くのがあたしの仕事」
この状況で、猫のように寛いでいるカヤ。今更ながらこの少女が規格外であることをサキは思い知る。それでも悪戯っぽい笑顔に、少しばかり勇気づけられた。震えが弱まってくれる。
上等の飾り。細工を凝らしたオルゴールの、フタを開くとくるくる音楽を奏でるからくり人形。
そんなものが、僕だ。せいぜい回ってやろう。盛り上げてやろう。
前線の土煙は、前より濃度を増している。
さらに十五分が経過した。
伝令がフェルミの周辺に集まり始めた。針ねずみを受け取るたび、大佐は舌打ちを繰り返す。
暫くその光景を見ていたサキが、再び前を見ると、煙がさらに濃くなっていた。
違う。煙の位置がこちらに接近しているのだ。それはつまり――
「はい、殿下。よくない報告です」
注意を惹くように、フェルミが拍手をする。
「前線が崩壊しました」
「ほうかい……」
「詳しく言うと、三個大隊が突き崩されて、横列の役割を果たせなくなりました。再構成できる部隊だけ、後方の一個大隊に合流させています。この一個大隊が最後の蓋です。破られたらここまで遮る部隊はない。おそらく敵は、歩兵横隊を前進させつつ、左右に騎兵を同行させるでしょう。歩兵同士がぶつかった後に、騎兵が囲みにくる手筈でしょうね。この本陣を」
意外と丁寧に解説してくれるが、感謝する余裕はサキにない。
「だからこちらも、虎の子の騎兵をぶつける他にない。予備兵力を保つ余裕はありません。それほど時間は経過してませんが、最後の局面ですね」
最後。その言葉がずしりと伸し掛かる。蓋が破れたら、もうおしまいなのだ。
「選抜民兵と言ったか。制度としては悪くないかもしれんな」
丘の上で、グロチウスは敵軍の動きをつぶさに吟味している。敵の最前線を叩き割った。しかし崩壊した前線から撤退した部隊の内、半数近くが後方の大隊に吸収され、次の前線を形作っている。遠景からでも窺えるその滑らかさに、老将は舌を巻いた。
「素人に毛が生えたようなものと聞いておりましたが、評価を改めるべきですな」
傍らのクローゼも、布陣図を眺めながら硬い表情だ。過小評価は、選抜民兵が職業軍人ではなかったからだ。革命軍も大半が市民で構成されているが、戦いに臨む意欲が違う。彼らは革命のために立ち上がり、君主を追放して市民国家を成立させた。選抜民兵は所詮、上からの命令によって集められた連中に過ぎない。こまめに訓練を施しても、士気という面でこちらの兵士に比べて見劣りするだろう、という予断があったのだ。やる気のない兵隊は、一度ひびわれたらあっけなく崩れるはずだった。
「郷土愛、か」
グロチウスは呟く。
「君主制であろうと、市民国家であろうと、民衆が生まれ故郷を愛する想いに変わりはない。慣れ親しんだ土地が敵国に蹂躙されるとなれば、懸命に戦うというわけか」
閉じた瞼の裏に、老将は未来図を描く。
「その郷土愛を、硬く束ねることができたなら――行ったこともない他国との国境線を侵されることが、自分たちの住処に攻め込まれるのと同様の屈辱を感じるように教育できるなら――増やせるかもしれぬな。今以上に、命がけで戦ってくれる兵士たちを」
そこまで口にして、グロチウスは敵陣に視線を戻す。今は未来の兵士よりも、目の前の配下を死なせないことが重要だ。
遠眼鏡を弄るうちに、サキは子供を見つけた。自分より年少に見える、小柄でやせた少年。顔は青白く、震えながら前線の近くをさまよっている。
サキは自分より年下の少年が戦場に駆り出される例もあることは知っていた。高級将校の従者や鼓笛隊であれば、成長途上の肉体でも役目を果たせるからだ。しかしレンズに映る少年は楽器を手にしておらず、将校が好んで侍らせるような見栄えの良さもない。一般の歩兵として放り込まれたにしては体格が貧弱すぎる。マスケットもまともに持てそうにない痩せぎすだ。これでは大人の兵隊と連携がとれないだろう。
制度上の不備というやつだろうか、とサキは考える。
選抜民兵は「良民より適性のあるものを選出」した兵士という説明だった。だが詳しい選出方法については聞いていない。例えば町の有力者が、息子を危険な戦場に送り込みたくない場合、ある種の不正を通す余地はありそうだ。選出担当に賄賂を贈ったり、金銭的援助をちらつかせて貧困家庭の子弟を身代わりにしたり、というやり方でだ。
あの少年は、そういう事情で前線に送り込まれたのかもしれない。
サキは少年から眼が離せなくなった。身代わりで連れてこられたのだとしたら、きっと家庭でも愛されていなかったのだろう。金と引き換えに死んでも構わないと見なされ、売られた少年。
下劣と知りながら、サキは嬉しくなってしまう。
十四歳で出陣を余儀なくされ、不幸の極みだと嘆いていた自分より、もっと可哀そうなやつを見つけたからだ。
あの子は、この戦場で生きていられるだろうか。死んでしまうのだったら、僕が見ている内に死んでほしい。今でもいい。今、大砲に吹き飛ばされても……
背後に轟音が響き、サキは慌てて遠眼鏡から目を離す。振り替えると土埃が顔に吹き付けた。せき込みながら、視界が整うのを待つ。
地面が凹んでいた。サキの位置から六ルーデ(約二十メートル)と離れていない。
周囲を見渡すと、カヤがすでにスケッチを開始していた。フェルミは平然と部下に指示を続けている。
(死ぬのは、僕の方かもしれなかった)
脳が震える。死の危険を感じながら、前線を眺めている内に見世物気分になっていた。この観客席は、砲弾も降ってくる距離なのだ。
これまで生きてきた十四年で、自分が死ぬことを意識しなかったわけではない。ただ想像していたそれは、靄のように曖昧なものだった。
こんな堂々と、ノックをして入ってくるような死なんて、思いもよらなかった。
サキは肉眼ではるか前線を眺めた。
脈動する灰と赤。
砲煙と土埃、軍服と鮮血が混ざり合った前線のモザイクだ。
あれが壊れたとき――敵兵はまっしぐらにこちらへ押し寄せ、自分を虜にするだろう。よくてギロチン、最悪ならサキの想像もつかない殺し方が待っている。
今、胴体の上に頼りなく乗っかっているこの頭が、猫の玩具のようになぶられ、転がされるかもしれない。
(いやだ。そんなひどい死に様はいやだ。欲を言えば、死ぬのもいやだ)
平然と指示を飛ばすフェルミ。担架の負傷兵を興味深気にスケッチするカヤ。
いいよなお前たちは。所詮、上級将校と部外者だ。革命軍が虐殺に走りさえしなければ、まだ生き永らえる芽が残っている。兵士たちだって、弾が当たりさえしなかったら、負けたところで皆殺しにされるわけではない。
けれども、この僕には道がない。
捕まったら、死。王国を背負っての死だ。国王の嗣子に名乗り出ただけで、たいしておいしい思いもしていない僕が、責務だけ押し付けられて死んでいく。
――逃げてやろうか。
ふいに、サキは思い立った。
「逃げたら駄目ですよ」
だしぬけに、フェルミが言った。サキを横目に、乾いた口調で浴びせた。
「どうしてわかったって?そんなにがたがた震えて、足を遊ばせていたら、サルでも気取ります」
己の醜態に、サキは初めて気が付いた。立ち方を忘れたように脚部がぐらついている。額に浮かぶ、不快な温さの汗玉。視線は落ち着かず、遠くも近くも焦点が合わない。
「生きててもらうのが、あんたの仕事ですけどね、殿下」
フェルミは早口で伝える。
「あんまりみっともないようなら、生きてるふりをしてもらうだけでもけっこうなんですよ」
怒る気力もない。
筆を止めたカヤが、サキとフェルミを交互に眺めた。
「誤解されてるようだが、おれたちは、あんたを軽く見てるわけではない。ばかにもしていませんよ」
傍らを、担架の列が通り過ぎる。薄汚れた肌の負傷兵から、草笛のようなうめき声が漏れたとき、フェルミは眉根を寄せた。
「ただ、要求しているだけです。必要な仕事をね。おれは布陣図とにらめっこ。嬢ちゃんは、この時間を絵に留める。あんたの場合、余裕ぶって突っ立っていることが大事な任務なんです」
反感を覚えながらも、サキはフェルミが本音を口にしていると理解した。
「わかったら、震えを抑える努力でもしてください。頭の中でお歌を歌うとか、なぞなぞを考えるとか、なんでも結構ですから」
言い捨てて、集まってきた士官に何やら新しい指示を与え始める。
サキは友達に助けを求めようとした。カヤは筆を止めたまま、依然としてこちらを見据えている。
この少女も、ニコラも同じだ。サキの身近にいる女性は、サキに慰めを与えてくれることは決してない。ただ、無言で突き放す。
(ああ、不幸だ。不幸すぎる……)
(……いや)
自分を押しつぶしそうになる寸前で、サキは踏みとどまる。遠眼鏡を動かす。僕より不幸なあいつを見て、恐怖を和らげるしかない。
幸運を、愚行で使い果たしたかもしれない。ものの数秒で、サキはその少年兵を探し当てた。
みじめな少年兵。泥に汚れ、先ほどより老けたようにも見えた。たぶん、混乱と恐怖に洗われた結果だろう。他の兵士より消耗が目立つのは、心の貯えが、元々乏しかったせいかもしれない。サキの見立て通り、ろくでもない境遇で暮らしていたのだろう。
(見苦しいなあ、あまりに見苦しい)
よだれか胃液か、少年の口元から粘液が垂れている。「だめなやつ」を眺めるのは本当に気分がいい。名門貴族であるサキの周辺には、身分を問わず如才ない人材がたむろしている。執事も下男も従僕も、小器用で物覚えのいい連中ばかり。彼らに傅かれながらサキは常々疑っていた。こいつら、胸の奥では、僕をどう思っているんだろう。
生まれがいいというだけで大した取り柄もない自分のことを、見えない角度ではあざ笑っているかもしれない。事実、サキは知っている。遊学中の長兄に較べて、自分が低く評価されているらしいことを、怒る気にはなれない。庶民の身でありながら、才覚で名家の名家の高級使用人にまで這い上がった彼らから見れば、貴族の子供、というだけのからっぽな僕など、蔑みの対象でしかないだろう。
だからこそサキは、身分が卑しく才能もない愚者を見つけると、喜んでしまうのだ。その感情こそ、さもしさの極と知りながら。
少年兵が吐いた。胃液のようだ。
いいぞ、もっと惨めになれ。
名前も知らない他人の不幸を、サキは切実に願う。
少年兵は胸に張り付いた吐瀉物を懸命にぬぐおうとするが、汚物は泥と混ざり、もう取り返しがつかない。その軍装が衛生兵のものであることにサキはようやく気付いた。この汚さでは、けが人に触れもしないだろう。表情が、ふいに笑顔へと変わる。いや、紛らわしいが、泣き顔だ。きっと上官に叱られるのが恐ろしいのだ。
死んでくれないかな。おもいきりむごたらしく、しんでくれないかな。
サキは願う。自分より理不尽で無様な死を見せてくれたなら、僕も、いくらかましな心地で死ぬことができる。
少年が殴られた。同僚らしき大男が顔を赤くして何かわめいている、今の失態のせいか、ただのやつあたりかは分からない。大男がわめき続けている。少年は何か応えようと胸元を探っているが要求に応えられなかったらしく、今度は平手を食らった。
叱責され、委縮し、さらに間違う。ああ、「だめなやつ」の典型だ。いいぞ。いいぞ。もっと「だめ」を見せてくれ。さらけ出した挙句に、あっけなく虫みたいに殺されてほしい。
三度殴られた少年は、救いを求めるように両手を伸ばした。
その手が、同僚を突き飛ばした。
少年の腹部が、赤に染まった。前のめりに倒れる。
しりもちをついた上官は、信じられないといった風で少年を見つめていたが、やがて口を大きく開き、少年兵を助け起こした。
サキが事態を飲み込むまで、さらに時間が必要だった。
あいつ。
かばいやがった。銃撃から、身を挺して仲間をかばいやがった。
しかも仲間とは呼び難いような、自分を虐げていたような相手を。
腹の底から、怒りがこみ上げる。自分でもわかっている、理不尽な怒りだ。
なんだよ?
なんで、そんなことができるんだよ。
僕より弱そうな体で、僕より弱そうな心で、たかが庶民の分際で。
その清らかさ。忌々しい清らかさを、どこから拾ってきた!
今、父親より革命軍より評議会より、この少年が憎かった。お前のせいだ、お前みたいな奴がいるから、僕は苦しいんだ!
視界が滲む。泣いている自分に、サキは驚いた。
くやしい――
掃き溜めにまみれながら、気高さを失わない魂がある。あの少年兵だ。
お菓子の国に育ちながら、ミミズの吐瀉物にも劣る、くずな魂がある。この僕だ。
くやしい。なさけない。
僕には何もない。何も身に付かなかった。何も育たなかった。
性根が空っぽだったから。生まれつきが無能だったから。
あるのは、立派な家柄だけ。お飾りの地位だけ。
こじつけの、「決闘の王子」だけ―――
何もない!何もない!何もない!
涙の視界がぐらぐらと揺れる。合わせて意識もぶれ始める。このまま真っ白に何も考えられなくなってしまいたい、とサキは願った。
何もないこの僕が、無に戻る。ふさわしい話じゃないか。何もない僕が、名前だけの僕が、飾りだけ、名前――
名前。
飾りだけ。
引っかかった。
その言葉だけが、サキの言葉にしがみつき、弱い光を放った。
名前だけしかない。
それは、名前だけは持っているという意味だ。だったら、あがくべきではないのか?獣に襲われる旅人が、持ち物すべてを投げつけて身を守るように、あるならば、それを使って抗うべきじゃあないのか?
(僕が、今、やるべきことは)
意識を立て直す。すぐ前方に、フェルミが立っている。
指示が一段落したのか、落ち着き払って直立しているが、首筋が強張っていた。
「な、なあ」
声をかけると、邪魔だと言いたげな視線を返された。サキはたまらず目を逸らす。それでも多大な努力を払って勇気を組み立て直し、もう一度呼びかけた。
視線を合わせるのも面倒と言いたげなフェルミの表情に、サキの心は再びおじけづいたが、もう止まれない。
「前線に出たい」
「はあ?」
虚を突かれたのか、間が抜けたフェルミの声。
「前線へ出る。大将たるこの僕が、前線に立つ」
「何を言い出すと思ったら……頭煮えましたか?あんたがあそこに入ったところで、何もできやしません」
「わかってる。だから、『何もできない』をやりに行くんだよ」
今度はひるまない。やけと勇気の中間くらいの感情が背中を押している。
「僕は、お飾りにすぎない。それでも、上等な飾りであることは間違いないだろう?だったら、前線に行った方が、ご利益があるんじゃないか?形だけとはいえ、国家の最高位にいる僕が、死の危険を兵士と共有する。いくらか士気が上がらないか?何もしないよりはましじゃあないか?」
フェルミは指先で頬を擦った。
「言っときますが、私はここに残りますからね」
「あたりまえだろ。君は布陣図とにらめっこ。僕は余裕ぶって前線に立つ。それが仕事なんだからさ」
「んじゃ、邪魔にならない程度でお願いします」フェルミは底意地悪そうに笑った。
「前線までに、その震えと汗を黙らせといてくださいね」
難しい。
前線へ急ぐ指揮車の中、サキは身体に鋼鉄の串が刺さったと仮定して震えを鎮めようとしたが、たった今、五本目の串がぐにゃりと曲がったところ。歯も噛み合わないこの有様では、兵士の鼓舞など、笑い話に終わってしまう。
「題名・震える偽摂政」
横合いを見ると、カヤが毛布の隙間から筆を動かしていた。
「なんでいるんだよ……」
「何でって」カヤは心外と言わんばかりに口を尖らせた。
「みんなが、それぞれの仕事をするんでしょーが。サキを描くのがあたしの仕事」
この状況で、猫のように寛いでいるカヤ。今更ながらこの少女が規格外であることをサキは思い知る。それでも悪戯っぽい笑顔に、少しばかり勇気づけられた。震えが弱まってくれる。
上等の飾り。細工を凝らしたオルゴールの、フタを開くとくるくる音楽を奏でるからくり人形。
そんなものが、僕だ。せいぜい回ってやろう。盛り上げてやろう。