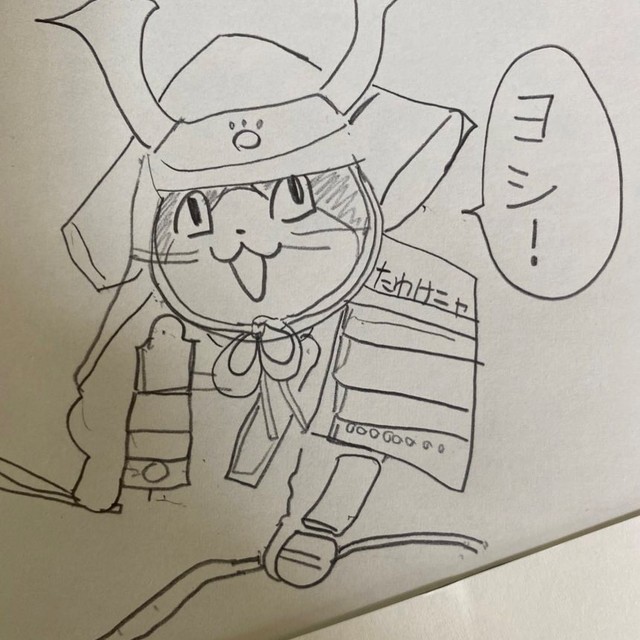第64話「軍事教練(恫喝)」
文字数 2,935文字
プレスター・ジョンの宿将であるウリエルこと劉学崇の案内により、時光一行はヌルガン城に向かった。
道中、ウリエルは時光に歴代王朝の歴史や文学について親し気に話しかけられていた。どうやら時光が漢詩を口ずさんでいた事から、漢人の知識人としての琴線に触れたらしい。その様ははっきり言って馴れ馴れしい程で、よっぽどこの様な会話を出来る相手に飢えていたようだ。
プレスター・ジョンの配下は多種多様である程度の知識人も含まれているが、それは西洋のキリスト教世界の者達が多く、東方世界の出身者は当然ながらモンゴル人がほとんどである。
モンゴル人は最近まで独自の文字を持っておらず、最近チベットの高僧にモンゴル語のために作らせたパスパ文字もまだ広まってはいない。口承文学や舞踏、楽曲には見るべきものがあるが、流石に漢人が積み上げて来たそれとは比較にならない。言ってみればモンゴル人は漢人から見れば蛮族なのである。
まあ当然のことながら日本人である時光も、漢人からしてみれば東夷であり紛れもない野蛮人である。その蛮族が漢詩等の文学に親しんでおりそれなりの知識を持っていたというのだから余計驚き、嬉しかったのかもしれない。また、お互い兵法にも通じているため、半年前の戦いで時光がトナカイを代用として実行した火牛の計に関して、戦国時代の田単の話などに話が飛び、大いに盛り上がった。
なお、今までの書き方からするとウリエルが周辺の日本人も含む異民族を低く見ている、いわゆる中華思想というある意味差別的な思想を持っているようにも思えるが、当時の漢人の王朝である宋とその他の国には文明度に格段の差がある。それはヨーロッパの国々も同様であり、漢人から見ればモンゴルも日本も、フランスもイングランドも野蛮国といっても過言ではない。宋王朝に匹敵する文明を持っているのは、中東付近の一部の国家位であろう。
とは言え野蛮な国々であっても戦闘力や、それに付随する一部の技術だけは高かったりするために、宋王朝は滅亡の危機に瀕しているのだが。
ともあれ、迎える側の幹部が迎えられる側の代表に好意的になったのだ、道中は実に快適に過ごすことができ、不愉快な思いをすることは無かった。半年前に大きな戦闘をしたばかりであるので、これは異例といっても良いだろう。それだけプレスター・ジョンの軍勢は統制が取れているといっても良い。
数日の行程を経てヌルガン城にたどり着いた時、城の前には人だかりができ、かなり騒がしかった。聞こえて来るのは様々な言語による応援や歓声だ。よく見るとその人だかりの正体は武装した兵士たちである。ぱっと見たところ数百人は超えている。
もしもこの兵士たちが時光達に襲いかかったら、ひとたまりもないだろう。
「あれは?」
時光は落ち着いた様子でウリエルに尋ねる。襲撃されたら、という恐怖はもちろんあるが、武士にとって臆病者と誹られることは絶対にあってはならない。そのためには虚勢も必要だ。また、殺すだけなら道中いくらでも機会があったのだ。この期に及んで攻撃を仕掛けて来る恐れは無いだろうという公算もある。
「あれは軍事教練ですな。我々は元朝皇帝たるフビライ様から、この地域の安寧を命じられております。それには弛まぬ修練が必要です。客人を迎える時に騒がしいですが、ご容赦ください」
「そうですか」
ウリエルは落ち着いた口調で丁寧に答えたが、時光は相手の真意に気が付いていた。軍事力を間近で見せつけることで脅しをかけようというのである。もしも従わなければ今見せている精鋭たちを相手にすることになる――単純だが古来から行われてきた恫喝方法であり、それだけに安定と信頼の脅迫手段だ。
「お。蒙古も流鏑馬 をやるんだな。馬上で弓を扱う兵はどこでも同じ様な修練をするんだな」
「固定した的だけではなく、鹿や猪などの獲物を狙う訓練もありますよ」
「犬追物みたいだな。これも同じだ」
時光はいかにも興味津々といった明るい口調で感想を述べた。恫喝に対して恐れを見せてしまったら、それは弱みである。今後の交渉で不利になってしまうので、それは絶対に避けなければならない。逆に平然として見せ、更には相手の実力を探る位の事はするのが兵法というものだ。
また、蒙古兵が馬を走らせながら並んだ的に弓を放つという、日本でいう所の流鏑馬と同じ様な訓練をしていたことに驚きと興味を感じたのは事実である。時光も幼いころから立派な武士になるため、流鏑馬や犬追物をして訓練に励んだのだ。同じような光景をみると親近感を覚える。
「あれは……長槍を持った騎兵が一対一でぶつかり合うのか。中々迫力があるな」
「あれは……」
「あれは馬上槍試合 と言って我々騎士の重要な訓練であるな」
ウリエルの言葉を遮って話しかけてきたのは、鎖帷子 に身を包んだ老人だった。老人とは言ってもかくしゃくとしており、衰えた様子は全く見えない。かなり大柄でその迫力は時光も内心圧倒された。
「失礼。名乗ってなかったな。我が名はミハイル。プレスター・ジョンに仕える騎士を束ねている。いつぞやの戦いでは世話になったな」
「こちらこそ。相模国の撓気十四郎時光 と申します。半年前にはこちらこそ。まあいずれ……」
半年前の戦いでは、時光はミハイルに一度目は完全な敗北、二度目は様々な要因で引き分けに持ち込んだものの戦闘では策に嵌っており、負け続けだ。いずれどうするのかは明言しなかったが、その胸に期するものがあるのだろう。
「なるほど。ヨーロッパではあの様にして騎士同士の突撃が主戦力なのですね?」
「左様。騎兵槍 による突撃こそ騎士の誉れ、戦の雌雄を決するものである。それ故、相手の騎士に後れを取らぬようああやって技量を高めているのだ」
「しかし、この東方地域には他に騎士を抱える軍団は無いのだから、騎士同士の衝突を前提にした訓練は無意味では?」
「……はっはっは!」
ミハイルは誤魔化すように豪快に笑った。別に気分を悪くした様子は見えない。騎士同士の戦いはこの地域ではないのだが、恐らく騎士としての矜持だとか、騎兵突撃の練度向上に最適だとか、闘争心の高揚だとか色々な意味合いがあるのだろう。また、ミハイルは突撃一辺倒の騎士ではない。氷上で大軍に後方を突かれた時、投石器で氷を砕いて敵を水に沈めるような奇策も使える人物である。何も考えていないなど、甘く見るわけにはいかない。
「あれは相撲ですか?」
「スモウ? ああ取っ組み合いの事か。あれはモンゴル人がやっている競技で、モンゴル相撲 というらしいな。我々ヨーロッパでのレスリングに近いな」
「そうですか。しかし、あそこで戦っている者。相手がかなりの巨漢なのに一歩も引かず、逆に押しているくらいだ。凄いな」
「あれはな……」
ミハイル達が答える前に決着がついた。小柄な方の男が巨漢を投げ飛ばして地面に倒し、時光達の方にゆっくりと歩み寄って来た。
「よくぞここまで来たな。タワケ=トキミツ。俺の名はタシアラ、皆からはプレスター・ジョンと呼ばれている。歓迎するぞ」
モンゴル相撲で相手を圧倒していた人物、それはこの地域におけるモンゴル帝国の支配者であるプレスター・ジョンその人であった。
道中、ウリエルは時光に歴代王朝の歴史や文学について親し気に話しかけられていた。どうやら時光が漢詩を口ずさんでいた事から、漢人の知識人としての琴線に触れたらしい。その様ははっきり言って馴れ馴れしい程で、よっぽどこの様な会話を出来る相手に飢えていたようだ。
プレスター・ジョンの配下は多種多様である程度の知識人も含まれているが、それは西洋のキリスト教世界の者達が多く、東方世界の出身者は当然ながらモンゴル人がほとんどである。
モンゴル人は最近まで独自の文字を持っておらず、最近チベットの高僧にモンゴル語のために作らせたパスパ文字もまだ広まってはいない。口承文学や舞踏、楽曲には見るべきものがあるが、流石に漢人が積み上げて来たそれとは比較にならない。言ってみればモンゴル人は漢人から見れば蛮族なのである。
まあ当然のことながら日本人である時光も、漢人からしてみれば東夷であり紛れもない野蛮人である。その蛮族が漢詩等の文学に親しんでおりそれなりの知識を持っていたというのだから余計驚き、嬉しかったのかもしれない。また、お互い兵法にも通じているため、半年前の戦いで時光がトナカイを代用として実行した火牛の計に関して、戦国時代の田単の話などに話が飛び、大いに盛り上がった。
なお、今までの書き方からするとウリエルが周辺の日本人も含む異民族を低く見ている、いわゆる中華思想というある意味差別的な思想を持っているようにも思えるが、当時の漢人の王朝である宋とその他の国には文明度に格段の差がある。それはヨーロッパの国々も同様であり、漢人から見ればモンゴルも日本も、フランスもイングランドも野蛮国といっても過言ではない。宋王朝に匹敵する文明を持っているのは、中東付近の一部の国家位であろう。
とは言え野蛮な国々であっても戦闘力や、それに付随する一部の技術だけは高かったりするために、宋王朝は滅亡の危機に瀕しているのだが。
ともあれ、迎える側の幹部が迎えられる側の代表に好意的になったのだ、道中は実に快適に過ごすことができ、不愉快な思いをすることは無かった。半年前に大きな戦闘をしたばかりであるので、これは異例といっても良いだろう。それだけプレスター・ジョンの軍勢は統制が取れているといっても良い。
数日の行程を経てヌルガン城にたどり着いた時、城の前には人だかりができ、かなり騒がしかった。聞こえて来るのは様々な言語による応援や歓声だ。よく見るとその人だかりの正体は武装した兵士たちである。ぱっと見たところ数百人は超えている。
もしもこの兵士たちが時光達に襲いかかったら、ひとたまりもないだろう。
「あれは?」
時光は落ち着いた様子でウリエルに尋ねる。襲撃されたら、という恐怖はもちろんあるが、武士にとって臆病者と誹られることは絶対にあってはならない。そのためには虚勢も必要だ。また、殺すだけなら道中いくらでも機会があったのだ。この期に及んで攻撃を仕掛けて来る恐れは無いだろうという公算もある。
「あれは軍事教練ですな。我々は元朝皇帝たるフビライ様から、この地域の安寧を命じられております。それには弛まぬ修練が必要です。客人を迎える時に騒がしいですが、ご容赦ください」
「そうですか」
ウリエルは落ち着いた口調で丁寧に答えたが、時光は相手の真意に気が付いていた。軍事力を間近で見せつけることで脅しをかけようというのである。もしも従わなければ今見せている精鋭たちを相手にすることになる――単純だが古来から行われてきた恫喝方法であり、それだけに安定と信頼の脅迫手段だ。
「お。蒙古も
「固定した的だけではなく、鹿や猪などの獲物を狙う訓練もありますよ」
「犬追物みたいだな。これも同じだ」
時光はいかにも興味津々といった明るい口調で感想を述べた。恫喝に対して恐れを見せてしまったら、それは弱みである。今後の交渉で不利になってしまうので、それは絶対に避けなければならない。逆に平然として見せ、更には相手の実力を探る位の事はするのが兵法というものだ。
また、蒙古兵が馬を走らせながら並んだ的に弓を放つという、日本でいう所の流鏑馬と同じ様な訓練をしていたことに驚きと興味を感じたのは事実である。時光も幼いころから立派な武士になるため、流鏑馬や犬追物をして訓練に励んだのだ。同じような光景をみると親近感を覚える。
「あれは……長槍を持った騎兵が一対一でぶつかり合うのか。中々迫力があるな」
「あれは……」
「あれは
ウリエルの言葉を遮って話しかけてきたのは、
「失礼。名乗ってなかったな。我が名はミハイル。プレスター・ジョンに仕える騎士を束ねている。いつぞやの戦いでは世話になったな」
「こちらこそ。相模国の
半年前の戦いでは、時光はミハイルに一度目は完全な敗北、二度目は様々な要因で引き分けに持ち込んだものの戦闘では策に嵌っており、負け続けだ。いずれどうするのかは明言しなかったが、その胸に期するものがあるのだろう。
「なるほど。ヨーロッパではあの様にして騎士同士の突撃が主戦力なのですね?」
「左様。
「しかし、この東方地域には他に騎士を抱える軍団は無いのだから、騎士同士の衝突を前提にした訓練は無意味では?」
「……はっはっは!」
ミハイルは誤魔化すように豪快に笑った。別に気分を悪くした様子は見えない。騎士同士の戦いはこの地域ではないのだが、恐らく騎士としての矜持だとか、騎兵突撃の練度向上に最適だとか、闘争心の高揚だとか色々な意味合いがあるのだろう。また、ミハイルは突撃一辺倒の騎士ではない。氷上で大軍に後方を突かれた時、投石器で氷を砕いて敵を水に沈めるような奇策も使える人物である。何も考えていないなど、甘く見るわけにはいかない。
「あれは相撲ですか?」
「スモウ? ああ取っ組み合いの事か。あれはモンゴル人がやっている競技で、
「そうですか。しかし、あそこで戦っている者。相手がかなりの巨漢なのに一歩も引かず、逆に押しているくらいだ。凄いな」
「あれはな……」
ミハイル達が答える前に決着がついた。小柄な方の男が巨漢を投げ飛ばして地面に倒し、時光達の方にゆっくりと歩み寄って来た。
「よくぞここまで来たな。タワケ=トキミツ。俺の名はタシアラ、皆からはプレスター・ジョンと呼ばれている。歓迎するぞ」
モンゴル相撲で相手を圧倒していた人物、それはこの地域におけるモンゴル帝国の支配者であるプレスター・ジョンその人であった。