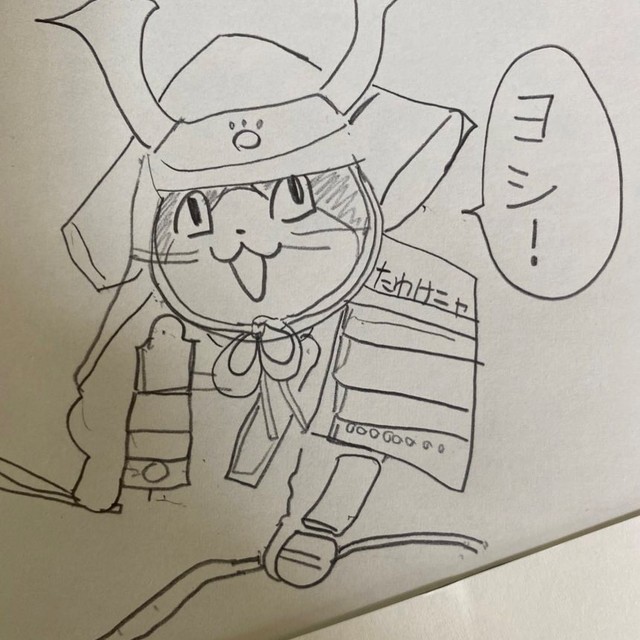第34話「鉄騎兵」
文字数 3,189文字
白主土城から追い払われたモンゴル軍に対する追撃は、執拗なものとなった。
軍を率いるアラムダルの統率力により軍規は保たれている。これは無能な大将を頂いていた時よりも、強敵になっていると言っても良い。勇将の下に弱卒なしとはよく言ったものである。統率力の低い大将であったバルタンを死なせてしまったのは、時光の誤算と言っても良いだろう。とは言え副将がこれ程の統率力を発揮するなどとは予想するのは難しい。バルタンよりも多少有能であったとしても、凡百の指揮官なら敵地奥深くで孤立した状況で、軍を立て直すなど不可能なのだからだ。
しかし、いかに指揮官が優れていようと、物理的な限界があると時光は踏んでいた。携行している保存食では、食いつないでも一週間が限界であろうし、モンゴル軍の主な武器であり大陸を制した強力な弓も、放つべき矢が早晩尽きてしまうことは当然の帰結である。
「ここは慎重に行かねばならんな」
「一揉みに押しつぶせないか? 最早圧倒的に有利だろう」
慎重策を唱える時光に、アイヌの戦士団を率いるサケノンクルが短期決戦の可能性について尋ねた。
「いや、まだそれには時期尚早だ。奴らはまだ軍規を保っている。あれと決戦をすれば負けないだろうが、こちらも出血は避けられない。決定的な一撃はまだ先だ」
「お前がそういうならそうするとしよう。しかし、奴らが弱るのを待つとして、それまで何かすることはないのか?」
「そうだな……」
時光はしばらく考え込んだ。
「先ずは当然のことながら斥侯を派遣して、奴らの行動を逐一観察するとしよう。そうでなければ決戦を挑むことも出来ないからな」
「まあ当たり前の事だな。もうそれ位の指示は出している」
敵の動きを探ることは戦 において当然の事である。人間同士の戦の経験に乏しいアイヌではあるが、狩猟においても獲物の動きを探るのは当たり前の事だ。これを応用して情報収集活動は怠る事はない。
「次に夜襲を繰り返して奴らを休ませない事だ。アイヌは夜戦に長けているし、この前の蝦夷ヶ島での蒙古軍との戦いでもこの方法で有利に進めることが出来た。この方法は今回も有効だろう」
「分かった。この前と同じ要領だな。こちらは休みながら戦えるように、いくつか隊を編成して順番に戦わせるとしよう」
蝦夷ヶ島での戦いで、時光と共に夜襲を実行した経験のあるエコリアチは時光の意図を理解し、それを実行するべくアイヌの戦士団の主だった者達に指示をするために離れて行った。
「後はこのカラプトの島中に住むニヴフ達に、蜂起を促すための使者を派遣するんだ。この前も俺が少しはやってきたが、まだその時は蒙古軍が優勢だったから、今この有利な状況でした方が効果が高いだろう。戦後の事を見据えても彼らを味方につけるのは必要だと思う。味方にできなかったとしても、蒙古軍に味方されるのだけでも防いでおきたい」
「確かにこの島の全土に散らばるニヴフ達にモンゴルに協力されたら、補給されながら離脱されてしまうからな。分かった。ニヴフと交流のある奴らを中心に、先回りするとしよう」
妹がニヴフに嫁いでおり関係の深いウテレキがそう返答すると、カラプトで暮らしていた経験のあるアイヌとともに本隊から出発した。
思いつく限りの策は実行した。後は果報を待つだけであると時光は思っていた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
白主土城での戦いから一週間ほど経過した後の事である。
戦況は時光達が予期していたのと同様に推移していた。
アイヌ側は決定的な攻撃を仕掛けることなくモンゴル軍を追い詰め、主に夜間に実施される攻撃で疲労を蓄積させ続けていた。また、モンゴル軍の撤退経路と予想される地域に存在するニヴフの村に、まとまった戦力を先行的に派遣することで補給を防ぎ、アイヌ側有利をニヴフ達に印象付けさせていった。
このままいけば、モンゴル軍の補給は尽き、カラプトの主要な民族であるニヴフの、アイヌとモンゴルのどちらに味方するかの去就も明らかになるはずである。
カラプト島から大陸に渡る地点への道のりは、どう見積っても三分の一程度なので、最早モンゴル軍が撤退に成功する見込みはないはずである。
もうそろそろ、本格的な攻撃か降伏勧告を試みるべきであろうかと、時光達が作戦を練っていたその時の事である。
「北から騎馬の集団が現れ、こちらに向かっている! その数約二千!」
斥侯から急報がもたらされた。斥侯であるアイヌの戦士は本当に急いでいたらしく、全身から湯気を発し体にまとわりつく粉雪を溶かしていた。
「騎馬の集団? 二千?」
「どうする? トキミツ。二千程度ならこちらの方が数なら上だ。この前と同じような戦法で勝てるんじゃないか??」
「そうかもしれんが……騎馬の集団と言うのが気になるな。騎兵はどの位いたんだ? 二十か? 三十か?」
強力な騎兵が特徴のモンゴル軍ではあるが、海を隔てた戦場にまで大量に馬を輸送するのは難しい。蝦夷ヶ島で活動していたモンゴル軍の斥侯は現地の日本人協力者である安藤五郎から提供された数頭の馬しか運用していなかったし、今まで戦ってきたカラプト駐留部隊は千から2千の部隊の内、騎兵は二十程度であった。ならば増援部隊における騎兵の割合も同じ程度のはずであった。しかし、
「それが……数百は騎兵であるかと……」
「騎兵数百だと!」
「見間違いではないのか?!」
時光やサケノンクルの首脳陣は斥侯の返答に驚愕した。モンゴル軍の騎兵の恐ろしさは、これまでの戦いで嫌と言うほど理解している。二十程度のモンゴル騎兵にすら苦戦していたのに、それが数百となればどれだけ恐ろしいものなのか想像すらできない。
出来れば斥侯の見間違いで、多くても百程度に収まって欲しい。
「いや、平地で隊列を組み、その前面に大量の騎兵を押し立てて進軍していた。数百と言うのは間違いではない」
「何という事だ……」
あまりの事態に時光は天を仰いだが、すぐに気を取り直して意識を戦いに向ける。
「来てしまったものは仕方がない。現実を見据えよう。戦の支度だサケノンクル。半数は分散配置で身を隠し、残りの本隊は敵が崩れたところを叩くぞ」
時光達は一週間前にモンゴル軍を打ち破った時と同様、散兵戦術を取ることにした。この戦法はアイヌの戦士の、弓の腕前と優れた狩人として独立行動をとれるという特性を、最も発揮して戦うことが出来るのだ。
「後、騎兵は今まで見たことが無いのが混じっている。気を付けてくれ」
戦いの方針を決めた時光達に、斥侯が今までの報告に付け加えてきた。
「見たことが無い奴? どんなやつだ?」
「分厚い鎧を着こんでいて、長い槍を持っていた」
「ああ。そう言えば蒙古の騎兵には重装備のもいるらしいな。確か金属の鎧を着ていて、槍と弓を使い分けるとか。そうだったな? グリエルモさん」
時光は傍らに控えていた羅馬 の坊主であるグリエルモに確認するように言った。グリエルモは大陸の西から旅を続けて蝦夷ヶ島まで来ており、モンゴル軍についてもかなりの知識がある。時光はモンゴル軍は軽装の弓騎兵だけではなく、重装騎兵もいることを知っていた。むしろ、この重装騎兵こそが軍の中核ともいえる精鋭なのだ。
「左様。軽装の弓騎兵だけでは決定力に欠け、大陸を制覇するまでは出来ません。モンゴルの重装騎兵が出てきたという事は、いよいよ本格的に侵攻してきたという事でしょうな」
時光の見解にグリエルモも同意見のようであった。しかし、斥侯は気になる事を付け加えてきた。
「そいつらは顔まで兜で覆い、弓は持っていなかった。そんで、大きな盾を持っていて……そう、そこのあんたが首から下げているそれと同じ模様が描かれていた」
斥侯の男が指さしたのは、グリエルモが首に下げている十字架であった。
軍を率いるアラムダルの統率力により軍規は保たれている。これは無能な大将を頂いていた時よりも、強敵になっていると言っても良い。勇将の下に弱卒なしとはよく言ったものである。統率力の低い大将であったバルタンを死なせてしまったのは、時光の誤算と言っても良いだろう。とは言え副将がこれ程の統率力を発揮するなどとは予想するのは難しい。バルタンよりも多少有能であったとしても、凡百の指揮官なら敵地奥深くで孤立した状況で、軍を立て直すなど不可能なのだからだ。
しかし、いかに指揮官が優れていようと、物理的な限界があると時光は踏んでいた。携行している保存食では、食いつないでも一週間が限界であろうし、モンゴル軍の主な武器であり大陸を制した強力な弓も、放つべき矢が早晩尽きてしまうことは当然の帰結である。
「ここは慎重に行かねばならんな」
「一揉みに押しつぶせないか? 最早圧倒的に有利だろう」
慎重策を唱える時光に、アイヌの戦士団を率いるサケノンクルが短期決戦の可能性について尋ねた。
「いや、まだそれには時期尚早だ。奴らはまだ軍規を保っている。あれと決戦をすれば負けないだろうが、こちらも出血は避けられない。決定的な一撃はまだ先だ」
「お前がそういうならそうするとしよう。しかし、奴らが弱るのを待つとして、それまで何かすることはないのか?」
「そうだな……」
時光はしばらく考え込んだ。
「先ずは当然のことながら斥侯を派遣して、奴らの行動を逐一観察するとしよう。そうでなければ決戦を挑むことも出来ないからな」
「まあ当たり前の事だな。もうそれ位の指示は出している」
敵の動きを探ることは
「次に夜襲を繰り返して奴らを休ませない事だ。アイヌは夜戦に長けているし、この前の蝦夷ヶ島での蒙古軍との戦いでもこの方法で有利に進めることが出来た。この方法は今回も有効だろう」
「分かった。この前と同じ要領だな。こちらは休みながら戦えるように、いくつか隊を編成して順番に戦わせるとしよう」
蝦夷ヶ島での戦いで、時光と共に夜襲を実行した経験のあるエコリアチは時光の意図を理解し、それを実行するべくアイヌの戦士団の主だった者達に指示をするために離れて行った。
「後はこのカラプトの島中に住むニヴフ達に、蜂起を促すための使者を派遣するんだ。この前も俺が少しはやってきたが、まだその時は蒙古軍が優勢だったから、今この有利な状況でした方が効果が高いだろう。戦後の事を見据えても彼らを味方につけるのは必要だと思う。味方にできなかったとしても、蒙古軍に味方されるのだけでも防いでおきたい」
「確かにこの島の全土に散らばるニヴフ達にモンゴルに協力されたら、補給されながら離脱されてしまうからな。分かった。ニヴフと交流のある奴らを中心に、先回りするとしよう」
妹がニヴフに嫁いでおり関係の深いウテレキがそう返答すると、カラプトで暮らしていた経験のあるアイヌとともに本隊から出発した。
思いつく限りの策は実行した。後は果報を待つだけであると時光は思っていた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
白主土城での戦いから一週間ほど経過した後の事である。
戦況は時光達が予期していたのと同様に推移していた。
アイヌ側は決定的な攻撃を仕掛けることなくモンゴル軍を追い詰め、主に夜間に実施される攻撃で疲労を蓄積させ続けていた。また、モンゴル軍の撤退経路と予想される地域に存在するニヴフの村に、まとまった戦力を先行的に派遣することで補給を防ぎ、アイヌ側有利をニヴフ達に印象付けさせていった。
このままいけば、モンゴル軍の補給は尽き、カラプトの主要な民族であるニヴフの、アイヌとモンゴルのどちらに味方するかの去就も明らかになるはずである。
カラプト島から大陸に渡る地点への道のりは、どう見積っても三分の一程度なので、最早モンゴル軍が撤退に成功する見込みはないはずである。
もうそろそろ、本格的な攻撃か降伏勧告を試みるべきであろうかと、時光達が作戦を練っていたその時の事である。
「北から騎馬の集団が現れ、こちらに向かっている! その数約二千!」
斥侯から急報がもたらされた。斥侯であるアイヌの戦士は本当に急いでいたらしく、全身から湯気を発し体にまとわりつく粉雪を溶かしていた。
「騎馬の集団? 二千?」
「どうする? トキミツ。二千程度ならこちらの方が数なら上だ。この前と同じような戦法で勝てるんじゃないか??」
「そうかもしれんが……騎馬の集団と言うのが気になるな。騎兵はどの位いたんだ? 二十か? 三十か?」
強力な騎兵が特徴のモンゴル軍ではあるが、海を隔てた戦場にまで大量に馬を輸送するのは難しい。蝦夷ヶ島で活動していたモンゴル軍の斥侯は現地の日本人協力者である安藤五郎から提供された数頭の馬しか運用していなかったし、今まで戦ってきたカラプト駐留部隊は千から2千の部隊の内、騎兵は二十程度であった。ならば増援部隊における騎兵の割合も同じ程度のはずであった。しかし、
「それが……数百は騎兵であるかと……」
「騎兵数百だと!」
「見間違いではないのか?!」
時光やサケノンクルの首脳陣は斥侯の返答に驚愕した。モンゴル軍の騎兵の恐ろしさは、これまでの戦いで嫌と言うほど理解している。二十程度のモンゴル騎兵にすら苦戦していたのに、それが数百となればどれだけ恐ろしいものなのか想像すらできない。
出来れば斥侯の見間違いで、多くても百程度に収まって欲しい。
「いや、平地で隊列を組み、その前面に大量の騎兵を押し立てて進軍していた。数百と言うのは間違いではない」
「何という事だ……」
あまりの事態に時光は天を仰いだが、すぐに気を取り直して意識を戦いに向ける。
「来てしまったものは仕方がない。現実を見据えよう。戦の支度だサケノンクル。半数は分散配置で身を隠し、残りの本隊は敵が崩れたところを叩くぞ」
時光達は一週間前にモンゴル軍を打ち破った時と同様、散兵戦術を取ることにした。この戦法はアイヌの戦士の、弓の腕前と優れた狩人として独立行動をとれるという特性を、最も発揮して戦うことが出来るのだ。
「後、騎兵は今まで見たことが無いのが混じっている。気を付けてくれ」
戦いの方針を決めた時光達に、斥侯が今までの報告に付け加えてきた。
「見たことが無い奴? どんなやつだ?」
「分厚い鎧を着こんでいて、長い槍を持っていた」
「ああ。そう言えば蒙古の騎兵には重装備のもいるらしいな。確か金属の鎧を着ていて、槍と弓を使い分けるとか。そうだったな? グリエルモさん」
時光は傍らに控えていた
「左様。軽装の弓騎兵だけでは決定力に欠け、大陸を制覇するまでは出来ません。モンゴルの重装騎兵が出てきたという事は、いよいよ本格的に侵攻してきたという事でしょうな」
時光の見解にグリエルモも同意見のようであった。しかし、斥侯は気になる事を付け加えてきた。
「そいつらは顔まで兜で覆い、弓は持っていなかった。そんで、大きな盾を持っていて……そう、そこのあんたが首から下げているそれと同じ模様が描かれていた」
斥侯の男が指さしたのは、グリエルモが首に下げている十字架であった。