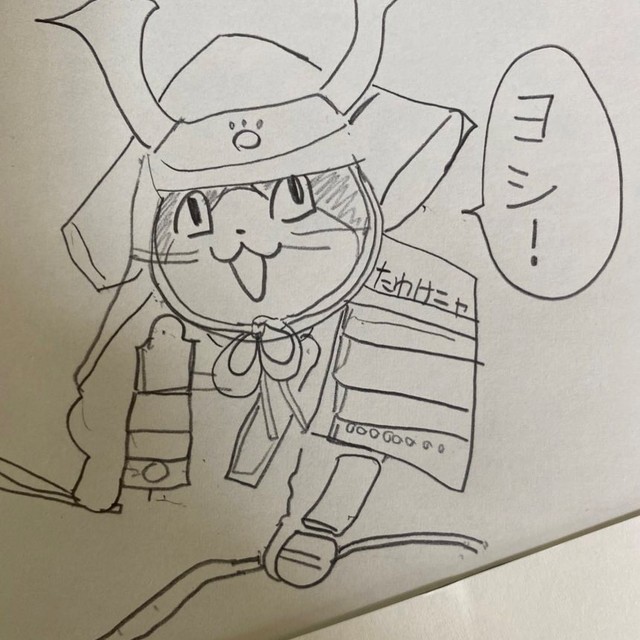第33話「額の的」
文字数 2,364文字
白主土城に戻ったカラプト駐留モンゴル軍の副将であるアラムダルを出迎えたのは、矢の雨とアイヌの戦士団を率いる日本の武士であった。
その日本の武士である撓気時光 はある人物を前に差し出してアラムダル達に叫んだ。
「見ろ! お前たちの大将だ! こいつの命が欲しければ降参するが良い! 悪いようにはしないし食料も分けてやっても良いぞ!」
「おい! アラムダル! 早く俺を助けろ! これは命令だ!」
「ぬうぅ……」
「アラムダル様。これはまずいのでは?」
「分かっている!」
時光に捕らえられて縄で縛られている大将であるバルタンは、モンゴルの有力な一族出身の貴族で、これを見捨てるのはモンゴル帝国内における立場を非常に悪くすることは予想できる。例え無様な姿を晒し、勝手な事を喚いていてもだ。自害でもすればよかったのにと、アラムダルは心の中で無能な上官に毒づいた。
しかし、大陸においてその威を示し、覇を唱えた誇り高きモンゴル軍の一員として、降参するのも問題である。
そして、自分達の大将が無様に捕虜になっているという事実は、アラムダルの配下たちの士気を著しく低下させていた。このままではアイヌの戦士団の本隊の追撃と、城の挟み撃ちになって一敗地に塗れてしまうだろう。
アラムダルは判断に困っていた。
「どうした? 返事がないぞ?! そうだ! ちょっとした遊びをしよう!」
悩んでいるアラムダルを眺めていた時光は、ふとしたことを思いついて懐から木炭の棒を取り出し、バルタンの額に丸の印を書いた。
これを見ていたアラムダル達は時光の意図を察した。要はこの印に矢を当ててみろという事なのだ。
見え透いた挑発だが、士気も態勢も最悪な状態の軍勢にはこれが中々に効く。このままでは退くも進むもならず、戦いの際には自信を喪失したまま臨むことになってしまうだろう。モンゴル族にとって弓は馬に並んで男達の誇りなのだ。その腕前を嘲弄され、それを雪 げないなど、戦士の誇りも何もあったものではない。
しかし、あまりの挑発に対して逆に覚悟を固めた男がただ一人いた。
「ふん! 城の骨嵬 どもと倭人よ! そして蒼き狼の血を引く勇者たちよ! 見るがいい!」
アラムダルは城の中の敵と配下の兵士たちに向かって吠えると、目にも止まらぬ速さで弓矢を構え、刹那の狙いの後に矢を放った。
「おおっ!」
「見事!」
アラムダルが放った矢は見事バルタンの額に書かれた丸印に突き立った。
城から矢降り注ぐため近づけず百歩は離れており、城と言う高所に位置する目標に対する狙撃はまさに神業と言っても過言ではない。しかも両陣営が見守る中で自らの上官を射殺するという、通常では考えられない重圧の中での事である。
もし外した場合、当然ながら士気はがた落ちになり、最早まともに戦うことが出来ないだろう。そして、例え生き延びたとしても生き残ったバルタンがモンゴル帝国に戻った時、皇帝のフビライに何を吹き込むか分かったものではない。フビライは英邁な君主であるが、やはり有力者の発言は重視せねばならず、アラムダルにどのような罰が待っているのやら想像することも出来ない。
その様な事情を察しているモンゴル軍兵士は、見事モンゴル族の戦士の誇りを守って神技を見せたアラムダルに惜しみの無い賛辞を贈った。
湧き立ったのはモンゴル軍だけではない、弓の達者揃いのアイヌの戦士団には、アラムダルの見せた技がどれだけ賞賛に値するものかよく理解できている。素朴な性質を残す彼らは両手両足を打ち鳴らして敵であるアラムダルを称えた。
一人の男を除いては、
「皆! 危ない! 身を隠せっ!」
「……え?」
時光の焦ったような指示に、アイヌの戦士団は疑問を持ちながらも物陰に身を隠した。
特に何も起こらなかったのだが。
「トキミツ。一体どうしたというのだ? 危険な事など何も起きないではないか」
「いや、無防備に敵を称えていると、その隙に追撃の矢が飛んで来て射殺されると思ったんだが……来ないな……」
相変わらずの戦闘狂な発想をする時光に、オピポーは呆れた顔をした。
「待て待てトキミツ。戦いの最中であっても、優れた勇者を称えるというのは普通の事だろう? それは奴らだって同じことだろう。無暗に警戒しすぎることはない」
「えーと……いや、ああ分かった」
何やら言い訳しようとしていた時光は、それを止めて素直にうなずくことにした。
確かにオピポーが言う通り、戦場にあって敵であろうとも優れた戦士を褒め称えるのは古今東西変わる事はない。ただ、その様な状況で容赦なく隙を見せた敵をぶち殺す者どもも存在しているのだ。
それは、日本とかいう辺境の島国に生息する、武士とか呼ばれる野蛮な戦闘集団のことなのだが。
「おい、トキミツ。モンゴルの奴ら逃げていくぞ」
「え?」
オピポーに言われて城の外に目をやると、撤退していくモンゴル軍が見えた。
「どうする? 追撃するか?」
「やめておこう。城にいるのは寡兵だ。いくら追撃戦でも危険すぎる」
整斉と隊列を整えて遠ざかるモンゴル軍を観察して、時光はそう言った。
とは言え戦 は勢いである。士気が下がり統率が取れない状態のモンゴル軍相手なら、戦力差があっても追撃出来た可能性は十分あった。自分の挑発行為を逆手に取られたために、敵が勢いを取り戻してしまった事に時光は深く反省した。あのような常識外れの力技で切り抜けられるなど、予想できなかったとしても仕方がない面もあるが、戦とは結果が全てである。
「伝令を出すぞ。撤退するあいつらと直接ぶつかるのは危険だ。狩りで獲物を追い詰めるように、じわじわとやるとな」
「分かった。すぐに本隊のサケノンクルに伝えよう」
カラプトにおけるモンゴル軍との戦いは、長期戦になるであろうことを時光は予感するのであった。
その日本の武士である
「見ろ! お前たちの大将だ! こいつの命が欲しければ降参するが良い! 悪いようにはしないし食料も分けてやっても良いぞ!」
「おい! アラムダル! 早く俺を助けろ! これは命令だ!」
「ぬうぅ……」
「アラムダル様。これはまずいのでは?」
「分かっている!」
時光に捕らえられて縄で縛られている大将であるバルタンは、モンゴルの有力な一族出身の貴族で、これを見捨てるのはモンゴル帝国内における立場を非常に悪くすることは予想できる。例え無様な姿を晒し、勝手な事を喚いていてもだ。自害でもすればよかったのにと、アラムダルは心の中で無能な上官に毒づいた。
しかし、大陸においてその威を示し、覇を唱えた誇り高きモンゴル軍の一員として、降参するのも問題である。
そして、自分達の大将が無様に捕虜になっているという事実は、アラムダルの配下たちの士気を著しく低下させていた。このままではアイヌの戦士団の本隊の追撃と、城の挟み撃ちになって一敗地に塗れてしまうだろう。
アラムダルは判断に困っていた。
「どうした? 返事がないぞ?! そうだ! ちょっとした遊びをしよう!」
悩んでいるアラムダルを眺めていた時光は、ふとしたことを思いついて懐から木炭の棒を取り出し、バルタンの額に丸の印を書いた。
これを見ていたアラムダル達は時光の意図を察した。要はこの印に矢を当ててみろという事なのだ。
見え透いた挑発だが、士気も態勢も最悪な状態の軍勢にはこれが中々に効く。このままでは退くも進むもならず、戦いの際には自信を喪失したまま臨むことになってしまうだろう。モンゴル族にとって弓は馬に並んで男達の誇りなのだ。その腕前を嘲弄され、それを
しかし、あまりの挑発に対して逆に覚悟を固めた男がただ一人いた。
「ふん! 城の
アラムダルは城の中の敵と配下の兵士たちに向かって吠えると、目にも止まらぬ速さで弓矢を構え、刹那の狙いの後に矢を放った。
「おおっ!」
「見事!」
アラムダルが放った矢は見事バルタンの額に書かれた丸印に突き立った。
城から矢降り注ぐため近づけず百歩は離れており、城と言う高所に位置する目標に対する狙撃はまさに神業と言っても過言ではない。しかも両陣営が見守る中で自らの上官を射殺するという、通常では考えられない重圧の中での事である。
もし外した場合、当然ながら士気はがた落ちになり、最早まともに戦うことが出来ないだろう。そして、例え生き延びたとしても生き残ったバルタンがモンゴル帝国に戻った時、皇帝のフビライに何を吹き込むか分かったものではない。フビライは英邁な君主であるが、やはり有力者の発言は重視せねばならず、アラムダルにどのような罰が待っているのやら想像することも出来ない。
その様な事情を察しているモンゴル軍兵士は、見事モンゴル族の戦士の誇りを守って神技を見せたアラムダルに惜しみの無い賛辞を贈った。
湧き立ったのはモンゴル軍だけではない、弓の達者揃いのアイヌの戦士団には、アラムダルの見せた技がどれだけ賞賛に値するものかよく理解できている。素朴な性質を残す彼らは両手両足を打ち鳴らして敵であるアラムダルを称えた。
一人の男を除いては、
「皆! 危ない! 身を隠せっ!」
「……え?」
時光の焦ったような指示に、アイヌの戦士団は疑問を持ちながらも物陰に身を隠した。
特に何も起こらなかったのだが。
「トキミツ。一体どうしたというのだ? 危険な事など何も起きないではないか」
「いや、無防備に敵を称えていると、その隙に追撃の矢が飛んで来て射殺されると思ったんだが……来ないな……」
相変わらずの戦闘狂な発想をする時光に、オピポーは呆れた顔をした。
「待て待てトキミツ。戦いの最中であっても、優れた勇者を称えるというのは普通の事だろう? それは奴らだって同じことだろう。無暗に警戒しすぎることはない」
「えーと……いや、ああ分かった」
何やら言い訳しようとしていた時光は、それを止めて素直にうなずくことにした。
確かにオピポーが言う通り、戦場にあって敵であろうとも優れた戦士を褒め称えるのは古今東西変わる事はない。ただ、その様な状況で容赦なく隙を見せた敵をぶち殺す者どもも存在しているのだ。
それは、日本とかいう辺境の島国に生息する、武士とか呼ばれる野蛮な戦闘集団のことなのだが。
「おい、トキミツ。モンゴルの奴ら逃げていくぞ」
「え?」
オピポーに言われて城の外に目をやると、撤退していくモンゴル軍が見えた。
「どうする? 追撃するか?」
「やめておこう。城にいるのは寡兵だ。いくら追撃戦でも危険すぎる」
整斉と隊列を整えて遠ざかるモンゴル軍を観察して、時光はそう言った。
とは言え
「伝令を出すぞ。撤退するあいつらと直接ぶつかるのは危険だ。狩りで獲物を追い詰めるように、じわじわとやるとな」
「分かった。すぐに本隊のサケノンクルに伝えよう」
カラプトにおけるモンゴル軍との戦いは、長期戦になるであろうことを時光は予感するのであった。