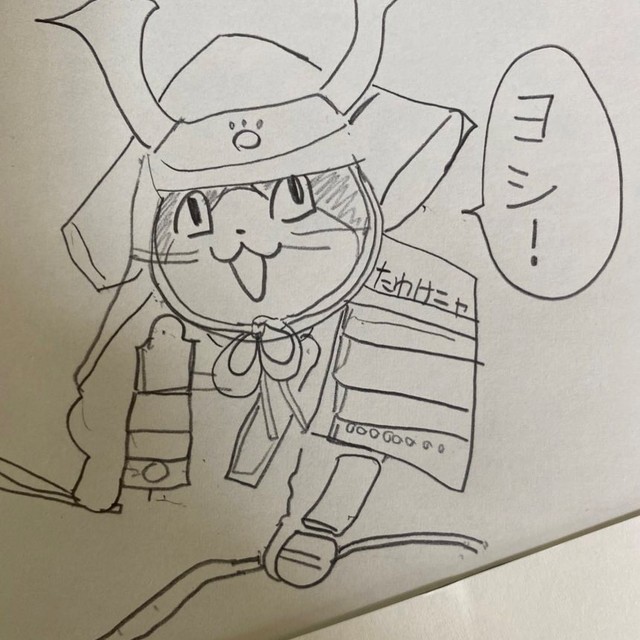第39話「蝦夷守就任」
文字数 4,586文字
アイヌの戦士団による槍衾により、モンゴル軍の騎士団の騎兵槍突撃 は完全に防がれた。ある者は槍に自ら追突して串刺しとなり、ある者は穂先を恐れて棹立ちとなった馬から落下してしまっている。
完全に混乱していると言ってよいだろう。立ち止まったモンゴル軍に正確な矢が狙い撃ちされ、次々と倒れ伏していく。鎧の隙間への射撃でかすり傷かもしれないが、アイヌの矢には毒が塗られている。即死しなくても戦闘不能にするには十分だ。
「今だ! 切り込むぞ!」
ただ一人騎乗している時光の合図の下、アイヌの戦士団の一部が混乱状態にある騎士達に向かって徒歩で突撃を敢行した。彼らの手には、槍だけでなく日本で作られた太刀が握られている。時光が交易の品として持ってきたものを配分したのである。
俗に西洋の刀剣は頑丈な鎧の上からダメージを負わせることが出来るように、切れ味ではなく頑丈さを重視して打撃を与えるように作られているという説がある。それとは反対に、日本の刀剣は気候の関係上そこまで強固な鎧が発達しなかったため、丈夫さよりも切れ味重視の刀が発達したという。
それは一部正確ではない。
西洋の刀剣とて切れ味の優れた物はいくらでもあるし、日本刀は西洋の鎧を貫くことも可能なのだ。つまり、時光達の持っている太刀は、十分西洋の鎧に効果があるのだ。まして、時光達が相対している騎士達が身に付けているのは、後世の板金鎧 ではなく鎖帷子 なのだ。防御力はそこまで高くはない。
また、太刀の質も十分である。
例えば、時光の所持している太刀は、山城国の刀匠である綾小路定利の作である。綾小路定利の作品は現在では国宝や重要文化財として残っており、値を付けるとすれば莫大な物となるだろう。
しかし、綾小路定利はこの時光の生きる時代に生きた刀匠である。もちろんこの時代から活躍して、名の知られた刀匠ではあるが、文化財とかそのような付加価値はついておらず、優れた実用品としてそれなりの値段で流通している。特に時光の出身である撓気 氏は、京とも交易をしているため、公家などの仲介により優れた刀匠とも交流がある。
つまり、時光達が手にしている太刀は、現代では重要文化財級の名刀揃いなのである。チェインメイル位貫くことは容易なのだ。
時光達は次々と落馬して雪の中に埋もれてもがいている騎士や、突撃が防がれて棒立ちになってしまった騎士達に容赦なく止めを刺していく。突進力が失われた騎士などこの様なものである。最初から下馬して抜刀していれば、苦戦したであろうが最早対応は後手に回っている。
モンゴル軍の歩兵は騎兵達から少し離れているため、すぐには掩護に来ることが出来ない。また、弓騎兵は騎士とアイヌの戦士たちが混交しているため、矢の雨を降らせることが出来ないので接近して精密射撃を行おうとしているが、アイヌの矢の雨に遭い中々進むことが出来ない。
このまま敵の中核である騎士を倒してしまえば、勝機は見えて来る。時光は馬を進めながら次々と騎士達を切り伏せて行く。目指すは敵の指揮官である。
統制の取れた行動を妨害するには、指揮官を始末するのが一番である。例外として、無能な指揮官が死ぬことで有能な部下が指揮を代行し、敵が強力になることもあり、以前はそれで失敗したのだが、前回の戦いを見るにモンゴル軍騎士の指揮官は有能であると考えて間違いないはずだ。
「見つけたぞ! 覚悟!」
一際立派な上衣 を身に纏った騎士を発見し、それを目掛けて突進する。それに気づいた騎士は穂先を時光に向け、馬を走らせて迎え撃った。
「甘い! はぁっ!」
気が付いた時には時光との間合いが近く、加速がつかなかったために繰り出されるランスの一撃はそれ程の速度ではなかった。それでも当たれば鎧を着ていない時光など貫通してしまうだろうが、当たらなければどうという事はない。
時光は攻撃を体をひねって回避しながら定利の太刀を片手で振るい、ランスの柄の中ほどから断ち切った。
自慢の得物を破壊されて驚愕する騎士に向かい、時光は馬をぶつけて行く。馬上での組討ちだ。
前の章で相撲は武士の嗜みだと記述したが、これは何も徒歩の場合のみではない。武士は騎乗して戦うものなのだから、当然馬上でも素手で戦えなければならない。
有名な逸話に、源平の合戦において活躍した巴御前――木曾義仲の妻にして武将――は、最後の戦いにおいて騎乗したまま組討ちをし、敵の頭をねじ切ったという。
流石に首をねじ切るというのはあまりに非現実的であり、脚色されているのだろうが、武士が馬に乗ったまま素手で戦うことは普通に起こり得るというのを表わした話である。
巴御前ほどではないが、時光の馬上組討ちの技量は中々のものである。鮮やかに騎士の馬に跳び移ると、相手の体を抱え込んで共に地面に落ちて行った。
騎士は意外と小柄で体重が軽く、容易く捻り落とすことが出来た。落ちる態勢は時光によって制御され、騎士が下になっているため二人分の体重を騎士が受けることになる。
二人分の落馬の衝撃をまともに受けた騎士は、動かなくなった。死んだわけではない。不規則に荒い息をしている。動けないだけだ。
「覚悟!」
止めを刺すべく、時光は短刀を引き抜きながら騎士の兜を取り払った。戦場の組討ちでは、組み伏せた相手の鎧兜の一部を剥ぎ取り、短刀で止めを刺すというのが定石である。
兜を剥ぎ取った時光の目に、金髪の端正な顔立ちが飛び込んできた。
「女……だと?」
「ガウリイル!」
鋭い声と殺気が迫ってくるのを感じた時光は、女騎士の上から素早く身を翻して離れると、転がりながら間合いを取って態勢を整えた。身を起こした時光が見ると、前回の戦いで時光に毒の刃を喰らわせた浅黒い肌の男が騎士を助け起こしていた。
「ガウリイル……それがお前の名前か? 俺の名は時光、撓気時光だ」
「トキミツ?」
お互い言葉は分からないが、何となく通じたように時光は感じていた。
そうこうしている内に、時光とガウリイルの周辺にそれぞれの仲間が集まって来る。双方損耗しているが、作戦が上手くいった分アイヌ側が優勢である。しかし、完全に圧倒するにはまだ足りない。このまま戦いを続ければ泥仕合の末の勝利となるだろう。
完全勝利のためには何か一手が必要である。
戦場に新たな集団が現れたのはその時であった。
「何だあいつらは、犬に橇 を引かせているぞ」
「聞いたことがある。ニヴフは雪に覆われている季節は犬ぞりを移動手段として使うのだとか」
いつの間にか近くに来ていたエコリアチが時光に教えた。
戦場に現れたニヴフの集団は犬ぞりに乗っており、手には弓矢や槍を構えていた。また、戦場に現れたその速度は疾風の如きものであり、この雪原では馬よりも犬ぞりの方が上のようだ。
つまり、この雪の戦場においては彼らニヴフが王者と言えるのかもしれない。その数は数千ほどであるように見て取った。
「どっちだ?」
「分からぬ……」
アイヌ側にとっても、モンゴル軍にとっても、関心事項はニヴフがどちらの味方として現れたのかだ。ニヴフが味方した方が、この戦いにおいて勝利するのは確実なのだから。
アイヌ側は時光の策で味方に付くように使者を出していた。しかし、現在ニヴフはモンゴル帝国の傘下である。そして昨日までモンゴル軍が優勢であった。モンゴル軍の援軍として駆けつけて来たと考える方が自然だろう。
その時であった。
「アイヌ達よ! 我々ニヴフの民は、古 からの縁 によりアベノヒラフの後継者であるタワケトキミツに助力しよう!」
ニヴフの男達の中から一際立派な服装をした者が進み出て、堂々たる声でアイヌの味方になる事を宣言した。どうやらウテレキ達ニヴフを説得しに行った者達の行動は成功したらしい。時光が古の日本の将軍である阿倍比羅夫の後継者であるというのは、誇張にも程があるが、どうやらそういった過去の行いなども利用して説得したようだ。
「そこにおられるのが蝦夷守 のタワケトキミツ殿ですな? 流石アベノヒラフの後継者ですな。モンゴル軍相手にここまでやるとは! 私はカラプトのニヴフの代表をしているバーリンだ。以後よろしく願おう」
「助力感謝する! って蝦夷守ってなんだ?」
「ん? 知らんのか? アベノヒラフはエゾノカミだったんだろう? それを利用してウテレキ達がトキミツもエゾノカミという事にしたんだろう。説得しやすいからな」
「いや、阿倍比羅夫は越後守 なんだが」
「……似たようなもんだろう」
蝦夷守とは実際の役職には無い。越後という地名を知らないアイヌやニヴフが勝手に似た語感の言葉に置き換えて、過去の和人の英雄について語り継いできたのだろう。
そして、時光にとっての問題はさらにある。
「それに、勝手に役職を作って、勝手に名乗るのはちょっとな……」
「朝敵、逆賊と言われても言い訳出来んな」
オピポーが何となく嬉しそうな口調で時光の悩みを具体的に述べた。かつてま つ ろ わ ぬ 民として朝廷に征服された蝦夷 の末裔であるオピポーとしては、仲間の時光が自分に近い存在になってくれるのが嬉しいのかもしれない。
「だからまずいんだよ」
「どうした? 何か違う事でもあるのか」
バーリンが怪訝な口調で尋ねてきた。
「トキミツ。アベノヒラフは昔アイヌをニヴフの侵攻から助けてくれただけでなく、倒したニヴフにも慈悲深く接して、彼らはそれを今でも尊敬して語り継いでいる。そのアベノヒラフと同じ和人の将軍であるトキミツがいるからこそ我々の味方をしてくれるのだろう」
エコリアチが真剣な口調で時光に語り掛けた。これを聞いて時光は覚悟を決めた。
「いやいや! 俺が蝦夷守の撓気十四郎時光である! ニヴフの民よ! よくぞ駆けつけてくれた! この恩は忘れないぞ!」
時光は高らかに自らを蝦夷守であると宣言した。半分やけっぱちであるが、こういうのは勢いが重要である。そして、モンゴル軍に向き直った。
「さて、モンゴル軍の戦士達よ。大勢は決したようだが、どうする? まだやるか? 無駄な血を流すか?」
既にどちらが勝利するのかは明白である。最早これ以上無用な流血を避けるべく、時光は拙いモンゴル語で交渉に乗り出した。
大勢は決しているが、モンゴル軍は精鋭揃いである。窮鼠猫を嚙むという言葉もあり、死に物狂いで抵抗されたらどれだけの被害が出るか分かったものではない。
そして、彼らに蝦夷ヶ島の豊富な資源に関する報告書は届いていない。このまま生かして帰しても問題が無いという判断だ。逆に全滅でもさせようものなら大国としての威信にかけて、大軍を送り込んで来るかもしれないのだ。
「退くとしよう……」
少し考えた金髪の女騎士は、時光の提案をのんだ。現実的な判断であり、包囲されて緊張状態にあったモンゴル軍に安堵の空気が流れているのが時光にも感じ取れた。
「トキミツ。貴様の事は忘れんぞ」
「俺も忘れないからな」
捨て台詞を吐いた女騎士は、モンゴル軍を率いて北に向かって帰って行く。その様子は敗軍とは思えないほど堂々として統率がとれており、この軍勢と最後の一兵まで戦う選択をしなくて正解だったとアイヌにもニヴフにも感じさせるものだった。
モンゴル軍の姿が見えなくなるまで、時光は瞬きすら忘れてその方向を眺めていた。
完全に混乱していると言ってよいだろう。立ち止まったモンゴル軍に正確な矢が狙い撃ちされ、次々と倒れ伏していく。鎧の隙間への射撃でかすり傷かもしれないが、アイヌの矢には毒が塗られている。即死しなくても戦闘不能にするには十分だ。
「今だ! 切り込むぞ!」
ただ一人騎乗している時光の合図の下、アイヌの戦士団の一部が混乱状態にある騎士達に向かって徒歩で突撃を敢行した。彼らの手には、槍だけでなく日本で作られた太刀が握られている。時光が交易の品として持ってきたものを配分したのである。
俗に西洋の刀剣は頑丈な鎧の上からダメージを負わせることが出来るように、切れ味ではなく頑丈さを重視して打撃を与えるように作られているという説がある。それとは反対に、日本の刀剣は気候の関係上そこまで強固な鎧が発達しなかったため、丈夫さよりも切れ味重視の刀が発達したという。
それは一部正確ではない。
西洋の刀剣とて切れ味の優れた物はいくらでもあるし、日本刀は西洋の鎧を貫くことも可能なのだ。つまり、時光達の持っている太刀は、十分西洋の鎧に効果があるのだ。まして、時光達が相対している騎士達が身に付けているのは、後世の
また、太刀の質も十分である。
例えば、時光の所持している太刀は、山城国の刀匠である綾小路定利の作である。綾小路定利の作品は現在では国宝や重要文化財として残っており、値を付けるとすれば莫大な物となるだろう。
しかし、綾小路定利はこの時光の生きる時代に生きた刀匠である。もちろんこの時代から活躍して、名の知られた刀匠ではあるが、文化財とかそのような付加価値はついておらず、優れた実用品としてそれなりの値段で流通している。特に時光の出身である
つまり、時光達が手にしている太刀は、現代では重要文化財級の名刀揃いなのである。チェインメイル位貫くことは容易なのだ。
時光達は次々と落馬して雪の中に埋もれてもがいている騎士や、突撃が防がれて棒立ちになってしまった騎士達に容赦なく止めを刺していく。突進力が失われた騎士などこの様なものである。最初から下馬して抜刀していれば、苦戦したであろうが最早対応は後手に回っている。
モンゴル軍の歩兵は騎兵達から少し離れているため、すぐには掩護に来ることが出来ない。また、弓騎兵は騎士とアイヌの戦士たちが混交しているため、矢の雨を降らせることが出来ないので接近して精密射撃を行おうとしているが、アイヌの矢の雨に遭い中々進むことが出来ない。
このまま敵の中核である騎士を倒してしまえば、勝機は見えて来る。時光は馬を進めながら次々と騎士達を切り伏せて行く。目指すは敵の指揮官である。
統制の取れた行動を妨害するには、指揮官を始末するのが一番である。例外として、無能な指揮官が死ぬことで有能な部下が指揮を代行し、敵が強力になることもあり、以前はそれで失敗したのだが、前回の戦いを見るにモンゴル軍騎士の指揮官は有能であると考えて間違いないはずだ。
「見つけたぞ! 覚悟!」
一際立派な
「甘い! はぁっ!」
気が付いた時には時光との間合いが近く、加速がつかなかったために繰り出されるランスの一撃はそれ程の速度ではなかった。それでも当たれば鎧を着ていない時光など貫通してしまうだろうが、当たらなければどうという事はない。
時光は攻撃を体をひねって回避しながら定利の太刀を片手で振るい、ランスの柄の中ほどから断ち切った。
自慢の得物を破壊されて驚愕する騎士に向かい、時光は馬をぶつけて行く。馬上での組討ちだ。
前の章で相撲は武士の嗜みだと記述したが、これは何も徒歩の場合のみではない。武士は騎乗して戦うものなのだから、当然馬上でも素手で戦えなければならない。
有名な逸話に、源平の合戦において活躍した巴御前――木曾義仲の妻にして武将――は、最後の戦いにおいて騎乗したまま組討ちをし、敵の頭をねじ切ったという。
流石に首をねじ切るというのはあまりに非現実的であり、脚色されているのだろうが、武士が馬に乗ったまま素手で戦うことは普通に起こり得るというのを表わした話である。
巴御前ほどではないが、時光の馬上組討ちの技量は中々のものである。鮮やかに騎士の馬に跳び移ると、相手の体を抱え込んで共に地面に落ちて行った。
騎士は意外と小柄で体重が軽く、容易く捻り落とすことが出来た。落ちる態勢は時光によって制御され、騎士が下になっているため二人分の体重を騎士が受けることになる。
二人分の落馬の衝撃をまともに受けた騎士は、動かなくなった。死んだわけではない。不規則に荒い息をしている。動けないだけだ。
「覚悟!」
止めを刺すべく、時光は短刀を引き抜きながら騎士の兜を取り払った。戦場の組討ちでは、組み伏せた相手の鎧兜の一部を剥ぎ取り、短刀で止めを刺すというのが定石である。
兜を剥ぎ取った時光の目に、金髪の端正な顔立ちが飛び込んできた。
「女……だと?」
「ガウリイル!」
鋭い声と殺気が迫ってくるのを感じた時光は、女騎士の上から素早く身を翻して離れると、転がりながら間合いを取って態勢を整えた。身を起こした時光が見ると、前回の戦いで時光に毒の刃を喰らわせた浅黒い肌の男が騎士を助け起こしていた。
「ガウリイル……それがお前の名前か? 俺の名は時光、撓気時光だ」
「トキミツ?」
お互い言葉は分からないが、何となく通じたように時光は感じていた。
そうこうしている内に、時光とガウリイルの周辺にそれぞれの仲間が集まって来る。双方損耗しているが、作戦が上手くいった分アイヌ側が優勢である。しかし、完全に圧倒するにはまだ足りない。このまま戦いを続ければ泥仕合の末の勝利となるだろう。
完全勝利のためには何か一手が必要である。
戦場に新たな集団が現れたのはその時であった。
「何だあいつらは、犬に
「聞いたことがある。ニヴフは雪に覆われている季節は犬ぞりを移動手段として使うのだとか」
いつの間にか近くに来ていたエコリアチが時光に教えた。
戦場に現れたニヴフの集団は犬ぞりに乗っており、手には弓矢や槍を構えていた。また、戦場に現れたその速度は疾風の如きものであり、この雪原では馬よりも犬ぞりの方が上のようだ。
つまり、この雪の戦場においては彼らニヴフが王者と言えるのかもしれない。その数は数千ほどであるように見て取った。
「どっちだ?」
「分からぬ……」
アイヌ側にとっても、モンゴル軍にとっても、関心事項はニヴフがどちらの味方として現れたのかだ。ニヴフが味方した方が、この戦いにおいて勝利するのは確実なのだから。
アイヌ側は時光の策で味方に付くように使者を出していた。しかし、現在ニヴフはモンゴル帝国の傘下である。そして昨日までモンゴル軍が優勢であった。モンゴル軍の援軍として駆けつけて来たと考える方が自然だろう。
その時であった。
「アイヌ達よ! 我々ニヴフの民は、
ニヴフの男達の中から一際立派な服装をした者が進み出て、堂々たる声でアイヌの味方になる事を宣言した。どうやらウテレキ達ニヴフを説得しに行った者達の行動は成功したらしい。時光が古の日本の将軍である阿倍比羅夫の後継者であるというのは、誇張にも程があるが、どうやらそういった過去の行いなども利用して説得したようだ。
「そこにおられるのが
「助力感謝する! って蝦夷守ってなんだ?」
「ん? 知らんのか? アベノヒラフはエゾノカミだったんだろう? それを利用してウテレキ達がトキミツもエゾノカミという事にしたんだろう。説得しやすいからな」
「いや、阿倍比羅夫は
「……似たようなもんだろう」
蝦夷守とは実際の役職には無い。越後という地名を知らないアイヌやニヴフが勝手に似た語感の言葉に置き換えて、過去の和人の英雄について語り継いできたのだろう。
そして、時光にとっての問題はさらにある。
「それに、勝手に役職を作って、勝手に名乗るのはちょっとな……」
「朝敵、逆賊と言われても言い訳出来んな」
オピポーが何となく嬉しそうな口調で時光の悩みを具体的に述べた。かつて
「だからまずいんだよ」
「どうした? 何か違う事でもあるのか」
バーリンが怪訝な口調で尋ねてきた。
「トキミツ。アベノヒラフは昔アイヌをニヴフの侵攻から助けてくれただけでなく、倒したニヴフにも慈悲深く接して、彼らはそれを今でも尊敬して語り継いでいる。そのアベノヒラフと同じ和人の将軍であるトキミツがいるからこそ我々の味方をしてくれるのだろう」
エコリアチが真剣な口調で時光に語り掛けた。これを聞いて時光は覚悟を決めた。
「いやいや! 俺が蝦夷守の撓気十四郎時光である! ニヴフの民よ! よくぞ駆けつけてくれた! この恩は忘れないぞ!」
時光は高らかに自らを蝦夷守であると宣言した。半分やけっぱちであるが、こういうのは勢いが重要である。そして、モンゴル軍に向き直った。
「さて、モンゴル軍の戦士達よ。大勢は決したようだが、どうする? まだやるか? 無駄な血を流すか?」
既にどちらが勝利するのかは明白である。最早これ以上無用な流血を避けるべく、時光は拙いモンゴル語で交渉に乗り出した。
大勢は決しているが、モンゴル軍は精鋭揃いである。窮鼠猫を嚙むという言葉もあり、死に物狂いで抵抗されたらどれだけの被害が出るか分かったものではない。
そして、彼らに蝦夷ヶ島の豊富な資源に関する報告書は届いていない。このまま生かして帰しても問題が無いという判断だ。逆に全滅でもさせようものなら大国としての威信にかけて、大軍を送り込んで来るかもしれないのだ。
「退くとしよう……」
少し考えた金髪の女騎士は、時光の提案をのんだ。現実的な判断であり、包囲されて緊張状態にあったモンゴル軍に安堵の空気が流れているのが時光にも感じ取れた。
「トキミツ。貴様の事は忘れんぞ」
「俺も忘れないからな」
捨て台詞を吐いた女騎士は、モンゴル軍を率いて北に向かって帰って行く。その様子は敗軍とは思えないほど堂々として統率がとれており、この軍勢と最後の一兵まで戦う選択をしなくて正解だったとアイヌにもニヴフにも感じさせるものだった。
モンゴル軍の姿が見えなくなるまで、時光は瞬きすら忘れてその方向を眺めていた。