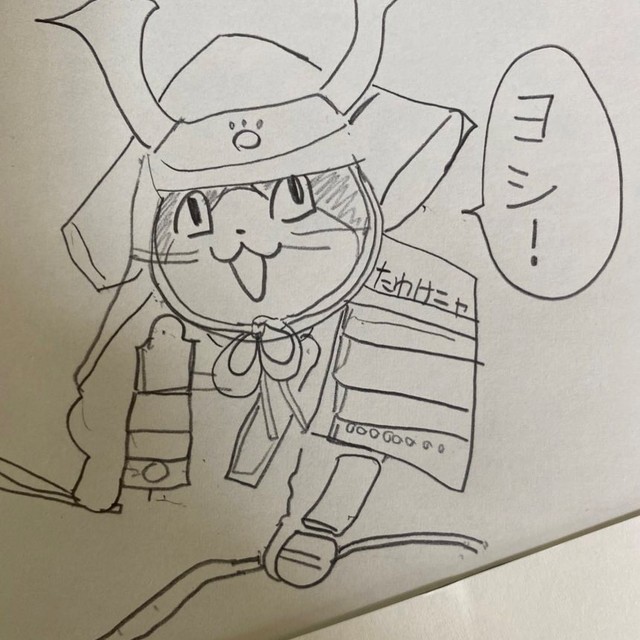第79話「アイヌ(エゾ)の匂い」
文字数 3,107文字
敵の指揮官であるトキミツを暗殺しようと近寄ったイスラフィールであったが、あと半歩で一足一刀の間合いに入れるという時に、トキミツが振り向いてしまった。
「セイッ!」
振り向くのと同時にトキミツは抜き放った太刀で鋭い斬撃を横殴りに繰り出す。短剣を装備しているイスラフィールにとっては間合いの外だが、トキミツにとっては既に間合いの内だ。
イスラフィールは素早く短剣を抜くと、烈風の様な一撃を柳の様に柔らかく受け流した。日本の武士が使う刀の切れ味は、以前の戦い等で既に承知している。正面から受け止めようとしていたなら、短剣ごと真っ二つになっていた事だろう。トキミツの所持する太刀は、後に国宝や重要文化財として伝わる太刀を作り出す、綾小路定利の作である。その様な化け物じみた切れ味の刃と真正面から打ち合わなかったイスラフィールの判断は正しいと言えよう。
「何故だ」
イスラフィールのアイヌへの変装は完璧だし、肌の色の違いなども闇の中では分からない筈だった。
「アイヌの匂いがしなかったんでな」
不意打ちが成功しなかったことによる精神的な衝撃で、イスラフィールが思わずこぼした独り言に、トキミツは端的に返答した。
以前イスラフィールがトキミツに対する不意打ちを成功させたのは、空気まで凍り付く雪原でのことである。その様な環境では臭いさえ凍り付き、広まることはない。しかし、北の大地蝦夷ヶ島とは言え、今は夏である。しかも夜の闇によって視力が制限されるという事は、嗅覚を鋭敏にする。優れた戦士は目や耳以外に鼻さえ活用するのだ。
アイヌ達は北の広大な大地で豊かな自然に囲まれて育っている。それに比べてイスラフィールは中東の砂漠や荒野で育ったのだ。その身に纏う匂いが違ったとしてもおかしくはない。
トキミツの返答でその事に思い至ったイスラフィールは、自分の迂闊さを悔やんだ。
「覚悟!」
失敗にいつまでもこだわらない事も、優れた戦士の条件である。すぐに気持ちを切り替えたイスラフィールは攻勢を開始した。魔人 の如き瞬足で間合いを詰めると、息もつかせぬ斬撃を繰り出した。短剣の間合いは太刀にとっては短すぎる。トキミツは防戦一方に追いやられてしまう。しかもイスラフィールとトキミツの距離が近すぎ、更には互いの位置が次々に入れ替わるので、アイヌの戦士達も迂闊に手出しをすることが出来ない。同士討ちを恐れるためだ。
「これならっ!」
近過ぎる間合いでの攻防に危険を感じたトキミツは、事態を改善させるために思い切った行動に出ることにした。間合いを遠ざけようとしてもイスラフィールはそれを許さず接近して来る。ならば逆に間合いを更に詰めることにしたのだ。
太刀をその場に捨てた時光は、イスラフィールに組み付いてそのまま投げ飛ばそうとする。
鎌倉武士の得意技の一つである武家相撲だ。もっと時代が下ってから発達した柔術の様に洗練されたものではないが、鍛え上げられた足腰や膂力は戦場において恐るべき威力を発揮するのだ。そしてトキミツの体格は当時の鎌倉武士の中でも立派な方であり、イスラフィールよりも筋肉量は上回っている。
だが、
「ハイヤッー!」
「ぐふっ」
絡みついた両腕は容易く外され、鋭い蹴りがトキミツの顎を跳ね上げた。後ろに吹き飛ばされたトキミツは、何とか意識を保とうと頭を振った。
時光はイスラフィールの格闘能力を見誤っていた。イスラフィールは暗殺者として育てられている。そして暗殺には毒なり、刃物なりと何らかの武器が必要なのだが、それらは暗殺対象に近づく際に見つかる危険性を高めてしまう。ならば決して取り上げられることなく、自分と不可分である我が身を武器とすれば良い。
この様な思想によって練り上げられた格闘技術は、比類無き威力を秘めるようになったのだ。何しろ、他の格闘技術は単なる力比べや祭事だったり、戦場で使用するにしても組み伏せた後は武器で止めを刺すしかないのだ。素手だけで勝負を決めようとするイスラフィールの技術は目的意識が違い過ぎるのだ。
しかし、トキミツ達にとって有利な事態にもなった。間合いが離れた事により他者が介入出来る余裕が生まれる。
「放て!」
アイヌ戦士団の指導者格であるエコリアチが、隙を見逃さずに矢を放つ合図を出す。大陸の歴史書で「射ること中らざる無し」と評されるアイヌの正確無比な射撃がイスラフィールに集中する。
通常なら即座に矢を全身に浴びて倒れ伏すこと間違いなしである。だが、イスラフィールは違った。半身になって命中する矢を減らし、それでも体に到達する矢を短剣で叩き落したのだ。古来矢を受けても戦い続ける勇士は数ある英雄譚で知られているし、アイヌが日頃相手にするヒグマも一本や二本の矢で倒れたりはしない。だが、ここまで完全に矢を回避する戦士についてトキミツ達は知らず、イスラフィールの恐るべき神技に戦慄した。
かと言ってこのまま手をこまねいている訳にもいかない。戦い続ければ死人が増え続けるだろうし、もし取り逃がせば恐るべき死神に命を狙われ続けることになる。
トキミツは覚悟を決めてイスラフィールに突進して組み付いた。組み付くまでは先ほどと同じだが、次が違う。前は投げ飛ばそうとしたのだが、今度はそのまま押し続けたのだ。頭を相手の胸板に押し付けるようにし、一心不乱に力を込める。
その様子は相撲で土俵の外に相手を押し出そうとするのとよく似ている。
古い相撲には土俵というものが無く、奈良や平安の時代に宮中で行われた相撲節会にも土俵は設けられれていない。しかし、鎌倉時代に入って民草で行われた相撲では、いつしか見物人で7~8メートルの輪を作るようになり、これを人方屋と呼んでいたのが土俵の起源と言われている。そして、この人方屋に相手を押し込むことも勝敗の手段として認められるようになったのだ。
相手を競技場の外に出せば勝ちと言うルールは、世界中の格闘技でも稀である。各民族に相撲と良く似た競技は存在しているが、相手を地面につけることが勝敗を決するのが普通だ。
つまり、トキミツは今イスラフィールに組み付いたまま押し込み続けているが、これはイスラフィールにとって初めての経験で、どう対処すればよいのか分からなかった。
そして、押し相撲にも終わりの時が来た。近くに生えていたエゾマツの大木にぶつかり、イスラフィールは抑え込まれてしまったのだ。
「いま!」
全身全霊の力で抑え続けながら、トキミツは短節に号令を発した。
次の瞬間、イスラフィールの顔に矢が十本ばかり殺到し、ほとんど同時に突き立った。トキミツが抑え込んでいるため、アイヌ戦士達から見て狙えるのは、イスラフィールの頭部しかなった。その小さな部位を過たずに狙い撃ちにする、恐るべきアイヌの神技であった。
ここまでされては流石のイスラフィールも最早生きてはいられない。力を失ってそのまま地面に崩れ落ちた。
得物が短剣ではなく、もっと長く、得意としている半月刀 だったなら、最初の不意打ちに成功しただろう。
また、雨が降り続き、匂いが弱まっていれば気付かれることは無かっただろう。
そして、トキミツ達が到着するのが、あと半日遅れていれば大陸に出航し、離散したイスラム教ニザール派の仲間を集め、中東にその名を轟かせた一大勢力を復活させることが出来ただろう。
更には単に相手を押し出すなどという、普通の格技ではあり得ぬ技に遭遇しなければ負けることも無かっただろう。
しかし、後の世に暗殺教団と一部誤解を含めて伝わる勢力を復興させようとした男は、東の果ての島でその生涯を終えたのだった。
「セイッ!」
振り向くのと同時にトキミツは抜き放った太刀で鋭い斬撃を横殴りに繰り出す。短剣を装備しているイスラフィールにとっては間合いの外だが、トキミツにとっては既に間合いの内だ。
イスラフィールは素早く短剣を抜くと、烈風の様な一撃を柳の様に柔らかく受け流した。日本の武士が使う刀の切れ味は、以前の戦い等で既に承知している。正面から受け止めようとしていたなら、短剣ごと真っ二つになっていた事だろう。トキミツの所持する太刀は、後に国宝や重要文化財として伝わる太刀を作り出す、綾小路定利の作である。その様な化け物じみた切れ味の刃と真正面から打ち合わなかったイスラフィールの判断は正しいと言えよう。
「何故だ」
イスラフィールのアイヌへの変装は完璧だし、肌の色の違いなども闇の中では分からない筈だった。
「アイヌの匂いがしなかったんでな」
不意打ちが成功しなかったことによる精神的な衝撃で、イスラフィールが思わずこぼした独り言に、トキミツは端的に返答した。
以前イスラフィールがトキミツに対する不意打ちを成功させたのは、空気まで凍り付く雪原でのことである。その様な環境では臭いさえ凍り付き、広まることはない。しかし、北の大地蝦夷ヶ島とは言え、今は夏である。しかも夜の闇によって視力が制限されるという事は、嗅覚を鋭敏にする。優れた戦士は目や耳以外に鼻さえ活用するのだ。
アイヌ達は北の広大な大地で豊かな自然に囲まれて育っている。それに比べてイスラフィールは中東の砂漠や荒野で育ったのだ。その身に纏う匂いが違ったとしてもおかしくはない。
トキミツの返答でその事に思い至ったイスラフィールは、自分の迂闊さを悔やんだ。
「覚悟!」
失敗にいつまでもこだわらない事も、優れた戦士の条件である。すぐに気持ちを切り替えたイスラフィールは攻勢を開始した。
「これならっ!」
近過ぎる間合いでの攻防に危険を感じたトキミツは、事態を改善させるために思い切った行動に出ることにした。間合いを遠ざけようとしてもイスラフィールはそれを許さず接近して来る。ならば逆に間合いを更に詰めることにしたのだ。
太刀をその場に捨てた時光は、イスラフィールに組み付いてそのまま投げ飛ばそうとする。
鎌倉武士の得意技の一つである武家相撲だ。もっと時代が下ってから発達した柔術の様に洗練されたものではないが、鍛え上げられた足腰や膂力は戦場において恐るべき威力を発揮するのだ。そしてトキミツの体格は当時の鎌倉武士の中でも立派な方であり、イスラフィールよりも筋肉量は上回っている。
だが、
「ハイヤッー!」
「ぐふっ」
絡みついた両腕は容易く外され、鋭い蹴りがトキミツの顎を跳ね上げた。後ろに吹き飛ばされたトキミツは、何とか意識を保とうと頭を振った。
時光はイスラフィールの格闘能力を見誤っていた。イスラフィールは暗殺者として育てられている。そして暗殺には毒なり、刃物なりと何らかの武器が必要なのだが、それらは暗殺対象に近づく際に見つかる危険性を高めてしまう。ならば決して取り上げられることなく、自分と不可分である我が身を武器とすれば良い。
この様な思想によって練り上げられた格闘技術は、比類無き威力を秘めるようになったのだ。何しろ、他の格闘技術は単なる力比べや祭事だったり、戦場で使用するにしても組み伏せた後は武器で止めを刺すしかないのだ。素手だけで勝負を決めようとするイスラフィールの技術は目的意識が違い過ぎるのだ。
しかし、トキミツ達にとって有利な事態にもなった。間合いが離れた事により他者が介入出来る余裕が生まれる。
「放て!」
アイヌ戦士団の指導者格であるエコリアチが、隙を見逃さずに矢を放つ合図を出す。大陸の歴史書で「射ること中らざる無し」と評されるアイヌの正確無比な射撃がイスラフィールに集中する。
通常なら即座に矢を全身に浴びて倒れ伏すこと間違いなしである。だが、イスラフィールは違った。半身になって命中する矢を減らし、それでも体に到達する矢を短剣で叩き落したのだ。古来矢を受けても戦い続ける勇士は数ある英雄譚で知られているし、アイヌが日頃相手にするヒグマも一本や二本の矢で倒れたりはしない。だが、ここまで完全に矢を回避する戦士についてトキミツ達は知らず、イスラフィールの恐るべき神技に戦慄した。
かと言ってこのまま手をこまねいている訳にもいかない。戦い続ければ死人が増え続けるだろうし、もし取り逃がせば恐るべき死神に命を狙われ続けることになる。
トキミツは覚悟を決めてイスラフィールに突進して組み付いた。組み付くまでは先ほどと同じだが、次が違う。前は投げ飛ばそうとしたのだが、今度はそのまま押し続けたのだ。頭を相手の胸板に押し付けるようにし、一心不乱に力を込める。
その様子は相撲で土俵の外に相手を押し出そうとするのとよく似ている。
古い相撲には土俵というものが無く、奈良や平安の時代に宮中で行われた相撲節会にも土俵は設けられれていない。しかし、鎌倉時代に入って民草で行われた相撲では、いつしか見物人で7~8メートルの輪を作るようになり、これを人方屋と呼んでいたのが土俵の起源と言われている。そして、この人方屋に相手を押し込むことも勝敗の手段として認められるようになったのだ。
相手を競技場の外に出せば勝ちと言うルールは、世界中の格闘技でも稀である。各民族に相撲と良く似た競技は存在しているが、相手を地面につけることが勝敗を決するのが普通だ。
つまり、トキミツは今イスラフィールに組み付いたまま押し込み続けているが、これはイスラフィールにとって初めての経験で、どう対処すればよいのか分からなかった。
そして、押し相撲にも終わりの時が来た。近くに生えていたエゾマツの大木にぶつかり、イスラフィールは抑え込まれてしまったのだ。
「いま!」
全身全霊の力で抑え続けながら、トキミツは短節に号令を発した。
次の瞬間、イスラフィールの顔に矢が十本ばかり殺到し、ほとんど同時に突き立った。トキミツが抑え込んでいるため、アイヌ戦士達から見て狙えるのは、イスラフィールの頭部しかなった。その小さな部位を過たずに狙い撃ちにする、恐るべきアイヌの神技であった。
ここまでされては流石のイスラフィールも最早生きてはいられない。力を失ってそのまま地面に崩れ落ちた。
得物が短剣ではなく、もっと長く、得意としている
また、雨が降り続き、匂いが弱まっていれば気付かれることは無かっただろう。
そして、トキミツ達が到着するのが、あと半日遅れていれば大陸に出航し、離散したイスラム教ニザール派の仲間を集め、中東にその名を轟かせた一大勢力を復活させることが出来ただろう。
更には単に相手を押し出すなどという、普通の格技ではあり得ぬ技に遭遇しなければ負けることも無かっただろう。
しかし、後の世に暗殺教団と一部誤解を含めて伝わる勢力を復興させようとした男は、東の果ての島でその生涯を終えたのだった。