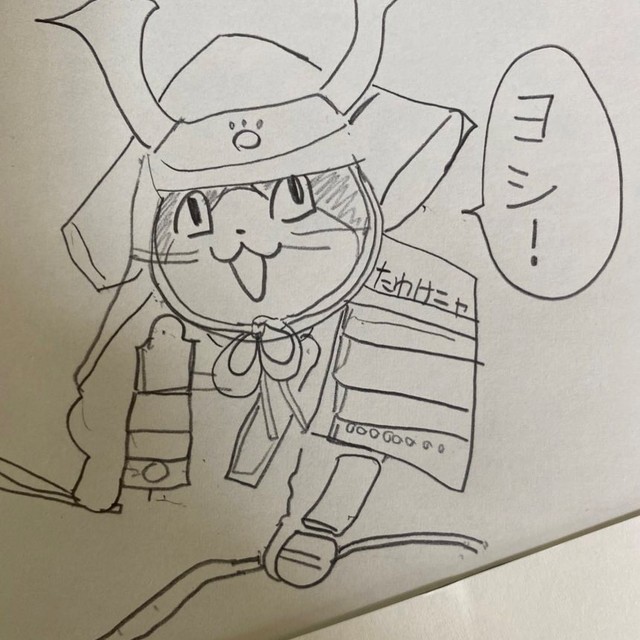第36話「氷上を渡り」
文字数 3,155文字
白主土城守備部隊のモンゴル軍副将――大将死亡の現在は長――であるアラムダルは増援部隊と合流し、十分な補給を受けて休養することで、一息ついていた。
この一週間というもの日本人の協力を得た骨嵬 に昼夜を問わず追い立てられ襲撃により仲間を失い、携行食を細く食いつなぐことで何とか生き延びていたのだ。根拠地である大陸に渡るには、カラプトとの間の海が最も狭い地点まで北上して撤退する必要があるが、それには更に二週間程度要する見積りであった。
恐らくはその間骨嵬の襲撃に耐えきることは不可能だったはずだ。一応モンゴル帝国の傘下に入っているこの島の主要な民族であるニヴフの協力を得られれば、十分挽回は可能なはずであるが、死んだ大将であるバルタンが生きている時、強引な収奪や労働で恨みを買っている。好意的な対応をされていたとは思えない。
しかも骨嵬 達はニヴフの村に先回りして補給を出来ないような措置をとっていた。増援が来なければ間違いなく壊滅していたことだろう。
問題は、この増援部隊に関してアラムダルは何も知らされていないことだ。白主土城が危機に陥ったのは最近の事だ。危険を感じてから救援要請を送り、それに対して大陸から増援を送った場合、とても間に合うとは思えない。それに、この騎兵の大軍はどうしたことだろう。ある程度の準備をしたアラムダルの部隊でさえ、海峡を渡る為の船が足りず騎兵はごく少数しか連れてこれなかったのだ。増援部隊はどの様にしてこれ程の騎兵で海を渡ったというのだろう。
「貴殿がカラプト方面部隊大将のバルタン殿かな?」
考え込んでいたアラムダルに対して声が掛けられた。声の主は増援部隊を率いていた西方――ヨーロッパの騎士である。鎖帷子 に全身を覆い、顔も金属の兜で隠しているので表情は一切わからない。チェインメイルの上に身に付けた上着 や左手に持った大きな盾には、彼らの信仰している神を象徴するという十字の紋章が描かれている。頭部が完全に金属製の兜に覆われているため声がくぐもっているが、意外と高い声をしているとアラムダルは思った。
「いや違う。私は副将のアラムダルだ。バルタンは死んだ」
「そうか」
正確には捕虜にとられて邪魔になったのでアラムダルが射殺したのだが、そこまで細かく言うつもりはない。どうせその内ばれるのだろうが、戦場に生きる者ならアラムダルのとった行動を理解してくれることだろう。問題はバルタンがモンゴルの貴族出身という事だが、この騎士はモンゴル出身ではないため、そのあたりの事情は気に留めないだろう。
「礼を言わせてもらおう。あなた方が来なければ我々は全滅していたことだろう。ええと……」
「ガウリイルと呼ばれている」
「そうか。ガウリイル殿。助けてくれてありがとう」
謎の増援部隊だが、同じくモンゴル帝国に属するものであるし命の恩人である。モンゴル帝国皇帝のクビライに反抗的な勢力は存在するが、この地域は完全にクビライの勢力圏である。味方とみて間違いはない。
「ところで、ガウリイル殿の軍は、どの様にして海を渡って来たのだ? この地域にこれ程の規模の騎兵を輸送できるだけの船は無かったはずだが……」
一応船を何度も往復させれば可能ではあるが、その場合かなりの時間を要することになる。
「おや? アラムダル殿は余りこの地域に詳しくないようだな」
「どういう事で?」
「簡単な事だ。この季節は北の海峡部分は凍結するのだ。船を使わずとも氷の上を渡れば良いのだよ」
「何と……」
これは、時光やアイヌの戦士団も知らないことであった。日本人の時光にとって海上が氷に覆われるなど想像を超えているし、アイヌもカラプトにおいては勢力圏は南部のみで北部には詳しくない。アイヌの一部はニヴフとの交流を通じて大陸に渡ったりして、海峡が凍結することを知っている者もいたのだが、首脳陣にはおらず増援の危険性に結び付けることは出来なかったのだ。
増援を受ける側である、当のモンゴル軍ですらそのことを知らなかったのだ。時光達がこれを予想できなかったとしても仕方がない事だろう。
「もう一つ聞かせて欲しいが、我々は救援の要請など出していなかったと思うが、何故ガウリイル殿達は助けに来たのだ? いや、助けてもらったことはありがたいのだが」
これが一番のアラムダルの疑問である。そもそもこの様な、ヨーロッパの騎士まで含むような部隊がこの地域にいるなど効いたことが無い。
「ところでアラムダル殿達は、蝦夷ヶ島と日本人が呼んでいる島に斥侯を派遣しましたかな? そして何か報告は来ましたかな?」
アラムダルの疑問に答えることなくガウリイルは質問をし返した。
「ん? ああ、出しましたよ。命令ではこのカラプト島の守備という事で南端まで行きましたが、そこに行ってみるとなんと蝦夷ヶ島はカラプトから直接見える程近くにありましたので、情報収集のために斥侯を出しました。骨嵬どもが反撃に来る可能性があるのでその本拠地を知らねば防衛できませんし、もし有益な資源があれば陛下に報告しなくてはなりませんしね。まあ帰っては来ませんでしたが」
「ほう? まあそうだろうな」
ガウリイルはアラムダルの返答内容を予見していたかのような口調で返事した。
「……まるでこちらの事情は全て承知しているかのように見えますが?」
「あまり余計な詮索をしない方が賢明だぞ?」
「承知した。ところで、これから先は我々がガウリイル殿の旗下に入るという事で良いのかな?」
「ああ、そうしてくれるとありがたい。奴らとの戦いの経験がある者達が加わってくれるのは心強い。先ほどの戦いでの奴らの動きを見るに、戦術を知らぬ単なる蛮族とは思えん」
ガウリイルの口調から、戦に負けて追い立てられてきたアラムダル達を侮っている様子は見受けられなかった。加えて自分たちは勝利したばかりだというのに、それに驕る様子は全く見受けられず、アラムダルはガウリイルの非凡さを心の奥底から感じた。
「イスラフィール。奴らは今どうしている?」
「森を通って南下しているな。もしかしたらこの島を脱出することを考えているのかもしれないな」
ガウリイルの問いに近くに控えていた浅黒い肌の若い男が答えた。その外見からこのイスラフィールと呼ばれた男が、西域のペルシャ辺りから来たのであろうとアラムダルは推察した。
ヨーロッパの東部に侵攻したのはジョチ・ウルス――キプチャク・カン国とも呼ばれる――であり、ペルシャの辺りを支配しているのはフレグ・ウルス――イル・カン国とも呼ばれる――であるため、今目の前にいるような者達は通常フビライの下で戦う事はない。何故この様な軍勢が存在しているのかアラムダルには理解が出来なかった。
しかし、理解は出来なくとも今は目の前の敵に集中しなくてはならない。余計な事は考えないことにした。
「森は厄介だな。負けることは無いだろうが、物陰から狙撃されては被害が大きくなるな」
「ガウリイル殿。良い方法がある。もっと南には奴らの使っている船が集まっている地域がありましてな。そこに向かって進軍すれば、奴らも森に立てこもる訳にはいかぬでしょう」
「ほう? それは良い。そのまま船を奪い取って海を渡り、蝦夷ヶ島まで攻め取るとしよう。船を新たに作る手間が省けるというものだ」
船を目掛けて進行することで、敵を森から引きずり出すというのは、この前失敗した戦いと同様ではあるが今度は戦力が違う。雪辱を果たすことが出来ることにアラムダルは喜びに打ち震えた。
その後、今後の戦いに関する打ち合わせが終わった後、ガウリイルと別れて一人になったアラムダルはふと思った。
もしかしたら、ガウリイル達は最初から蝦夷ヶ島を攻め取るつもりでここに来たのではないかと。
この一週間というもの日本人の協力を得た
恐らくはその間骨嵬の襲撃に耐えきることは不可能だったはずだ。一応モンゴル帝国の傘下に入っているこの島の主要な民族であるニヴフの協力を得られれば、十分挽回は可能なはずであるが、死んだ大将であるバルタンが生きている時、強引な収奪や労働で恨みを買っている。好意的な対応をされていたとは思えない。
しかも
問題は、この増援部隊に関してアラムダルは何も知らされていないことだ。白主土城が危機に陥ったのは最近の事だ。危険を感じてから救援要請を送り、それに対して大陸から増援を送った場合、とても間に合うとは思えない。それに、この騎兵の大軍はどうしたことだろう。ある程度の準備をしたアラムダルの部隊でさえ、海峡を渡る為の船が足りず騎兵はごく少数しか連れてこれなかったのだ。増援部隊はどの様にしてこれ程の騎兵で海を渡ったというのだろう。
「貴殿がカラプト方面部隊大将のバルタン殿かな?」
考え込んでいたアラムダルに対して声が掛けられた。声の主は増援部隊を率いていた西方――ヨーロッパの騎士である。
「いや違う。私は副将のアラムダルだ。バルタンは死んだ」
「そうか」
正確には捕虜にとられて邪魔になったのでアラムダルが射殺したのだが、そこまで細かく言うつもりはない。どうせその内ばれるのだろうが、戦場に生きる者ならアラムダルのとった行動を理解してくれることだろう。問題はバルタンがモンゴルの貴族出身という事だが、この騎士はモンゴル出身ではないため、そのあたりの事情は気に留めないだろう。
「礼を言わせてもらおう。あなた方が来なければ我々は全滅していたことだろう。ええと……」
「ガウリイルと呼ばれている」
「そうか。ガウリイル殿。助けてくれてありがとう」
謎の増援部隊だが、同じくモンゴル帝国に属するものであるし命の恩人である。モンゴル帝国皇帝のクビライに反抗的な勢力は存在するが、この地域は完全にクビライの勢力圏である。味方とみて間違いはない。
「ところで、ガウリイル殿の軍は、どの様にして海を渡って来たのだ? この地域にこれ程の規模の騎兵を輸送できるだけの船は無かったはずだが……」
一応船を何度も往復させれば可能ではあるが、その場合かなりの時間を要することになる。
「おや? アラムダル殿は余りこの地域に詳しくないようだな」
「どういう事で?」
「簡単な事だ。この季節は北の海峡部分は凍結するのだ。船を使わずとも氷の上を渡れば良いのだよ」
「何と……」
これは、時光やアイヌの戦士団も知らないことであった。日本人の時光にとって海上が氷に覆われるなど想像を超えているし、アイヌもカラプトにおいては勢力圏は南部のみで北部には詳しくない。アイヌの一部はニヴフとの交流を通じて大陸に渡ったりして、海峡が凍結することを知っている者もいたのだが、首脳陣にはおらず増援の危険性に結び付けることは出来なかったのだ。
増援を受ける側である、当のモンゴル軍ですらそのことを知らなかったのだ。時光達がこれを予想できなかったとしても仕方がない事だろう。
「もう一つ聞かせて欲しいが、我々は救援の要請など出していなかったと思うが、何故ガウリイル殿達は助けに来たのだ? いや、助けてもらったことはありがたいのだが」
これが一番のアラムダルの疑問である。そもそもこの様な、ヨーロッパの騎士まで含むような部隊がこの地域にいるなど効いたことが無い。
「ところでアラムダル殿達は、蝦夷ヶ島と日本人が呼んでいる島に斥侯を派遣しましたかな? そして何か報告は来ましたかな?」
アラムダルの疑問に答えることなくガウリイルは質問をし返した。
「ん? ああ、出しましたよ。命令ではこのカラプト島の守備という事で南端まで行きましたが、そこに行ってみるとなんと蝦夷ヶ島はカラプトから直接見える程近くにありましたので、情報収集のために斥侯を出しました。骨嵬どもが反撃に来る可能性があるのでその本拠地を知らねば防衛できませんし、もし有益な資源があれば陛下に報告しなくてはなりませんしね。まあ帰っては来ませんでしたが」
「ほう? まあそうだろうな」
ガウリイルはアラムダルの返答内容を予見していたかのような口調で返事した。
「……まるでこちらの事情は全て承知しているかのように見えますが?」
「あまり余計な詮索をしない方が賢明だぞ?」
「承知した。ところで、これから先は我々がガウリイル殿の旗下に入るという事で良いのかな?」
「ああ、そうしてくれるとありがたい。奴らとの戦いの経験がある者達が加わってくれるのは心強い。先ほどの戦いでの奴らの動きを見るに、戦術を知らぬ単なる蛮族とは思えん」
ガウリイルの口調から、戦に負けて追い立てられてきたアラムダル達を侮っている様子は見受けられなかった。加えて自分たちは勝利したばかりだというのに、それに驕る様子は全く見受けられず、アラムダルはガウリイルの非凡さを心の奥底から感じた。
「イスラフィール。奴らは今どうしている?」
「森を通って南下しているな。もしかしたらこの島を脱出することを考えているのかもしれないな」
ガウリイルの問いに近くに控えていた浅黒い肌の若い男が答えた。その外見からこのイスラフィールと呼ばれた男が、西域のペルシャ辺りから来たのであろうとアラムダルは推察した。
ヨーロッパの東部に侵攻したのはジョチ・ウルス――キプチャク・カン国とも呼ばれる――であり、ペルシャの辺りを支配しているのはフレグ・ウルス――イル・カン国とも呼ばれる――であるため、今目の前にいるような者達は通常フビライの下で戦う事はない。何故この様な軍勢が存在しているのかアラムダルには理解が出来なかった。
しかし、理解は出来なくとも今は目の前の敵に集中しなくてはならない。余計な事は考えないことにした。
「森は厄介だな。負けることは無いだろうが、物陰から狙撃されては被害が大きくなるな」
「ガウリイル殿。良い方法がある。もっと南には奴らの使っている船が集まっている地域がありましてな。そこに向かって進軍すれば、奴らも森に立てこもる訳にはいかぬでしょう」
「ほう? それは良い。そのまま船を奪い取って海を渡り、蝦夷ヶ島まで攻め取るとしよう。船を新たに作る手間が省けるというものだ」
船を目掛けて進行することで、敵を森から引きずり出すというのは、この前失敗した戦いと同様ではあるが今度は戦力が違う。雪辱を果たすことが出来ることにアラムダルは喜びに打ち震えた。
その後、今後の戦いに関する打ち合わせが終わった後、ガウリイルと別れて一人になったアラムダルはふと思った。
もしかしたら、ガウリイル達は最初から蝦夷ヶ島を攻め取るつもりでここに来たのではないかと。