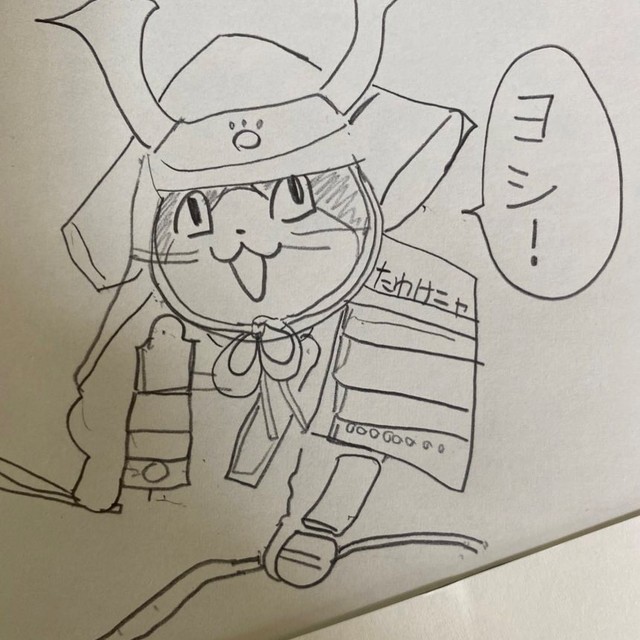第13話「蝦夷ヶ島の石炭」
文字数 3,060文字
安藤五郎は、漢人の張文祥 が報告があると言うので、その案内に従って馬に乗って進んでいた。張文祥の仲間である蒙古も二十人ほど連れており、結構な大所帯である。安藤五郎を除き、この蝦夷ヶ島で自由に活動するために皆アイヌに変装している。
ただ、この一行の中に日本人は安藤五郎ただ一人である。
安藤五郎は蝦夷代官職 に任じられている。このため、本来の役目は陸奥国 における重要な港である十三湊の管理や、蝦夷ヶ島 に住む蝦夷 との外交、そして異国からの防衛である。
その蝦夷代官職である安藤五郎が、日本への野心を隠さない蒙古の兵隊と共に行動するなどあってはならない事なのだ。故に安藤五郎自ら単独で行動している。情報を抑制したいからだ。
もし、鎌倉にでもこの様な動きが発覚すれば、たちまち周辺の御家人に命じて、かつての奥州藤原氏を滅ぼした時と同様、あっという間に滅ぼされてしまうだろう。いや、安藤氏の中では反安藤五郎派が根強くいるので、そちらに手を貸すかもしれない。
どちらにせよ安藤五郎にとっては身の破滅である。
それでも危険を冒して安藤五郎が蒙古に寝返ろうとしているのは、安藤氏内での勢力争いを蒙古の支援で得た金などで勝利すること。また、どうせ蒙古の強力な軍勢には敵わないのだから、自分の価値が出来るだけ高いうちに売り払う必要があるからだ。
ここに来ている蒙古は日本語が話せないし、安藤五郎も蒙古の言葉を使えないので、意思の疎通は張文祥と、漢人の国である宋の言葉で行っている。安藤五郎が管理する十三湊や函館には宋の船がやってくることも珍しくないので、宋の言葉なら理解できるのだ。
そして話してみると、この張文祥は蝦夷ヶ島を調査する蒙古兵の長なのだと言う。
張文祥はかつて宋に仕えていたが、蒙古と宋の戦いで捕虜になり、その知識などを買われて登用されたのだという。そして、能力を重視する蒙古のお国柄もあって、現在では蒙古を部下に従えているのだ。
実力次第でこの世で一番の勢力を誇る国で出世できる。これはもう、寝返るべきだと天が啓示しているようではないか。
驚くべきことに、蒙古は日本の最北端の防衛を担う安藤五郎のことを重要な調略目標と位置付けているらしく、陸奥国と出羽国を与えても良いと、非常に好条件が用意されていた。
張文祥によると、土地を与えるというのは蒙古においては例外的な事で、通常は地位に応じて与えられるのは、「何千戸」、「何万戸」といった風に人単位であり、土地は与えられない。
これは遊牧民族である蒙古の文化的なものであろう。それを、土地に執着する日本の武士の習慣を尊重してくれるというのだ。
中華の歴史書である史記に「士は己を知る者の為に死す」という言葉が記されている。
ならば、たとえ異国であろうと自分の事を最大限評価してくれる国のために働くのは、武士の道として決して恥じることはないという事も出来るのではないだろうか? いやそうなのだ。それが例え生まれた国を裏切るようなことになっても構わない。
安藤五郎はこんな理屈を付けて自分の行いを正当化していた。まったく「理屈と膏薬は何にでも付く」とはよく言ったものである。
この様な事情から、蒙古は安藤五郎の事を非常に尊重して行動し、機嫌を損ねないようにしている。樺太への侵攻や、その後の蝦夷ヶ島、日本への攻撃成功の成否は、安藤五郎の協力にかかっているのだから。
そういう訳で、この一団の中で唯一、安藤五郎のみが馬に乗っていても、ケチをつける者は誰もいない。本当なら騎馬民族としての誇りから、自らが馬に乗りたくても我慢している。
「おい。まだか? もうそろそろ疲れてきたぞ」
「はい。もうしばらくです」
実際に疲労の色を滲ませながら不満そうに発現する安藤五郎に、張文祥は冷静に返答した。
このやり取りを聞いていた蒙古達は内心、安藤五郎の事を嘲笑した。言葉は分からなくとも、安藤五郎の様子を見れば何を言っているのか一目瞭然である。
自分だけ馬上の人でありながら、疲れたなどとは一体何事であろうか。
実際は、馬を御するのにかなり下半身の筋肉であったり神経を使うので、疲れるのは決しておかしいことではない。ましてやここは山道で平地を進むのとは訳が違う。しかし、馬上で育ってきた蒙古にとっては、馬に乗っていながら疲れるなどとは口が裂けても、言えない事なのだ。
馬になれていない平民なら話は別であるが、安藤五郎はれっきとした武士であり、一朝事が起こらば鎧を纏い、騎乗して、弓を手に戦わなくてはならない。
しかし、安藤五郎は戦いを生業にしているのとは思えないほどの肥満体であり、馬の制御にも苦労しているのが見て取れる。これが戦士階級の中でも上級に位置しているとは、日本恐れるに足らずとの念が蒙古に自然と広まって行く。
「ここでございます。あれをご覧ください」
「何だあれは? ただの石ではないか」
つまらなそうに安藤五郎は言う。木々の少ない開けた土地に出たが、その場所に置いてあるのは、木製の箱に詰められた黒い石であった。
「張文祥。お前は金よりも面白くて重要な物を見つけたと言っていたではないか。それがあの石か? それに、竜の骨はどうなったのだ? 儂はてっきり竜の骨に関係しているものとばかり思っておったぞ」
「安藤様。竜の骨など何の役にも立ちません。いや、あれを砕いて薬にする医者やら方士やらがいるとも聞きますが、その様な事はどうでも良い事。重要なのは竜の石の近くにはあのような石が見つかる傾向にあるという事で、今回、実際に見つけることが出来ました」
「ほう? では、何の役に立つのか聞かせてもらおうか」
「はい。それでは百聞は一見に如かずと言います。おいっ」
張文祥は、蒙古の数人に命ずると、命令を受けた蒙古は黒い石を小分けにして、火打石で火を起こし始めた。
「んん? 石に火など……なんと! 火がつきおったわ! なるほど、だからわざわざ採掘現場から離れた所に連れてきたのか。確かにこんなものが沢山埋まっているところで火をつけるなど、危険極まりない」
安藤五郎の言う通り、着火剤として用いていた油の染み込ませた布を通じて、火が黒い石に燃え移り、黒い石は次第に赤く燃え始めた。
「その通りです。同じ炭であっても木炭よりも高温が得られますし、わざわざ木を伐採して来て炭焼きをせずとも燃料が手に入ります。砕いて粉上にすれば火薬にも活用できますし、これは戦略的に重要かと」
「うむ。多数の兵を駐留させるとなれば、その分燃料を多く消費するし、それを木で賄おうとすればはげ山が量産されるが、この黒い石があれば問題あるまい。特にこの蝦夷ヶ島の冬場にこの様なものがあるなら心強いだろう。それに、刀鍛冶では多くの木炭を使用するが、鍛冶場の近隣が木材が失われていくと聞く。その解決にもなろう」
「あ……前半部分は私も同意しますが、残念ながら製鉄には使えません。どういう訳かこれで鉄を作ろうとすると品質が落ちてしまうのです」
鉄の品質が落ちるのは、石に含まれる硫黄分が原因なのであるが、流石にこの時代ではそこまで詳細に解明はできない。ただ経験則で結果を知るのみである。石炭にもう一手間かけた加工をし、製鉄に活用出来る様になるのはもう少し後の時代の事だ。
「それは残念だ。木炭を超える高温で作り上げた刀などを持ってみたかったが、出来ないならば仕方ない。ところでこの石。一体何なのだ?」
「石 炭 と申します。宋ではかなり普及が進んでおりますよ」
ただ、この一行の中に日本人は安藤五郎ただ一人である。
安藤五郎は
その蝦夷代官職である安藤五郎が、日本への野心を隠さない蒙古の兵隊と共に行動するなどあってはならない事なのだ。故に安藤五郎自ら単独で行動している。情報を抑制したいからだ。
もし、鎌倉にでもこの様な動きが発覚すれば、たちまち周辺の御家人に命じて、かつての奥州藤原氏を滅ぼした時と同様、あっという間に滅ぼされてしまうだろう。いや、安藤氏の中では反安藤五郎派が根強くいるので、そちらに手を貸すかもしれない。
どちらにせよ安藤五郎にとっては身の破滅である。
それでも危険を冒して安藤五郎が蒙古に寝返ろうとしているのは、安藤氏内での勢力争いを蒙古の支援で得た金などで勝利すること。また、どうせ蒙古の強力な軍勢には敵わないのだから、自分の価値が出来るだけ高いうちに売り払う必要があるからだ。
ここに来ている蒙古は日本語が話せないし、安藤五郎も蒙古の言葉を使えないので、意思の疎通は張文祥と、漢人の国である宋の言葉で行っている。安藤五郎が管理する十三湊や函館には宋の船がやってくることも珍しくないので、宋の言葉なら理解できるのだ。
そして話してみると、この張文祥は蝦夷ヶ島を調査する蒙古兵の長なのだと言う。
張文祥はかつて宋に仕えていたが、蒙古と宋の戦いで捕虜になり、その知識などを買われて登用されたのだという。そして、能力を重視する蒙古のお国柄もあって、現在では蒙古を部下に従えているのだ。
実力次第でこの世で一番の勢力を誇る国で出世できる。これはもう、寝返るべきだと天が啓示しているようではないか。
驚くべきことに、蒙古は日本の最北端の防衛を担う安藤五郎のことを重要な調略目標と位置付けているらしく、陸奥国と出羽国を与えても良いと、非常に好条件が用意されていた。
張文祥によると、土地を与えるというのは蒙古においては例外的な事で、通常は地位に応じて与えられるのは、「何千戸」、「何万戸」といった風に人単位であり、土地は与えられない。
これは遊牧民族である蒙古の文化的なものであろう。それを、土地に執着する日本の武士の習慣を尊重してくれるというのだ。
中華の歴史書である史記に「士は己を知る者の為に死す」という言葉が記されている。
ならば、たとえ異国であろうと自分の事を最大限評価してくれる国のために働くのは、武士の道として決して恥じることはないという事も出来るのではないだろうか? いやそうなのだ。それが例え生まれた国を裏切るようなことになっても構わない。
安藤五郎はこんな理屈を付けて自分の行いを正当化していた。まったく「理屈と膏薬は何にでも付く」とはよく言ったものである。
この様な事情から、蒙古は安藤五郎の事を非常に尊重して行動し、機嫌を損ねないようにしている。樺太への侵攻や、その後の蝦夷ヶ島、日本への攻撃成功の成否は、安藤五郎の協力にかかっているのだから。
そういう訳で、この一団の中で唯一、安藤五郎のみが馬に乗っていても、ケチをつける者は誰もいない。本当なら騎馬民族としての誇りから、自らが馬に乗りたくても我慢している。
「おい。まだか? もうそろそろ疲れてきたぞ」
「はい。もうしばらくです」
実際に疲労の色を滲ませながら不満そうに発現する安藤五郎に、張文祥は冷静に返答した。
このやり取りを聞いていた蒙古達は内心、安藤五郎の事を嘲笑した。言葉は分からなくとも、安藤五郎の様子を見れば何を言っているのか一目瞭然である。
自分だけ馬上の人でありながら、疲れたなどとは一体何事であろうか。
実際は、馬を御するのにかなり下半身の筋肉であったり神経を使うので、疲れるのは決しておかしいことではない。ましてやここは山道で平地を進むのとは訳が違う。しかし、馬上で育ってきた蒙古にとっては、馬に乗っていながら疲れるなどとは口が裂けても、言えない事なのだ。
馬になれていない平民なら話は別であるが、安藤五郎はれっきとした武士であり、一朝事が起こらば鎧を纏い、騎乗して、弓を手に戦わなくてはならない。
しかし、安藤五郎は戦いを生業にしているのとは思えないほどの肥満体であり、馬の制御にも苦労しているのが見て取れる。これが戦士階級の中でも上級に位置しているとは、日本恐れるに足らずとの念が蒙古に自然と広まって行く。
「ここでございます。あれをご覧ください」
「何だあれは? ただの石ではないか」
つまらなそうに安藤五郎は言う。木々の少ない開けた土地に出たが、その場所に置いてあるのは、木製の箱に詰められた黒い石であった。
「張文祥。お前は金よりも面白くて重要な物を見つけたと言っていたではないか。それがあの石か? それに、竜の骨はどうなったのだ? 儂はてっきり竜の骨に関係しているものとばかり思っておったぞ」
「安藤様。竜の骨など何の役にも立ちません。いや、あれを砕いて薬にする医者やら方士やらがいるとも聞きますが、その様な事はどうでも良い事。重要なのは竜の石の近くにはあのような石が見つかる傾向にあるという事で、今回、実際に見つけることが出来ました」
「ほう? では、何の役に立つのか聞かせてもらおうか」
「はい。それでは百聞は一見に如かずと言います。おいっ」
張文祥は、蒙古の数人に命ずると、命令を受けた蒙古は黒い石を小分けにして、火打石で火を起こし始めた。
「んん? 石に火など……なんと! 火がつきおったわ! なるほど、だからわざわざ採掘現場から離れた所に連れてきたのか。確かにこんなものが沢山埋まっているところで火をつけるなど、危険極まりない」
安藤五郎の言う通り、着火剤として用いていた油の染み込ませた布を通じて、火が黒い石に燃え移り、黒い石は次第に赤く燃え始めた。
「その通りです。同じ炭であっても木炭よりも高温が得られますし、わざわざ木を伐採して来て炭焼きをせずとも燃料が手に入ります。砕いて粉上にすれば火薬にも活用できますし、これは戦略的に重要かと」
「うむ。多数の兵を駐留させるとなれば、その分燃料を多く消費するし、それを木で賄おうとすればはげ山が量産されるが、この黒い石があれば問題あるまい。特にこの蝦夷ヶ島の冬場にこの様なものがあるなら心強いだろう。それに、刀鍛冶では多くの木炭を使用するが、鍛冶場の近隣が木材が失われていくと聞く。その解決にもなろう」
「あ……前半部分は私も同意しますが、残念ながら製鉄には使えません。どういう訳かこれで鉄を作ろうとすると品質が落ちてしまうのです」
鉄の品質が落ちるのは、石に含まれる硫黄分が原因なのであるが、流石にこの時代ではそこまで詳細に解明はできない。ただ経験則で結果を知るのみである。石炭にもう一手間かけた加工をし、製鉄に活用出来る様になるのはもう少し後の時代の事だ。
「それは残念だ。木炭を超える高温で作り上げた刀などを持ってみたかったが、出来ないならば仕方ない。ところでこの石。一体何なのだ?」
「