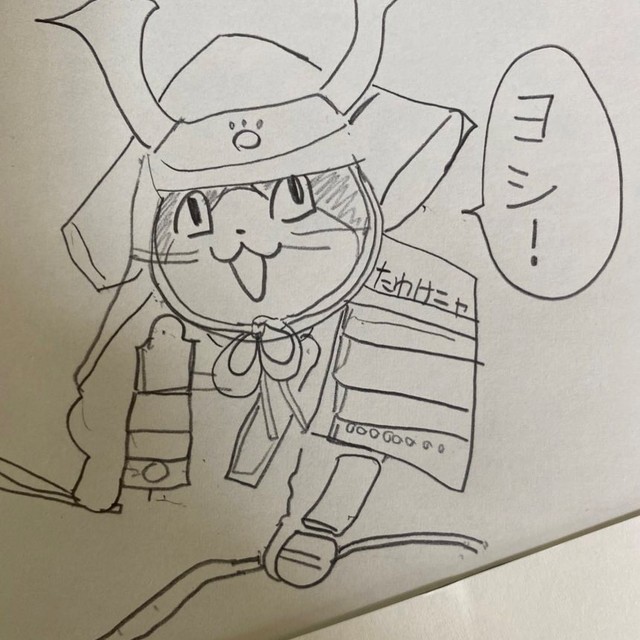第30話「蒙古軍出撃」
文字数 3,145文字
モンゴル帝国カラプト方面部隊の副将であるアラムダルはその日、拠点の大半の兵を引き連れて進軍していた。
連日続いていた雪は鳴りを潜め、空は雲一つなく晴れわたり、空気は冷たく澄んでいる。進軍する経路は海と森に挟まれてはいるものの、視界の良い平原であり、アラムダルは故郷のモンゴル高原を思い出していた。海の方から漂う潮の臭い以外は、空も大地も似た雰囲気がある。
進軍の目的は、このカラプト島に侵入した骨嵬 ――自分たちではアイヌと称しているらしい――との軍事的な均衡を崩すため、骨嵬の本境地である蝦夷ヶ島との連絡に使用する船を奪取に行くことである。
これは、カラプト方面部隊の兵站戦略が失敗したことに端を発している。本来モンゴル軍にとって兵站はもっとも得意な分野であった。
主力の騎兵は数頭の馬ともに進軍し、迅速な機動と時には馬を食料にすることで飢えることは無かった。これは、遊牧騎馬民族が軍を編成すれば自動的にそうなるものであり、古来から続く特段珍しいものではない。
しかし、今のモンゴル帝国の軍隊はそれだけではない。戦の天才であるチンギス・ハーンはモンゴル高原を統一した後、大規模な侵略を開始したが、その際兵站の重要性に気が付いたのだ。
世界各地につくられた軍団駐屯地 は、何処においても整然とゲルが展開され、武器庫や食糧庫がどこにあるのか初めて訪れたものにも分かるようになっていた。また、オルドの運営には補給の任務を専門とする者が当てられて、組織的に管理されていた。
単に遊牧民特有の拠点ごと移動するという習慣だけでは、大軍団を維持できないのだ。
そして、今回のカラプトにおける拠点構築は、これまでのものとは違っていた。海を隔てた場所に進出したため、物資の輸送には船が必要となり、予定よりも物資の輸送が遅れた。当初は築城のための資材が優先され、食料は当座をしのぐくらいしか持ってこなかったが、それがいけなかった。
ある程度築城が概成した後、蝦夷ヶ島から骨嵬が大挙して押し寄せ、城の近くに蟠踞したのだ。
平野部で戦えば、例え勢力が少なくとも、集団戦の訓練を積んだモンゴル軍は骨嵬に負けたりはしない。森に入った場合、骨嵬の得意な地形だし、数では相手の方が多いので油断は禁物である。
そして、骨嵬に味方する妙な戦士が現れた事で状況が変わった。
そいつは、骨嵬との小競り合いの途中に突然海から馬に乗って現れた。罠に嵌った骨嵬の戦士たちを殲滅できるという時に横槍を入れてきて、恐るべき弓の腕前を発揮し、モンゴル軍の騎兵を瞬く間に射殺した。大陸にその名を轟かせた弓騎兵を擁するモンゴル兵の目からしても、その戦いぶりは目を見張るほど素晴らしいものであった。
更に、数日後にそいつはまた現れた。
何と食料調達に出ていたモンゴル兵の首を持参してである。そして、城の食糧事情の乏しさを見透かすような挑発をすると、風の様に去って行った。
城兵の指揮はがた落ちである。下級の兵士は、食糧事情について詳しいことは知らず、故郷から遠く離れた島に孤立していることに対しての不安が増大したのである。これでは籠城などとてもできたものではない。
この危機的状況の打開策が骨嵬の船への攻撃なのである。
元々アラムダルはこの積極策を指揮官に献策していた。しかし、有力な族長の家柄だけで指揮官になったその男は、失敗を恐れて結論を先延ばしにしていたのだ。腹立たしかったが、階級は絶対だ。アラムダルは従うしかなかったのである。
しかし、兵士の大半に食料不足が知れ渡ってしまったことにより、城内に不安と不満が蓄積しているのは、いくら無能で臆病な指揮官でも、いや、臆病だからこそ敏感に感じ取り、アラムダルによる出撃を許したのである。
アラムダルには今回の出撃に、絶対の自信があった。
モンゴル軍が平原で戦えば、よほどのことが無い限り絶対に負けないのである。これは、これまで厳しい訓練を重ねてきたことによる自信である。
モンゴル軍の強さの秘密として、よく言われているのは、遊牧騎馬民族特有の強さについてである。
生まれた時から馬上で育ち、狩猟によって糧を得ているため、馬と弓というこの時代における最強の武器に習熟していることがその理由だ。確かにこれは強さの大きな理由と言っても良い。
しかし、モンゴル軍の強さはこれだけではない。何故なら、モンゴル帝国以前の歴史に名を遺す騎馬民族である、匈奴やフン族も今あげたのと同様の理由で無類の強さを誇ったが、モンゴル帝国ほど広く、そして継続して勢力を保つことは無かった。
他の理由として挙げられるのは、先ほど記した、チンギス・ハーンによる兵站組織の確立である。戦争の強さとは、個々の武勇や華麗な戦術に目が行きがちだが、兵站をおろそかにしていては何も出来ない。この地味な部分に目を向け、心血を注ぐものこそ勝利するのだ。何の軍事的教育を受けていないはずの、一介の遊牧民族、その中でも弱小部族の族長の息子に過ぎなかった男が、大陸を東西に結ぶだけの兵站組織を作り上げたのは、まさに天命としか言えないだろう。
そして、その英雄は兵站だけでなく、軍事組織にも着目していた。
遊牧騎馬民族は集団による狩猟を日常的に行い、それで戦士としての腕前を磨いているが、それだけでは小集団としての力しか発揮できない。つまり、何百、何千、何万人集まろうと、それは数万の軍勢というよりも何十人の集団が多数いるだけなのだ。これでは大軍としての真価を発揮できない。
チンギス・ハーンが定めた軍事教練のやり方に、次の様なものがある。
少数の集団ごとに、斥侯、囮、防御、包囲などの役割を与え狩猟をし、連携行動を訓練する方法、これはモンゴル軍の基本戦術である。
また、大軍を一列に並べ――時には百キロ以上に達した――完全武装した一団は、合図により数百キロ先の目標地点に向けて、狩りの獲物を追い立てながら、足並みを揃えて進むのである。そして、目標地点に近づくと、両翼が獲物を包囲するように機動し、最終的に追い込んできた獲物の群れを包囲するのである。
百キロも離れた両翼がどのようにして連携して包囲するのか、疑問に思うかもしれないが、モンゴル軍は旗、伝令、狼煙などによって極めて早く、そして遠くまで届く通信を確立していたのである。ある意味、モンゴル軍の大陸遠征において一番威力を発揮したのはこの通信だったのかもしれない。
ここまで縷々述べてきたが、モンゴル軍は決して騎馬民族としての戦闘能力だけに頼った軍隊ではなく、チンギス・ハーンが高度に組織化したことによって空前絶後の大帝国を築き上げてきたのである。
はっきり言って、欧州諸国の騎士達は、王の下で戦うと言ってもその実態は、諸侯が自分勝手な思惑で動くという組織化には程遠い存在であるし、比較的中央集権化が皇帝の下に組織化している中国の王朝ですら定期的に軍閥下するため、全軍一体となった戦いなど出来るものではない。
当然日本の武士も組織化した軍事組織には程遠い存在である。この時代の西国では蒙古襲来に備えてある程度まとまって戦う訓練をしているが、チンギス・ハーンによる軍事教練とは比べるべくもない。
もっとも、それを補って余りあるだけの、蛮性とか闘争本能と呼ばれるようなものが備わっているのだが。
兎に角、蒙古軍はこの時代のあらゆる軍事組織に勝るだけの態勢を作り上げており、正面切って戦えば負けるはずはないのであった。
アラムダルはその様な考えで意気揚々と出撃していった。その功績で出世を望んでいるのであろう。
これから待ち受ける、今まで経験したことのない戦場が待っていることを知る由も無かったのだ。
連日続いていた雪は鳴りを潜め、空は雲一つなく晴れわたり、空気は冷たく澄んでいる。進軍する経路は海と森に挟まれてはいるものの、視界の良い平原であり、アラムダルは故郷のモンゴル高原を思い出していた。海の方から漂う潮の臭い以外は、空も大地も似た雰囲気がある。
進軍の目的は、このカラプト島に侵入した
これは、カラプト方面部隊の兵站戦略が失敗したことに端を発している。本来モンゴル軍にとって兵站はもっとも得意な分野であった。
主力の騎兵は数頭の馬ともに進軍し、迅速な機動と時には馬を食料にすることで飢えることは無かった。これは、遊牧騎馬民族が軍を編成すれば自動的にそうなるものであり、古来から続く特段珍しいものではない。
しかし、今のモンゴル帝国の軍隊はそれだけではない。戦の天才であるチンギス・ハーンはモンゴル高原を統一した後、大規模な侵略を開始したが、その際兵站の重要性に気が付いたのだ。
世界各地につくられた
単に遊牧民特有の拠点ごと移動するという習慣だけでは、大軍団を維持できないのだ。
そして、今回のカラプトにおける拠点構築は、これまでのものとは違っていた。海を隔てた場所に進出したため、物資の輸送には船が必要となり、予定よりも物資の輸送が遅れた。当初は築城のための資材が優先され、食料は当座をしのぐくらいしか持ってこなかったが、それがいけなかった。
ある程度築城が概成した後、蝦夷ヶ島から骨嵬が大挙して押し寄せ、城の近くに蟠踞したのだ。
平野部で戦えば、例え勢力が少なくとも、集団戦の訓練を積んだモンゴル軍は骨嵬に負けたりはしない。森に入った場合、骨嵬の得意な地形だし、数では相手の方が多いので油断は禁物である。
そして、骨嵬に味方する妙な戦士が現れた事で状況が変わった。
そいつは、骨嵬との小競り合いの途中に突然海から馬に乗って現れた。罠に嵌った骨嵬の戦士たちを殲滅できるという時に横槍を入れてきて、恐るべき弓の腕前を発揮し、モンゴル軍の騎兵を瞬く間に射殺した。大陸にその名を轟かせた弓騎兵を擁するモンゴル兵の目からしても、その戦いぶりは目を見張るほど素晴らしいものであった。
更に、数日後にそいつはまた現れた。
何と食料調達に出ていたモンゴル兵の首を持参してである。そして、城の食糧事情の乏しさを見透かすような挑発をすると、風の様に去って行った。
城兵の指揮はがた落ちである。下級の兵士は、食糧事情について詳しいことは知らず、故郷から遠く離れた島に孤立していることに対しての不安が増大したのである。これでは籠城などとてもできたものではない。
この危機的状況の打開策が骨嵬の船への攻撃なのである。
元々アラムダルはこの積極策を指揮官に献策していた。しかし、有力な族長の家柄だけで指揮官になったその男は、失敗を恐れて結論を先延ばしにしていたのだ。腹立たしかったが、階級は絶対だ。アラムダルは従うしかなかったのである。
しかし、兵士の大半に食料不足が知れ渡ってしまったことにより、城内に不安と不満が蓄積しているのは、いくら無能で臆病な指揮官でも、いや、臆病だからこそ敏感に感じ取り、アラムダルによる出撃を許したのである。
アラムダルには今回の出撃に、絶対の自信があった。
モンゴル軍が平原で戦えば、よほどのことが無い限り絶対に負けないのである。これは、これまで厳しい訓練を重ねてきたことによる自信である。
モンゴル軍の強さの秘密として、よく言われているのは、遊牧騎馬民族特有の強さについてである。
生まれた時から馬上で育ち、狩猟によって糧を得ているため、馬と弓というこの時代における最強の武器に習熟していることがその理由だ。確かにこれは強さの大きな理由と言っても良い。
しかし、モンゴル軍の強さはこれだけではない。何故なら、モンゴル帝国以前の歴史に名を遺す騎馬民族である、匈奴やフン族も今あげたのと同様の理由で無類の強さを誇ったが、モンゴル帝国ほど広く、そして継続して勢力を保つことは無かった。
他の理由として挙げられるのは、先ほど記した、チンギス・ハーンによる兵站組織の確立である。戦争の強さとは、個々の武勇や華麗な戦術に目が行きがちだが、兵站をおろそかにしていては何も出来ない。この地味な部分に目を向け、心血を注ぐものこそ勝利するのだ。何の軍事的教育を受けていないはずの、一介の遊牧民族、その中でも弱小部族の族長の息子に過ぎなかった男が、大陸を東西に結ぶだけの兵站組織を作り上げたのは、まさに天命としか言えないだろう。
そして、その英雄は兵站だけでなく、軍事組織にも着目していた。
遊牧騎馬民族は集団による狩猟を日常的に行い、それで戦士としての腕前を磨いているが、それだけでは小集団としての力しか発揮できない。つまり、何百、何千、何万人集まろうと、それは数万の軍勢というよりも何十人の集団が多数いるだけなのだ。これでは大軍としての真価を発揮できない。
チンギス・ハーンが定めた軍事教練のやり方に、次の様なものがある。
少数の集団ごとに、斥侯、囮、防御、包囲などの役割を与え狩猟をし、連携行動を訓練する方法、これはモンゴル軍の基本戦術である。
また、大軍を一列に並べ――時には百キロ以上に達した――完全武装した一団は、合図により数百キロ先の目標地点に向けて、狩りの獲物を追い立てながら、足並みを揃えて進むのである。そして、目標地点に近づくと、両翼が獲物を包囲するように機動し、最終的に追い込んできた獲物の群れを包囲するのである。
百キロも離れた両翼がどのようにして連携して包囲するのか、疑問に思うかもしれないが、モンゴル軍は旗、伝令、狼煙などによって極めて早く、そして遠くまで届く通信を確立していたのである。ある意味、モンゴル軍の大陸遠征において一番威力を発揮したのはこの通信だったのかもしれない。
ここまで縷々述べてきたが、モンゴル軍は決して騎馬民族としての戦闘能力だけに頼った軍隊ではなく、チンギス・ハーンが高度に組織化したことによって空前絶後の大帝国を築き上げてきたのである。
はっきり言って、欧州諸国の騎士達は、王の下で戦うと言ってもその実態は、諸侯が自分勝手な思惑で動くという組織化には程遠い存在であるし、比較的中央集権化が皇帝の下に組織化している中国の王朝ですら定期的に軍閥下するため、全軍一体となった戦いなど出来るものではない。
当然日本の武士も組織化した軍事組織には程遠い存在である。この時代の西国では蒙古襲来に備えてある程度まとまって戦う訓練をしているが、チンギス・ハーンによる軍事教練とは比べるべくもない。
もっとも、それを補って余りあるだけの、蛮性とか闘争本能と呼ばれるようなものが備わっているのだが。
兎に角、蒙古軍はこの時代のあらゆる軍事組織に勝るだけの態勢を作り上げており、正面切って戦えば負けるはずはないのであった。
アラムダルはその様な考えで意気揚々と出撃していった。その功績で出世を望んでいるのであろう。
これから待ち受ける、今まで経験したことのない戦場が待っていることを知る由も無かったのだ。