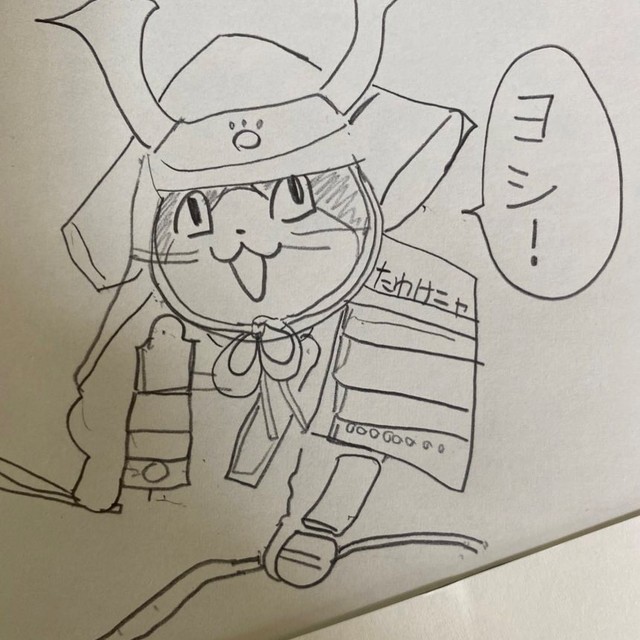第87話「神(カムイ)の怒り」
文字数 6,187文字
フラヌ平原における決戦は、最終段階に入っていると時光は判断していた。
時光は味方の内ただ一人馬上にあり、周囲には少数の仲間だけが待機していた。
当初から味方の被害を積み重ねながらも順調に戦線を前進させていたし、途中から目に見えて速度が速くなった。敵の様子を見る限り士気を失って統制が取れなくなった様子は無いので、幹部であり各種作戦の立案者と目されるウリエルと呼ばれている漢人の将軍に対する襲撃に成功したのだろう。
もう既に敵には下がるところは無く、フラヌの盆地の南端に押し込まれている。敵の一番の強みは騎兵による機動力の発揮である。機動力を発揮するための地積が無ければその真価を発揮することが出来ない。
「どうなされる? このまま一挙に殲滅されますか?」
時光の家来である丑松が尋ねて来る。形勢は時光達に優勢だがその表情は険しいものがある。
「もうそろそろ交渉に移れないだろうか? このまま力攻めしたら互いに被害が増えるだけだ」
「窮鼠猫を嚙むも申しますからな」
これだけ形勢が不利になっても士気が衰えないというのは恐るべきことである。通常なら不利になった時点で戦意を失い、まともに戦闘することが出来ないのだ。そして、その様な敵は多少数が多かったとしても戦力にはならないものなのだ。
しかし、プレスター・ジョン率いる敵は、プレスター・ジョンの魅力か、宗教心か、モンゴル帝国内で低い地位にある者の上昇意欲かは分からないが、未だに勢いが衰える様子を見せない。
この様な敵に対して殲滅戦を仕掛けると、最後の一兵まで死に物狂いで立ち向かって来ることだろう。もしそうなったら時光と共に戦うアイヌやニヴフの戦士達も半数は命を失うだろう。
時光は戦の采配を任されてはいるものの、北方の民にとっては部外者である。彼らにそこまでの犠牲を強いて良いのか判断できなかった。
「それは構わんが、俺達はどれだけの犠牲を払ってでも最後まで戦い抜く覚悟は出来ているぞ」
傍にいたサケノンクルが特に気を張った様子も無く答えた。サケノンクルはアイヌの代表格である。彼の考えはアイヌの戦士達の一般的なもの、そして総意ととっても問題ないだろう。
「そうか……では、軍使を派遣……」
「大変だ! 西の方から新手が現れたぞ! 鉄と馬の奴らだ!」
慌てた様子の報告の声に遮られ、時光は最後まで言い終える事が出来なかった。「鉄と馬の奴ら」とは、ガウリイルが率いる騎士団であろう。ミハイルが率いる騎士団が蝦夷ヶ島に上陸したという報告はまだ受けていない。
ガウリイルはカムイコタンからイシカリに向かったはずであり、この戦場には来ない筈であった。プレスター・ジョンの率いる本隊とイシカリで合流する予定だったはずだし、方針が変わってこちらに向かおうとしてもその経路は大規模な倒木で塞がれているはずなのだ。とてもこの短期間で除去できたとは信じられない。
予想外の事態に混乱する時光の耳に、聞いたことのある声が響いて来た。
「覚悟ー!」
時光が声のする方向を見ると、数機の騎士達が穂先を前にして突撃してくるのが見えた。その戦闘を駆けて来る騎士は、兜で顔こそ見えないものの誰なのか時光には理解できた。
プレスター・ジョンの軍勢の幹部として騎士団の一部を率いる女騎士のガウリイルである。やはり彼女が妨害を突破してこの戦場に駆けつけてきたのだ。
ガウリイルの攻撃は完全な奇襲となり、馬上の時光はそれに対応することが出来ない。意識だけ相手の方に向けたとしても、物理的な動き、馬を操り回避行動をするだけの余裕は無いのだ。
このままではガウリイルの構えた長大な馬上槍 の餌食になる事だろう。騎馬の速度と体重が穂先に集中するランスの一撃を食らっては、大鎧を装着した時光もひとたまりも無く冥府に旅立つことだろう。
「させるかー! ぐぁ!」
死を覚悟した時光を救ったのは、傍にいたサケノンクルであった。傍にいたアイヌの戦士から木製の手盾を奪い取り、ガウリイルと時光の間に割って入り、ランスを防ごうとした。
その結果時光の命は救われたが、代償も大きかった。ちゃちな盾では勢いのついたランスを受け止めきれず、盾は粉砕されて左手も貫かれ、馬の体当たりをその身に受けてサケノンクルは吹き飛ばされた。馬蹄にかけられなかったのは幸運だっただろう。なんとか息はあるようだ。
「くっ……」
もう一人すぐ近くに控えていた丑松が佩いていた太刀を引き抜き、ランスの柄を切り払った。丑松の所有する太刀も時光の物と同じく名工綾小路定利の作である。その切れ味と、時光を上回る丑松の剣技の冴えにより、硬い木で作成されたランスの柄が綺麗な断面を見せて切断された。
「馬鹿な……イシカリからここに来る道は塞いだはずだ」
「木など燃やせばよいだけの事」
「水気を含んだ生木がそう簡単に燃えるわけがない!」
「忘れたのか? 道の途中にはイクスンペツという石炭の採掘場があっただろう? 石炭を大量に敷き詰めればいかに大量の倒木とはいえ燃えないわけがない」
ガウリイルの答えに時光は納得するとともに、その事に気が付かなかった自分の迂闊さを責めた。気付いていれば、増援が来ることを見越した作戦を立てられたのに、実際はこのざまだ。
また、ガウリイルは言わなかったが、時光がイシカリを奪回した時、気が付かずに取り逃がしたマルコ=ポーロの知らせで時光達の動きや、道を封鎖したことは全てガウリイルの耳に入っていたのだ。
ここで異変に気が付いたアイヌの戦士達が駆け付けて来て矢を放ち、騎士達を追い払った。
一陣の風の如く騎士達が駆け抜けた後、戦況の把握に気を向けた時光は前線の様子が混乱している事に気が付いた。どうやら到着した騎士団の本隊が側面から攻撃したことで、味方が混乱しているようだ。騎士団の兵数は大したことは無いものの、意識外からの攻撃を食らえば冷静ではいられないものだ。
幸い味方は分散しているので騎兵槍突撃 を受けても被害はあまりないようだ。
だが、この状態で戦い続けることは危険すぎる。そう判断した時光はすぐに撤退の指示を出した。
幸い敵も戦いに継ぐ戦いで追撃してくる余裕は無かったようだ。トキミツ達はピイエ丘陵まで無事に退却することが出来た。
ピイエ丘陵に時光達が後退してから一夜明けた。夜の内に態勢を立て直し、戦支度を整えることが出来た時光達だったが、ピイエ丘陵から見下ろす眼前には敵の立ち並ぶ姿があった。折角昨日の戦いで押し込んだのにそれを挽回された形だ。
「敵の士気は全然落ちていないな。増援が来たからっていうのもあるかもしれんが、昨日あれだけやられたのに、良く戦意を保ってられるものだ」
敵の士気は落ちていないが、幸い味方の士気も落ちていない。アイヌの代表格であるサケノンクルが重傷となって下げられているが、その代わりを務めるエコリアチの下で未だ闘志は衰えていない。
「宗教的情熱かもしれませんな。彼らはキリスト者として大陸の東方で生きてきましたが、それは決して安寧なものではなかったのでしょう。それがこの苦境でも戦い抜く意思を保てる理由なのでしょう。ここを耐え抜けばきっと神の国がやってくると信じて。それに例え死んだとしても神の救いがあると信じれば、死への恐怖などありますまい」
時光の問いに答えたのは、羅馬 からやって来たドミニコ会の修道士であるグリエルモであった。彼はキリスト教徒でありながら同じキリスト教徒であるプレスター・ジョンの軍勢と戦う時光と、最後まで共に戦う決意をしてくれた。
カトリックの彼にとって、プレスター・ジョン達の信じるネストリウス派は異端であるという事情もあるのだが。
「なるほどね。そういうものか。しかし恐ろしいものだな、宗教とは。わが国でも権力争いをする坊主どもや、狂信者どもは恐ろしいがそれは何処も変わらないか」
「いいえ。神の教えの本質とはその様な所にはありません。神の教えの本質とは愛 です」
「あ が ぺ ー ?」
「そうです。異端者や異教徒と戦う事も大切かもしれませんが、最も重要なのは限りない隣人愛なのです。互いに愛し合い、思いやる事こそ宗教の本義であり、その他は枝葉末節といっても良いでしょう。日本の神やら仏とやらの教えもそんなところなのでは? それに、アイヌ達がいう所のカムイも人々が傷つけ合うことなど望んではいないでしょう」
「確かにそうかもしれんな」
人間は時として宗教を原因として争う事があるが、それは本来の神仏の教えからは外れる事だろう。結局のところ争い、命を奪い合うのは人間の欲や社会的要因に他ならない。それを神の意思のせいにするのは、つまるところ人間の思惑なのだ。
流石に大陸を横断してこの様な東の果ての島までくる情熱を持った坊主である。グリエルモの発言に時光はいたく感心した。
グリエルモの片手に刺付き棍棒 がぶら下げられていなければ、もっと良かっただろう。結局のところ人間は自らの都合を優先させる生き物なのだ。プレスター・ジョン達が自分達の勢力を拡大し、モンゴル帝国を乗っ取り、キリスト教徒を主体にした国家を築くことで安寧を得たいのと同様に、アイヌやニヴフはそれぞれの穏やかな生活を守りたいのだ。これはどちらが正義とかの問題ではない。
時光はふと思った。自分の事情とは何なのだろうかと。
元々親から相続する土地が無いため、恩賞を貰うためにこの蝦夷ヶ島までやって来た。果たして今もそうなのだろうか。
グリエルモとの問答でしばし深い思索に入った頃、それを遮るように敵陣で鬨の声が上がった。敵は丘陵を駆け上がって攻め込むつもりのようだ。
早朝から始まった戦いは熾烈を極める事になった。
これまで幾度となく双方の陣営は戦戈を交えている。そのためお互いのやり口は知り抜いているのだ。
モンゴル騎兵が弓を構えて一斉射撃すると、分散して被害を最小限にしたアイヌの戦士達が狙い撃ちにする。
そのアイヌの戦士達を騎士達がランスによるチャージで蹴散らしていく。
その騎士達はアイヌの戦士達が構えた長槍に阻まれて落馬し、討ち取られていく。
長槍を構えたアイヌの一団は、そこに漢人の兵士が投げ込んだ震天雷で肉塊に変わっていく。
漢人達もアイヌの毒矢の前に倒れ伏していった。
凄惨な戦いが続き、夕刻頃になった。お互いにその兵力を減らしていき、双方半数近くまで減少している。ここまでの状態になってもまだ互いに手を緩めることはない。
乱戦になって自ら前線で戦っている時光の前に、一騎の戦士が現れた。プレスター・ジョンである。
「ようやく会えたな。トキミツ! お前を討ち取ればこちらの勝利だ!」
「果たしてそうかな?」
「何?」
「俺は一介の武士だ。俺が死んだところで皆の戦う意思は変わらない。それは今日の戦いぶりが示している。それに引き換え俺がお前を倒せばそちらの軍は瓦解する。プレスター・ジョンというキリスト者の救世主、チンギス・ハーンとトオリル・ハンという二人の英雄の血を引く者。そんな求心力を持った男を失うのだからな」
「それは違う。俺が死んだところで我が軍の戦う意思は潰えはしない。既に神の国を地上に顕現する道、モンゴル帝国を打ち倒して安寧を築く道は見えているのだ。それは俺が死んでも変わる事などない。それに知らないのか? 我らが救世主 のイエスは死んだが、その教えは千年たっても人々の心に残り続けたのだ」
どうやら、お互いの軍の指揮官である時光やプレスター・ジョンが死んだとしても、どちらかが完全に殲滅されるまで戦いは続くようだ。プレスター・ジョンの言葉に嘘は感じない。彼の首を獲って敵に晒したとしても、敵は最後の一兵まで死力を尽くして戦い続けるのだろう。
一瞬、この場でプレスター・ジョンとの戦いを始める事に虚しさを感じた時光だったが、それでも指揮官が戦死すれば形勢は有利になるはずだ。気を取り直して弓を構えた。
二人の戦いは互いの弓を引き絞るところから始まった。双方とも強弓の使い手だ。まともに命中すれば致命傷になるだろう。それを警戒した二人は複雑な軌道で馬を走らせながら矢を放っていく。お互い何本かの矢を回避しながら戦闘していたが、何本目かの矢が、時光の騎乗している馬を貫いた。
落馬して背中を強かに地面にうった時光だったが、ここで怯んでいては命が無い。すぐに態勢を整えると太刀を引き抜き、止めの矢を射ようとするプレスター・ジョン目掛けて投げた。この行動は予想外だったのだろう、迫りくる太刀を避けることが出来ずに落馬してしまう。
そこを見逃さずに時光はプレスター・ジョンに突撃し、馬乗りになって殴りつけた。お互い最早武器を持っていないため、己の肉体で戦うより他にない。時光の拳が効いたのだろう。プレスター・ジョンとてモンゴル相撲 の名手であり、組み技の技量は時光に引けを取ることは無いのだが、成すすべなく殴られ続けた。
勝利を確信した時光の脳裏に、このまま相手を殺しても良いのだろうかという考えが浮かぶ。プレスター・ジョンを倒せば指揮する者の居なくなった敵軍は、統制が取れなくなり殲滅しやすくなるはずだ。
だが、本当にそうするべきなのだろうか?
そんな事を刹那の間考えていた時光は、背筋が凍る予感に駆られてプレスター・ジョンの上から身を放り出し、迫りくる何かから身を躱した。
「プレスター・ジョンよ。お乗りください! ここは退きます!」
迫っていたのはランスを構えたガウリイルであった。一瞬でも遅れれば穂先の露と消えていただろう。
指揮官が退いたことで敵軍が皆後退した。彼らは皆傷ついているが、退いていく様子は統制が取れておりまだまだ戦う意思は残っているように見えた。
「どうするトキミツ。 夜襲を仕掛けるか?」
敵が退いたことで味方も戦いを止め、時光の周りに集まって来て態勢を整え始めた。そして彼らの代表格であるであるエコリアチが問うているのである。
夜の狩りによって夜目が利くアイヌ達は、夜襲が得意と言っても過言ではない。敵も警戒しているだろうが昼間よりも有利に戦えるだろう。朝から夕まで地獄の様な戦いを繰り広げてきた彼らであるが、まだまだ戦う意思は減るところではない。当然かもしれない。ここで戦わねば彼らの平穏な生活は失われてしまうのだから。
「いや、止めよう。敵も警戒して罠を仕掛けている可能性がある。そうだったら大損害だ。それに……」
「それに?」
「いや、何でもない」
時光は「もうこれ以上戦うべきではないのでないか」という言葉を口にすることは出来なかった。戦を仕掛けられている立場であるアイヌ達に、戦を止めようとはとても言えなかったし、武士として生まれた立場がその言葉を封じ込めたのだ。
結局夜襲はしない事になり、敵の動きを警戒しながら明日の朝まで休息することになった。明日の朝にはまた今日と同じような死闘が待っているはずである。暗い思い出時光は眠りについた。
そして、時光が目を覚ましたのは明け方の少し前、激しい轟音によって覚醒した。この轟音は以前震天雷をまとめて爆破した時を遥かに超えるものだった。
目覚めた時光の目に飛び込んできたもの。それは噴煙と共に炎を噴き上げるトカプチの山であった。
時光は味方の内ただ一人馬上にあり、周囲には少数の仲間だけが待機していた。
当初から味方の被害を積み重ねながらも順調に戦線を前進させていたし、途中から目に見えて速度が速くなった。敵の様子を見る限り士気を失って統制が取れなくなった様子は無いので、幹部であり各種作戦の立案者と目されるウリエルと呼ばれている漢人の将軍に対する襲撃に成功したのだろう。
もう既に敵には下がるところは無く、フラヌの盆地の南端に押し込まれている。敵の一番の強みは騎兵による機動力の発揮である。機動力を発揮するための地積が無ければその真価を発揮することが出来ない。
「どうなされる? このまま一挙に殲滅されますか?」
時光の家来である丑松が尋ねて来る。形勢は時光達に優勢だがその表情は険しいものがある。
「もうそろそろ交渉に移れないだろうか? このまま力攻めしたら互いに被害が増えるだけだ」
「窮鼠猫を嚙むも申しますからな」
これだけ形勢が不利になっても士気が衰えないというのは恐るべきことである。通常なら不利になった時点で戦意を失い、まともに戦闘することが出来ないのだ。そして、その様な敵は多少数が多かったとしても戦力にはならないものなのだ。
しかし、プレスター・ジョン率いる敵は、プレスター・ジョンの魅力か、宗教心か、モンゴル帝国内で低い地位にある者の上昇意欲かは分からないが、未だに勢いが衰える様子を見せない。
この様な敵に対して殲滅戦を仕掛けると、最後の一兵まで死に物狂いで立ち向かって来ることだろう。もしそうなったら時光と共に戦うアイヌやニヴフの戦士達も半数は命を失うだろう。
時光は戦の采配を任されてはいるものの、北方の民にとっては部外者である。彼らにそこまでの犠牲を強いて良いのか判断できなかった。
「それは構わんが、俺達はどれだけの犠牲を払ってでも最後まで戦い抜く覚悟は出来ているぞ」
傍にいたサケノンクルが特に気を張った様子も無く答えた。サケノンクルはアイヌの代表格である。彼の考えはアイヌの戦士達の一般的なもの、そして総意ととっても問題ないだろう。
「そうか……では、軍使を派遣……」
「大変だ! 西の方から新手が現れたぞ! 鉄と馬の奴らだ!」
慌てた様子の報告の声に遮られ、時光は最後まで言い終える事が出来なかった。「鉄と馬の奴ら」とは、ガウリイルが率いる騎士団であろう。ミハイルが率いる騎士団が蝦夷ヶ島に上陸したという報告はまだ受けていない。
ガウリイルはカムイコタンからイシカリに向かったはずであり、この戦場には来ない筈であった。プレスター・ジョンの率いる本隊とイシカリで合流する予定だったはずだし、方針が変わってこちらに向かおうとしてもその経路は大規模な倒木で塞がれているはずなのだ。とてもこの短期間で除去できたとは信じられない。
予想外の事態に混乱する時光の耳に、聞いたことのある声が響いて来た。
「覚悟ー!」
時光が声のする方向を見ると、数機の騎士達が穂先を前にして突撃してくるのが見えた。その戦闘を駆けて来る騎士は、兜で顔こそ見えないものの誰なのか時光には理解できた。
プレスター・ジョンの軍勢の幹部として騎士団の一部を率いる女騎士のガウリイルである。やはり彼女が妨害を突破してこの戦場に駆けつけてきたのだ。
ガウリイルの攻撃は完全な奇襲となり、馬上の時光はそれに対応することが出来ない。意識だけ相手の方に向けたとしても、物理的な動き、馬を操り回避行動をするだけの余裕は無いのだ。
このままではガウリイルの構えた長大な
「させるかー! ぐぁ!」
死を覚悟した時光を救ったのは、傍にいたサケノンクルであった。傍にいたアイヌの戦士から木製の手盾を奪い取り、ガウリイルと時光の間に割って入り、ランスを防ごうとした。
その結果時光の命は救われたが、代償も大きかった。ちゃちな盾では勢いのついたランスを受け止めきれず、盾は粉砕されて左手も貫かれ、馬の体当たりをその身に受けてサケノンクルは吹き飛ばされた。馬蹄にかけられなかったのは幸運だっただろう。なんとか息はあるようだ。
「くっ……」
もう一人すぐ近くに控えていた丑松が佩いていた太刀を引き抜き、ランスの柄を切り払った。丑松の所有する太刀も時光の物と同じく名工綾小路定利の作である。その切れ味と、時光を上回る丑松の剣技の冴えにより、硬い木で作成されたランスの柄が綺麗な断面を見せて切断された。
「馬鹿な……イシカリからここに来る道は塞いだはずだ」
「木など燃やせばよいだけの事」
「水気を含んだ生木がそう簡単に燃えるわけがない!」
「忘れたのか? 道の途中にはイクスンペツという石炭の採掘場があっただろう? 石炭を大量に敷き詰めればいかに大量の倒木とはいえ燃えないわけがない」
ガウリイルの答えに時光は納得するとともに、その事に気が付かなかった自分の迂闊さを責めた。気付いていれば、増援が来ることを見越した作戦を立てられたのに、実際はこのざまだ。
また、ガウリイルは言わなかったが、時光がイシカリを奪回した時、気が付かずに取り逃がしたマルコ=ポーロの知らせで時光達の動きや、道を封鎖したことは全てガウリイルの耳に入っていたのだ。
ここで異変に気が付いたアイヌの戦士達が駆け付けて来て矢を放ち、騎士達を追い払った。
一陣の風の如く騎士達が駆け抜けた後、戦況の把握に気を向けた時光は前線の様子が混乱している事に気が付いた。どうやら到着した騎士団の本隊が側面から攻撃したことで、味方が混乱しているようだ。騎士団の兵数は大したことは無いものの、意識外からの攻撃を食らえば冷静ではいられないものだ。
幸い味方は分散しているので
だが、この状態で戦い続けることは危険すぎる。そう判断した時光はすぐに撤退の指示を出した。
幸い敵も戦いに継ぐ戦いで追撃してくる余裕は無かったようだ。トキミツ達はピイエ丘陵まで無事に退却することが出来た。
ピイエ丘陵に時光達が後退してから一夜明けた。夜の内に態勢を立て直し、戦支度を整えることが出来た時光達だったが、ピイエ丘陵から見下ろす眼前には敵の立ち並ぶ姿があった。折角昨日の戦いで押し込んだのにそれを挽回された形だ。
「敵の士気は全然落ちていないな。増援が来たからっていうのもあるかもしれんが、昨日あれだけやられたのに、良く戦意を保ってられるものだ」
敵の士気は落ちていないが、幸い味方の士気も落ちていない。アイヌの代表格であるサケノンクルが重傷となって下げられているが、その代わりを務めるエコリアチの下で未だ闘志は衰えていない。
「宗教的情熱かもしれませんな。彼らはキリスト者として大陸の東方で生きてきましたが、それは決して安寧なものではなかったのでしょう。それがこの苦境でも戦い抜く意思を保てる理由なのでしょう。ここを耐え抜けばきっと神の国がやってくると信じて。それに例え死んだとしても神の救いがあると信じれば、死への恐怖などありますまい」
時光の問いに答えたのは、
カトリックの彼にとって、プレスター・ジョン達の信じるネストリウス派は異端であるという事情もあるのだが。
「なるほどね。そういうものか。しかし恐ろしいものだな、宗教とは。わが国でも権力争いをする坊主どもや、狂信者どもは恐ろしいがそれは何処も変わらないか」
「いいえ。神の教えの本質とはその様な所にはありません。神の教えの本質とは
「
「そうです。異端者や異教徒と戦う事も大切かもしれませんが、最も重要なのは限りない隣人愛なのです。互いに愛し合い、思いやる事こそ宗教の本義であり、その他は枝葉末節といっても良いでしょう。日本の神やら仏とやらの教えもそんなところなのでは? それに、アイヌ達がいう所のカムイも人々が傷つけ合うことなど望んではいないでしょう」
「確かにそうかもしれんな」
人間は時として宗教を原因として争う事があるが、それは本来の神仏の教えからは外れる事だろう。結局のところ争い、命を奪い合うのは人間の欲や社会的要因に他ならない。それを神の意思のせいにするのは、つまるところ人間の思惑なのだ。
流石に大陸を横断してこの様な東の果ての島までくる情熱を持った坊主である。グリエルモの発言に時光はいたく感心した。
グリエルモの片手に
時光はふと思った。自分の事情とは何なのだろうかと。
元々親から相続する土地が無いため、恩賞を貰うためにこの蝦夷ヶ島までやって来た。果たして今もそうなのだろうか。
グリエルモとの問答でしばし深い思索に入った頃、それを遮るように敵陣で鬨の声が上がった。敵は丘陵を駆け上がって攻め込むつもりのようだ。
早朝から始まった戦いは熾烈を極める事になった。
これまで幾度となく双方の陣営は戦戈を交えている。そのためお互いのやり口は知り抜いているのだ。
モンゴル騎兵が弓を構えて一斉射撃すると、分散して被害を最小限にしたアイヌの戦士達が狙い撃ちにする。
そのアイヌの戦士達を騎士達がランスによるチャージで蹴散らしていく。
その騎士達はアイヌの戦士達が構えた長槍に阻まれて落馬し、討ち取られていく。
長槍を構えたアイヌの一団は、そこに漢人の兵士が投げ込んだ震天雷で肉塊に変わっていく。
漢人達もアイヌの毒矢の前に倒れ伏していった。
凄惨な戦いが続き、夕刻頃になった。お互いにその兵力を減らしていき、双方半数近くまで減少している。ここまでの状態になってもまだ互いに手を緩めることはない。
乱戦になって自ら前線で戦っている時光の前に、一騎の戦士が現れた。プレスター・ジョンである。
「ようやく会えたな。トキミツ! お前を討ち取ればこちらの勝利だ!」
「果たしてそうかな?」
「何?」
「俺は一介の武士だ。俺が死んだところで皆の戦う意思は変わらない。それは今日の戦いぶりが示している。それに引き換え俺がお前を倒せばそちらの軍は瓦解する。プレスター・ジョンというキリスト者の救世主、チンギス・ハーンとトオリル・ハンという二人の英雄の血を引く者。そんな求心力を持った男を失うのだからな」
「それは違う。俺が死んだところで我が軍の戦う意思は潰えはしない。既に神の国を地上に顕現する道、モンゴル帝国を打ち倒して安寧を築く道は見えているのだ。それは俺が死んでも変わる事などない。それに知らないのか? 我らが
どうやら、お互いの軍の指揮官である時光やプレスター・ジョンが死んだとしても、どちらかが完全に殲滅されるまで戦いは続くようだ。プレスター・ジョンの言葉に嘘は感じない。彼の首を獲って敵に晒したとしても、敵は最後の一兵まで死力を尽くして戦い続けるのだろう。
一瞬、この場でプレスター・ジョンとの戦いを始める事に虚しさを感じた時光だったが、それでも指揮官が戦死すれば形勢は有利になるはずだ。気を取り直して弓を構えた。
二人の戦いは互いの弓を引き絞るところから始まった。双方とも強弓の使い手だ。まともに命中すれば致命傷になるだろう。それを警戒した二人は複雑な軌道で馬を走らせながら矢を放っていく。お互い何本かの矢を回避しながら戦闘していたが、何本目かの矢が、時光の騎乗している馬を貫いた。
落馬して背中を強かに地面にうった時光だったが、ここで怯んでいては命が無い。すぐに態勢を整えると太刀を引き抜き、止めの矢を射ようとするプレスター・ジョン目掛けて投げた。この行動は予想外だったのだろう、迫りくる太刀を避けることが出来ずに落馬してしまう。
そこを見逃さずに時光はプレスター・ジョンに突撃し、馬乗りになって殴りつけた。お互い最早武器を持っていないため、己の肉体で戦うより他にない。時光の拳が効いたのだろう。プレスター・ジョンとて
勝利を確信した時光の脳裏に、このまま相手を殺しても良いのだろうかという考えが浮かぶ。プレスター・ジョンを倒せば指揮する者の居なくなった敵軍は、統制が取れなくなり殲滅しやすくなるはずだ。
だが、本当にそうするべきなのだろうか?
そんな事を刹那の間考えていた時光は、背筋が凍る予感に駆られてプレスター・ジョンの上から身を放り出し、迫りくる何かから身を躱した。
「プレスター・ジョンよ。お乗りください! ここは退きます!」
迫っていたのはランスを構えたガウリイルであった。一瞬でも遅れれば穂先の露と消えていただろう。
指揮官が退いたことで敵軍が皆後退した。彼らは皆傷ついているが、退いていく様子は統制が取れておりまだまだ戦う意思は残っているように見えた。
「どうするトキミツ。 夜襲を仕掛けるか?」
敵が退いたことで味方も戦いを止め、時光の周りに集まって来て態勢を整え始めた。そして彼らの代表格であるであるエコリアチが問うているのである。
夜の狩りによって夜目が利くアイヌ達は、夜襲が得意と言っても過言ではない。敵も警戒しているだろうが昼間よりも有利に戦えるだろう。朝から夕まで地獄の様な戦いを繰り広げてきた彼らであるが、まだまだ戦う意思は減るところではない。当然かもしれない。ここで戦わねば彼らの平穏な生活は失われてしまうのだから。
「いや、止めよう。敵も警戒して罠を仕掛けている可能性がある。そうだったら大損害だ。それに……」
「それに?」
「いや、何でもない」
時光は「もうこれ以上戦うべきではないのでないか」という言葉を口にすることは出来なかった。戦を仕掛けられている立場であるアイヌ達に、戦を止めようとはとても言えなかったし、武士として生まれた立場がその言葉を封じ込めたのだ。
結局夜襲はしない事になり、敵の動きを警戒しながら明日の朝まで休息することになった。明日の朝にはまた今日と同じような死闘が待っているはずである。暗い思い出時光は眠りについた。
そして、時光が目を覚ましたのは明け方の少し前、激しい轟音によって覚醒した。この轟音は以前震天雷をまとめて爆破した時を遥かに超えるものだった。
目覚めた時光の目に飛び込んできたもの。それは噴煙と共に炎を噴き上げるトカプチの山であった。