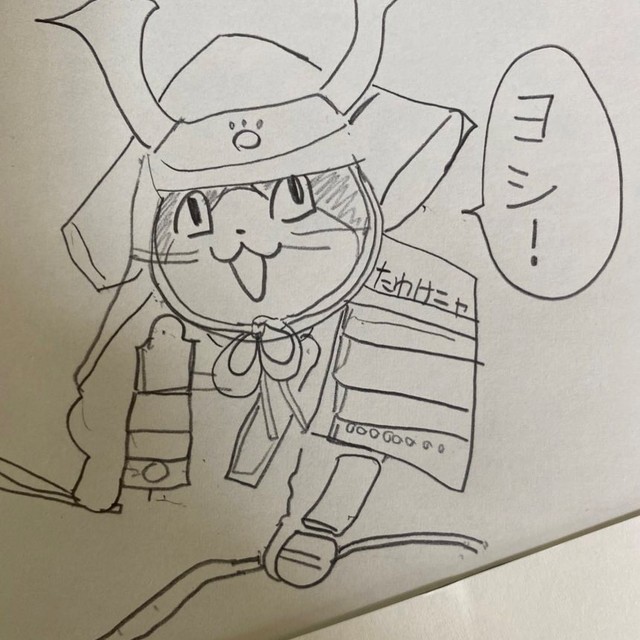第55話「タタールのくびき」
文字数 3,280文字
カラプト侵攻軍の先遣部隊を率いるミハイルは部下の撤収状況を眺めていた。普段からよく訓練されている部隊のため、逐次指示を出さなくても問題なく進んでいる。もうすぐ移動準備は完了し、この島から離脱出来ることだろう。投石器 は残念ながら置いていくが、技術者がいるのでまた作るのは容易だ。この遠征での被害はほとんどないと言っても良い。
近くにカラプトの各部族の戦士達が多数集まっているが、ミハイルの部隊に確実に勝利、または損耗無くできるような勢力ではない。整然と撤退すれば追撃は無いだろう。
「ミハイル様。悪い知らせです。対岸のワシブニに敵が集まっています。その数は数百です。撤収前に回り込まれたのでしょうか?」
赤い髪をした青年が悪い知らせを持ってきた。プレスター・ジョンに協力しているヴェネツィアの若者であるマルコ=ポーロである。彼の父と叔父は以前からプレスター・ジョンに協力しており、最近彼らに故郷から連れ出され、遥か西方世界から東の果てまでやって来たのだ。
先ほどまで追撃はないと判断していたが、回り込まれているとすれば話は別である。進軍を阻まれたところに追撃されたら大損害が出てしまう。一体いつの間に海を渡ったのであろうか。
これは挟み撃ち――それも鉄 床 戦 術 という奴だ。おそらく敵は騎士がその突進力を発揮できない氷上に陣を構え、ミハイルの軍を拘束してその背後を突くつもりだろう。
「敵の種類はどうだったか? この島の住人らしく弓兵や犬ぞり主体か? 以前奴らは長槍で騎士の突撃を阻止したと聞いたから、長槍兵か?」
「いえ。トナカイに引かせたソリで内陸部から現れたそうです」
「ほう? ……読めた。そいつらは我々の目をかいくぐって対岸に渡ったのではない。このボコベー城を落とした時に離脱した者どもが海を渡って我々の本拠地であるヌルガンを攻めたようだが、そ奴らが帰還してきたのだろう。我らが主が本隊を率いて帰還したから戻って来たのだろう」
「なるほど、では奴らはプレスター・ジョンに敗れて逃げて来たという事ですね?」
「そうではあるまい。報告にあったトナカイは大陸で調達したのだろう。このカラプトの島にもトナカイを使役する部族はいるようだが、その数はあまり多くないようだ。つまり我々の本拠地で物資を奪取し、それを持ち帰るだけの余力があるのだ。逃走したというより、見事退却戦を成功させたという方が正確だろう。主には他の四大天使もついていたはずだが、彼らの裏をかくとはな」
ミハイルは出現した敵の部隊や、それを率いる時光の能力を高く評価した。それは最悪の事態を想定することにより作戦の習性に資するためでもあるし、実際に感心しているという事でもある。
数々の戦いに身を投じ軍略に明るいミハイルではあるが、まさか時光達が震天雷を満載したトナカイを敵陣に突っ込ませて自爆させ、撤退路を確保したとは夢にも思っていない。
「奴らの指揮官は確かトキミツと言ったか。以前の戦いでもガウリイルを敗北させたとかで、ガウリイルが何度も奴の事を言っていたな」
「ガウリイル殿はミハイル様の娘だと聞きましたが?」
「義理だがな。あれの故郷がモンゴル軍に蹂躙され、一人泣いていた赤子を助けて育てたのだ。生き延びるために騎士としての技を教えたのだが、まさかあそこまで成長するとは思わなかった」
プレスター・ジョンの軍勢には数多くの騎士が加わっているが、正式に騎士として叙任させているのは老齢のミハイルだけである。他の者は若者ばかりで、ミハイルが孤児だったところを拾って騎士として育てたのだ。彼らの親には貴族や騎士としてモンゴル軍と戦い、既知のミハイルに子どもを託した者達もいるが、大半は氏素性の知れぬ者達だ。
騎士団としては本場ヨーロッパのものに比べたら微妙なものであるが、歴戦の騎士であるミハイルが厳しく育て上げたので、その実力は本物である。
また、キリスト教徒として神の信仰心も篤く、その結束力は並大抵ではない。本場の騎士達には騎士道精神は表面だけの、盗賊の類の精神性しか持たない連中も多いのだが、ミハイルは謹厳実直な本気で騎士道と神への信仰に身を捧げる騎士の鑑である。そのミハイルに育てられたプレスター・ジョンの騎士達は、ある意味本場の騎士達よりも騎士らしいと言えるかもしれない。
「しかし、彼らの待ち受ける氷の上では、我々の主力である馬よりも奴らのトナカイが有利ですし、騎士の槍突撃 も効果を発揮できず不利なのでは? どうしますか?」
「マルコ殿は騎士が草原でしか戦力を発揮できないと思っていませんかな? 実際はヨーロッパは森が多いですし、海賊と海戦もあれば、パレスチナの砂漠で戦うこともある。もちろん雪上や氷上で戦う者もな」
「そう言えばミハイル様はルーシの出身だとか? では氷上での戦いにも通じいるという訳ですね」
「その中でもノヴゴロド公国であるな」
ルーシは現在のウクライナの辺りを指す地名であり、ロシアの語源である。当然極寒の地であり、この地域の騎士達はそれに適応した戦い方に通じている。また、ルーシはこの時代モンゴルに支配されており、タ タ ー ル の く び き と呼ばれている。
ただ、ルーシ諸国が支配されて行く中、ノヴゴロド公国は一応の独立は保っていた。大公であるアレクサンドル・ネフスキーは英邁な君主であり、従属的な立場であるもののモンゴルとの外交に成功し、征服されることを免れたのだ。
アレクサンドルは戦争における指揮官としても優秀であり、スウェーデンやドイツ騎士団などの侵攻を打ち破っている。それだけの軍事的な実績がありながらモンゴルとの決戦を選ばなかったというのは、恐るべき深慮であると言えよう。
強い君主は普通ならその実力に物を言わせて戦ってしまう者である。後世日本の戦国時代における大名である武田勝頼などは強 す ぎ る 大 将 と評価されている。これは戦では強く、名将として知られた父の武田信玄を超える版図を手に入れたものの、戦により却って消耗し、最終的に家を滅ぼした事にあらわれている。
そして、そのアレクサンドル・ネフスキーを主君としていたミハイルは、従属の証としてモンゴル帝国に差し出されたのであった。それから紆余曲折があって現在プレスター・ジョンに仕えておりその境遇には満足しているのだが、敬愛する主君とその国を守るだけの力がなかったという事は、今でもミハイルの心にトゲの様に刺さったままだ。
「まあ見ているがいい。ルーシ仕込みの氷上の戦いを見せてやろう。寒冷地での戦いは奴らの専売特許ではない事をお見せしよう」
ミハイルは老齢とは思えぬ覇気を放ちながら不敵に笑った。彼は殺し合いを望む性格ではないが、騎士としての戦いに臨んではやる心は抑えきれないようだ。
「これは頼もしい。話は変わりますが、ルーシの地は寒いので、体を温めるためにストーブ小屋や酒が欠かせないのだとか?」
「おお。良く知っているな。ストーブによって体を外から温め、酒によって内から温める。そうしなければ凍死してしまうだろう」
ミハイルは故郷の事を良く知っているマルコ=ポーロの言葉に気を良くした。現代においてもロシア人の酒好きは知られるところである。また、ルーシの民の酒宴については「東方見聞録」にも書かれれている。
「それに、その大宴会中に席を外すことの出来ない貴婦人は、尿意を催した時侍女に海綿を裾にあてがわせ、座ったまま用を足すのだとか聞きました。お聞きしたいのですが、その尿を吸い込んだ海綿はどう処理するんですか? 世界各地で聞いた話を本にまとめたいので、この件もよく知っておきたいのですが」
調子にのったマルコ=ポーロは何やら変態的な事を質問してきた。正気とは思えない内容の質問だが表情は真面目である。
「おい。そのような与太話を何処で聞いたのか知らぬが、絶対に本などに書くんじゃないぞ。いいな?」
「あっ、分かりました」
マルコ=ポーロは素直に頷いた。
なお、宴会中の貴婦人は座ったまま海綿に尿を云々の話は「東方見聞録」に記述されている。
近くにカラプトの各部族の戦士達が多数集まっているが、ミハイルの部隊に確実に勝利、または損耗無くできるような勢力ではない。整然と撤退すれば追撃は無いだろう。
「ミハイル様。悪い知らせです。対岸のワシブニに敵が集まっています。その数は数百です。撤収前に回り込まれたのでしょうか?」
赤い髪をした青年が悪い知らせを持ってきた。プレスター・ジョンに協力しているヴェネツィアの若者であるマルコ=ポーロである。彼の父と叔父は以前からプレスター・ジョンに協力しており、最近彼らに故郷から連れ出され、遥か西方世界から東の果てまでやって来たのだ。
先ほどまで追撃はないと判断していたが、回り込まれているとすれば話は別である。進軍を阻まれたところに追撃されたら大損害が出てしまう。一体いつの間に海を渡ったのであろうか。
これは挟み撃ち――それも
「敵の種類はどうだったか? この島の住人らしく弓兵や犬ぞり主体か? 以前奴らは長槍で騎士の突撃を阻止したと聞いたから、長槍兵か?」
「いえ。トナカイに引かせたソリで内陸部から現れたそうです」
「ほう? ……読めた。そいつらは我々の目をかいくぐって対岸に渡ったのではない。このボコベー城を落とした時に離脱した者どもが海を渡って我々の本拠地であるヌルガンを攻めたようだが、そ奴らが帰還してきたのだろう。我らが主が本隊を率いて帰還したから戻って来たのだろう」
「なるほど、では奴らはプレスター・ジョンに敗れて逃げて来たという事ですね?」
「そうではあるまい。報告にあったトナカイは大陸で調達したのだろう。このカラプトの島にもトナカイを使役する部族はいるようだが、その数はあまり多くないようだ。つまり我々の本拠地で物資を奪取し、それを持ち帰るだけの余力があるのだ。逃走したというより、見事退却戦を成功させたという方が正確だろう。主には他の四大天使もついていたはずだが、彼らの裏をかくとはな」
ミハイルは出現した敵の部隊や、それを率いる時光の能力を高く評価した。それは最悪の事態を想定することにより作戦の習性に資するためでもあるし、実際に感心しているという事でもある。
数々の戦いに身を投じ軍略に明るいミハイルではあるが、まさか時光達が震天雷を満載したトナカイを敵陣に突っ込ませて自爆させ、撤退路を確保したとは夢にも思っていない。
「奴らの指揮官は確かトキミツと言ったか。以前の戦いでもガウリイルを敗北させたとかで、ガウリイルが何度も奴の事を言っていたな」
「ガウリイル殿はミハイル様の娘だと聞きましたが?」
「義理だがな。あれの故郷がモンゴル軍に蹂躙され、一人泣いていた赤子を助けて育てたのだ。生き延びるために騎士としての技を教えたのだが、まさかあそこまで成長するとは思わなかった」
プレスター・ジョンの軍勢には数多くの騎士が加わっているが、正式に騎士として叙任させているのは老齢のミハイルだけである。他の者は若者ばかりで、ミハイルが孤児だったところを拾って騎士として育てたのだ。彼らの親には貴族や騎士としてモンゴル軍と戦い、既知のミハイルに子どもを託した者達もいるが、大半は氏素性の知れぬ者達だ。
騎士団としては本場ヨーロッパのものに比べたら微妙なものであるが、歴戦の騎士であるミハイルが厳しく育て上げたので、その実力は本物である。
また、キリスト教徒として神の信仰心も篤く、その結束力は並大抵ではない。本場の騎士達には騎士道精神は表面だけの、盗賊の類の精神性しか持たない連中も多いのだが、ミハイルは謹厳実直な本気で騎士道と神への信仰に身を捧げる騎士の鑑である。そのミハイルに育てられたプレスター・ジョンの騎士達は、ある意味本場の騎士達よりも騎士らしいと言えるかもしれない。
「しかし、彼らの待ち受ける氷の上では、我々の主力である馬よりも奴らのトナカイが有利ですし、騎士の
「マルコ殿は騎士が草原でしか戦力を発揮できないと思っていませんかな? 実際はヨーロッパは森が多いですし、海賊と海戦もあれば、パレスチナの砂漠で戦うこともある。もちろん雪上や氷上で戦う者もな」
「そう言えばミハイル様はルーシの出身だとか? では氷上での戦いにも通じいるという訳ですね」
「その中でもノヴゴロド公国であるな」
ルーシは現在のウクライナの辺りを指す地名であり、ロシアの語源である。当然極寒の地であり、この地域の騎士達はそれに適応した戦い方に通じている。また、ルーシはこの時代モンゴルに支配されており、
ただ、ルーシ諸国が支配されて行く中、ノヴゴロド公国は一応の独立は保っていた。大公であるアレクサンドル・ネフスキーは英邁な君主であり、従属的な立場であるもののモンゴルとの外交に成功し、征服されることを免れたのだ。
アレクサンドルは戦争における指揮官としても優秀であり、スウェーデンやドイツ騎士団などの侵攻を打ち破っている。それだけの軍事的な実績がありながらモンゴルとの決戦を選ばなかったというのは、恐るべき深慮であると言えよう。
強い君主は普通ならその実力に物を言わせて戦ってしまう者である。後世日本の戦国時代における大名である武田勝頼などは
そして、そのアレクサンドル・ネフスキーを主君としていたミハイルは、従属の証としてモンゴル帝国に差し出されたのであった。それから紆余曲折があって現在プレスター・ジョンに仕えておりその境遇には満足しているのだが、敬愛する主君とその国を守るだけの力がなかったという事は、今でもミハイルの心にトゲの様に刺さったままだ。
「まあ見ているがいい。ルーシ仕込みの氷上の戦いを見せてやろう。寒冷地での戦いは奴らの専売特許ではない事をお見せしよう」
ミハイルは老齢とは思えぬ覇気を放ちながら不敵に笑った。彼は殺し合いを望む性格ではないが、騎士としての戦いに臨んではやる心は抑えきれないようだ。
「これは頼もしい。話は変わりますが、ルーシの地は寒いので、体を温めるためにストーブ小屋や酒が欠かせないのだとか?」
「おお。良く知っているな。ストーブによって体を外から温め、酒によって内から温める。そうしなければ凍死してしまうだろう」
ミハイルは故郷の事を良く知っているマルコ=ポーロの言葉に気を良くした。現代においてもロシア人の酒好きは知られるところである。また、ルーシの民の酒宴については「東方見聞録」にも書かれれている。
「それに、その大宴会中に席を外すことの出来ない貴婦人は、尿意を催した時侍女に海綿を裾にあてがわせ、座ったまま用を足すのだとか聞きました。お聞きしたいのですが、その尿を吸い込んだ海綿はどう処理するんですか? 世界各地で聞いた話を本にまとめたいので、この件もよく知っておきたいのですが」
調子にのったマルコ=ポーロは何やら変態的な事を質問してきた。正気とは思えない内容の質問だが表情は真面目である。
「おい。そのような与太話を何処で聞いたのか知らぬが、絶対に本などに書くんじゃないぞ。いいな?」
「あっ、分かりました」
マルコ=ポーロは素直に頷いた。
なお、宴会中の貴婦人は座ったまま海綿に尿を云々の話は「東方見聞録」に記述されている。