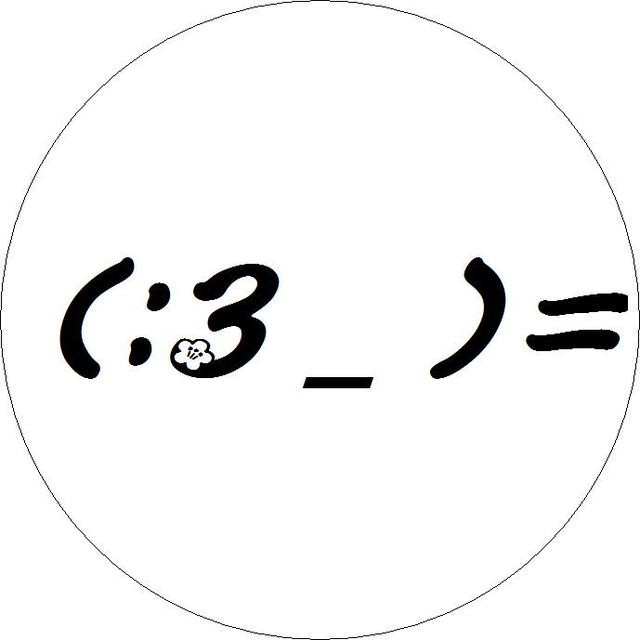釣瓶の国へ
文字数 5,021文字
ランマルはカンタロウとマリアを背中に乗せ、ジャンプして穴から脱出した。
地面は斜面になってしまい、気をつけなければ、転んでしまう。
土の塊が、ポロポロと下へと落ちていく。
「土だらけだ」
カンタロウは服を払った。
マリアとランマルも、同じく手で服を払う。
「うわっ、きったねぇ」
アゲハがカンタロウを指さして笑った。
「ほっとけ」
「ほら、後ろむいて。払ってあげるよ」
「あっ、ああ。すまん」
急にしおらしくなるアゲハ。
カンタロウは急変する性格に、動揺を隠せなかった。
「ごめんね。罠だと気づかなかった。もう少し早く気づいていれば、こんなことにならなかったのに……」
「いいさ。仕方ない」
カンタロウの背中が、アゲハによって優しく払われる。
――ふふん。男って、ほんと単純。
アゲハはカンタロウの後ろで、本心を明かしていた。その表情に、誰も気づかなかった。
「それにしても、さっきのエコーズ。どうして爆発したのでしょうか?」
「ああ、あれはたぶん、第二種のゴーストエコーズで、上位種に操られて、自爆させられたんだ」
カンタロウがマリアに、すらすらと説明する。
ゴーストエコーズとの戦闘経験があるので、基礎知識は持っていた。
「第二種?」
「ゴーストエコーズの中でも、一番の下だ。次にえらいのが第一種。一番えらいのが特種だ」
カンタロウの説明がわかりにくかったのか、マリアは首を傾げる。
「詳しく言うとね。第二種は知能が低いし、言語能力もないの。第一種は、言語能力はあるけど、知能が低い。特種は、両方とも高い」
アゲハが補足説明した。
マリアはゴーストエコーズの序列を理解する。
「つまり、あのゴーストエコーズを操っていた者は、第一種か特種になるが……」
「特種の可能性が高い」
「ああ、恐らく。いや、絶対そうだな」
カンタロウとアゲハがうなずき合う。
「そりゃ最悪だな。特種エコーズなんて、俺はやりあったことないぞ」
赤眼化から黒い瞳に戻ったランマルが、両手を天に上げた。
「そりゃそうだよ。滅多にいないもん」
アゲハも両手を上げる。
「あのっ、それなら、特種ゴーストエコーズと普通のエコーズの違いって、何があるんでしょう?」
マリアが片手を上げて、質問する。
「……さあ」
「……そういえば、そうだな」
カンタロウとランマルは、お互いを見合わせた。
「ぜんぜん違うよ。エコーズは、ゴーストエコーズを操れないの。逆にゴーストエコーズは、上位種が下位種を操れる。その能力をコンタクト・リンクって言うんだけどね。それに、ゴーストエコーズは生まれた環境も謎で、エコーズは母大樹から生まれるけど、アイツ等はどこで生まれているのかわかんないの」
アゲハが皆に、流ちょうに説明した。
三人はアゲハに目を見張った。
「どうしたのみんな?」
三人が黙ってしまったので、アゲハは思わずぎくりとした。自分の正体について、よけいな事を言ったかもしれない。
「やけに詳しいな?」
「えっ? そう? 習わなかったの?」
「いいや。そんなこと、習うのか?」
ランマルが首を横に振った。
エコーズの生態など、学校で習ったことがない。
カンタロウとマリアも、首を横に振る。
アゲハはほっと、息をついた。自分の博学に驚いているだけだとわかったからだ。
「まあアゲハなら習っているかもな。国章血印の持ち主だし」
カンタロウが何気に、国章血印のことを言ってしまった。
「えっ?」マリアは目をパチクリさせた。
ランマルも驚いたのか、息がつまる。
「ええっ! すごい! アゲハさん! 国章血印刻まれてるんですか?」
国章血印が何か、マリアは知っているようだ。手を合わせて驚く。
「俺は団長なのに、刻まれてないのに!」
ランマルも、若い女の子に国章血印が刻まれていることに、舌を巻いた。
「……カンタロウ君」
アゲハが非難するような目で、カンタロウを見る。
「あっ、言っちゃいけなかったのか? すまん」
カンタロウは自分の口を、手でふさいだ。
アゲハは隠すことを諦め、手袋を脱いで、赤眼化してみせた。盲目の蛇が、右手の甲にはっきりと姿をあらわす。
「大帝国。双頭蛇、盲目の蛇が、私の右手の甲に刻まれてるよ」
マリアとランマルは、興味津々に、アゲハの盲目の蛇を眺めた。
「本当だ。なんだ。どうりで強いと思ったぜ。国章血印でもびっくりなのに、まさか盲目の蛇とは。こりゃ恐れ入った」
ランマルは鼻を、指でさすった。
「盲目の蛇ってなんですか?」
さっそくマリアが、素朴な質問をランマルにする。
「大帝国のエコーズ討伐専門部隊。確か、帝国軍第四類に属するんだっけか? 通称死帝と呼ばれる精鋭部隊だ。あのエコーズの王、コウダの息がかかってる」
ランマルは質問に答えた。
大帝国軍は四つに分かれている。
エリートである第一類。一般兵の第二類。技術兵の第三類。そして、死帝と恐れられている第四類である。
「えっ……エコーズの王の……」
マリアが明らかに嫌な顔をした。
アゲハはそれを見逃さず、
「軽蔑した?」
「いっ、いいえっ! すみません。顔にでてましたか?」
「別にいいよ。慣れてるし」
「ごめんなさい。私、エコーズが嫌いなんです」
マリアの言葉に、アゲハは視線を下に落とし、
「……そっか」
弱々しい声。そのためか、誰も、アゲハのつぶやきが聞こえなかった。
「まあ、エコーズが好きな奴は、この大陸にはいないわな」
ランマルがマリアに同意する。
カンタロウは特に何も言わなかったが、否定することもなかった。
「……ねえ、マリア」
「はい?」
突然、アゲハがマリアの胸をもんだ。
ヒナゲシとは違い、弾力があり押し返してくる。
アゲハの小さな手では少し余った。
マリアは何をされているのかわからず、きょとんとアゲハを見つめる。
「超箱入り娘だよね? だからおっぱいでかくなるの?」
「きゃあ! どこ触ってるんですか!」
我に返ったマリアは、胸を慌てて隠す。
アゲハは悪戯っ子のように、白い歯をだして笑い、
「きひひ……うん? 何、カンタロウ君?」
「大丈夫だ。俺の母を見習えば――大きくなる」
カンタロウは同情的な視線をむけ、親指を立てた。
「カンタロウ君。ぶん殴るぞ」
アゲハは少し、イラッとした。
「まあともかく。今は特種エコーズを探すことが先決だな」
ランマルが話を元に戻した。
「どこかにいることは、間違いないんだけどね」
「臭いでわからないのか?」
「無理だよ」
「そうか」
カンタロウは顎に手をやり、考えている。
――そもそも私、獣人じゃないし。
アゲハは顔をそらし、赤い舌をだした。
「あっ、そういえば、さっきのハンターの中に、エスリナというニンフがいましたよね?」
マリアが思い起こしたように、声を上げ、
「今思い出したんですけど。彼女、エリニスではかなり有名な魔法の使い手だったはずです。この件は報酬金が高いですし。みすみす逃すとは思えないんですけど……」
マリアの話を聞き、ラッハ達がむかった先に、皆視線をむけた。
「あっ、アイツ等が行った方向……釣瓶の国の町だ!」
唐突に、ランマルが叫んだ。
「釣瓶? なんだ、それは?」
聞いたことがない国なのか、カンタロウは首を傾げる。
「昔、剣帝国に攻め入ろうとした、敵国だ。我が国と同盟を結んでいたが、契約を破棄し、裏切ったんだ。それで、黒陽騎士団が滅ぼした」
「ふぅん。それで?」
「アイツ等確か、魔帝国から来たと言ったな?」
ランマルに言われ、アゲハは記憶の奥を探ってみる。
「そういえば……アゲハさんに、魔帝国から来たのかと、訪ねてましたね」
マリアに言われ、「あっ、そうだね」アゲハはようやく思い出した。
ライヤという獣人が、確かにそんなことを言っていた。
「しまった! 馬鹿か俺は! アイツ等ゴーストエコーズを諦めて帰ったんじゃない! 本体の居場所をつかんだんだ! こうしちゃおれん! 行くぞ! お前等!」
ランマルが土砂を滑り下り、森の中を走る。
カンタロウ達もその後ろを、急いで追いかけた。
「ちょ、どういうこと?」
アゲハがランマルに追いつき、理由を聞いてみる。
「実は内密な話なんだが、魔帝国、賢帝国、剣帝国で領土問題があってな。釣瓶の国の王が死に、その領土をどちらが取るかで、揉めてる最中なんだ。そこで魔帝国の女王が、ハンターを雇って、ゴーストエコーズを倒した国の領土にしようと提案してきた。だからアイツ等はたぶん、女王に雇われたハンターだ!」
興奮気味に早口で話すランマル。
「そんなことで、決めていいんですか?」
マリアは遅れ気味になりながらも、何とかランマルについて行く。
「そもそも釣瓶の国が、敵対したという情報自体が嘘くさくてな。前王が騒いでただけで、証拠はいっさい見つからなかった。だから今の王様は何かとつっこまれると弱いんだ」
早口になるランマル。
もし釣瓶の国が敵国ではなく、前王の侵略目的であれば、剣帝国の信頼は失墜する。そうなれば、援助を受けている国から、それを理由に打ち切りもありうる。
国が青息吐息になるのは、時間の問題だ。
アゲハが「えっほ、えっほ」と言いながら、
「それ。女王の口車に引っかかっただけなんじゃないの?」
「そうだろうな。まだ若い女王で、口が達者。悪知恵も働くと聞く。金銭問題で頭の痛い王様にとって、よけいな揉め事を起こしたくなかったんだろう」
「でも、釣瓶の国ってそんなに大事なの? 聞いたことないし、ちっこい国なんじゃないの?」
「そうだ。釣瓶の国の領土は小さく。国といっても、城下町一つしかない。だけど水源があって、水が豊富に取れる。だから他の国も狙ってるんだ」
ランマルは地元兵だけあって事情をよく知っていた。
水は生命にとって、必要不可欠だ。
人間の体の約半分は水でできており、水なしでは三日ともたない。
汚染されていない水源を持つ釣瓶の国は、貴重な資源を供給する代わりに、巨大帝国と同盟を組み、自国を守ってもらっていたのである。
「しかし、そこに特種エコーズがいるとは、かぎらないぞ」
カンタロウはぴったりと、ランマルについてくる。
ランマルは汗を流しながら、
「いや、可能性は高い。ゴーストエコーズが隠れるには、あの町はうってつけだ。火で燃やされたとはいえ、地下や貴族の逃げ道はあるはずだからな」
「なるほど。たぶん、さっきの二種エコーズは、その城下町から私達を離すための囮だよ」
アゲハが敵の意図を読み取った。
エコーズが逃げて行った先。
釣瓶の国の町から、ちょうど逆の方角になっている。うまく離されてしまったようだ。
「くそっ! どうして気づかなかったんだ! このままじゃ、魔帝国に領土を取られちまう!」
「団長失格になっちゃうね」
「違うぞアゲハちゃん! そもそも平和条約で、軍は動かせないんだ。つまり、俺は概要は聞いてたが、自分はまったく関係ないと思ってた。だからすっかり忘れてた!」
ランマルは言い訳を並べた。
「ほんとか? 酒飲んで、忘れてたんじゃないのか?」
カンタロウは疑いの視線を、ランマルにむけた。
「いいか! 特種エコーズがでたら、君達が討伐するしかない! 俺はサポートに回る! 頼んだぞ!」
「真面目か! 結局何にもしないじゃん! それ!」
ランマルはあくまで、剣帝国の軍の人間なので、裏手に回るつもりのようだ。
アゲハは不満をブーブー言った。
「もういいじゃないですか」
マリアがアゲハを、後ろでなだめていた。
*
男が、窓の外を眺めていた。
そこから見える光景は、釣瓶の国の城下町。
城の最上階にいるため、遠くまで見渡せる。
雲は無秩序にもつれ、どこからか鳩吹く風が聞こえてくる。
「あの罠で、よく生き残ったものだ」
ツネミツは静かにつぶやいた。腰には刀を持ち、鎧を着ている。顔は若く、背は高い。風が黒髪を揺らす。
すぐ近くには、長く少し茶色がかった髪を持つ、ツツジ姫が座っていた。
女房装束を着て、ツネミツに顔も見せず、後ろをむいたまま何もしゃべらない。
「今日は二組ものハンターがここに気づいた。だが大丈夫だ。すぐに不穏は消える」
ツネミツがツツジを黒い瞳で見る。だが、ツツジは何も答えず、ツネミツの方にも振りむかない。ただしんと座っている。
「姫。あなたを脅かす者は、すべて我等神獣がなくしておこう」
ツネミツは悲しげな表情をした。
「だから――安心していい」
それはとても、優しい声だった。
地面は斜面になってしまい、気をつけなければ、転んでしまう。
土の塊が、ポロポロと下へと落ちていく。
「土だらけだ」
カンタロウは服を払った。
マリアとランマルも、同じく手で服を払う。
「うわっ、きったねぇ」
アゲハがカンタロウを指さして笑った。
「ほっとけ」
「ほら、後ろむいて。払ってあげるよ」
「あっ、ああ。すまん」
急にしおらしくなるアゲハ。
カンタロウは急変する性格に、動揺を隠せなかった。
「ごめんね。罠だと気づかなかった。もう少し早く気づいていれば、こんなことにならなかったのに……」
「いいさ。仕方ない」
カンタロウの背中が、アゲハによって優しく払われる。
――ふふん。男って、ほんと単純。
アゲハはカンタロウの後ろで、本心を明かしていた。その表情に、誰も気づかなかった。
「それにしても、さっきのエコーズ。どうして爆発したのでしょうか?」
「ああ、あれはたぶん、第二種のゴーストエコーズで、上位種に操られて、自爆させられたんだ」
カンタロウがマリアに、すらすらと説明する。
ゴーストエコーズとの戦闘経験があるので、基礎知識は持っていた。
「第二種?」
「ゴーストエコーズの中でも、一番の下だ。次にえらいのが第一種。一番えらいのが特種だ」
カンタロウの説明がわかりにくかったのか、マリアは首を傾げる。
「詳しく言うとね。第二種は知能が低いし、言語能力もないの。第一種は、言語能力はあるけど、知能が低い。特種は、両方とも高い」
アゲハが補足説明した。
マリアはゴーストエコーズの序列を理解する。
「つまり、あのゴーストエコーズを操っていた者は、第一種か特種になるが……」
「特種の可能性が高い」
「ああ、恐らく。いや、絶対そうだな」
カンタロウとアゲハがうなずき合う。
「そりゃ最悪だな。特種エコーズなんて、俺はやりあったことないぞ」
赤眼化から黒い瞳に戻ったランマルが、両手を天に上げた。
「そりゃそうだよ。滅多にいないもん」
アゲハも両手を上げる。
「あのっ、それなら、特種ゴーストエコーズと普通のエコーズの違いって、何があるんでしょう?」
マリアが片手を上げて、質問する。
「……さあ」
「……そういえば、そうだな」
カンタロウとランマルは、お互いを見合わせた。
「ぜんぜん違うよ。エコーズは、ゴーストエコーズを操れないの。逆にゴーストエコーズは、上位種が下位種を操れる。その能力をコンタクト・リンクって言うんだけどね。それに、ゴーストエコーズは生まれた環境も謎で、エコーズは母大樹から生まれるけど、アイツ等はどこで生まれているのかわかんないの」
アゲハが皆に、流ちょうに説明した。
三人はアゲハに目を見張った。
「どうしたのみんな?」
三人が黙ってしまったので、アゲハは思わずぎくりとした。自分の正体について、よけいな事を言ったかもしれない。
「やけに詳しいな?」
「えっ? そう? 習わなかったの?」
「いいや。そんなこと、習うのか?」
ランマルが首を横に振った。
エコーズの生態など、学校で習ったことがない。
カンタロウとマリアも、首を横に振る。
アゲハはほっと、息をついた。自分の博学に驚いているだけだとわかったからだ。
「まあアゲハなら習っているかもな。国章血印の持ち主だし」
カンタロウが何気に、国章血印のことを言ってしまった。
「えっ?」マリアは目をパチクリさせた。
ランマルも驚いたのか、息がつまる。
「ええっ! すごい! アゲハさん! 国章血印刻まれてるんですか?」
国章血印が何か、マリアは知っているようだ。手を合わせて驚く。
「俺は団長なのに、刻まれてないのに!」
ランマルも、若い女の子に国章血印が刻まれていることに、舌を巻いた。
「……カンタロウ君」
アゲハが非難するような目で、カンタロウを見る。
「あっ、言っちゃいけなかったのか? すまん」
カンタロウは自分の口を、手でふさいだ。
アゲハは隠すことを諦め、手袋を脱いで、赤眼化してみせた。盲目の蛇が、右手の甲にはっきりと姿をあらわす。
「大帝国。双頭蛇、盲目の蛇が、私の右手の甲に刻まれてるよ」
マリアとランマルは、興味津々に、アゲハの盲目の蛇を眺めた。
「本当だ。なんだ。どうりで強いと思ったぜ。国章血印でもびっくりなのに、まさか盲目の蛇とは。こりゃ恐れ入った」
ランマルは鼻を、指でさすった。
「盲目の蛇ってなんですか?」
さっそくマリアが、素朴な質問をランマルにする。
「大帝国のエコーズ討伐専門部隊。確か、帝国軍第四類に属するんだっけか? 通称死帝と呼ばれる精鋭部隊だ。あのエコーズの王、コウダの息がかかってる」
ランマルは質問に答えた。
大帝国軍は四つに分かれている。
エリートである第一類。一般兵の第二類。技術兵の第三類。そして、死帝と恐れられている第四類である。
「えっ……エコーズの王の……」
マリアが明らかに嫌な顔をした。
アゲハはそれを見逃さず、
「軽蔑した?」
「いっ、いいえっ! すみません。顔にでてましたか?」
「別にいいよ。慣れてるし」
「ごめんなさい。私、エコーズが嫌いなんです」
マリアの言葉に、アゲハは視線を下に落とし、
「……そっか」
弱々しい声。そのためか、誰も、アゲハのつぶやきが聞こえなかった。
「まあ、エコーズが好きな奴は、この大陸にはいないわな」
ランマルがマリアに同意する。
カンタロウは特に何も言わなかったが、否定することもなかった。
「……ねえ、マリア」
「はい?」
突然、アゲハがマリアの胸をもんだ。
ヒナゲシとは違い、弾力があり押し返してくる。
アゲハの小さな手では少し余った。
マリアは何をされているのかわからず、きょとんとアゲハを見つめる。
「超箱入り娘だよね? だからおっぱいでかくなるの?」
「きゃあ! どこ触ってるんですか!」
我に返ったマリアは、胸を慌てて隠す。
アゲハは悪戯っ子のように、白い歯をだして笑い、
「きひひ……うん? 何、カンタロウ君?」
「大丈夫だ。俺の母を見習えば――大きくなる」
カンタロウは同情的な視線をむけ、親指を立てた。
「カンタロウ君。ぶん殴るぞ」
アゲハは少し、イラッとした。
「まあともかく。今は特種エコーズを探すことが先決だな」
ランマルが話を元に戻した。
「どこかにいることは、間違いないんだけどね」
「臭いでわからないのか?」
「無理だよ」
「そうか」
カンタロウは顎に手をやり、考えている。
――そもそも私、獣人じゃないし。
アゲハは顔をそらし、赤い舌をだした。
「あっ、そういえば、さっきのハンターの中に、エスリナというニンフがいましたよね?」
マリアが思い起こしたように、声を上げ、
「今思い出したんですけど。彼女、エリニスではかなり有名な魔法の使い手だったはずです。この件は報酬金が高いですし。みすみす逃すとは思えないんですけど……」
マリアの話を聞き、ラッハ達がむかった先に、皆視線をむけた。
「あっ、アイツ等が行った方向……釣瓶の国の町だ!」
唐突に、ランマルが叫んだ。
「釣瓶? なんだ、それは?」
聞いたことがない国なのか、カンタロウは首を傾げる。
「昔、剣帝国に攻め入ろうとした、敵国だ。我が国と同盟を結んでいたが、契約を破棄し、裏切ったんだ。それで、黒陽騎士団が滅ぼした」
「ふぅん。それで?」
「アイツ等確か、魔帝国から来たと言ったな?」
ランマルに言われ、アゲハは記憶の奥を探ってみる。
「そういえば……アゲハさんに、魔帝国から来たのかと、訪ねてましたね」
マリアに言われ、「あっ、そうだね」アゲハはようやく思い出した。
ライヤという獣人が、確かにそんなことを言っていた。
「しまった! 馬鹿か俺は! アイツ等ゴーストエコーズを諦めて帰ったんじゃない! 本体の居場所をつかんだんだ! こうしちゃおれん! 行くぞ! お前等!」
ランマルが土砂を滑り下り、森の中を走る。
カンタロウ達もその後ろを、急いで追いかけた。
「ちょ、どういうこと?」
アゲハがランマルに追いつき、理由を聞いてみる。
「実は内密な話なんだが、魔帝国、賢帝国、剣帝国で領土問題があってな。釣瓶の国の王が死に、その領土をどちらが取るかで、揉めてる最中なんだ。そこで魔帝国の女王が、ハンターを雇って、ゴーストエコーズを倒した国の領土にしようと提案してきた。だからアイツ等はたぶん、女王に雇われたハンターだ!」
興奮気味に早口で話すランマル。
「そんなことで、決めていいんですか?」
マリアは遅れ気味になりながらも、何とかランマルについて行く。
「そもそも釣瓶の国が、敵対したという情報自体が嘘くさくてな。前王が騒いでただけで、証拠はいっさい見つからなかった。だから今の王様は何かとつっこまれると弱いんだ」
早口になるランマル。
もし釣瓶の国が敵国ではなく、前王の侵略目的であれば、剣帝国の信頼は失墜する。そうなれば、援助を受けている国から、それを理由に打ち切りもありうる。
国が青息吐息になるのは、時間の問題だ。
アゲハが「えっほ、えっほ」と言いながら、
「それ。女王の口車に引っかかっただけなんじゃないの?」
「そうだろうな。まだ若い女王で、口が達者。悪知恵も働くと聞く。金銭問題で頭の痛い王様にとって、よけいな揉め事を起こしたくなかったんだろう」
「でも、釣瓶の国ってそんなに大事なの? 聞いたことないし、ちっこい国なんじゃないの?」
「そうだ。釣瓶の国の領土は小さく。国といっても、城下町一つしかない。だけど水源があって、水が豊富に取れる。だから他の国も狙ってるんだ」
ランマルは地元兵だけあって事情をよく知っていた。
水は生命にとって、必要不可欠だ。
人間の体の約半分は水でできており、水なしでは三日ともたない。
汚染されていない水源を持つ釣瓶の国は、貴重な資源を供給する代わりに、巨大帝国と同盟を組み、自国を守ってもらっていたのである。
「しかし、そこに特種エコーズがいるとは、かぎらないぞ」
カンタロウはぴったりと、ランマルについてくる。
ランマルは汗を流しながら、
「いや、可能性は高い。ゴーストエコーズが隠れるには、あの町はうってつけだ。火で燃やされたとはいえ、地下や貴族の逃げ道はあるはずだからな」
「なるほど。たぶん、さっきの二種エコーズは、その城下町から私達を離すための囮だよ」
アゲハが敵の意図を読み取った。
エコーズが逃げて行った先。
釣瓶の国の町から、ちょうど逆の方角になっている。うまく離されてしまったようだ。
「くそっ! どうして気づかなかったんだ! このままじゃ、魔帝国に領土を取られちまう!」
「団長失格になっちゃうね」
「違うぞアゲハちゃん! そもそも平和条約で、軍は動かせないんだ。つまり、俺は概要は聞いてたが、自分はまったく関係ないと思ってた。だからすっかり忘れてた!」
ランマルは言い訳を並べた。
「ほんとか? 酒飲んで、忘れてたんじゃないのか?」
カンタロウは疑いの視線を、ランマルにむけた。
「いいか! 特種エコーズがでたら、君達が討伐するしかない! 俺はサポートに回る! 頼んだぞ!」
「真面目か! 結局何にもしないじゃん! それ!」
ランマルはあくまで、剣帝国の軍の人間なので、裏手に回るつもりのようだ。
アゲハは不満をブーブー言った。
「もういいじゃないですか」
マリアがアゲハを、後ろでなだめていた。
*
男が、窓の外を眺めていた。
そこから見える光景は、釣瓶の国の城下町。
城の最上階にいるため、遠くまで見渡せる。
雲は無秩序にもつれ、どこからか鳩吹く風が聞こえてくる。
「あの罠で、よく生き残ったものだ」
ツネミツは静かにつぶやいた。腰には刀を持ち、鎧を着ている。顔は若く、背は高い。風が黒髪を揺らす。
すぐ近くには、長く少し茶色がかった髪を持つ、ツツジ姫が座っていた。
女房装束を着て、ツネミツに顔も見せず、後ろをむいたまま何もしゃべらない。
「今日は二組ものハンターがここに気づいた。だが大丈夫だ。すぐに不穏は消える」
ツネミツがツツジを黒い瞳で見る。だが、ツツジは何も答えず、ツネミツの方にも振りむかない。ただしんと座っている。
「姫。あなたを脅かす者は、すべて我等神獣がなくしておこう」
ツネミツは悲しげな表情をした。
「だから――安心していい」
それはとても、優しい声だった。