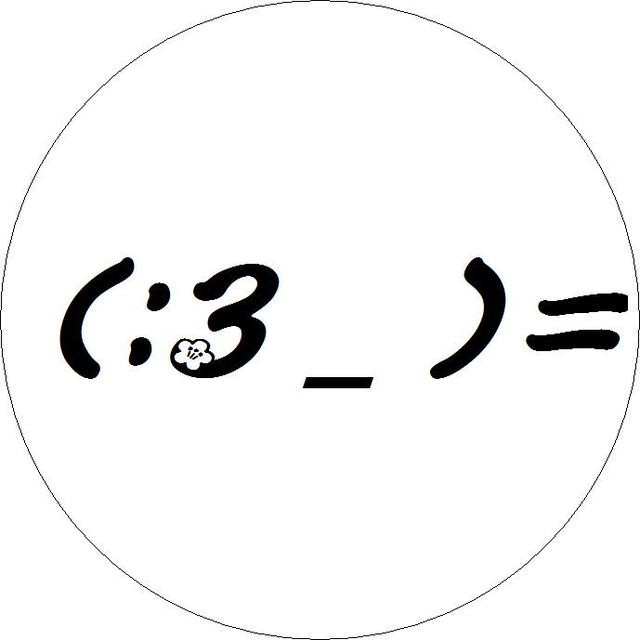パンドラック・ミクス
文字数 5,493文字
カンタロウはマリアを追いかけて、廊下を走っていた。
研究所の廊下は、植物が窓に張り付いているため、隙間から入り込む薄い光しかない。
白いホコリが、光に反射して空に舞い上がっている。
走る足音が、大きく反響してくる。
手にはたいまつを持っているが、それでも植物の茎や蔓に足を取られそうになった。
「マリア……」
カンタロウはマリアを完全に見失った。
気配を感じるため、走る足を止める。
耳に全神経を集中し、物音を探っていく。
ある部屋から、女の低い声が聞こえてきた。
カンタロウは、その部屋に入った。
部屋の中は木製の机や椅子が、乱雑に置かれてあった。
食器やコップが、地面に投げだされている。
部屋をゆっくりと歩いていると、壊れた椅子のむこう側に、白い髪の少女が見えた。
床には、たいまつが転がっている。
「うっ、ううっ……」
マリアは口を押さえ、部屋の角で嗚咽を漏らしていた。
妹の死を、はっきりと見てしまったのだ。もう、シオンが生還する希望はない。
カンタロウは声をかけようか、どうか、迷ったが、勇気をだして近づくことにした。
この施設にマリアを一人にしておくことが、危険だと思ったからだ。ただ、慰めの言葉は、何一つ思い浮かばない。
「マリア……」
カンタロウが声をかけると、すぐに反応した。ゆっくりと振りむく。
「カンタロウ……様……」
マリアの茶色の瞳から、涙が幾度も流れていく。
それを見たカンタロウは、頭の中が真っ白になり、何も言うことができなかった。
悲しさが伝染し、言葉を失う。
マリアの表情を直視することができず、つい目をそらす。
「おっ……」
唐突に、カンタロウの体に、軽い衝撃が走った。
マリアが抱きついてきたのだ。
カンタロウの背中に、両手の温もりを感じる。
「ごめんなさい……迷惑なのはわかってます……だけど……私……耐えられない」
マリアはカンタロウの胸に顔を埋め、泣き続けた。
カンタロウは少し躊躇したが、マリアを優しく抱きしめた。髪が手に、さらさらと流れていく。
「俺でよかったら――いっぱい泣けばいい」
カンタロウの精一杯の気持ちだった。
*
ツバメとアゲハは、実験室でカンタロウとマリアの帰りを待っていた。
二人を追いかけてもよかったのだが、迷う可能性もあったため、ここはカンタロウを信じて待つしかなかった。
月の氷は完全に故障し、いくらボタンを押しても録画を再生しなかった。
「マリアの奴、大丈夫かね? 心配だなぁ」
ツバメはうろうろと、腕を組んで、室内を歩き回っている。
「大丈夫だよ。カンタロウ君が行ってるし。けっこう女には優しいし」
アゲハは椅子に座り、一見落ち着いているように見えるが、足のゆすりが苛立ちを隠せないでいた。
「そうだねぇ。カンタロウっちって、ちょっと偉そうな所あるけど、何か男っぽくないっていうか、ガツガツいかない所があるからね。マリアみたいなタイプは合うかもね」
「…………」
ツバメが二人の関係について語ると、急にアゲハは黙り込む。
「何か浮かない顔だね。二人の関係が気になるかい?」
「別に」
アゲハはツバメに顔もむけず、一言で、言葉を切ってしまった。
ツバメは息を吐くと、アゲハの前に立ち、
「あんたさ。カンタロウっちの前で、泣いたことある?」
「ないよ。なんで?」
「女の涙は男の心を動かす武器ってことさ。そんな態度だと、カンタロウっち取られちまうよ。女ってのは、女同士で競争しちまうもんなんだからさ」
ツバメはカンタロウとマリアが一緒になるのを応援していない。
組織の一員というモラルもあるが、多少個人的な感情も含まれているのだろう。
当人には伝わっていないが、マリアのことを思って言っているのである。
「これが私のキャラだもん。変えようがないよ。それに、カンタロウ君を取られるって、どういうこと?」
アゲハがツバメを椅子から見上げた。その碧い瞳から、好奇心と、疑問が浮かんでいる。
ツバメはその宝石のような瞳に、吸い込まれそうになり、体を横へむけ、
「言ったとおりだよ。他の女に取られるってこと」
「取る? それって、自分のものにするってこと?」
「まあ、そういうことかな?」
「じゃ、例えるのなら、マリアはカンタロウ君を自分のものにしたいの?」
アゲハに直接そう言われると、うなずくしかない。
「そうだと思うけどね」
ツバメは遠回しに言うことをやめ、はっきりと口にだした。
「違うよ」
「えっ?」
「マリアはカンタロウ君を、自分のものにしたいんじゃない。カンタロウ君が好きなだけだよ。マリアの態度を見てても、おかしい所ないじゃん」
アゲハはきちんと理解していた。
マリアがカンタロウに好意的であることを。
アゲハはマリアに嫉妬したり、羨んだりすることがない。それは、カンタロウを恋愛相手だと見ていないことになる。
「そっ、それはそうなんだけどさ」
ツバメはまじまじとアゲハを見つめ、戸惑った。
アゲハはカンタロウのことを、好きなものだと思っていたからだ。
違っていたという割には、不機嫌な態度から、根拠を集めるのは難しい。
「だったら別にいいじゃん。ツバメの言ってること、意味わかんない」
アゲハは視線を床に落とすと、話すのをやめてしまった。
――う~ん。この子とは、なんだか男女関係の話になると、つじつまが合わないねぇ。
ツバメはどうしていいかわからず、頭を手でかく。
それは仕方のないことだった。
目の前にいる相手が、男女の色恋沙汰とは無縁の種族であることを、知らないのだ。
アゲハの心の中は、他人が思っている以上に葛藤し、本人もどうしていいかわかっていないのだ。
「……ん?」
ツバメが反応した。
細い廊下から、物音が聞こえた。
アゲハの先の尖った耳が、ピクリと動き、
「さっき、何か物音しなかった?」
「ああ、したね。マリアとカンタロウっちかい?」
ツバメも気づいていた。二人して暗い廊下を見つめるが、何もでてこない。
「なんだろ?」
アゲハは立ち上がると、暗い廊下にむかって歩んでいく。音はそれ以上、何も聞こえない。
「気をつけなよ」
ツバメが一応、声をかけた。
「えっ? 何か言っ」
アゲハはツバメの言葉が聞き取れず、後ろをむいた。
金髪の髪が、はらりと落ちていく。
考えるのに時間はかからなかった。
「くっ!」
アゲハは素早く、その場から逃げだした。
「どうしたんだい? アゲハ?」
「ツバメ! 敵だ!」
「へっ?」
たいまつの明かりに、鈍く何かが光った。
錆びた剣だった。
色の剥げ落ちた鎧を着た何者かが、二人の前に立っている。
「くはぁ……」
それは白い息を吐くと、赤い両目を二人にむけた。
白い歯がギシギシと、摩擦する音が聞こえる。
皮膚が腐食しているのか、血の通った色をなしていない。
「両目が赤い! ゴーストエコーズか?」
ツバメは剣を持つと、それにむかって構える。
――違う。エコーズの気配はしなかった。これは……。
アゲハは激しく動揺していた。
この大陸で、その術を使うのは、死刑を覚悟した者のみ。
禁忌とされた術。
「パンドラック・ミクスだ」
アゲハが術の名前を言ったと同時に、それは牙を剥きだして襲いかかってきた。
*
カンタロウとマリアは、長椅子に座っていた。
マリアの嗚咽もやみ、だいぶ落ち着いたようだ。
たいまつの火が、パチパチと静寂な空間に響いている。
壁に二つの影が、寄り添って揺れていた。
「ごめんなさい。だいぶ、落ち着きました」
マリアは両手を膝に置くと、小さく言った。
「そうか。良かった」
カンタロウはその隣で、たいまつの火を見つめている。
「…………」
「…………」
しばらく、二人とも何もしゃべらなかった。
口を最初に開いたのは、マリアで、
「ねえ、カンタロウ様」
「ああ」
「シオンは――死んだのでしょうね」
あの月の氷の映像を見る限りでは、確実にシオンは死んでいる。
試験管の中で、大量に飛び散った血液。
普通の人間であれば、もはや生きてはいない。
「……そう……」
カンタロウはそれだけ言うと、口をつぐんだ。
「そうだな」とは、はっきりと言えなかったのだ。
マリアの表情を見やってみる。
「それでは、仕方ないですね」
マリアはあっさりとしていた。
声に淀みはない。
感情の変化が、急激に変わった。
――仕方、ない?
カンタロウは異様な違和感がした。
妹を失った悲しみが、もうその顔つきからは感じ取れない。
カンタロウの背筋に冷たい何かが、神経を凍らせていく。
「シオンのことは諦めました。あの子もこうなることが、運命だったのでしょう」
――マリア?
「きっと幸せだったと思います。少しでも、女神に近づけたのだから」
――マリア、いったい。
「シオンはいなくなりましたけど、私の気持ちは変わりません。カンタロウ様と一緒にいたいという気持ちです。帰りましょ。あなたの家へ」
――何を、言ってるんだ?
「私、あなたのお母さんとお姉さんに、話したいことがあるんです。だから帰りましょ――私達の家へ」
マリアの瞳が、笑っていた。
涙で濡れた瞳が、紅い唇が、頬の筋肉が、まぎれもなく、カラカラと笑っている。
カンタロウはそこに例えようのない恐怖を感じ、目を見張った。
ゴミを捨ててすっきりしたような、そんなさっぱりとした感覚。
マリアはまだ、カンタロウに告白を続けている。
カンタロウの耳には、何一つ言葉が入ってこなかった。
幼少のとき、目の前に自分がいるのに、見られることもなく、話を続ける大人達と重なった。
「カンタロウ様」
マリアの柔らかい体に触れ、ようやくカンタロウは我に返った。
気づくと、マリアの方から、肩を寄せてきていた。
マリアの匂いが、柔らかな感触が、甘い息遣いが、すべての神経を逆なでし始める。
「私を――受け入れてくれますか?」
マリアが優し気な表情をしながら、顔を近づけてくる。
近くで見た顔つきは、女神のように美しい。
白い髪が闇に輝き、茶色の瞳が炎のように神秘的な灯りを照らす。
「…………」
カンタロウは動けなかった。
拒否することも、拒絶することも。
受け入れることも、自ら動くことも。
これから何をするのか、さすがのカンタロウでもわかっていた。
マリアが何を望んでいるのか、何をしたいのか、すべてわかっていた。
ただ、自分の意志がそこにはない。
意志がないのだから、何もすることができない。
無機質のように、固まる。
「カンタロウ様……私……あっ」
唇が、カンタロウの唇に触れそうになった瞬間、マリアの目が何かに気づいた。
マリアは慌てて顔を離し、
「誰か、いる?」
固まっていたカンタロウの体に、熱い血液が流れだす。
感覚が戻ってきた。
嫌な気配が部屋に充満している。
「誰だ!」
カンタロウは気配の正体の方を見ると、そこには鎧を着、剣を持った男達が四人、幽鬼のように立っていた。
――あの格好は傭兵? なぜこんな所に?
カンタロウは、椅子から立ち上がる。
「あっ、あの人達……」
マリアが男達の顔を見て、目を白黒させた。
カンタロウが刀の柄を手に取り、
「知り合いか?」
「えっ? あっ、いえ。確か、大使徒様が雇った、ハンターだと思います。でも、一ヶ月間、音信不通だったのに……」
マリアが言う。
刹那、男達がゲラゲラと笑いだした。
口は締まりなく開き、ヨダレが垂れている。
赤い両目は充血し、色の悪い頬が一層不気味さを醸しだしていた。
「なんだ? 誰かいると思ったら、顔のいいお兄ちゃんと、美人なお姉ちゃんじゃねぇか。豚がいるよぉ。醜い小鳥がぁ」
「俺の嫁さんと子供よりかは劣るがな。嫉妬だ! 若造が! 俺の嫁に何かするつもりだな!」
「お前の不細工な嫁なんて相手にしねぇよ。二人を殺すのか? 犯すのか? 食べるのか? 刻むのか? 俺が好きなのは、飛んでいくことさ」
「黙れ! ワンワン、ワンワン、ワンワン、ワンワン、俺の耳で鳴くんじゃない! 黙れ! 黙れぇぇぇ! えっ? 何か言った?」
四人の男達は、訳の分からないことを喚きながら、大声で笑い続けた。
閑静だった施設が、喧噪の場に変わっている。
二人は何が起こったのかわからず、動揺を隠せない。
「カンタロウ様、あの人達、両目が……」
マリアが青ざめた。
四人の男達全員の両目が、真っ赤になっていた。
元は違っていたのだろう。
マリアの声が、微妙に引きつっている。
「ああ、赤い。ゴーストエコーズか? お前等、何を言ってるんだ?」
カンタロウが声をかけるが、四人ともまったく答えない。
一人の男が、剣を振り上げた。
「こっ、こここっ、ここおここおこおっ、殺せぇ!」
唾を飛ばしながら、男は戦闘を宣言した。
右頬が赤く光り、文字があらわれる。
赤眼化所持者なら誰でもわかる、神文字だった。
「神文字? そんなっ!」
「エコーズじゃないのか?」
マリアとカンタロウが、あまりのことに、立ちすくんだ。
エコーズは神文字を持てない。
男の右頬にあらわれたのが神文字ならば、それはエコーズではない証。
彼は正真正銘の赤眼化できる人間なのだ。
「いえぇさあぁ!」
「化け物どもがぁ! 正義の鉄槌をくれてやる!」
「金だ! お前達を殺して、嫁と子供を食わすんだぁ!」
ハンター達が、一斉にカンタロウとマリアにむかって襲いかかってきた。
顔はすでに正気を失っており、理性すらなかった。
黒いカビのついた歯が、獣のように獲物にむかって噛みついてくる。
――いったい、何が起こってる?
カンタロウは四人の男達にむかって、目を見開いていた。
研究所の廊下は、植物が窓に張り付いているため、隙間から入り込む薄い光しかない。
白いホコリが、光に反射して空に舞い上がっている。
走る足音が、大きく反響してくる。
手にはたいまつを持っているが、それでも植物の茎や蔓に足を取られそうになった。
「マリア……」
カンタロウはマリアを完全に見失った。
気配を感じるため、走る足を止める。
耳に全神経を集中し、物音を探っていく。
ある部屋から、女の低い声が聞こえてきた。
カンタロウは、その部屋に入った。
部屋の中は木製の机や椅子が、乱雑に置かれてあった。
食器やコップが、地面に投げだされている。
部屋をゆっくりと歩いていると、壊れた椅子のむこう側に、白い髪の少女が見えた。
床には、たいまつが転がっている。
「うっ、ううっ……」
マリアは口を押さえ、部屋の角で嗚咽を漏らしていた。
妹の死を、はっきりと見てしまったのだ。もう、シオンが生還する希望はない。
カンタロウは声をかけようか、どうか、迷ったが、勇気をだして近づくことにした。
この施設にマリアを一人にしておくことが、危険だと思ったからだ。ただ、慰めの言葉は、何一つ思い浮かばない。
「マリア……」
カンタロウが声をかけると、すぐに反応した。ゆっくりと振りむく。
「カンタロウ……様……」
マリアの茶色の瞳から、涙が幾度も流れていく。
それを見たカンタロウは、頭の中が真っ白になり、何も言うことができなかった。
悲しさが伝染し、言葉を失う。
マリアの表情を直視することができず、つい目をそらす。
「おっ……」
唐突に、カンタロウの体に、軽い衝撃が走った。
マリアが抱きついてきたのだ。
カンタロウの背中に、両手の温もりを感じる。
「ごめんなさい……迷惑なのはわかってます……だけど……私……耐えられない」
マリアはカンタロウの胸に顔を埋め、泣き続けた。
カンタロウは少し躊躇したが、マリアを優しく抱きしめた。髪が手に、さらさらと流れていく。
「俺でよかったら――いっぱい泣けばいい」
カンタロウの精一杯の気持ちだった。
*
ツバメとアゲハは、実験室でカンタロウとマリアの帰りを待っていた。
二人を追いかけてもよかったのだが、迷う可能性もあったため、ここはカンタロウを信じて待つしかなかった。
月の氷は完全に故障し、いくらボタンを押しても録画を再生しなかった。
「マリアの奴、大丈夫かね? 心配だなぁ」
ツバメはうろうろと、腕を組んで、室内を歩き回っている。
「大丈夫だよ。カンタロウ君が行ってるし。けっこう女には優しいし」
アゲハは椅子に座り、一見落ち着いているように見えるが、足のゆすりが苛立ちを隠せないでいた。
「そうだねぇ。カンタロウっちって、ちょっと偉そうな所あるけど、何か男っぽくないっていうか、ガツガツいかない所があるからね。マリアみたいなタイプは合うかもね」
「…………」
ツバメが二人の関係について語ると、急にアゲハは黙り込む。
「何か浮かない顔だね。二人の関係が気になるかい?」
「別に」
アゲハはツバメに顔もむけず、一言で、言葉を切ってしまった。
ツバメは息を吐くと、アゲハの前に立ち、
「あんたさ。カンタロウっちの前で、泣いたことある?」
「ないよ。なんで?」
「女の涙は男の心を動かす武器ってことさ。そんな態度だと、カンタロウっち取られちまうよ。女ってのは、女同士で競争しちまうもんなんだからさ」
ツバメはカンタロウとマリアが一緒になるのを応援していない。
組織の一員というモラルもあるが、多少個人的な感情も含まれているのだろう。
当人には伝わっていないが、マリアのことを思って言っているのである。
「これが私のキャラだもん。変えようがないよ。それに、カンタロウ君を取られるって、どういうこと?」
アゲハがツバメを椅子から見上げた。その碧い瞳から、好奇心と、疑問が浮かんでいる。
ツバメはその宝石のような瞳に、吸い込まれそうになり、体を横へむけ、
「言ったとおりだよ。他の女に取られるってこと」
「取る? それって、自分のものにするってこと?」
「まあ、そういうことかな?」
「じゃ、例えるのなら、マリアはカンタロウ君を自分のものにしたいの?」
アゲハに直接そう言われると、うなずくしかない。
「そうだと思うけどね」
ツバメは遠回しに言うことをやめ、はっきりと口にだした。
「違うよ」
「えっ?」
「マリアはカンタロウ君を、自分のものにしたいんじゃない。カンタロウ君が好きなだけだよ。マリアの態度を見てても、おかしい所ないじゃん」
アゲハはきちんと理解していた。
マリアがカンタロウに好意的であることを。
アゲハはマリアに嫉妬したり、羨んだりすることがない。それは、カンタロウを恋愛相手だと見ていないことになる。
「そっ、それはそうなんだけどさ」
ツバメはまじまじとアゲハを見つめ、戸惑った。
アゲハはカンタロウのことを、好きなものだと思っていたからだ。
違っていたという割には、不機嫌な態度から、根拠を集めるのは難しい。
「だったら別にいいじゃん。ツバメの言ってること、意味わかんない」
アゲハは視線を床に落とすと、話すのをやめてしまった。
――う~ん。この子とは、なんだか男女関係の話になると、つじつまが合わないねぇ。
ツバメはどうしていいかわからず、頭を手でかく。
それは仕方のないことだった。
目の前にいる相手が、男女の色恋沙汰とは無縁の種族であることを、知らないのだ。
アゲハの心の中は、他人が思っている以上に葛藤し、本人もどうしていいかわかっていないのだ。
「……ん?」
ツバメが反応した。
細い廊下から、物音が聞こえた。
アゲハの先の尖った耳が、ピクリと動き、
「さっき、何か物音しなかった?」
「ああ、したね。マリアとカンタロウっちかい?」
ツバメも気づいていた。二人して暗い廊下を見つめるが、何もでてこない。
「なんだろ?」
アゲハは立ち上がると、暗い廊下にむかって歩んでいく。音はそれ以上、何も聞こえない。
「気をつけなよ」
ツバメが一応、声をかけた。
「えっ? 何か言っ」
アゲハはツバメの言葉が聞き取れず、後ろをむいた。
金髪の髪が、はらりと落ちていく。
考えるのに時間はかからなかった。
「くっ!」
アゲハは素早く、その場から逃げだした。
「どうしたんだい? アゲハ?」
「ツバメ! 敵だ!」
「へっ?」
たいまつの明かりに、鈍く何かが光った。
錆びた剣だった。
色の剥げ落ちた鎧を着た何者かが、二人の前に立っている。
「くはぁ……」
それは白い息を吐くと、赤い両目を二人にむけた。
白い歯がギシギシと、摩擦する音が聞こえる。
皮膚が腐食しているのか、血の通った色をなしていない。
「両目が赤い! ゴーストエコーズか?」
ツバメは剣を持つと、それにむかって構える。
――違う。エコーズの気配はしなかった。これは……。
アゲハは激しく動揺していた。
この大陸で、その術を使うのは、死刑を覚悟した者のみ。
禁忌とされた術。
「パンドラック・ミクスだ」
アゲハが術の名前を言ったと同時に、それは牙を剥きだして襲いかかってきた。
*
カンタロウとマリアは、長椅子に座っていた。
マリアの嗚咽もやみ、だいぶ落ち着いたようだ。
たいまつの火が、パチパチと静寂な空間に響いている。
壁に二つの影が、寄り添って揺れていた。
「ごめんなさい。だいぶ、落ち着きました」
マリアは両手を膝に置くと、小さく言った。
「そうか。良かった」
カンタロウはその隣で、たいまつの火を見つめている。
「…………」
「…………」
しばらく、二人とも何もしゃべらなかった。
口を最初に開いたのは、マリアで、
「ねえ、カンタロウ様」
「ああ」
「シオンは――死んだのでしょうね」
あの月の氷の映像を見る限りでは、確実にシオンは死んでいる。
試験管の中で、大量に飛び散った血液。
普通の人間であれば、もはや生きてはいない。
「……そう……」
カンタロウはそれだけ言うと、口をつぐんだ。
「そうだな」とは、はっきりと言えなかったのだ。
マリアの表情を見やってみる。
「それでは、仕方ないですね」
マリアはあっさりとしていた。
声に淀みはない。
感情の変化が、急激に変わった。
――仕方、ない?
カンタロウは異様な違和感がした。
妹を失った悲しみが、もうその顔つきからは感じ取れない。
カンタロウの背筋に冷たい何かが、神経を凍らせていく。
「シオンのことは諦めました。あの子もこうなることが、運命だったのでしょう」
――マリア?
「きっと幸せだったと思います。少しでも、女神に近づけたのだから」
――マリア、いったい。
「シオンはいなくなりましたけど、私の気持ちは変わりません。カンタロウ様と一緒にいたいという気持ちです。帰りましょ。あなたの家へ」
――何を、言ってるんだ?
「私、あなたのお母さんとお姉さんに、話したいことがあるんです。だから帰りましょ――私達の家へ」
マリアの瞳が、笑っていた。
涙で濡れた瞳が、紅い唇が、頬の筋肉が、まぎれもなく、カラカラと笑っている。
カンタロウはそこに例えようのない恐怖を感じ、目を見張った。
ゴミを捨ててすっきりしたような、そんなさっぱりとした感覚。
マリアはまだ、カンタロウに告白を続けている。
カンタロウの耳には、何一つ言葉が入ってこなかった。
幼少のとき、目の前に自分がいるのに、見られることもなく、話を続ける大人達と重なった。
「カンタロウ様」
マリアの柔らかい体に触れ、ようやくカンタロウは我に返った。
気づくと、マリアの方から、肩を寄せてきていた。
マリアの匂いが、柔らかな感触が、甘い息遣いが、すべての神経を逆なでし始める。
「私を――受け入れてくれますか?」
マリアが優し気な表情をしながら、顔を近づけてくる。
近くで見た顔つきは、女神のように美しい。
白い髪が闇に輝き、茶色の瞳が炎のように神秘的な灯りを照らす。
「…………」
カンタロウは動けなかった。
拒否することも、拒絶することも。
受け入れることも、自ら動くことも。
これから何をするのか、さすがのカンタロウでもわかっていた。
マリアが何を望んでいるのか、何をしたいのか、すべてわかっていた。
ただ、自分の意志がそこにはない。
意志がないのだから、何もすることができない。
無機質のように、固まる。
「カンタロウ様……私……あっ」
唇が、カンタロウの唇に触れそうになった瞬間、マリアの目が何かに気づいた。
マリアは慌てて顔を離し、
「誰か、いる?」
固まっていたカンタロウの体に、熱い血液が流れだす。
感覚が戻ってきた。
嫌な気配が部屋に充満している。
「誰だ!」
カンタロウは気配の正体の方を見ると、そこには鎧を着、剣を持った男達が四人、幽鬼のように立っていた。
――あの格好は傭兵? なぜこんな所に?
カンタロウは、椅子から立ち上がる。
「あっ、あの人達……」
マリアが男達の顔を見て、目を白黒させた。
カンタロウが刀の柄を手に取り、
「知り合いか?」
「えっ? あっ、いえ。確か、大使徒様が雇った、ハンターだと思います。でも、一ヶ月間、音信不通だったのに……」
マリアが言う。
刹那、男達がゲラゲラと笑いだした。
口は締まりなく開き、ヨダレが垂れている。
赤い両目は充血し、色の悪い頬が一層不気味さを醸しだしていた。
「なんだ? 誰かいると思ったら、顔のいいお兄ちゃんと、美人なお姉ちゃんじゃねぇか。豚がいるよぉ。醜い小鳥がぁ」
「俺の嫁さんと子供よりかは劣るがな。嫉妬だ! 若造が! 俺の嫁に何かするつもりだな!」
「お前の不細工な嫁なんて相手にしねぇよ。二人を殺すのか? 犯すのか? 食べるのか? 刻むのか? 俺が好きなのは、飛んでいくことさ」
「黙れ! ワンワン、ワンワン、ワンワン、ワンワン、俺の耳で鳴くんじゃない! 黙れ! 黙れぇぇぇ! えっ? 何か言った?」
四人の男達は、訳の分からないことを喚きながら、大声で笑い続けた。
閑静だった施設が、喧噪の場に変わっている。
二人は何が起こったのかわからず、動揺を隠せない。
「カンタロウ様、あの人達、両目が……」
マリアが青ざめた。
四人の男達全員の両目が、真っ赤になっていた。
元は違っていたのだろう。
マリアの声が、微妙に引きつっている。
「ああ、赤い。ゴーストエコーズか? お前等、何を言ってるんだ?」
カンタロウが声をかけるが、四人ともまったく答えない。
一人の男が、剣を振り上げた。
「こっ、こここっ、ここおここおこおっ、殺せぇ!」
唾を飛ばしながら、男は戦闘を宣言した。
右頬が赤く光り、文字があらわれる。
赤眼化所持者なら誰でもわかる、神文字だった。
「神文字? そんなっ!」
「エコーズじゃないのか?」
マリアとカンタロウが、あまりのことに、立ちすくんだ。
エコーズは神文字を持てない。
男の右頬にあらわれたのが神文字ならば、それはエコーズではない証。
彼は正真正銘の赤眼化できる人間なのだ。
「いえぇさあぁ!」
「化け物どもがぁ! 正義の鉄槌をくれてやる!」
「金だ! お前達を殺して、嫁と子供を食わすんだぁ!」
ハンター達が、一斉にカンタロウとマリアにむかって襲いかかってきた。
顔はすでに正気を失っており、理性すらなかった。
黒いカビのついた歯が、獣のように獲物にむかって噛みついてくる。
――いったい、何が起こってる?
カンタロウは四人の男達にむかって、目を見開いていた。