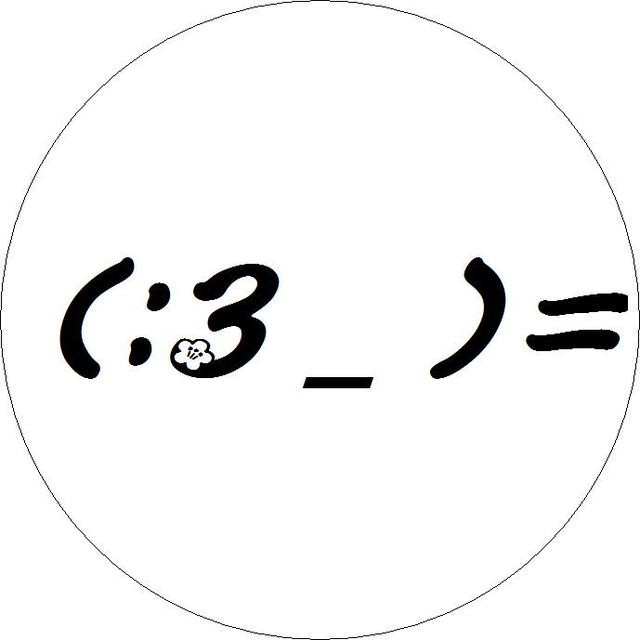ツネミツの真実
文字数 5,481文字
「なんだと? どういうことだ? ツツジはどこに行った?」
ツネミツは布になった姫に、目を丸くしている。
「もしも、無知が故意の場合は犯罪だが、これでもまだわかんねぇようだな」
カッコウが動揺するツネミツにむかって、目を細めた。
カンタロウはツネミツの言動を、注意深く聞いていた。ある一点に違和感を覚えた。
――この男、一兵卒のわりにはやけに……。
口を開きかけるカンタロウ。
「気安いな。クハッ、自分が守るべき姫様を呼び捨てか?」
カンタロウの疑問点を、カッコウが言ってしまった。
タイミングがよかったため、カンタロウはギョッとして、カッコウの方へ振りむく。
カッコウは特にカンタロウを意識して、しゃべったつもりはないようだ。
「……っ!」
ツネミツは的を当てられ、言葉がつまった。図星だ。
ツネミツとツツジは、兵士と王族の身分を越える関係なのだ。
「まあそうだよな。この城が落ちる前、お前とツツジって姫様は、親密な仲だったもんな。――身分違いの許されざる恋ってやつだ」
カッコウはどこから知ったのか、ツネミツの過去に詳しい。
ツネミツの血の上った頭が、急速に引き、青ざめ始めている。
「ちっ、ちが……」
「違わないね。お前のことはよく調べさせてもらった。逢瀬を重ね、姫様は身ごもっちまったんだろ? お前は焦ったはずだ。このことが知れれば、処刑は確実。そこでお前は、どんどん狂った方向にいってしまった」
「おっ、俺は……」
刀を落とし、頭を抱えるツネミツ。
楽しむかのように、カッコウはニヤニヤ笑っている。
「何をしたの?」
ツネミツの変わりに、アゲハが先をうながした。
「姫の暗殺だよ。ちょうど剣帝国が、この国を襲ってきた。お前はチャンスだと思ったはずだ。その状況を利用して――姫様を殺した。まっ、国が落ちるとは、予想外だったようだがな」
カッコウがナイフを使って、突き刺す仕草をする。
「違う……」
頭を抱えたツネミツの声は、消え入りそうなぐらい小さい。
カッコウの言うことが正しいのなら、違和感がでてくる。
今神獣を操り、月の魔都を発動させたのは誰なのか?
カンタロウとアゲハは、お互いこの点に気づいていた。
「となるとおかしいな。この城にいるゴーストエコーズは、誰になるんだろうな?」
カッコウの赤い両目に、ツネミツが映る。
「……まさか」
アゲハがツネミツの顔を、凝視した。
「違う……違う……違う」
ツネミツの両目が、黒から赤に変色していた。
目の中から、白い液体が流れていく。
神獣が、ツネミツの目に入り、瞳の色を誤魔化していたのだ。目から頬を伝わるその白い液体は、まるで涙のようだった。
「お前が……」
「ゴーストエコーズだったの……」
カンタロウとアゲハは意表をつかれ、言葉を失った。
ツネミツは神獣だと思っていた。
神獣に擬態する、ゴーストエコーズだとは考えてもいなかった。
「違う……あの女が言ったんだ。俺に、言ってくれたんだ」
ツネミツの知りたくもない過去が、頭の脳を活性化させる。
十六年前、白いマリアベールをかぶった女が、自分の耳元で囁いた。
ツツジ姫がいたはずだ。
姫は霧のように薄く、呼吸音も、体温も感じない。
『自分が傷つくだけの世界なら――逃げてしまえばいい。それにお前は、良いことをした』
女はそう言った。
ツネミツはツツジに手を伸ばした。
手が身体に触れたとき、ツツジの身体は透明になり、腕がすり抜けてしまった。
ツネミツの両手は、真っ赤に染まっており、その血はとても新鮮で、畳に赤いシミを作っていた。
自分の腕に、痛みはなかった。
女はツネミツの頬を、白い手で優しくなでると、紫の唇で、小声でそっと囁く。
ツツジはもうそこに、いなかった。
「死は、なくなる怖さじゃない。――永遠になれる、喜びなのだと」
ツネミツはゆっくりと立ち上がった。
見開かれた両目は、流れる血よりも深紅。
頬に伝わる涙は、鮮血だった。
カンタロウとアゲハは、呆然と立ち尽くした。
「ぐっ!?」
突然、ツネミツの胸が裂けた。
心臓の部分から、槍の穂先が見える。
ツネミツの後ろには、槍を持ったマリアがいた。
「神の敵。――死になさい」
マリアの顔に、表情はない。
躊躇いも、興奮も、哀れみですら、表情にでていない。
人が毒虫を容赦なく殺すような、そんな目をしていた。
「ぐはっ!」
ツネミツは赤い血を吐くと、その場に倒れた。
胸から大量の血が流れている。止まる気配がない。
マリアはツネミツに、見下すような目つきをむけていた。
助けたいという気持ちすら、起こっていない。
マリアの中では、ツネミツは人ではなく、害虫なのだ。
「……マリア」
カンタロウは一瞬、マリアの目に恐怖した。
自分が受けてきた他者の扱いに、とても似ていたからだ。
蟻達が蝶の幼虫に群がり、攻撃しているような、強者が弱者にむける視線。卑しめ、蔑み、薄笑いした目。
「がはっ……。ぐっ……ツツジ……」
ツネミツは畳をつかみ、ゆっくりとツツジがいた場所に這っていく。
ツツジに化けていた神獣は、すでに結界に吸収されていた。
「ツツジ……俺は……俺……は……」
ツツジが着ていた女房装束を手につかむと、ツネミツの顔から、苦痛が消えた。
うつ伏せに倒れ、赤い両目は開いたままだった。
ツネミツは、事切れていた。
「クハッ、あらら。死んじまったか。まっ、いいか。神獣すらうまく使えず、自分がゴーストエコーズだと、気づきもしない欠陥品だ。捨て駒としては役に立ったが……おう?」
カッコウの喉元に、切っ先がむけられている。
剣身には、アゲハの姿が映っていて、
「あなた。詳しいよね。この城のことについて。それに、偶然しては、タイミングよく、私達の前にあらわれたよね?」
「そりゃそうだ。お前達に、この仕事を紹介したのは、俺だからな。実力が見たくて試験したのさ」
リア・チャイルドマンに仕事を依頼し、カンタロウに紹介させたのは、カッコウの仕業だった。
カンタロウはそれを初めて知り、不可解な顔をし、
「なぜそんなことを? わざわざ俺に?」
「お前のことは調べたぜ。ゴーストエコーズをかなりの数、倒しているようだな。例えば――カインとかな」
カッコウが言う名前。
カイン。精神病院で会ったカンタロウの親友。今は大地に眠っている。
ふいにでた親友の名前に、カンタロウは目を白黒させる。
その反応を、マリアは見逃さなかったが、我慢して口を閉ざした。
「カインのことを知っているのか?」
「ああ。スカウトしようと思ってたんだ。まっ、行ってみたら死んでたがな。そこでお前達のことを知った。赤眼化もできるようだし、今度の仕事に使えるかと思ったが、残念だ。クハハッ」
「何の仕事なんだ?」
「さぁてねぇ。まっ、世界が覆る――とでも言っとこうか」
カッコウはふざけた顔で、カンタロウから答えをはぐらかした。
無視されていたアゲハは、剣をさらに突きだし、
「へえ。で、私はどう? 合格?」
「言ったろう。不合格だ。お前は見込みがありそうだが、駄目だな。まるで点数が足りねぇ」
「あっ、そう。じゃ、力づくで合格にしてもらおうかなっ!」
剣がカッコウの肩にむかって、突いてくる。
カッコウはそれをジャンプでかわし、城の天井に張りついた。
「なっ!」
あまりの速さに、呆気にとられるアゲハ。
「クハッ! 合格したけりゃ、大金持ってくるんだなっ!」
カッコウの口から、透明な唾液が垂れる。赤い舌が、小馬鹿にするようにだされていた。
「このっ!」
天井にむかって、アゲハは剣を振り上げた。
「まっ、お前の体でもいいぜぇ」
カッコウはすでに、天井から消えていた。
アゲハは声がどこからするのか、一時わからなかった。
アゲハの頬が、ベロリと舐められ、
「ひっ?」
ザラザラとした感触。悪寒を誘う唾液。すべてが嫌悪。
アゲハは急いで、唾液のついた頬を、腕で拭った。
「いい味だ。じゃな、お嬢ちゃん」
カッコウは素早く窓まで走ると、ぴょんと外に飛びだしていった。
「こっ、このっ! よくもっ!」
アゲハは頬を汚された怒りで赤眼化し、水神の魔法で、カッコウが逃げた窓を破壊した。
躍起になって外に飛びだす。
「アゲハさん!」
「大丈夫だ。アゲハなら心配ない。あの男には、逃げられるだろう……けどな」
マリアのそばで、カンタロウの足がふらついた。その場に倒れる。
「えっ? カンタロウさん!」
マリアが慌てて、カンタロウのそばにかけ寄る。
額に手を当ててみるが、高熱が原因ではない。
身体を調べてみても、怪我はなかった。
「どうした! 何があった!」
ランマルがようやく、最上階まで上がってきた。
途中で体力が尽きたため、マリアを先に行かせていたようだ。
日頃体力をつけていないためか、ゼイゼイ息をしている。
「カンタロウさん! カンタロウさんがっ!」
「しっかりしろカンタロウ! 何があった?」
ランマルがカンタロウの体を軽く叩き、耳近くで名前を呼んでみる。
マリアは両手を強く握りしめ、カンタロウの様子を見守っていた。
「は……は……」
仰向けになったカンタロウは、かすれた声で、何かを言っている。
手をプルプル震わせ、何かをつかもうとしているようだ。
いったいそれが何を意味するのか、ランマルはまだわからない。
「『は』? 『は』って何だ?」
ランマルは耳を、カンタロウの口に近づけた。
「――母よ」
小さくそう言うと、カンタロウは白目を剥き、気絶した。
「持病が悪化しただけかっ! 心配させやがって。こいつは……ほんとに」
ランマルがキレる。
単にホームシックが悪化し、母が恋しいあまり、現実逃避しただけだった。
「えっ? 持病って?」
マリアはまだ、カンタロウの持病の内容を知らないので、意味がわからず首を傾げる。
ランマルはふと、カンタロウの右手の甲に目がいった。
赤眼化を解除したばかりのためか、薄く国章血印があらわれていた。
「うん? 国章血印? これは、『夜刀』か」
角のある蛇。
カンタロウの父、コウタロウの右手の甲に刻まれていたもの。
前国王時代の剣帝国の国章。
「まだ持っていたんだな。――すべてが夢のように、懐かしいもんだ」
ランマルは白い歯をだして、笑った。
*
アゲハは城をでて、静かになった城下町を走り、カッコウを追って森に入った。
カッコウの姿は、すでにそこにはなかった。
癖のある笑いが響いてくる。
「くそっ! せっかくの情報を……」
アゲハは怒りで、骨のような木の幹を、拳で叩く。
幹にヒビが入り、木は地面に倒れていった。
人の骸骨のようなもろさだった。
*
魔帝国、城内。
城の最上階から一階下にある浴室に、女王エメルダが入ってきた。
浴室には絵や鏡が飾られており、壁は防水処理がされたタイル張りとなっていた。
上げ下げ窓から、明るい太陽の日差しが入ってくる。
外では体格のよいガードナーが、見習いに庭園管理の指導をしていた。
エメルダは服を脱ぐと、乳白色の水に、赤いバラが浮かべられた浴槽に、白い素肌を浸す。
ブルーの長い髪を使用人の女に櫛でとかせ、長く、細い素足を浴槽からだした。
冷えた体温が暖まるまで、エメルダはバラの花びらを手で弄ぶ。
「エメルダ様」
側近であるエルフの女が、浴室のドアをノックした。
心地よい時間を邪魔したのだ。よほどの事態が発生したのだろう。
エメルダは髪をとかしている女に、チラリと視線をむけた。
使用人の女は、何も言わず、浴室からでていった。
エメルダは髪を一振りし、
「どうした?」
「申し訳ありません。緊急のお知らせがございます。ムー殿がお亡くなりになりました」
第二級ハンター、ムー。
釣瓶の国を手に入れるために、送り込んだハンターだ。
そういえばもう、二十日はたっただろうか。
エメルダは死因を知りたくなり、
「ほう? どのような、死に方をしたのだ?」
「仲間を見捨て、神獣から逃げたようですが、結局体を串刺しにされ、捨てられておりました」
凄惨な死に方。
言葉からも、その残酷さがよくわかる。
金銭主義のムーはろくな死に方をしないだろうと思っていたため、エメルダは特に驚かなかった。
「なるほどな。あの男らしい死に方だ。それで、勝者はどっちだ?」
「剣帝国です」
側近の女の言葉に、エメルダの息がつまった。
予想では、豊富な資金を持つ、賢帝国だろうと思っていたからだ。
金欠で、優秀なハンターすら雇えない、剣帝国が勝利するとは思っていなかった。
――ほう。優秀なハンターを、そんなに早く準備していたのか? まさか……な。
エメルダは水を口まで浸し、考えてみるが、こちらから情報が漏れていたということは有り得ない。
何よりも、あまりにも行動が速すぎる。
偶然にしては怪しい。
「剣帝国の軍は、動いていまいな?」
「はい。間違いなくハンターです。ハンターギルドには所属していない者達なので、詳細は不明ですが。リア・チャイルドマンという有名な金貸しが雇ったハンターのようです」
側近の女の高揚のない声。
剣帝国で有名であるのなら、その豊富な人脈を利用して、強いハンターを雇ったのかもしれない。
釣瓶の国の領土を失った。
賭けの言いだしっぺが、今更取り消すことなどできないのだから。
「そうか。もうよい」
「はっ、失礼しました」
側近の女の気配が消える。
エメルダは細い足を組むと、天井を見上げ、
「さて、次はどのような退屈しのぎをしようか。人生は、長いのだから」
エメルダの顔に、悲壮感はなかった。
ツネミツは布になった姫に、目を丸くしている。
「もしも、無知が故意の場合は犯罪だが、これでもまだわかんねぇようだな」
カッコウが動揺するツネミツにむかって、目を細めた。
カンタロウはツネミツの言動を、注意深く聞いていた。ある一点に違和感を覚えた。
――この男、一兵卒のわりにはやけに……。
口を開きかけるカンタロウ。
「気安いな。クハッ、自分が守るべき姫様を呼び捨てか?」
カンタロウの疑問点を、カッコウが言ってしまった。
タイミングがよかったため、カンタロウはギョッとして、カッコウの方へ振りむく。
カッコウは特にカンタロウを意識して、しゃべったつもりはないようだ。
「……っ!」
ツネミツは的を当てられ、言葉がつまった。図星だ。
ツネミツとツツジは、兵士と王族の身分を越える関係なのだ。
「まあそうだよな。この城が落ちる前、お前とツツジって姫様は、親密な仲だったもんな。――身分違いの許されざる恋ってやつだ」
カッコウはどこから知ったのか、ツネミツの過去に詳しい。
ツネミツの血の上った頭が、急速に引き、青ざめ始めている。
「ちっ、ちが……」
「違わないね。お前のことはよく調べさせてもらった。逢瀬を重ね、姫様は身ごもっちまったんだろ? お前は焦ったはずだ。このことが知れれば、処刑は確実。そこでお前は、どんどん狂った方向にいってしまった」
「おっ、俺は……」
刀を落とし、頭を抱えるツネミツ。
楽しむかのように、カッコウはニヤニヤ笑っている。
「何をしたの?」
ツネミツの変わりに、アゲハが先をうながした。
「姫の暗殺だよ。ちょうど剣帝国が、この国を襲ってきた。お前はチャンスだと思ったはずだ。その状況を利用して――姫様を殺した。まっ、国が落ちるとは、予想外だったようだがな」
カッコウがナイフを使って、突き刺す仕草をする。
「違う……」
頭を抱えたツネミツの声は、消え入りそうなぐらい小さい。
カッコウの言うことが正しいのなら、違和感がでてくる。
今神獣を操り、月の魔都を発動させたのは誰なのか?
カンタロウとアゲハは、お互いこの点に気づいていた。
「となるとおかしいな。この城にいるゴーストエコーズは、誰になるんだろうな?」
カッコウの赤い両目に、ツネミツが映る。
「……まさか」
アゲハがツネミツの顔を、凝視した。
「違う……違う……違う」
ツネミツの両目が、黒から赤に変色していた。
目の中から、白い液体が流れていく。
神獣が、ツネミツの目に入り、瞳の色を誤魔化していたのだ。目から頬を伝わるその白い液体は、まるで涙のようだった。
「お前が……」
「ゴーストエコーズだったの……」
カンタロウとアゲハは意表をつかれ、言葉を失った。
ツネミツは神獣だと思っていた。
神獣に擬態する、ゴーストエコーズだとは考えてもいなかった。
「違う……あの女が言ったんだ。俺に、言ってくれたんだ」
ツネミツの知りたくもない過去が、頭の脳を活性化させる。
十六年前、白いマリアベールをかぶった女が、自分の耳元で囁いた。
ツツジ姫がいたはずだ。
姫は霧のように薄く、呼吸音も、体温も感じない。
『自分が傷つくだけの世界なら――逃げてしまえばいい。それにお前は、良いことをした』
女はそう言った。
ツネミツはツツジに手を伸ばした。
手が身体に触れたとき、ツツジの身体は透明になり、腕がすり抜けてしまった。
ツネミツの両手は、真っ赤に染まっており、その血はとても新鮮で、畳に赤いシミを作っていた。
自分の腕に、痛みはなかった。
女はツネミツの頬を、白い手で優しくなでると、紫の唇で、小声でそっと囁く。
ツツジはもうそこに、いなかった。
「死は、なくなる怖さじゃない。――永遠になれる、喜びなのだと」
ツネミツはゆっくりと立ち上がった。
見開かれた両目は、流れる血よりも深紅。
頬に伝わる涙は、鮮血だった。
カンタロウとアゲハは、呆然と立ち尽くした。
「ぐっ!?」
突然、ツネミツの胸が裂けた。
心臓の部分から、槍の穂先が見える。
ツネミツの後ろには、槍を持ったマリアがいた。
「神の敵。――死になさい」
マリアの顔に、表情はない。
躊躇いも、興奮も、哀れみですら、表情にでていない。
人が毒虫を容赦なく殺すような、そんな目をしていた。
「ぐはっ!」
ツネミツは赤い血を吐くと、その場に倒れた。
胸から大量の血が流れている。止まる気配がない。
マリアはツネミツに、見下すような目つきをむけていた。
助けたいという気持ちすら、起こっていない。
マリアの中では、ツネミツは人ではなく、害虫なのだ。
「……マリア」
カンタロウは一瞬、マリアの目に恐怖した。
自分が受けてきた他者の扱いに、とても似ていたからだ。
蟻達が蝶の幼虫に群がり、攻撃しているような、強者が弱者にむける視線。卑しめ、蔑み、薄笑いした目。
「がはっ……。ぐっ……ツツジ……」
ツネミツは畳をつかみ、ゆっくりとツツジがいた場所に這っていく。
ツツジに化けていた神獣は、すでに結界に吸収されていた。
「ツツジ……俺は……俺……は……」
ツツジが着ていた女房装束を手につかむと、ツネミツの顔から、苦痛が消えた。
うつ伏せに倒れ、赤い両目は開いたままだった。
ツネミツは、事切れていた。
「クハッ、あらら。死んじまったか。まっ、いいか。神獣すらうまく使えず、自分がゴーストエコーズだと、気づきもしない欠陥品だ。捨て駒としては役に立ったが……おう?」
カッコウの喉元に、切っ先がむけられている。
剣身には、アゲハの姿が映っていて、
「あなた。詳しいよね。この城のことについて。それに、偶然しては、タイミングよく、私達の前にあらわれたよね?」
「そりゃそうだ。お前達に、この仕事を紹介したのは、俺だからな。実力が見たくて試験したのさ」
リア・チャイルドマンに仕事を依頼し、カンタロウに紹介させたのは、カッコウの仕業だった。
カンタロウはそれを初めて知り、不可解な顔をし、
「なぜそんなことを? わざわざ俺に?」
「お前のことは調べたぜ。ゴーストエコーズをかなりの数、倒しているようだな。例えば――カインとかな」
カッコウが言う名前。
カイン。精神病院で会ったカンタロウの親友。今は大地に眠っている。
ふいにでた親友の名前に、カンタロウは目を白黒させる。
その反応を、マリアは見逃さなかったが、我慢して口を閉ざした。
「カインのことを知っているのか?」
「ああ。スカウトしようと思ってたんだ。まっ、行ってみたら死んでたがな。そこでお前達のことを知った。赤眼化もできるようだし、今度の仕事に使えるかと思ったが、残念だ。クハハッ」
「何の仕事なんだ?」
「さぁてねぇ。まっ、世界が覆る――とでも言っとこうか」
カッコウはふざけた顔で、カンタロウから答えをはぐらかした。
無視されていたアゲハは、剣をさらに突きだし、
「へえ。で、私はどう? 合格?」
「言ったろう。不合格だ。お前は見込みがありそうだが、駄目だな。まるで点数が足りねぇ」
「あっ、そう。じゃ、力づくで合格にしてもらおうかなっ!」
剣がカッコウの肩にむかって、突いてくる。
カッコウはそれをジャンプでかわし、城の天井に張りついた。
「なっ!」
あまりの速さに、呆気にとられるアゲハ。
「クハッ! 合格したけりゃ、大金持ってくるんだなっ!」
カッコウの口から、透明な唾液が垂れる。赤い舌が、小馬鹿にするようにだされていた。
「このっ!」
天井にむかって、アゲハは剣を振り上げた。
「まっ、お前の体でもいいぜぇ」
カッコウはすでに、天井から消えていた。
アゲハは声がどこからするのか、一時わからなかった。
アゲハの頬が、ベロリと舐められ、
「ひっ?」
ザラザラとした感触。悪寒を誘う唾液。すべてが嫌悪。
アゲハは急いで、唾液のついた頬を、腕で拭った。
「いい味だ。じゃな、お嬢ちゃん」
カッコウは素早く窓まで走ると、ぴょんと外に飛びだしていった。
「こっ、このっ! よくもっ!」
アゲハは頬を汚された怒りで赤眼化し、水神の魔法で、カッコウが逃げた窓を破壊した。
躍起になって外に飛びだす。
「アゲハさん!」
「大丈夫だ。アゲハなら心配ない。あの男には、逃げられるだろう……けどな」
マリアのそばで、カンタロウの足がふらついた。その場に倒れる。
「えっ? カンタロウさん!」
マリアが慌てて、カンタロウのそばにかけ寄る。
額に手を当ててみるが、高熱が原因ではない。
身体を調べてみても、怪我はなかった。
「どうした! 何があった!」
ランマルがようやく、最上階まで上がってきた。
途中で体力が尽きたため、マリアを先に行かせていたようだ。
日頃体力をつけていないためか、ゼイゼイ息をしている。
「カンタロウさん! カンタロウさんがっ!」
「しっかりしろカンタロウ! 何があった?」
ランマルがカンタロウの体を軽く叩き、耳近くで名前を呼んでみる。
マリアは両手を強く握りしめ、カンタロウの様子を見守っていた。
「は……は……」
仰向けになったカンタロウは、かすれた声で、何かを言っている。
手をプルプル震わせ、何かをつかもうとしているようだ。
いったいそれが何を意味するのか、ランマルはまだわからない。
「『は』? 『は』って何だ?」
ランマルは耳を、カンタロウの口に近づけた。
「――母よ」
小さくそう言うと、カンタロウは白目を剥き、気絶した。
「持病が悪化しただけかっ! 心配させやがって。こいつは……ほんとに」
ランマルがキレる。
単にホームシックが悪化し、母が恋しいあまり、現実逃避しただけだった。
「えっ? 持病って?」
マリアはまだ、カンタロウの持病の内容を知らないので、意味がわからず首を傾げる。
ランマルはふと、カンタロウの右手の甲に目がいった。
赤眼化を解除したばかりのためか、薄く国章血印があらわれていた。
「うん? 国章血印? これは、『夜刀』か」
角のある蛇。
カンタロウの父、コウタロウの右手の甲に刻まれていたもの。
前国王時代の剣帝国の国章。
「まだ持っていたんだな。――すべてが夢のように、懐かしいもんだ」
ランマルは白い歯をだして、笑った。
*
アゲハは城をでて、静かになった城下町を走り、カッコウを追って森に入った。
カッコウの姿は、すでにそこにはなかった。
癖のある笑いが響いてくる。
「くそっ! せっかくの情報を……」
アゲハは怒りで、骨のような木の幹を、拳で叩く。
幹にヒビが入り、木は地面に倒れていった。
人の骸骨のようなもろさだった。
*
魔帝国、城内。
城の最上階から一階下にある浴室に、女王エメルダが入ってきた。
浴室には絵や鏡が飾られており、壁は防水処理がされたタイル張りとなっていた。
上げ下げ窓から、明るい太陽の日差しが入ってくる。
外では体格のよいガードナーが、見習いに庭園管理の指導をしていた。
エメルダは服を脱ぐと、乳白色の水に、赤いバラが浮かべられた浴槽に、白い素肌を浸す。
ブルーの長い髪を使用人の女に櫛でとかせ、長く、細い素足を浴槽からだした。
冷えた体温が暖まるまで、エメルダはバラの花びらを手で弄ぶ。
「エメルダ様」
側近であるエルフの女が、浴室のドアをノックした。
心地よい時間を邪魔したのだ。よほどの事態が発生したのだろう。
エメルダは髪をとかしている女に、チラリと視線をむけた。
使用人の女は、何も言わず、浴室からでていった。
エメルダは髪を一振りし、
「どうした?」
「申し訳ありません。緊急のお知らせがございます。ムー殿がお亡くなりになりました」
第二級ハンター、ムー。
釣瓶の国を手に入れるために、送り込んだハンターだ。
そういえばもう、二十日はたっただろうか。
エメルダは死因を知りたくなり、
「ほう? どのような、死に方をしたのだ?」
「仲間を見捨て、神獣から逃げたようですが、結局体を串刺しにされ、捨てられておりました」
凄惨な死に方。
言葉からも、その残酷さがよくわかる。
金銭主義のムーはろくな死に方をしないだろうと思っていたため、エメルダは特に驚かなかった。
「なるほどな。あの男らしい死に方だ。それで、勝者はどっちだ?」
「剣帝国です」
側近の女の言葉に、エメルダの息がつまった。
予想では、豊富な資金を持つ、賢帝国だろうと思っていたからだ。
金欠で、優秀なハンターすら雇えない、剣帝国が勝利するとは思っていなかった。
――ほう。優秀なハンターを、そんなに早く準備していたのか? まさか……な。
エメルダは水を口まで浸し、考えてみるが、こちらから情報が漏れていたということは有り得ない。
何よりも、あまりにも行動が速すぎる。
偶然にしては怪しい。
「剣帝国の軍は、動いていまいな?」
「はい。間違いなくハンターです。ハンターギルドには所属していない者達なので、詳細は不明ですが。リア・チャイルドマンという有名な金貸しが雇ったハンターのようです」
側近の女の高揚のない声。
剣帝国で有名であるのなら、その豊富な人脈を利用して、強いハンターを雇ったのかもしれない。
釣瓶の国の領土を失った。
賭けの言いだしっぺが、今更取り消すことなどできないのだから。
「そうか。もうよい」
「はっ、失礼しました」
側近の女の気配が消える。
エメルダは細い足を組むと、天井を見上げ、
「さて、次はどのような退屈しのぎをしようか。人生は、長いのだから」
エメルダの顔に、悲壮感はなかった。