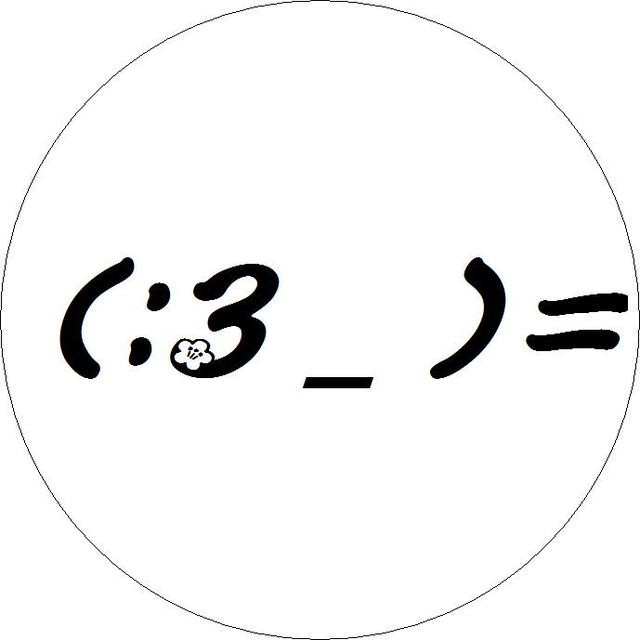朝食の出来事
文字数 5,076文字
*
朝。
カンタロウ、アゲハ、スズは、朝食を食べるために、囲炉裏の間に集まっていた。
マリアとヒナゲシは、料理を作るために台所で作業をしている。
しばらく待っていると、マリアが料理を持ってきた。
「カンタロウ様。今日の朝ご飯、私が作ってみたんです。お口に合うかどうか、自信はないんですけど……」
マリアはみんなの前に、朝食を置いた。
卵やスープを使った料理だ。
良い香りが、部屋に充満する。
「そうなのか? おいしそうだ」
カンタロウは素直に、そう感想を言った。
マリアは皆に料理を配り終えると、カンタロウのすぐ隣に座った。
カンタロウの反対側には、アゲハが陣取っている。
ヒナゲシが座ったことで、食事が開始された。
「はい、カンタロウ様」
マリアは自分の箸で料理を取ると、手を添え、カンタロウに差しだした。
「どっ、どうしたんだ?」
マリアの行動に、カンタロウは少し驚いた。
「食べさせてあげます。嫌、ですか?」
「ああ、そうなのか。それならいただくよ」
マリアが料理を作ったのは、自分に食べさせたかったのだと、カンタロウは察し、素直にそれを受けることにした。
「はい、あ~ん」
マリアは恐ろしく丁寧だ。
多少恥ずかしさはあるものの、カンタロウはマリアから差しだされた料理を口にふくみ、
「うん、おいしいよ」
ヒナゲシが作る料理とは、また違った味だ。
不味くなく、むしろうまい。
マリアの特技が料理だったと、初めて知る。
「ほんとですか? 嬉しい」
マリアは頬を赤らめて喜んだ。
「マリアさん。一生懸命作ったものね。私の出番なくなっちゃいそう」
ヒナゲシは、マリアの料理のうまさを認めていた。
スズが、何気にうなずいている。
「あっ、ごめんなさい。勝手に台所使わせてもらって……」
マリアは遠慮がちに、ヒナゲシに言った。
「いいのよ。気にしないで。それよりどう? カンタロウさん」
「うん。マリアの手料理はおいしいよ」
「そうじゃなくて。マリアさんのこと」
ヒナゲシの言葉の意味がわかり、マリアは真剣な目つきで、カンタロウを見つめた。恥ずかしさで濡れた茶色の瞳が、カンタロウの表情を映す。
「うん? マリアのことがどうかしたのか?」
カンタロウはモグモグと、食事を進めていた。その顔に、マリアやヒナゲシが期待した感情は見えない。
マリアは小さく、ため息をついた。
――さすがカンタロウ。鈍い。
スズは食事を進めながら、カンタロウの女性に対する恋愛音痴を嘆いた。
「もう! カンタロウさんたら!」
ヒナゲシはカンタロウの無反応さに、子供のように頬をむくれさせた。
カンタロウはなぜ母に怒られているのか、理由がわからず首を傾げるばかりだった。
「じゃ、今度は私だな。はい、あ~ん」
アゲハが料理を箸で取ると、マリアと同じように、カンタロウに差しだす。
マリアがどうしてそんなことをしているのか、アゲハなりに知りたいようだ。それで行動を真似しているのである。
「アゲハは何も作ってないだろ?」
「いいじゃん。はい、あ~ん」
食べないと終わりそうにないので、カンタロウは仕方なく料理を口にふくみ、
「うん、うまい」
「そうだろ?」
アゲハは満足気に微笑んだ。
「いや、マリアの料理がだ」
「いやいや、私が料理を運んだから、うまいんだ」
「なんなんだ? それは?」
「そういうことだよ。カンタロウ君」
何か嬉しいものを感じたのか、アゲハはニコニコ笑っている。
「じゃ、次は私ですね。はい、カンタロウ様」
マリアが再び、箸で料理を取り、カンタロウに差しだす。
「待って。まだ私がやるから」
アゲハは髪をかき上げると、箸で料理をつまもうとする。
「順番ですよ。アゲハさん」
「そんなの決まってないじゃん」
「アゲハさん、料理――作ってないですよね?」
「ぐっ……」
マリアは痛い所をつき、アゲハを圧倒した。満面な笑顔が、より一層不気味さを増している。
アゲハはマリアの威圧感に負け、箸を置いた。
――アゲハの扱い方、わかってきたな。
と、カンタロウは思った。
マリアとアゲハの距離が、次第に近づきつつある。
アゲハの方からちょっかいをだすことが多いが、マリアはその対処方法を学びつつあるのだ。
カンタロウはそれが何となく嬉しくなり、顔にはださないが心地良かった。
「うむ。なぜかドロドロしてますね」
「ほんとね。ちょっと羨ましいわ。はい、スズ、あ~んして」
ヒナゲシは料理を箸で持つと、スズに差しだした。
「えっ? ヒナゲシ様?」
「いいから、あ~ん」
「はっ、はい! いただきます! あっ、あ~ん」
スズは大きく口を開け、ヒナゲシから料理をもらった。
「おいしい?」
「当然です!」
スズはあまりのおいしさに、涙ぐんだ。
*
アゲハは食事を終えると、散歩をするため外にでていった。
有刺鉄線の柵を越えるため、入り口にいる兵士に挨拶をする。
最近兵士は、アゲハに慣れてきたのか、声にはださないが、会釈をするようになってきた。
今回、コオロギとの待ち合わせ場所は、巨大なブナの木だ。
幹や枝は大きく、根っこは地面からはみだし、巨大な樹を支えている。
根っこに腰を下ろし、黒いフードをかぶった男が一人、座っていた。
腕には神獣で作った、赤い鳥を乗せているので、間違いなくコオロギだ。
アゲハはいつもの挨拶をせず、コオロギのそばに立った。
コオロギはアゲハの感情の揺らぎに気づき、赤い目で見上げ、
「どうしたんだい? 今日は不機嫌だね」
「別に」
「それならいいけど……」
それからしばらく、二人は何も話さなかった。
岩の影から、おこじょのような動物が、二人を眺めている。
顔は茶色く、腹は白く、長い体は人の腕ほどしかない。
つぶらな黒い瞳が、パチパチと動いた。
「……ねえ。コオロギってさ。いつもどこにいるの?」
アゲハの方から、口を開いた。
「森だよ。この大陸では、町に入れないからね」
エコーズは結界の中に入れない。それはコオロギとて、例外ではない。
「私が呼んだら、すぐに来てくれるよね? この近くの森に住んでいるの?」
アゲハは赤い鳥を呼び、自分の腕に乗せた。
「今はね。でもアゲハが遠くに行ってしまったら、来るのも遅くなる」
「へえ。私の後を、ついてきてるわけじゃないんだ?」
「それは危険だからしない。町や都市、今では村でさえ吸収式神脈装置があるからね。エコーズだと、バレてはまずいんだ」
「そっか。でも、もし私が死んだらどうするの? いつも監視してないんじゃ、気づかないんじゃないの?」
「月に一回。僕は神獣をアゲハに送ってるよ。前に初めて会ったときも、この青い鳥をアゲハに送ったろ? それで返事がなければ、君がどうなったか、調査することになってる」
コオロギはアゲハに、神獣で作った青い鳥を見せた。
「えっ? そうだったんだ? 初めに説明しといてよ」
アゲハにとって、それは初耳だった。
「あれ? 旅立つ前に、仲間から聞かなかったの?」
コオロギは知っているものだと思っており、あえて説明はしなかったのだ。
「そうだっけ? 旅にでる興奮で、聞いてなかったかも。監視者を一人つけることは、覚えてたけど」
「ふふっ、意外にアゲハって、抜けてるんだね」
「そうかも」
緊張した雰囲気が、アゲハとコオロギの笑いで和んできた。
コオロギはアゲハの調子が良くなったと判断し、
「さて、そろそろ、僕を呼んだ理由を話してくれるかい? アゲハと会話するのは楽しいけど、いつまでもこの状態を維持できない。誰かに見られるとまずいからね」
「うん……そうだよねぇ」
アゲハはモジモジしている。
両手を握り、恥ずかしそうに下をむく。
ざっくばらんとした性格だと思っていただけに、コオロギは目を白黒させ、
「どうしたんだい? 元気がないね?」
「あのさ、怒らない?」
「怒る? 何かやらかしたの?」
「いや、ゴーストエコーズと、まったく関係ない話なんだけど……」
つまり、あまり仕事と関係ないことで、コオロギを呼びだしてしまったのだ。
意外なしおらしさに、コオロギの胸は高鳴っていた。それは快感でもあり、喜びでもあった。
「いいよ。僕でよければ、相談にのるよ」
「あっ、あのさ。私って、前会ったときと、変わった?」
アゲハは、カンタロウとマリアに、悲しい顔を見せてしまったことを気にしていた。
エコーズの精鋭として、見せてはいけない感情。
それは人間に同情すること。
それがわかっていたからこそ、今まで隠してきたし、言葉で自分を納得させていた。
不気味な笑顔も、そのために用意された、感情を隠すための仮面だ。
それなのに、あっさりマリアに自分の本心を見破られ、仲間を失う辛さを感情にだしてしまった。
それが結果として、より深い仲間の絆として、カンタロウの信頼を得てしまったのだが、それはアゲハの演技ではない。
もし、今後も、こんな感情をだしてしまうのであれば、任務に失敗する可能性があった。
「うん? 特に変化はないと思うけど……」
コオロギはアゲハに言われ、顔を覗いてきた。
アゲハはつい顔をそらし、
「そうだよね。そう。私は変わってない。変わるわけがない」
そう言葉で納得させても、自信がない。
でもそれが、今では精一杯だった。
コオロギに自分の表情を見られるのも、恥ずかしかった。
「何かあったの? あの人間の男が、何かしたとか?」
「ううん! 違うよ! カンタロウ君は関係ないよ!」
コオロギに言われ、アゲハは両手を大きく振る。
自分の感情を誤魔化すために、カンタロウにしがみついてしまったことは、また一つの恥ずかしさだった。
カンタロウ本人は、いつものアゲハの悪ふざけだと思っているので、感情の変化に気づいていない。
そもそも、女の感情に鈍感な男なので、アゲハの心境をまったく理解はしていないだろう。
「……そう」
アゲハの大げさな手振りに、コオロギは何か嫌な感じはしたが、あえて言葉にだすのをやめた。
アゲハは深呼吸すると、話を変えることにし、
「コオロギってさ。男と女の関係ってわかる?」
「関係?」
「そう。男と女の、何て言うのかな。愛って、言うのかな。そういうの」
「それは……わからない。僕達エコーズにも性別はあるけど、生殖能力はないから、人間のように交尾をすることもないし。恐らく、愛っていうのは、交尾をする前の過程で生まれるものだと思う。クジャクの雄が、雌に綺麗な羽を見せたり、鳴き声を聞かせるようなものかな」
コオロギは自分の知っている知識を、アゲハに言ってみた。
アゲハもさっぱり意味がわからないのか、
「そういうものなの?」
「いや、わかんないや。僕は経験がないし。それに、高度な知能を持った生物の場合、動物のようにはいかないだろうしね」
コオロギが下をむくと、黄色の花が咲いていることに気づいた。花は大きく、よく目立つ。
「例えば、そうだな。僕がこの花を、アゲハにプレゼントするっていうのも、愛なのかもしれない」
「ふぅん……。コオロギってさ。私のこと好きなの?」
アゲハは意味もなく、コオロギにそんなことを聞いてみた。
「例えばだよ」
コオロギの声が少し震え、アゲハから視線を外した。
「あっ、今、目をそらしたじゃん」
「目にゴミが入っただけさ」
誤魔化しているが、明らかに照れている。
アゲハはコオロギのそんな純朴な所が、何となく好きだった。
「ふふっ、そっか。じゃ、女の子がさ。男の子のために、料理をしてあげるってのも、愛情表現ってわけなんだ」
「そうだね……料理?」
料理という単語の意味がわからないのか、コオロギはオウム返しに聞いてくる。
「例えばの話」
アゲハはどことなく気分が良くなり、ポンッと木の根っこから地面に飛んだ。
「ありがと。ちょっとスッキリした」
「そう。それはよかった」
「うん。じゃ、またね」
手を振ると、後ろをむくアゲハ。
「――アゲハ」
カンタロウの家に戻ろうとするアゲハを、コオロギが呼び止めた。
「うん?」
「僕達に――愛というものはないよ。神ですら、僕等を愛してくれないのだから」
高揚のない声で、コオロギはしゃべった。
アゲハの方にはむいていない。
地面にむかって、まるで独り言のようにつぶやいていた。
「……そう、だね」
アゲハも沈んだ声で、それに応えた。
二人の間を、乾いた風が通りすぎていく。
「また、会おうね。アゲハ」
「うん。お前も元気にしてろよ」
アゲハは精一杯明るい声を上げると、その場から走り去る。
「君も……元気でね」
コオロギは目を伏せたまま、黄色の花を見つめていた。
朝。
カンタロウ、アゲハ、スズは、朝食を食べるために、囲炉裏の間に集まっていた。
マリアとヒナゲシは、料理を作るために台所で作業をしている。
しばらく待っていると、マリアが料理を持ってきた。
「カンタロウ様。今日の朝ご飯、私が作ってみたんです。お口に合うかどうか、自信はないんですけど……」
マリアはみんなの前に、朝食を置いた。
卵やスープを使った料理だ。
良い香りが、部屋に充満する。
「そうなのか? おいしそうだ」
カンタロウは素直に、そう感想を言った。
マリアは皆に料理を配り終えると、カンタロウのすぐ隣に座った。
カンタロウの反対側には、アゲハが陣取っている。
ヒナゲシが座ったことで、食事が開始された。
「はい、カンタロウ様」
マリアは自分の箸で料理を取ると、手を添え、カンタロウに差しだした。
「どっ、どうしたんだ?」
マリアの行動に、カンタロウは少し驚いた。
「食べさせてあげます。嫌、ですか?」
「ああ、そうなのか。それならいただくよ」
マリアが料理を作ったのは、自分に食べさせたかったのだと、カンタロウは察し、素直にそれを受けることにした。
「はい、あ~ん」
マリアは恐ろしく丁寧だ。
多少恥ずかしさはあるものの、カンタロウはマリアから差しだされた料理を口にふくみ、
「うん、おいしいよ」
ヒナゲシが作る料理とは、また違った味だ。
不味くなく、むしろうまい。
マリアの特技が料理だったと、初めて知る。
「ほんとですか? 嬉しい」
マリアは頬を赤らめて喜んだ。
「マリアさん。一生懸命作ったものね。私の出番なくなっちゃいそう」
ヒナゲシは、マリアの料理のうまさを認めていた。
スズが、何気にうなずいている。
「あっ、ごめんなさい。勝手に台所使わせてもらって……」
マリアは遠慮がちに、ヒナゲシに言った。
「いいのよ。気にしないで。それよりどう? カンタロウさん」
「うん。マリアの手料理はおいしいよ」
「そうじゃなくて。マリアさんのこと」
ヒナゲシの言葉の意味がわかり、マリアは真剣な目つきで、カンタロウを見つめた。恥ずかしさで濡れた茶色の瞳が、カンタロウの表情を映す。
「うん? マリアのことがどうかしたのか?」
カンタロウはモグモグと、食事を進めていた。その顔に、マリアやヒナゲシが期待した感情は見えない。
マリアは小さく、ため息をついた。
――さすがカンタロウ。鈍い。
スズは食事を進めながら、カンタロウの女性に対する恋愛音痴を嘆いた。
「もう! カンタロウさんたら!」
ヒナゲシはカンタロウの無反応さに、子供のように頬をむくれさせた。
カンタロウはなぜ母に怒られているのか、理由がわからず首を傾げるばかりだった。
「じゃ、今度は私だな。はい、あ~ん」
アゲハが料理を箸で取ると、マリアと同じように、カンタロウに差しだす。
マリアがどうしてそんなことをしているのか、アゲハなりに知りたいようだ。それで行動を真似しているのである。
「アゲハは何も作ってないだろ?」
「いいじゃん。はい、あ~ん」
食べないと終わりそうにないので、カンタロウは仕方なく料理を口にふくみ、
「うん、うまい」
「そうだろ?」
アゲハは満足気に微笑んだ。
「いや、マリアの料理がだ」
「いやいや、私が料理を運んだから、うまいんだ」
「なんなんだ? それは?」
「そういうことだよ。カンタロウ君」
何か嬉しいものを感じたのか、アゲハはニコニコ笑っている。
「じゃ、次は私ですね。はい、カンタロウ様」
マリアが再び、箸で料理を取り、カンタロウに差しだす。
「待って。まだ私がやるから」
アゲハは髪をかき上げると、箸で料理をつまもうとする。
「順番ですよ。アゲハさん」
「そんなの決まってないじゃん」
「アゲハさん、料理――作ってないですよね?」
「ぐっ……」
マリアは痛い所をつき、アゲハを圧倒した。満面な笑顔が、より一層不気味さを増している。
アゲハはマリアの威圧感に負け、箸を置いた。
――アゲハの扱い方、わかってきたな。
と、カンタロウは思った。
マリアとアゲハの距離が、次第に近づきつつある。
アゲハの方からちょっかいをだすことが多いが、マリアはその対処方法を学びつつあるのだ。
カンタロウはそれが何となく嬉しくなり、顔にはださないが心地良かった。
「うむ。なぜかドロドロしてますね」
「ほんとね。ちょっと羨ましいわ。はい、スズ、あ~んして」
ヒナゲシは料理を箸で持つと、スズに差しだした。
「えっ? ヒナゲシ様?」
「いいから、あ~ん」
「はっ、はい! いただきます! あっ、あ~ん」
スズは大きく口を開け、ヒナゲシから料理をもらった。
「おいしい?」
「当然です!」
スズはあまりのおいしさに、涙ぐんだ。
*
アゲハは食事を終えると、散歩をするため外にでていった。
有刺鉄線の柵を越えるため、入り口にいる兵士に挨拶をする。
最近兵士は、アゲハに慣れてきたのか、声にはださないが、会釈をするようになってきた。
今回、コオロギとの待ち合わせ場所は、巨大なブナの木だ。
幹や枝は大きく、根っこは地面からはみだし、巨大な樹を支えている。
根っこに腰を下ろし、黒いフードをかぶった男が一人、座っていた。
腕には神獣で作った、赤い鳥を乗せているので、間違いなくコオロギだ。
アゲハはいつもの挨拶をせず、コオロギのそばに立った。
コオロギはアゲハの感情の揺らぎに気づき、赤い目で見上げ、
「どうしたんだい? 今日は不機嫌だね」
「別に」
「それならいいけど……」
それからしばらく、二人は何も話さなかった。
岩の影から、おこじょのような動物が、二人を眺めている。
顔は茶色く、腹は白く、長い体は人の腕ほどしかない。
つぶらな黒い瞳が、パチパチと動いた。
「……ねえ。コオロギってさ。いつもどこにいるの?」
アゲハの方から、口を開いた。
「森だよ。この大陸では、町に入れないからね」
エコーズは結界の中に入れない。それはコオロギとて、例外ではない。
「私が呼んだら、すぐに来てくれるよね? この近くの森に住んでいるの?」
アゲハは赤い鳥を呼び、自分の腕に乗せた。
「今はね。でもアゲハが遠くに行ってしまったら、来るのも遅くなる」
「へえ。私の後を、ついてきてるわけじゃないんだ?」
「それは危険だからしない。町や都市、今では村でさえ吸収式神脈装置があるからね。エコーズだと、バレてはまずいんだ」
「そっか。でも、もし私が死んだらどうするの? いつも監視してないんじゃ、気づかないんじゃないの?」
「月に一回。僕は神獣をアゲハに送ってるよ。前に初めて会ったときも、この青い鳥をアゲハに送ったろ? それで返事がなければ、君がどうなったか、調査することになってる」
コオロギはアゲハに、神獣で作った青い鳥を見せた。
「えっ? そうだったんだ? 初めに説明しといてよ」
アゲハにとって、それは初耳だった。
「あれ? 旅立つ前に、仲間から聞かなかったの?」
コオロギは知っているものだと思っており、あえて説明はしなかったのだ。
「そうだっけ? 旅にでる興奮で、聞いてなかったかも。監視者を一人つけることは、覚えてたけど」
「ふふっ、意外にアゲハって、抜けてるんだね」
「そうかも」
緊張した雰囲気が、アゲハとコオロギの笑いで和んできた。
コオロギはアゲハの調子が良くなったと判断し、
「さて、そろそろ、僕を呼んだ理由を話してくれるかい? アゲハと会話するのは楽しいけど、いつまでもこの状態を維持できない。誰かに見られるとまずいからね」
「うん……そうだよねぇ」
アゲハはモジモジしている。
両手を握り、恥ずかしそうに下をむく。
ざっくばらんとした性格だと思っていただけに、コオロギは目を白黒させ、
「どうしたんだい? 元気がないね?」
「あのさ、怒らない?」
「怒る? 何かやらかしたの?」
「いや、ゴーストエコーズと、まったく関係ない話なんだけど……」
つまり、あまり仕事と関係ないことで、コオロギを呼びだしてしまったのだ。
意外なしおらしさに、コオロギの胸は高鳴っていた。それは快感でもあり、喜びでもあった。
「いいよ。僕でよければ、相談にのるよ」
「あっ、あのさ。私って、前会ったときと、変わった?」
アゲハは、カンタロウとマリアに、悲しい顔を見せてしまったことを気にしていた。
エコーズの精鋭として、見せてはいけない感情。
それは人間に同情すること。
それがわかっていたからこそ、今まで隠してきたし、言葉で自分を納得させていた。
不気味な笑顔も、そのために用意された、感情を隠すための仮面だ。
それなのに、あっさりマリアに自分の本心を見破られ、仲間を失う辛さを感情にだしてしまった。
それが結果として、より深い仲間の絆として、カンタロウの信頼を得てしまったのだが、それはアゲハの演技ではない。
もし、今後も、こんな感情をだしてしまうのであれば、任務に失敗する可能性があった。
「うん? 特に変化はないと思うけど……」
コオロギはアゲハに言われ、顔を覗いてきた。
アゲハはつい顔をそらし、
「そうだよね。そう。私は変わってない。変わるわけがない」
そう言葉で納得させても、自信がない。
でもそれが、今では精一杯だった。
コオロギに自分の表情を見られるのも、恥ずかしかった。
「何かあったの? あの人間の男が、何かしたとか?」
「ううん! 違うよ! カンタロウ君は関係ないよ!」
コオロギに言われ、アゲハは両手を大きく振る。
自分の感情を誤魔化すために、カンタロウにしがみついてしまったことは、また一つの恥ずかしさだった。
カンタロウ本人は、いつものアゲハの悪ふざけだと思っているので、感情の変化に気づいていない。
そもそも、女の感情に鈍感な男なので、アゲハの心境をまったく理解はしていないだろう。
「……そう」
アゲハの大げさな手振りに、コオロギは何か嫌な感じはしたが、あえて言葉にだすのをやめた。
アゲハは深呼吸すると、話を変えることにし、
「コオロギってさ。男と女の関係ってわかる?」
「関係?」
「そう。男と女の、何て言うのかな。愛って、言うのかな。そういうの」
「それは……わからない。僕達エコーズにも性別はあるけど、生殖能力はないから、人間のように交尾をすることもないし。恐らく、愛っていうのは、交尾をする前の過程で生まれるものだと思う。クジャクの雄が、雌に綺麗な羽を見せたり、鳴き声を聞かせるようなものかな」
コオロギは自分の知っている知識を、アゲハに言ってみた。
アゲハもさっぱり意味がわからないのか、
「そういうものなの?」
「いや、わかんないや。僕は経験がないし。それに、高度な知能を持った生物の場合、動物のようにはいかないだろうしね」
コオロギが下をむくと、黄色の花が咲いていることに気づいた。花は大きく、よく目立つ。
「例えば、そうだな。僕がこの花を、アゲハにプレゼントするっていうのも、愛なのかもしれない」
「ふぅん……。コオロギってさ。私のこと好きなの?」
アゲハは意味もなく、コオロギにそんなことを聞いてみた。
「例えばだよ」
コオロギの声が少し震え、アゲハから視線を外した。
「あっ、今、目をそらしたじゃん」
「目にゴミが入っただけさ」
誤魔化しているが、明らかに照れている。
アゲハはコオロギのそんな純朴な所が、何となく好きだった。
「ふふっ、そっか。じゃ、女の子がさ。男の子のために、料理をしてあげるってのも、愛情表現ってわけなんだ」
「そうだね……料理?」
料理という単語の意味がわからないのか、コオロギはオウム返しに聞いてくる。
「例えばの話」
アゲハはどことなく気分が良くなり、ポンッと木の根っこから地面に飛んだ。
「ありがと。ちょっとスッキリした」
「そう。それはよかった」
「うん。じゃ、またね」
手を振ると、後ろをむくアゲハ。
「――アゲハ」
カンタロウの家に戻ろうとするアゲハを、コオロギが呼び止めた。
「うん?」
「僕達に――愛というものはないよ。神ですら、僕等を愛してくれないのだから」
高揚のない声で、コオロギはしゃべった。
アゲハの方にはむいていない。
地面にむかって、まるで独り言のようにつぶやいていた。
「……そう、だね」
アゲハも沈んだ声で、それに応えた。
二人の間を、乾いた風が通りすぎていく。
「また、会おうね。アゲハ」
「うん。お前も元気にしてろよ」
アゲハは精一杯明るい声を上げると、その場から走り去る。
「君も……元気でね」
コオロギは目を伏せたまま、黄色の花を見つめていた。