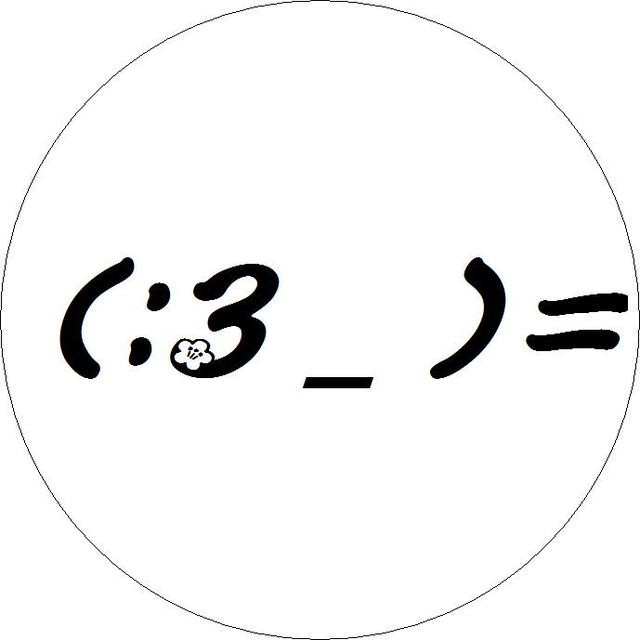エピローグ 動揺
文字数 5,448文字
カンタロウの実家から、数キロ離れた森の中。
もう太陽は傾いており、赤い夕日が溶けた鉄のように、森の中をそそいでいた。
木のそばでは、フードを頭までかぶったコオロギが、アゲハを待っていた。
コオロギの腕には、神獣で作られた赤い鳥が乗っている。
アゲハがコオロギを呼びだすときに使うものだ。
「ヤッホー」
アゲハがやってきた。
カンタロウの家を見張っている兵士には、どうどうと散歩に行くと言ってある。
下手に誤魔化すと、カンタロウ達に知られるだろうと思ったからだ。
「やあ、元気そうだね」
コオロギは赤い鳥を、地面に置いた。
鳥は溶けるように、大地に帰っていく。
アゲハがにかっと笑い、
「君もね。で、どうだった? ゴーストエコーズがいた町は?」
「イデリオの町のことだね。駄目だった。何の手がかりもなし」
「そっか」
コオロギは何も得られなかったらしい。
やはりカインが、ゴーストエコーズとなったことは、町の人間には関係のないことだった。
外部から来た者が、カインをそそのかしたのだろう。
誰にも知られずに。
「ところで、ソフィヤって子を知ってる? 全盲の子なんだけど。偶然知り合ったんだ。赤い目を見られたと思って、少し焦ったけど」
コオロギが言う少女。
ソフィヤはカインによって、神格化する障害者の一人として、城に招待された少女だ。
野心は打ち砕かれ、今は一般の庶民として、姉のエルガと暮らしている。
「えっ? ああ、あの子。知ってるよ? でもよく結界の中に入れたね?」
「僕は入れないよ。町に入って調査していたのは、僕達と同じ、盲目の蛇を持つタテハさ。彼女は普通に神脈を持っているからね。僕がソフィヤと出会ったのは、森の中だ」
「森で?」
「うん。森でタテハを待っていたら、彼女に出会った。お姉さんと一緒に来ていたみたいだけどね。僕を見たら……ていう表現はおかしいけど、アゲハと一緒にいる人間の男と、間違われたよ。ついそいつを知ってるって言っちゃった」
コオロギは初歩的なミスに、アゲハに向かって頬をかいた。
――森……まさか、私達を探していたの?
アゲハはそんな想像をしてみる。
町の人間には黙って、自分達が逃げた方向を目指し、森に入った。
エルガが一緒にいたのは、ソフィヤのことが心配だったのと、多少は自責感があったからだろう。
そうアゲハは思った。
「君達にメッセージ。『ごめんなさい。あと、ありがとう』だってさ」
コオロギから出る感謝の言葉。
ソフィヤはカンタロウとアゲハに、お礼が言いたかったのだ。
町の人間のように、邪険にしていなかった。
「……そっか。わかった」
カンタロウ君が聞けば、きっと喜ぶだろうな。
アゲハはそう思うと、笑みがこぼれていた。
「嬉しそうだね」
「別に」
コオロギに笑みを見られ、アゲハは恥ずかしそうに顔をそらし、
「それにしても、タテハって誰? 君が彼女って言ったから、女だということはわかるけど。聞いたことないよ?」
同じ盲目の蛇を持つ女。
神脈結界に入れるということは、エコーズではない。
コオロギが気を許している人物だ。
相当エコーズと、関わりが深い。
コオロギはしまったとばかり、つい口に手をやり、
「あっ……ごめん。それは言えないんだ」
「どうして?」
「その……彼女は人間にしては良い人なんだけど……あっ」
また情報を、アゲハに与えてしまった。
種族は人間。
アゲハはすぐにそれを記憶した。
コオロギは頭をかかえ、
「ああっ、僕は馬鹿だ。何で言っちゃうんだ。彼女に口止めされてるのに……」
「えっ? どうして?」
「君に、あまり自分のことを知られたくないみたいなんだ。たぶん、コウダ様によって、そういうふうに育てられたんだと思う。あの方は孤児なんかを集めて、どこかで教育しているみたいだから……」
アゲハも知らない、コウダの企てがあるのだろう。
盲目の蛇を持つ者は少ない。
情報は一般に公開されているので、『エコーズ討伐専門部隊』と、ランマルでも知っていたが、実際の人数は十人もいないと聞く。
皆種族はバラバラだが、唯一の共通点は、コウダの息がかかり、エコーズに協力的であること。
「ふぅん……」
アゲハはそれ以上、何も聞かなかった。
沈黙が、辺りに漂う。
「とっ、ところで、アゲハの方は、僕に報告はあるかい?」
「うん。また言語をしゃべるゴーストエコーズと戦った」
「へぇ」
コオロギは目をパチパチさせた。
立て続けに、特種エコーズと戦ったのだ。
アゲハの強運、もしくは悪運の良さに、驚きを隠せない。
「そのエコーズは死んじゃったけど。ゴーストエコーズを生みだしている者は、もしかすると――女かもしれない」
「そいつが言ったの?」
「うん。あとS級犯罪者。カッコウが何か知っているかもしれない」
S級犯罪者という単語に、コオロギはしばらく考えを巡らせた。
「カッコウ……ああ、『人の名を持てない者』か。どんな特徴をしてるんだい?」
「両目が赤い。あとピアスや指輪をつけてる、変な男。見つけだしたら、一発殴っといて」
「何かされたのかい?」
「大切なものを奪われちゃった」
アゲハは冗談のつもりで言ったが、コオロギの目がナイフのようにギラリと鈍く光る。
「そうか。なら、腕の一本もぎ取っとくよ」
コオロギの声色は静かだが、本気だ。
アゲハはあまりの冗談のつうじなさに、コオロギの肩をバシバシ叩いた。
「痛いよ……」
「そんなに固くならないの。とにかく、捕まえて、情報を吐かせれば、目的のものが見つかるかも」
「わかった。他の盲目の蛇にも言っとくよ」
「あとは、特にないかな」
「そう。……君が無事でよかったよ。あまり危険なことはしないでくれよ」
「わかってるよ」
アゲハは自信があるのか、コオロギに向かって胸を張っている。
「あと、いつも君と一緒にいる男。彼とは離れないのかい?」
コオロギはカンタロウの名前を知っているが、あえて言わなかった。
なぜかその名前がでてくると、胸がモヤモヤして気分が悪いからだ。
だから人間の男という、抽象的な表現しか使わなかった。
「ああ、カンタロウ君ね。別に問題ないよ。仕事内容とか、親に言ってないみたいだし。いざとなれば――消せるし」
アゲハの表情が変わった。
カンタロウのことは確かに気になる。しかし、それは仕事の間だけの話だ。
利用するだけ利用し、いらなくなれば捨てればいい。それだけの付き合いだ。
「そう簡単にいくかな?」
コオロギの声が、少し高揚した。
アゲハがカンタロウのことについて、何の感情も持っていないことが、愉快なのだ。
「大丈夫だよ。いろいろ調べてみると、友達や仲間はいないみたいだし。他人からも疎まれてるからね。死んだ所で、誰も心配し、助けないでしょ」
「親兄弟は?」
「全盲の母親と、血の繋がっていない姉がいるだけ。あの程度だったら、すぐに殺せると思うよ。二人とも社会から疎外されてるしね。一応、姉の方は、赤眼化できるから気をつけてね」
アゲハはカンタロウの家族関係や人間関係を、簡潔にコオロギに教えた。
ただ、荊棘魔法、結界切りについては、何も教えなかった。
まだその仕組みや、魔力の形態がわからないからだ。
「なるほど。そいつ等は、とても弱い立場にいる人間ということだね。それなら問題ないか。弱者は強者に踏みにじられるのが、運命だからね」
コオロギは息をつき、胸をなで下ろした。
最後の言葉は、エコーズ達が人間達に受けてきた迫害を意味している。
アゲハに被害はないだろうと、コオロギは安心した。
「ほんと、仲間として組むのに都合がよかったよ」
カンタロウは人不信な所があるが、アゲハに対しては、その素直さや優しさを素でだしていた。
アゲハが女であるということと、人間の大陸で鍛えられた社交性、呉越同舟がきいたのだろう。
カンタロウに自分がエコーズだと気づかれず、任務を遂行できる自信が、アゲハにはあった。
「じゃ、私は風呂に入りに行くから、今日はここまで」
「もう?」
火が消えたように、つい小さな声を漏らしてしまうコオロギ。
「そんな寂しそうな顔しないの」
「べっ、別にしてないさ」
自分の立場を忘れ、アゲハと一緒にいたいと思ってしまったコオロギは、慌てて前の言葉を取り消した。
「ははっ、じゃ、またね。コオロギ」
アゲハは手を大きく振ると、家へと戻っていく。
「うん。アゲハ。絶対に死なないで」
コオロギもアゲハと同じく、大きく手を振っていた。
アゲハが有刺鉄線の柵を越え、丘を上り、カンタロウの家が見えてきた所で、二人の影が夕日の中を射していた。
カンタロウとマリアだ。
カンタロウは腕を組み、マリアは両手を前で組んで、アゲハを待っていた。
「あれ? どうしたの? 二人とも?」
アゲハはいぶかりながら、二人に近づいていく。
コオロギに会ったときに、人の気配はなかったし、後ろをついてこられた形跡もない。それでも、頭の中で、確認せずにはいられなかった。
「……やっぱり、間違いだったんじゃないのか?」
「いいえ。間違いありません」
カンタロウの問いに、マリアは首を大きく横に振った。
アゲハは意味がわからず、二人を見交わす。
「アゲハさん」
マリアがアゲハの前に立った。その表情に、疑惑の眼差しはない。
アゲハはつい、後ろに一歩下がり、身構え、
「何? マリア?」
「私達が土砂崩れにあったとき、助けにきてくれましたよね? あのときの表情が、忘れられなくて」
アゲハの記憶が一気に弾けた。
ツネミツの罠に引っかかったカンタロウ達を、見捨てたあの場面だ。
自分がどんな表情をし、どんな感情だったのか、アゲハはしっかりと覚えていた。
――やばっ、もしかして、笑ってた?
アゲハはおかしい気持ちを、表情にだしていた記憶がある。
こんな単純な罠に引っかかる人間達を、笑っていたのだ。
あれを見られたとしたら、カンタロウとの人間関係が何もかも壊れてしまう。
ちょっとしたミスに、アゲハは焦り、額から汗を流した。
「ははっ」
「ふふっ」
責められると身構えている、アゲハの態度とは逆に、カンタロウとマリアはおかしそうに笑った。
笑いには悪意や蔑む感情はなく、本物の素の笑いだ。
「なっ、何よ? 二人して笑って……」
撃たれた鳥のように、アゲハは驚いている。
カンタロウは自宅のほうへ振り返り、
「やっぱり大丈夫そうだな」
「だから、何がよ」
二人の意図がわからず、アゲハはイライラし始めた。
マリアがアゲハに、ニッコリと笑いかけ、
「あのとき、アゲハさん。――とても悲しそうな表情をしていました。まるで、すぐ泣いてしまいそうな顔」
マリアはあの土砂崩れで、カンタロウに助けられ、ランマルの能力によって大穴があき、それを覗き込むアゲハの表情を、しっかりと覚えていた。
アゲハは、とても悲しそうな顔をして、笑っていた。
嬉しさと悲しさが、混ざり合ったような、そんな表情をしていたのだ。
マリアはそこに、アゲハの本音を感じ、外に散歩にでたのは、強がりの性格から感情を発露できないためではないかと、カンタロウに相談していた。
――えっ?
アゲハは自分の感情に、耳を疑った。
マリアの言うことが本当なら、実は泣きたいぐらい、仲間の死が悲しかったことになる。もしくは、仲間を見捨てた自分に、罪悪感を感じていたかだ。
仲間。
その空虚であった言葉が、色を持たなかった単語が、アゲハの頭でグラグラ回る。
「それがちょっと心配だったんです。もしかして、無理してるんじゃないかって。でも、杞憂でした。アゲハさん、仲間思いですもんね」
マリアはアゲハの動揺に気づかず、そう結論づけてしまった。
――そんな……どうして? 人間が死んだ所で、そんな表情、私がするはずない。
アゲハは目を見開き、両手を無意識に頬にやり、汗で冷たくなった自分の顔を動かしてみる。
今、自分はとても困惑している。それが手からもよくわかる。
なぜ自分は、こんなにもモロいのか。
作られた表情ができないのか。
「驚いたよ。アゲハはもっと、仕事にシビアな獣人だと思ってた。意外だったな」
「ええ。私、お二人と仲間になれてよかったです」
「さっ、風呂が沸いてる。家に帰ろう」
カンタロウとマリアは、二人で勝手に話を進めると、家へと踵を返していく。
アゲハは歯を食いしばり、
「しっ……してない! そんな顔、してないよ!」
完全な自己否定。自分は弱くない。剣の腕だって、魔法の力だって、人間のあしらい方だってうまいはずだ。
弱いはずがない。
アゲハは弱い自分を、無理矢理強い自分に置き換えていた。
「わかったわかった。そういうことにしとくよ」
カンタロウの軽い扱い方に、アゲハはムッとした。
自分の弱点を、わかっているかのような態度だからだ。
あまりに悔しくて、アゲハはカンタロウの背中に飛び乗り、
「してないって、言ってるだろ!」
耳元で、おもいっきり言ってやる。それでもまだ足りず、アゲハはカンタロウの首を強く抱きしめた。
「ぐわっ! 背中に乗るな! 首を絞めるな!」
突然の奇襲に、カンタロウの背骨が折れそうになる。
アゲハは恥ずかしさと情けなさから、燃えるように真っ赤になっていた。
それでも、どこからかくる心地良さを、否定することができない。
こうしてカンタロウを抱きしめていると、胸の高鳴りを感じてしまう。
「ふふ」
マリアは二人の子供を見守る母親のように、優しく微笑んでいた。
もう太陽は傾いており、赤い夕日が溶けた鉄のように、森の中をそそいでいた。
木のそばでは、フードを頭までかぶったコオロギが、アゲハを待っていた。
コオロギの腕には、神獣で作られた赤い鳥が乗っている。
アゲハがコオロギを呼びだすときに使うものだ。
「ヤッホー」
アゲハがやってきた。
カンタロウの家を見張っている兵士には、どうどうと散歩に行くと言ってある。
下手に誤魔化すと、カンタロウ達に知られるだろうと思ったからだ。
「やあ、元気そうだね」
コオロギは赤い鳥を、地面に置いた。
鳥は溶けるように、大地に帰っていく。
アゲハがにかっと笑い、
「君もね。で、どうだった? ゴーストエコーズがいた町は?」
「イデリオの町のことだね。駄目だった。何の手がかりもなし」
「そっか」
コオロギは何も得られなかったらしい。
やはりカインが、ゴーストエコーズとなったことは、町の人間には関係のないことだった。
外部から来た者が、カインをそそのかしたのだろう。
誰にも知られずに。
「ところで、ソフィヤって子を知ってる? 全盲の子なんだけど。偶然知り合ったんだ。赤い目を見られたと思って、少し焦ったけど」
コオロギが言う少女。
ソフィヤはカインによって、神格化する障害者の一人として、城に招待された少女だ。
野心は打ち砕かれ、今は一般の庶民として、姉のエルガと暮らしている。
「えっ? ああ、あの子。知ってるよ? でもよく結界の中に入れたね?」
「僕は入れないよ。町に入って調査していたのは、僕達と同じ、盲目の蛇を持つタテハさ。彼女は普通に神脈を持っているからね。僕がソフィヤと出会ったのは、森の中だ」
「森で?」
「うん。森でタテハを待っていたら、彼女に出会った。お姉さんと一緒に来ていたみたいだけどね。僕を見たら……ていう表現はおかしいけど、アゲハと一緒にいる人間の男と、間違われたよ。ついそいつを知ってるって言っちゃった」
コオロギは初歩的なミスに、アゲハに向かって頬をかいた。
――森……まさか、私達を探していたの?
アゲハはそんな想像をしてみる。
町の人間には黙って、自分達が逃げた方向を目指し、森に入った。
エルガが一緒にいたのは、ソフィヤのことが心配だったのと、多少は自責感があったからだろう。
そうアゲハは思った。
「君達にメッセージ。『ごめんなさい。あと、ありがとう』だってさ」
コオロギから出る感謝の言葉。
ソフィヤはカンタロウとアゲハに、お礼が言いたかったのだ。
町の人間のように、邪険にしていなかった。
「……そっか。わかった」
カンタロウ君が聞けば、きっと喜ぶだろうな。
アゲハはそう思うと、笑みがこぼれていた。
「嬉しそうだね」
「別に」
コオロギに笑みを見られ、アゲハは恥ずかしそうに顔をそらし、
「それにしても、タテハって誰? 君が彼女って言ったから、女だということはわかるけど。聞いたことないよ?」
同じ盲目の蛇を持つ女。
神脈結界に入れるということは、エコーズではない。
コオロギが気を許している人物だ。
相当エコーズと、関わりが深い。
コオロギはしまったとばかり、つい口に手をやり、
「あっ……ごめん。それは言えないんだ」
「どうして?」
「その……彼女は人間にしては良い人なんだけど……あっ」
また情報を、アゲハに与えてしまった。
種族は人間。
アゲハはすぐにそれを記憶した。
コオロギは頭をかかえ、
「ああっ、僕は馬鹿だ。何で言っちゃうんだ。彼女に口止めされてるのに……」
「えっ? どうして?」
「君に、あまり自分のことを知られたくないみたいなんだ。たぶん、コウダ様によって、そういうふうに育てられたんだと思う。あの方は孤児なんかを集めて、どこかで教育しているみたいだから……」
アゲハも知らない、コウダの企てがあるのだろう。
盲目の蛇を持つ者は少ない。
情報は一般に公開されているので、『エコーズ討伐専門部隊』と、ランマルでも知っていたが、実際の人数は十人もいないと聞く。
皆種族はバラバラだが、唯一の共通点は、コウダの息がかかり、エコーズに協力的であること。
「ふぅん……」
アゲハはそれ以上、何も聞かなかった。
沈黙が、辺りに漂う。
「とっ、ところで、アゲハの方は、僕に報告はあるかい?」
「うん。また言語をしゃべるゴーストエコーズと戦った」
「へぇ」
コオロギは目をパチパチさせた。
立て続けに、特種エコーズと戦ったのだ。
アゲハの強運、もしくは悪運の良さに、驚きを隠せない。
「そのエコーズは死んじゃったけど。ゴーストエコーズを生みだしている者は、もしかすると――女かもしれない」
「そいつが言ったの?」
「うん。あとS級犯罪者。カッコウが何か知っているかもしれない」
S級犯罪者という単語に、コオロギはしばらく考えを巡らせた。
「カッコウ……ああ、『人の名を持てない者』か。どんな特徴をしてるんだい?」
「両目が赤い。あとピアスや指輪をつけてる、変な男。見つけだしたら、一発殴っといて」
「何かされたのかい?」
「大切なものを奪われちゃった」
アゲハは冗談のつもりで言ったが、コオロギの目がナイフのようにギラリと鈍く光る。
「そうか。なら、腕の一本もぎ取っとくよ」
コオロギの声色は静かだが、本気だ。
アゲハはあまりの冗談のつうじなさに、コオロギの肩をバシバシ叩いた。
「痛いよ……」
「そんなに固くならないの。とにかく、捕まえて、情報を吐かせれば、目的のものが見つかるかも」
「わかった。他の盲目の蛇にも言っとくよ」
「あとは、特にないかな」
「そう。……君が無事でよかったよ。あまり危険なことはしないでくれよ」
「わかってるよ」
アゲハは自信があるのか、コオロギに向かって胸を張っている。
「あと、いつも君と一緒にいる男。彼とは離れないのかい?」
コオロギはカンタロウの名前を知っているが、あえて言わなかった。
なぜかその名前がでてくると、胸がモヤモヤして気分が悪いからだ。
だから人間の男という、抽象的な表現しか使わなかった。
「ああ、カンタロウ君ね。別に問題ないよ。仕事内容とか、親に言ってないみたいだし。いざとなれば――消せるし」
アゲハの表情が変わった。
カンタロウのことは確かに気になる。しかし、それは仕事の間だけの話だ。
利用するだけ利用し、いらなくなれば捨てればいい。それだけの付き合いだ。
「そう簡単にいくかな?」
コオロギの声が、少し高揚した。
アゲハがカンタロウのことについて、何の感情も持っていないことが、愉快なのだ。
「大丈夫だよ。いろいろ調べてみると、友達や仲間はいないみたいだし。他人からも疎まれてるからね。死んだ所で、誰も心配し、助けないでしょ」
「親兄弟は?」
「全盲の母親と、血の繋がっていない姉がいるだけ。あの程度だったら、すぐに殺せると思うよ。二人とも社会から疎外されてるしね。一応、姉の方は、赤眼化できるから気をつけてね」
アゲハはカンタロウの家族関係や人間関係を、簡潔にコオロギに教えた。
ただ、荊棘魔法、結界切りについては、何も教えなかった。
まだその仕組みや、魔力の形態がわからないからだ。
「なるほど。そいつ等は、とても弱い立場にいる人間ということだね。それなら問題ないか。弱者は強者に踏みにじられるのが、運命だからね」
コオロギは息をつき、胸をなで下ろした。
最後の言葉は、エコーズ達が人間達に受けてきた迫害を意味している。
アゲハに被害はないだろうと、コオロギは安心した。
「ほんと、仲間として組むのに都合がよかったよ」
カンタロウは人不信な所があるが、アゲハに対しては、その素直さや優しさを素でだしていた。
アゲハが女であるということと、人間の大陸で鍛えられた社交性、呉越同舟がきいたのだろう。
カンタロウに自分がエコーズだと気づかれず、任務を遂行できる自信が、アゲハにはあった。
「じゃ、私は風呂に入りに行くから、今日はここまで」
「もう?」
火が消えたように、つい小さな声を漏らしてしまうコオロギ。
「そんな寂しそうな顔しないの」
「べっ、別にしてないさ」
自分の立場を忘れ、アゲハと一緒にいたいと思ってしまったコオロギは、慌てて前の言葉を取り消した。
「ははっ、じゃ、またね。コオロギ」
アゲハは手を大きく振ると、家へと戻っていく。
「うん。アゲハ。絶対に死なないで」
コオロギもアゲハと同じく、大きく手を振っていた。
アゲハが有刺鉄線の柵を越え、丘を上り、カンタロウの家が見えてきた所で、二人の影が夕日の中を射していた。
カンタロウとマリアだ。
カンタロウは腕を組み、マリアは両手を前で組んで、アゲハを待っていた。
「あれ? どうしたの? 二人とも?」
アゲハはいぶかりながら、二人に近づいていく。
コオロギに会ったときに、人の気配はなかったし、後ろをついてこられた形跡もない。それでも、頭の中で、確認せずにはいられなかった。
「……やっぱり、間違いだったんじゃないのか?」
「いいえ。間違いありません」
カンタロウの問いに、マリアは首を大きく横に振った。
アゲハは意味がわからず、二人を見交わす。
「アゲハさん」
マリアがアゲハの前に立った。その表情に、疑惑の眼差しはない。
アゲハはつい、後ろに一歩下がり、身構え、
「何? マリア?」
「私達が土砂崩れにあったとき、助けにきてくれましたよね? あのときの表情が、忘れられなくて」
アゲハの記憶が一気に弾けた。
ツネミツの罠に引っかかったカンタロウ達を、見捨てたあの場面だ。
自分がどんな表情をし、どんな感情だったのか、アゲハはしっかりと覚えていた。
――やばっ、もしかして、笑ってた?
アゲハはおかしい気持ちを、表情にだしていた記憶がある。
こんな単純な罠に引っかかる人間達を、笑っていたのだ。
あれを見られたとしたら、カンタロウとの人間関係が何もかも壊れてしまう。
ちょっとしたミスに、アゲハは焦り、額から汗を流した。
「ははっ」
「ふふっ」
責められると身構えている、アゲハの態度とは逆に、カンタロウとマリアはおかしそうに笑った。
笑いには悪意や蔑む感情はなく、本物の素の笑いだ。
「なっ、何よ? 二人して笑って……」
撃たれた鳥のように、アゲハは驚いている。
カンタロウは自宅のほうへ振り返り、
「やっぱり大丈夫そうだな」
「だから、何がよ」
二人の意図がわからず、アゲハはイライラし始めた。
マリアがアゲハに、ニッコリと笑いかけ、
「あのとき、アゲハさん。――とても悲しそうな表情をしていました。まるで、すぐ泣いてしまいそうな顔」
マリアはあの土砂崩れで、カンタロウに助けられ、ランマルの能力によって大穴があき、それを覗き込むアゲハの表情を、しっかりと覚えていた。
アゲハは、とても悲しそうな顔をして、笑っていた。
嬉しさと悲しさが、混ざり合ったような、そんな表情をしていたのだ。
マリアはそこに、アゲハの本音を感じ、外に散歩にでたのは、強がりの性格から感情を発露できないためではないかと、カンタロウに相談していた。
――えっ?
アゲハは自分の感情に、耳を疑った。
マリアの言うことが本当なら、実は泣きたいぐらい、仲間の死が悲しかったことになる。もしくは、仲間を見捨てた自分に、罪悪感を感じていたかだ。
仲間。
その空虚であった言葉が、色を持たなかった単語が、アゲハの頭でグラグラ回る。
「それがちょっと心配だったんです。もしかして、無理してるんじゃないかって。でも、杞憂でした。アゲハさん、仲間思いですもんね」
マリアはアゲハの動揺に気づかず、そう結論づけてしまった。
――そんな……どうして? 人間が死んだ所で、そんな表情、私がするはずない。
アゲハは目を見開き、両手を無意識に頬にやり、汗で冷たくなった自分の顔を動かしてみる。
今、自分はとても困惑している。それが手からもよくわかる。
なぜ自分は、こんなにもモロいのか。
作られた表情ができないのか。
「驚いたよ。アゲハはもっと、仕事にシビアな獣人だと思ってた。意外だったな」
「ええ。私、お二人と仲間になれてよかったです」
「さっ、風呂が沸いてる。家に帰ろう」
カンタロウとマリアは、二人で勝手に話を進めると、家へと踵を返していく。
アゲハは歯を食いしばり、
「しっ……してない! そんな顔、してないよ!」
完全な自己否定。自分は弱くない。剣の腕だって、魔法の力だって、人間のあしらい方だってうまいはずだ。
弱いはずがない。
アゲハは弱い自分を、無理矢理強い自分に置き換えていた。
「わかったわかった。そういうことにしとくよ」
カンタロウの軽い扱い方に、アゲハはムッとした。
自分の弱点を、わかっているかのような態度だからだ。
あまりに悔しくて、アゲハはカンタロウの背中に飛び乗り、
「してないって、言ってるだろ!」
耳元で、おもいっきり言ってやる。それでもまだ足りず、アゲハはカンタロウの首を強く抱きしめた。
「ぐわっ! 背中に乗るな! 首を絞めるな!」
突然の奇襲に、カンタロウの背骨が折れそうになる。
アゲハは恥ずかしさと情けなさから、燃えるように真っ赤になっていた。
それでも、どこからかくる心地良さを、否定することができない。
こうしてカンタロウを抱きしめていると、胸の高鳴りを感じてしまう。
「ふふ」
マリアは二人の子供を見守る母親のように、優しく微笑んでいた。