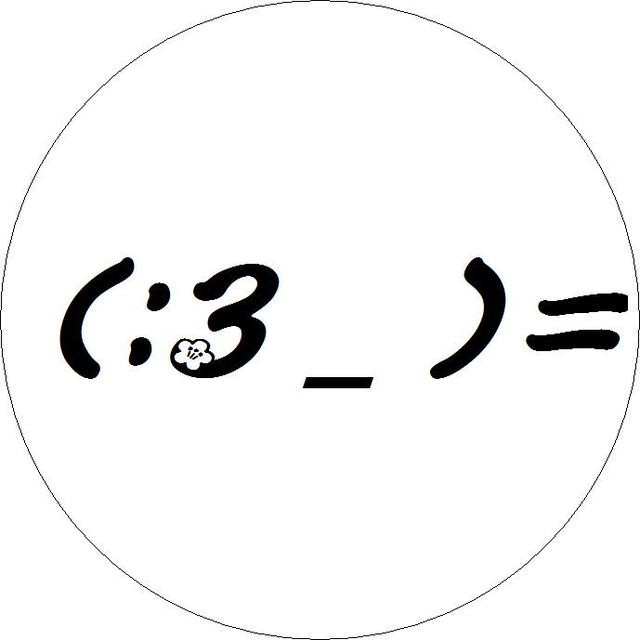私自身の存在が悪
文字数 7,904文字
*
カンタロウが鼻を動かすと、カビと湿気の臭いがした。
まぶたに、淡い光が入ってくる。
目を開けると、フィラメントの灯りが、チラチラ燃えているのが見えた。
「う……ん?」
カンタロウの意識がはっきりしてくると、隣で誰かが会話している。
視線をむけると、アゲハとシオンが何かを話していた。
カンタロウはボウッと、その内容を聞いてみる。
「さっ、私のことを、アゲハお姉ちゃんと言え」
「アケハお姉たん?」
「アゲハお姉ちゃん」
「アデバお姉たん」
「ア・ゲ・ハ」
「ア・ビ・バ」
「……もうお姉たんでいいよ」
「お姉たん!」
シオンがアゲハに抱きついてくる。
アゲハはシオンを優しく受け止め、頭をなでなでしてやっていた。
もうこの短時間で、仲良くなったようだ。
「あ~。よしよし。おっ、気づいた?」
アゲハが倒れていたカンタロウに、話しかけてくる。
「……何してるんだ?」
カンタロウはボヤッとする頭に手を置き、上半身を起こした。
アゲハは両手を広げ、
「この子に社会の礼儀を教えてたの。覚えてくれないけど」
「あっ! お兄たん!」
シオンは小走りにカンタロウの元にむかうと、無邪気に抱きついてきた。
背中についた動物の骨が、ギシギシときしむ。
遠慮なしにカンタロウの胸に顔を埋めると、犬のようにくんくん匂いを嗅いでいた。
「おっと」
「いい匂い~。お兄たん」
シオンの白く長い髪が、カンタロウの腕をなでる。
はしゃいでいる目は、やはり赤い。
顔つきはマリアの妹だけあって、笑うと、とても愛らしく感じる。
――もう殺意がないのか。
カンタロウはシオンの頭をなでた。
この少女が、クロワや信者を皆殺しにし、この地にやってきたハンターを狂人化させ、ゴーストエコーズを操り、自分達を襲わせた張本人だとは、とても思えなかった。
しかし、事実、シオンは植物型神獣を召還し、アゲハにパンドラック・ミクスをかけようとした。
植物を操れることから、この森を生みだしたのもシオンなのだろう。
いったい何が起これば、この子にこんな巨大な力が宿るのか、まったくわからない。
カンタロウは振り向き、
「アゲハ、どうなってるんだ?」
「その子、私達を助けてくれたみたい。ゴーストエコーズなのに、変わってる」
アゲハもはっきりと、シオンをゴーストエコーズだと認めていた。
「ここは?」
カンタロウが周囲に視線をやる。
赤い煉瓦の壁には、白熱灯が灯っていた。
窓はどこにも見当たらない。
天井から、木の根っこのようなものが見える。
気温は低く、寒気がしてきた。
「教会の地下にある通路。電気はこの子に教えてもらって、私がつけたの。たぶん、クロワ達、ここから逃げようとしてたんじゃないかな?」
アゲハが予想する。
つまり、何かあったときのための、緊急用避難通路なのだ。
「この子が運んでくれたのか?」
「うん」
「……そうなのか」
アゲハから事情を聞き、カンタロウは改めて、シオンを見つめる。
――この子が、クロワ達を殺したんだろうな。
カンタロウはそう思うが、やはり、信じられない。
無垢な笑みを見せる少女が、人殺しを平然と行ったことを。
「まあ報いなんじゃないの。その子にひどいことしたさ」
アゲハがあっさりと、カンタロウに答えた。
「……よく俺の考えを読めるな」
「顔にでてる」
「そうか?」
カンタロウは自分の顔を、手で触れてみた。
さっきまで地面に倒れていたため、肌にくっついた小石がポロポロ取れた。
「ニャー」
翼のはえた猫が、三人の前で鳴く。
「あっ、ビネビネ。どこ行ってたんですか? お姉ちゃんのそばを離れちゃ駄目ですよ」
どうやら、翼のはえた猫の名前は、ビネビネというらしい。急にシオンは、お姉さん口調で、ビネビネに注意した。
ビネビネは、足で顔をかくことで応えた。
「ニャ」
ビネビネは気まぐれに、どこかに歩いて行ってしまう。
「あっ、こらっ。待ちなさい」
シオンはビネビネを追いかけていく。
「遠くに行っちゃ駄目だよ」
アゲハがシオンに声をかける。
「わかったぁ」
シオンはそう応えると、通路の奥へ行ってしまった。
「ふう、やれやれだね」
アゲハはシオンを見送ると、カンタロウの隣に座った。
長い金髪の間から、碧い獣の目がカンタロウを覗いてくる。
カンタロウはその綺麗な瞳で見られることに、恥ずかしさを感じ、目をそらして何か話すことはないか考え、
「……あの猫。ビネビネっていうのか?」
「そうみたい。変な名前だよね。たぶん、合成獣化の実験体として、研究所にいたんだと思う」
「ああいうのを、合成獣っていうのか?」
「そうだよ。昔、武帝国が考えた方法なの。大陸戦争時、より強靭な肉体と戦闘能力を得るために、考案されたんだけどね。拒絶反応が起こって、まったく使えなかったの。今じゃ、禁止されてる魔術」
さすが獣人の義父をもっているだけあって、アゲハはとても詳しかった。
「そんなことをしてたのか?」
カンタロウは初めて得る知識に、目を丸くする。
「うん。獣人に、鳥の翼やトカゲのしっぽなんかも合成させたみたいだよ。でもほとんどは死亡しちゃって、大問題になったみたい」
アゲハの話は、今まで聞いたこともない話だった。
大方、武帝国内で隠蔽されたのだろう。
「そうか……でも、それならなんで、クロワはシオンにそんなことをしようと考えたんだ?」
「たぶん、合成に成功したからじゃないかな? ほら、ビネビネって、どうみても猫と鳥を組み合わせた合成獣じゃん。動物実験でうまくいって、それで人間で試してみようと思ったんじゃない?」
「それで……そんなことであの子を……」
アゲハの憶測に、カンタロウはショックを受けた。
動物実験で成功したから、何も知らない少女に成果を試してみる。
自分達は絶対に傷つかない所で。
アゲハの言うことが、すべて正しいとは限らない。だが実際に、一人の少女が犠牲となった。
「マリアは、どうしてそんなことを許したんだろうな?」
カンタロウは、いまだに信じられない。
マリアは一見、とても普通の女の子だった。
カンタロウは、マリアに好意を抱いていた。
優しく、思いやりがあり、最初はシオンのことだって心配していた。
それがここへきて、裏返したように変わってしまった。
「それは本人に聞かないとわからないけど。マリアってさ。女神様は絶対だって、エリニスの信者として信じ込まされてる所があったからね。だから、彼女にとって、シオンを女神にすることは良いことなんだよ。もちろん、それが完璧に正しいってわけじゃないよ? でも、きっと、彼女も何かとてつもない辛さを抱えていたんだと思う。だから、何か大きなものに依存したいんだと思う。うまく言えないけど」
アゲハに言われてみれば、マリアは人にすぐ依存する性格だったような気がする。
あの傭兵達に騙されたのも、その依存心から来ているのかもしれない。
だから、自分達と別れることになると知ったとき、あれほど動揺し、取り乱したのではないか。
そう、カンタロウは考え、
「マリアのこと、何か知ってるのか?」
「うん。ツバメに聞いたんだけどさ。彼女は両親を亡くしてるの。盗賊に殺されて。シオンと二人っきりだったんだって。それで親戚の元に身を寄せてたみたい」
アゲハから聞いて、カンタロウの表情が暗く沈んだ。
「そう……なのか。そんなこと、知らなかったな。結局俺は、彼女のこと、何も知らなかったんだな」
カンタロウは暗い表情になった。座っている膝を寄せ、胸に抱える。
アゲハはそれ以上、何もしゃべらなかった。
沈黙が、二人に訪れた。
小さな蛾が、白熱灯の周りをクルクル回る。
地下通路は、何の物音もしない。
「……また、二人っきりになっちゃったね」
アゲハが沈黙を破る。
「そうだな。振りだしに戻ったな」
「あっ、ありがとね」
「うん? 何か言ったか?」
「だから、ありがとうって言ってんの」
「何が?」
「鈍いなぁ。私を守ってくれたこと」
アゲハの頬が、薄っすらと赤く染まる。
碧い瞳は、少し嬉しそうに微笑んだ。
シオンのパンドラック・ミクスから、守ってくれたお礼を言っているようだ。
カンタロウはそれに気づき、恥ずかしそうに顔を伏せる。
まさかアゲハが、そのことを覚えているとは思っていなかったからだ。
カンタロウは自分が言った台詞を思い出し、頭まで血流が上り、
「あっ、ああ。いいさ。アゲハが無事でよかった」
「逃げればよかったのに。私のこと置いてさ」
「そんなことはできないよ。俺は」
「……そっか」
再び沈黙。
だが、それは、長く続かなかった。
「ねえ、カンタロウ君。もし――私がエコーズだったらどうする?」
突然アゲハが、妙なことを聞いてきた。
当然カンタロウは驚き、顔を見つめる。
アゲハは膝を抱えた腕の中に、口元を埋めていた。
「このコスタリア大陸で、エコーズが自由に動き回れるのは、大帝国首都、中央政府があるエディンのみ。それ以外の地域に行くことは禁止されている。もし、犯罪を犯せば、同族であるエコーズの精鋭部隊が殲滅することになっている。つまりね。この大陸じゃ、エコーズを殺害することは――合法なの」
アゲハは淡々と、エコーズの現状について説明している。
カンタロウは黙って聞いていた。
「どうしてそうなったのかっていうと、やっぱり一代目コウダが起こした、大陸戦争が原因かな。最初はさ。エコーズに対する差別をなくすために立ち上がったのにね。ほら、エコーズって長寿だし、特殊能力者が多いじゃん? その生体を知りたくて、人身売買や死体を盗まれたりしてたんだよ。それに怒ったコウダが、戦争に同意した十神人を連れて、エコーズ達を救済したり、エトピリカ大陸に移住させたりしてたの。それがいつの間にか、コスタリア大陸を支配する方向に変わってしまっていた」
アゲハは天井を見上げる。
エコーズは昔、このコスタリア大陸で、普通に暮らしていた人種の一つだった。
もちろん、母大樹のあるエトピリカ大陸の方が、数は多い。
その頃は、王政もなく、国家として機能していなかった。
それを変えたのが、一代目コウダだった。
「五十年前のことだな」
「そう。だけど、一代目コウダの快進撃は十年と保てなかった。なぜなら、吸収式神脈装置が開発されたから。神脈結界レベル1で、コウダは身動きとれなくなり、あっさり死亡してしまった。その後を継いだ、二代目コウダも、結界に進軍を阻まれ、エトピリカ大陸まで後退を余儀なくされた。そして戦争を終わらせたのが、今の三代目コウダ。前に話したよね? ホーストホースのこと」
「ああ」
カンタロウがアゲハにうなずく。
ホーストホース。三代目コウダが作った魔物。
これが、戦争を終わらせるきっかけとなる。
三代目コウダは、二代目と違い、種族の温存を重視していた。
戦争で多くの同種を失い、絶滅の危機にあったのだ。
しかも、その頃から母大樹の調子が悪く、新しいエコーズの誕生が期待できなくなっていた。
現在はコオロギが言ったように、数千人程度しか生存していない。
つまり、小さな都市五個分の人口なのである。
アゲハは話を続け、
「戦争を終わらせたのはいいけど、エコーズに対する憎悪や差別は戦争前以上に膨れ上がった。それが一代目コウダの犯した最大の罪。エコーズが一生背負わされる罪」
戦争が終わった後、エコーズはコスタリア大陸から排斥され、エトピリカ大陸でしか暮らせなくなった。
吸収式神脈装置は、すでに普及率八十パーセントを超え、どの町や都市にもエコーズに対する対策が取られている。
さらにエコーズという種族の名前は、化け物として人々に知れ渡っていた。
すでにこの大陸に、住処はないのだ。
アゲハが目線を上にし、
「前に影無っていうエコーズと戦ったじゃん? 彼は平和条約に違反しているから、同族に殺されても文句は言えない。それに彼が自滅したのは、その死体を高く売買されるから。きっと自分の体を、他人に触れられたくなかったんだね。誇り高いエコーズだったから」
帝国平和条約の一つに、コスタリア大陸でエコーズが罪を犯した場合、リンドブルムは全面的に協力しなければならないという条文があった。
そのため、アゲハは同族である影無に容赦しなかったのだ。
それは、エコーズの性質にも影響されている。
一人一人が特殊能力を持ち、神獣召還を可能としているため、エコーズは例え同族でも、一緒の家に住む習慣がない。
人間のように雄と雌が家族となり、子を育てるという家族社会を形成しない。
子は皆で育て、ある程度成長すれば、放置という形が取られる。
女王社会である蟻のような昆虫に似ていた。
個人の不始末には異常に厳しい。
それは種族の維持の危機に繋がるからである。
影無が同じ同族に殺されても、犯罪者リストに名前が書かれている以上、自業自得として処理される。
それは、アゲハも同じことだった。
「もし、私がエコーズだったら。彼と同じ。同胞に見捨てられるし、カンタロウ君に殺されても、誰も同情してくれない。むしろ、カンタロウ君は誉められるんだよ。それは私自身の存在が――悪だってこと」
アゲハの説明は続く。
アゲハが現在、ここにいるという事実は、平和条約に違反する。
例え、神脈を持ち、奇跡の子として祭り上げられていたとしても、風向きはいつ変わるかわからない。
それは、根源的な恐怖。
「ねえ、カンタロウ君。もし私がエコーズだったらさ。逃げてたでしょ? 助けなくてもいいもんね。死体になったら高く売れるし、借金の足しになるんじゃないかな。まあそれ以前に、大事だもんね。他人の命より、自分の命のほうが。だからさ、今度あんな危ないことになったら、私のことを置いて……」
「逃げないよ。例え、アゲハがエコーズでも」
カンタロウの言葉に、自虐的になっていたアゲハが、「えっ?」と声をつまらせた。
「……どうして? エコーズでも?」
「うん」
「どうしてよ? 私がエコーズでも逃げないって……。なんでそこまでして、私に付き合うの?」
その理由が知りたいのか、アゲハはカンタロウの顔を、真っ直ぐ見つめた。
カンタロウは天井を見上げた。
茶色の蛾が、フラフラと飛んでいる。それは二匹いた。
「なんでかな……アゲハはどこか、俺と似ているからかな」
「似ている?」
「人を信用していないけど、どこかで信じようと足掻いている。人の悪意に触れて嫌になるけど、それでも前に進もうとしている。そういう所が俺と似ていて、少しだけ安心する」
「そうかな……私、そういう風に見えるかな?」
「ツバメに胸を触らせようとしたのも、マリアのためだろ?」
カンタロウはこの森に入る前、アゲハとツバメの様子を、しっかりと見ていた。
プライドの高いアゲハが、女好きのツバメに体を許すことはまず有り得ない。
何かの条件を提示された。
ツバメからマリアの事情を聞いたことから、それに関連する何かだと予想できる。
図星なのか、アゲハの顔が真っ赤になっていき、
「そっ、それは、マリアに同情しちゃったから。あの子も、私と同じ、孤独だったんだなって、思っちゃったから……」
ボソボソと、つぶやくようにしゃべるアゲハ。
「そうか。やっぱり、アゲハも孤独を抱えていたんだな」
意外な一面を知り、カンタロウは少し安心して笑った。
「あっ! ずるいぞ! 誘導尋問だ!」
「ははっ。悪かった。そんなつもりじゃなかったんだ」
「もう! 知らない!」
アゲハは恥ずかしさで、そっぽをむいた。
「……最初はさ。俺はアゲハのことを、得体の知れない奴だって思ってた。俺の事情を知って、まだくっついて来るもんな。コイツは馬鹿か、詐欺師だなって思ってたよ」
カンタロウが静かに話し始める。
アゲハは何も言わず、耳を立てた。
「だけど、アゲハと旅をしていくうちに、戦っていくうちに、きっと何か強い信念を持って行動しているんだろうと思った。その信念のために、残酷なことだってしていこうと、自分に誓ったんだろうと思った。自分自身を傷つけても、何か達成したい目的があるんだろ? それが何かは聞かないよ。俺を踏み台にしてでも、前に進んでいけばいい」
カンタロウからの予想外の言葉。
アゲハは、狐につままれたような気分になり、
「いいの? それで」
「いいさ。そういう奴ほどタフで死なない。もう仲間が死ぬのは見たくない。墓を作るのもうんざりだ。俺はこれからも危険な仕事をしていくだろうけど、アゲハとなら仲間としてやっていける」
カンタロウの本心。
アゲハを邪険に扱わない理由。
アゲハは大切なハンター仲間だった。
「だから、たとえアゲハがエコーズでも、俺は助けると思う。むしろ好都合だ。――優秀なパートナーに、自分の背中を預けられるからな」
カンタロウは白い歯をだして、笑顔になった。
アゲハに初めて見せた表情だった。人を信用できない者が、本気で人を信じたときに見せる感情が、そこには表れていた。
「……カンタロウ君」
アゲハはカンタロウの体に、身を寄せる。
「おっ、おい」
「はい、どぉん!」
アゲハは両手を使って、カンタロウを突き飛ばした。
「ぐわっ!」
カンタロウは煉瓦の壁に、頭を打った。
「何言ってるのか、わかんないぞ!」
アゲハは両手を腰にやり、堂々と言い放った。
「おっ、お前な……」
「つまり、どういうことなの? 男ってロマンチックなことばっかり言って、さっぱり意味わかんない」
「なぜ? 女が言うことより、わかりやすかったと思うんだが……」
カンタロウは打った頭を、手でさする。
「単純な話。私のことが好きだから、助けたいってことなの? このアゲハ様を、愛してるということなの? 好きか嫌いか、どっちなの?」
アゲハの弾丸のような話し方に、カンタロウの両目が踊る。
アゲハは両手を地面につき、顔を近づけせまってきた。
カンタロウの思考回路はまともに機能しなくなり、
「うんまあ……好きだから助けたいんだろうな」
「たとえエコーズでも?」
「ああ、エコーズでも」
「…………」
「…………」
しばらくの沈黙。
見つめ合う二人の間に、時間が流れる。
アゲハは耳たぶまで真っ赤になり、
「はい、どどぉん!」
再び、カンタロウを突き飛ばす。
「ぐはっ!」
また、カンタロウは壁に頭を打った。
「急に何言いだすの。そんなこと言われても、私、困るから」
「アゲハが言わせたんだろうが……」
さすがのカンタロウも、少しアゲハに怒っていた。
手で頭をさすり、目には痛さから涙を浮かべている。
アゲハは浮かれ、まったく気にも留めていなかった。
「でもまっ、君の気持ちはわかったよ。嬉しいぞ、カンタロウ君」
人差し指を口に当て、ニッと笑うアゲハ。
――母よ。やはり女というものは……魔物だ。
カンタロウは、複雑な心境だった。
「お兄たん!」
突然、シオンが二人に声をかけてきた。腕には猫を抱いている。
カンタロウが刀を持ち、
「どうした?」
「何か来る! 怖い!」
シオンが脅えている。その震えが伝わってくるのか、猫は一声も鳴かない。
赤い瞳で、二人を眺めている。
カンタロウはチリチリとした威圧感を感じ、通路の奥に急いで視線を移す。
通路の奥の、さらに奥の方から、何か巨大なものがやってきていた。
天井から粉のようなものが、降ってくる。
カンタロウの額から汗が流れ、
「何か……この気配。アゲハ」
「うん。これは……」
アゲハも気づいた。この気配の正体に。
「――鉄人だ」
アゲハの頬から、一筋の汗が流れ落ちた。
カンタロウが鼻を動かすと、カビと湿気の臭いがした。
まぶたに、淡い光が入ってくる。
目を開けると、フィラメントの灯りが、チラチラ燃えているのが見えた。
「う……ん?」
カンタロウの意識がはっきりしてくると、隣で誰かが会話している。
視線をむけると、アゲハとシオンが何かを話していた。
カンタロウはボウッと、その内容を聞いてみる。
「さっ、私のことを、アゲハお姉ちゃんと言え」
「アケハお姉たん?」
「アゲハお姉ちゃん」
「アデバお姉たん」
「ア・ゲ・ハ」
「ア・ビ・バ」
「……もうお姉たんでいいよ」
「お姉たん!」
シオンがアゲハに抱きついてくる。
アゲハはシオンを優しく受け止め、頭をなでなでしてやっていた。
もうこの短時間で、仲良くなったようだ。
「あ~。よしよし。おっ、気づいた?」
アゲハが倒れていたカンタロウに、話しかけてくる。
「……何してるんだ?」
カンタロウはボヤッとする頭に手を置き、上半身を起こした。
アゲハは両手を広げ、
「この子に社会の礼儀を教えてたの。覚えてくれないけど」
「あっ! お兄たん!」
シオンは小走りにカンタロウの元にむかうと、無邪気に抱きついてきた。
背中についた動物の骨が、ギシギシときしむ。
遠慮なしにカンタロウの胸に顔を埋めると、犬のようにくんくん匂いを嗅いでいた。
「おっと」
「いい匂い~。お兄たん」
シオンの白く長い髪が、カンタロウの腕をなでる。
はしゃいでいる目は、やはり赤い。
顔つきはマリアの妹だけあって、笑うと、とても愛らしく感じる。
――もう殺意がないのか。
カンタロウはシオンの頭をなでた。
この少女が、クロワや信者を皆殺しにし、この地にやってきたハンターを狂人化させ、ゴーストエコーズを操り、自分達を襲わせた張本人だとは、とても思えなかった。
しかし、事実、シオンは植物型神獣を召還し、アゲハにパンドラック・ミクスをかけようとした。
植物を操れることから、この森を生みだしたのもシオンなのだろう。
いったい何が起これば、この子にこんな巨大な力が宿るのか、まったくわからない。
カンタロウは振り向き、
「アゲハ、どうなってるんだ?」
「その子、私達を助けてくれたみたい。ゴーストエコーズなのに、変わってる」
アゲハもはっきりと、シオンをゴーストエコーズだと認めていた。
「ここは?」
カンタロウが周囲に視線をやる。
赤い煉瓦の壁には、白熱灯が灯っていた。
窓はどこにも見当たらない。
天井から、木の根っこのようなものが見える。
気温は低く、寒気がしてきた。
「教会の地下にある通路。電気はこの子に教えてもらって、私がつけたの。たぶん、クロワ達、ここから逃げようとしてたんじゃないかな?」
アゲハが予想する。
つまり、何かあったときのための、緊急用避難通路なのだ。
「この子が運んでくれたのか?」
「うん」
「……そうなのか」
アゲハから事情を聞き、カンタロウは改めて、シオンを見つめる。
――この子が、クロワ達を殺したんだろうな。
カンタロウはそう思うが、やはり、信じられない。
無垢な笑みを見せる少女が、人殺しを平然と行ったことを。
「まあ報いなんじゃないの。その子にひどいことしたさ」
アゲハがあっさりと、カンタロウに答えた。
「……よく俺の考えを読めるな」
「顔にでてる」
「そうか?」
カンタロウは自分の顔を、手で触れてみた。
さっきまで地面に倒れていたため、肌にくっついた小石がポロポロ取れた。
「ニャー」
翼のはえた猫が、三人の前で鳴く。
「あっ、ビネビネ。どこ行ってたんですか? お姉ちゃんのそばを離れちゃ駄目ですよ」
どうやら、翼のはえた猫の名前は、ビネビネというらしい。急にシオンは、お姉さん口調で、ビネビネに注意した。
ビネビネは、足で顔をかくことで応えた。
「ニャ」
ビネビネは気まぐれに、どこかに歩いて行ってしまう。
「あっ、こらっ。待ちなさい」
シオンはビネビネを追いかけていく。
「遠くに行っちゃ駄目だよ」
アゲハがシオンに声をかける。
「わかったぁ」
シオンはそう応えると、通路の奥へ行ってしまった。
「ふう、やれやれだね」
アゲハはシオンを見送ると、カンタロウの隣に座った。
長い金髪の間から、碧い獣の目がカンタロウを覗いてくる。
カンタロウはその綺麗な瞳で見られることに、恥ずかしさを感じ、目をそらして何か話すことはないか考え、
「……あの猫。ビネビネっていうのか?」
「そうみたい。変な名前だよね。たぶん、合成獣化の実験体として、研究所にいたんだと思う」
「ああいうのを、合成獣っていうのか?」
「そうだよ。昔、武帝国が考えた方法なの。大陸戦争時、より強靭な肉体と戦闘能力を得るために、考案されたんだけどね。拒絶反応が起こって、まったく使えなかったの。今じゃ、禁止されてる魔術」
さすが獣人の義父をもっているだけあって、アゲハはとても詳しかった。
「そんなことをしてたのか?」
カンタロウは初めて得る知識に、目を丸くする。
「うん。獣人に、鳥の翼やトカゲのしっぽなんかも合成させたみたいだよ。でもほとんどは死亡しちゃって、大問題になったみたい」
アゲハの話は、今まで聞いたこともない話だった。
大方、武帝国内で隠蔽されたのだろう。
「そうか……でも、それならなんで、クロワはシオンにそんなことをしようと考えたんだ?」
「たぶん、合成に成功したからじゃないかな? ほら、ビネビネって、どうみても猫と鳥を組み合わせた合成獣じゃん。動物実験でうまくいって、それで人間で試してみようと思ったんじゃない?」
「それで……そんなことであの子を……」
アゲハの憶測に、カンタロウはショックを受けた。
動物実験で成功したから、何も知らない少女に成果を試してみる。
自分達は絶対に傷つかない所で。
アゲハの言うことが、すべて正しいとは限らない。だが実際に、一人の少女が犠牲となった。
「マリアは、どうしてそんなことを許したんだろうな?」
カンタロウは、いまだに信じられない。
マリアは一見、とても普通の女の子だった。
カンタロウは、マリアに好意を抱いていた。
優しく、思いやりがあり、最初はシオンのことだって心配していた。
それがここへきて、裏返したように変わってしまった。
「それは本人に聞かないとわからないけど。マリアってさ。女神様は絶対だって、エリニスの信者として信じ込まされてる所があったからね。だから、彼女にとって、シオンを女神にすることは良いことなんだよ。もちろん、それが完璧に正しいってわけじゃないよ? でも、きっと、彼女も何かとてつもない辛さを抱えていたんだと思う。だから、何か大きなものに依存したいんだと思う。うまく言えないけど」
アゲハに言われてみれば、マリアは人にすぐ依存する性格だったような気がする。
あの傭兵達に騙されたのも、その依存心から来ているのかもしれない。
だから、自分達と別れることになると知ったとき、あれほど動揺し、取り乱したのではないか。
そう、カンタロウは考え、
「マリアのこと、何か知ってるのか?」
「うん。ツバメに聞いたんだけどさ。彼女は両親を亡くしてるの。盗賊に殺されて。シオンと二人っきりだったんだって。それで親戚の元に身を寄せてたみたい」
アゲハから聞いて、カンタロウの表情が暗く沈んだ。
「そう……なのか。そんなこと、知らなかったな。結局俺は、彼女のこと、何も知らなかったんだな」
カンタロウは暗い表情になった。座っている膝を寄せ、胸に抱える。
アゲハはそれ以上、何もしゃべらなかった。
沈黙が、二人に訪れた。
小さな蛾が、白熱灯の周りをクルクル回る。
地下通路は、何の物音もしない。
「……また、二人っきりになっちゃったね」
アゲハが沈黙を破る。
「そうだな。振りだしに戻ったな」
「あっ、ありがとね」
「うん? 何か言ったか?」
「だから、ありがとうって言ってんの」
「何が?」
「鈍いなぁ。私を守ってくれたこと」
アゲハの頬が、薄っすらと赤く染まる。
碧い瞳は、少し嬉しそうに微笑んだ。
シオンのパンドラック・ミクスから、守ってくれたお礼を言っているようだ。
カンタロウはそれに気づき、恥ずかしそうに顔を伏せる。
まさかアゲハが、そのことを覚えているとは思っていなかったからだ。
カンタロウは自分が言った台詞を思い出し、頭まで血流が上り、
「あっ、ああ。いいさ。アゲハが無事でよかった」
「逃げればよかったのに。私のこと置いてさ」
「そんなことはできないよ。俺は」
「……そっか」
再び沈黙。
だが、それは、長く続かなかった。
「ねえ、カンタロウ君。もし――私がエコーズだったらどうする?」
突然アゲハが、妙なことを聞いてきた。
当然カンタロウは驚き、顔を見つめる。
アゲハは膝を抱えた腕の中に、口元を埋めていた。
「このコスタリア大陸で、エコーズが自由に動き回れるのは、大帝国首都、中央政府があるエディンのみ。それ以外の地域に行くことは禁止されている。もし、犯罪を犯せば、同族であるエコーズの精鋭部隊が殲滅することになっている。つまりね。この大陸じゃ、エコーズを殺害することは――合法なの」
アゲハは淡々と、エコーズの現状について説明している。
カンタロウは黙って聞いていた。
「どうしてそうなったのかっていうと、やっぱり一代目コウダが起こした、大陸戦争が原因かな。最初はさ。エコーズに対する差別をなくすために立ち上がったのにね。ほら、エコーズって長寿だし、特殊能力者が多いじゃん? その生体を知りたくて、人身売買や死体を盗まれたりしてたんだよ。それに怒ったコウダが、戦争に同意した十神人を連れて、エコーズ達を救済したり、エトピリカ大陸に移住させたりしてたの。それがいつの間にか、コスタリア大陸を支配する方向に変わってしまっていた」
アゲハは天井を見上げる。
エコーズは昔、このコスタリア大陸で、普通に暮らしていた人種の一つだった。
もちろん、母大樹のあるエトピリカ大陸の方が、数は多い。
その頃は、王政もなく、国家として機能していなかった。
それを変えたのが、一代目コウダだった。
「五十年前のことだな」
「そう。だけど、一代目コウダの快進撃は十年と保てなかった。なぜなら、吸収式神脈装置が開発されたから。神脈結界レベル1で、コウダは身動きとれなくなり、あっさり死亡してしまった。その後を継いだ、二代目コウダも、結界に進軍を阻まれ、エトピリカ大陸まで後退を余儀なくされた。そして戦争を終わらせたのが、今の三代目コウダ。前に話したよね? ホーストホースのこと」
「ああ」
カンタロウがアゲハにうなずく。
ホーストホース。三代目コウダが作った魔物。
これが、戦争を終わらせるきっかけとなる。
三代目コウダは、二代目と違い、種族の温存を重視していた。
戦争で多くの同種を失い、絶滅の危機にあったのだ。
しかも、その頃から母大樹の調子が悪く、新しいエコーズの誕生が期待できなくなっていた。
現在はコオロギが言ったように、数千人程度しか生存していない。
つまり、小さな都市五個分の人口なのである。
アゲハは話を続け、
「戦争を終わらせたのはいいけど、エコーズに対する憎悪や差別は戦争前以上に膨れ上がった。それが一代目コウダの犯した最大の罪。エコーズが一生背負わされる罪」
戦争が終わった後、エコーズはコスタリア大陸から排斥され、エトピリカ大陸でしか暮らせなくなった。
吸収式神脈装置は、すでに普及率八十パーセントを超え、どの町や都市にもエコーズに対する対策が取られている。
さらにエコーズという種族の名前は、化け物として人々に知れ渡っていた。
すでにこの大陸に、住処はないのだ。
アゲハが目線を上にし、
「前に影無っていうエコーズと戦ったじゃん? 彼は平和条約に違反しているから、同族に殺されても文句は言えない。それに彼が自滅したのは、その死体を高く売買されるから。きっと自分の体を、他人に触れられたくなかったんだね。誇り高いエコーズだったから」
帝国平和条約の一つに、コスタリア大陸でエコーズが罪を犯した場合、リンドブルムは全面的に協力しなければならないという条文があった。
そのため、アゲハは同族である影無に容赦しなかったのだ。
それは、エコーズの性質にも影響されている。
一人一人が特殊能力を持ち、神獣召還を可能としているため、エコーズは例え同族でも、一緒の家に住む習慣がない。
人間のように雄と雌が家族となり、子を育てるという家族社会を形成しない。
子は皆で育て、ある程度成長すれば、放置という形が取られる。
女王社会である蟻のような昆虫に似ていた。
個人の不始末には異常に厳しい。
それは種族の維持の危機に繋がるからである。
影無が同じ同族に殺されても、犯罪者リストに名前が書かれている以上、自業自得として処理される。
それは、アゲハも同じことだった。
「もし、私がエコーズだったら。彼と同じ。同胞に見捨てられるし、カンタロウ君に殺されても、誰も同情してくれない。むしろ、カンタロウ君は誉められるんだよ。それは私自身の存在が――悪だってこと」
アゲハの説明は続く。
アゲハが現在、ここにいるという事実は、平和条約に違反する。
例え、神脈を持ち、奇跡の子として祭り上げられていたとしても、風向きはいつ変わるかわからない。
それは、根源的な恐怖。
「ねえ、カンタロウ君。もし私がエコーズだったらさ。逃げてたでしょ? 助けなくてもいいもんね。死体になったら高く売れるし、借金の足しになるんじゃないかな。まあそれ以前に、大事だもんね。他人の命より、自分の命のほうが。だからさ、今度あんな危ないことになったら、私のことを置いて……」
「逃げないよ。例え、アゲハがエコーズでも」
カンタロウの言葉に、自虐的になっていたアゲハが、「えっ?」と声をつまらせた。
「……どうして? エコーズでも?」
「うん」
「どうしてよ? 私がエコーズでも逃げないって……。なんでそこまでして、私に付き合うの?」
その理由が知りたいのか、アゲハはカンタロウの顔を、真っ直ぐ見つめた。
カンタロウは天井を見上げた。
茶色の蛾が、フラフラと飛んでいる。それは二匹いた。
「なんでかな……アゲハはどこか、俺と似ているからかな」
「似ている?」
「人を信用していないけど、どこかで信じようと足掻いている。人の悪意に触れて嫌になるけど、それでも前に進もうとしている。そういう所が俺と似ていて、少しだけ安心する」
「そうかな……私、そういう風に見えるかな?」
「ツバメに胸を触らせようとしたのも、マリアのためだろ?」
カンタロウはこの森に入る前、アゲハとツバメの様子を、しっかりと見ていた。
プライドの高いアゲハが、女好きのツバメに体を許すことはまず有り得ない。
何かの条件を提示された。
ツバメからマリアの事情を聞いたことから、それに関連する何かだと予想できる。
図星なのか、アゲハの顔が真っ赤になっていき、
「そっ、それは、マリアに同情しちゃったから。あの子も、私と同じ、孤独だったんだなって、思っちゃったから……」
ボソボソと、つぶやくようにしゃべるアゲハ。
「そうか。やっぱり、アゲハも孤独を抱えていたんだな」
意外な一面を知り、カンタロウは少し安心して笑った。
「あっ! ずるいぞ! 誘導尋問だ!」
「ははっ。悪かった。そんなつもりじゃなかったんだ」
「もう! 知らない!」
アゲハは恥ずかしさで、そっぽをむいた。
「……最初はさ。俺はアゲハのことを、得体の知れない奴だって思ってた。俺の事情を知って、まだくっついて来るもんな。コイツは馬鹿か、詐欺師だなって思ってたよ」
カンタロウが静かに話し始める。
アゲハは何も言わず、耳を立てた。
「だけど、アゲハと旅をしていくうちに、戦っていくうちに、きっと何か強い信念を持って行動しているんだろうと思った。その信念のために、残酷なことだってしていこうと、自分に誓ったんだろうと思った。自分自身を傷つけても、何か達成したい目的があるんだろ? それが何かは聞かないよ。俺を踏み台にしてでも、前に進んでいけばいい」
カンタロウからの予想外の言葉。
アゲハは、狐につままれたような気分になり、
「いいの? それで」
「いいさ。そういう奴ほどタフで死なない。もう仲間が死ぬのは見たくない。墓を作るのもうんざりだ。俺はこれからも危険な仕事をしていくだろうけど、アゲハとなら仲間としてやっていける」
カンタロウの本心。
アゲハを邪険に扱わない理由。
アゲハは大切なハンター仲間だった。
「だから、たとえアゲハがエコーズでも、俺は助けると思う。むしろ好都合だ。――優秀なパートナーに、自分の背中を預けられるからな」
カンタロウは白い歯をだして、笑顔になった。
アゲハに初めて見せた表情だった。人を信用できない者が、本気で人を信じたときに見せる感情が、そこには表れていた。
「……カンタロウ君」
アゲハはカンタロウの体に、身を寄せる。
「おっ、おい」
「はい、どぉん!」
アゲハは両手を使って、カンタロウを突き飛ばした。
「ぐわっ!」
カンタロウは煉瓦の壁に、頭を打った。
「何言ってるのか、わかんないぞ!」
アゲハは両手を腰にやり、堂々と言い放った。
「おっ、お前な……」
「つまり、どういうことなの? 男ってロマンチックなことばっかり言って、さっぱり意味わかんない」
「なぜ? 女が言うことより、わかりやすかったと思うんだが……」
カンタロウは打った頭を、手でさする。
「単純な話。私のことが好きだから、助けたいってことなの? このアゲハ様を、愛してるということなの? 好きか嫌いか、どっちなの?」
アゲハの弾丸のような話し方に、カンタロウの両目が踊る。
アゲハは両手を地面につき、顔を近づけせまってきた。
カンタロウの思考回路はまともに機能しなくなり、
「うんまあ……好きだから助けたいんだろうな」
「たとえエコーズでも?」
「ああ、エコーズでも」
「…………」
「…………」
しばらくの沈黙。
見つめ合う二人の間に、時間が流れる。
アゲハは耳たぶまで真っ赤になり、
「はい、どどぉん!」
再び、カンタロウを突き飛ばす。
「ぐはっ!」
また、カンタロウは壁に頭を打った。
「急に何言いだすの。そんなこと言われても、私、困るから」
「アゲハが言わせたんだろうが……」
さすがのカンタロウも、少しアゲハに怒っていた。
手で頭をさすり、目には痛さから涙を浮かべている。
アゲハは浮かれ、まったく気にも留めていなかった。
「でもまっ、君の気持ちはわかったよ。嬉しいぞ、カンタロウ君」
人差し指を口に当て、ニッと笑うアゲハ。
――母よ。やはり女というものは……魔物だ。
カンタロウは、複雑な心境だった。
「お兄たん!」
突然、シオンが二人に声をかけてきた。腕には猫を抱いている。
カンタロウが刀を持ち、
「どうした?」
「何か来る! 怖い!」
シオンが脅えている。その震えが伝わってくるのか、猫は一声も鳴かない。
赤い瞳で、二人を眺めている。
カンタロウはチリチリとした威圧感を感じ、通路の奥に急いで視線を移す。
通路の奥の、さらに奥の方から、何か巨大なものがやってきていた。
天井から粉のようなものが、降ってくる。
カンタロウの額から汗が流れ、
「何か……この気配。アゲハ」
「うん。これは……」
アゲハも気づいた。この気配の正体に。
「――鉄人だ」
アゲハの頬から、一筋の汗が流れ落ちた。