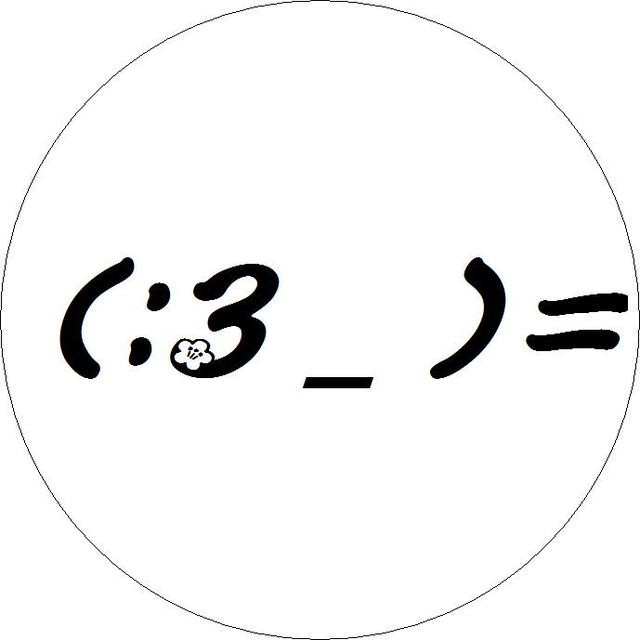月の魔都
文字数 8,522文字
*
カンタロウとアゲハは、橋の前で、マリアとランマルを待っていた。
橋はかずらでできており、橋の底に敷かれてあるのは木片だ。長い間、使われてなかったのか、腐食しずらいかずらも、黒ずみ始めている。床の木は、何本か間が抜けていた。
橋の下は崖で、底が暗くまったく見えない。
橋の長さは五十メートルほど。幅は一メートル以上はあるだろうか。
人が動くたびに、橋は大きく風で揺れる。
「大丈夫か! マリア!」
カンタロウが、橋に残されたマリアにむかって大声をだした。
「怖いですぅ。もう動けません~」
マリアは橋の真ん中で、動けず綱を持ったまま立ち尽くしていた。恐怖からか、両足がガクガク震えている。目は涙目になっていた。
「マリア。平気だよ、こんな橋。ほらほら」
アゲハがふざけ半分で、橋を手でバシバシ叩いた。
「やっ、やめてくださいっ! アゲハさんっ! 本気で怒りますよっ!」
普段は大人しいマリアも、さすがに怒鳴ってしまった。
「やだ。怖い」
アゲハは橋から手を離し、両腕を胸に抱え、脅えているポーズをしてみせた。
「アゲハ、やりすぎだ」
カンタロウがそれを注意した。
「この橋、まったく整備されてないな。……と、いうわけで、誰か助けて!」
ランマルはマリアのさらに後ろの、入り口部分で止まっていた。橋に座り込み、まったく動けないようだ。顔は真っ青になっている。
「もう。さっきまでの勢いはどうしたの? マリアより後ろじゃん!」
アゲハがランマルに活を入れた。
ランマルは手を振っただけで、何も答えなかった。
「あとマリアちゃん、一つ言っていいか?」
「はぁい、なんですかぁ、ランマルさん……」
「実はさっきから、風でスカートがめくれて、ちらちら下着が見えてるんだ。すまん」
「きゃああ! 何見てるんですかっ!」
マリアはすぐに橋に座りこんだ。
橋の木の間から、上昇風が吹き、マリアのスカートを押し上げていたようだ。
マリアは橋に集中していたため、まったく気づかなかった。
「だから、先に謝ったんだ。ごめんよ」
ランマルは言おうかどうか迷っていたが、結局言うことにした。
「ランマル兄さん。マリアの下着は何色?」
アゲハが手を上げて質問した。
「純白だ。しかもかなり――きわどい」
ランマルは正直に答えた。
「きゃ、セクシー」
アゲハは手を口に当て、悪戯っぽく笑っている。
「何言ってるんですかっ! もう嫌ですっ! 私、ここから落ちます!」
恥ずかしさから、マリアが無茶苦茶なことを言い始めた。
「はあ、仕方ない。アゲハ。飛翔魔法でランマルを助けてやってくれ。マリアは俺が助ける」
「えぇ~。やだ、疲れる」
「我慢しろ」
カンタロウはアゲハにそう言うと、橋を渡り始めた。
アゲハは口を尖らせたが、仕方なく赤眼化し、ランマルの元へと魔法の翼をはばたかせる。
「よっと、大丈夫か? マリア?」
軽く橋を渡ると、カンタロウはマリアのそばで腰を下ろした。
崖から風の唸りが聞こえてくる。
「はっ、はっ、はい。だだ大丈夫です」
「立ち上がれるか?」
「なななんとか」
「じゃ、俺の背中に乗れ」
カンタロウは背中をマリアにむける。
「嫌ですぅ」
マリアは首を、ブンブン横に振った。
「どうして?」
「私、男の人に下着……」
「俺は見てないから」
なんとかマリアを説得し、カンタロウの背中に乗せる。
「ちくしょう。もう少し若ければ、こんな橋余裕だったのに」
「都市でぬくぬくしてたからだろ? しっかりしてよね。ランマル兄さん」
「お恥ずかしいッス……」
アゲハに脇を抱えられながら、ランマルは情けなさで顔を手で覆った。
二人は無事、橋のむこう側に渡ることができた。
「うん?」
カンタロウがマリアを背負い、運んでいると、突然、木がきしむ音が聞こえてきた。
橋の腕木が折れ始めている。
橋がガクンと、一段下に落ちた。
――まずい! 橋が!
カンタロウが向かう、むこう側までまだ距離がある。
急がなくては、二人とも崖の底に転落する。
カンタロウが走ろうとした瞬間、入り口の腕木がボキリと折れた。
「えっ? あっ?」
橋が斜めに傾いた衝撃で、マリアはカンタロウから手を離してしまった。
暗い底へと、真っ逆さまに転落する。
手で何かを持とうと動かしてみても、空振りするだけだった。
「マリアっ!」
カンタロウはすぐに赤眼化し、マリアの腕をつかんだ。マリアの体重と重力が一気に、腕に負担をかける。
「きゃああ!」
「くっ!」
カンタロウは腕に力を込めると、マリアを抱き寄せ、横に抱えた。
マリアは怖さから、カンタロウの首に抱きつく。
「カンタロウ!」
「カンタロウ君!」
ランマルとアゲハが、むこう岸で叫んでいる。
「はっ!」
カンタロウは木片をうまく伝い、出口まで一息で飛びついた。
「おおっ、無事だったか! カンタロウ!」
「心配させて」
出口では、ランマルとアゲハが安堵の息を吐いた。
「…………」
マリアはまだカンタロウにしがみついていた。両目がぎゅっと閉じられ、何も聞こえていないようだ。
カンタロウは赤眼化を解除し、
「マリア」
「……えっ?」
カンタロウがマリアの耳元で囁き、ようやく我に返った。
「マリア。助かったぞ。よかったな。二人とも無事で」
「あっ。私」
マリアの腕の力が緩んだ。すぐそばには、カンタロウの顔がある。
「そうだ。助かったんだ」
カンタロウの表情が、女性のように柔和になる。
マリアはしばらく、それから目が離せなかった。
「はい。カンタロウ様」
マリアは花のように微笑んだ。
「おいおい。見せつけてくれるな。目が痛いぜ」
「ぼんやりしちゃって」
すっかり二人の世界に入っていたようだ。
マリアはアゲハとランマルの存在に、気づかなかった。まだカンタロウに抱えられていることも、忘れていた。
「あっ! ごっ、ごめんなさい!」
慌てて下りようとするマリア。
「いいさ。下りれるか?」
カンタロウは丁寧に、マリアを腕から下ろした。
「はい……」
マリアは少し未練が残っているのか、わざとゆっくりカンタロウから離れる。
「何マリア? ちょっと残念そうじゃん」
「違います! からかわないでください! アゲハさん!」
マリアは自分の本心を見破られ、アゲハからそっぽをむいた。
「ふっ、恐怖は、恋を燃え上がらせるのか」
「何それ? 哲学?」
「そう。ある意味、人生の」
ランマルはアゲハにうなずいていた。
橋を渡り終え、四人は森の中へと入った。
一応人が通る道があったみたいだが、緑の草で埋まってしまい、今ではまったく機能を喪失している。
歩くたびに、木の実が砕ける音がする。
道の脇では、破傘や薇など、山菜が我が物顔ではえていた。
マリアはまだ興奮が収まらないのか、頬が仄かに赤い。両手を前でぐっと組み、下をむいたまま歩いている。チラチラとカンタロウの方を見るが、当人はさっさと先を歩いていた。
「ねえねえマリア。どうして顔赤いの?」
マリアの頬が赤い理由を知りたいのか、アゲハが腕を引っ張った。
「そんなに赤くありませんよ。普通です」
マリアは努めて、冷静に答えた。まだ自分の気持ちを、カンタロウに知られるのが怖いのだ。しかし、頬の紅色は急には引かない。
「嘘だぁ。超赤いじゃん。ねえ、どうして?」
しつこく腕の服を引っ張るアゲハ。
「知りません!」
マリアはつい大声をだし、アゲハの手を振り払った。
「こらっ、やめろ。マリアが嫌がってる」
カンタロウがアゲハの頭上に、手刀をくらわした。
「てっ、何よぉ。ちょっと聞いただけじゃん」
アゲハは子供のように、口を尖らせる。
「人にはいろいろあるんだ」
「何よそれ? じゃ、カンタロウ君。マリアの下着見て、どう思ったの?」
アゲハは仕返しとばかりに、男が最も反応するであろう事を質問した。
「ひっ!」マリアが逆に反応し、急激に顔を沸騰させる。
「そうだな。俺は見ていないが。やはり母の方が――」
「あっ、もういい。やめろ」
カンタロウの無反応さを見て、これは使えないと判断し、アゲハは言葉を切った。
「なぜだ? まだすべてを言ってないぞ?」
「興味ないもん」
「聞けば興味がでてくる」
「絶対でないね。このマザコン」
「マザコンって言うな。親孝行と言え」
それからも、二人は雑談を続けた。
「…………」
マリアは会話に入れず、モジモジするしかなかった。
――マリアちゃん。やっぱりカンタロウのことが気になるんだなぁ。いじらしいっていうか、何ていうか。それに比べ、アゲハちゃんはズケズケ入ってくるな。
二人の女性の性格の違いを比べ、ランマルが三人の後ろで、独自の分析をしていた。
――あいつも乙女心ってのがわかってないからな。母親のことばっかり気にしてるし。
そんなことを考えていると、自分がまるでスズに相手にされていないことを思い出した。
「だが……俺が言える立場じゃないな」
ランマルは目頭を押さえると、天をむいた。
森を進んで行くと、緑の葉が土に積もっていた。
今は冬ではなく、太陽もでている。しかし、緑の葉をつけた木は、骨のような枯れ木に変わっていた。
土は乾燥し、所々にヒビが入っている。
――なんだ? 森が、枯れている?
カンタロウが異常な状況に気づいた。
他の三人も不気味な光景に、黙り込んでしまっている。
動物の物音も、鳥の鳴き声も、消えている。
寂しい風が、枯れた木の間をかけ抜ける。
緑の草すらはえず、虫のかさつく音もない。
「ここだ。ここで、コウタロウさんに出会ったんだ」
ランマルが懐かしそうに、緩やかな坂を見上げた。
昔は背の高い、緑の草がはえていた。
今は見る影もなく、乾いた土が風で転がっている。
カンタロウの顔つきが変わり、
「ランマル、父はまさか……」
「いや、違う。コウタロウさんは王の命令で、黒陽騎士団についていっただけだ。あの人は大火災の中、人助けをしてた」
釣瓶の城下町が、火災で燃え上がっている中、コウタロウは赤子を助けだしていた。ランマルはそれを、しみじみと話す。
「……そうか」
カンタロウは身体がほぐれるような、安堵感を感じた。
「もうすぐ町だ。形は残っていないと思うけどな」
ランマルはあの赤い炎を、思い出していた。
竜が吐く火柱のように、天にまで昇る火炎の嵐。
あの中で生きている者は誰もいないし、町は木片ですら残っていないだろう。
しかし、釣瓶の町は存在した。
町並みは木造建築で、幅の狭い通路を、水が何本も流れていた。
地面は石でできている。
水車もあり、音をたてながら回っていた。
「すごく綺麗な町じゃん」
アゲハの感想のとおり、家すべてが新築のように、痛んでいない。
水も綺麗に透き通っており、底まで丸見えだ。
まるで今町が出来上がったような、奇妙な感覚に捕らわれる。
「わあ、水が流れてる。さすが水源のある町ですね」
マリアが腰を下ろし、水を手に取ってみた。冷ややかで、さらりとした感触がある。
三人が町の景観に感心している中、ランマルだけが、顔中から汗を流していた。
「どうした? ランマル?」
カンタロウが真っ青になったランマルに、声をかけた。
「……馬鹿な。あの大火災だぞ? 町なんて残っているわけがない」
昔、ランマルがこの町を見たとき、炎がすべてを灰に変えようとしていた。
真夜中なのに、昼間のように明るく、寒い気温の中この辺りだけが、地獄の業火のように異常な熱さだった。
そんな大火災が、この町を燃やし尽くしていたというのに、黒い炭一つ見つからない。
アゲハが背伸びし、
「見間違いじゃないの?」
「いや、確かに俺は見た。黒陽騎士団が町に火を放ったんだ。それにあれから、もう十年以上はたってるんだ。町が残っているはずがない」
夢でも見ているかのように、ランマルは立ち尽くしたまま動かない。
――確かに、人の気配がしないな。
カンタロウは町の異様な静けさに、違和感を感じていた。
枯れた森に入ったときに感じた、嫌な気配も残ったままだ。
水車がカタカタと、骨を鳴らすように、無機質な音をたてる。
――気配がする。ここにいるな。あれが。
アゲハはエコーズの気配を、感じ取っていた。
目に見えない視線。体に突き刺さる殺意。
明らかに自分達は、この町に歓迎されていない。
「綺麗な水。透き通ってる」
マリアはまだ手に水をつけていた。
後ろの三人が、遠くに離れてしまっていることに、気づいていない。ふと、手に赤いものが触れた。
――赤い、水?
手でその赤いものをすくってみる。それはスルリとマリアの手から逃げ、水に溶けてしまう。
――なんだろう?
上流から、赤いものが流れている。
マリアは不思議に思い、上流へと歩いていった。
坂道を上り、石の道から外れた山側に、小さな池があった。
池は真っ赤に染まっていた。
何かのプランクトンかと思い、マリアは池に近づき、中を覗いてみる。自分の姿が池に映り、体を赤く染めていた。
池の中心に、何かがある。
波紋をたてながら、ゆらゆらと浮いている。
マリアはよく見ようと、目をパチパチさせ、
「あれは?」
池の周辺を歩きながら、浮いているものを追いかける。
だんだんそれが何か、わかってきた。
獣の毛に、ガタイのいい体。その人物には、ほんの数時間前に会っている。
それは、獣人、ライヤの死体だった。
「ひっ!」
マリアは小さく悲鳴を上げた。と同時に、何かにつまずいた。
「きゃっ?」
その場に転び、尻餅をつく。
「何……」
手に何かぬめっとした感触があった。
恐る恐る手を上げてみると、赤い血がべっとりとついている。
第一級ハンター、ラッハが仰向けに倒れていた。
「あっ……ああ……」
ラッハは断末魔を叫んだのか、大きく口を開けていた。腹は真っ赤に染まっている。鋭いもので何度も刺されたのだろう。鎧は粉々に破壊されていた。
死が蛆のように、にょろにょろとマリアの足を這った。
マリアはあまりのショックに、叫ぶことすら忘れ、その場から無意識に離れようと手を動かした。
手についた血が、ラッハのものでないことに、ようやく気づいた。
血の流れを目で追ってみると、山の土壁で、糸の切れた人形のように、座り込んでいる人物がいた。
エスリナだった。
「そんな……エスリナ……」
マリアは四つん這いになり、這うように地面を進んだ。
エスリナにたどりつき、右手で白い頬に触れてみる。すでに冷たくなっていて、目から生命の鼓動が消えていた。
「ようやく……あなたのこと……思い出したのに」
エスリナとはたった一度しか、会ったことがなかった。それはちょっとした出会い、挨拶程度の会話、そして別れ。
あまりの短さに、マリアはエスリナをすぐに忘却してしまった。
しかし、エスリナはマリアをよく覚えていた。もしかすると、エスリナの方から、話しかけてきたのかもしれない。
マリアは全身の力が抜けた。
恐怖、喪失、後悔、懺悔。
感情があまりにも自分の体内に流れこみ、容量を超えてしまったからだった。
虚ろな瞳で、マリアはエスリナを眺める。赤い血は背中から流れてきていた。
正面の体は、生きているかのように、傷一つない。
――えっ?
エスリナのお腹が、小刻みに動いている。
マリアがそれを何気に見ていると、突然、ボコッと膨れ上がった。そして、ゴボゴボと、エスリナの口から赤い液体が流れだす。
「何?」
エスリナのお腹が割れた。赤く、小さな両手が、腹をこじ開けようとしている。
「あっ……」
長い髪が垂れ、小さな口が動き、細い背中が腹からでてきた。それは全身を外界にだすと、ゆっくりとその場に立ち上がった。
赤い血塗れの少女が、呆然と座り込んでいるマリアを、見下ろしている。
――オネエチャン。
それは一言。そうマリアを呼んだ。
「あっ、ああっ……シオン……」
それは懐かしさだろうか。それとも、異様な者を見た恐怖からか。いや、もしかすると、愛らしいと思ったのかもしれない。
マリアは口元に笑みを浮かべ、一粒の涙を流していた。
赤い少女は、マリアにむかって、腕を振り上げた。腕はいつの間にか、鋭い剣に変わっていた。
マリアの白い頬に、剣から垂れた、赤い血が線を引く。
「マリア!」
少女の腕が刀で切り落とされた。少女は悲鳴を上げることもなく、何事もなかったように、立っている。
マリアの目に、刀を持った、カンタロウが見えた。
「カンタロウ……様」
「マリア! しっかりしろ! コイツは神獣だ!」
カンタロウはマリアを立ち上がらせ、その場から素早く逃げだした。
少女の姿をした神獣は、ゆっくりと視線をカンタロウ達にむかわせる。
マリアはもう一度、少女の姿を確認しようと、後ろを振りむいたとき、何かの声が聞こえてきて、
「この声は……」
「ハウリング・コール! 奴等が来るぞ! ランマル達と合流しよう!」
カンタロウはマリアの手を強く握った。そこから、暖かさ、血の脈動、力強さが伝わってくる。そして、血の濃厚な臭いが鼻腔をうるわし、封印していた現実感が蘇ってきた。
マリアが最後に後ろを振りむいたとき、そこにいたのは少女ではなく、顔のない神獣だった。
「うわっ! なんだ? この神獣の数は!」
「ちょっと! 数多すぎ!」
ランマルとアゲハは、あまりの神獣の数に焦っていた。
空からイカロス型の翼を持つ神獣が、舞い下りてくる。
地上からは剣を持つソード型、体の固いアーマー型、地面を素早く走るドッグ型が二人を囲い始めていた。
すべてを合わせて、もう五十近くは超えただろうか。
カンタロウがランマル達と合流し、
「マリアを連れてきた! この数じゃ、俺達が不利だ! いったん逃げよう!」
「よっ、よし! そうするか!」
カンタロウの提案に、ランマルは即賛成した。
四人は町の外にでるべく、出口にむかって走りだす。
先行はランマルとカンタロウが勤め、赤眼化して神獣達を蹴散らしていく。
「マリア? その血は?」
アゲハがマリアの頬についた、赤い血に気づいた。
「ラッハさん達の血です……」
「ラッハ? あっ、あのハンター達のこと? 神獣と戦っているの?」
「いえ……もうお亡くなりになっていました」
マリアの声が沈んだ。少なくとも、三人の死亡は確定している。
――えっ? そう簡単に死ぬような連中とは、思えなかったけど……。
アゲハは予想外の答えに、言葉をつまらせる。
特種エコーズの罠を見破る知恵。
自信に満ちた強さ。
そして、自分達を罠にはめる狡猾さ。
アゲハにとって、やっかいな敵はゴーストエコーズよりも、むしろラッハ達の方だった。
あまりにも呆気ない末路だ。
嫌な予感がアゲハの背筋を凍らし始める。
「もうすぐ町からでられるぞ!」
ランマルの言うとおり、町の外が見えてきた。
四人の体に、力が入る。
突如、白い膜が地上からあらわれた。
「なっ、なんだ?」
ランマルが立ち止まる。
白い膜は空高く上がっていくと、他の膜と繋がった。ちょうど町を覆う形になっている。
「これは……結界?」
アゲハが何度も見た光景だ。
神脈結界。
その結界の中では、神獣は活動できない。
――どうして? レベル1結界すらなかったのに……まさか。
アゲハは恐ろしい想像にたどりつき、愕然となった。もし、それが正しければ、ラッハ達が生き残れなかった理由も合点がいく。薄い氷を踏んでいるような、そんな気持ちになった。
「何にせよ助かったな。これで神獣なんて怖くな……いっ!」
ランマルは叫び、舌を噛みそうになった。
神獣は消失するどころか、さらに数を増している。
結界の神脈から、次々と生まれでてきているのだ。それは赤子のように結界の中から生まれ、羽虫の幼虫のようにわいてくる。
「結界から神獣が……」
カンタロウも信じられない光景に、自分の目を疑った。
「どっ、どんどんわいてでてくるぞ!」
「そんな、結界の中なのにっ!」
ランマルとマリアは、絶望した声を上げた。
――しまった。罠だ!
アゲハは唇を噛みしめた。
*
カンタロウ達から遠く離れた場所。
そこは結界の中だった。
ツネミツは罠にはまったハンター達を眺めながら、小さな声で呟く。
「普通、吸収式神脈装置は、結界内部の神脈を吸い取る方式のため、神脈そのものである神獣は活動ができない。しかし、昔、結界の外側の神脈を吸い取る方式の、吸収式神脈装置が開発されていた」
ツネミツは空を見上げた。結界から、翼のある神獣が、ボコボコ生まれている。
「その欠点は、結界の中で、神獣が自由に活動できるうえに、恐ろしいほどの数を生産してしまうこと。ゆえに外側吸収方式は不採用となり、今では開発されていない。開発者はその結界の名前を――『月の魔都』と名づけた」
ツネミツは今、体の奥底から気持ち良さを感じていた。
ちょこまかと逃げるネズミを、小さな檻に捕らえ、川に沈める残酷さ。
ネズミが水の中でもがき、逃げようとも檻の中からでられぬ絶望。
想像するだけでも、快感に満ち足りる。
「逃れられない――地獄へようこそ」
ツネミツは猫がネズミをじらすような、残酷な笑みを浮かべた。
カンタロウとアゲハは、橋の前で、マリアとランマルを待っていた。
橋はかずらでできており、橋の底に敷かれてあるのは木片だ。長い間、使われてなかったのか、腐食しずらいかずらも、黒ずみ始めている。床の木は、何本か間が抜けていた。
橋の下は崖で、底が暗くまったく見えない。
橋の長さは五十メートルほど。幅は一メートル以上はあるだろうか。
人が動くたびに、橋は大きく風で揺れる。
「大丈夫か! マリア!」
カンタロウが、橋に残されたマリアにむかって大声をだした。
「怖いですぅ。もう動けません~」
マリアは橋の真ん中で、動けず綱を持ったまま立ち尽くしていた。恐怖からか、両足がガクガク震えている。目は涙目になっていた。
「マリア。平気だよ、こんな橋。ほらほら」
アゲハがふざけ半分で、橋を手でバシバシ叩いた。
「やっ、やめてくださいっ! アゲハさんっ! 本気で怒りますよっ!」
普段は大人しいマリアも、さすがに怒鳴ってしまった。
「やだ。怖い」
アゲハは橋から手を離し、両腕を胸に抱え、脅えているポーズをしてみせた。
「アゲハ、やりすぎだ」
カンタロウがそれを注意した。
「この橋、まったく整備されてないな。……と、いうわけで、誰か助けて!」
ランマルはマリアのさらに後ろの、入り口部分で止まっていた。橋に座り込み、まったく動けないようだ。顔は真っ青になっている。
「もう。さっきまでの勢いはどうしたの? マリアより後ろじゃん!」
アゲハがランマルに活を入れた。
ランマルは手を振っただけで、何も答えなかった。
「あとマリアちゃん、一つ言っていいか?」
「はぁい、なんですかぁ、ランマルさん……」
「実はさっきから、風でスカートがめくれて、ちらちら下着が見えてるんだ。すまん」
「きゃああ! 何見てるんですかっ!」
マリアはすぐに橋に座りこんだ。
橋の木の間から、上昇風が吹き、マリアのスカートを押し上げていたようだ。
マリアは橋に集中していたため、まったく気づかなかった。
「だから、先に謝ったんだ。ごめんよ」
ランマルは言おうかどうか迷っていたが、結局言うことにした。
「ランマル兄さん。マリアの下着は何色?」
アゲハが手を上げて質問した。
「純白だ。しかもかなり――きわどい」
ランマルは正直に答えた。
「きゃ、セクシー」
アゲハは手を口に当て、悪戯っぽく笑っている。
「何言ってるんですかっ! もう嫌ですっ! 私、ここから落ちます!」
恥ずかしさから、マリアが無茶苦茶なことを言い始めた。
「はあ、仕方ない。アゲハ。飛翔魔法でランマルを助けてやってくれ。マリアは俺が助ける」
「えぇ~。やだ、疲れる」
「我慢しろ」
カンタロウはアゲハにそう言うと、橋を渡り始めた。
アゲハは口を尖らせたが、仕方なく赤眼化し、ランマルの元へと魔法の翼をはばたかせる。
「よっと、大丈夫か? マリア?」
軽く橋を渡ると、カンタロウはマリアのそばで腰を下ろした。
崖から風の唸りが聞こえてくる。
「はっ、はっ、はい。だだ大丈夫です」
「立ち上がれるか?」
「なななんとか」
「じゃ、俺の背中に乗れ」
カンタロウは背中をマリアにむける。
「嫌ですぅ」
マリアは首を、ブンブン横に振った。
「どうして?」
「私、男の人に下着……」
「俺は見てないから」
なんとかマリアを説得し、カンタロウの背中に乗せる。
「ちくしょう。もう少し若ければ、こんな橋余裕だったのに」
「都市でぬくぬくしてたからだろ? しっかりしてよね。ランマル兄さん」
「お恥ずかしいッス……」
アゲハに脇を抱えられながら、ランマルは情けなさで顔を手で覆った。
二人は無事、橋のむこう側に渡ることができた。
「うん?」
カンタロウがマリアを背負い、運んでいると、突然、木がきしむ音が聞こえてきた。
橋の腕木が折れ始めている。
橋がガクンと、一段下に落ちた。
――まずい! 橋が!
カンタロウが向かう、むこう側までまだ距離がある。
急がなくては、二人とも崖の底に転落する。
カンタロウが走ろうとした瞬間、入り口の腕木がボキリと折れた。
「えっ? あっ?」
橋が斜めに傾いた衝撃で、マリアはカンタロウから手を離してしまった。
暗い底へと、真っ逆さまに転落する。
手で何かを持とうと動かしてみても、空振りするだけだった。
「マリアっ!」
カンタロウはすぐに赤眼化し、マリアの腕をつかんだ。マリアの体重と重力が一気に、腕に負担をかける。
「きゃああ!」
「くっ!」
カンタロウは腕に力を込めると、マリアを抱き寄せ、横に抱えた。
マリアは怖さから、カンタロウの首に抱きつく。
「カンタロウ!」
「カンタロウ君!」
ランマルとアゲハが、むこう岸で叫んでいる。
「はっ!」
カンタロウは木片をうまく伝い、出口まで一息で飛びついた。
「おおっ、無事だったか! カンタロウ!」
「心配させて」
出口では、ランマルとアゲハが安堵の息を吐いた。
「…………」
マリアはまだカンタロウにしがみついていた。両目がぎゅっと閉じられ、何も聞こえていないようだ。
カンタロウは赤眼化を解除し、
「マリア」
「……えっ?」
カンタロウがマリアの耳元で囁き、ようやく我に返った。
「マリア。助かったぞ。よかったな。二人とも無事で」
「あっ。私」
マリアの腕の力が緩んだ。すぐそばには、カンタロウの顔がある。
「そうだ。助かったんだ」
カンタロウの表情が、女性のように柔和になる。
マリアはしばらく、それから目が離せなかった。
「はい。カンタロウ様」
マリアは花のように微笑んだ。
「おいおい。見せつけてくれるな。目が痛いぜ」
「ぼんやりしちゃって」
すっかり二人の世界に入っていたようだ。
マリアはアゲハとランマルの存在に、気づかなかった。まだカンタロウに抱えられていることも、忘れていた。
「あっ! ごっ、ごめんなさい!」
慌てて下りようとするマリア。
「いいさ。下りれるか?」
カンタロウは丁寧に、マリアを腕から下ろした。
「はい……」
マリアは少し未練が残っているのか、わざとゆっくりカンタロウから離れる。
「何マリア? ちょっと残念そうじゃん」
「違います! からかわないでください! アゲハさん!」
マリアは自分の本心を見破られ、アゲハからそっぽをむいた。
「ふっ、恐怖は、恋を燃え上がらせるのか」
「何それ? 哲学?」
「そう。ある意味、人生の」
ランマルはアゲハにうなずいていた。
橋を渡り終え、四人は森の中へと入った。
一応人が通る道があったみたいだが、緑の草で埋まってしまい、今ではまったく機能を喪失している。
歩くたびに、木の実が砕ける音がする。
道の脇では、破傘や薇など、山菜が我が物顔ではえていた。
マリアはまだ興奮が収まらないのか、頬が仄かに赤い。両手を前でぐっと組み、下をむいたまま歩いている。チラチラとカンタロウの方を見るが、当人はさっさと先を歩いていた。
「ねえねえマリア。どうして顔赤いの?」
マリアの頬が赤い理由を知りたいのか、アゲハが腕を引っ張った。
「そんなに赤くありませんよ。普通です」
マリアは努めて、冷静に答えた。まだ自分の気持ちを、カンタロウに知られるのが怖いのだ。しかし、頬の紅色は急には引かない。
「嘘だぁ。超赤いじゃん。ねえ、どうして?」
しつこく腕の服を引っ張るアゲハ。
「知りません!」
マリアはつい大声をだし、アゲハの手を振り払った。
「こらっ、やめろ。マリアが嫌がってる」
カンタロウがアゲハの頭上に、手刀をくらわした。
「てっ、何よぉ。ちょっと聞いただけじゃん」
アゲハは子供のように、口を尖らせる。
「人にはいろいろあるんだ」
「何よそれ? じゃ、カンタロウ君。マリアの下着見て、どう思ったの?」
アゲハは仕返しとばかりに、男が最も反応するであろう事を質問した。
「ひっ!」マリアが逆に反応し、急激に顔を沸騰させる。
「そうだな。俺は見ていないが。やはり母の方が――」
「あっ、もういい。やめろ」
カンタロウの無反応さを見て、これは使えないと判断し、アゲハは言葉を切った。
「なぜだ? まだすべてを言ってないぞ?」
「興味ないもん」
「聞けば興味がでてくる」
「絶対でないね。このマザコン」
「マザコンって言うな。親孝行と言え」
それからも、二人は雑談を続けた。
「…………」
マリアは会話に入れず、モジモジするしかなかった。
――マリアちゃん。やっぱりカンタロウのことが気になるんだなぁ。いじらしいっていうか、何ていうか。それに比べ、アゲハちゃんはズケズケ入ってくるな。
二人の女性の性格の違いを比べ、ランマルが三人の後ろで、独自の分析をしていた。
――あいつも乙女心ってのがわかってないからな。母親のことばっかり気にしてるし。
そんなことを考えていると、自分がまるでスズに相手にされていないことを思い出した。
「だが……俺が言える立場じゃないな」
ランマルは目頭を押さえると、天をむいた。
森を進んで行くと、緑の葉が土に積もっていた。
今は冬ではなく、太陽もでている。しかし、緑の葉をつけた木は、骨のような枯れ木に変わっていた。
土は乾燥し、所々にヒビが入っている。
――なんだ? 森が、枯れている?
カンタロウが異常な状況に気づいた。
他の三人も不気味な光景に、黙り込んでしまっている。
動物の物音も、鳥の鳴き声も、消えている。
寂しい風が、枯れた木の間をかけ抜ける。
緑の草すらはえず、虫のかさつく音もない。
「ここだ。ここで、コウタロウさんに出会ったんだ」
ランマルが懐かしそうに、緩やかな坂を見上げた。
昔は背の高い、緑の草がはえていた。
今は見る影もなく、乾いた土が風で転がっている。
カンタロウの顔つきが変わり、
「ランマル、父はまさか……」
「いや、違う。コウタロウさんは王の命令で、黒陽騎士団についていっただけだ。あの人は大火災の中、人助けをしてた」
釣瓶の城下町が、火災で燃え上がっている中、コウタロウは赤子を助けだしていた。ランマルはそれを、しみじみと話す。
「……そうか」
カンタロウは身体がほぐれるような、安堵感を感じた。
「もうすぐ町だ。形は残っていないと思うけどな」
ランマルはあの赤い炎を、思い出していた。
竜が吐く火柱のように、天にまで昇る火炎の嵐。
あの中で生きている者は誰もいないし、町は木片ですら残っていないだろう。
しかし、釣瓶の町は存在した。
町並みは木造建築で、幅の狭い通路を、水が何本も流れていた。
地面は石でできている。
水車もあり、音をたてながら回っていた。
「すごく綺麗な町じゃん」
アゲハの感想のとおり、家すべてが新築のように、痛んでいない。
水も綺麗に透き通っており、底まで丸見えだ。
まるで今町が出来上がったような、奇妙な感覚に捕らわれる。
「わあ、水が流れてる。さすが水源のある町ですね」
マリアが腰を下ろし、水を手に取ってみた。冷ややかで、さらりとした感触がある。
三人が町の景観に感心している中、ランマルだけが、顔中から汗を流していた。
「どうした? ランマル?」
カンタロウが真っ青になったランマルに、声をかけた。
「……馬鹿な。あの大火災だぞ? 町なんて残っているわけがない」
昔、ランマルがこの町を見たとき、炎がすべてを灰に変えようとしていた。
真夜中なのに、昼間のように明るく、寒い気温の中この辺りだけが、地獄の業火のように異常な熱さだった。
そんな大火災が、この町を燃やし尽くしていたというのに、黒い炭一つ見つからない。
アゲハが背伸びし、
「見間違いじゃないの?」
「いや、確かに俺は見た。黒陽騎士団が町に火を放ったんだ。それにあれから、もう十年以上はたってるんだ。町が残っているはずがない」
夢でも見ているかのように、ランマルは立ち尽くしたまま動かない。
――確かに、人の気配がしないな。
カンタロウは町の異様な静けさに、違和感を感じていた。
枯れた森に入ったときに感じた、嫌な気配も残ったままだ。
水車がカタカタと、骨を鳴らすように、無機質な音をたてる。
――気配がする。ここにいるな。あれが。
アゲハはエコーズの気配を、感じ取っていた。
目に見えない視線。体に突き刺さる殺意。
明らかに自分達は、この町に歓迎されていない。
「綺麗な水。透き通ってる」
マリアはまだ手に水をつけていた。
後ろの三人が、遠くに離れてしまっていることに、気づいていない。ふと、手に赤いものが触れた。
――赤い、水?
手でその赤いものをすくってみる。それはスルリとマリアの手から逃げ、水に溶けてしまう。
――なんだろう?
上流から、赤いものが流れている。
マリアは不思議に思い、上流へと歩いていった。
坂道を上り、石の道から外れた山側に、小さな池があった。
池は真っ赤に染まっていた。
何かのプランクトンかと思い、マリアは池に近づき、中を覗いてみる。自分の姿が池に映り、体を赤く染めていた。
池の中心に、何かがある。
波紋をたてながら、ゆらゆらと浮いている。
マリアはよく見ようと、目をパチパチさせ、
「あれは?」
池の周辺を歩きながら、浮いているものを追いかける。
だんだんそれが何か、わかってきた。
獣の毛に、ガタイのいい体。その人物には、ほんの数時間前に会っている。
それは、獣人、ライヤの死体だった。
「ひっ!」
マリアは小さく悲鳴を上げた。と同時に、何かにつまずいた。
「きゃっ?」
その場に転び、尻餅をつく。
「何……」
手に何かぬめっとした感触があった。
恐る恐る手を上げてみると、赤い血がべっとりとついている。
第一級ハンター、ラッハが仰向けに倒れていた。
「あっ……ああ……」
ラッハは断末魔を叫んだのか、大きく口を開けていた。腹は真っ赤に染まっている。鋭いもので何度も刺されたのだろう。鎧は粉々に破壊されていた。
死が蛆のように、にょろにょろとマリアの足を這った。
マリアはあまりのショックに、叫ぶことすら忘れ、その場から無意識に離れようと手を動かした。
手についた血が、ラッハのものでないことに、ようやく気づいた。
血の流れを目で追ってみると、山の土壁で、糸の切れた人形のように、座り込んでいる人物がいた。
エスリナだった。
「そんな……エスリナ……」
マリアは四つん這いになり、這うように地面を進んだ。
エスリナにたどりつき、右手で白い頬に触れてみる。すでに冷たくなっていて、目から生命の鼓動が消えていた。
「ようやく……あなたのこと……思い出したのに」
エスリナとはたった一度しか、会ったことがなかった。それはちょっとした出会い、挨拶程度の会話、そして別れ。
あまりの短さに、マリアはエスリナをすぐに忘却してしまった。
しかし、エスリナはマリアをよく覚えていた。もしかすると、エスリナの方から、話しかけてきたのかもしれない。
マリアは全身の力が抜けた。
恐怖、喪失、後悔、懺悔。
感情があまりにも自分の体内に流れこみ、容量を超えてしまったからだった。
虚ろな瞳で、マリアはエスリナを眺める。赤い血は背中から流れてきていた。
正面の体は、生きているかのように、傷一つない。
――えっ?
エスリナのお腹が、小刻みに動いている。
マリアがそれを何気に見ていると、突然、ボコッと膨れ上がった。そして、ゴボゴボと、エスリナの口から赤い液体が流れだす。
「何?」
エスリナのお腹が割れた。赤く、小さな両手が、腹をこじ開けようとしている。
「あっ……」
長い髪が垂れ、小さな口が動き、細い背中が腹からでてきた。それは全身を外界にだすと、ゆっくりとその場に立ち上がった。
赤い血塗れの少女が、呆然と座り込んでいるマリアを、見下ろしている。
――オネエチャン。
それは一言。そうマリアを呼んだ。
「あっ、ああっ……シオン……」
それは懐かしさだろうか。それとも、異様な者を見た恐怖からか。いや、もしかすると、愛らしいと思ったのかもしれない。
マリアは口元に笑みを浮かべ、一粒の涙を流していた。
赤い少女は、マリアにむかって、腕を振り上げた。腕はいつの間にか、鋭い剣に変わっていた。
マリアの白い頬に、剣から垂れた、赤い血が線を引く。
「マリア!」
少女の腕が刀で切り落とされた。少女は悲鳴を上げることもなく、何事もなかったように、立っている。
マリアの目に、刀を持った、カンタロウが見えた。
「カンタロウ……様」
「マリア! しっかりしろ! コイツは神獣だ!」
カンタロウはマリアを立ち上がらせ、その場から素早く逃げだした。
少女の姿をした神獣は、ゆっくりと視線をカンタロウ達にむかわせる。
マリアはもう一度、少女の姿を確認しようと、後ろを振りむいたとき、何かの声が聞こえてきて、
「この声は……」
「ハウリング・コール! 奴等が来るぞ! ランマル達と合流しよう!」
カンタロウはマリアの手を強く握った。そこから、暖かさ、血の脈動、力強さが伝わってくる。そして、血の濃厚な臭いが鼻腔をうるわし、封印していた現実感が蘇ってきた。
マリアが最後に後ろを振りむいたとき、そこにいたのは少女ではなく、顔のない神獣だった。
「うわっ! なんだ? この神獣の数は!」
「ちょっと! 数多すぎ!」
ランマルとアゲハは、あまりの神獣の数に焦っていた。
空からイカロス型の翼を持つ神獣が、舞い下りてくる。
地上からは剣を持つソード型、体の固いアーマー型、地面を素早く走るドッグ型が二人を囲い始めていた。
すべてを合わせて、もう五十近くは超えただろうか。
カンタロウがランマル達と合流し、
「マリアを連れてきた! この数じゃ、俺達が不利だ! いったん逃げよう!」
「よっ、よし! そうするか!」
カンタロウの提案に、ランマルは即賛成した。
四人は町の外にでるべく、出口にむかって走りだす。
先行はランマルとカンタロウが勤め、赤眼化して神獣達を蹴散らしていく。
「マリア? その血は?」
アゲハがマリアの頬についた、赤い血に気づいた。
「ラッハさん達の血です……」
「ラッハ? あっ、あのハンター達のこと? 神獣と戦っているの?」
「いえ……もうお亡くなりになっていました」
マリアの声が沈んだ。少なくとも、三人の死亡は確定している。
――えっ? そう簡単に死ぬような連中とは、思えなかったけど……。
アゲハは予想外の答えに、言葉をつまらせる。
特種エコーズの罠を見破る知恵。
自信に満ちた強さ。
そして、自分達を罠にはめる狡猾さ。
アゲハにとって、やっかいな敵はゴーストエコーズよりも、むしろラッハ達の方だった。
あまりにも呆気ない末路だ。
嫌な予感がアゲハの背筋を凍らし始める。
「もうすぐ町からでられるぞ!」
ランマルの言うとおり、町の外が見えてきた。
四人の体に、力が入る。
突如、白い膜が地上からあらわれた。
「なっ、なんだ?」
ランマルが立ち止まる。
白い膜は空高く上がっていくと、他の膜と繋がった。ちょうど町を覆う形になっている。
「これは……結界?」
アゲハが何度も見た光景だ。
神脈結界。
その結界の中では、神獣は活動できない。
――どうして? レベル1結界すらなかったのに……まさか。
アゲハは恐ろしい想像にたどりつき、愕然となった。もし、それが正しければ、ラッハ達が生き残れなかった理由も合点がいく。薄い氷を踏んでいるような、そんな気持ちになった。
「何にせよ助かったな。これで神獣なんて怖くな……いっ!」
ランマルは叫び、舌を噛みそうになった。
神獣は消失するどころか、さらに数を増している。
結界の神脈から、次々と生まれでてきているのだ。それは赤子のように結界の中から生まれ、羽虫の幼虫のようにわいてくる。
「結界から神獣が……」
カンタロウも信じられない光景に、自分の目を疑った。
「どっ、どんどんわいてでてくるぞ!」
「そんな、結界の中なのにっ!」
ランマルとマリアは、絶望した声を上げた。
――しまった。罠だ!
アゲハは唇を噛みしめた。
*
カンタロウ達から遠く離れた場所。
そこは結界の中だった。
ツネミツは罠にはまったハンター達を眺めながら、小さな声で呟く。
「普通、吸収式神脈装置は、結界内部の神脈を吸い取る方式のため、神脈そのものである神獣は活動ができない。しかし、昔、結界の外側の神脈を吸い取る方式の、吸収式神脈装置が開発されていた」
ツネミツは空を見上げた。結界から、翼のある神獣が、ボコボコ生まれている。
「その欠点は、結界の中で、神獣が自由に活動できるうえに、恐ろしいほどの数を生産してしまうこと。ゆえに外側吸収方式は不採用となり、今では開発されていない。開発者はその結界の名前を――『月の魔都』と名づけた」
ツネミツは今、体の奥底から気持ち良さを感じていた。
ちょこまかと逃げるネズミを、小さな檻に捕らえ、川に沈める残酷さ。
ネズミが水の中でもがき、逃げようとも檻の中からでられぬ絶望。
想像するだけでも、快感に満ち足りる。
「逃れられない――地獄へようこそ」
ツネミツは猫がネズミをじらすような、残酷な笑みを浮かべた。