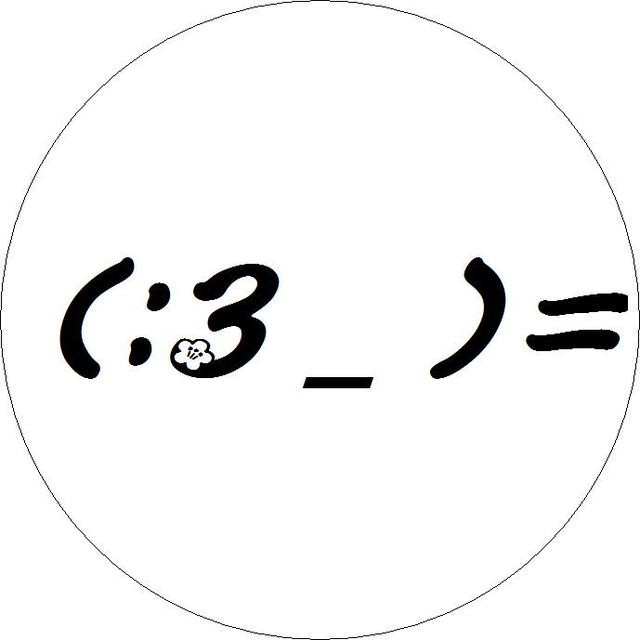植物の研究所
文字数 5,415文字
四人は何事もなく、森を抜け、研究施設にたどり着くことができた。
研究施設は四角の形をしており、五階建て、赤茶色い煉瓦で造られていて、大貴族の屋敷と同じぐらい大きい。
見た目は異常な姿をしていた。
マリアが研究所を、下から見上げ、
「ここが……研究所?」
森に囲まれたその施設は、緑や茶色の植物でびっしり埋め尽くされていた。
巨大化した茎や葉が、研究所を隠してしまっているのだ。
何十にも重なり、窓という窓をふさいでしまっていた。
「すごい植物だな。こんなの初めて見た」
カンタロウはあまりの姿に、呆然と見上げる。
「やだぁ。お化けでるんじゃない?」
お化け嫌いのアゲハは、その異様な姿に、イデリオ城と同じ反応をしている。
見た目が不気味なものが、苦手のようだ。
アゲハはカンタロウの隣に行くと、恐怖を感じた子供のように、がっしりとその体を抱きしめた。
「なんだい。アゲハはお化けが怖いのかい?」
「私は曖昧で、変なものが嫌いなんだ」
「おやおや。可愛い所あるじゃないか。カンタロウもモテモテだねぇ」
ツバメがカンタロウをからかってみるが、特に動揺はない。
「不本意だが、仕方ない」
カンタロウはアゲハの苦手なものを知っているので、平然としていた。
「……私も」
様子を見ていたマリアは、おずおずと挙手し、
「私も、お化け、怖いです」
カンタロウのことをチラリと見つめる。
目には、淡い期待感が込められていた。
自分もアゲハと同じように、カンタロウに付き添われたいようだ。
「仕方ないなぁ。じゃ、私と手を繋いでいいぞ」
アゲハがカンタロウの服をつかんだまま、手を伸ばす。
「……はい」
マリアはしばらくその手を見ていたが、諦めたように手を繋いだ。表情には落胆の色が見える。
「ぶふっ!」
ツバメがつい、息を吹き散らかした。
「なんですか? ツバメさん」
「別にぃ」
暗い目で見つめるマリアを、ツバメはしばらく笑っていた。
四人は入り口まで浸食している植物を、魔法で燃やし、何とか中に入ることができた。
中はヒヤリとしており、植物が窓を隠しているためか、かなり薄暗い。
廊下は石でできており、壁は赤い煉瓦が続く。
物音一つせず、外から森がざわめく声が入ってくる。
「うわぁ。まだ太陽があるのに、中は真っ暗」
マリアがあまりの暗さに、つい声が大きくなる。その声が施設に響く。
「最新式の設備だからね。電灯があるはずなんだけど、電気がきてないようだね。自家用発電が故障してるのかも」
ツバメは魔法でたいまつに火をつけると、三人に配った。
パチパチと音が響き、施設内で臭いも充満してしまうが、他に明かりがないので仕方ない。
皆植物に火が燃え移らないように、気をつけてたいまつを持った。
「ゴホッ」マリアが煙に当たり、つい咳込む。
「まずは吸収式神脈装置を起動させるよ。信者達を助けるのはその後だ。大丈夫、場所はこのあたしの頭に入ってるからね」
ツバメは自分の頭を、指でつつく。
施設内の地図は、すべてツバメの頭の中にあるようだ。
ビルヘンで大使徒から、研究所の完成図を見せてもらっていたので、よく知っていた。
「電気なしで、神脈装置は動くの?」
「神脈さえあれば、起動できる仕組みになってるからね」
アゲハの質問に、ツバメはすらすらと答えていく。
綿密な調査をしているのだろう。
こういうときは頼りになるなと、アゲハは思った。
廊下を歩いていくと、植物があらゆる所から侵入している。
茎が異常に太く、またいで通らなくては進めない植物もでてきた。
他にも、不気味な黒い花や、動物の歯のような鋭い棘を持った植物など、建物に多種の野草が寄生している。
マリアは汗をかいているのに、肌寒さを感じていた。
他の三人と比べて戦闘経験が浅いためか、不安を甘受しやすくなっている。
カンタロウの腕に飛びつきたいが、何が起こるかわからないため、我慢することにした。
「怖い~。カンタロウ君。私をおんぶしろ」
アゲハは不安をすぐに口にだし、カンタロウに甘え始める。
「嫌だ」
カンタロウも、状況が悪いためか、アゲハの甘えをすぐに拒否した。
「じゃあ、だっこしろ」
「嫌だ。何が起こるかわからん。我慢しろ」
カンタロウに甘えられず、アゲハは不安気な表情を隠せない。
そんな様子を見ていたマリアは、少しだけ同情の気持ちが生まれた。
シオンがここにいたら、自分は何をしてあげられるのか考えてみる。
「私でよければ、手を繋ぎましょうか?」
マリアの答えだった。
この状況で、おんぶやだっこはしてやれないが、手を繋ぐことなら簡単だ。
アゲハの不安が軽くなるのなら、自分は良いことをしていると思った。
「えっ? ほんと?」
「はい、いいですよ」
「やった、って!」
アゲハが喜ぶ前に、カンタロウの手刀が軽く頭を叩き、
「やめろ。そんなことしたら危険だ」
「じゃ、私のこの恐怖と不安は誰が癒してくれるんだよ」
アゲハが文句を言うと、カンタロウは手を差しだし、
「俺が手を繋いでやる。それでいいだろ?」
「手だけ?」
「手だけ」
「はぁ……まっ、いっか。それで妥協してやる」
アゲハは腰に両手をやると、偉そうに言った。
「お前は何様なんだ? っと?」
カンタロウの腕に、アゲハが飛びついてきた。
「へへぇ。腕取ったぁ」
「はぁ。しょうがない奴」
「私は実はお姫様なんだぞ。ちゃんとリードしろよ」
「了解。姫様」
アゲハは嬉しそうに、カンタロウの体に身を寄せる。笑顔が太陽のように眩しい。
アゲハを見ていると、カンタロウも気分が良いのか、優しく微笑んでいる。
――アゲハの奴、マリアと同じことしてるよ。
ツバメはアゲハの行動が、マリアから学ばれていると分析した。
「……むぅ」
マリアは二人の様子を見て、口を尖らせていた。
アゲハにかなり嫉妬しているようだ。同情してしまったことを、多少後悔している。
――マリアはマリアで、二人の関係が気になって仕方ないみたいだし。はぁ、ほんと、どうしよ。
ツバメはストレスからか、頭を何度も手でかいていた。
何かが動いた。
ツバメの手が止まる。
「うん? 何かいるね?」
廊下の先に、四本足の動物がいる。
赤い瞳が闇の中から、ギラリと輝いた。
「おっ、おっ、おっ、お化け?」
アゲハがカンタロウの体を、また抱きしめた。
「違う。猫だ。だけど……」
カンタロウがたいまつをむけてみる。
紫の毛色をした、猫がこちらを睨んでいた。
猫の背中には、鳥の羽のような、茶色い翼がついている。
――なんだ? あの猫。背中に翼がはえている?
カンタロウは一歩引く。
猫から、不気味な波動を感じる。
胸に、黒い何かが入り込むような不安。
カンタロウの手の平が、いつの間にか湿っていた。
「ニャア」
猫は一声鳴くと、二本足で立った。
「なっ!」
カンタロウは目を丸くした。
二本足で立つ猫を、今まで見たことがなかったからだ。
ただの偶然ではなく、猫は人間のように、バランス良く立っている。
「猫が……」
マリアの息がつまった。
「なんてこったい、猫が……」
ツバメも言葉をつまらせる。
「カンタロウ君、猫が……」
アゲハでさえ、言葉を失った。
「ああ、あの猫はどこかおかし」
「きゃわいいっ!」
「へっ?」
アゲハが飛び上がって喜ぶ姿に、カンタロウは唖然となった。
「こんな所に猫がいるなんて。可愛いですね」
マリアは満面な笑みで、猫を見つめる。
「ほんとだよ。何か、場が一気に和むね」
ツバメは腕を組み、うんうんとうなずいている。
「ほらほら、おいで。私の所に来い、猫」
アゲハはお化けのことも忘れて、腰を下ろすと、猫をちょいちょいと呼び寄せている。
「いっ、いや。猫が二本足で立っているのはいいのか?」
カンタロウが三人につっこんだが聞く耳をもたない。
三人とも猫に夢中になっているのだ。
「猫ちゃん、おいでぇ」
マリアは腰を下ろすと、手で猫を誘う。
「あっ、そういえば。あたしお菓子持ってたよ。えっと」
ツバメはポケットをまさぐった。
「猫、私の所に来い。可愛がってやるぞ」
アゲハはしびれを切らしたのか、猫を捕まえようと近づいた。
「ニャア」
猫は踵を返し、二本足で歩いて闇に消えていった。
最後に鳴いたのは、まるで「さようなら」と言ったようだった。
――猫が……人間のように歩いてる。
カンタロウの脳が情報を処理できず、真っ白になる。軽く頭痛がした。
「あっ、行っちゃいましたね……」
マリアが残念そうに、猫を見送る。
「あ~あ。せっかくお菓子やろうと思ったのに」
「しょうがない猫だな。まっ、可愛いから許してやるか」
ツバメとアゲハも、猫を追いかけようとまではしなかった。
「そうですね。あの猫を見てたら、怖いのもどっかに行っちゃいました」
マリアは可愛いものを見たためか、上機嫌になっている。
「やっぱり小動物は可愛いねぇ」
ツバメもそれに同意する。
「次あの猫見つけたら、絶対捕まえてやろうぜ」
アゲハはお化けの恐怖すらなくなったのか、さっさと廊下の先を進んでいく。
女性陣の猫に対する雑談は続いた。
静寂だった施設内に、女達の活気ある声が波紋のように広がっていく。
「……母よ。女という生き物がわからない」
カンタロウだけはその後ろで、こめかみを押さえていた。
廊下を歩いて行くと、ツバメが地下へと続く階段を見つけた。
下りていくと、そこには吸収式神脈装置が置かれていた。
数は二台だけだ。
研究施設は都市と比べると、面積をまったく取らないので、本機と予備機のみで十分なのだろう。
四人は装置の前に立ち尽くした。
「何もなく、ここまで来れましたね」
マリアが周りを見回した。
煉瓦の壁、神脈を吸収するための大きなポンプ、神脈を送る魔導管。
背丈よりも高い大きな鉄の箱の中には、神脈を魔力に変換する装置が入っている。
「うん。鉄人の気配もないしね」
アゲハがわざと、くんくんと鼻を動かして見せた。
「それはいいが。この装置は動かせるのか?」
カンタロウが鉄の箱を叩いてみる。
赤い錆がポロポロと落ちていく。
使用せず、定期メンテナンスもしていないため、かなり腐食が進んでいる。
「あたしに任せな」
ツバメは鉄の箱の扉を、平然と開けた。
普通、その中は技術者しか入れないように、鍵がかけられている。
鍵を壊して、扉を開けたようだ。
「ふむふむ。よしっ! この装置は動くね」
ツバメは中を一通り調べると、確信を持って言った。
カンタロウは驚き、
「わかるのか?」
「まあね。あたしは実は、この装置を運転した経験があるんだよ。まあ見てな」
ツバメが制御盤の前に立つと、ボタン操作をし始めた。
手つきに無駄がない。
手動で弁を開いていき、ポンプを動かした。
地下にポンプのけたたましい音が、響きだす。
「よし。これで装置が起動するはずだ」
ツバメが額の汗をぬぐう。
吸収式神脈装置の起動ランプが点灯し、鉄の箱の中から、装置の起動音が大きく唸った。
地面が軽く振動する。
室内温度上昇を避けるために、空調も起動した。
「うわっ、本当に起動したよ」
ツバメの行動を見張っていたアゲハは、目を白黒させた。
「すごい。ツバメさん。どうして普段は、そんなに駄目なんですか? もっとやる気をだしてください」
「一言多いねマリア。あたしにかかれば、こんな装置なんでもないんだよ」
マリアの嫌味も、軽く受け流すツバメ。
「すごいな。ツバメ。初めて尊敬した」
「やだよぉカンタロウっち。あたしがほしいだなんて。他の二人に悪いじゃないかい」
「うん? そんなことは、一言も言ってないぞ?」
ツバメの狂言に、カンタロウは顔をしかめた。
「そうだよ。耳膿んでんの?」
「耳、腐ってますよね?」
アゲハとマリアから、容赦のない野次が飛んでくる。
「ほら二人に嫉妬されたじゃないか。あたしがほしいんだったら、名前はカン子に改名して、女装しな」
「尊敬は取り消しだ。俺はお前を軽蔑する」
カンタロウは早くも、ツバメへの信頼を取り消した。
「冗談だよ。装置は起動できた。あと二十分で起動完了するからね。ここでじっとしてるのも暇だし、研究所を探索して、信者とクロワを探すよ。いいね?」
ツバメはカンタロウの胸を、軽く拳で叩く。
振る舞いは、戦友のように気安い。
ニヤニヤと笑っているが、一瞬だけ、真面目な表情をした。
「あっ、ああ」
ツバメの今までとは違う表情に、カンタロウは少し動揺した。
アゲハやマリアとは違う、大人びた表情。
経験豊富で、悲しみも、喜びも、苦しみさえも飲み込んだ大人の女性。
ふざけていたのが、すべて嘘のように思えてくる。
「よし。じゃ、行こうか」
ツバメは後ろをむくと、階段へと歩いていく。
「ねえ、ツバメってさ。いくつなの?」
アゲハが、ツバメの年齢を聞いた。
ちょっとだけ、ツバメに興味がわいたようだ。少なくとも、十代ではないだろう。
「あたし? あたしは十三歳さね」
ツバメは後ろむきのまま、右手を五本、左手を三本にして横に広げる。
アゲハは驚き、
「へぇ。すごく若いのに、よく知ってるんだ」
「まあね。があっはっはっはっはぁ!」
ツバメの大笑い。
カンタロウとマリアは怪訝な顔つきをむけている。
「どう考えても嘘だろ? 二十歳ぐらいだろ?」
「ええ。確実に、完璧に、嘘ですね」
カンタロウとマリアはツバメの言うことを、信じていなかった。
研究施設は四角の形をしており、五階建て、赤茶色い煉瓦で造られていて、大貴族の屋敷と同じぐらい大きい。
見た目は異常な姿をしていた。
マリアが研究所を、下から見上げ、
「ここが……研究所?」
森に囲まれたその施設は、緑や茶色の植物でびっしり埋め尽くされていた。
巨大化した茎や葉が、研究所を隠してしまっているのだ。
何十にも重なり、窓という窓をふさいでしまっていた。
「すごい植物だな。こんなの初めて見た」
カンタロウはあまりの姿に、呆然と見上げる。
「やだぁ。お化けでるんじゃない?」
お化け嫌いのアゲハは、その異様な姿に、イデリオ城と同じ反応をしている。
見た目が不気味なものが、苦手のようだ。
アゲハはカンタロウの隣に行くと、恐怖を感じた子供のように、がっしりとその体を抱きしめた。
「なんだい。アゲハはお化けが怖いのかい?」
「私は曖昧で、変なものが嫌いなんだ」
「おやおや。可愛い所あるじゃないか。カンタロウもモテモテだねぇ」
ツバメがカンタロウをからかってみるが、特に動揺はない。
「不本意だが、仕方ない」
カンタロウはアゲハの苦手なものを知っているので、平然としていた。
「……私も」
様子を見ていたマリアは、おずおずと挙手し、
「私も、お化け、怖いです」
カンタロウのことをチラリと見つめる。
目には、淡い期待感が込められていた。
自分もアゲハと同じように、カンタロウに付き添われたいようだ。
「仕方ないなぁ。じゃ、私と手を繋いでいいぞ」
アゲハがカンタロウの服をつかんだまま、手を伸ばす。
「……はい」
マリアはしばらくその手を見ていたが、諦めたように手を繋いだ。表情には落胆の色が見える。
「ぶふっ!」
ツバメがつい、息を吹き散らかした。
「なんですか? ツバメさん」
「別にぃ」
暗い目で見つめるマリアを、ツバメはしばらく笑っていた。
四人は入り口まで浸食している植物を、魔法で燃やし、何とか中に入ることができた。
中はヒヤリとしており、植物が窓を隠しているためか、かなり薄暗い。
廊下は石でできており、壁は赤い煉瓦が続く。
物音一つせず、外から森がざわめく声が入ってくる。
「うわぁ。まだ太陽があるのに、中は真っ暗」
マリアがあまりの暗さに、つい声が大きくなる。その声が施設に響く。
「最新式の設備だからね。電灯があるはずなんだけど、電気がきてないようだね。自家用発電が故障してるのかも」
ツバメは魔法でたいまつに火をつけると、三人に配った。
パチパチと音が響き、施設内で臭いも充満してしまうが、他に明かりがないので仕方ない。
皆植物に火が燃え移らないように、気をつけてたいまつを持った。
「ゴホッ」マリアが煙に当たり、つい咳込む。
「まずは吸収式神脈装置を起動させるよ。信者達を助けるのはその後だ。大丈夫、場所はこのあたしの頭に入ってるからね」
ツバメは自分の頭を、指でつつく。
施設内の地図は、すべてツバメの頭の中にあるようだ。
ビルヘンで大使徒から、研究所の完成図を見せてもらっていたので、よく知っていた。
「電気なしで、神脈装置は動くの?」
「神脈さえあれば、起動できる仕組みになってるからね」
アゲハの質問に、ツバメはすらすらと答えていく。
綿密な調査をしているのだろう。
こういうときは頼りになるなと、アゲハは思った。
廊下を歩いていくと、植物があらゆる所から侵入している。
茎が異常に太く、またいで通らなくては進めない植物もでてきた。
他にも、不気味な黒い花や、動物の歯のような鋭い棘を持った植物など、建物に多種の野草が寄生している。
マリアは汗をかいているのに、肌寒さを感じていた。
他の三人と比べて戦闘経験が浅いためか、不安を甘受しやすくなっている。
カンタロウの腕に飛びつきたいが、何が起こるかわからないため、我慢することにした。
「怖い~。カンタロウ君。私をおんぶしろ」
アゲハは不安をすぐに口にだし、カンタロウに甘え始める。
「嫌だ」
カンタロウも、状況が悪いためか、アゲハの甘えをすぐに拒否した。
「じゃあ、だっこしろ」
「嫌だ。何が起こるかわからん。我慢しろ」
カンタロウに甘えられず、アゲハは不安気な表情を隠せない。
そんな様子を見ていたマリアは、少しだけ同情の気持ちが生まれた。
シオンがここにいたら、自分は何をしてあげられるのか考えてみる。
「私でよければ、手を繋ぎましょうか?」
マリアの答えだった。
この状況で、おんぶやだっこはしてやれないが、手を繋ぐことなら簡単だ。
アゲハの不安が軽くなるのなら、自分は良いことをしていると思った。
「えっ? ほんと?」
「はい、いいですよ」
「やった、って!」
アゲハが喜ぶ前に、カンタロウの手刀が軽く頭を叩き、
「やめろ。そんなことしたら危険だ」
「じゃ、私のこの恐怖と不安は誰が癒してくれるんだよ」
アゲハが文句を言うと、カンタロウは手を差しだし、
「俺が手を繋いでやる。それでいいだろ?」
「手だけ?」
「手だけ」
「はぁ……まっ、いっか。それで妥協してやる」
アゲハは腰に両手をやると、偉そうに言った。
「お前は何様なんだ? っと?」
カンタロウの腕に、アゲハが飛びついてきた。
「へへぇ。腕取ったぁ」
「はぁ。しょうがない奴」
「私は実はお姫様なんだぞ。ちゃんとリードしろよ」
「了解。姫様」
アゲハは嬉しそうに、カンタロウの体に身を寄せる。笑顔が太陽のように眩しい。
アゲハを見ていると、カンタロウも気分が良いのか、優しく微笑んでいる。
――アゲハの奴、マリアと同じことしてるよ。
ツバメはアゲハの行動が、マリアから学ばれていると分析した。
「……むぅ」
マリアは二人の様子を見て、口を尖らせていた。
アゲハにかなり嫉妬しているようだ。同情してしまったことを、多少後悔している。
――マリアはマリアで、二人の関係が気になって仕方ないみたいだし。はぁ、ほんと、どうしよ。
ツバメはストレスからか、頭を何度も手でかいていた。
何かが動いた。
ツバメの手が止まる。
「うん? 何かいるね?」
廊下の先に、四本足の動物がいる。
赤い瞳が闇の中から、ギラリと輝いた。
「おっ、おっ、おっ、お化け?」
アゲハがカンタロウの体を、また抱きしめた。
「違う。猫だ。だけど……」
カンタロウがたいまつをむけてみる。
紫の毛色をした、猫がこちらを睨んでいた。
猫の背中には、鳥の羽のような、茶色い翼がついている。
――なんだ? あの猫。背中に翼がはえている?
カンタロウは一歩引く。
猫から、不気味な波動を感じる。
胸に、黒い何かが入り込むような不安。
カンタロウの手の平が、いつの間にか湿っていた。
「ニャア」
猫は一声鳴くと、二本足で立った。
「なっ!」
カンタロウは目を丸くした。
二本足で立つ猫を、今まで見たことがなかったからだ。
ただの偶然ではなく、猫は人間のように、バランス良く立っている。
「猫が……」
マリアの息がつまった。
「なんてこったい、猫が……」
ツバメも言葉をつまらせる。
「カンタロウ君、猫が……」
アゲハでさえ、言葉を失った。
「ああ、あの猫はどこかおかし」
「きゃわいいっ!」
「へっ?」
アゲハが飛び上がって喜ぶ姿に、カンタロウは唖然となった。
「こんな所に猫がいるなんて。可愛いですね」
マリアは満面な笑みで、猫を見つめる。
「ほんとだよ。何か、場が一気に和むね」
ツバメは腕を組み、うんうんとうなずいている。
「ほらほら、おいで。私の所に来い、猫」
アゲハはお化けのことも忘れて、腰を下ろすと、猫をちょいちょいと呼び寄せている。
「いっ、いや。猫が二本足で立っているのはいいのか?」
カンタロウが三人につっこんだが聞く耳をもたない。
三人とも猫に夢中になっているのだ。
「猫ちゃん、おいでぇ」
マリアは腰を下ろすと、手で猫を誘う。
「あっ、そういえば。あたしお菓子持ってたよ。えっと」
ツバメはポケットをまさぐった。
「猫、私の所に来い。可愛がってやるぞ」
アゲハはしびれを切らしたのか、猫を捕まえようと近づいた。
「ニャア」
猫は踵を返し、二本足で歩いて闇に消えていった。
最後に鳴いたのは、まるで「さようなら」と言ったようだった。
――猫が……人間のように歩いてる。
カンタロウの脳が情報を処理できず、真っ白になる。軽く頭痛がした。
「あっ、行っちゃいましたね……」
マリアが残念そうに、猫を見送る。
「あ~あ。せっかくお菓子やろうと思ったのに」
「しょうがない猫だな。まっ、可愛いから許してやるか」
ツバメとアゲハも、猫を追いかけようとまではしなかった。
「そうですね。あの猫を見てたら、怖いのもどっかに行っちゃいました」
マリアは可愛いものを見たためか、上機嫌になっている。
「やっぱり小動物は可愛いねぇ」
ツバメもそれに同意する。
「次あの猫見つけたら、絶対捕まえてやろうぜ」
アゲハはお化けの恐怖すらなくなったのか、さっさと廊下の先を進んでいく。
女性陣の猫に対する雑談は続いた。
静寂だった施設内に、女達の活気ある声が波紋のように広がっていく。
「……母よ。女という生き物がわからない」
カンタロウだけはその後ろで、こめかみを押さえていた。
廊下を歩いて行くと、ツバメが地下へと続く階段を見つけた。
下りていくと、そこには吸収式神脈装置が置かれていた。
数は二台だけだ。
研究施設は都市と比べると、面積をまったく取らないので、本機と予備機のみで十分なのだろう。
四人は装置の前に立ち尽くした。
「何もなく、ここまで来れましたね」
マリアが周りを見回した。
煉瓦の壁、神脈を吸収するための大きなポンプ、神脈を送る魔導管。
背丈よりも高い大きな鉄の箱の中には、神脈を魔力に変換する装置が入っている。
「うん。鉄人の気配もないしね」
アゲハがわざと、くんくんと鼻を動かして見せた。
「それはいいが。この装置は動かせるのか?」
カンタロウが鉄の箱を叩いてみる。
赤い錆がポロポロと落ちていく。
使用せず、定期メンテナンスもしていないため、かなり腐食が進んでいる。
「あたしに任せな」
ツバメは鉄の箱の扉を、平然と開けた。
普通、その中は技術者しか入れないように、鍵がかけられている。
鍵を壊して、扉を開けたようだ。
「ふむふむ。よしっ! この装置は動くね」
ツバメは中を一通り調べると、確信を持って言った。
カンタロウは驚き、
「わかるのか?」
「まあね。あたしは実は、この装置を運転した経験があるんだよ。まあ見てな」
ツバメが制御盤の前に立つと、ボタン操作をし始めた。
手つきに無駄がない。
手動で弁を開いていき、ポンプを動かした。
地下にポンプのけたたましい音が、響きだす。
「よし。これで装置が起動するはずだ」
ツバメが額の汗をぬぐう。
吸収式神脈装置の起動ランプが点灯し、鉄の箱の中から、装置の起動音が大きく唸った。
地面が軽く振動する。
室内温度上昇を避けるために、空調も起動した。
「うわっ、本当に起動したよ」
ツバメの行動を見張っていたアゲハは、目を白黒させた。
「すごい。ツバメさん。どうして普段は、そんなに駄目なんですか? もっとやる気をだしてください」
「一言多いねマリア。あたしにかかれば、こんな装置なんでもないんだよ」
マリアの嫌味も、軽く受け流すツバメ。
「すごいな。ツバメ。初めて尊敬した」
「やだよぉカンタロウっち。あたしがほしいだなんて。他の二人に悪いじゃないかい」
「うん? そんなことは、一言も言ってないぞ?」
ツバメの狂言に、カンタロウは顔をしかめた。
「そうだよ。耳膿んでんの?」
「耳、腐ってますよね?」
アゲハとマリアから、容赦のない野次が飛んでくる。
「ほら二人に嫉妬されたじゃないか。あたしがほしいんだったら、名前はカン子に改名して、女装しな」
「尊敬は取り消しだ。俺はお前を軽蔑する」
カンタロウは早くも、ツバメへの信頼を取り消した。
「冗談だよ。装置は起動できた。あと二十分で起動完了するからね。ここでじっとしてるのも暇だし、研究所を探索して、信者とクロワを探すよ。いいね?」
ツバメはカンタロウの胸を、軽く拳で叩く。
振る舞いは、戦友のように気安い。
ニヤニヤと笑っているが、一瞬だけ、真面目な表情をした。
「あっ、ああ」
ツバメの今までとは違う表情に、カンタロウは少し動揺した。
アゲハやマリアとは違う、大人びた表情。
経験豊富で、悲しみも、喜びも、苦しみさえも飲み込んだ大人の女性。
ふざけていたのが、すべて嘘のように思えてくる。
「よし。じゃ、行こうか」
ツバメは後ろをむくと、階段へと歩いていく。
「ねえ、ツバメってさ。いくつなの?」
アゲハが、ツバメの年齢を聞いた。
ちょっとだけ、ツバメに興味がわいたようだ。少なくとも、十代ではないだろう。
「あたし? あたしは十三歳さね」
ツバメは後ろむきのまま、右手を五本、左手を三本にして横に広げる。
アゲハは驚き、
「へぇ。すごく若いのに、よく知ってるんだ」
「まあね。があっはっはっはっはぁ!」
ツバメの大笑い。
カンタロウとマリアは怪訝な顔つきをむけている。
「どう考えても嘘だろ? 二十歳ぐらいだろ?」
「ええ。確実に、完璧に、嘘ですね」
カンタロウとマリアはツバメの言うことを、信じていなかった。