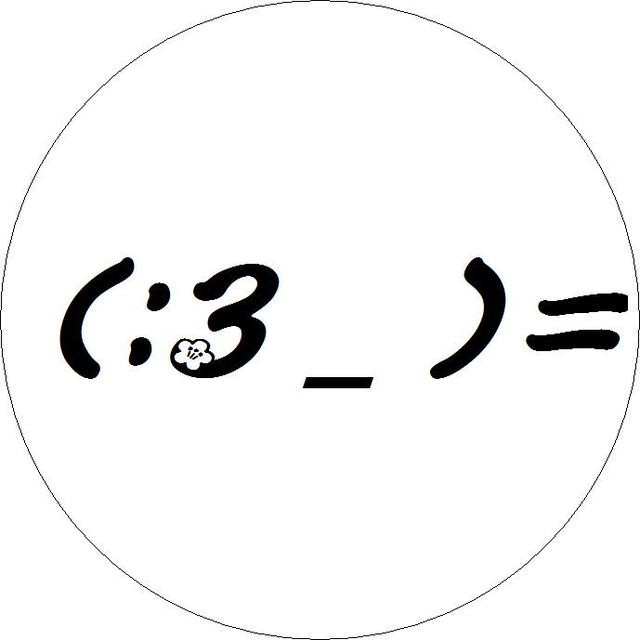酒場の傭兵達
文字数 8,582文字
その後、カンタロウはザクロからなんとか逃げだし、酒場をでて、ランマルの元にむかった。
マリアは自分もハンターであることを明かし、カンタロウの仕事を手伝うことになった。
その代わり、カンタロウはマリアの仕事を受けることにした。これで等価交換は成立した。
「私達に付き合っていいの? 急ぎの仕事じゃないの?」
「大丈夫です。時間はありませんが、三日程度なら我慢できます」
アゲハはマリアからそう聞くと、もう何も言わなかった。
「おうっ! 終わったか?」
家の壁に背中を預けていたランマルが、三人に手を振っている。
「ランマル、仕事が入った」
「えっ? そうなのか?」
「ああ」
「まっ、それなら、居酒屋で話を聞いてやるよ。いい所知ってるからな。それに……」
カンタロウからマリアに、視線を移すランマル。
「あっ、私、マリアといいます。よろしくお願いします。これからカンタロウさんに、お世話になる者です」
マリアは丁寧に、頭を下げた。
「……カンタロウ。若いから、何かと活力にあふれているのはわかる。だけどな。いい加減にしないと、ヒナゲシさんは悲しむと思うぞ?」
「どういう意味だ?」
ランマルが何を勘違いしているのか、カンタロウはよくわからなかった。
マリアがカンタロウの仕事を手伝ってくれるハンターだと説明され、ランマルはようやく納得した。
「なんだ。早く言えよ。まったく、ヒナゲシさんにどう説明しようか、本気で悩んじまった」
ランマルはそう笑いながら、なじみの居酒屋に三人を案内する。
途中、武器や防具、道具や果物屋など、店が連なる通りを歩くが、ほとんどが夜に備え、店を閉めていた。
「さすが都市。いろんな店があるね」
「都市の外にある市場よりも安いし、品質も安全だぞ」
ランマルがアゲハに、自慢気に説明する。
「へぇ、そうなんだ。ねえ、カンタロウ君。明日買い物に行こうよ」
アゲハがカンタロウの腕を引っ張る。
「明日は仕事だ。また今度な」
「えぇ~。やだぁ」
「やだじゃない。我慢しろ」
カンタロウに言われ、渋々引き下がるアゲハ。仏頂面になっている。
カンタロウは息を吐くと、ふと、都市の中心部に設置されている、銅像に目がいった。
そこは噴水が吹き上げ、市民の憩いの場になっているようだ。恋人達が、腕を組み歩いている。
銅像の人物は、中年の男性。頭には立派な冠、髭をはやし、フィールド・アーマーを着ている。
振り上げられた剣は、美しく装飾されていた。
足下に、人物の名前が掘られており、『英雄カストラル王』と読める。
――あれが、カストラルの銅像か。
カンタロウはその銅像を、初めて見た。
都市の中心に建てられたことから、相当国民に人気があったようだ。
カストラル前王は、無料の学校や騎士学校を建て、病院を充実させ、軍を強化し、都市の結界を強化させた実績がある。
広がった貧富の格差も、解消することを国民に約束していた。
しかし、現在でも貧富の差は広がり続け、現王はそのせいで、あまり人気がない。
――王は本当に、暴君だったのだろうか。父は本当に、偶然王を殺めてしまったのだろうか。
今のカンタロウに、父の真実を確かめるすべはない。
ランマルが言ったとおり、王は本当に他国に戦争をしかけていたのか。
すべてが曖昧模糊。
現場にいなかった自分は、蚊帳の外だ。
ただ残った現実は、自分の父が王を暗殺者から守れなかったという虚実。
「なんか立派じゃん」
銅像に見とれていたカンタロウに、アゲハが話かける。
カンタロウは我に返り、
「そうだな。それだけ、慕われてたんだろうな」
アゲハは道に転がっている石を持つと、悪戯っぽく笑い、
「これで傷でもつけとく?」
「やめろ」
カンタロウがアゲハの頭に、軽く手刀をくらわし、ランマルを追いかける。
「おうっ? もう。冗談だよ」
アゲハは石を捨てると、カンタロウの後ろを、小走りに追いかけた。
居酒屋に到着したときには、すでに太陽は沈み、夜になっていた。
四人は四角の木製の机を、囲んで座った。
酒場の中では、すでに傭兵や都市の住人が活気よく酒を飲んでいた。
都市の外と比べると、服装も良く、貧相さを感じさせない。
「よし、とりあえず、酒でも頼むか?」
やってきた女の給仕人にむかって、ランマルが注文をとり始めた。
「俺はいい。明日は仕事だ」
「私もいいです。飲めませんから……」
カンタロウは首を横に振り、マリアも手を振った。
「マリアさんていくつ?」
アゲハはなんとなく、マリアの年齢を聞いてみた。
「十六です」
「俺と同じ年だな」
「そうなんですか? なんか、偶然ですね」
「うん」
カンタロウと共通点があったというだけで、マリアは素直に喜んでいる。
アゲハはその態度が面白くないのか、マリアとの会話を切ってしまった。
「私は酒を頼むぞ」
「アゲハちゃんは何歳なんだ?」
「二十八だ」
ランマルに、正直に生存年齢を答えるアゲハ。
「嘘つけ。十四だろ」
「まあ、そういう設定になってる」
「設定ってなんだ?」
カンタロウに、人間世界での設定年齢を言われ、アゲハは周りがどういう反応するか期待した。
誰もがアゲハの年齢に違和感がないのか、まったくの無反応だった。
アゲハは少しがっかりした。
「十四か……まだ早いんじゃないか?」
ランマルの目には、アゲハはどう考えても成長途中の少女にしか見えていない。
「いいからいいから。酒程度じゃ、私は酔わないの」
「まあ、いいけど。あまり飲み過ぎるなよ。酒を二つ。それと水二つだ。あと食事もだしてくれ」
アゲハにおされ、ランマルは注文を取る。
「はい」給仕の女性は紙に注文内容を書くと、厨房へ引き下がった。
「さてと、仕事の内容を聞こうか?」
ランマルがカンタロウの仕事の内容を聞く態勢をとると、唐突に、毛皮を持った身なりのいい男がやってきて、
「兄ちゃん達、ハンターか? いい毛皮あるよ」
「いらねぇよ。あっちいってろ」
ランマルは商人を追い払った。
*
その後、カンタロウの話を聞き、ランマルは腕を組んだ。表情は真顔だった。
「……なるほど。あそこか。そういえば、ゴーストエコーズが出現しているとは聞くな」
「剣帝国から報酬金がでているらしい。何か聞いてないか?」
「いや、まあ……そうだろうな。あそこは、報酬金が高くなるはずだわな」
何かを知っているのか、ランマルは、カンタロウに何を言おうか迷いが見えた。
「どうしてよ?」
「まあ……いろいろあるんだよ。そうか、もうチャイルドマンの所にもいっていたか。危険だな。それなら保護者代表として、俺も仲間になってやるよ」
「ほんと暇なんだね。団長って」
「それを言うなよ。あっ、酒がきたな。よしっ、明日の仕事にむけて、乾杯だ!」
アゲハに痛い所をつっこまれ、ランマルはさっさと酒を口に含んでしまった。
酒の空瓶が三本増えたところで、顔を真っ赤にしたランマルが愚痴を言い始め、
「ふぅ。まったくスズの奴。初めて会ったときは、生意気な小娘だなと思ってたんだ。成長するたびに女らしくなりやがって。絶対、メスゴリラになると思ってたのに」
「あははっ、メスゴリラって。いい。その表現いい。私好き。でも、今でもメスゴリラじゃん」
アゲハも相当酔っていた。それなのにまた、給仕の女を呼びだし、酒を注文する。
「だぁはっはっはっ! アゲハちゃん。やっぱわかるだろ?」
ランマルは酒場に響くような、大笑いをした。他のお客も、酔いのピークに達しているので、あまり気にしていなかった。
「お前等。スズ姉に殺されるぞ」
「スズさんて、誰ですか?」
「俺の家族だよ。姉みたいなものかな」
「お強そうですね」
「まあね」
マリアは、アゲハとランマルにはかまわず、酔っていないカンタロウを中心として会話することにしているようだ。どうやら酔っ払いに、絡まれたくないらしい。
ランマルとアゲハは、二人だけで盛り上がり、
「ほんと。あれも、ヒナゲシさんの影響なんだろうな。ヒナゲシさん。いい女だもんな」
「ヒナゲシエキスを吸ったからかね?」
「ははっ! そうだな! そうとしか考えられん!」
マリアはさっそく、ヒナゲシという人物が気になり、カンタロウのほうを向き、
「ヒナゲシさんて、誰なんですか?」
「俺の母だ。スズ姉を女らしくさせるほどの――美人だ」
「へぇ。そうなんですか。一度会ってみたいです」
「そうか?」
「はい。会わせてください。ご挨拶したいです」
「ああ」
カンタロウの力強く、心地よい声。素直なしゃべり方。照れて笑う姿。
なぜフードで頭を覆い、布で口を隠しているのか理由はわからないが、マリアはカンタロウに好印象をもっていた。
「そんなにスズのことが好きならさぁ。告白しちゃえばいいじゃん。人を好きとか、告白とか、私は意味わかってないけど」
「うん? だけどなぁ。無理だと思うなぁ」
「どうしてよ?」
「あいつはさ。ヒナゲシさんのことが、好きなんだよ。なんかこう、説明できないが。友達以上の関係というか。あれだよ。あれ」
「どれどれ?」
「だから、あれなんだよ。もういいよ。俺のことは、ほっといてくれ」
ランマルはアゲハを無視し、机に顔を伏してしまった。
「なぁに、つまんなぁい。教えてよぉ」
しつこくランマルを揺するアゲハを、カンタロウが肩に手を置き止め、
「おいっ、飲み過ぎだ。アゲハ」
アゲハは肩から、カンタロウの手を払いのけ、
「うっさい! 私はお前よりお姉さんなんだぞ! だから、アゲハじゃなくて、アゲハさんって言え!」
アゲハは椅子に乗ると、カンタロウの前で仁王立ちした。それでようやく、カンタロウの目線より、少し上の立場になった。
「アゲハさん、ちょ、二人ともやめてください」
不穏な空気を感じ、マリアが間に入ろうとしたが、それをカンタロウが手を上げて制止する。
「今から私に土下座して謝れ! そして今後、アゲハ様と呼ぶと誓え! もしくは、アゲハ王女様でもよろしくてよっ!」
「ほう。わかった。すまなかったな。アゲハ様」
カンタロウはアゲハのこめかみに、両拳を置くと、グリグリしながら持ち上げた。
「きゃあああああ! 痛い! 痛い! いたぁい!」
あまりの痛さに、アゲハはすぐにカンタロウの腕をつかむ。引き剥がそうと必死になるが、酔っていて力が入らない。
「どうだ? 誠心誠意、謝ってるだろ?」
どう考えても、カンタロウは一言も謝っていなかった。
「ごめん! ごめん! 調子に乗りすぎた! もうやめて!」
「カンタロウさん。やりすぎです!」
マリアが制止に入って、ようやくカンタロウの拳がアゲハから離れた。
「ううっ……。カンタロウ君。これで勝ったと思うなよ!」
アゲハは悔し涙を浮かべ、その場にへたり込んだ。
「スズ……。あの笑顔は駄目だろ……。どうしてもっと早く気づかなかったんだ……俺の馬鹿……ちくしょう」
ランマルは独り言を、ぶつぶつと呟いていた。
「あれっ? マリアちゃんじゃない」
「あっ……」
酒場にいた四人の男が、マリアに話しかけてきた。
年齢は三十代あたり、鎧を着、腰に剣をつけている。四人ともいかつい顔をして、口元にはニヤニヤと笑みを浮かべていた。そのガタイのいい体格からして、主に戦闘を得意とする剣士だ。
――傭兵? 人間が四人か。
カンタロウは一目で、四人の職業を見抜いた。
マリアの表情が、明らかに険しくなる。
「へっへっへっ、昨日の夜は楽しくやってたのに、どうして逃げだしちゃったの?」
頭の頭頂部が禿げた傭兵の一人が、マリアの体に手を伸ばした。
「触らないでくださいっ!」
マリアはそれを、全身を使ってはねのけた。表情に嫌悪感があらわれている。
「おいおい。昨日はあんなに素直だったのに? どうしたの?」
「昨日は……あれは、あなた達が仲間になってくれるって言うから、我慢してたんです」
マリアの表情が曇る。どうやら知り合いのようだ。マリアの態度からして、会いたくもない傭兵達なのだろう。
「だから。仲間になるって言ってるのに」
「嘘です! 妹の事を話したら、口をつむぐじゃないですか! 行く気なんて、ないくせに!」
「悪かったよ。おじさん達、つい黙っちゃうんだ。だからね? 今から飲みなおそう。明日、絶対に妹さんを助けに行くから」
「行きません。私は、この方達と行くと決めましたから」
マリアは両手を胸に当て、視線でカンタロウ達を指した。
傭兵達が、カンタロウ達を血走った目で見下ろす。口から酒臭い臭いが、プンプンしてきた。四人とも相当飲んでいるようだ。
「この方? なんだ。ガキばっかりじゃねぇか。こんなひ弱な僕ちゃん達よりも、俺達の方が強いって。だから、行こうぜ」
素早い動きで、傭兵はマリアの腕を乱暴につかんだ。
よほどマリアのことが気に入っているのか、どんなことを言われようと躊躇がない。
「痛い! 嫌です! やめてください!」
マリアは男の手から逃れようと、必死で抵抗する。
カンタロウは鞘で、男の腕をしばいた。
「ぐわっ! なんだっ?」
男の手が、マリアから離れた。前腕が赤く腫れている。
「やめろ。嫌がってる」
「ふう。おいおい僕ちゃん。今、自分が何をしたかわかってるのか?」
茶髪の傭兵が、カンタロウを脅すように強い口調で言った。
四人の傭兵のリーダー格なのだろう。
偉そうな態度が、鼻につく。
「悪かったな。手がすべった」
「ふざけんじゃねぇ! てめぇ! よくも俺の腕を!」
頭の禿げた傭兵が、カンタロウに向かって、剣のグリップを握る。
「落ち着けって。ここは話し合いで解決しよう」
それを茶髪の傭兵が止める。長髪の髪をかき上げ、マリアをじろりと見た。
マリアは警戒心をあらわし、体を男からそらした。
「そこの女はね。盗賊なんだ」
傭兵の不意打ちに、マリアは呆然となった。
「なっ、何を……」
「嘘じゃない。その女は悪い女でね。旅人に取り入っては、隙を見て金品を盗む盗賊なんだ。たぶん、今日、その女は君達の仲間になったんじゃないか? それまでは、赤の他人だったはずだ」
「……確かに、今日この人達の仲間になりましたけど」
マリアは傭兵の罠だと知らず、認めてしまった。
茶髪の傭兵はニヤリと、汚らしい笑みを浮かべる。
「えっ?」
「ほらみろ。女も認めている」
アリアは男に誘導されたことに気づき、慌てふためき、
「待ってください! 私は盗賊なんかじゃありません!」
「なら、盗賊じゃないと、証明できる奴、いるか?」
傭兵が周りを見回した。
酒場はいつの間にか静かになり、皆が傭兵達とマリアの動向に注目していた。
剣帝国出身でもなく、外部から来た赤の他人であるマリアを、助ける者はいない。
誰も、マリアを盗賊ではないと、証明できる者はいなかった。
「いないだろ。まあ、盗賊であると証明もできない。がっ、俺達は昨日、そこの女が盗みを働いている現場を見ている」
「してません!」
「盗人はそう言うんだよ。みんな。まあ、証拠は明日見せるとして、これがどういうことか。若い君にわかるかな?」
マリアの息がつまった。どういうことか、わからない。
「つまり、盗賊をかばってる君達を、俺達は討伐できるってことだ。この剣を使ってね」
「えっ……それって……」
「ひひっ……」傭兵達が、皆剣を抜き始めた。
盗賊をかばうということは、同じ犯罪者と見なされるのだ。
都市の法律は犯罪者に厳しく、処刑は絶対。それを手助けした者も例外ではない。
「お客さん。やるなら外で、やってくれねぇか?」
色黒い酒場の主人が、腕を組んでやってきた。
「まだ話し合いの途中だ。もう少し待てよ」
茶髪の傭兵が、うっとおしそうな目つきで、主人を睨む。
「なあ、マリア。俺はお前のこと、気に入ってるんだ。嫁にしたいと思っている。だから、一緒に罪を償おう。なっ?」
どうやら、マリアを本気で自分の女にしたいようだ。語気に淀みがない。
「私……」
追いつめられたマリアは、顔を沈ませた。
「お前が俺達と来るなら、そこの酔っぱらいとガキは助けてやる。なっ、悪くないだろ?」
「ぶふふっ……」禿げた傭兵の男が、マリアの体を不純な視線で舐めまわす。兜をつけた傭兵は、赤い舌で剣の刃を舐めた。
「私は……私は……」
誰もが、マリアから視線を外した。よけいな事に、関わりたくない。表情から、そう読みとれる。
「マリア。さあ、どうする?」
マリアの右目から、一粒の涙が流れ、
「私……はい……あなたと行きます」
決意のあらわれなのか、両手を胸で握りしめる。
マリアは、カンタロウ達を助けることを選択した。
自分が犠牲になることを選んだのだ。
他人に迷惑をかけるよりも、それが一番正しいことだと信じていた。
「いい子だ。マリア。さあ、来いよ」
女を落とした満足感から、茶髪の傭兵は白い歯を剥きだして喜んだ。
マリアが傭兵達の元へ歩みだそうとしたとき、カンタロウがすっと、前にでてきた。
「カンタロウさん、いいんです。私、耐えられますから……」
「マリアは盗人じゃない。それを、俺は知っている」
カンタロウは今までの話を、すべてなかったことにした。
マリアは目をパチクリさせる。
茶髪の傭兵も、カンタロウの言い分に言葉がつまり、
「ふぅ。おいおい僕ちゃん。なら、その証拠はあるのか?」
「そんなものはない。どうせ、お前等だってないだろ?」
「はぁ。一応言っとくけど。俺達は傭兵だ。剣だって所持している。しかも、戦えるのがお前一人だとしたら、四対一だ。馬鹿じゃないとしたら、この状況はわかるよな?」
傭兵達の目つきが、血なま臭いものに変わった。それぞれが剣を構え、カンタロウを睨む。
酒場に殺気が、充満する。
「おっ、おい!」
酒場の主人は、さすがにまずいと思ったのか、語気を強める。
「黙ってろ! なあ僕ちゃん。そんな細い体で、俺達とやりあって、どちらが勝つか。わかるよな?」
傭兵の威嚇。
カンタロウはそんな緊迫した状況にもかかわらず、刀を鞘から抜かず、柄をにぎり、
「これでいい」
「はっ? 何それ?」
「これだけで、お前達を倒すのは十分だ」
カンタロウの言動に、傭兵達はきょとんとした。
「うわっ、コイツ! 頭おかしいぜ!」
「ヒーロー妄想か? そういうのは思春期だけにしとけ!」
「もうやっちまおうぜ!」
イライラし始めたのか、三人の傭兵が怒鳴った。
リーダーである茶髪の傭兵は、頭をポリポリかき、
「あぁ、めんどくせぇ。仕方ねぇ。おいお前等。殺さない程度にボコッとけ……」
返事がない。それどころか、床がガタリと響いた。その後、何事も起こらない。
「えっ?」
茶髪の傭兵が後ろをむくと、三人の傭兵が白目を剥いて倒れていた。
「あとはお前だけだ。三人をつれて帰れ」
カンタロウは刀の鞘を、肩に乗せた。
「なっ、えっ……何?」
何が起こったのかわからず、茶髪の傭兵は困惑している。
――すごい。あまりにも速くて、まったく見えなかった。
マリアはカンタロウの剣術に、呆然と立ち尽くす。
「おい! どうした? おいっ!」
茶髪の傭兵は、慌てて仲間の傭兵の体を揺らしてみるが、起きる気配がない。
頭には強打した跡があり、完全に気絶している。
茶髪の傭兵が、カンタロウを下から見上げた。
フードで隠された暗い表情から、赤い片目が見える。それが赤眼化だと、ようやく気づいた。
――コイツ、赤眼化所持者か!
茶髪の傭兵の背筋に寒気がはしる。
赤眼化できない自分は、圧倒的に不利。力の天秤が、カンタロウに傾いた。
「わかったよ……女はお前の好きにしろっ」
茶髪の傭兵は、気絶している仲間を置いて、さっさと酒場からでて行った。
「……カンタロウさん」
マリアがカンタロウに近づく。両目はしっとりと濡れていた。
「大丈夫か? あんなのは、ほっとけばいい」
「はい……」
カンタロウの黒い瞳に見つめられ、マリアの白い頬が赤く染まった。
「いいぞ兄ちゃん! かっこいい!」
「すげぇ! すげぇ、剣技だ! やるなぁ! まったく見えねぇ!」
「かっこいい彼氏を持って幸せだなぁ! 姉ちゃん羨ましいぜ!」
酒場の観客達は、カンタロウの鮮やかな剣技に拍手喝采を送った。
マリアは耳たぶまで真っ赤になり、
「ちっ、違います! 私とカンタロウさんは……」
マリアは慌てて弁解しようとした。
「もういいさ。でよう」
「はっ、はい!」
カンタロウに言われ、マリアは小さく飛び上がった。
「行くぞ、ランマル」
「んにゃ? まだのめるぞぉ、スズぅ」
呂律が回っていない。完璧に酔って、寝ていたようだ。
「よくこの状況で寝てられたな? 幸せな奴」
カンタロウは1つ息を吐く。
ランマルは大欠伸をして立ち上がると、お金を机に置いて、外にでていった。
次にアゲハの体を揺する。アゲハも机に伏していた。
「アゲハ、行くぞ」
アゲハはカンタロウに持ち上げられ、立ち上がる。軽いパンチが、カンタロウの腹に入り、
「なんだ?」
「別にぃ」
アゲハは意味深気に、楽しそうに笑った。
「ひゅうひゅう! 美人な彼女を、守ってやれよ!」
「結婚式には呼んでくれ!」
「俺もあんな若い美人と結婚してぇ!」
マリアはカンタロウの腕をつかみ、
「早く行きましょ! カンタロウさん!」
「あっ、ああ。そうだな」
マリアの白い肌は、まだ赤く火照っていた。
マリアは自分もハンターであることを明かし、カンタロウの仕事を手伝うことになった。
その代わり、カンタロウはマリアの仕事を受けることにした。これで等価交換は成立した。
「私達に付き合っていいの? 急ぎの仕事じゃないの?」
「大丈夫です。時間はありませんが、三日程度なら我慢できます」
アゲハはマリアからそう聞くと、もう何も言わなかった。
「おうっ! 終わったか?」
家の壁に背中を預けていたランマルが、三人に手を振っている。
「ランマル、仕事が入った」
「えっ? そうなのか?」
「ああ」
「まっ、それなら、居酒屋で話を聞いてやるよ。いい所知ってるからな。それに……」
カンタロウからマリアに、視線を移すランマル。
「あっ、私、マリアといいます。よろしくお願いします。これからカンタロウさんに、お世話になる者です」
マリアは丁寧に、頭を下げた。
「……カンタロウ。若いから、何かと活力にあふれているのはわかる。だけどな。いい加減にしないと、ヒナゲシさんは悲しむと思うぞ?」
「どういう意味だ?」
ランマルが何を勘違いしているのか、カンタロウはよくわからなかった。
マリアがカンタロウの仕事を手伝ってくれるハンターだと説明され、ランマルはようやく納得した。
「なんだ。早く言えよ。まったく、ヒナゲシさんにどう説明しようか、本気で悩んじまった」
ランマルはそう笑いながら、なじみの居酒屋に三人を案内する。
途中、武器や防具、道具や果物屋など、店が連なる通りを歩くが、ほとんどが夜に備え、店を閉めていた。
「さすが都市。いろんな店があるね」
「都市の外にある市場よりも安いし、品質も安全だぞ」
ランマルがアゲハに、自慢気に説明する。
「へぇ、そうなんだ。ねえ、カンタロウ君。明日買い物に行こうよ」
アゲハがカンタロウの腕を引っ張る。
「明日は仕事だ。また今度な」
「えぇ~。やだぁ」
「やだじゃない。我慢しろ」
カンタロウに言われ、渋々引き下がるアゲハ。仏頂面になっている。
カンタロウは息を吐くと、ふと、都市の中心部に設置されている、銅像に目がいった。
そこは噴水が吹き上げ、市民の憩いの場になっているようだ。恋人達が、腕を組み歩いている。
銅像の人物は、中年の男性。頭には立派な冠、髭をはやし、フィールド・アーマーを着ている。
振り上げられた剣は、美しく装飾されていた。
足下に、人物の名前が掘られており、『英雄カストラル王』と読める。
――あれが、カストラルの銅像か。
カンタロウはその銅像を、初めて見た。
都市の中心に建てられたことから、相当国民に人気があったようだ。
カストラル前王は、無料の学校や騎士学校を建て、病院を充実させ、軍を強化し、都市の結界を強化させた実績がある。
広がった貧富の格差も、解消することを国民に約束していた。
しかし、現在でも貧富の差は広がり続け、現王はそのせいで、あまり人気がない。
――王は本当に、暴君だったのだろうか。父は本当に、偶然王を殺めてしまったのだろうか。
今のカンタロウに、父の真実を確かめるすべはない。
ランマルが言ったとおり、王は本当に他国に戦争をしかけていたのか。
すべてが曖昧模糊。
現場にいなかった自分は、蚊帳の外だ。
ただ残った現実は、自分の父が王を暗殺者から守れなかったという虚実。
「なんか立派じゃん」
銅像に見とれていたカンタロウに、アゲハが話かける。
カンタロウは我に返り、
「そうだな。それだけ、慕われてたんだろうな」
アゲハは道に転がっている石を持つと、悪戯っぽく笑い、
「これで傷でもつけとく?」
「やめろ」
カンタロウがアゲハの頭に、軽く手刀をくらわし、ランマルを追いかける。
「おうっ? もう。冗談だよ」
アゲハは石を捨てると、カンタロウの後ろを、小走りに追いかけた。
居酒屋に到着したときには、すでに太陽は沈み、夜になっていた。
四人は四角の木製の机を、囲んで座った。
酒場の中では、すでに傭兵や都市の住人が活気よく酒を飲んでいた。
都市の外と比べると、服装も良く、貧相さを感じさせない。
「よし、とりあえず、酒でも頼むか?」
やってきた女の給仕人にむかって、ランマルが注文をとり始めた。
「俺はいい。明日は仕事だ」
「私もいいです。飲めませんから……」
カンタロウは首を横に振り、マリアも手を振った。
「マリアさんていくつ?」
アゲハはなんとなく、マリアの年齢を聞いてみた。
「十六です」
「俺と同じ年だな」
「そうなんですか? なんか、偶然ですね」
「うん」
カンタロウと共通点があったというだけで、マリアは素直に喜んでいる。
アゲハはその態度が面白くないのか、マリアとの会話を切ってしまった。
「私は酒を頼むぞ」
「アゲハちゃんは何歳なんだ?」
「二十八だ」
ランマルに、正直に生存年齢を答えるアゲハ。
「嘘つけ。十四だろ」
「まあ、そういう設定になってる」
「設定ってなんだ?」
カンタロウに、人間世界での設定年齢を言われ、アゲハは周りがどういう反応するか期待した。
誰もがアゲハの年齢に違和感がないのか、まったくの無反応だった。
アゲハは少しがっかりした。
「十四か……まだ早いんじゃないか?」
ランマルの目には、アゲハはどう考えても成長途中の少女にしか見えていない。
「いいからいいから。酒程度じゃ、私は酔わないの」
「まあ、いいけど。あまり飲み過ぎるなよ。酒を二つ。それと水二つだ。あと食事もだしてくれ」
アゲハにおされ、ランマルは注文を取る。
「はい」給仕の女性は紙に注文内容を書くと、厨房へ引き下がった。
「さてと、仕事の内容を聞こうか?」
ランマルがカンタロウの仕事の内容を聞く態勢をとると、唐突に、毛皮を持った身なりのいい男がやってきて、
「兄ちゃん達、ハンターか? いい毛皮あるよ」
「いらねぇよ。あっちいってろ」
ランマルは商人を追い払った。
*
その後、カンタロウの話を聞き、ランマルは腕を組んだ。表情は真顔だった。
「……なるほど。あそこか。そういえば、ゴーストエコーズが出現しているとは聞くな」
「剣帝国から報酬金がでているらしい。何か聞いてないか?」
「いや、まあ……そうだろうな。あそこは、報酬金が高くなるはずだわな」
何かを知っているのか、ランマルは、カンタロウに何を言おうか迷いが見えた。
「どうしてよ?」
「まあ……いろいろあるんだよ。そうか、もうチャイルドマンの所にもいっていたか。危険だな。それなら保護者代表として、俺も仲間になってやるよ」
「ほんと暇なんだね。団長って」
「それを言うなよ。あっ、酒がきたな。よしっ、明日の仕事にむけて、乾杯だ!」
アゲハに痛い所をつっこまれ、ランマルはさっさと酒を口に含んでしまった。
酒の空瓶が三本増えたところで、顔を真っ赤にしたランマルが愚痴を言い始め、
「ふぅ。まったくスズの奴。初めて会ったときは、生意気な小娘だなと思ってたんだ。成長するたびに女らしくなりやがって。絶対、メスゴリラになると思ってたのに」
「あははっ、メスゴリラって。いい。その表現いい。私好き。でも、今でもメスゴリラじゃん」
アゲハも相当酔っていた。それなのにまた、給仕の女を呼びだし、酒を注文する。
「だぁはっはっはっ! アゲハちゃん。やっぱわかるだろ?」
ランマルは酒場に響くような、大笑いをした。他のお客も、酔いのピークに達しているので、あまり気にしていなかった。
「お前等。スズ姉に殺されるぞ」
「スズさんて、誰ですか?」
「俺の家族だよ。姉みたいなものかな」
「お強そうですね」
「まあね」
マリアは、アゲハとランマルにはかまわず、酔っていないカンタロウを中心として会話することにしているようだ。どうやら酔っ払いに、絡まれたくないらしい。
ランマルとアゲハは、二人だけで盛り上がり、
「ほんと。あれも、ヒナゲシさんの影響なんだろうな。ヒナゲシさん。いい女だもんな」
「ヒナゲシエキスを吸ったからかね?」
「ははっ! そうだな! そうとしか考えられん!」
マリアはさっそく、ヒナゲシという人物が気になり、カンタロウのほうを向き、
「ヒナゲシさんて、誰なんですか?」
「俺の母だ。スズ姉を女らしくさせるほどの――美人だ」
「へぇ。そうなんですか。一度会ってみたいです」
「そうか?」
「はい。会わせてください。ご挨拶したいです」
「ああ」
カンタロウの力強く、心地よい声。素直なしゃべり方。照れて笑う姿。
なぜフードで頭を覆い、布で口を隠しているのか理由はわからないが、マリアはカンタロウに好印象をもっていた。
「そんなにスズのことが好きならさぁ。告白しちゃえばいいじゃん。人を好きとか、告白とか、私は意味わかってないけど」
「うん? だけどなぁ。無理だと思うなぁ」
「どうしてよ?」
「あいつはさ。ヒナゲシさんのことが、好きなんだよ。なんかこう、説明できないが。友達以上の関係というか。あれだよ。あれ」
「どれどれ?」
「だから、あれなんだよ。もういいよ。俺のことは、ほっといてくれ」
ランマルはアゲハを無視し、机に顔を伏してしまった。
「なぁに、つまんなぁい。教えてよぉ」
しつこくランマルを揺するアゲハを、カンタロウが肩に手を置き止め、
「おいっ、飲み過ぎだ。アゲハ」
アゲハは肩から、カンタロウの手を払いのけ、
「うっさい! 私はお前よりお姉さんなんだぞ! だから、アゲハじゃなくて、アゲハさんって言え!」
アゲハは椅子に乗ると、カンタロウの前で仁王立ちした。それでようやく、カンタロウの目線より、少し上の立場になった。
「アゲハさん、ちょ、二人ともやめてください」
不穏な空気を感じ、マリアが間に入ろうとしたが、それをカンタロウが手を上げて制止する。
「今から私に土下座して謝れ! そして今後、アゲハ様と呼ぶと誓え! もしくは、アゲハ王女様でもよろしくてよっ!」
「ほう。わかった。すまなかったな。アゲハ様」
カンタロウはアゲハのこめかみに、両拳を置くと、グリグリしながら持ち上げた。
「きゃあああああ! 痛い! 痛い! いたぁい!」
あまりの痛さに、アゲハはすぐにカンタロウの腕をつかむ。引き剥がそうと必死になるが、酔っていて力が入らない。
「どうだ? 誠心誠意、謝ってるだろ?」
どう考えても、カンタロウは一言も謝っていなかった。
「ごめん! ごめん! 調子に乗りすぎた! もうやめて!」
「カンタロウさん。やりすぎです!」
マリアが制止に入って、ようやくカンタロウの拳がアゲハから離れた。
「ううっ……。カンタロウ君。これで勝ったと思うなよ!」
アゲハは悔し涙を浮かべ、その場にへたり込んだ。
「スズ……。あの笑顔は駄目だろ……。どうしてもっと早く気づかなかったんだ……俺の馬鹿……ちくしょう」
ランマルは独り言を、ぶつぶつと呟いていた。
「あれっ? マリアちゃんじゃない」
「あっ……」
酒場にいた四人の男が、マリアに話しかけてきた。
年齢は三十代あたり、鎧を着、腰に剣をつけている。四人ともいかつい顔をして、口元にはニヤニヤと笑みを浮かべていた。そのガタイのいい体格からして、主に戦闘を得意とする剣士だ。
――傭兵? 人間が四人か。
カンタロウは一目で、四人の職業を見抜いた。
マリアの表情が、明らかに険しくなる。
「へっへっへっ、昨日の夜は楽しくやってたのに、どうして逃げだしちゃったの?」
頭の頭頂部が禿げた傭兵の一人が、マリアの体に手を伸ばした。
「触らないでくださいっ!」
マリアはそれを、全身を使ってはねのけた。表情に嫌悪感があらわれている。
「おいおい。昨日はあんなに素直だったのに? どうしたの?」
「昨日は……あれは、あなた達が仲間になってくれるって言うから、我慢してたんです」
マリアの表情が曇る。どうやら知り合いのようだ。マリアの態度からして、会いたくもない傭兵達なのだろう。
「だから。仲間になるって言ってるのに」
「嘘です! 妹の事を話したら、口をつむぐじゃないですか! 行く気なんて、ないくせに!」
「悪かったよ。おじさん達、つい黙っちゃうんだ。だからね? 今から飲みなおそう。明日、絶対に妹さんを助けに行くから」
「行きません。私は、この方達と行くと決めましたから」
マリアは両手を胸に当て、視線でカンタロウ達を指した。
傭兵達が、カンタロウ達を血走った目で見下ろす。口から酒臭い臭いが、プンプンしてきた。四人とも相当飲んでいるようだ。
「この方? なんだ。ガキばっかりじゃねぇか。こんなひ弱な僕ちゃん達よりも、俺達の方が強いって。だから、行こうぜ」
素早い動きで、傭兵はマリアの腕を乱暴につかんだ。
よほどマリアのことが気に入っているのか、どんなことを言われようと躊躇がない。
「痛い! 嫌です! やめてください!」
マリアは男の手から逃れようと、必死で抵抗する。
カンタロウは鞘で、男の腕をしばいた。
「ぐわっ! なんだっ?」
男の手が、マリアから離れた。前腕が赤く腫れている。
「やめろ。嫌がってる」
「ふう。おいおい僕ちゃん。今、自分が何をしたかわかってるのか?」
茶髪の傭兵が、カンタロウを脅すように強い口調で言った。
四人の傭兵のリーダー格なのだろう。
偉そうな態度が、鼻につく。
「悪かったな。手がすべった」
「ふざけんじゃねぇ! てめぇ! よくも俺の腕を!」
頭の禿げた傭兵が、カンタロウに向かって、剣のグリップを握る。
「落ち着けって。ここは話し合いで解決しよう」
それを茶髪の傭兵が止める。長髪の髪をかき上げ、マリアをじろりと見た。
マリアは警戒心をあらわし、体を男からそらした。
「そこの女はね。盗賊なんだ」
傭兵の不意打ちに、マリアは呆然となった。
「なっ、何を……」
「嘘じゃない。その女は悪い女でね。旅人に取り入っては、隙を見て金品を盗む盗賊なんだ。たぶん、今日、その女は君達の仲間になったんじゃないか? それまでは、赤の他人だったはずだ」
「……確かに、今日この人達の仲間になりましたけど」
マリアは傭兵の罠だと知らず、認めてしまった。
茶髪の傭兵はニヤリと、汚らしい笑みを浮かべる。
「えっ?」
「ほらみろ。女も認めている」
アリアは男に誘導されたことに気づき、慌てふためき、
「待ってください! 私は盗賊なんかじゃありません!」
「なら、盗賊じゃないと、証明できる奴、いるか?」
傭兵が周りを見回した。
酒場はいつの間にか静かになり、皆が傭兵達とマリアの動向に注目していた。
剣帝国出身でもなく、外部から来た赤の他人であるマリアを、助ける者はいない。
誰も、マリアを盗賊ではないと、証明できる者はいなかった。
「いないだろ。まあ、盗賊であると証明もできない。がっ、俺達は昨日、そこの女が盗みを働いている現場を見ている」
「してません!」
「盗人はそう言うんだよ。みんな。まあ、証拠は明日見せるとして、これがどういうことか。若い君にわかるかな?」
マリアの息がつまった。どういうことか、わからない。
「つまり、盗賊をかばってる君達を、俺達は討伐できるってことだ。この剣を使ってね」
「えっ……それって……」
「ひひっ……」傭兵達が、皆剣を抜き始めた。
盗賊をかばうということは、同じ犯罪者と見なされるのだ。
都市の法律は犯罪者に厳しく、処刑は絶対。それを手助けした者も例外ではない。
「お客さん。やるなら外で、やってくれねぇか?」
色黒い酒場の主人が、腕を組んでやってきた。
「まだ話し合いの途中だ。もう少し待てよ」
茶髪の傭兵が、うっとおしそうな目つきで、主人を睨む。
「なあ、マリア。俺はお前のこと、気に入ってるんだ。嫁にしたいと思っている。だから、一緒に罪を償おう。なっ?」
どうやら、マリアを本気で自分の女にしたいようだ。語気に淀みがない。
「私……」
追いつめられたマリアは、顔を沈ませた。
「お前が俺達と来るなら、そこの酔っぱらいとガキは助けてやる。なっ、悪くないだろ?」
「ぶふふっ……」禿げた傭兵の男が、マリアの体を不純な視線で舐めまわす。兜をつけた傭兵は、赤い舌で剣の刃を舐めた。
「私は……私は……」
誰もが、マリアから視線を外した。よけいな事に、関わりたくない。表情から、そう読みとれる。
「マリア。さあ、どうする?」
マリアの右目から、一粒の涙が流れ、
「私……はい……あなたと行きます」
決意のあらわれなのか、両手を胸で握りしめる。
マリアは、カンタロウ達を助けることを選択した。
自分が犠牲になることを選んだのだ。
他人に迷惑をかけるよりも、それが一番正しいことだと信じていた。
「いい子だ。マリア。さあ、来いよ」
女を落とした満足感から、茶髪の傭兵は白い歯を剥きだして喜んだ。
マリアが傭兵達の元へ歩みだそうとしたとき、カンタロウがすっと、前にでてきた。
「カンタロウさん、いいんです。私、耐えられますから……」
「マリアは盗人じゃない。それを、俺は知っている」
カンタロウは今までの話を、すべてなかったことにした。
マリアは目をパチクリさせる。
茶髪の傭兵も、カンタロウの言い分に言葉がつまり、
「ふぅ。おいおい僕ちゃん。なら、その証拠はあるのか?」
「そんなものはない。どうせ、お前等だってないだろ?」
「はぁ。一応言っとくけど。俺達は傭兵だ。剣だって所持している。しかも、戦えるのがお前一人だとしたら、四対一だ。馬鹿じゃないとしたら、この状況はわかるよな?」
傭兵達の目つきが、血なま臭いものに変わった。それぞれが剣を構え、カンタロウを睨む。
酒場に殺気が、充満する。
「おっ、おい!」
酒場の主人は、さすがにまずいと思ったのか、語気を強める。
「黙ってろ! なあ僕ちゃん。そんな細い体で、俺達とやりあって、どちらが勝つか。わかるよな?」
傭兵の威嚇。
カンタロウはそんな緊迫した状況にもかかわらず、刀を鞘から抜かず、柄をにぎり、
「これでいい」
「はっ? 何それ?」
「これだけで、お前達を倒すのは十分だ」
カンタロウの言動に、傭兵達はきょとんとした。
「うわっ、コイツ! 頭おかしいぜ!」
「ヒーロー妄想か? そういうのは思春期だけにしとけ!」
「もうやっちまおうぜ!」
イライラし始めたのか、三人の傭兵が怒鳴った。
リーダーである茶髪の傭兵は、頭をポリポリかき、
「あぁ、めんどくせぇ。仕方ねぇ。おいお前等。殺さない程度にボコッとけ……」
返事がない。それどころか、床がガタリと響いた。その後、何事も起こらない。
「えっ?」
茶髪の傭兵が後ろをむくと、三人の傭兵が白目を剥いて倒れていた。
「あとはお前だけだ。三人をつれて帰れ」
カンタロウは刀の鞘を、肩に乗せた。
「なっ、えっ……何?」
何が起こったのかわからず、茶髪の傭兵は困惑している。
――すごい。あまりにも速くて、まったく見えなかった。
マリアはカンタロウの剣術に、呆然と立ち尽くす。
「おい! どうした? おいっ!」
茶髪の傭兵は、慌てて仲間の傭兵の体を揺らしてみるが、起きる気配がない。
頭には強打した跡があり、完全に気絶している。
茶髪の傭兵が、カンタロウを下から見上げた。
フードで隠された暗い表情から、赤い片目が見える。それが赤眼化だと、ようやく気づいた。
――コイツ、赤眼化所持者か!
茶髪の傭兵の背筋に寒気がはしる。
赤眼化できない自分は、圧倒的に不利。力の天秤が、カンタロウに傾いた。
「わかったよ……女はお前の好きにしろっ」
茶髪の傭兵は、気絶している仲間を置いて、さっさと酒場からでて行った。
「……カンタロウさん」
マリアがカンタロウに近づく。両目はしっとりと濡れていた。
「大丈夫か? あんなのは、ほっとけばいい」
「はい……」
カンタロウの黒い瞳に見つめられ、マリアの白い頬が赤く染まった。
「いいぞ兄ちゃん! かっこいい!」
「すげぇ! すげぇ、剣技だ! やるなぁ! まったく見えねぇ!」
「かっこいい彼氏を持って幸せだなぁ! 姉ちゃん羨ましいぜ!」
酒場の観客達は、カンタロウの鮮やかな剣技に拍手喝采を送った。
マリアは耳たぶまで真っ赤になり、
「ちっ、違います! 私とカンタロウさんは……」
マリアは慌てて弁解しようとした。
「もういいさ。でよう」
「はっ、はい!」
カンタロウに言われ、マリアは小さく飛び上がった。
「行くぞ、ランマル」
「んにゃ? まだのめるぞぉ、スズぅ」
呂律が回っていない。完璧に酔って、寝ていたようだ。
「よくこの状況で寝てられたな? 幸せな奴」
カンタロウは1つ息を吐く。
ランマルは大欠伸をして立ち上がると、お金を机に置いて、外にでていった。
次にアゲハの体を揺する。アゲハも机に伏していた。
「アゲハ、行くぞ」
アゲハはカンタロウに持ち上げられ、立ち上がる。軽いパンチが、カンタロウの腹に入り、
「なんだ?」
「別にぃ」
アゲハは意味深気に、楽しそうに笑った。
「ひゅうひゅう! 美人な彼女を、守ってやれよ!」
「結婚式には呼んでくれ!」
「俺もあんな若い美人と結婚してぇ!」
マリアはカンタロウの腕をつかみ、
「早く行きましょ! カンタロウさん!」
「あっ、ああ。そうだな」
マリアの白い肌は、まだ赤く火照っていた。