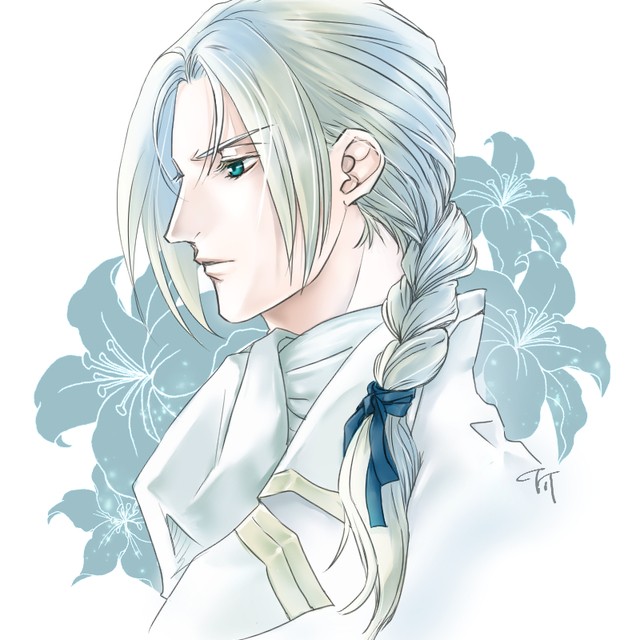4-17 アドビスの弱点
文字数 5,668文字
「こんなものに頼らなければ、俺はアドビスに勝てないっていうワケか!? そういう事か。えっ?」
夜色の瞳を細め、ヴィスルは両腕を組んだまま部屋の中をせわしなく歩き回った。
「……正面きって仕掛けるのはあまりにも無謀だ。船長、君の呼び掛けでどれぐらいの海賊船が集まるのか知らんが、所詮、アドビスの艦隊にはかなうまい」
ツヴァイスに背を向けていたヴィズルが、銀髪をひるがえして猛然と振り返る。
「そんなことはない。俺を見くびると、痛い思いをすることになるぜ。ツヴァイス」
「……ふん」
ぎらぎらした熱を帯びたヴィズルのにらみをあっさり受け流し、ツヴァイスは船尾窓の前に置かれた、応接椅子にゆったりと腰を下ろした。曇り一つなく磨かれた、黒いブーツを履いた足を軽く組み、物憂気に肘当てに腕をのせる。
「血を流すのは、アドビスだけで充分だと思うがね。ノーブルブルーを壊滅させたいと言う君に協力したせいで、多くの有能な部下を死なせてしまったよ」
ヴィズルは腕を掴む手に力を込めた。ツヴァイスの冷ややかな横顔を見るだけで、今にも飛びかかりたくなる衝動にかられる。
それを堪えるために噛みしめた唇から、塩辛い味がゆっくりと広がった。
「よく言うぜ。まっ先に海軍の士官どもを皆殺しにするよう、指示を出していたのはあんたのくせに」
ツヴァイスが口元に不敵な笑みを浮かべながらヴィズルを見上げた。
「海賊は海軍の人間を憎んでいるものじゃないのかね?」
ツヴァイスの銀縁の眼鏡の反射が影になり、薄紫色の瞳が一瞬はっきりと見えた。そこには、死んだ者達に対する哀れみや同情や後悔という感情が、一切表れていない。
胸くそが悪いぜ……。
ヴィズルはエルガード号に乗せていた、死んだ仲間達のことを思った。皆、海軍に一矢報いるため協力してくれたかけがえのない連中だ。彼等の事を忘れるつもりはない。これからも。
「てめぇの保身のためじゃねーのか? 生き残りがいれば後々どんな災いを起こすかわからねぇ……だから、シャインを?」
ヴィズルははっとした。
だがツヴァイスは相変わらず頬杖をついたまま、ヴィズルに薄く微笑を向ける。
「スカーヴィズ船長。私は君の味方だ。私はアドビスさえ葬り去れればそれで満足だ。だから君に協力したということを、忘れてもらっては困る。ノーブルブルーの水兵として、君の仲間を潜り込ませ、ありもしない偽の海賊が出没する海域へ向かわせる。君が罠を張って待ち伏せている場所へ、行くよう命じることができるのは私だけだ。そのために――多少の防御策を講じるのは、いたし方ないと、思ってもらえないかね?」
ヴィズルは歯ぎしりして大きく鼻息を鳴らした。
ツヴァイスはアドビスを破滅させられるなら、他人の命さえ踏みにじる男なのだ。
けれど。
ヴィズルは自分の中で、ツヴァイスに対する嫌悪感がすっと引いていくのを感じた。自分も海軍の人間に対しては、同じような感情を抱いているのだ。
何人死のうが血を流そうが知ったことではない。
死にたくなければ邪魔しなければいい。だから。
――シャインも例外ではない。
本当なら一ヶ月前に、この手で殺していたはずだったのだから。
ヴィズルは口元をひきつらせてうつむいた。視界の隅に見える金髪頭をいまいましく思いながら一瞥し、のん気に寝息を立てるその様子に毒づく。
「わかったぜ、ツヴァイス。だがな、シャインを使うつもりはない。うっとおしいから、こいつをどこかへ監禁して、俺の邪魔をしないようにしてくれ」
ふっとツヴァイスが笑った。肩をそびやかして小さく首を横に振りながら、本当に滑稽そうに笑った。
「私の所は駄目だ。ジェミナ・クラスに戻れば、アドビスの息がかかった憲兵が待ち受けているだろうよ。いや、ひょっとしたらウインガード号を追って、すでに船を出しているかもしれない」
「あんたがシャインなんか乗せてくるからだろーが! 厄介事を俺に押し付けるな!!」
ヴィズルは銀髪を震わせて叫んだ。ツヴァイスはそれにまったく動じず、むしろさらにおもしろがるようにヴィズルを凝視した。
「何がおかしい」
むきになる自分を抑えながら、ヴィズルはつぶやいた。
「……シャインなくして君に勝機があるとは思えなくてね。言っただろう、アドビスに正面から仕掛けるのは無謀だと。この二十年で力をつけたのは君だけじゃない。君はノーブルブルーに手を出したことで、エルシーア海軍を敵に回したのだ」
「俺が海賊である以上、それは今に始まったことじゃねぇ」
「……すべての艦隊と言ったらどうするかね? 今、主だった外洋艦隊がアスラトルへ召集されているのだぞ。エルシーア海に現れた君を捕らえるために。エルガード号クラスの船が五十隻以上集まってくる。それらをまとめるアドビスに、君は一歩も近付けやしないだろう」
「……」
ヴィズルは悔し気に唇を噛んだ。
確かに、ツヴァイスの言う通りなら分が悪い。
エルガード号は射程の長い大砲をメインに64門積んだ中堅の3等軍艦。二、三隻ならまだなんとかなるが、最高五十隻という、そんなまとまった数で構成された艦隊に近付けば、あっというまに集中砲火を浴びて沈められてしまう。
これではまるで国同士がやる戦争と同じだ。
ツヴァイスの言いたい事はわかる。
だからこそ、ヴィズルはあるものを欲した。
どんな船も自在に操ることができるという『エクセントリオンの船鐘』。
『船鐘』は確かに手に入れた。けれどあれを今すぐ扱えるのはただ一人――。
ヴィズルはぎりと奥歯を噛みしめ、再びシャインの金髪頭を睨み付けた。
「アドビスに勝ちたければ、急ぐことだ。アスラトルへ外洋艦隊が帰ってくる前に、しかも迅速に手を打つ必要がある。いや、間に合わなくても……」
ヴィズルは黙ってツヴァイスを見つめた。
ツヴァイスは小さくうなずきながらつぶやいた。
「シャインがいれば、アドビスの艦隊をたった一隻にすることが可能だ」
ヴィズルは眉をしかめた。
くっきりと眉間にしわが寄り、夜色の瞳が強い光を放つ。
「ツヴァイス、それは気に食わねぇってさっき……」
「この方がアドビスを自らの手で葬ることができる。つまらない砲撃のせいであの男が死んでもいいのかね!」
ツヴァイスの言葉に体が強ばる。ヴィズルは息をするのも忘れて、右手を胸の前でにぎりしめたまま、ツヴァイスの冷ややかな顔を見つめていた。
その通りかもしれない。
二十年前は泣くことしかできない小さな子供だったが、今はそれなりの力を手に入れ、アドビスと互角に戦うことができると信じている。呼び掛けに応じる海賊船はあちこちで、その時を待ってくれている。
けれど、自分は戦争をするつもりではない。
スカーヴィズの想いを裏切り、自分を裏切り、すべてを奪ったアドビス――ただその一人だけを殺したいだけなのだ。
「……」
ヴィズルは疲れたように、やっと椅子に腰を下ろした。
皮の手袋を外して、傍らに投げ置く。
思わずうなだれて、肩で大きく息を一つつく。
「……あんたの言いたいことはわかった」
流れ落ちてきた銀髪を手で払い、ヴィズルは言葉を続けた。
「だがな、本当にアドビスの船一隻だけにすることができるのか? シャインはアドビスを嫌っているようだったぜ。親子の仲はかなり悪いんじゃないのか? アドビスは――あの男は愛していた女すら手にかけたんだ。シャインを人質にしたって……」
「確かにシャインはあの男を嫌っている。だが、アドビスは違う」
「そうなのか?」
ヴィズルは思わず聞き返した。
「あの男がシャインを見殺しになどできるものか。私ですら、消し去りたい罪をシャインの存在で思い出してしまうのに……あの男にとっては、それ以上の思いがあるはずだ。いや、ないなど言わせない」
「ツヴァイス?」
手の関節が白くなるほど、ツヴァイスは肘当てを握りしめ、目の前の床に横たえてあるシャインを見つめていた。
「おい、どういうことだ? 説明しろよ、ツヴァイス」
ヴィズルの不機嫌そうな声にツヴァイスは我に返った。
そっと右手を上げて銀縁の眼鏡を掛け直す。
「シャインは……彼はあの男の……そして、私の大切だったひとに生き写しなのだよ。噂には聞いていたが、先日初めて会った時、驚いてしまった。シャインの母親だがね。彼女はアドビスのせいで命を落としたのだ。アドビス自身もそれを嫌という程認識している」
「何であんたがそんなことを知っているんだ?」
「……君に話すつもりはないな」
「ああそうかい。ならいいぜ」
ヴィズルは面白くなかった。
それは、ツヴァイスが話すことを拒んだせいではなく、アドビスが死んだスカーヴィズ以外に、愛した女がいたということを知ったせいだった。
どんな女だったのか。
スカーヴィズは殺せても、その女は殺せないというのか。
ヴィズルは母親に似ているというシャインの顔をながめた。
ふと二十年前――六才の頃の記憶が蘇ってくる。
海賊船の中で何時もひとりにされていた自分に、声をかけてくれたアドビス。
話し相手になってくれたアドビス。船のことを教えてくれたアドビス。
大切な航海術の本をくれたアドビス……。
すべては幻想にすぎなかった。
けれど今でも、頭をなでてくれたアドビスの、大きな手の感覚を覚えている自分がいる。その温もりを手に入れたいと、願っていた幼い自分の気持ちも覚えている。
アドビスが父親だったら――。
ヴィズルは唇を歪めながら、シャインに嫉妬せずにはいられなかった。
シャインはあの温かい手に包まれて、さぞや大切に育てられたのだろう。
アドビスのせいでささやかな幸せを奪われ、海軍の追跡に怯え続ける、悲惨な幼少期を過ごした自分と違って。
馬鹿馬鹿しい……。
口の中で声を出さずにつぶやき、ヴィズルは子供じみたその感情を一蹴した。
アドビスに対する未練などない。とにかく奴さえいなければ、スカーヴィズや仲間たちは死なずに済んだのだ。今も一緒にこの海で暴れていたに違いないのだ。この無念さを、理不尽さを何としてでもあの男にわからせたい。
ヴィズルは鼻で小さく笑い、眠ったままのシャインを一瞥した。
もしもツヴァイスの言う通りなら、シャインがアドビスの唯一の弱点なのだ。
これを利用しない手はない。
「ツヴァイス、じゃあ……シャインは俺が預る」
「そうかね。それはよかった」
ツヴァイスはにこやかに微笑んだ。
「ま、せいぜい活用させてもらうことにするさ。それに、シャインがいつ海に現れて、俺の邪魔をするかということを、いちいち気にしなくて済む」
ヴィズルはため息をつきながら答えた。満足げに自分を見るツヴァイスが、実に腹立たしかったが。けれど彼の言う通りにしなければ、アドビスとの戦いは苦戦を強いられる。
それに、目が覚めたシャインは何をするかわからないと思っていた。何しろ、エルガード号を襲う際に使ったロワールハイネス号を、乗組員ごとそのままアジトへ持って帰ってしまったのだ。シャインが取り返しにくるのは時間の問題だったはず。そしてついでに自分の邪魔をするに違いない。そのお節介ぶりはいやというほど分かっている。ヴィズルは無意識の内に左脇腹をさすった。
「シャインは君に預けるとして……一つだけ条件があるのだが」
ツヴァイスはゆっくりと椅子から立ち上がった。黒い滑らかな光沢を放つマントがゆらりと波打ち、その細身の体を覆う。
柔和なツヴァイスの顔の表情が、先程とはうって変わって固くなっている。
声も普段のそれよりトーンが低い。
ヴィズルは彼が真剣であることに気がついた。
静かにヴィズルも立ち上がり、ツヴァイスの前に立つ。
「何だよ。そんな怖い顔しやがって」
軽口を叩きつつ、ヴィズルは相手のえも言われぬ気迫に、少し驚きを感じていた。にこりともしないツヴァイスが静かに口を開き、その暗い深淵から発せられた声は、ヴィズルの耳に脅迫めいた響きを残した。
「シャインを殺したら、私が君を必ず殺す」
「……」
たっぷり一呼吸の間をおいて、ヴィズルはツヴァイスから目をそらせた。
肩をすくめて、その大きめの唇に薄笑いを浮かべて。
「わかってるさ。心配するな。俺だってあんたの協力が欲しい。だから、その機嫌を損ねるようなマネはしない」
ツヴァイスの黒マントが、風もないのにざわりと揺れる。
ヴィズルは目を細め、小さく安堵の息を吐いた。
ツヴァイスがマントの内側から腰の辺りで小銃を構え、銃口をこちらへ向けていたのだ。
「船長、これを使え」
再びツヴァイスのマントが大きく動いたので、ヴィズルは一瞬身構えた。
だが自分に向かって放たれたのは、青く光る小さな――。
「指輪?」
右手でそれを掴んだヴィズルは、ゆっくりと手のひらを開いた。
古風な何の装飾もなされていない銀の指輪。いや、違う。
ブルーエイジ。魔力の指輪。
ヴィズルはそれに見覚えがあることに気がついた。
確か、シャインがこれと同じようなものをはめていたような気がする。
年代を経たブルーエイジは透明感のある青い光を放つ。ここまで青いものを見たことがなかったので、記憶の隅に止めておいたのだ。時価で幾らの価値になるか、調べようと思いつつ。
冷たい。まるで指が凍り付きそうだ。この指輪は長年使われたことがないせいで、相当な力を貯えている。
ヴィズルは椅子にかけておいた手袋を再びはめた。
「やはり術者は敏感なのだな」
ツヴァイスの声に、ヴィズルは舌打ちした。
「まあな。ブルーエイジは『災厄の鉱石』と呼ばれている。人の魂を求める呪われた石だとな。長生きしたけりゃ、関わらないに越したことはねぇ」
ツヴァイスは動じることなく薄い唇を歪ませて微笑した。
「分かっていると思うが、君にくれてやるのではない。アドビスにそれを見せたまえ。そうすれば、奴はひとりで必ず君の所へ来る。必ずな」
嘲笑にも似たツヴァイスの笑い声を聞きながら、ヴィズルはシャインの指輪をぐっと握りしめた。
夜色の瞳を細め、ヴィスルは両腕を組んだまま部屋の中をせわしなく歩き回った。
「……正面きって仕掛けるのはあまりにも無謀だ。船長、君の呼び掛けでどれぐらいの海賊船が集まるのか知らんが、所詮、アドビスの艦隊にはかなうまい」
ツヴァイスに背を向けていたヴィズルが、銀髪をひるがえして猛然と振り返る。
「そんなことはない。俺を見くびると、痛い思いをすることになるぜ。ツヴァイス」
「……ふん」
ぎらぎらした熱を帯びたヴィズルのにらみをあっさり受け流し、ツヴァイスは船尾窓の前に置かれた、応接椅子にゆったりと腰を下ろした。曇り一つなく磨かれた、黒いブーツを履いた足を軽く組み、物憂気に肘当てに腕をのせる。
「血を流すのは、アドビスだけで充分だと思うがね。ノーブルブルーを壊滅させたいと言う君に協力したせいで、多くの有能な部下を死なせてしまったよ」
ヴィズルは腕を掴む手に力を込めた。ツヴァイスの冷ややかな横顔を見るだけで、今にも飛びかかりたくなる衝動にかられる。
それを堪えるために噛みしめた唇から、塩辛い味がゆっくりと広がった。
「よく言うぜ。まっ先に海軍の士官どもを皆殺しにするよう、指示を出していたのはあんたのくせに」
ツヴァイスが口元に不敵な笑みを浮かべながらヴィズルを見上げた。
「海賊は海軍の人間を憎んでいるものじゃないのかね?」
ツヴァイスの銀縁の眼鏡の反射が影になり、薄紫色の瞳が一瞬はっきりと見えた。そこには、死んだ者達に対する哀れみや同情や後悔という感情が、一切表れていない。
胸くそが悪いぜ……。
ヴィズルはエルガード号に乗せていた、死んだ仲間達のことを思った。皆、海軍に一矢報いるため協力してくれたかけがえのない連中だ。彼等の事を忘れるつもりはない。これからも。
「てめぇの保身のためじゃねーのか? 生き残りがいれば後々どんな災いを起こすかわからねぇ……だから、シャインを?」
ヴィズルははっとした。
だがツヴァイスは相変わらず頬杖をついたまま、ヴィズルに薄く微笑を向ける。
「スカーヴィズ船長。私は君の味方だ。私はアドビスさえ葬り去れればそれで満足だ。だから君に協力したということを、忘れてもらっては困る。ノーブルブルーの水兵として、君の仲間を潜り込ませ、ありもしない偽の海賊が出没する海域へ向かわせる。君が罠を張って待ち伏せている場所へ、行くよう命じることができるのは私だけだ。そのために――多少の防御策を講じるのは、いたし方ないと、思ってもらえないかね?」
ヴィズルは歯ぎしりして大きく鼻息を鳴らした。
ツヴァイスはアドビスを破滅させられるなら、他人の命さえ踏みにじる男なのだ。
けれど。
ヴィズルは自分の中で、ツヴァイスに対する嫌悪感がすっと引いていくのを感じた。自分も海軍の人間に対しては、同じような感情を抱いているのだ。
何人死のうが血を流そうが知ったことではない。
死にたくなければ邪魔しなければいい。だから。
――シャインも例外ではない。
本当なら一ヶ月前に、この手で殺していたはずだったのだから。
ヴィズルは口元をひきつらせてうつむいた。視界の隅に見える金髪頭をいまいましく思いながら一瞥し、のん気に寝息を立てるその様子に毒づく。
「わかったぜ、ツヴァイス。だがな、シャインを使うつもりはない。うっとおしいから、こいつをどこかへ監禁して、俺の邪魔をしないようにしてくれ」
ふっとツヴァイスが笑った。肩をそびやかして小さく首を横に振りながら、本当に滑稽そうに笑った。
「私の所は駄目だ。ジェミナ・クラスに戻れば、アドビスの息がかかった憲兵が待ち受けているだろうよ。いや、ひょっとしたらウインガード号を追って、すでに船を出しているかもしれない」
「あんたがシャインなんか乗せてくるからだろーが! 厄介事を俺に押し付けるな!!」
ヴィズルは銀髪を震わせて叫んだ。ツヴァイスはそれにまったく動じず、むしろさらにおもしろがるようにヴィズルを凝視した。
「何がおかしい」
むきになる自分を抑えながら、ヴィズルはつぶやいた。
「……シャインなくして君に勝機があるとは思えなくてね。言っただろう、アドビスに正面から仕掛けるのは無謀だと。この二十年で力をつけたのは君だけじゃない。君はノーブルブルーに手を出したことで、エルシーア海軍を敵に回したのだ」
「俺が海賊である以上、それは今に始まったことじゃねぇ」
「……すべての艦隊と言ったらどうするかね? 今、主だった外洋艦隊がアスラトルへ召集されているのだぞ。エルシーア海に現れた君を捕らえるために。エルガード号クラスの船が五十隻以上集まってくる。それらをまとめるアドビスに、君は一歩も近付けやしないだろう」
「……」
ヴィズルは悔し気に唇を噛んだ。
確かに、ツヴァイスの言う通りなら分が悪い。
エルガード号は射程の長い大砲をメインに64門積んだ中堅の3等軍艦。二、三隻ならまだなんとかなるが、最高五十隻という、そんなまとまった数で構成された艦隊に近付けば、あっというまに集中砲火を浴びて沈められてしまう。
これではまるで国同士がやる戦争と同じだ。
ツヴァイスの言いたい事はわかる。
だからこそ、ヴィズルはあるものを欲した。
どんな船も自在に操ることができるという『エクセントリオンの船鐘』。
『船鐘』は確かに手に入れた。けれどあれを今すぐ扱えるのはただ一人――。
ヴィズルはぎりと奥歯を噛みしめ、再びシャインの金髪頭を睨み付けた。
「アドビスに勝ちたければ、急ぐことだ。アスラトルへ外洋艦隊が帰ってくる前に、しかも迅速に手を打つ必要がある。いや、間に合わなくても……」
ヴィズルは黙ってツヴァイスを見つめた。
ツヴァイスは小さくうなずきながらつぶやいた。
「シャインがいれば、アドビスの艦隊をたった一隻にすることが可能だ」
ヴィズルは眉をしかめた。
くっきりと眉間にしわが寄り、夜色の瞳が強い光を放つ。
「ツヴァイス、それは気に食わねぇってさっき……」
「この方がアドビスを自らの手で葬ることができる。つまらない砲撃のせいであの男が死んでもいいのかね!」
ツヴァイスの言葉に体が強ばる。ヴィズルは息をするのも忘れて、右手を胸の前でにぎりしめたまま、ツヴァイスの冷ややかな顔を見つめていた。
その通りかもしれない。
二十年前は泣くことしかできない小さな子供だったが、今はそれなりの力を手に入れ、アドビスと互角に戦うことができると信じている。呼び掛けに応じる海賊船はあちこちで、その時を待ってくれている。
けれど、自分は戦争をするつもりではない。
スカーヴィズの想いを裏切り、自分を裏切り、すべてを奪ったアドビス――ただその一人だけを殺したいだけなのだ。
「……」
ヴィズルは疲れたように、やっと椅子に腰を下ろした。
皮の手袋を外して、傍らに投げ置く。
思わずうなだれて、肩で大きく息を一つつく。
「……あんたの言いたいことはわかった」
流れ落ちてきた銀髪を手で払い、ヴィズルは言葉を続けた。
「だがな、本当にアドビスの船一隻だけにすることができるのか? シャインはアドビスを嫌っているようだったぜ。親子の仲はかなり悪いんじゃないのか? アドビスは――あの男は愛していた女すら手にかけたんだ。シャインを人質にしたって……」
「確かにシャインはあの男を嫌っている。だが、アドビスは違う」
「そうなのか?」
ヴィズルは思わず聞き返した。
「あの男がシャインを見殺しになどできるものか。私ですら、消し去りたい罪をシャインの存在で思い出してしまうのに……あの男にとっては、それ以上の思いがあるはずだ。いや、ないなど言わせない」
「ツヴァイス?」
手の関節が白くなるほど、ツヴァイスは肘当てを握りしめ、目の前の床に横たえてあるシャインを見つめていた。
「おい、どういうことだ? 説明しろよ、ツヴァイス」
ヴィズルの不機嫌そうな声にツヴァイスは我に返った。
そっと右手を上げて銀縁の眼鏡を掛け直す。
「シャインは……彼はあの男の……そして、私の大切だったひとに生き写しなのだよ。噂には聞いていたが、先日初めて会った時、驚いてしまった。シャインの母親だがね。彼女はアドビスのせいで命を落としたのだ。アドビス自身もそれを嫌という程認識している」
「何であんたがそんなことを知っているんだ?」
「……君に話すつもりはないな」
「ああそうかい。ならいいぜ」
ヴィズルは面白くなかった。
それは、ツヴァイスが話すことを拒んだせいではなく、アドビスが死んだスカーヴィズ以外に、愛した女がいたということを知ったせいだった。
どんな女だったのか。
スカーヴィズは殺せても、その女は殺せないというのか。
ヴィズルは母親に似ているというシャインの顔をながめた。
ふと二十年前――六才の頃の記憶が蘇ってくる。
海賊船の中で何時もひとりにされていた自分に、声をかけてくれたアドビス。
話し相手になってくれたアドビス。船のことを教えてくれたアドビス。
大切な航海術の本をくれたアドビス……。
すべては幻想にすぎなかった。
けれど今でも、頭をなでてくれたアドビスの、大きな手の感覚を覚えている自分がいる。その温もりを手に入れたいと、願っていた幼い自分の気持ちも覚えている。
アドビスが父親だったら――。
ヴィズルは唇を歪めながら、シャインに嫉妬せずにはいられなかった。
シャインはあの温かい手に包まれて、さぞや大切に育てられたのだろう。
アドビスのせいでささやかな幸せを奪われ、海軍の追跡に怯え続ける、悲惨な幼少期を過ごした自分と違って。
馬鹿馬鹿しい……。
口の中で声を出さずにつぶやき、ヴィズルは子供じみたその感情を一蹴した。
アドビスに対する未練などない。とにかく奴さえいなければ、スカーヴィズや仲間たちは死なずに済んだのだ。今も一緒にこの海で暴れていたに違いないのだ。この無念さを、理不尽さを何としてでもあの男にわからせたい。
ヴィズルは鼻で小さく笑い、眠ったままのシャインを一瞥した。
もしもツヴァイスの言う通りなら、シャインがアドビスの唯一の弱点なのだ。
これを利用しない手はない。
「ツヴァイス、じゃあ……シャインは俺が預る」
「そうかね。それはよかった」
ツヴァイスはにこやかに微笑んだ。
「ま、せいぜい活用させてもらうことにするさ。それに、シャインがいつ海に現れて、俺の邪魔をするかということを、いちいち気にしなくて済む」
ヴィズルはため息をつきながら答えた。満足げに自分を見るツヴァイスが、実に腹立たしかったが。けれど彼の言う通りにしなければ、アドビスとの戦いは苦戦を強いられる。
それに、目が覚めたシャインは何をするかわからないと思っていた。何しろ、エルガード号を襲う際に使ったロワールハイネス号を、乗組員ごとそのままアジトへ持って帰ってしまったのだ。シャインが取り返しにくるのは時間の問題だったはず。そしてついでに自分の邪魔をするに違いない。そのお節介ぶりはいやというほど分かっている。ヴィズルは無意識の内に左脇腹をさすった。
「シャインは君に預けるとして……一つだけ条件があるのだが」
ツヴァイスはゆっくりと椅子から立ち上がった。黒い滑らかな光沢を放つマントがゆらりと波打ち、その細身の体を覆う。
柔和なツヴァイスの顔の表情が、先程とはうって変わって固くなっている。
声も普段のそれよりトーンが低い。
ヴィズルは彼が真剣であることに気がついた。
静かにヴィズルも立ち上がり、ツヴァイスの前に立つ。
「何だよ。そんな怖い顔しやがって」
軽口を叩きつつ、ヴィズルは相手のえも言われぬ気迫に、少し驚きを感じていた。にこりともしないツヴァイスが静かに口を開き、その暗い深淵から発せられた声は、ヴィズルの耳に脅迫めいた響きを残した。
「シャインを殺したら、私が君を必ず殺す」
「……」
たっぷり一呼吸の間をおいて、ヴィズルはツヴァイスから目をそらせた。
肩をすくめて、その大きめの唇に薄笑いを浮かべて。
「わかってるさ。心配するな。俺だってあんたの協力が欲しい。だから、その機嫌を損ねるようなマネはしない」
ツヴァイスの黒マントが、風もないのにざわりと揺れる。
ヴィズルは目を細め、小さく安堵の息を吐いた。
ツヴァイスがマントの内側から腰の辺りで小銃を構え、銃口をこちらへ向けていたのだ。
「船長、これを使え」
再びツヴァイスのマントが大きく動いたので、ヴィズルは一瞬身構えた。
だが自分に向かって放たれたのは、青く光る小さな――。
「指輪?」
右手でそれを掴んだヴィズルは、ゆっくりと手のひらを開いた。
古風な何の装飾もなされていない銀の指輪。いや、違う。
ブルーエイジ。魔力の指輪。
ヴィズルはそれに見覚えがあることに気がついた。
確か、シャインがこれと同じようなものをはめていたような気がする。
年代を経たブルーエイジは透明感のある青い光を放つ。ここまで青いものを見たことがなかったので、記憶の隅に止めておいたのだ。時価で幾らの価値になるか、調べようと思いつつ。
冷たい。まるで指が凍り付きそうだ。この指輪は長年使われたことがないせいで、相当な力を貯えている。
ヴィズルは椅子にかけておいた手袋を再びはめた。
「やはり術者は敏感なのだな」
ツヴァイスの声に、ヴィズルは舌打ちした。
「まあな。ブルーエイジは『災厄の鉱石』と呼ばれている。人の魂を求める呪われた石だとな。長生きしたけりゃ、関わらないに越したことはねぇ」
ツヴァイスは動じることなく薄い唇を歪ませて微笑した。
「分かっていると思うが、君にくれてやるのではない。アドビスにそれを見せたまえ。そうすれば、奴はひとりで必ず君の所へ来る。必ずな」
嘲笑にも似たツヴァイスの笑い声を聞きながら、ヴィズルはシャインの指輪をぐっと握りしめた。