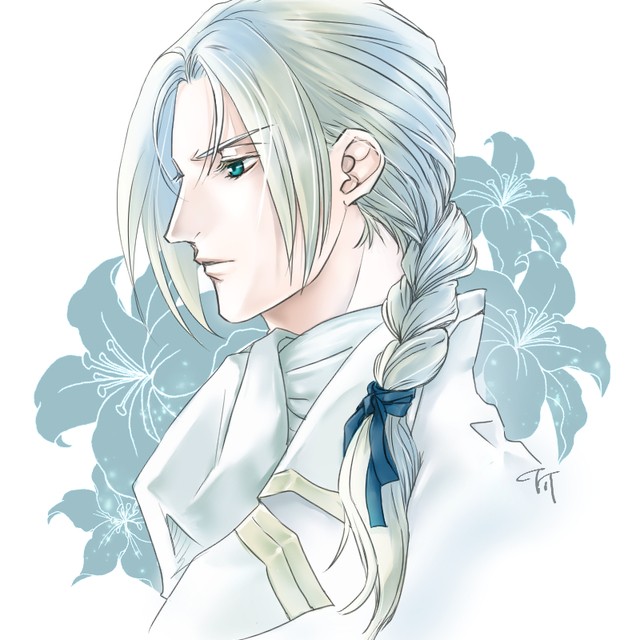4-11 氷塊
文字数 3,620文字
ツヴァイスの長い話が終わった。
肘掛けの付いた応接椅子の背に身を沈め、両手を組んだ指に力を込めながら、シャインはもどかしい気分に陥っていた。
アドビスが決してシャインに話そうとしなかった、母リュイーシャの死のてん末。冷たい甲板の上で、言葉を返すことのない彼女を抱くアドビスの姿が、目の前で見えた気がした。その胸中はいかばかりだったのだろう。
「遅くなってすまなかった」
もの思いにふけっていたシャインの意識を、ツヴァイスの穏やかな声が現実へと引き戻した。シャインは二、三度まばたきを繰り返し、眉根を寄せて自分を見つめるツヴァイスに顔を向けた。
「どういう意味ですか?」
ひと呼吸おいて、ツヴァイスの口元が自嘲気味に引きつる。
「リュイーシャの言葉だよ。君へ伝えるように頼まれていたのに、私はその務めを果たさず、二十年もの月日が過ぎるにまかせた。申し訳ない」
ツヴァイスの口調は重かった。察するにずっとその事を気にしていたのだろう。
ゆったりと構え、いつも余裕をみせる雰囲気が、今のツヴァイスからは全く感じられなかった。
「いいえ。閣下には大変感謝しています。こうしてお話して下さらなければ、俺は母の人柄や、遺した思いを知る事が叶いませんでした。あの人はこれからもずっと、自分だけの胸に秘めていくつもりでしょうから……」
そう言ってシャインは、ツヴァイスへはにかんだ笑みを向けた。
アドビスが何故自分に母親の死の真相を話したがらないのか、その理由は依然わからない。だが、心の奥につかえていた、一生消えないだろうと思っていた氷のような塊が、一片だけ溶け落ちていった。
『私がお前の母を死に追いやった。私があのひとを殺したのだ』
幼かったあの日の自分へ、そう呟いたアドビス。
それ以来ずっと、アドビスが母を手にかけたのだと思っていた。
アドビスは否定しなかったから。むしろシャインの非難を、すすんで受け入れ弁解すらしなかったから。何度となく言い合いをしたが、アドビスの態度はいつも頑 であった。
けれど真実はそうではなかった。
アドビスは愛した者を、自分の都合で殺したわけではなかったのだ。
胃の辺りを誰かにつかまれているように、ぎゅっと締め付けられるのを感じながら、それでもシャインは、自分の中に安堵感が広がっていくのを覚えた。
「そして……その後のことを少し話しておく。リュイーシャを抱えたアドビスは、艦長室に入ったまま暫く出てこなかった。私もリュイーシャを失ったことで動揺し……このあたりの記憶は――少し曖昧なのだ。けれど時間は1時間にも満たなかったと思う。夜明け前の薄暗い宵闇の中、我々はまだスカーヴィズのアジトの島にいた。無謀なことにな。
島に集っていた海賊船はリュイーシャの起こした嵐ですべて沈んだと思っていた。けれど、島の裏側に避難してやり過ごしていた船がまだ十数隻いたのだ。後から知ったことだが、「月影のスカーヴィズ」と対立していた「隻眼のロードウェル」の海賊船団だった。流石にこの数の船を我々一隻だけでは対処できない。私は艦長室に籠るアドビスへ報告しに部屋へ行こうとした時だった」
ツヴァイスがここで不意に口を閉ざした。
夕暮れ色の瞳が何かに怯える様に暗い光を放つ。
シャインはツヴァイスの言葉を待った。
「アドビスが部屋から丁度出てきた所だった。その手には、あの『船鐘 』が携えられていた」
「えっ……」
「そう。君のロワールハイネス号に設置されている『船鐘』だ。あの時は恐ろしいほどまでに冴えた青い光を発していた。その光を見ただけで、私はえもいわれぬ不安に慄き、その場から動くことができなかった」
ツヴァイスは両手で自らの腕を抱いた。シャインから顔を背けながら。
「アドビスは何も言わず甲板へ上がっていった。奴がいなくなってから、私は膝の震えが止まらないのを堪えながら甲板へ上がった。外に出るとロードウェルの海賊船が我々を見つけて、こちらへ向かって来る所だった。リュイーシャが伝えてきた海軍の討伐隊の船はまだ海上に見えなかった。どう見てもこちらが劣勢だ。私はアドビスへ撤退を進言しに、後部甲板の指揮所へ行った。その時だった。ロードウェルの船団に異変が起きたのは」
「異変、ですか」
ツヴァイスは冷ややかに頷いた。
そして目の前でその光景を見るかのように口を開いた。
「先頭の船へ後続の船が衝突したのだ。突風など吹いていない。けれど吸い寄せられるように両船が近づいて、そのまま船体がぶつかった。続いて衝突した二隻に向かって、その後方にいた海賊船が回避する間もなく突っ込んでいった。その光景に驚いていると、後ろからアドビスの笑い声が聞こえてきたのだ」
「……それは……」
ツヴァイスはシャインの顔を一瞥し、わかっているだろうと言わんばかりに唇の端を吊り上げた。
「アドビスは舵輪の隣に立ち、右手で『船鐘』を持って海上を見つめていた。『船鐘』の放つ青い光が奴の体を包んだかと思うと、私は再びロードウェルの海賊船が衝突し、横倒しになるのを見た。そうだよ、シャイン。あの『エクセントリオンの船鐘』の逸話は本当だったのだ。あの『船鐘』は、鐘を扱える者の意のままに、船を操ることができるのだ」
シャインは暫しツヴァイスの横顔を黙って見つめていた。
曰くのある『船鐘』だというのはわかっていたが、二十年前に父アドビスがそれを操り、海賊船を沈めていたとは。
「にわかには信じられないという顔だな」
シャインは戸惑いながらも静かに首を横に振った。
「いえ。ツヴァイス司令。あの『船鐘』を扱える者が、船を動かす事ができるというのは、本当なのです」
ツヴァイスの目元が細くなる。
「知っている。だからこそ君は、ジェミナ・クラスまで四日間で行くことができた」
「閣下、お尋ねして良いでしょうか。ロワールハイネス号にあの『船鐘』をつけるよう命じたのは――」
ふふっとツヴァイスが笑みを漏らした。
「私ではない。寧ろ、あの『船鐘』を欲しがっていたのはヴィズルでね」
シャインは息を飲んだ。
ツヴァイスの笑みがさらに広がる。
「あの『船鐘』がいつ作られたものかは知らないが、エルシーア海軍の参謀司令官が門外不出として、代々守っているものだ。理由はあの鐘を扱える者は、自らの意思で船を動かす事が出来る――ということらしいが。二十年前にアドビスがそれをやってみせたので、本当の事だった。
その話をヴィズルにした所、奴が欲しがってね。かといって、私自身が持ち出すわけにもいかないので、アイル号のウェルツを利用することにした。奴は金に困っていた。『船鐘』を運び出す話を持ちかけたら、あっさり食いついてきた。指定の海域に来たら、ヴィズルがアイル号を襲撃して鐘を奪い、船を沈ませる算段だった。勿論、ウェルツもろともな」
「……」
「でもまさか、アイル号に君が乗っていたとは。ウェルツも馬鹿ではなかった。万一鐘の持ち出しが見つかった時は、君を人質にして、アドビスの追跡を躱すつもりだったのだろう。だが現実は思わぬ展開をみせるものだな」
ツヴァイスが意味ありげにシャインを眺める。
彼の考えていることはわからなくもない。
「何故君はあの『船鐘』を扱えるのだろうね」
シャインは首を横に振った。
「……わかりません。でも」
「でも?」
「あの船鐘には、恐ろしい力が潜んでいるのは確かです。閣下が恐れを感じて身動きができなくなったように」
シャインは思い出していた。
命名式で祝酒のビンを舳先に打ち付け割ろうとした時。
ロワールと同じ顔をした、青い髪の少女の姿を。
処女航海の時に、再び現れた彼女を一度は退けたものの、彼女は依然、あの『船鐘』の中に存在している。
ロワールが『青き悪魔 』と言っていた――人の魂を求めるという、恐るべき存在として。
「ツヴァイス司令。先程あの鐘の事を『エクセントリオンの船鐘』と言っておられましたが。それが、あの鐘のつけられるべき元の船名なのですか?」
ツヴァイスが困ったように眉間を寄せた。
「おそらく、な。船体は現存しないだろうが、私もそれだけしか知らないのだよ。ただ二十年前にアドビスが、青く光るあの鐘を手にして、ロードウェルの海賊船をすべて操り、海に沈めてしまったのは事実だ」
「……」
シャインは震えてきた両手を無意識の内に合わせた。武者震いだろう。
『船鐘』とアドビスの関係。母リュイーシャの死のてん末。
「大丈夫かね? まあ、これだけいろんな話を一度に聞けば、驚くなという方が無理だとは思うが」
ツヴァイスは執務机の上に置いてあるティーポットを取り、自分のカップへ注いだが、気に食わぬ様子で眉間をしかめた。
「どうもここの分は冷めてしまったな。レイフに言って、新しいシルヴァンティーを作らせよう」
「閣下、どうぞお構いなく」
ツヴァイスが席を立ったので、シャインも慌てて椅子から立ち上がった。
肘掛けの付いた応接椅子の背に身を沈め、両手を組んだ指に力を込めながら、シャインはもどかしい気分に陥っていた。
アドビスが決してシャインに話そうとしなかった、母リュイーシャの死のてん末。冷たい甲板の上で、言葉を返すことのない彼女を抱くアドビスの姿が、目の前で見えた気がした。その胸中はいかばかりだったのだろう。
「遅くなってすまなかった」
もの思いにふけっていたシャインの意識を、ツヴァイスの穏やかな声が現実へと引き戻した。シャインは二、三度まばたきを繰り返し、眉根を寄せて自分を見つめるツヴァイスに顔を向けた。
「どういう意味ですか?」
ひと呼吸おいて、ツヴァイスの口元が自嘲気味に引きつる。
「リュイーシャの言葉だよ。君へ伝えるように頼まれていたのに、私はその務めを果たさず、二十年もの月日が過ぎるにまかせた。申し訳ない」
ツヴァイスの口調は重かった。察するにずっとその事を気にしていたのだろう。
ゆったりと構え、いつも余裕をみせる雰囲気が、今のツヴァイスからは全く感じられなかった。
「いいえ。閣下には大変感謝しています。こうしてお話して下さらなければ、俺は母の人柄や、遺した思いを知る事が叶いませんでした。あの人はこれからもずっと、自分だけの胸に秘めていくつもりでしょうから……」
そう言ってシャインは、ツヴァイスへはにかんだ笑みを向けた。
アドビスが何故自分に母親の死の真相を話したがらないのか、その理由は依然わからない。だが、心の奥につかえていた、一生消えないだろうと思っていた氷のような塊が、一片だけ溶け落ちていった。
『私がお前の母を死に追いやった。私があのひとを殺したのだ』
幼かったあの日の自分へ、そう呟いたアドビス。
それ以来ずっと、アドビスが母を手にかけたのだと思っていた。
アドビスは否定しなかったから。むしろシャインの非難を、すすんで受け入れ弁解すらしなかったから。何度となく言い合いをしたが、アドビスの態度はいつも
けれど真実はそうではなかった。
アドビスは愛した者を、自分の都合で殺したわけではなかったのだ。
胃の辺りを誰かにつかまれているように、ぎゅっと締め付けられるのを感じながら、それでもシャインは、自分の中に安堵感が広がっていくのを覚えた。
「そして……その後のことを少し話しておく。リュイーシャを抱えたアドビスは、艦長室に入ったまま暫く出てこなかった。私もリュイーシャを失ったことで動揺し……このあたりの記憶は――少し曖昧なのだ。けれど時間は1時間にも満たなかったと思う。夜明け前の薄暗い宵闇の中、我々はまだスカーヴィズのアジトの島にいた。無謀なことにな。
島に集っていた海賊船はリュイーシャの起こした嵐ですべて沈んだと思っていた。けれど、島の裏側に避難してやり過ごしていた船がまだ十数隻いたのだ。後から知ったことだが、「月影のスカーヴィズ」と対立していた「隻眼のロードウェル」の海賊船団だった。流石にこの数の船を我々一隻だけでは対処できない。私は艦長室に籠るアドビスへ報告しに部屋へ行こうとした時だった」
ツヴァイスがここで不意に口を閉ざした。
夕暮れ色の瞳が何かに怯える様に暗い光を放つ。
シャインはツヴァイスの言葉を待った。
「アドビスが部屋から丁度出てきた所だった。その手には、あの『
「えっ……」
「そう。君のロワールハイネス号に設置されている『船鐘』だ。あの時は恐ろしいほどまでに冴えた青い光を発していた。その光を見ただけで、私はえもいわれぬ不安に慄き、その場から動くことができなかった」
ツヴァイスは両手で自らの腕を抱いた。シャインから顔を背けながら。
「アドビスは何も言わず甲板へ上がっていった。奴がいなくなってから、私は膝の震えが止まらないのを堪えながら甲板へ上がった。外に出るとロードウェルの海賊船が我々を見つけて、こちらへ向かって来る所だった。リュイーシャが伝えてきた海軍の討伐隊の船はまだ海上に見えなかった。どう見てもこちらが劣勢だ。私はアドビスへ撤退を進言しに、後部甲板の指揮所へ行った。その時だった。ロードウェルの船団に異変が起きたのは」
「異変、ですか」
ツヴァイスは冷ややかに頷いた。
そして目の前でその光景を見るかのように口を開いた。
「先頭の船へ後続の船が衝突したのだ。突風など吹いていない。けれど吸い寄せられるように両船が近づいて、そのまま船体がぶつかった。続いて衝突した二隻に向かって、その後方にいた海賊船が回避する間もなく突っ込んでいった。その光景に驚いていると、後ろからアドビスの笑い声が聞こえてきたのだ」
「……それは……」
ツヴァイスはシャインの顔を一瞥し、わかっているだろうと言わんばかりに唇の端を吊り上げた。
「アドビスは舵輪の隣に立ち、右手で『船鐘』を持って海上を見つめていた。『船鐘』の放つ青い光が奴の体を包んだかと思うと、私は再びロードウェルの海賊船が衝突し、横倒しになるのを見た。そうだよ、シャイン。あの『エクセントリオンの船鐘』の逸話は本当だったのだ。あの『船鐘』は、鐘を扱える者の意のままに、船を操ることができるのだ」
シャインは暫しツヴァイスの横顔を黙って見つめていた。
曰くのある『船鐘』だというのはわかっていたが、二十年前に父アドビスがそれを操り、海賊船を沈めていたとは。
「にわかには信じられないという顔だな」
シャインは戸惑いながらも静かに首を横に振った。
「いえ。ツヴァイス司令。あの『船鐘』を扱える者が、船を動かす事ができるというのは、本当なのです」
ツヴァイスの目元が細くなる。
「知っている。だからこそ君は、ジェミナ・クラスまで四日間で行くことができた」
「閣下、お尋ねして良いでしょうか。ロワールハイネス号にあの『船鐘』をつけるよう命じたのは――」
ふふっとツヴァイスが笑みを漏らした。
「私ではない。寧ろ、あの『船鐘』を欲しがっていたのはヴィズルでね」
シャインは息を飲んだ。
ツヴァイスの笑みがさらに広がる。
「あの『船鐘』がいつ作られたものかは知らないが、エルシーア海軍の参謀司令官が門外不出として、代々守っているものだ。理由はあの鐘を扱える者は、自らの意思で船を動かす事が出来る――ということらしいが。二十年前にアドビスがそれをやってみせたので、本当の事だった。
その話をヴィズルにした所、奴が欲しがってね。かといって、私自身が持ち出すわけにもいかないので、アイル号のウェルツを利用することにした。奴は金に困っていた。『船鐘』を運び出す話を持ちかけたら、あっさり食いついてきた。指定の海域に来たら、ヴィズルがアイル号を襲撃して鐘を奪い、船を沈ませる算段だった。勿論、ウェルツもろともな」
「……」
「でもまさか、アイル号に君が乗っていたとは。ウェルツも馬鹿ではなかった。万一鐘の持ち出しが見つかった時は、君を人質にして、アドビスの追跡を躱すつもりだったのだろう。だが現実は思わぬ展開をみせるものだな」
ツヴァイスが意味ありげにシャインを眺める。
彼の考えていることはわからなくもない。
「何故君はあの『船鐘』を扱えるのだろうね」
シャインは首を横に振った。
「……わかりません。でも」
「でも?」
「あの船鐘には、恐ろしい力が潜んでいるのは確かです。閣下が恐れを感じて身動きができなくなったように」
シャインは思い出していた。
命名式で祝酒のビンを舳先に打ち付け割ろうとした時。
ロワールと同じ顔をした、青い髪の少女の姿を。
処女航海の時に、再び現れた彼女を一度は退けたものの、彼女は依然、あの『船鐘』の中に存在している。
ロワールが『
「ツヴァイス司令。先程あの鐘の事を『エクセントリオンの船鐘』と言っておられましたが。それが、あの鐘のつけられるべき元の船名なのですか?」
ツヴァイスが困ったように眉間を寄せた。
「おそらく、な。船体は現存しないだろうが、私もそれだけしか知らないのだよ。ただ二十年前にアドビスが、青く光るあの鐘を手にして、ロードウェルの海賊船をすべて操り、海に沈めてしまったのは事実だ」
「……」
シャインは震えてきた両手を無意識の内に合わせた。武者震いだろう。
『船鐘』とアドビスの関係。母リュイーシャの死のてん末。
「大丈夫かね? まあ、これだけいろんな話を一度に聞けば、驚くなという方が無理だとは思うが」
ツヴァイスは執務机の上に置いてあるティーポットを取り、自分のカップへ注いだが、気に食わぬ様子で眉間をしかめた。
「どうもここの分は冷めてしまったな。レイフに言って、新しいシルヴァンティーを作らせよう」
「閣下、どうぞお構いなく」
ツヴァイスが席を立ったので、シャインも慌てて椅子から立ち上がった。