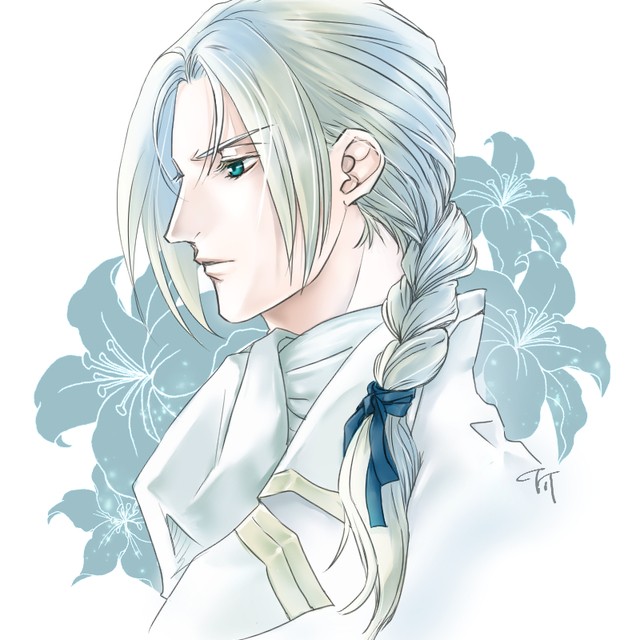4-104 正装(1)
文字数 6,363文字
帰港した翌日。ジャーヴィスはシャインの執務机の上に、濃紺のろうけつ紙で作られた書類入れが置かれている事に気がついた。
いや、ジャーヴィスだからこそ、気付く事ができたのだ。
それは正確に言うと、普段の倍近く積み上げられた本の一番下に埋もれて、ほとんど見えない状態になっていた。他の書類の整理に追われたシャインが、明らかにその存在を忘れ、次々と用済の資料をその上に重ねてしまったことは言う間でもない。
ジャーヴィスは小さく嘆息しながら、積み重ねられている資料本を本来あるべき場所に片付けて、下敷きになっていた書類入れを救出した。
「……今頃、海軍省で困ってるでしょうね」
ジャーヴィスは書類入れを机上からつまみあげ、切れ長の目を細めながら視線を虚空に彷徨わせた。
任務を終え帰港した船は、三日以内に航海日誌とその他諸々の書類を海軍省へ提出しなければならない。
適切な航海が行われたか、積荷の横領や乗組員の不正行為がなかったか、専門の機関で監査を受けるためだ。
ちなみにシャインが忘れた書類は、ロワールハイネス号の船籍登録書だ。
これがないとロワールハイネス号がエルシーア国籍で王立海軍所属の軍艦である証明ができない。
船の戸籍とも言える大切な書類なのだが、ジャーヴィスはそれを忘れたシャインのことを咎める気はさらさらなかった。
ロワールハイネス号は大きな試練を伴った航海を終えて、一昨日アスラトルに帰港したばかりだからだ。
シャイン自身も右手首を折る負傷を抱え、アスラトルに着く前日まで熱を出して寝台に臥せっていた。幸い今はそれも下がり回復期に入ったのだが、まだ万全の体調とはいえない。本当なら仕事など後回しにして、彼には休養が必要なのだ。
ジャーヴィスは書類入れを持ったまま、今から一時間前のことを思い返した。
あれは15時前の事だった。
シャインが艦長として義務を果たすべく、必要書類の確認作業を終えて船を降り、海軍省に行った事は知っている。勿論それを止める気はないし、ジャーヴィスに黙って出て行ったことも構わない。
ただ気になったのは、船を降りた時に見かけた彼が、普段着ているケープがついた濃紺の航海服ではなく、純白の
これはシャインが少なくとも将官以上の高位者と会うつもりであるということが推測できる。もしくはアリスティド統括将に呼ばれたのかもしれない。
シャインは海賊拿捕専門艦隊(通称・ノーブルブルー)襲撃事件に端を発した一連の戦闘に、深く関わる事になってしまったから、今日は事情聴取のために海軍省へ行ったのかも――。
「……」
ジャーヴィスは小さくため息をついて書類入れを小脇に抱えた。
アスラトルに戻っても、シャインの身辺に平穏が訪れるのは当分先のようだ。
ジャーヴィスは書類入れに視線を落とした。『船籍登録書』も海軍省へ提出する大切な書類である。副長として、艦長が忘れた重要書類を届けるのは当然の義務だろう。
取りあえず海軍省へ行く
ジャーヴィスは急いで艦長室を後にした。
◇
「あ! よかった。誰かいらしたんですね!」
「えっ?」
ジャーヴィスはロワールハイネス号の舷門 から突堤へと降り立った。
日は傾きつつあり、赤味を帯びた光が周囲を照らしている。
その中で赤い飾り布を髪に巻いた、十七、八才ぐらいの少女が立っていた。
どことなく王都に居るジャーヴィスの妹、ファルーナに雰囲気が似ている。
緩く巻かれた栗色の髪が肩に流れ、少女のあどけなさを残しつつも、それが女性としての艶っぽさを醸し出している。
「何かご用ですか?」
ジャーヴィスは戸惑いながら少女に訊ねた。
ここは軍関係者しか立ち入りが許されない軍港である。
少女はどうみても一般人だった。
「あの。この船はシャイン・グラヴェール艦長さまのロワールハイネス号ですか」
「ああ。そうだとも」
少女は安堵したように胸に小さな掌をのせた。
「私、フェメリア通りにある花屋『緑の籠』のアルメと申します。あの、グラヴェール艦長さまは船に……?」
ジャーヴィスは眉間をしかめ首を振った。
「いや不在だ。何か用件があるのなら、私もこれから艦長に会いに行くので、伝言なら承るが?」
アルメは一瞬顔を曇らせたが、黒いスカートのポケットに手を入れ、白い封筒をそこから取り出した。
「それではこちらをグラヴェール艦長さまにお渡ししていただけますでしょうか。船にお届けするようにと承っていましたので。それから、御注文の品はすでにお届けしておりますと、一緒にお伝え下さい」
ジャーヴィスは小さくうなずいた。
「確かに」
「では、私はこれで失礼いたします」
アルメはジャーヴィスに会釈して、足早に突堤を歩いていった。
その先には一台の小型の馬車が止まっていた。アルメはそれに乗って、エルドロイン河沿いの道を北に走っていった。
ジャーヴィスは白い封筒を持ったまま首を捻った。
わざわざ花屋が納品の連絡に軍港まで来るとは。
シャインは何を頼んだのだろう。
「……まあ、あの人は変わってるからな」
ジャーヴィスは封筒をなくさないように、ロワールハイネス号の船籍登録書が入っている書類入れの中にそれをはさんだ。
「さて、急がないと」
ジャーヴィスは足早に突堤を後にして、海軍省へと向かった。
◇◇◇
「えっ。それは本当ですか?」
「はい。ロワールハイネス号のグラヴェール艦長ですが、今日はこちらに来られてはいませんよ」
海軍省の総務部に向かったジャーヴィスは、書類入れを持ったまま窓口で絶句した。
「今から一時間前に船を降りたのですが……本当に艦長は来てないんですか!?」
二十代後半の若い窓口の女性は肩をそびやかし、残念そうに目を伏せた。
「私だってお会いできるならお会いしたかったですわよ。昨日お帰りになったとこちらでも話題でしたし。けれど受付時間はもう終わりだから、今日お越しになっても帰港報告の書類を受理できません……ああ、悔しい」
「……」
ジャーヴィスは唇を噛みしめながら唸った。
脳裏を白い正装を纏ったシャインの姿が浮かんだ。
きっと彼は将官の誰かと面会していて、まだ話が終わっていないのだ。
「あの……ロワールハイネス号のジャーヴィス中尉、でしたっけ?」
窓口の女性は金縁の眼鏡に手を添えて、じっとジャーヴィスの顔を見ていた。
その表情はどこか冷めていて、感情を沈ませたような暗さがあった。
「ああ。そうだが」
窓口の女性は周囲を見回し、声を潜めた。
怪訝な表情を浮かべ、ジャーヴィスを手招きする。
「グラヴェール艦長のあの
「噂?」
ジャーヴィスは首を傾げながら聞き返した。
「えっ、ご存知ないんですか?」
「何をご存知ないのかがわからないんだが」
窓口の女性はささやくように小さな声で呟いた。
「ノーブルブルーのファスガード号とエルガード号が海賊に襲われたことは知ってます?」
「ああ。それは勿論」
「でも、船が沈んだのは海賊のせいじゃないんです」
ジャーヴィスは頬を強ばらせ、鋭い青の瞳を見開いたまま女性の顔を凝視した。
こんな場所でこんな話を聞く事になるなんて。
ジャーヴィスは声を潜めながら女性に言い返した。
「いや、ファスガード号はエルガード号に砲撃されたんだ。海賊が水兵としてエルガード号に乗っていたから……」
「問題はそこじゃありません。なんでも、ラフェール提督が亡くなった後、ファスガード号の指揮を執っていたのは、あのお若いグラヴェール艦長だったそうじゃないですか」
ジャーヴィスはあきれたようにつぶやいた。
「当然だ。ラフェール提督とファスガード号のルウム艦長は砲撃で亡くなられた。副長のイストリア大尉より、上位の少佐であるグラヴェール艦長がその指揮を引き継ぐのは何もおかしいことではない」
「で、でも。イストリア大尉はこんなことを言ってるそうですよ? グラヴェール艦長は提督の剣を奪い、ファスガード号の指揮権を無理矢理自分のものにしたんだと。イストリア大尉はグラヴェール艦長に脅されて、仕方なく彼の命令に従ったんだって……」
「――馬鹿な!」
ジャーヴィスは我知らず大声を張り上げていた。
「う、うわっ! 中尉、お願いだから叫ばないで下さいっ。これはあくまでも『噂』で……」
窓口の女性は顔を青白くさせながら、周囲の様子を伺った。
ジャーヴィスはいらいらと女性を睨みつけた。
「『噂』だって? その割に、あなたは当事者でないと知り得ない事を知っているように思われるが? 何故あなたがそんな話を知っている? ファスガード号の乗組員には箝口 令が発せられていて、軽々しくその件に関して口外するのは禁止されてるんだぞ」
「そ、それは……その」
窓口の女性はジャーヴィスの今にも怒りだしそうな剣幕に唇を震わせながら、そっと金縁の眼鏡に手をやった。
「……私の恋人が、エルガード号に乗ってたんです。でも、彼。帰って来なかった。船と一緒に沈んじゃったんです」
「……」
窓口の女性は潤んできた瞳を伏せジャーヴィスから顔を背けた。
「私、参謀部の知り合いに頼んで、エルガード号が何故沈んだのか調べてもらったの。だって、本当のことが知りたかったから……! でないと私、どうしても納得できなかったから! 彼が帰って来ないなんて今でも信じられないから!」
ジャーヴィスは黙ったまま女性を見つめていた。
彼女の気持ちはわからなくもない。
突然恋人の死を告げられ、遺体も戻らないというのに、その事実だけをいきなり受け入れろというのは残酷で無理というもの。
「あなたの気持ちはわかった。だが、この件に関してはまだ調査中だ。だから人前で話さない方があなたのためだぞ」
女性は顔を上げた。白い頬に涙の筋が細くついていた。
「あなたもグラヴェール艦長を庇うのね? 部下らしく。参謀部はエルガード号が沈んだのは海賊のせいだなんて言ってるけどそれは嘘。グラヴェール艦長がエルガード号に残っている生存者を確認せず、砲撃を命じたのはファスガード号の士官達がみんな証言しているのよ? それなのに参謀部はその事実を認めない。いえ、事実を隠したがっているわけはわかってるわ。グラヴェール艦長はあの参謀司令の息子だから……」
「やめないか」
ジャーヴィスは腹の底から低く唸る声で呟いた。
窓口の女性はジャーヴィスの剣幕にひるむことなく眼鏡の奥の瞳を細めた。
「私が嘘をついているというのですか?」
ジャーヴィスは静かに頭を振った。
「嘘かどうか私にはわからない。だがあの時私もファスガード号に乗っていて、負傷した身だからこれだけは言っておく」
女性はきっと唇を噛みしめたままジャーヴィスを見上げた。
その青い目は何が一体真実なのか、戸惑い途方に暮れる幼い少女のようであった。
ジャーヴィスはゆっくりと息を吐き、女性に告げた。
「彼がいなかったら、ファスガード号の人間も救われなかっただろう。指揮官を失った艦ほど悲惨なものはないんだ。命令系統は伝わらず、水兵達は右往左往するばかり。そしてエルガード号の生存者だと? 彼等はファスガード号が沈没するだけの砲撃をしてきたんだ。先にな。悪いが、私には彼等が味方だったとは思えない」
「……」
女性は黙ったまま席を立った。
そしてジャーヴィスに向かって首を振った。
「私の恋人は海賊じゃなかった。ひょっとしたら、海賊にすでに殺されていたかもしれないけれど……参謀部がいくら隠しだてしても、グラヴェール艦長が味方の船を砲撃した事実は消えない」
ジャーヴィスは言い返さずその場に立ち尽くしていた。
女性の言う事は確かに無視できない部分があるからだ。
最初の砲撃で、二等軍艦ファスガード号のサロンが被弾した。
信じがたいことに、それは僚船である三等軍艦エルガード号からの砲撃だった。
サロンには艦隊の提督であるラフェールと、ファスガード号艦長ルウム。
そして海軍省の命令書を届けたシャインと一緒に、ジャーヴィスも同席していた。
ジャーヴィスは当然の如く無我夢中でシャインの肩を掴み、床にその身を伏せた。
その甲斐あってシャインは無傷だった。
だがジャーヴィスは、飛び散った窓ガラスの破片を背中に受け負傷してしまった。
失血のせいで、どうやって戦闘が終わり、母港アスラトルまで帰ったのか、当時の記憶は曖昧な部分が確かにある。
けれど。
ジャーヴィスは後悔にも似た息を吐いた。
あの女性に言ってやりたい。
シャインは確かに味方の船を砲撃した。
けれどこれは正当な命令だったのだ。
死に瀕したラフェール提督は枕元にシャインを呼び寄せ、自ら佩刀を手渡し指揮を委任した。
その時の二人のやりとりは、脳裏にはっきりと焼きついている。
「黙ってるけど、あなたは彼を信じているのね」
俯いた女性は再び金縁の眼鏡に手をやり力なく微笑んだ。一つにまとめられた栗色の髪が女性の細い肩から滑り落ちる。ジャーヴィスは薄い唇を噛みしめながら、じっと女性の視線を受け止めた。
残念だが、この案件は箝口 令が敷かれている。
自分が話をすれば、シャインの立場に何かしら影響を与えてしまう。
「もう一言だけ言わせてくれ。私が艦長と同じ立場であったなら、私もきっと――」
「じゃ、今日はもう終わりですから、お引き取り下さい」
女性はジャーヴィスの言葉を最後まで聞かず、窓口に灰色のカーテンを引いて姿を消した。
「おい……!」
ジャーヴィスは暫しカーテンが引かれた窓口の前に立っていた。
意外な場所で意外な話を聞かされただけに、頭の中が少しこんがらがっている。
けれどいつまでもここにいたって仕方ない。
窓口の女性はいなくなってしまったし、受付時間も終了した。シャインが今日ここへ来ることはまずないだろう。
いや、今日は来なくてよかった。あの女性とシャインが会っていたら、ここは物凄い騒ぎになっていたかもしれない。
『確かに海軍省の対応には疑問が残る。けれど遺族感情を考えて、ファスガード号とエルガード号は海賊に襲われたということにしているのだろう。だが、いつまでも事実を隠す事はできないだろうな……』
ジャーヴィスは額に手をやり小さく溜息をつくと、書類を抱えたまま総務部の部屋から外に出た。
深海を思わせる濃紺の絨毯が敷かれた廊下には人気がなく、また、誰かがやってくる気配もない。海軍省へ来たのは余計なことだったようだ。
そう。
余計な事だった。
虚しさを抱えつつ、再び船に戻ろうと思った時、抱えていた書類入れから白い封筒が滑り落ちた。花屋の娘がシャインに渡してくれと言付かった、あの封筒である。
「おっと、いけない」
ジャーヴィスはそれを拾い上げた。
だが封筒から一枚の紙がひらりひらりと宙を舞い、絨毯の上に落ちた。
封がしてあったわけではなかったらしい。
ジャーヴィスは再び手を伸ばして絨毯の上に落ちた紙切れを拾った。
それは二つに折り曲げられていたが、薄い紙で花屋の名前が飾り文字で『緑の籠』と書かれているのが透けて見える。同時にそこには金額らしき数字も書かれていた。
ジャーヴィスは無意識のうちに折り曲げられていた紙を広げていた。
「ふむ。思った通り、花代の請求書のようだな。って……えっ?」
ジャーヴィスは一瞬、紙に書かれた数字の桁を目で追った。
「20万5千リュール……だと?」
ジャーヴィスは手紙を持ったまま信じられない思いでそれを睨み付けた。
花もそれはそれは高額な商品があるのだろうが、贈答用であってもせいぜい1万リュールぐらいが相場である。
「……」
ジャーヴィスは腑に落ちないまま、花屋の請求書を封筒の中に収めた。
気になる事があった。
いや、ジャーヴィスだからこそ、気付く事ができたのだ。
それは正確に言うと、普段の倍近く積み上げられた本の一番下に埋もれて、ほとんど見えない状態になっていた。他の書類の整理に追われたシャインが、明らかにその存在を忘れ、次々と用済の資料をその上に重ねてしまったことは言う間でもない。
ジャーヴィスは小さく嘆息しながら、積み重ねられている資料本を本来あるべき場所に片付けて、下敷きになっていた書類入れを救出した。
「……今頃、海軍省で困ってるでしょうね」
ジャーヴィスは書類入れを机上からつまみあげ、切れ長の目を細めながら視線を虚空に彷徨わせた。
任務を終え帰港した船は、三日以内に航海日誌とその他諸々の書類を海軍省へ提出しなければならない。
適切な航海が行われたか、積荷の横領や乗組員の不正行為がなかったか、専門の機関で監査を受けるためだ。
ちなみにシャインが忘れた書類は、ロワールハイネス号の船籍登録書だ。
これがないとロワールハイネス号がエルシーア国籍で王立海軍所属の軍艦である証明ができない。
船の戸籍とも言える大切な書類なのだが、ジャーヴィスはそれを忘れたシャインのことを咎める気はさらさらなかった。
ロワールハイネス号は大きな試練を伴った航海を終えて、一昨日アスラトルに帰港したばかりだからだ。
シャイン自身も右手首を折る負傷を抱え、アスラトルに着く前日まで熱を出して寝台に臥せっていた。幸い今はそれも下がり回復期に入ったのだが、まだ万全の体調とはいえない。本当なら仕事など後回しにして、彼には休養が必要なのだ。
ジャーヴィスは書類入れを持ったまま、今から一時間前のことを思い返した。
あれは15時前の事だった。
シャインが艦長として義務を果たすべく、必要書類の確認作業を終えて船を降り、海軍省に行った事は知っている。勿論それを止める気はないし、ジャーヴィスに黙って出て行ったことも構わない。
ただ気になったのは、船を降りた時に見かけた彼が、普段着ているケープがついた濃紺の航海服ではなく、純白の
正装
姿だったことだ。これはシャインが少なくとも将官以上の高位者と会うつもりであるということが推測できる。もしくはアリスティド統括将に呼ばれたのかもしれない。
シャインは海賊拿捕専門艦隊(通称・ノーブルブルー)襲撃事件に端を発した一連の戦闘に、深く関わる事になってしまったから、今日は事情聴取のために海軍省へ行ったのかも――。
「……」
ジャーヴィスは小さくため息をついて書類入れを小脇に抱えた。
アスラトルに戻っても、シャインの身辺に平穏が訪れるのは当分先のようだ。
ジャーヴィスは書類入れに視線を落とした。『船籍登録書』も海軍省へ提出する大切な書類である。副長として、艦長が忘れた重要書類を届けるのは当然の義務だろう。
取りあえず海軍省へ行く
口実
はできた。ジャーヴィスは急いで艦長室を後にした。
◇
「あ! よかった。誰かいらしたんですね!」
「えっ?」
ジャーヴィスはロワールハイネス号の
日は傾きつつあり、赤味を帯びた光が周囲を照らしている。
その中で赤い飾り布を髪に巻いた、十七、八才ぐらいの少女が立っていた。
どことなく王都に居るジャーヴィスの妹、ファルーナに雰囲気が似ている。
緩く巻かれた栗色の髪が肩に流れ、少女のあどけなさを残しつつも、それが女性としての艶っぽさを醸し出している。
「何かご用ですか?」
ジャーヴィスは戸惑いながら少女に訊ねた。
ここは軍関係者しか立ち入りが許されない軍港である。
少女はどうみても一般人だった。
「あの。この船はシャイン・グラヴェール艦長さまのロワールハイネス号ですか」
「ああ。そうだとも」
少女は安堵したように胸に小さな掌をのせた。
「私、フェメリア通りにある花屋『緑の籠』のアルメと申します。あの、グラヴェール艦長さまは船に……?」
ジャーヴィスは眉間をしかめ首を振った。
「いや不在だ。何か用件があるのなら、私もこれから艦長に会いに行くので、伝言なら承るが?」
アルメは一瞬顔を曇らせたが、黒いスカートのポケットに手を入れ、白い封筒をそこから取り出した。
「それではこちらをグラヴェール艦長さまにお渡ししていただけますでしょうか。船にお届けするようにと承っていましたので。それから、御注文の品はすでにお届けしておりますと、一緒にお伝え下さい」
ジャーヴィスは小さくうなずいた。
「確かに」
「では、私はこれで失礼いたします」
アルメはジャーヴィスに会釈して、足早に突堤を歩いていった。
その先には一台の小型の馬車が止まっていた。アルメはそれに乗って、エルドロイン河沿いの道を北に走っていった。
ジャーヴィスは白い封筒を持ったまま首を捻った。
わざわざ花屋が納品の連絡に軍港まで来るとは。
シャインは何を頼んだのだろう。
「……まあ、あの人は変わってるからな」
ジャーヴィスは封筒をなくさないように、ロワールハイネス号の船籍登録書が入っている書類入れの中にそれをはさんだ。
「さて、急がないと」
ジャーヴィスは足早に突堤を後にして、海軍省へと向かった。
◇◇◇
「えっ。それは本当ですか?」
「はい。ロワールハイネス号のグラヴェール艦長ですが、今日はこちらに来られてはいませんよ」
海軍省の総務部に向かったジャーヴィスは、書類入れを持ったまま窓口で絶句した。
「今から一時間前に船を降りたのですが……本当に艦長は来てないんですか!?」
二十代後半の若い窓口の女性は肩をそびやかし、残念そうに目を伏せた。
「私だってお会いできるならお会いしたかったですわよ。昨日お帰りになったとこちらでも話題でしたし。けれど受付時間はもう終わりだから、今日お越しになっても帰港報告の書類を受理できません……ああ、悔しい」
「……」
ジャーヴィスは唇を噛みしめながら唸った。
脳裏を白い正装を纏ったシャインの姿が浮かんだ。
きっと彼は将官の誰かと面会していて、まだ話が終わっていないのだ。
「あの……ロワールハイネス号のジャーヴィス中尉、でしたっけ?」
窓口の女性は金縁の眼鏡に手を添えて、じっとジャーヴィスの顔を見ていた。
その表情はどこか冷めていて、感情を沈ませたような暗さがあった。
「ああ。そうだが」
窓口の女性は周囲を見回し、声を潜めた。
怪訝な表情を浮かべ、ジャーヴィスを手招きする。
「グラヴェール艦長のあの
噂
、本当ですの?」「噂?」
ジャーヴィスは首を傾げながら聞き返した。
「えっ、ご存知ないんですか?」
「何をご存知ないのかがわからないんだが」
窓口の女性はささやくように小さな声で呟いた。
「ノーブルブルーのファスガード号とエルガード号が海賊に襲われたことは知ってます?」
「ああ。それは勿論」
「でも、船が沈んだのは海賊のせいじゃないんです」
ジャーヴィスは頬を強ばらせ、鋭い青の瞳を見開いたまま女性の顔を凝視した。
こんな場所でこんな話を聞く事になるなんて。
ジャーヴィスは声を潜めながら女性に言い返した。
「いや、ファスガード号はエルガード号に砲撃されたんだ。海賊が水兵としてエルガード号に乗っていたから……」
「問題はそこじゃありません。なんでも、ラフェール提督が亡くなった後、ファスガード号の指揮を執っていたのは、あのお若いグラヴェール艦長だったそうじゃないですか」
ジャーヴィスはあきれたようにつぶやいた。
「当然だ。ラフェール提督とファスガード号のルウム艦長は砲撃で亡くなられた。副長のイストリア大尉より、上位の少佐であるグラヴェール艦長がその指揮を引き継ぐのは何もおかしいことではない」
「で、でも。イストリア大尉はこんなことを言ってるそうですよ? グラヴェール艦長は提督の剣を奪い、ファスガード号の指揮権を無理矢理自分のものにしたんだと。イストリア大尉はグラヴェール艦長に脅されて、仕方なく彼の命令に従ったんだって……」
「――馬鹿な!」
ジャーヴィスは我知らず大声を張り上げていた。
「う、うわっ! 中尉、お願いだから叫ばないで下さいっ。これはあくまでも『噂』で……」
窓口の女性は顔を青白くさせながら、周囲の様子を伺った。
ジャーヴィスはいらいらと女性を睨みつけた。
「『噂』だって? その割に、あなたは当事者でないと知り得ない事を知っているように思われるが? 何故あなたがそんな話を知っている? ファスガード号の乗組員には
「そ、それは……その」
窓口の女性はジャーヴィスの今にも怒りだしそうな剣幕に唇を震わせながら、そっと金縁の眼鏡に手をやった。
「……私の恋人が、エルガード号に乗ってたんです。でも、彼。帰って来なかった。船と一緒に沈んじゃったんです」
「……」
窓口の女性は潤んできた瞳を伏せジャーヴィスから顔を背けた。
「私、参謀部の知り合いに頼んで、エルガード号が何故沈んだのか調べてもらったの。だって、本当のことが知りたかったから……! でないと私、どうしても納得できなかったから! 彼が帰って来ないなんて今でも信じられないから!」
ジャーヴィスは黙ったまま女性を見つめていた。
彼女の気持ちはわからなくもない。
突然恋人の死を告げられ、遺体も戻らないというのに、その事実だけをいきなり受け入れろというのは残酷で無理というもの。
「あなたの気持ちはわかった。だが、この件に関してはまだ調査中だ。だから人前で話さない方があなたのためだぞ」
女性は顔を上げた。白い頬に涙の筋が細くついていた。
「あなたもグラヴェール艦長を庇うのね? 部下らしく。参謀部はエルガード号が沈んだのは海賊のせいだなんて言ってるけどそれは嘘。グラヴェール艦長がエルガード号に残っている生存者を確認せず、砲撃を命じたのはファスガード号の士官達がみんな証言しているのよ? それなのに参謀部はその事実を認めない。いえ、事実を隠したがっているわけはわかってるわ。グラヴェール艦長はあの参謀司令の息子だから……」
「やめないか」
ジャーヴィスは腹の底から低く唸る声で呟いた。
窓口の女性はジャーヴィスの剣幕にひるむことなく眼鏡の奥の瞳を細めた。
「私が嘘をついているというのですか?」
ジャーヴィスは静かに頭を振った。
「嘘かどうか私にはわからない。だがあの時私もファスガード号に乗っていて、負傷した身だからこれだけは言っておく」
女性はきっと唇を噛みしめたままジャーヴィスを見上げた。
その青い目は何が一体真実なのか、戸惑い途方に暮れる幼い少女のようであった。
ジャーヴィスはゆっくりと息を吐き、女性に告げた。
「彼がいなかったら、ファスガード号の人間も救われなかっただろう。指揮官を失った艦ほど悲惨なものはないんだ。命令系統は伝わらず、水兵達は右往左往するばかり。そしてエルガード号の生存者だと? 彼等はファスガード号が沈没するだけの砲撃をしてきたんだ。先にな。悪いが、私には彼等が味方だったとは思えない」
「……」
女性は黙ったまま席を立った。
そしてジャーヴィスに向かって首を振った。
「私の恋人は海賊じゃなかった。ひょっとしたら、海賊にすでに殺されていたかもしれないけれど……参謀部がいくら隠しだてしても、グラヴェール艦長が味方の船を砲撃した事実は消えない」
ジャーヴィスは言い返さずその場に立ち尽くしていた。
女性の言う事は確かに無視できない部分があるからだ。
最初の砲撃で、二等軍艦ファスガード号のサロンが被弾した。
信じがたいことに、それは僚船である三等軍艦エルガード号からの砲撃だった。
サロンには艦隊の提督であるラフェールと、ファスガード号艦長ルウム。
そして海軍省の命令書を届けたシャインと一緒に、ジャーヴィスも同席していた。
ジャーヴィスは当然の如く無我夢中でシャインの肩を掴み、床にその身を伏せた。
その甲斐あってシャインは無傷だった。
だがジャーヴィスは、飛び散った窓ガラスの破片を背中に受け負傷してしまった。
失血のせいで、どうやって戦闘が終わり、母港アスラトルまで帰ったのか、当時の記憶は曖昧な部分が確かにある。
けれど。
ジャーヴィスは後悔にも似た息を吐いた。
あの女性に言ってやりたい。
シャインは確かに味方の船を砲撃した。
けれどこれは正当な命令だったのだ。
死に瀕したラフェール提督は枕元にシャインを呼び寄せ、自ら佩刀を手渡し指揮を委任した。
その時の二人のやりとりは、脳裏にはっきりと焼きついている。
「黙ってるけど、あなたは彼を信じているのね」
俯いた女性は再び金縁の眼鏡に手をやり力なく微笑んだ。一つにまとめられた栗色の髪が女性の細い肩から滑り落ちる。ジャーヴィスは薄い唇を噛みしめながら、じっと女性の視線を受け止めた。
残念だが、この案件は
自分が話をすれば、シャインの立場に何かしら影響を与えてしまう。
「もう一言だけ言わせてくれ。私が艦長と同じ立場であったなら、私もきっと――」
「じゃ、今日はもう終わりですから、お引き取り下さい」
女性はジャーヴィスの言葉を最後まで聞かず、窓口に灰色のカーテンを引いて姿を消した。
「おい……!」
ジャーヴィスは暫しカーテンが引かれた窓口の前に立っていた。
意外な場所で意外な話を聞かされただけに、頭の中が少しこんがらがっている。
けれどいつまでもここにいたって仕方ない。
窓口の女性はいなくなってしまったし、受付時間も終了した。シャインが今日ここへ来ることはまずないだろう。
いや、今日は来なくてよかった。あの女性とシャインが会っていたら、ここは物凄い騒ぎになっていたかもしれない。
『確かに海軍省の対応には疑問が残る。けれど遺族感情を考えて、ファスガード号とエルガード号は海賊に襲われたということにしているのだろう。だが、いつまでも事実を隠す事はできないだろうな……』
ジャーヴィスは額に手をやり小さく溜息をつくと、書類を抱えたまま総務部の部屋から外に出た。
深海を思わせる濃紺の絨毯が敷かれた廊下には人気がなく、また、誰かがやってくる気配もない。海軍省へ来たのは余計なことだったようだ。
そう。
余計な事だった。
虚しさを抱えつつ、再び船に戻ろうと思った時、抱えていた書類入れから白い封筒が滑り落ちた。花屋の娘がシャインに渡してくれと言付かった、あの封筒である。
「おっと、いけない」
ジャーヴィスはそれを拾い上げた。
だが封筒から一枚の紙がひらりひらりと宙を舞い、絨毯の上に落ちた。
封がしてあったわけではなかったらしい。
ジャーヴィスは再び手を伸ばして絨毯の上に落ちた紙切れを拾った。
それは二つに折り曲げられていたが、薄い紙で花屋の名前が飾り文字で『緑の籠』と書かれているのが透けて見える。同時にそこには金額らしき数字も書かれていた。
ジャーヴィスは無意識のうちに折り曲げられていた紙を広げていた。
「ふむ。思った通り、花代の請求書のようだな。って……えっ?」
ジャーヴィスは一瞬、紙に書かれた数字の桁を目で追った。
「20万5千リュール……だと?」
ジャーヴィスは手紙を持ったまま信じられない思いでそれを睨み付けた。
花もそれはそれは高額な商品があるのだろうが、贈答用であってもせいぜい1万リュールぐらいが相場である。
「……」
ジャーヴィスは腑に落ちないまま、花屋の請求書を封筒の中に収めた。
気になる事があった。