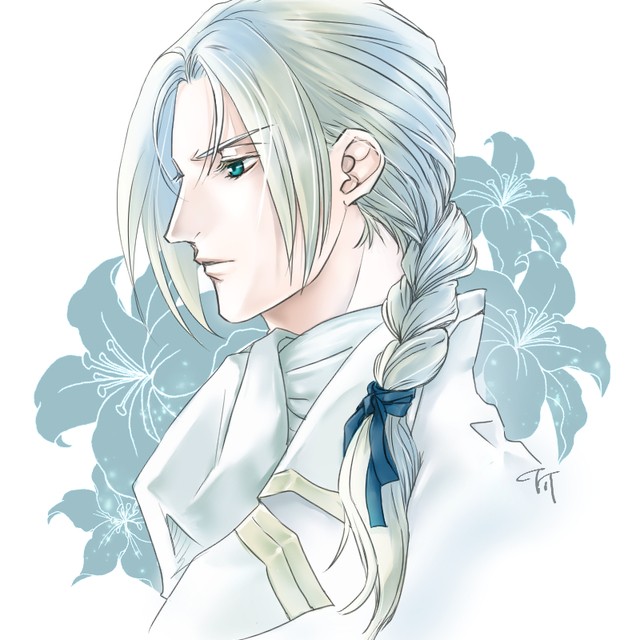4-1 女海賊の島
文字数 3,603文字
珊瑚のかけらが混ざったきめ細かい乳白色の砂を、さわさわと、透き通った海水が優しく洗っていく。
大人の足で一日あれば一周できる小さな島だが、その周囲は切り立った崖や岩場で囲まれており、唯一上陸できる浜辺は、北側の湾内にあるこの場所だけである。
幹に繊維状の毛を生やした枝のない木が、細長い葉をこんもりと茂らせ、その下で原色の鮮やかな大輪の花が、かぐわしい香りを周囲に漂わせる。
昼を過ぎた太陽は、それらを慈しむように光を降り注いでいるようだ。
無地の白いシャツの襟を立て、黒いズボン、同色のブーツというラフな格好で、ヴィズルは一人、人気のないこの小さな浜にたたずんでいた。
寄せては返す波の音を聞きながら、両手を腰に当てて島の中央部へ視線を向ける。太陽の光が、夜色をしたヴィズルの瞳を明るい青へ変化させると、緑鮮やかな木々の間に見え隠れする、石造りの建物を映し出す。
小高い山の頂上に作られたそれは、遥か百年ほど前の昔、エルシーア人が自国の南端であるこの島を、守るために築いた城塞であった。
だがそれは、南方の大国リュニスとの不可侵条約が五十年前に締結されて以来、必要がなくなり打ち捨てられたのだった。
その後、今から二十年前。栄華を極めたエルシーア海賊の一人、月影のスカーヴィズが自身の根城として手を入れ使用していたが、彼女はもう亡い。
現在この島には誰もいないようだ。
周りを珊瑚礁に囲まれているため、漁場として優良なので、時折漁船が近くを航行しているだけだと、配下の者から報告だけは聞いていた。
ヴィズルはその城塞に背を向け、再び海上を見やった。
白く続く砂浜の右手が細く突き出た岬になっていて、その先の海が錨泊地として最適の場所だった。
周りが珊瑚礁だらけの中、ここだけがほどよい深度であることを、育ての親であるスカーヴィズに教えてもらって知っていたのだった。
そこにはヴィズルの船が錨を下ろして停泊している。
エルシーアの商船よりやや長めの優美な船体だが、横幅は細く後方から風を受けて走れば、ヴィズルの船の方が俊足だというのが分かるだろう。
獲物に追いつく速さもさるものながら、中~近距離専用の大砲を24門積んでいて、その気になれば警護船をも相手にできる火力も備えている。
グローリアス号。そう名付けられたかの船の濃紺の帆はきれいに畳まれて、羽根を休めている海鳥のように、ゆらゆらと波間を漂っている。
鮮やかな碧海の上を。
その青とも緑ともいえない、澄んだ海面がきらきら光る様を、ヴィズルは黙ったまま眺めていた。無意識の内に上げた右手で、左脇腹の辺りを押さえながら。
「エルシーアの海は……気に入らねぇな……」
唇の端でつぶやく。
嫌な奴を思い出してしまった。
自然と顔がひきつってきて、ヴィズルはため息をついた。
『君の方こそ、ロワールの居場所を俺に教えてエルシーアから立ち去れ!』
夜の闇を焦がさんばかりに燃えるファスガード号のマスト。それが松明のように炎上するオレンジの光の中で、自分を見据えていたシャインの瞳――。
エルシーアの海の色……。
あれから一ヶ月以上が過ぎた。
ヴィズルは押さえていた右手の力をゆるめ、そっと左脇腹をさすった。
あの時、シャインから受けた刀傷は肉が盛り上がって、跡はあるが治っていた。意表を突かれ一瞬焦ったものの、元々深い傷ではなかったのだ。
ヴィズルは視線を脇腹へ落とし、苦々しく眉をひそめた。
怒りのあまり総毛立つ程の震えと、腹の奥からたぎる熱が蘇ってくる。
――お前に罪があるとすれば、あの男の息子だということしかない。
私怨がない故、いくばくか罪悪感を感じてはいた。けれど迷いはなかった。
ヴィズルとしては海軍に留まる回答をしたシャインは、今後自分の計画を邪魔される存在になる。
しかし、シャインに止めを刺すべく繰り出した、その一撃が外れた瞬間。
ヴィズルは再びシャインに剣をふるう事ができなかった。
決して、自分を見るシャインの眼差しに怖じけついたわけでもないし、情に流されたわけでもない。
悟ったのだ。この時、死んでいたのは自分の方だったのだと。
優美なラフェ-ルの細剣は、ヴィズルの左脇腹をえぐったのではなく、かすめるように切り裂いていた。最低限の傷で済むように。ヴィズルが死なないように。シャインが致命傷を与えまいと、手加減したのは明白だった。
「ふざけやがって!!」
ヴィズルは右足を後ろへ素早く引くと、思いきり足元の砂を蹴り上げた。乾いた白い砂はぱっと宙を舞い、波しぶきのように太陽の光を受けて輝く。
ざんばらの灰色を帯びた銀髪が、ヴィズルの鬼気迫る顔にまとわりつき、そのいらだちを更につのらせる。
なんのために?
お前を憐れんでいたのは俺のはずだ。
それなのに……。
顔にかかった銀髪を荒々しくかき揚げ、ヴィズルは大きく息をついて頭を振った。砂を踏み締めるかすかな音がしたような気がする。不意に人の気配に気付いて、ヴィズルは後ろを振り向いた。
「何をそんなに荒れてんだ? ヴィズル……いや、スカーヴィズ船長」
野太い声の主は、がっしりした赤銅色の肌と髪をした副船長のものだった。
「ティレグ……か」
ヴィズルは少し乱れていた息を整えながら、こちらへ近付いて来るティレグへ返事をした。
彼は二十年前、エルシーア海賊を一つにまとめた“月影のスカーヴィズ”の元で副船長を務めた人物で、今はその跡目を継いだヴィズルに付き従っている男である。
まるで本当の弟のように、目をかけてくれた事には少し恩義を感じている。
航海術の先生としては役不足であったが、剣術、体術問わず戦いの方法をヴィズルに教え、東方連国へ潜伏していた時も、<赤熊のティレグ>という名前のおかげで、向こうの海賊との交渉が有利に動いた。
四十才を過ぎたティレグは、髪に白いものが混じり始めたが、自慢の体力はまったく衰えを見せていない。
ヴィズルはスカーヴィズの跡目を継ぐのは、彼の方がふさわしいと一旦自ら辞退した。
だがティレグは自分の酒癖の悪さを上げ、自分が仕込んだヴィズルに跡目を継いでもらった方が、先代スカ-ヴィズへのはなむけになると答えたのだった。
「体はもういいみたいだな。怒る元気があるなら大丈夫だ」
しわが目立ちだした目元を細め、ティレグは唇の端を吊り上げてにやりと笑んだ。
「……ちょっと嫌な事を思い出しただけさ」
ヴィズルは肩をそびやかして、拗ねた笑みを浮かべた。
馬鹿な所を見られてしまった。いつものことなのでティレグは敢えて言わないが。
「嫌なことか。まあ、そうだな。この島に来れば……嫌でも昔の事を思い出しちまう」
ティレグが針金のように生えた顎鬚へ小指のない右手を添えた。
ヴィズルはいつになくそのがっしりした手を見つめた。
先代・月影のスカーヴィズに劣らぬ剛剣使いであるティレグ。彼の小指は切り落とされたのだという。だが誰にいつ切り落とされたのか、本人もよく覚えていないと言う。
この二十年。再びエルシーアで海賊として立ち上がるために、いろんな事を共に乗り越えてきた。お尋ね者だったティレグは、賞金稼ぎにいつも追いかけ回されて、たいていは返り討ちにしたものの、いくつも生傷を作っていた。
「そうそう、<金庫番・ストーム>が昨日釈放されたぜ。1500万リュールの保釈金が必要になったがな」
ヴィズルは思わず小さくうなった。
ティレグも同情するように口元へ笑みを浮かべる。
「1500万か。随分とふっかけたな、ツヴァイスの奴」
「仕方ねぇだろ。奴もいろいろ今回危ない橋を渡ったからな。海軍の目を逸らすためにその手間賃と思えば安い方だ」
ふんと鼻を鳴らし、ヴィズルはいまいましげに波間を睨む。
「俺達だって命かけてるんだぜ。アドビスをひきずりだすためにな」
いきりたつヴィズルをなだめるように、ティレグはその肩を親し気に叩いた。
「ま、文句があるなら本人へ言えばいいさ。ツヴァイスが会いに行くから迎えを寄越して欲しいと連絡してきた」
「本当か?」
半ばうんざりしたようにヴィズルは答えた。
どうもツヴァイスのすました雰囲気が好きではないし、あの眼鏡の奥に光る薄紫の瞳は何を考えているのか分からない所がある。
だが今は共通の敵、アドビス・グラヴェールを葬るために、ツヴァイスを大いに利用したかった。だから、その機嫌を損ねるようなことはできない。
「それで……いつ来るって?」
ヴィズルは浜辺に引き上げていたボートへ向かって歩き出した。
その後ろから、そそくさとティレグがついて行く。
「今夜、いつものところで」
「……毎度のことながら、こっちの都合を考えない奴だな!」
ティレグとヴィズルは鮮やかな青色の海面へボートを浮かべて海へこぎだした。
停泊しているグローリアス号へ急いで戻るために。
大人の足で一日あれば一周できる小さな島だが、その周囲は切り立った崖や岩場で囲まれており、唯一上陸できる浜辺は、北側の湾内にあるこの場所だけである。
幹に繊維状の毛を生やした枝のない木が、細長い葉をこんもりと茂らせ、その下で原色の鮮やかな大輪の花が、かぐわしい香りを周囲に漂わせる。
昼を過ぎた太陽は、それらを慈しむように光を降り注いでいるようだ。
無地の白いシャツの襟を立て、黒いズボン、同色のブーツというラフな格好で、ヴィズルは一人、人気のないこの小さな浜にたたずんでいた。
寄せては返す波の音を聞きながら、両手を腰に当てて島の中央部へ視線を向ける。太陽の光が、夜色をしたヴィズルの瞳を明るい青へ変化させると、緑鮮やかな木々の間に見え隠れする、石造りの建物を映し出す。
小高い山の頂上に作られたそれは、遥か百年ほど前の昔、エルシーア人が自国の南端であるこの島を、守るために築いた城塞であった。
だがそれは、南方の大国リュニスとの不可侵条約が五十年前に締結されて以来、必要がなくなり打ち捨てられたのだった。
その後、今から二十年前。栄華を極めたエルシーア海賊の一人、月影のスカーヴィズが自身の根城として手を入れ使用していたが、彼女はもう亡い。
現在この島には誰もいないようだ。
周りを珊瑚礁に囲まれているため、漁場として優良なので、時折漁船が近くを航行しているだけだと、配下の者から報告だけは聞いていた。
ヴィズルはその城塞に背を向け、再び海上を見やった。
白く続く砂浜の右手が細く突き出た岬になっていて、その先の海が錨泊地として最適の場所だった。
周りが珊瑚礁だらけの中、ここだけがほどよい深度であることを、育ての親であるスカーヴィズに教えてもらって知っていたのだった。
そこにはヴィズルの船が錨を下ろして停泊している。
エルシーアの商船よりやや長めの優美な船体だが、横幅は細く後方から風を受けて走れば、ヴィズルの船の方が俊足だというのが分かるだろう。
獲物に追いつく速さもさるものながら、中~近距離専用の大砲を24門積んでいて、その気になれば警護船をも相手にできる火力も備えている。
グローリアス号。そう名付けられたかの船の濃紺の帆はきれいに畳まれて、羽根を休めている海鳥のように、ゆらゆらと波間を漂っている。
鮮やかな碧海の上を。
その青とも緑ともいえない、澄んだ海面がきらきら光る様を、ヴィズルは黙ったまま眺めていた。無意識の内に上げた右手で、左脇腹の辺りを押さえながら。
「エルシーアの海は……気に入らねぇな……」
唇の端でつぶやく。
嫌な奴を思い出してしまった。
自然と顔がひきつってきて、ヴィズルはため息をついた。
『君の方こそ、ロワールの居場所を俺に教えてエルシーアから立ち去れ!』
夜の闇を焦がさんばかりに燃えるファスガード号のマスト。それが松明のように炎上するオレンジの光の中で、自分を見据えていたシャインの瞳――。
エルシーアの海の色……。
あれから一ヶ月以上が過ぎた。
ヴィズルは押さえていた右手の力をゆるめ、そっと左脇腹をさすった。
あの時、シャインから受けた刀傷は肉が盛り上がって、跡はあるが治っていた。意表を突かれ一瞬焦ったものの、元々深い傷ではなかったのだ。
ヴィズルは視線を脇腹へ落とし、苦々しく眉をひそめた。
怒りのあまり総毛立つ程の震えと、腹の奥からたぎる熱が蘇ってくる。
――お前に罪があるとすれば、あの男の息子だということしかない。
私怨がない故、いくばくか罪悪感を感じてはいた。けれど迷いはなかった。
ヴィズルとしては海軍に留まる回答をしたシャインは、今後自分の計画を邪魔される存在になる。
しかし、シャインに止めを刺すべく繰り出した、その一撃が外れた瞬間。
ヴィズルは再びシャインに剣をふるう事ができなかった。
決して、自分を見るシャインの眼差しに怖じけついたわけでもないし、情に流されたわけでもない。
悟ったのだ。この時、死んでいたのは自分の方だったのだと。
優美なラフェ-ルの細剣は、ヴィズルの左脇腹をえぐったのではなく、かすめるように切り裂いていた。最低限の傷で済むように。ヴィズルが死なないように。シャインが致命傷を与えまいと、手加減したのは明白だった。
「ふざけやがって!!」
ヴィズルは右足を後ろへ素早く引くと、思いきり足元の砂を蹴り上げた。乾いた白い砂はぱっと宙を舞い、波しぶきのように太陽の光を受けて輝く。
ざんばらの灰色を帯びた銀髪が、ヴィズルの鬼気迫る顔にまとわりつき、そのいらだちを更につのらせる。
なんのために?
お前を憐れんでいたのは俺のはずだ。
それなのに……。
顔にかかった銀髪を荒々しくかき揚げ、ヴィズルは大きく息をついて頭を振った。砂を踏み締めるかすかな音がしたような気がする。不意に人の気配に気付いて、ヴィズルは後ろを振り向いた。
「何をそんなに荒れてんだ? ヴィズル……いや、スカーヴィズ船長」
野太い声の主は、がっしりした赤銅色の肌と髪をした副船長のものだった。
「ティレグ……か」
ヴィズルは少し乱れていた息を整えながら、こちらへ近付いて来るティレグへ返事をした。
彼は二十年前、エルシーア海賊を一つにまとめた“月影のスカーヴィズ”の元で副船長を務めた人物で、今はその跡目を継いだヴィズルに付き従っている男である。
まるで本当の弟のように、目をかけてくれた事には少し恩義を感じている。
航海術の先生としては役不足であったが、剣術、体術問わず戦いの方法をヴィズルに教え、東方連国へ潜伏していた時も、<赤熊のティレグ>という名前のおかげで、向こうの海賊との交渉が有利に動いた。
四十才を過ぎたティレグは、髪に白いものが混じり始めたが、自慢の体力はまったく衰えを見せていない。
ヴィズルはスカーヴィズの跡目を継ぐのは、彼の方がふさわしいと一旦自ら辞退した。
だがティレグは自分の酒癖の悪さを上げ、自分が仕込んだヴィズルに跡目を継いでもらった方が、先代スカ-ヴィズへのはなむけになると答えたのだった。
「体はもういいみたいだな。怒る元気があるなら大丈夫だ」
しわが目立ちだした目元を細め、ティレグは唇の端を吊り上げてにやりと笑んだ。
「……ちょっと嫌な事を思い出しただけさ」
ヴィズルは肩をそびやかして、拗ねた笑みを浮かべた。
馬鹿な所を見られてしまった。いつものことなのでティレグは敢えて言わないが。
「嫌なことか。まあ、そうだな。この島に来れば……嫌でも昔の事を思い出しちまう」
ティレグが針金のように生えた顎鬚へ小指のない右手を添えた。
ヴィズルはいつになくそのがっしりした手を見つめた。
先代・月影のスカーヴィズに劣らぬ剛剣使いであるティレグ。彼の小指は切り落とされたのだという。だが誰にいつ切り落とされたのか、本人もよく覚えていないと言う。
この二十年。再びエルシーアで海賊として立ち上がるために、いろんな事を共に乗り越えてきた。お尋ね者だったティレグは、賞金稼ぎにいつも追いかけ回されて、たいていは返り討ちにしたものの、いくつも生傷を作っていた。
「そうそう、<金庫番・ストーム>が昨日釈放されたぜ。1500万リュールの保釈金が必要になったがな」
ヴィズルは思わず小さくうなった。
ティレグも同情するように口元へ笑みを浮かべる。
「1500万か。随分とふっかけたな、ツヴァイスの奴」
「仕方ねぇだろ。奴もいろいろ今回危ない橋を渡ったからな。海軍の目を逸らすためにその手間賃と思えば安い方だ」
ふんと鼻を鳴らし、ヴィズルはいまいましげに波間を睨む。
「俺達だって命かけてるんだぜ。アドビスをひきずりだすためにな」
いきりたつヴィズルをなだめるように、ティレグはその肩を親し気に叩いた。
「ま、文句があるなら本人へ言えばいいさ。ツヴァイスが会いに行くから迎えを寄越して欲しいと連絡してきた」
「本当か?」
半ばうんざりしたようにヴィズルは答えた。
どうもツヴァイスのすました雰囲気が好きではないし、あの眼鏡の奥に光る薄紫の瞳は何を考えているのか分からない所がある。
だが今は共通の敵、アドビス・グラヴェールを葬るために、ツヴァイスを大いに利用したかった。だから、その機嫌を損ねるようなことはできない。
「それで……いつ来るって?」
ヴィズルは浜辺に引き上げていたボートへ向かって歩き出した。
その後ろから、そそくさとティレグがついて行く。
「今夜、いつものところで」
「……毎度のことながら、こっちの都合を考えない奴だな!」
ティレグとヴィズルは鮮やかな青色の海面へボートを浮かべて海へこぎだした。
停泊しているグローリアス号へ急いで戻るために。